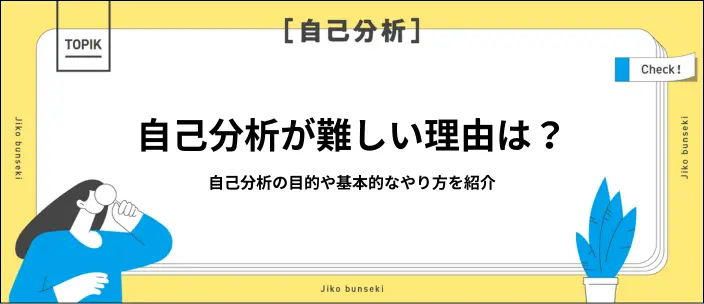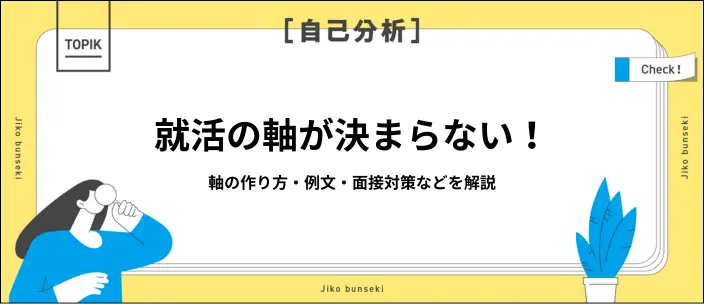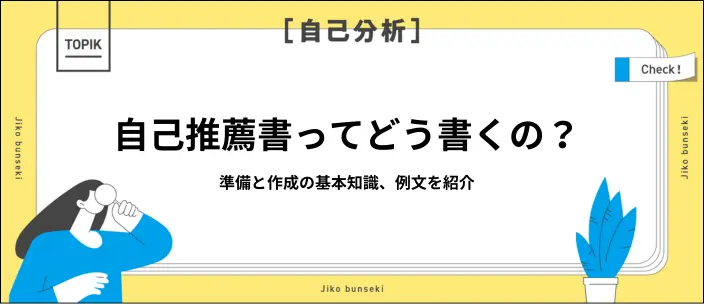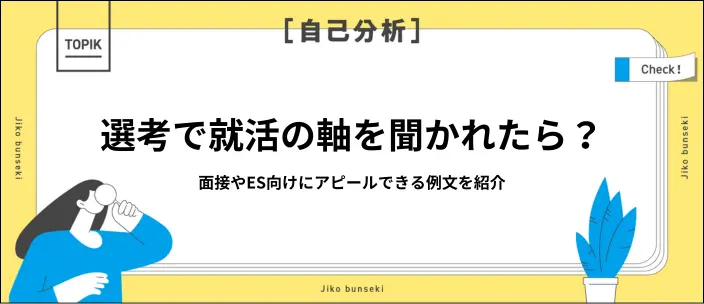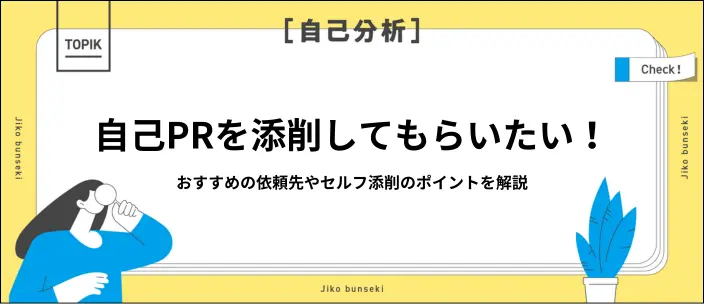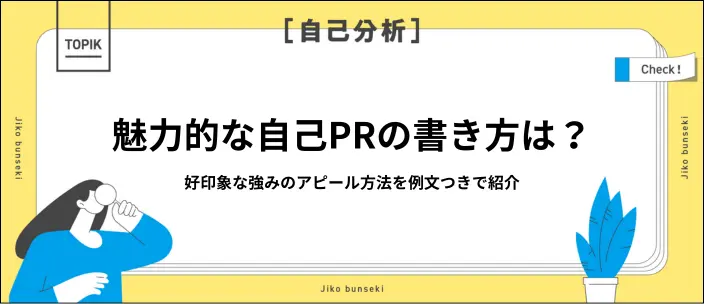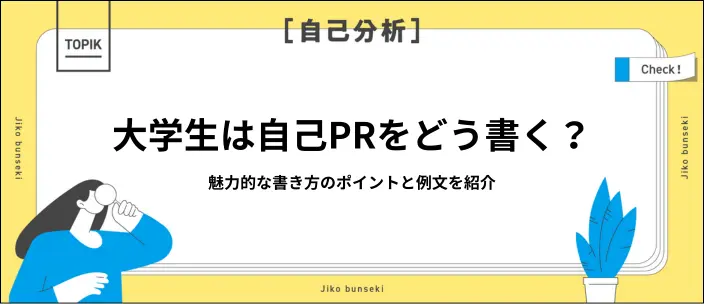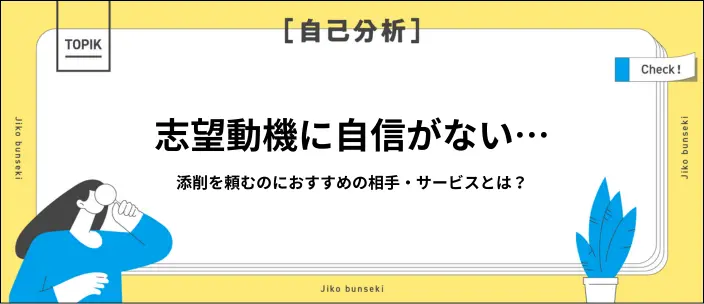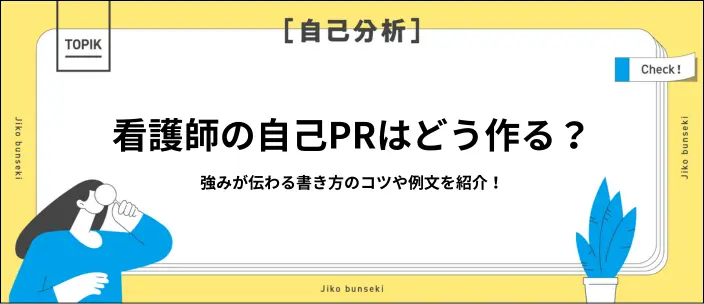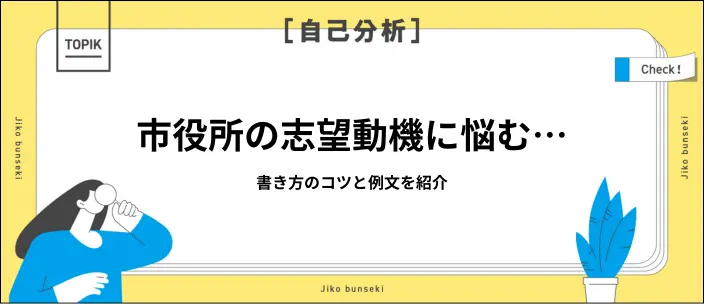このページのまとめ
- 自己分析は完璧に行う必要はない
- 自己分析をすると自分と企業の相性を判断しやすくなる
- 自己分析のやり方がわからない人は診断ツールや自分史などを取り入れる

自己分析に対して、「とにかくやらないと」「やり方が分からない」と悩んだり焦ったりすることもあるでしょう。しかし、やみくもに自己分析を行っても期待する効果が得られないことも。就活で活用するには、なぜ自己分析が必要なのかを理解することが大切です。
この記事では、自己分析の目的と就活で活用するコツについてまとめています。就活で自己分析を行う理由や具体的なやり方も紹介しているので参考にしてください。
かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 就活で自己分析が必要な理由
- 自分について深掘りするため
- 企業に効果的なアピールをするため
- 自己分析を実施するメリット
- 自分を客観的に捉えられるようになる
- 相性の良い企業を見つけやすくなる
- 選考の通過率が良くなる
- 自己分析がわからないと悩む人の特徴
- 先入観をもっている
- ポジティブな内容しか対象にならないと思っている
- 自己分析の目的を理解していない
- 自己分析の基本的なやり方
- 過去の経験を振り返る
- 自分の価値観を把握する
- キャリアビジョンを作成する
- 効率的に自己分析を行う5つの方法
- 1.適性診断テストを利用する
- 2.自分史を作成する
- 3.モチベーショングラフを作成する
- 4.他己分析を行う
- 5.就活エージェントサービスを利用する
- 自己分析がよくわからないと悩む人へ
就活で自己分析が必要な理由
自己分析をする大きな目的は「自分について深掘りするため」です。自分の強みや適性、得意・不得意などを理解していないと、就活で応募する企業を選べなかったり、自己アピールや志望動機が思いつかなかったりするでしょう。
自分について深掘りするため
自己分析とは、言葉通り「自分について分析すること」。自己分析を行うことで自分がどんな強みを持っているか、どんな適性があるか、どんな将来を送りたいかなどを明らかにできるため、志望企業の選定に役立ちます。
自己分析では自分で把握していなかった強みが見つかったり漠然としていた考えが明確になったりするため、「将来自分がどうなりたいか」「どんなキャリアを目指したいか」も分かるでしょう。
企業に効果的なアピールをするため
就活では、自己PRや志望動機で「応募企業に合っている」「採用メリットがある」とアピールする必要があります。このとき、自己分析を行っていれば具体的なエピソードや信憑性とともにマッチ度をアピールできるため、企業に好印象を与えることができるでしょう。
漠然と「コミュニケーション能力があるから御社の業務に生かせる」と伝えるよりも、「学生時代に△△部の部長をした経験から、△△を通してコミュニケーション能力を身に付けた」と具体的に伝えるほうが説得力が増します。
自己分析の基本や目的については「自己分析とは?おすすめのやり方8選や実施時の注意点を紹介」の記事でもまとめているので、併せてご覧ください。
かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
自己分析を実施するメリット
自己分析を行うことで、自分を客観視する機会となるため説得力をもって自己アピールを行えるようになります。また、前述したように自分と相性のいい企業を見つけやすくなり、その結果選考の突破率が上がることも。ここでは、自己分析を実施するメリットをまとめました。
自分を客観的に捉えられるようになる
自己分析の大きなメリットの一つは、自分を客観的に見る力が身につくことです。自分の性格や価値観、強みや弱みを把握することで、これまで無意識だった傾向や思考パターンに気づけるようになります。
たとえば、「自分はコミュニケーションが苦手」と思っていても、自己分析を行って「人と話すのは得意ではないけど、人の話を聞いて相手を理解することは得意」と気付くこともあるはず。また、自分では当たり前だと思っていたことが大きな強みだと分かることもあるでしょう。
自分を客観視できれば、自己PRや志望動機で説得力のあるアピールを行えます。
相性の良い企業を見つけやすくなる
自己分析を行うことで、自分に合った企業や職場環境を見つけやすくなります。なぜなら、自分の「やりがいを感じるポイント」や「苦手な業務」、「得意なスキル」などを明確にできるからです。
たとえば、過去に達成感を得た経験や反対にストレスを感じた場面を深掘りすることで、自分にとってやりがいを感じる仕事の特徴が明確になります。「興味があるから」「有名企業だから」といった曖昧な基準で企業を選ぶのではなく、自分の基準で仕事を選ぶ力につながるでしょう。
結果として自分の特性に合った職場や仕事内容を選びやすくなり、ミスマッチを防ぐことにつながります。また、企業からも「自社に合っている」と好印象を持ってもらえるでしょう。
選考の通過率が良くなる
自己分析を行うと、面接や書類選考における通過率が高まります。その理由は、自分の価値観や経験、強みを整理できることで、説得力のある自己PRや志望動機を語れるようになるからです。
たとえば、過去の経験から得た学びや、それによって形成された考え方を明確にしておけば、「なぜその企業を志望するのか」「どのように貢献できるのか」といった質問にも、一貫性を持って答えられます。ただ表面的に「御社に魅力を感じたから」ではなく、「これまでの経験を活かして△△のように働きたい」というように、未来のビジョンを語れるようになるのです。
このように、自己分析によって深めた自己理解は、応募書類の作成や面接時の受け答えに直結します。選考で自分らしさをしっかり伝えるためにも、準備としての自己分析は欠かせないプロセスといえるでしょう。
自己分析のメリットを最大限に生かすためには、やり方が大切です。この記事でも後述するほか、「自己分析のやり方おすすめ10選!正しく長所を理解するコツも解説」の記事にもまとめているので参考にしてください。
かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
自己分析がわからないと悩む人の特徴
自己分析に対して、「やったけど効果がいまいち実感できない」「やったけど合っているかわからない」と悩む人は多いようです。自己分析に対して悩みを持つのは、「先入観を持って行っている」「目的を理解していない」などが挙げられます。
先入観をもっている
自己分析がわからないと悩む人のなかには、「自分の強みは絶対に△△」「自分には△△の仕事が向いている」「就活では△△のスキルが絶対に評価される」など、思い込んでしまっている可能性があります。
前述したように、自己分析は自分を客観視して気付かない強みや価値観、適性を見出す作業。思い込みがある時点で客観視ができておらず、本来の自分を見つけることは難しくなるでしょう。
また、就活や企業の求める人材に対して先入観を持っていると、無意識のうちに「理想の人物像」「企業が求める人物像」に自己分析結果を寄せてしまうことに。自己分析は自分を「作り出す機会」ではありません。理想や求められる人物に寄せた自己分析結果は、本来の自分とは異なる内容になるでしょう。
先入観をもって自己分析を行ってしまうと、本来の自分に適さない企業を志望してしまったり、効果的なアピールにつながらなかったりする可能性が高まります。
先入観のない状態で自己分析を行うには、他己分析で周囲の意見を参考にするのがおすすめ。「自分は△△だから」という考えとは異なる意見をもらえるため、自分を客観視できるチャンスになります。また、自認していない特性に気付けることもあるでしょう。
ポジティブな内容しか対象にならないと思っている
自己分析がよくわからなくなる要因の一つに、「いい結果や良かったことしか対象にならない」と考えているものが挙げられます。また、「華やかな実績」「人に褒められる内容」がないと評価につながらないと考えている方もいるでしょう。
しかし、就活では成功体験より失敗の経験や苦手を克服する意識が重視されることも。自己分析でネガティブな内容を深掘りすることで、「自分はどんなときに失敗しやすいのか」「何が苦手なのか」「どんな課題を持っているのか」が分かります。こういった側面も含めて志望先を探すと、より自分にマッチした企業を見つけることができるでしょう。
また、選考では短所や失敗談を聞かれることもあるため、エピソードの確認にも有効です。短所の伝え方については、「履歴書に短所を書くときは短く簡潔にまとめよう!例文24選も紹介」の記事でチェックしてみましょう。
自己分析の目的を理解していない
自己分析に対して、「就活について調べたらやるべきと書いてあったから」「周りもやってるからとりあえず」のように、目的を理解せずに実施すると「自己分析がわからない」という状況になってしまいます。
冒頭でもお伝えしたように、自己分析は自分について深く理解して「自分に合う企業を見つける」「自分のキャリアプランを確認する」「企業に好アピールをする」などに活用します。目的が分からないまま行っても、どこに注目すればいいか分からず期待するような効果は得られません。
いまいち自己分析の目的がわからない人は、「自己PRを作るため」「自分の強みを見つけるため」など、具体的な目的を設定してみましょう。自己分析を行う理由が分かればスムーズに進められるはずです。
かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
自己分析の基本的なやり方
自己分析は、「過去を振り返る」「価値観を把握する」「キャリアビジョンを作る」の3ステップで行います。基本のやり方をまとめました。
過去の経験を振り返る
自己分析を進める第一歩は、これまでの経験を振り返ることです。なぜなら、自分の行動や考え方のベースとなる価値観や思考パターンは、過去の出来事に強く影響されているから。
たとえば、学生時代や社会人生活の中で、嬉しかったこと・悔しかったこと・達成感を得た瞬間などを思い出しながら、どんどん書き出してみましょう。良い出来事だけでなく、失敗や挫折といったネガティブな経験も含めるのがポイントです。そのうえで、「なぜその場面が印象に残っているのか」を考えると、思考の傾向や価値観が浮き彫りになってきます。
こうした振り返りを丁寧に行うことで、自分を形づくってきた土台が明確になり、今後の行動や選択の軸を作る手助けになるのです。
自分の価値観を把握する
自己分析では、自分の価値観を明確にすることが非常に重要です。価値観を把握することで、「自分がどんな生き方を望んでいるのか」「どんな環境で力を発揮できるのか」といった根本的な問いに答えやすくなります。
たとえば、過去の経験とそれに対する感情を並べて見比べることで、「人と協力することに喜びを感じる」「自分で決めて行動することに充実感を覚える」など、共通する傾向が見えてくるでしょう。そうした共通点を言葉にすることで、自分の価値観をより具体的に理解できるように。
価値観が明確になると、仕事選びやライフスタイルの決定においてブレない判断軸が生まれます。これをもとに企業選びを行えば、ミスマッチのない就活が叶うでしょう。
キャリアビジョンを作成する
価値観を明確にしたあとは、それにもとづいてキャリアビジョンを描いてみましょう。自分がどんな働き方を望み、どのような未来を目指したいのかを言語化することで、行動の方向性が定まりやすくなります。
なお、キャリアビジョンは単なる理想論ではなく、実現可能な目標として設計することが大切。価値観に沿った未来像を描くことで、モチベーションを維持しながら、より納得感のあるキャリア選択ができるようになるでしょう。
キャリアビジョンは、選考で「入社したらやりたいこと」として問われることも。考え方や答え方を「「入社後したいこと」はどう答えたら良い?キャリアプランを聞く理由と答え方を解説!」の記事でまとめています。
かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
効率的に自己分析を行う5つの方法
自己分析に対して「どこから手をつけて良いのか分からない」「自分だけでは深掘りできない」と感じているなら、外部ツールや異なる視点から自分を見つめ直す方法が有効。ここでは、適性診断テストや自分史、モチベーショングラフといった自己分析の補助的な手法を紹介します。
1.適性診断テストを利用する
「自己分析をどう始めれば良いのかわからない」と感じている人にとって、適性診断テストはとても役立つツールです。なぜなら、簡単な質問に答えるだけで自分の性格傾向や向いている職種、仕事への価値観などを客観的に把握できるから。
たとえば、結果を見て「確かに自分は一人でコツコツ進める作業が得意だな」と思い当たる経験があれば、そこを起点にして過去の行動や考えを掘り下げてみましょう。自分でも気づかなかった特徴に気づけることもあり、自己分析の幅がぐっと広がります。
診断結果をきっかけに自分の過去の選択や行動パターンを振り返ることで、表面的な情報だけでなく、価値観や思考の傾向まで見えてくるはずです。
ただし、適性判断だけで自己分析を完結させるのは避けましょう。あくまでも傾向を把握するものとして、結果から自分だけの経験や傾向を深掘りします。また、個人情報を不必要に記入するなど悪質なサイトも存在するようなので、必ず信頼できる運営元化を確認してください。
2.自分史を作成する
「自分史」を作ることも、自己分析に取り組むうえで効果的な方法の一つ。自分のこれまでの経験を時系列で振り返り、印象的だった出来事を整理することで、自分の性格や価値観、行動パターンを客観的に把握していきます。自己分析のやり方がわからないと感じている人にとっては、具体的なエピソードをもとに考えられる点が大きなメリットになるでしょう。
幼少期から振り返るのがベストですが、自己分析に苦手意識があるなら直近にあたる高校から大学までの期間に絞るのが効果的。たとえば、「なぜその部活動を選んだのか」「どうして今の大学・学部を選んだのか」「どのような理由でそのアルバイトを始めたのか」といった問いを自分に投げかけてみてください。この時期は、人生の中でも自分で意思決定をする場面が増える時期であり、自己理解のヒントが多く詰まっています。
それらの選択に至るまでの考えや、選んだ結果どのようなことを感じたかを丁寧に言葉にしていくことで、自分の行動の傾向や価値観が浮かび上がるでしょう。
追加で未来について考えるのもおすすめ
過去から現在までを振り返ったうえで、余裕があれば「これから先の自分」についても想像してみましょう。過去の経験から得られた気づきをもとに、「どのような仕事でやりがいを感じそうか」「どんな環境が自分に合っていそうか」といった未来のビジョンを描いてみると、進むべき方向性が見えてきます。
就職活動の際に「5年後・10年後の自分」について問われたときにも、説得力のある回答を準備するのに役立つでしょう。
3.モチベーショングラフを作成する
感情の浮き沈みを可視化する「モチベーショングラフ」を作ることも、自己分析の方法として有効。モチベーションが高まった時期や落ち込んだ時期をグラフにすることで、自分がどのような状況や出来事に影響を受けやすいのかが明確になり、そこから自分の価値観や行動パターンを読み解けます。
モチベーショングラフの作成ポイントは、直近の出来事だけにとらわれず、なるべく過去全体を振り返ること。自分史と同じように幼少期から現在までの中で、モチベーションが大きく上がった時期、逆に下がった時期を曲線で表現します。
このとき、細かい出来事をすべて思い出す必要はなく、感情の動きが特に大きかった場面に注目して描いてみてください。そして、その曲線を眺めながら、「なぜこの時モチベーションが高まったのか」「なぜこの時は低下したのか」といった背景を考えていくと、自分が何に喜びややりがいを感じ、どんな出来事にストレスを感じるのかといった傾向が見えてくるでしょう。
次に、描いたグラフをもとに、それぞれの波の要因を深掘りしていきます。一つひとつの起伏について、その時どんな出来事があったのか、どのような気持ちだったのかを振り返りましょう。モチベーションが上がった理由だけでなく、下がった原因や、その出来事を通して得た学びや成果にも目を向けることが大切です。
単に「嬉しかった」「つらかった」という感情だけでなく、自分がどんな価値観を大切にしているのか、どのような場面で力を発揮しやすいのか、といった自分の強みや特性を明確にできます。その結果、自分が何に影響されやすいのか、どんな状況で力を発揮できるのかといった「自分らしさ」の輪郭をつかめるように。就職活動やキャリア選択の場面での自己理解にもつながるため、時間をかけて取り組む価値のある自己分析方法といえるでしょう。
4.他己分析を行う
自己分析がわからないと悩む人におすすめなのが、他己分析。他己分析とは、他者に自分を分析してもらうことで、自己分析の目的である「客観的に自分を見る」が叶う方法です。
周囲から自分がどのように見えているのか、自己認識と同じ点・異なる点は何かなどを確認することで、自己分析のきっかけになるだけでなく、説得力のある内容を作れるでしょう。
なお、他己分析を行うときは回答をまとめるためにも「自分ってどんな人?」と漠然と質問するのではなく、具体的な質問を作成するのがおすすめ。また、特定の関係性やコミュニティに限らず、「家族」「親友」「バイト先の先輩・後輩」「ゼミの仲間」など、幅広い関係性の人に頼みましょう。自分と関わる立場が変わることで、抱く印象や挙げるエピソードが変わるからです。環境や関係性が変わっても一貫しているものがあれば、それは自分の強みや弱み、適性と考えることができるでしょう。
他己分析の質問例を「他己分析とは?有意義かつ効率的なやり方のポイントや質問例30選を紹介」の記事にもまとめているので、参考にしてください。
5.就活エージェントサービスを利用する
自己分析の目的ややり方がわからないときは、エージェントサービスを活用するのもおすすめです。エージェントとは、就職や転職を希望する人を総合的にサポートする民間サービスのこと。登録すると専任のアドバイザーがつき、相談から内定までを一環してサポートしてもらえます。
担当アドバイザーに自己分析のやり方を教えてもらうほか、他己分析を依頼することもOK。就活のプロが行ってくれるので、企業にアピールできる強みや長所が見つかるでしょう。
かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
自己分析がよくわからないと悩む人へ
就活の第一歩といわれる自己分析ですが、具体的に何をやればいいのか・どうすればいいのか悩む方も多いでしょう。しかし、説明した通り目的がわからないまま自己分析を行っても期待する結果は得られず、やり直すことに。
就活は時間との戦いでもあるため、余裕のあるうちから自己分析をスタートさせてフェーズごとにやり直すのもおすすめです。やり直すうちに自己分析の目的がわかり、内容もブラッシュアップしていくでしょう。
それでも自己分析のやり方がわからなかったり、取り組んでみてもいまいちな結果しか出なかったりするときは、就職エージェントのキャリアチケットに相談してください。キャリアチケットでは専任の就職アドバイザーが自己分析のやり方とコツをサポート。自己分析結果から適性に合う仕事の紹介も行っています。
自己分析に限らず、就職活動でわからないことがあればぜひご相談ください。
かんたん1分!無料登録自己分析のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら