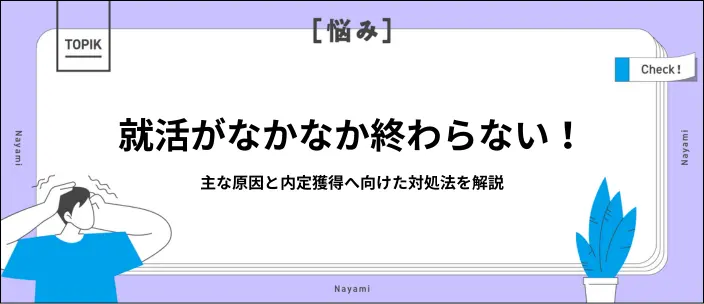このページのまとめ
- 就活の軸とは、「働くうえで譲れない自分なりの基準」になるもの
- 企業が就活の軸について質問する理由は、応募者の価値観や志望度の高さを確認するため
- 就活の軸について答えるときは、結論から述べて理由を裏付けるエピソードを伝える

「就活の軸を聞かれたらどのように答えればよいのか」「そもそもなぜ軸が必要なのか」など、疑問を持つ就活生もいるでしょう。就活の軸とは、自分に合った企業や仕事を探すための基準になるものです。
この記事では、就活の軸を聞かれたときの答え方について、例文とあわせて解説します。就活の軸を定めるメリットや具体的な決め方も紹介するので、自信を持って就活を進めるためにチェックしておきましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 就活の軸とは?具体例を一覧で紹介
- 職種や仕事内容
- 企業の社風や雰囲気
- 企業理念
- 労働環境や待遇
- 企業が面接やESで就活の軸について質問する理由
- 応募者の価値観・志望度を見極めるため
- 社風に合う人材かを確かめるため
- 長く働いてくれるかを判断するため
- 面接やESで就活の軸について聞かれたときの答え方
- 結論から答える
- 理由を裏付けるエピソードを伝える
- 企業と関連性のある内容にする
- 面接やESで就活の軸について回答する際の注意点
- 給与や待遇に焦点を当てないようにする
- 就活の軸と志望動機に一貫性を持たせる
- どの業種にも当てはまる内容は避ける
- 面接やESにおける就活の軸の回答例文12選
- 例文1.「顧客の課題を解決したい」
- 例文2.「関わる人を笑顔にしたい」
- 例文3.「相手に寄り添う仕事をしたい」
- 例文4.「人々の生活を支える仕事をしたい」
- 例文5.「チームワークを重視して働きたい」
- 例文6.「人々の生活を豊かにしたい」
- 例文7.「人の役に立つサービスを生み出したい」
- 例文8.「コツコツと集中できる仕事をしたい」
- 例文9.「世界で活躍したい」
- 例文10.「将来性のある業界で働きたい」
- 例文11.「地域に密着した仕事をしたい」
- 例文12.「専門知識を活かしたい」
- 就活の軸はES提出前に決めておくことがおすすめ
- 就活の軸を定める3つのメリット
- 1.自分に合う企業を見つけられる
- 2.一貫性のあるアピールができる
- 3.内定を獲得したときの判断基準になる
- 就活の軸の決め方4ステップ
- 1.自己分析を行う
- 2.業界研究や企業研究で情報を集める
- 3.将来のビジョンや目標を考える
- 4.就職で重視するものを考える
- 就活の軸が決まらないときにできる対策
- インターンシップに参加する
- 企業説明会に参加する
- 他己分析を行う
- 企業を比較してみる
- 選択肢から外す軸を考えてみる
- 就活エージェントに相談する
- 自信を持って就活の軸を回答できるようになりたい方へ
就活の軸とは?具体例を一覧で紹介
就活の軸とは、「自分なりの仕事選びや企業選びにおける譲れない基準」を意味します。就活の軸は、「強みを活かせるか」「やりたい仕事ができるか」「理想の働き方ができるか」などを基準に考えましょう。
ここでは、就活の軸の具体例を紹介します。
職種や仕事内容
営業職や事務職などの職種や、仕事内容から就活の軸を選ぶのも方法の一つです。職種や仕事内容といった軸であれば、比較的決めやすいといえるでしょう。
具体的には、以下のようなものが職種や仕事内容に関する就活の軸にする例です。
・人と関わる仕事をしたい
・関わる人を笑顔にしたい
・顧客の問題を解決したい
・周囲と協力して規模が大きい仕事をしたい
・コツコツと集中できる仕事をしたい
これらの軸を考える際にまずは、「自分がどのような仕事に就きたいのか」「何を成し遂げたいのか」から考えると、イメージが湧きやすくなります。
企業の社風や雰囲気
企業の社風や雰囲気が自分に合うかどうかで、応募先を選ぶ就活生も少なくありません。どの企業であっても同僚と協力して働くことになるため、社風や雰囲気、人が合うかは重要なポイントです。
企業の社風や雰囲気に関する就活の軸として、以下のような内容が考えられます。
・明るい職場で働きたい
・チームワークを重視する環境で働きたい
・若手のうちから裁量権を持って働きたい
・スピード感のある環境で働きたい
・新しいことにチャレンジしやすい環境で働きたい
どのような雰囲気であれば、自分に合った環境かを考えてみてください。
企業理念
企業理念が自分に合うかどうかも、就活の軸を決める判断材料になります。企業と自分の考え方が一致していれば、仕事を進めやすく、モチベーションも上がるでしょう。
企業理念に関する就活の軸として、以下のような例が挙げられます。
・理念に共感できる企業で働きたい
・経営者との距離が近い環境で働きたい
・海外で活躍したい
・海外展開している企業で働きたい
・将来性のある企業で働きたい
なお、企業理念は、会社のWebサイトや採用ページに書いてあるケースが一般的です。ミスマッチ防止にもつながるので、自分の価値観が企業理念とかけ離れていないかチェックしてみてください。
労働環境や待遇
労働環境や待遇などを就活の軸に選ぶのもおすすめです。たとえば、以下のような内容を就活の軸に定められます。
・残業が少ない環境で働きたい
・ワークライフバランスへの取り組みが行われている環境で働きたい
・リモートワークができる環境で働きたい
・フレキシブルな勤務体制がある企業で働きたい
・完全土日祝休みの企業で働きたい
働きやすい環境は、成果の出しやすさにもつながるでしょう。働くモチベーションも高まるため、労働環境に関する希望についても考えてみてください。
面接で就活の軸を聞かれた場合は、職種や仕事内容など、仕事に対して前向きな印象を与える事柄を選ぶことがポイントです。就活の軸をどのように伝えるか悩む場合は、「面接官に伝わりやすい「就活の軸」の作り方とは?」の記事も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
企業が面接やESで就活の軸について質問する理由
企業がなぜ就活の軸を聞くのかを知っておくと、軸を考えるヒントになります。ここでは、企業が就活の軸を聞く理由を解説します。企業が知りたいことを網羅できているかどうかを意識して、就活の軸を考えてみてください。
応募者の価値観・志望度を見極めるため
企業が就活の軸について質問するのは、応募者がどのような価値観を持ち、どのような企業で働きたいと考えているかを知るためです。就活の軸を通して、応募者の考え方と自社の理念や方針が合っているかどうかを確認し、入社後に長く活躍してくれる人材かを見極めています。
また、就活の軸が明確であれば、企業選びに一貫性があると判断され、志望度の高さも伝わりやすくなります。反対に、軸があいまいな場合は、企業選びの基準が見えにくく、「なんとなく応募している」という印象を与えることもあります。
企業が何を大切にしているかを理解したうえで、自分の考えや価値観に合った軸を伝えることが大切です。
社風に合う人材かを確かめるため
企業が就活の軸について質問するのは、応募者が自社の社風に合う人材かどうかを確かめる意図もあります。社風に合わない企業に入社すると、周囲とうまく馴染めなかったり、スキルアップできなかったりして、早期離職につながるためです。
企業は就活の軸を聞いて、応募者が自社に馴染めるのか、実力を発揮できるのかを判断しています。
長く働いてくれるかを判断するため
働く意欲がどれほどあるかを判断するのも、企業が就活の軸を質問する理由です。企業は採用活動において、できるだけ長く働いてくれる人材を求めています。
特に、新卒採用はポテンシャル採用と呼ばれ、即戦力になるスキルや経験よりも、就活生の将来性を高く評価される傾向です。働く意欲や仕事に対する熱意がなければ、長く働き続けるのは難しいでしょう。
企業がどのような考えで採用を行っているかは、企業研究を通して理解できます。企業研究の方法について、「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事で解説しているので参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
面接やESで就活の軸について聞かれたときの答え方
面接やエントリーシートで就活の軸について聞かれたときは、結論から伝えると好印象です。分かりやすく内容が伝わるように、答え方を工夫しましょう。
ここでは、実際にどう答えればよいか、ポイントを紹介します。
結論から答える
就活の軸について聞かれたら、「私の就活の軸は△△です」のようにまず結論から伝えます。結論から伝えたほうが、面接官が内容を理解しやすくなるからです。
補足説明やエピソードから伝えてしまうと、「結局、何が軸なのだろうか」と思われてしまう可能性があります。内容が良くても、伝わらなければ評価にはつながりにくいでしょう。
結論のあとにエピソードを伝えれば、話の流れを理解しやすく、説得力も増します。就活の軸に限らず、面接やエントリーシートでは結論から伝えるよう意識してください。
理由を裏付けるエピソードを伝える
就活の軸を伝える場合は、理由を説明するためのエピソードも添える必要があります。軸にする理由が伝わらなければ、評価されにくいからです。たとえば、「人と関わる仕事をしたい」とだけ伝えても、面接官からするとなぜなのか理由が分かりません。
「接客のアルバイトでは、お客さまからの『ありがとう』という言葉がモチベーションになった。これからもたくさん『ありがとう』の言葉をいただけるように、人と関わる仕事に就きたい」といったエピソードがあると、面接官も納得しやすいでしょう。
エピソードがあると説得力が増すだけではなく、内容にオリジナリティが加わります。自分にしかないエピソードを探し、就活の軸とあわせて伝えましょう。
就活で伝えるエピソードを探すコツについては、「学生時代に頑張ったことがない…エピソードの見つけ方や例文を解説」の記事を参考にしてください。
企業と関連性のある内容にする
就活の軸で伝える内容は、応募企業と関係があるものを選びましょう。企業に関係ない軸を伝えても、評価してもらえない可能性があります。
就活の軸が企業と合わないと、「入社後のミスマッチが起きる」「早期離職のリスクが高い」といったマイナスの印象を与えかねません。就活の軸に合った働き方が志望企業で実現できるかを考えたうえで回答するようにしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
面接やESで就活の軸について回答する際の注意点
面接やエントリーシートで就活の軸について聞かれたときは、給与や待遇、ありきたりな内容を避けて回答しましょう。
面接やエントリーシートで就活の軸について回答する際の注意点を解説するので、参考にしてください。
給与や待遇に焦点を当てないようにする
面接やエントリーシートで就活の軸を伝える際は、給与や待遇に焦点を当てないようにしましょう。給与や待遇だけに触れてしまうと、採用担当者に仕事への意欲が低いといった印象を与えかねません。
給与や待遇を就活の軸にしたり、働く環境に魅力を感じて企業選びしたりする方もいるでしょう。しかし、面接やエントリーシートで回答する際は、職種や仕事内容など、仕事に対する意欲をアピールするような軸のほうが好印象につながります。
就活の軸と志望動機に一貫性を持たせる
面接やエントリーシートで就活の軸について回答する際は、志望動機と一貫性を持たせるのもポイントです。志望動機とは、応募先企業で働きたいと思った理由や動機などを説明するもので、就活でたびたび質問されます。
就活の軸と志望動機に一貫性を持たせられると、それぞれの回答に説得力が生まれ、企業からの高評価につながるでしょう。ただし、就活の軸と志望動機を同一の内容にしてしまうと、採用担当者から「質問の意図を理解していない」と評価される可能性がある点に注意してください。
どの業種にも当てはまる内容は避ける
就活の軸について聞かれた際、どの業種や仕事にも当てはまる回答は避けましょう。抽象的な内容は採用担当者の印象に残りづらく、アピールにつながりにくいためです。
たとえば、「仕事を通して成長したい」のような内容は、どの企業でも共通します。そうすると、志望先を絞り込みできず、企業選びの軸を明確に伝えるのが難しくなるでしょう。抽象的な内容になってしまう場合は、あらためて業界研究や企業研究に取り組んだり、インターンシップに参加したりするのがおすすめです。
企業研究のやり方や活かし方については、「企業研究の目的とやり方は?簡単に情報をまとめられる方法を解説」の記事を参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
面接やESにおける就活の軸の回答例文12選
ここでは、面接やエントリーシートで就活の軸について聞かれた場合の回答例文を紹介します。就活の軸ごとに回答例文をまとめているので、参考にしてみてください。
例文1.「顧客の課題を解決したい」
私の就活の軸は、顧客の問題を解決できる仕事に就くことです。
大学のゼミで、グループワークをうまく進められなかった経験があります。そのとき、進捗状況をLINEグループで報告して共有するなど、自分なりに工夫してメンバーと接したところ、メンバーから「△△のおかげで話し合いがしやすくなった」と言われました。
この経験から、私は問題を解決することで人の役に立ちたいと思うようになりました。そのため、自身が関わった広告で顧客の悩みに寄り添い、問題解決に向けたサポートができるこの仕事に就きたいと考えています。
例文2.「関わる人を笑顔にしたい」
私の就活の軸は、関わった人を笑顔にできる仕事に就くことです。
私は大学時代に4年間、レストランで接客のアルバイトをしていました。料理を提供するときやお客さまが帰るときに見せてくれた笑顔が、仕事のやりがいにつながっていました。
このような経験から、関わった人の笑顔を近くで見ることのできるサービス業に就きたいと考えています。
例文3.「相手に寄り添う仕事をしたい」
私の就活の軸は、相手に寄り添い、人々の支えになれる仕事をすることです。
高校3年生のとき、大学選びに迷って学校の先生に相談した経験があります。当時、先生がとても親身になって寄り添ってくれたからこそ、後悔のない学生生活が送れています。この経験を通して、私は自分に寄り添い、支えてくれる存在のありがたさに気づきました。
私自身も、親身になって相手に寄り添える仕事に就きたいと考えています。
例文4.「人々の生活を支える仕事をしたい」
私の就活の軸は、人々の生活を支える仕事に就くことです。
日本には震災や台風といった自然災害が多く、当たり前の日常が送れることの大切さを実感する場面があります。去年の台風では、自宅が停電し、とても不安な気持ちで夜を越しました。
この経験から、私は人々の日常における「当たり前」を守り、社会に安心感を届けられる仕事に就きたいと考えています。
例文5.「チームワークを重視して働きたい」
私の就活の軸は、チームワークを重視して働くことです。
私はバレーボール部の部長を務めています。個々の部員の能力は高いものの、連携プレーに課題があり、なかなか大会で勝ち進めない状況が続いていました。そこで、監督と相談してチームプレーを中心としたメニューに変更したところ、地区大会ベスト4という目標を達成しました。
この経験を通してチームで協力して成果を出すことに喜びを感じたことから、チームワークを重視して働きたいと考えています。
例文6.「人々の生活を豊かにしたい」
私の就活の軸は、人々の生活を豊かにする仕事に就くことです。
私は大学のゼミでロボット競技会の全国大会に出場しました。自律走行のレスキューロボットを製作した経験から、自分が作る製品やサービスを通して社会に良い影響を与えたいと考えるようになりました。
これまでの経験を活かし、技術を活用して人々の生活の質を向上させる製品の開発に携わりたいと考えています。
例文7.「人の役に立つサービスを生み出したい」
私の就活の軸は、人の役に立つサービスを提供する仕事に就くことです。
私は大学時代にホテルのレストランで接客のアルバイトをしていました。記念日やお祝いのために利用されるお客さまが多く、私はご来店目的を丁寧にヒアリングし、ニーズに合わせてプランを提案しました。お客さまから「ここに決めて良かった」と言われた経験をきっかけに、相手の期待を超えるサービスを生み出す仕事にやりがいを感じました。
これまでの接客経験を活かし、今後も仕事を通してお客さまが求める以上のサービスを提供していきたいと考えています。
例文8.「コツコツと集中できる仕事をしたい」
私の就活の軸は、コツコツと集中できる仕事をすることです。
私は中学時代から大学までバスケットボール部に所属していました。中学時代からベンチメンバーとしてチームを支える場面が多く、決して才能に恵まれているわけではありませんでした。しかし、ほかのベンチメンバーと協力し、工夫しながらコツコツと毎日練習に取り組んだ結果、大学3年生になってからレギュラーの座をつかみました。
この成功体験を活かし、コツコツと仕事に取り組みながら、スキルの向上を図れる仕事に就きたいと考えています。
例文9.「世界で活躍したい」
私の就活の軸は、グローバルに活躍できる企業で能力を発揮することです。
大学3年の夏、私はマレーシアのホテルでのインターンシップに参加しました。多国籍のスタッフと現地で働く中で語学力を高め、異文化理解を深めました。世界中のお客さまにサービスを提供することにやりがいを感じ、将来はグローバルな視野を持って働きたいと考えるようになりました。
この経験を通して身につけた国際感覚を活かし、グローバル事業の発展に携わりたいと考えています。
例文10.「将来性のある業界で働きたい」
私の就活の軸は、将来性のある業界で働くことです。
大学時代に、所属するゼミで都市インフラのDX化に関する研究に取り組みました。地域防災システムを地域の防災訓練で使用した事例調査をきっかけに、IT技術を活用して社会に貢献できる仕事に就きたいと考えるようになりました。
大学で学んだ知識を活かし、最先端の技術を駆使して社会課題の解決に努めたいと考えています。
例文11.「地域に密着した仕事をしたい」
私の就活の軸は、地域に密着した仕事をすることです。
大学では公共政策学研究科に所属し、行政が社会に果たす役割について深い関心を抱きました。ゼミでは政策提言プロジェクトに取り組み、行政が適切な政策を策定・実行することで、地域はもとより国全体にも大きな影響を与えられると実感しました。
大学での学びをきっかけに、私は地域に密着した仕事を通して国民一人ひとりの暮らしを支え、より良い社会の実現に向けて貢献していきたいと考えています。
例文12.「専門知識を活かしたい」
私の就活の軸は、プログラミングの専門知識を活かせる仕事に就くことです。
私は高校時代から独学でプログラミングを勉強し、Webサイト制作に取り組んできました。大学ではプログラミングサークルに所属し、ほかのサークルや部活のWebサイト制作を担いました。ユーザーが使いやすく、視覚的に分かりやすいWebサイトを構築し、自分のスキルを活かして人の想いを可視化することにやりがいを感じました。
この経験と専門知識を活かしながら、スキルを高めていける環境で働きたいと考えています。
面接やエントリーシートにおいて自分の言葉でうまく説明できるよう、あらためて何を就活の軸にするか考えてみましょう。就活の軸の例文や一覧を「就活の軸一覧100選!納得がいく決め方や面接での答え方を例文付きで解説」の記事で紹介しているので参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の軸はES提出前に決めておくことがおすすめ
就活をスムーズに進めるためにも、就活の軸はエントリーシート提出前に考えておきましょう。具体的には、遅くても大学3年生の3月までには就活の軸を決めておくのがポイントです。
内閣府の「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書」によると、就活におけるエントリーシートの提出時期は大学3年の3月がピークでした。

引用元:内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(62p)」
エントリーシートの提出までには就活の軸を決めておくと、企業選びがしやすくなるほか、志望動機を考えるのにも役立ちます。なお、同調査によると、大学3年の9月より前に最初のエントリーシートを提出している学生の割合は3割を超えていました。

引用元:内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(62p)」
大学3年の9月より前にエントリーシートを提出している背景には、インターンシップに参加する就活生が多い点が挙げられます。また、経団連に参加していない企業や外資系企業、ベンチャー企業などは大学3年生の秋ごろから募集を行うケースもあるからです。
志望企業がいつエントリーを始めても困らないように、就活の軸は早めに決めておきましょう。就活の軸さえ決めておけば、企業選びはもちろん、履歴書やエントリーシート作成にも役立ちます。
就活の流れや一般的なスケジュールについては、「就活のやり方を徹底解説!基本的な進め方やスケジュールをご紹介」の記事も参考にしてください。
参照元
内閣府
学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の軸を定める3つのメリット
就活の軸を決めておくと、ミスマッチを防止できたり、選考で一貫性のあるアピールができたりするメリットがあります。ここでは、就活の軸を定めて就活を行うメリットを解説するので、参考にしてください。
1.自分に合う企業を見つけられる
就活の軸を決めておくと、自分に合う企業・合わない企業が分かりやすくなります。判断基準がある分、効率的に就活を進められるでしょう。
就活の軸が決まっていないと、選択肢が多過ぎてしまい、どの企業を選べばよいのか分かりにくくなります。一方で、「営業職に就きたい」「チームで成果を出す仕事がしたい」といった就活の軸があれば、企業の絞り込みが可能です。
就活は、企業研究から面接対策までやることが多く、効率的に進める必要があります。就活の軸を決めて、企業選びをスムーズに行いましょう。
2.一貫性のあるアピールができる
就活の軸を定めると、企業に対して一貫性のあるアピールができます。就活の軸に沿って履歴書やエントリーシートを作成したり、面接官からの質問に回答したりできるからです。就活の軸を明確に伝えられると、自己分析ができているといった評価にもつながります。
一方で、就活の軸が定まっていない場合は、「自分の考えを持っていない」「企業研究が足りていない」などとマイナスの印象を与えかねません。どのような考えや価値観を持って就活に取り組んでいるかを重視する企業もあるので、就活の軸は明確にしておくようにしてください。
3.内定を獲得したときの判断基準になる
就活の軸があれば、内定を獲得したときに「承諾する・しない」の判断がしやすくなります。特に、複数の企業から内定を得た場合、就職先選びに悩む学生も少なくありません。しかし、就活の軸を判断基準にすると、より自分の価値観に合った企業選びが可能になります。
「就活の軸を決めなくても、就活はうまくいっている」という人もいるでしょう。しかし、複数の企業から内定をもらった場合の判断基準になる点で、就活の軸を定めておくメリットはあるといえます。
企業から内定をもらったときの対応については、「就活で内定をもらったときの対応!辞退するときの注意点」の記事を参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の軸の決め方4ステップ
ここでは、就活の軸を見つけるために実施したい4つのステップを解説します。就活の軸をなかなか決められない方は、自己分析や業界研究に取り組み、自分の譲れない条件や価値観について考えてみましょう。
1.自己分析を行う
就活の軸を決めるためには、まず自己分析から始めるのがおすすめです。自分が就職に何を求めているのか分からなければ、軸は定まりません。
たとえば、次のような質問を通して自分について探ってみましょう。
・自分は何をすることが好きか
・得意なことは何か
・強みは何か
・長所や短所は何か
・どのような環境で活躍できるか
・仕事に何を求めるのか
すでに興味を持っている仕事がある場合、「なぜその仕事に興味があるのか」を深掘りしていく方法もおすすめです。なお、自己分析の方法は、「自己分析とは?就活におすすめの簡単なやり方10選や活用例を解説」も参考にしてください。
2.業界研究や企業研究で情報を集める
業界研究や企業研究に取り組み、「どのような業界・企業があるのか」を知ることも重要です。知識が増えると選択肢が広がり、就活の軸を決めやすくなります。
業界研究を通して自分が知らなかった業界に興味が生まれ、エントリーにつながるケースもあるでしょう。また、企業研究から新しい職種や仕事内容を知り、自分に合うものが見つかる可能性も考えられます。
世の中には知らない企業や仕事も少なくありません。就活の軸や企業選びで迷う場合は、業界研究や企業研究に力を入れるのがおすすめです。
3.将来のビジョンや目標を考える
「将来どのような仕事をしたいか」「達成したい目標はあるか」といった問いから、就活の軸を考える方法もあります。業界研究や企業研究に取り組むうちに、将来のビジョンや目標の具体的なイメージが湧いてくるでしょう。
仕事内容だけではなく、「リーダーとして成果を出したい」「社長を目指す」などのように、役割や立場から考えるのも方法の一つです。将来のビジョンや目標を考えていくと、希望する条件や価値観の明確化につながります。
4.就職で重視するものを考える
就職にあたって、自分が大事にしている条件や考え方があれば、あらかじめピックアップしておいてください。
たとえば、「英語を使う仕事がしたい」といった希望も就活の軸になります。海外出張がある業種や海外に事業所がある企業を探せると、就活の軸が明確になるだけではなく、志望動機にも一貫性を持たせられるでしょう。
難しく考えずに、自分の希望から就活の軸を考えてみるのがポイントです。譲れない条件がある場合は、その内容を就活の軸にしてみてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の軸が決まらないときにできる対策
就活の軸が決まらずに困っている場合は、インターンシップや企業説明会に参加すると、働くうえで譲れない条件を見つけるヒントになります。就活の軸が決まらないときにできる対策を紹介するので、参考にしてください。
インターンシップに参加する
就活の軸が決まらない就活生に多いのが、「仕事内容が分からない」「働くイメージが湧かない」といった悩みです。インターンシップに参加して、実際に仕事を経験してみると、このような悩みの解決につながるでしょう。
インターンシップによっては実際に仕事を体験できる企業もあり、就職に対するイメージの具体化に役立ちます。もし、仕事内容が合わない場合でも、「△△の職種や仕事内容以外を選ぶ」といった軸を決めることも可能です。
企業選びには避けたいことの明確化も役立つため、インターンシップを通じて自分に合う・合わないといった条件を洗い出しておきましょう。
企業説明会に参加する
就活の軸が決まらないときは、企業説明会に参加して情報収集に努めるのも方法の一つです。情報が増えるほど、就活の軸も決めやすくなります。
社会にはイメージが湧かない企業や仕事も多く、情報がない状態では向き・不向きの判断ができません。特に、BtoBの業界や企業は日常で目にする機会が少なく、自分から情報を探す必要があります。
企業説明会は、担当者に直接質問できる貴重な機会です。Webサイトや採用ページに記載されていない情報が入手できるケースもあるので、積極的に参加してみてください。
企業説明会の探し方や参加方法については、「企業説明会の種類や見つけ方は?参加時の注意点や質問の悩みについても解説」の記事を参考にしてください。
他己分析を行う
他者から見た自分の長所やスキルを参考に、就活の軸になるヒントを得る方法もあります。客観的な意見を通して、自分では気づかなかった新しい視点が得られるでしょう。
たとえば、「チームメンバーが困っているときは、いつでも助けてくれる」と他者に評価されたとします。この場合、チームでする仕事が向いているといえるでしょう。就活の軸としては、「チームワークを重視する企業を優先する」「個人主義の企業は避ける」などが考えられます。
他者からの客観的な分析は就活を進めるうえで貴重な視点になるので、積極的に意見をもらってみてください。
企業を比較してみる
企業同士を比較し、自分の考え方や希望する条件を探す方法もおすすめです。「A社とB社であればどちらがよいのか」に答えられる場合は、何を基準に企業選びをしているのかを深掘りできます。
たとえば、「給与は下がっても、年間休日が多いB社がよい」となれば、休日を重視している点に気づけるでしょう。一方で、「残業は多いけど、仕事のやりがいを追求したい」といった考えもあります。
ほかにも、「C社には、A社とB社にはない気になる職種がある」など、複数社の比較を繰り返すと、企業選びの軸が見えてくるでしょう。
選択肢から外す軸を考えてみる
長所や強みではなく、短所から就活の軸を探す方法もあります。優先して選ぶ軸が見つからない場合は、選択肢から外す軸を考えるのも効果的です。
たとえば、「新しいアイディアを発想するのが苦手で、企画力がない」といった短所がある場合、「デザインなどのクリエイティブ職は就活の軸から外したほうがよい」と考えられます。
就活では、向いている仕事を探すだけではなく、向いていない業種や職種を選択肢から外すことも大切です。短所もあわせて分析しながら、仕事の向き・不向きを考えてみましょう。
就活エージェントに相談する
自分だけでは就活の軸を見つけられないと感じたら、就活のプロへの相談がおすすめです。就活エージェントであれば、一人ひとりの状況に応じて適切なアドバイスをしてくれます。
就活エージェントを利用する場合、就活の軸だけではなく、自己分析や企業研究などに関するアドバイスもあわせてもらえるのが特徴です。これから就活の軸を探そうとしている学生や、自己分析からやり直したいと考えている方も安心して利用できます。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
自信を持って就活の軸を回答できるようになりたい方へ
就活の軸を考えても、なかなか決まらなかったり、答え方に迷ったりしてしまう学生も多いでしょう。業界や仕事内容、企業規模など、就活では選択肢が多く、自分なりの軸を持っておかなければ、判断を誤ってしまう可能性があります。
「自分だけでは就活の軸を決めるのが難しい」「どのように就活の軸を答えたらよいか分からない」と感じる方は、エージェントへの相談もおすすめです。
就活エージェントのキャリアチケットでは、就活の軸を決めるために欠かせない自己分析や業界研究、企業研究の進め方をサポートしています。自信を持って企業にエントリーできるようにアドバイスをしているので、就活の軸で悩んでいる就活生は気軽にご相談ください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら