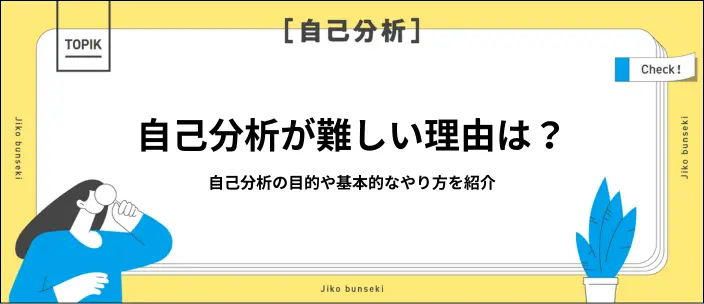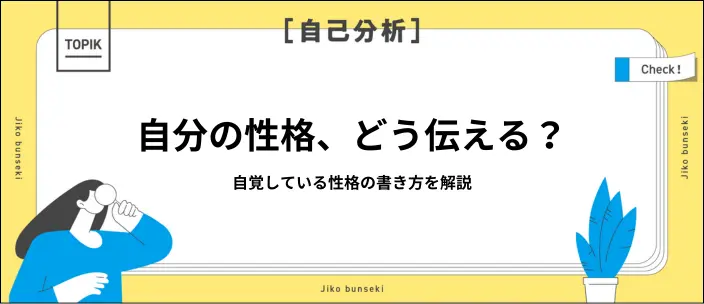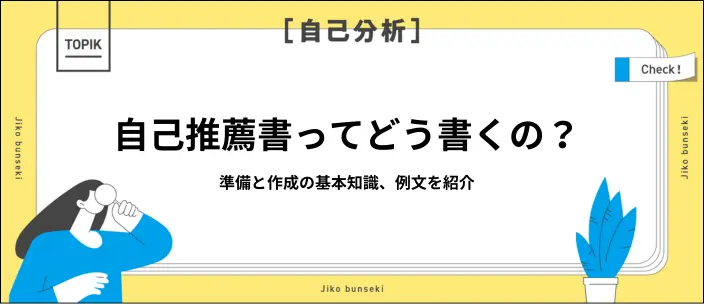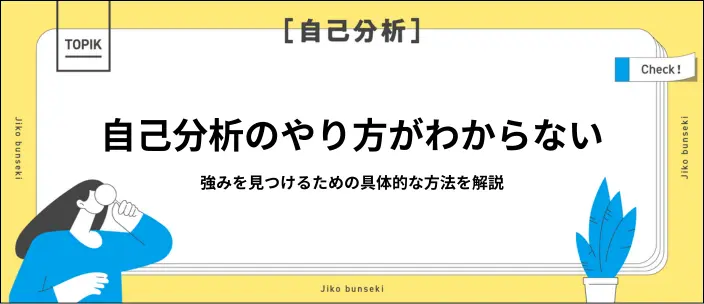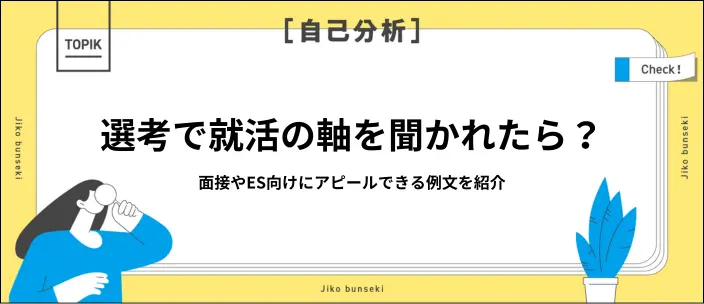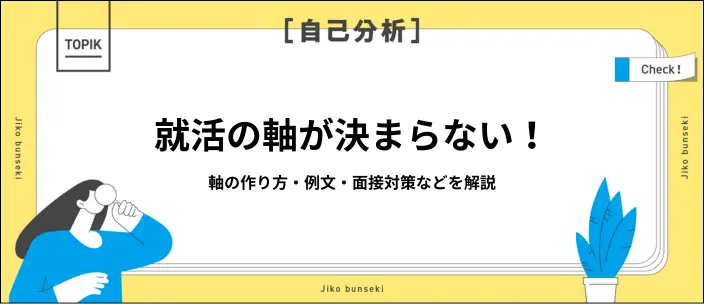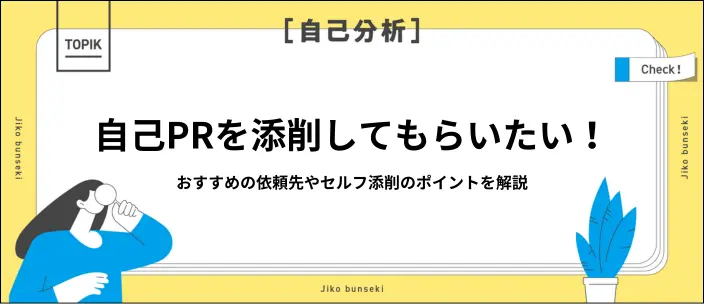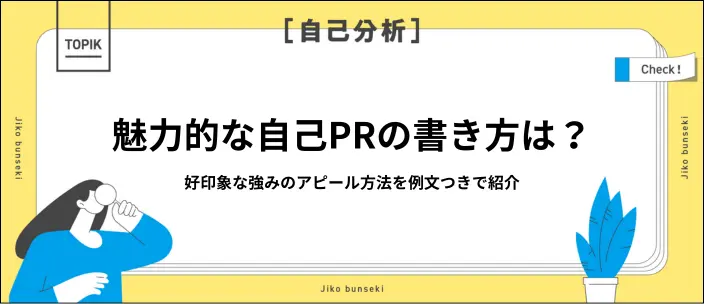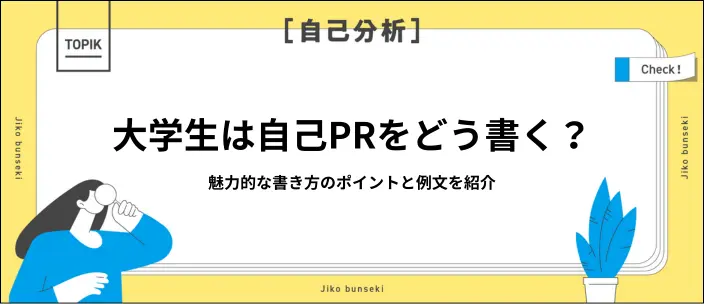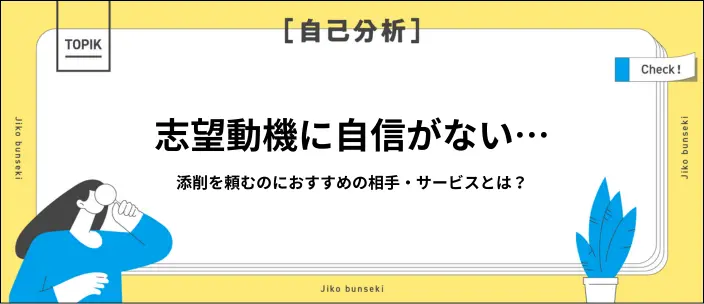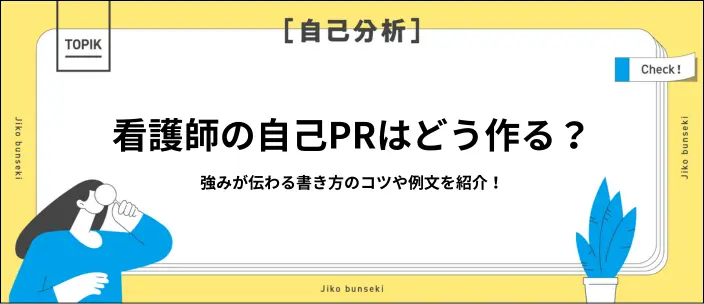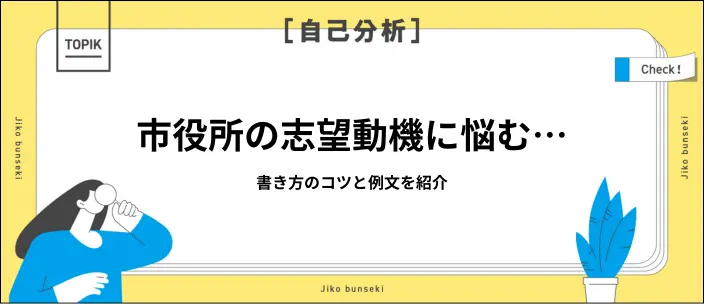このページのまとめ
- 就活の軸を設定するメリットは、入社後のミスマッチが防ぎやすくなること
- 企業側が就活の軸を聞く理由は、応募者が自社に合う人材か知りたいから
- 就活の軸がない人は、自己分析をして自分の価値観を明確にすると良い
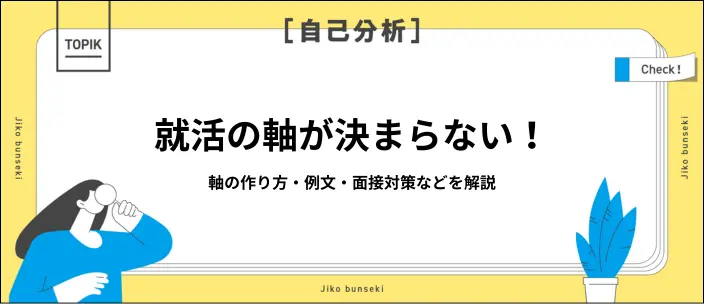
「就活の軸がない」「軸の見つけ方が分からない」と悩む人もいるでしょう。就活の軸がない人は、自己分析を行い自分の価値観を理解することから始めてみてください。就活の軸を定めると企業選びの基準が明確になり、入社後のミスマッチをなくせます。
この記事では、就活の軸の定義や設定するメリット、見つけ方、面接で伝えるコツなどを解説。軸探しに悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就活の軸の考え方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 就活の軸の定義
- 就活の軸がない人向け!設定するメリットとは
- 企業選びの基準が明確になる
- 就職活動がスムーズに進められる
- 入社後のミスマッチ防止になる
- 入社後の自分をイメージしやすくなる
- 企業側が就活の軸を聞く意図
- 就活生の仕事選びの基準を知りたい
- 志望度の高さを確かめたい
- 自社に合う人材か知りたい
- 就活の軸がない状態に陥る原因
- 就活を進めるほど迷いが生まれる
- 選択肢が多過ぎて決められなくなる
- 経験が少なく自信が持てない
- 企業のデメリットばかり見て選べなくなっている
- 就活の軸がないときの見つけ方
- 就活の軸になりやすい3つの内容
- 働き方・環境
- 企業の文化や理念
- 仕事内容
- 就活の軸で避けるべき3つの内容
- 1.給料や福利厚生などの待遇面
- 2.どの業界・企業にも当てはまる内容
- 3.消費者目線の内容
- 面接で就活の軸を伝える際のポイント
- 志望度の高さをアピールする
- 説得力のあるエピソードを添える
- 企業との共通点を具体的に伝える
- 就活の軸の例文
- 「就活の軸がない」と悩んでいるあなたへ
就活の軸の定義
就活の軸とは、「仕事をするうえで自分が大切にしたいものや譲れないもの」のことです。たとえば、「直接顧客と関わる仕事がしたい」「この業界で働きたい」「転勤はしたくない」などが就活の軸といえます。
就活を成功させるためにも、自分の強みややりたいこと、将来の目標を明確にしておきましょう。なお、就活の軸は就活がスタートしたらできるだけ早い段階で決める必要があります。
就活の軸の定義は、「就活の軸の回答例文12選!企業の質問に対する答え方のコツや注意点を解説」の記事でも解説しています。
かんたん1分!無料登録就活の軸の考え方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の軸がない人向け!設定するメリットとは
就活の軸を定めることには、以下のようなさまざまなメリットがあります。
企業選びの基準が明確になる
就活の軸を決めるメリットの一つは、志望企業が絞りやすくなることです。
軸が定まっていない場合、規模や知名度、イメージといった表面的な事柄だけにとらわれてしまうことがあります。一方、軸が定まれば、自分の価値観に合う企業や本当にやりたいことが実現できる企業を見つけられるでしょう。
就職活動がスムーズに進められる
就活の軸を持つことで、就職活動をスムーズに進められるのもメリットです。
さまざまな企業があるので、どこにエントリーするか迷う場面もあるでしょう。就活の軸が定まっていれば軸に沿って応募先を定められるので、迷う時間が減らせます。
入社後のミスマッチ防止になる
就活の軸を定めることで、入社後のミスマッチを防止しやすくなるというメリットもあります。就活の軸を持てば、自分の希望や価値観に合致しない企業に応募することが少なくなるからです。
また、面接官も就活の軸を聞き、自社の理念や仕事とマッチするかを判断しています。
入社後の自分をイメージしやすくなる
入社後の自分を想像しやすくなるのも、就活の軸を持つメリットです。
自分の価値観と全く異なる方針の企業では、入社後のイメージを思い描くのが難しいこともあります。就活の軸をもとにして選択したら、実際に働く姿が想像しやすいでしょう。
就活の軸は上記の役割を果たすだけではなく、説得力ある志望動機の作成にも役立ちます。就活の軸を設定するメリットは、「よく聞く『就活の軸』。何がそんなに大事なの?」の記事でも解説しています。
かんたん1分!無料登録就活の軸の考え方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
企業側が就活の軸を聞く意図
面接で企業側から「あなたの就活の軸は何ですか?」と問われることもあります。就活の軸は、企業側にとっても大切な要素なのです。ここでは、企業側が就活の軸を聞く意図を解説します。
就活生の仕事選びの基準を知りたい
企業が就活の軸から判断するのは、就活生が自分なりの仕事選びの基準をきちんと持っているかという点です。仕事選びの基準が明確であれば、応募企業や仕事内容への理解は深まっているはずだと企業は考えます。
仕事選びの基準が明確でない人は、知名度の高さやイメージで企業を選んでしまいがちです。企業からは、志望する業界に統一性がなく、業務内容に対する理解も伴っていないと判断されてしまう可能性があるでしょう。企業は、仕事選びに対する真剣さや志望度の高さを見抜くためにも就活の軸を聞いています。
志望度の高さを確かめたい
企業が就活生に「あなたの就活の軸は何ですか?」と質問する理由の一つは、その学生がどれだけ業界や企業に対して本気で志望しているかを確かめたいからです。
たとえば、「有名だから」「テレビCMを見たことがあるから」という漠然とした理由だけで企業を選ぶと、軸がなく本気度が足りないと思われるでしょう。
一方、「その業界の将来性に魅力を感じた」「自分のスキルを活かせると考えた」「大学で学んだ専門分野に関連している」などの具体的な理由を持っていると、志望企業に対して一貫した軸を示せます。
自社に合う人材か知りたい
企業側が就活の軸を聞くのは、就活の軸が自社に合っているか、社内で実現できるキャリアビジョンになっているかを見極めるという意図もあります。
就活生の、働き方に求めるものや仕事を通して実現したいことと、企業の理念や働き方にずれがあった場合、モチベーションを維持しながら働くのは難しいでしょう。これは、応募者と企業の双方にとって望ましいことではありません。ミスマッチを防ぐためにも、企業側は就活の軸を知る必要があるのです。
就活の軸は就活のビジョンとも言い換えられます。「就活で将来のビジョンを聞かれたら?考え方のコツと面接で使える例文7選」の記事では、就活のビジョンの答え方を解説しています。
かんたん1分!無料登録就活の軸の考え方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の軸がない状態に陥る原因
就活の軸が定まらない状態になるのは、多くの情報に触れる中で迷いや不安が生まれる自然な流れです。ここでは、就活の軸がない状態に陥ってしまう原因を整理しながら、再び自信をもって就活を進められるようになるヒントをお伝えします。
就活を進めるほど迷いが生まれる
就活を進めるほど「自分は何がやりたいのかわからなくなってきた」と悩むのは自然なことです。多くの企業・業界の情報が入ってくることで、最初はやりたいと思っていたことにもデメリットや不安を感じ、気持ちが揺れてしまうこともあります。
たとえば、最初は志望していた業界でも、働き方の厳しさや将来性への不安を知ると「本当にこの業界で良いのだろうか」と迷い、志望度が下がることがあるでしょう。こうした状況では焦って決めるのではなく、一度立ち止まり「自分が本当に大事にしたいことは何か」「何を優先したいのか」を再確認することが大切です。
選択肢が多過ぎて決められなくなる
興味のある業界が多過ぎて、どれを選べば良いかわからない状態になるのは、真剣に就活を考えている証拠です。就活は将来のキャリアを左右する大きな選択であり、どれか一つに絞るのは簡単ではありません。
実際、選択肢が多過ぎると「全部やってみたい」と思ってしまい、気づけばどれも中途半端になってしまうことがあります。そのため、自己分析やES準備、面接対策も進まず、焦りや迷いがさらに大きくなりがちです。
こうした状況を防ぐためには、インターンシップ、OB訪問、企業説明会などを活用し、実際に関わってみて自分の興味が続くかどうかを確かめてみましょう。まずは広く興味を持ち、少しずつ体験しながら興味が深まるものを見極めること自分の軸を具体化できます。
経験が少なく自信が持てない
特別な経験がない自分には、就活の軸なんて作れないのではと不安になる気持ちは自然です。しかし、軸を作るのに大きな成果や特別な経験は必要ありません。企業が知りたいのはどのような場面で何を考え、どのように行動したかという部分だからです。
たとえば、アルバイトでお客さま対応を工夫した経験や、授業のグループワークでチームをまとめた経験など、日常の中での小さな挑戦や努力は立派な強みになります。特別な結果がなくても、「そのとき自分は何を考えてどう行動したか」「そこから何を学んだか」を振り返ることで、就活で語れる自分の軸を見つけられるでしょう。
企業のデメリットばかり見て選べなくなっている
企業や業界研究を進めるほど、「デメリットばかり目についてしまい選べなくなる」ことは珍しくありません。情報収集を進める過程で、その企業や業界の課題、働くことの難しさなどのマイナス面も自然と目に入るようになるからです。
たとえば、当初は「広告業界で企画に携わりたい」と思っていたのに、「長時間労働が多い」「数字管理が厳しい」といった情報を知り、気持ちが揺れてしまう場合があります。しかしここで大切なのは、デメリットをただ避けるのではなく、自分にとって何が大事で、どこまでなら受け入れられるかを判断基準に変えていくことです。
「残業が多くてもクリエイティブに挑戦したい」など、デメリットを踏まえたうえで価値観や優先順位を整理することで、自分に合う業界・企業を見つけやすくなります。ただ否定して選択肢を狭めるのではなく、自己分析の材料として活用することで、ブレない就活の軸を作れるようになるでしょう。
かんたん1分!無料登録就活の軸の考え方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の軸がないときの見つけ方
就活の軸がないときは、以下の3ステップに沿って見つけるのがおすすめです。
1.自己分析を行う
2.自分がやりがいや喜びを感じることを把握する
3.キャリアビジョンを明確にし、就活の軸を完成させる
就活の軸がないときには、まず自己分析を行いましょう。就活の軸を決める際に大切なのは、自分の価値観をきちんと把握することです。
忙しく生活していると、自分自身に真剣に向き合う機会は少ないのではないでしょうか。就活は、人生のなかで大きなイベントの一つです。この機会に、ぜひ自分への理解を深めましょう。
自己分析で気をつける点は、特別な経験に固執しないことです。華やかなものでなかったとしても、あなたがやりがいや喜びを感じたのであれば、それは貴重な経験といえます。自分の感情に焦点を当て、経験を棚卸ししましょう。そこで分かったことが就活の軸の要素となり、その後のステップの指針になります。
かんたん1分!無料登録就活の軸の考え方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の軸になりやすい3つの内容
就活の軸が見つからず悩んでいる人は、「何を基準に企業を選べば良いのか」がわからず止まってしまうことが多いようです。ここでは、就活の軸を考える際の3つの視点を紹介します。
働き方・環境
「どんな働き方や環境で働きたいか」は就活の軸として重要なポイントです。勤務地や勤務体系(休日・フレックス・残業の有無など)が自分の理想と大きく異なると、どんなに仕事内容や給与が魅力的でも長く働き続けることが難しくなります。
たとえば、以下のような視点が「働き方・環境」の軸です。
・勤務地(地元・都心・転勤有無)
・勤務体系(完全週休二日制、フレックス制度、残業時間)
・福利厚生、給与、社宅制度
・人間関係、職場の雰囲気
ただし、これらの条件をそのまま企業に伝えると「条件だけで選んでいる」というマイナスイメージを持たれる可能性があります。そのため「なぜこの条件を重視するのか」を自分の中で整理し、優先順位を明確にしておくことが大切です。
この準備をしておくことで、自分が快適に働ける環境を見つけやすくなり、結果的に納得感を持って就職先を選べるようになるでしょう。
企業の文化や理念
企業の文化や理念に共感できるかは、就活の軸として大切です。どれだけ待遇や仕事内容が魅力的でも、企業の価値観や社風が自分に合わないと、入社後に違和感を覚えてミスマッチにつながる可能性が高いでしょう。
企業の文化や理念を軸にする場合、以下の視点で整理すると進めやすくなります。
・企業の規模(大手・ベンチャー・中小)
・業務の成長スピード、挑戦できる環境か
・ブランド力、社会貢献性
・経営理念、ビジョン、社風
特に重要なのは「企業のビジョンや社風に共感できるかどうか」です。理念に共感していることは志望動機にもつなげやすく、面接時に「なぜこの会社を選んだのか」という問いに説得力を持って答えられるようになります。
企業文化や理念を基準に選ぶことで、自分が心地良く成長できる環境で働ける可能性が高まり、ミスマッチを防ぐことが可能です。
仕事内容
「どのような仕事をしたいのか」という視点も就活の軸として重要です。仕事内容に興味が持てない仕事ではモチベーションが続かず、達成感や成長を感じられずに早期離職してしまうリスクが高くなります。
仕事内容を軸にする場合は、以下のポイントを整理すると具体化しやすくなるでしょう。
・自分の努力が評価される環境か
・達成感や成長を実感できるか
・興味・経験に基づく職種選択
・企業内でのキャリア展望(昇進・独立支援・海外挑戦制度など)
たとえば、「人と関わる仕事で成長したい」「企画・マーケティングでアイデアを活かしたい」「技術を磨いて専門性を高めたい」など、あなたが働く中で何を大事にしたいのかを基準に選ぶことが大切です。
さらに、将来のキャリアプランも考慮し、昇進やスキルアップの機会、独立支援や留学制度など、企業が用意している成長支援制度も確認しておくと良いでしょう。
かんたん1分!無料登録就活の軸の考え方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の軸で避けるべき3つの内容
働くうえで大切にしたいことは、人によって違います。就活の軸は自分の気持ちを優先して考えるべきですが、なかには適さないものがあることも知っておきましょう。以下で、詳しく解説します。
1.給料や福利厚生などの待遇面
待遇面は大切な要素ではありますが、就活の軸にするのは避けたほうが無難です。
先に述べたように、企業はあなたの志望度の高さや会社との相性を見ています。そのため、就活の軸を問われて待遇面を伝えると、「ほかに条件の良い会社があったら、そちらに行くのだろう」「仕事への意欲が感じられない」と見なされてしまうこともあるでしょう。
待遇面は、あくまでもあなたが大切にしたい「条件」として、自分の心のなかに留めておくのが得策です。
2.どの業界・企業にも当てはまる内容
どれほど素晴らしい就活の軸を述べたとしても、どこの会社にも当てはまるものだった場合、あまり良い印象は与えないでしょう。「△△社のほうが良いのでは」と、面接で指摘されてしまう恐れもあります。
自分で定めた就活の軸は、受ける業界・企業の特徴や理念に合わせて言い換えてみてください。
3.消費者目線の内容
就活生が企業に関心を持つ背景には、「製品が好き」「サービスが気に入っている」という理由も多いと考えられます。その思い入れ自体は自然なものですが、就活の軸にすると企業にその会社で達成したいことや採用するメリットは伝えられません。
「とにかく好き」という気持ちはあっても、働くことに言及していない就活の軸を伝えると、「消費者のままでいてほしい」と思われてしまう可能性があります。
かんたん1分!無料登録就活の軸の考え方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
面接で就活の軸を伝える際のポイント
面接で就活の軸を伝える際、「私の就活の軸は、△△です。」と伝えるだけでは説得力を持たせることはできません。就活の軸を伝える際には、以下2つのポイントを意識した伝え方を心掛けましょう。
志望度の高さをアピールする
面接で就活の軸を伝える際には、志望度の高さをアピールしましょう。就活の軸と応募先企業ならではの特色が結びつけられれば、志望度の高さと熱意をアピールできます。
そのためには、応募先企業の事業内容はもちろん、理念や社風などを深く知ることが大切です。その際、できる限り「他企業にはないその会社独自の特徴」を見つけるようにしましょう。
説得力のあるエピソードを添える
就活の軸の背景にある、具体的なエピソードを説明するのも大事なポイントです。就活の軸は、ときに漠然とした内容になりがちです。あなたのことをよく知らない面接官にアピールするには、就活の軸に説得力を持たせるエピソードが欠かせません。
企業との共通点を具体的に伝える
面接で就活の軸を伝える際は、「自分の軸と企業の特徴がどのように一致しているのか」を具体的に伝えましょう。企業は、自社の理念や方針に共感し、一緒に目標を目指せる価値観を持つ人材を求めています。そのため、「なぜその企業でなければならないのか」という理由も加えましょう。
たとえば、「御社が海外展開にも積極的に挑戦している姿勢に魅力を感じており、私も将来的に海外事業で挑戦したいと考えているため、他社ではなく御社を志望しています」というように伝えると、志望度の高さとマッチ度が伝わりやすくなります。
そのためには、企業のビジョン・文化・取り組みを深くリサーチし、企業の独自性を理解したうえで具体的な共通点を述べる準備が欠かせません。
かんたん1分!無料登録就活の軸の考え方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の軸の例文
最後に、就活の軸の例文をご紹介します。志望する業界・業種により内容は変わりますが、これから就活の軸を作成する方は、一例として参考にしてください。
私の就活の軸は、「人の気持ちを汲み取り、相手が求めているものを見出す仕事をすること」です。
私は学生生活を通じて△△のアルバイトをしましたが、最初はお客さまのお気持ちを汲みとるのが難しかったです。それでも、お話にじっくりと耳を傾けることで、徐々にご希望に沿った商品の提案ができるようになりました。一人ひとりが求めるものを見出すことでお客さまに喜ばれ、自分自身も幸せを感じたことから、先に述べた就活の軸を企業選びの指針にしたいと思った次第です。
貴社は他社にはない個別性を重視したサービスを提供しているため、経験で得た傾聴スキルを活かしつつ、やりがいを感じながら働けるのではないかと考えております。
かんたん1分!無料登録就活の軸の考え方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
「就活の軸がない」と悩んでいるあなたへ
ここまで、就活の軸を定めるメリットや見つけ方を解説しました。しかし、「どうしても就活の軸が見つからない」「自分の就活の軸が志望企業にマッチしているか分からない」と悩む人もいるでしょう。
就活を自分一人で進めるのに自信がない方は、就活エージェントに登録するのも選択肢の一つです。
就活エージェントのキャリアチケットでは、就活の軸を見つけるためのサポートはもちろん、面接対策やエントリーシートの添削も行っています。
カウンセリングを行い、あなたの価値観に合った企業もご紹介。就活の軸に関して悩んだら、ぜひキャリアチケットにご相談ください。
かんたん1分!無料登録就活の軸の考え方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。