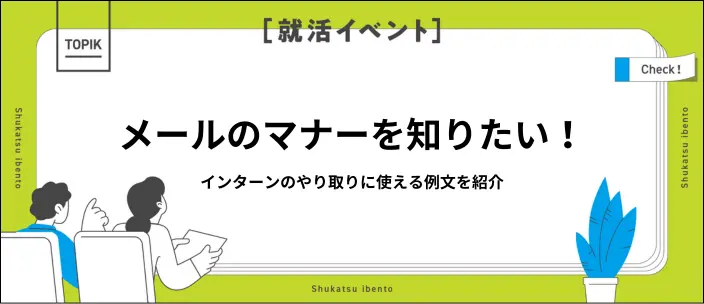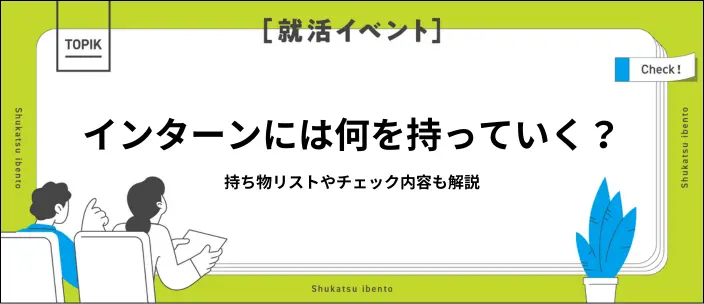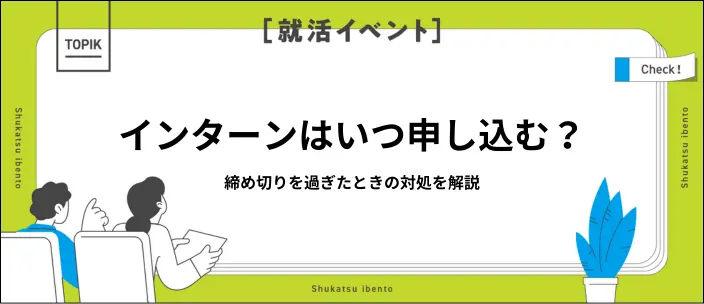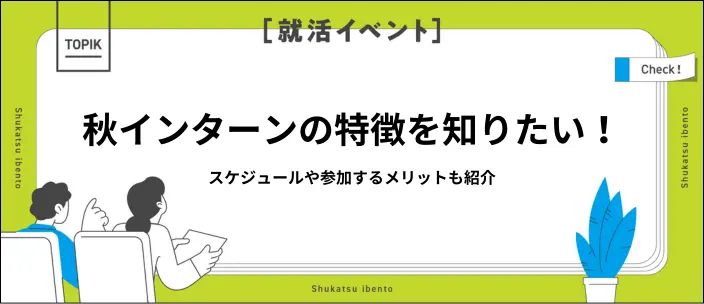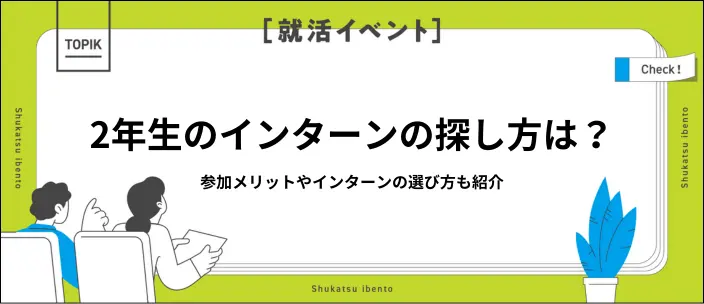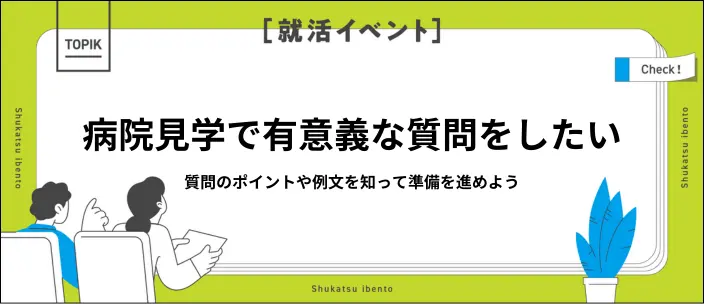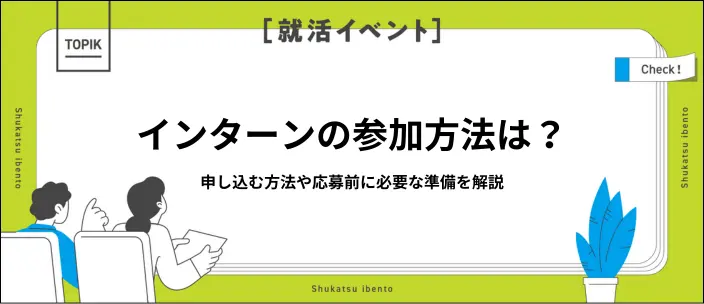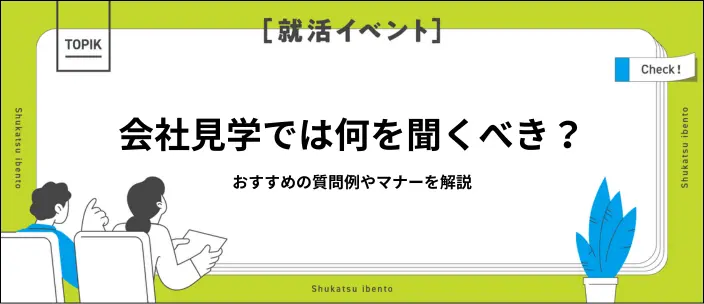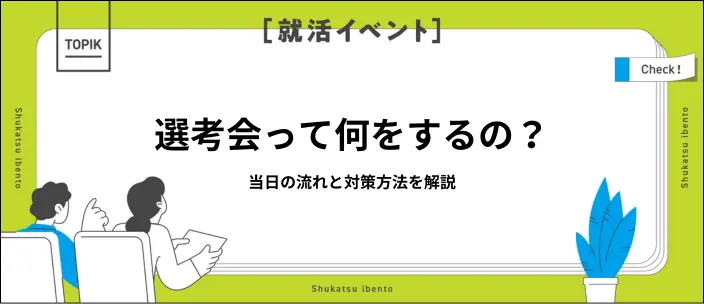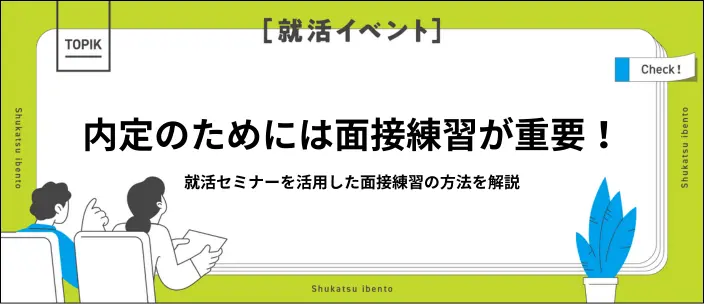このページのまとめ
- 採用直結型インターンは2025年卒から解禁され、内定直結のチャンスが広がった
- 実際の業務に近い内容を経験できるのが採用直結型インターンのメリット
- 参加前に目的を明確にして積極的な姿勢で臨むことが採用直結型インターン成功のカギ
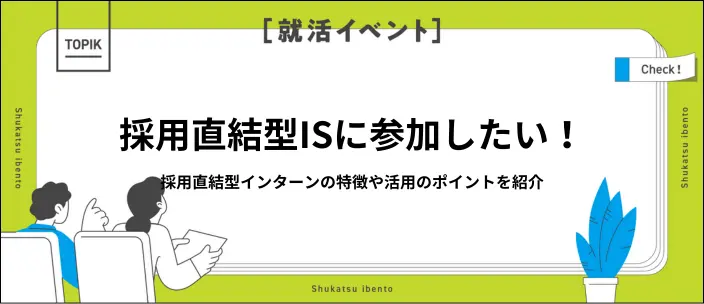
採用直結型インターンとはどのような特徴があるのか、よく分からない就活生も多いでしょう。早期内定のチャンスがあると聞いても、「本当に参加すべき?」「メリット・デメリットは?」と迷うのは自然な流れです。
この記事では、採用直結型インターンのメリット・デメリット、実際に活用するポイントなどを紹介します。この記事を参考に、納得感を持って就活を進められるようにしましょう。
かんたん1分!無料登録インターンについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 2025年卒から見直された採用直結型インターンとは
- 採用直結型を含むインターンは4つに分類される
- 1.オープン・カンパニー
- 2.キャリア教育
- 3.汎用的能力・専門活用型
- 4.高度専門型
- 採用直結型インターンの主な特徴
- インターン前に事前選考を行うケースが多い
- インターン期間が長めの傾向がある
- 実際の業務に近い内容を経験できる
- 採用直結型インターンの3つのメリット
- 早いタイミングで内定をもらえる
- 業界や企業理解が深まる
- 実務に役立つスキルを習得できる
- 採用直結型インターンの2つのデメリット
- 業界や企業を幅広く比較できなくなる
- 参加中のプレッシャーが大きい
- 採用直結型インターンを有効活用するためのポイント
- 業界・企業研究を深めておく
- 目的をもって参加する
- 気になることは積極的に質問する
- インターンの実施目的は業界によって違う
- 外資系企業
- 総合商社
- 日系金融企業
- ベンチャー企業
- どのインターンに参加すべきか分からない方へ
2025年卒から見直された採用直結型インターンとは
採用直結型インターンは「インターンに参加することが、そのまま本選考や内定に直結するインターン」のことです。通常の職業体験だけのインターンとは違い、早期内定の可能性があるのが最大の特徴。
文部科学省・厚生労働省・経済産業省の連名による2022年6月13日改正「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(1p)」では、インターンシップを以下のように定義しています。
「学生が、その仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか(その仕事で通用するかどうか)を見極めることを目的に、専攻分野や将来のキャリアに関連した企業の実務を体験する活動」
つまりインターンは単なる職場見学ではなく、「自分がその仕事で通用するかを確認する場」であり、採用直結型インターンはその延長線上で、企業が学生の能力や適性を評価し、そのまま内定につなげる仕組みになっているのです。
採用直結型インターンは、「自分のキャリアの可能性を早期に確認できるチャンス」であり、「内定直結型で効率的に就活を進められる手段」であることを理解しておきましょう。
内定につながるインターンシップについては、「内定直結インターンとは?参加するメリットや選考突破のコツを徹底解説」のコラムでも紹介しているため、あわせて参考にしてください。
参照元
文部科学省・厚生労働省・経済産業省
インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る 取組の推進に当たっての基本的考え方
かんたん1分!無料登録インターンについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
採用直結型を含むインターンは4つに分類される
インターンシップにはさまざまな種類がありますが、「採用直結型インターンシップ」に該当するのは、「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」と「高度専門型インターンシップ」の2つです。
そのほかにも、企業や業界理解を目的とした「オープン・カンパニー」や、働くことへの理解を深める「キャリア教育」など、目的や内容に応じて大きく4つのタイプに分類されます。
ここでは、それぞれのタイプについて詳しく見ていきましょう。
1.オープン・カンパニー
オープン・カンパニーは、「企業版のオープン・キャンパス」と表現できます。企業や業界、仕事内容の理解を目的に開催され、情報提供やPRが中心のプログラムであることが特徴です。
オープン・カンパニーは参加ハードルが低く、就活生が気軽に企業の雰囲気を知ったり、業界研究を進めたりする場として活用されています。興味のある企業や業界の情報収集のために参加する学生が多く、「まずは就活の第一歩を踏み出したい」という人に最適な機会といえるでしょう。
「どの業界が自分に合うのか分からない」「どの企業を選ぶべきか迷っている」という場合、まずオープン・カンパニーに参加することで情報収集ができ、その後のインターン・本選考での志望動機の解像度を上げることにもつながります。
2.キャリア教育
キャリア教育とは、企業や大学が実施する「働くこと」への理解を深める教育プログラムです。具体的には、企業がCSR(社会貢献活動)の一環として行うプログラムや、大学が主導する授業・産学協働プログラム(正課・正課外問わず)で実施されるインターンシップのことを指します。
キャリア教育型インターンは、「就職活動のための選考直結インターン」というよりも、学生が社会や仕事の役割を学び、キャリア観を育むことを目的としたプログラムです。企業が地域や社会に貢献しつつ、学生のキャリア形成を支援することが主な目的となっています。
「まだ本格的に就活を始める前で、社会人としての働き方や業界全体の理解を深めたい」「将来のキャリア選択の幅を広げたい」という学生にとって、キャリア教育型インターンは貴重な学びの場となるでしょう。
3.汎用的能力・専門活用型
汎用的能力・専門活用型インターンシップとは、企業や大学・地域が連携して実施する「実践型インターンシップ」です。ここでの「汎用的能力」とは、社会で働くうえで必要なコミュニケーション力、課題解決力、協調性などを指し、専門活用型は自分の専門知識を実務で活かす機会を指します。
このタイプのインターンは、企業が単独、または大学・地域コンソーシアムと連携し実施されるのが特徴で、オンラインを含めた職場で実際の業務を体験しながらスキルを伸ばすことが可能です。通常は無給ですが、社員と同様の業務・働き方を求められる場合は労働関係法令の適用対象となり、有給で実施される場合もあります。
「学んだことを実務で活かしてみたい」「実際の職場で自分がどこまで通用するのか試したい」という学生にとって、汎用的能力・専門活用型インターンシップは成長のチャンスです。参加することで、自己理解が深まり、エントリーシートや面接でも具体的なエピソードとしてアピールできる経験を得られるでしょう。
4.高度専門型
高度専門型インターンシップとは、自然科学分野の博士課程学生を対象に文部科学省と経団連が共同で試行している「プロジェクト形式の実践型インターンシップ」です。通常のインターンシップとの違いは、高度な専門知識・研究スキルを実社会で活かすことを目的とし、企業側も即戦力となる高度人材の育成・発掘を目的としている点にあります。
現在は民間企業が単独で実施しているものではなく、政府主導で試行が進められており、今後の結果を踏まえて正式な制度化や展開が検討される予定です。
「博士課程で研究している知識やスキルを社会でどう活かせるのか試したい」「将来的に研究職や高度専門職に就きたい」という博士課程の学生にとって、高度専門型インターンシップはキャリアの可能性を広げる貴重な機会となるでしょう。
「インターンに行くべき?参加のメリット・種類・注意点を理解して選ぼう」のコラムでは、細分化したインターンの種類を紹介しているため、あわせて参考にしてください。
かんたん1分!無料登録インターンについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
採用直結型インターンの主な特徴
採用直結型インターンシップは、単なる職業体験の枠を超え、学生の採用につながる重要な機会として注目されているプログラムです。
ここでは、採用直結型インターンの主な特徴を3つ紹介します。
インターン前に事前選考を行うケースが多い
採用直結型インターンシップには、多くの場合、事前選考があります。これは企業が、職務に適応できる学生を見極めるために、本選考に近い選考プロセスを設けているからです。
従来のインターンでも選考はありましたが、採用直結型では選考ステップがより多く、書類選考や面接だけでなく、適性検査や複数回の面接が行われることも珍しくありません。そのため、「内定が出る」という魅力だけで応募しても、事前準備が不十分だと参加できないリスクが高いといえます。事前選考を突破するための対策は必須だと覚えておきましょう。
インターン期間が長めの傾向がある
採用直結型インターンシップは、実際に内定を出すことを目的としているため、一般的なインターンシップよりも期間が長い傾向にあります。短期間で会社説明を中心としたインターンも多い中で、採用直結型はしっかりと職業体験を提供することが特徴です。
長期間かけて実務に携わることで、入社後の働くイメージを具体的に持てるようになります。このため、業務内容や職場環境を深く理解したい学生にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
実際の業務に近い内容を経験できる
採用直結型インターンシップでは、企業が学生の適性や能力を評価し、採用につなげるため、プログラム内容は実際の業務に近いものとなっています。
たとえば、「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」では、参加期間の半分以上が就業体験に充てられることがルール化されており、学生は業界や職種を問わず、実際の仕事を経験できるのです。
さらに、最近ではテレワークが普及していることから、在宅勤務形式での就業体験を行う企業も増えています。これにより、入社後の働き方もリアルに体験可能です。このように実務に即した経験を積むことで、学生は自身の適性を見極めやすくなり、企業側も入社後の活躍を見通しやすくなります。
長期インターンは給与が出ることも多いのがメリットです。「無給とはここが違う!有給インターンシップ参加のメリット」のコラムでも特徴を紹介しているため、あわせてチェックしてみてください。
かんたん1分!無料登録インターンについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
採用直結型インターンの3つのメリット
採用直結型インターンシップは、単なる職業体験にとどまらず、早期内定のチャンスや業界・企業理解の深化、そして実践的なスキル習得など、就活生にとって大きなメリットが多数あります。
「就活を有利に進めたい」「自分に合った企業を見極めたい」「社会で役立つスキルを身につけたい」そのように考える就活生におすすめの制度です。ここでは、採用直結型インターンシップがもたらす具体的な3つのメリットを解説します。
早いタイミングで内定をもらえる
採用直結型インターンシップで高い評価を得られれば、選考が通常より早く進み、早期に内定を獲得できる可能性があります。「就活のプレッシャーから早く解放されたい」「残りの学生生活をもっと充実させたい」と考えている学生にとっては、大きなメリットです。
早い段階で内定を得ることで、その後の就活に余裕が生まれ、安心して学生生活や卒業研究に集中できるようになります。
業界や企業理解が深まる
採用直結型インターンシップでは、実際の業務に携わることで、業界の動向や企業文化、事業内容をより深く理解できます。
現場での体験を通じて、「本当にこの業界で働きたいのか」「企業の価値観に共感できるか」を自分自身で判断する材料になるのが大きなポイントです。このように納得感を持って入社を決められるため、入社後のミスマッチを減らせるのも大きなメリットといえます。
実務に役立つスキルを習得できる
採用直結型インターンシップは、実際の業務に近いプログラムが中心のため、ビジネスメールの作成や顧客対応、資料作成、マーケティング分析など、実践的なスキルを在学中に身につけられます。これらの経験は、企業が即戦力として求めるスキルの習得につながり、ほかの就活生との差別化にもなるでしょう。
また、現場で働く社員から直接フィードバックを受ける機会も多く、自己の強みや成長すべき点を客観的に理解できる貴重な場となります。
かんたん1分!無料登録インターンについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
採用直結型インターンの2つのデメリット
採用直結型インターンは早期内定や実務経験など多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。ここでは、2つのデメリットを解説するため、失敗を防ぐための対策を立てられるようにしましょう。
業界や企業を幅広く比較できなくなる
採用直結型インターンは特定企業と深く関われる反面、ほかの業界や企業をじっくり比較検討する時間が減ってしまうリスクがあります。これは、「本当にこの業界が自分に合っているのか」を見極める前に早い段階で意思決定を迫られることが原因です。
特に、「早く就活を終わらせたい」という気持ちが強いと、視野が狭くなりやすく結果的に自分に合わない業界を選んでしまうおそれもあります。そのため、まだ将来の方向性がはっきりしない段階で採用直結型インターンに参加する場合は、慎重に検討しましょう。
幅広い業界理解と自己分析を十分に行ったうえで、参加を決めることが失敗を防ぐポイントです。
参加中のプレッシャーが大きい
採用直結型インターンは選考が絡むため、参加中に強いプレッシャーを感じることが多いでしょう。実務に近い長期間のプログラムでは、常に成果や行動が評価対象となるため、「失敗したらどうしよう」「期待に応えられるか不安」と感じる学生も少なくありません。
こうした不安を抱えたまま臨むと、実力を十分に発揮できない可能性があります。
プレッシャーに負けず、自己管理やストレスケアに努めることが、採用直結型インターンを成功させるカギです。
かんたん1分!無料登録インターンについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
採用直結型インターンを有効活用するためのポイント
採用直結型インターンシップは、内定直結のチャンスを得られる貴重な機会である一方で、活かし方次第で結果が大きく変わります。「参加したけれど何も得られなかった」とならないためには、準備と心構えが重要です。
ここでは採用直結型インターンを最大限に活用し、内定獲得や成長へとつなげるための具体的なポイントを解説します。
業界・企業研究を深めておく
インターンシップで最大限の成果を出すためには、事前の業界・企業研究が欠かせません。知識があることで、仕事の背景や必要性を理解しやすくなり、パフォーマンスも向上します。
たとえば、業界や企業の役割を理解していれば、インターン中に任される仕事の意義をイメージしやすくなります。逆に準備不足だと、実務への理解が浅くなり、貴重な経験を十分に活かせません。
また、企業研究は参加企業だけでなく、関連する業界や競合他社も含めて行うことが重要です。広い視点で比較することで、参加先企業の強みや特徴を正確に把握できます。
目的をもって参加する
採用直結型インターンでは、企業は選考段階から学生の「参加目的」や「仕事への意欲」を重視しています。受け身ではなく主体的に取り組んでいる姿勢が高く評価されるため、事前に自分の目的を明確にしておきましょう。
多くの学生が持つ参加目的の例として、「志望業界や職種の明確化」「視野を広げる」「自己理解を深める」などがあります。まだ目的が定まっていない場合は、これらを参考にしながら自分の参加理由を整理しましょう。
目的をはっきりさせることで、インターン中の行動や質問内容も具体的になり、より良い評価につながります。
気になることは積極的に質問する
インターン中に疑問をそのままにしないことは、理解を深めるだけでなく、企業に対して積極性やコミュニケーション能力をアピールする絶好の機会です。実務の内容や業務の背景はもちろん、職場環境や社員のキャリアパスについても質問すると、企業のリアルな情報が得られ、就活に役立ちます。
質問ができる人は「仕事を覚える姿勢がある」「チームに貢献しようとする人」として好印象を持たれやすいでしょう。反対に、疑問を抱えたまま黙っていると、積極性不足の印象を与えかねません。
自分にあったインターンに参加して、選考に役立てたい方は「インターンの探し方を解説!自分に合う企業を選ぶには」のコラムもあわせてご覧ください。
かんたん1分!無料登録インターンについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
インターンの実施目的は業界によって違う
基本的に企業がインターンを行う目的には、企業への志望度を高めてもらったり、マッチング度を確認してもらったりすることが挙げられます。
しかし、業界によってインターンの重要性や見ているポイントは異なる部分があることも。事前に、志望企業がインターンを実施する目的を確認しておくと良いでしょう。
こちらでは、業界別にインターンの実施目的をまとめました。
外資系企業
即戦力としての活躍が期待できたり、成長性が高い人材を求めたりする傾向にあるのが外資系企業の特徴です。しかし、面接だけでこれを判別するのは困難といえるでしょう。インターンでは、実務を通してその能力を見極めています。
日系企業と外資系企業のインターンの違いについて知りたい方は「日系企業とは違う?外資系インターンの内容と選考の特徴」もあわせてチェックしてみてください。
総合商社
総合商社が見ているのは、志望度の高さです。インターンへ参加したかどうかが、本選考にある程度影響するといわれています。
もちろん、インターンに参加していない人の採用も行なっていますが、参加者のほうが志望度が高いと捉えられるのは自然な流れでしょう。インターンに参加するためのESでも、志望動機が重要視されています。
日系金融企業
金融企業やBtoB企業などの業務内容は、関わりのない人にとってはイメージしづらい傾向があります。イメージできないことで、就職後にギャップを感じる、そもそも志望度を下げてしまう、という人も少なくありません。業界や業務について詳しく説明し興味を持ってもらえるようインターンが実施されています。
ベンチャー企業
ベンチャー企業は起業して間もないため、大手企業と比べて比較的知名度が低いのが特徴です。広報や、優秀な学生の志望度を高める目的でインターンを実施します。優秀な学生がインターンを通して入社意欲を高められるような、実務による長期インターンを行う傾向があるようです。
ベンチャー企業が実施するインターンの特徴や魅力を知りたい方は「ベンチャー企業の長期インターンに参加する魅力とは」のコラムも参考にしてください。
かんたん1分!無料登録インターンについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
どのインターンに参加すべきか分からない方へ
どんなインターンを選べばよいか分からない、そもそも志望業界や企業、職種を絞れない、という方はキャリアチケットへ。キャリアチケットでは、新卒の就職に特化した専門のアドバイザーが、マンツーマンでカウンセリング・サポートを行います。
適職のご紹介はもちろん、業界や企業選びも徹底フォロー。無料の就職支援サービスを賢く使い、ぜひ内定を獲得してください。
かんたん1分!無料登録インターンについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら