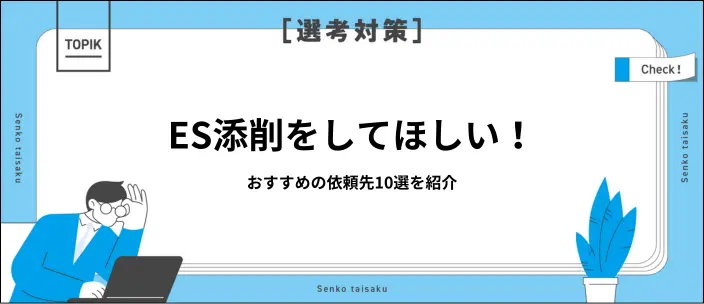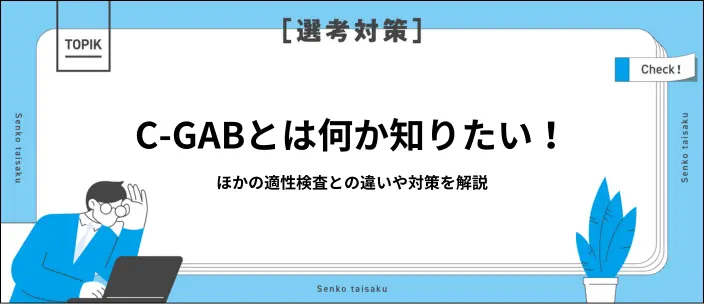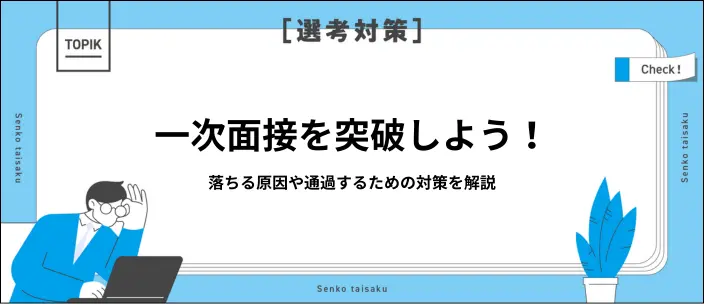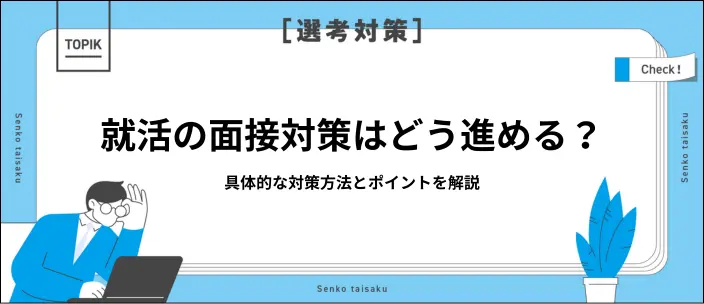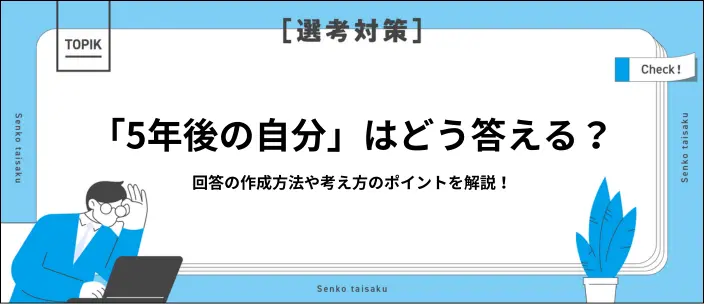このページのまとめ
- 既卒の就活は新卒よりハードルは上がるが、積極採用する企業も増加傾向にある
- 卒業後3年以内なら新卒枠での応募も可能なので、就活エージェントを活用しよう
- 既卒になった場合の就活では、具体的なキャリアプランを示すことが大切
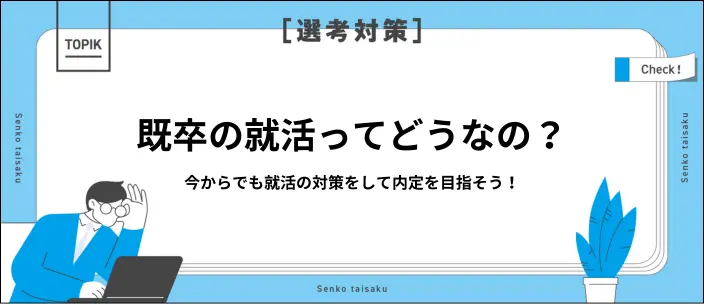
就活が思うように進まず、このまま既卒になるのではないかと不安を感じている方もいるのではないでしょうか。既卒とは、学校を卒業後に正社員として就職していない状態を指します。
本記事では、既卒になってからの就活の進め方や、就活のスタートが遅れても内定獲得を目指すためのポイントなどを詳しく解説していきます。既卒の就活に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就活の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- そもそも既卒とは?
- 既卒になると就活が厳しいといわれる理由
- 採用は新卒が優先される傾向にある
- 新卒と社会人経験がある中途がライバルになる
- 既卒になったときの就活の進め方
- 既卒歓迎の求人を探す
- 既卒になった場合も3年以内なら新卒枠を狙える
- 既卒になった場合の就活で企業に伝える3つのポイント
- 1.既卒になった理由
- 2.明確なキャリアプラン
- 3.就職への熱意と意欲
- 内定獲得のために今からできる7つのこと
- 1.自己分析を徹底的に行う
- 2.業界・企業研究を徹底的に行う
- 3.履歴書やESを丁寧に作成する
- 4.面接対策をする
- 5.就活サイトやエージェントを活用する
- 6.スケジュール管理を徹底する
- 7.物事を前向きに考える
- 諦めずに内定を目指して就活を続けよう
そもそも既卒とは?
既卒とは、学校を卒業したあと、正社員として働いた経験がない人のことを指す言葉です。学生時代に就職が決まらなかった場合や、進路を迷って就職を見送った場合なども既卒に該当します。
なお、一度新卒で正社員として就職し、3年以内に退職した場合は「第二新卒」にカテゴライズされるのが一般的です。
また、企業によっては卒業後3年以内であれば新卒採用枠で応募できる場合もあります。就活の選択肢を広げるためにも、この点は覚えておくと良いでしょう。
既卒は、「就活浪人」と呼ばれることもあります。詳しくは、「就活浪人とは?不利といわれる理由や就職留年との違い、デメリットを解説」の記事で解説しているので、合わせてご覧ください。
かんたん1分!無料登録就活の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
既卒になると就活が厳しいといわれる理由
既卒の就活は、新卒と比べて多少なりともハードルは上がります。しかし、近年は既卒採用を積極的に行っている企業も増加傾向にあるため、諦めずに対策や準備を万全にし、就活を続けていくことが大切です。
採用は新卒が優先される傾向にある
現在は採用が多様化しているものの、新卒の一括採用を優先的に行う企業もあります。理由としては、新卒だと新入社員を一から育成しやすく、社風に合わせた人材教育がしやすいことが挙げられるでしょう。
また、採用予算やスケジュールの面の事情で、新卒採用が中心となっている場合があるようです。そのため、既卒として就活する場合、新卒と比べて応募できる求人が少ない可能性もあるでしょう。
新卒と社会人経験がある中途がライバルになる
既卒者は、新卒採用と中途採用の中間に位置します。新卒採用では内定を獲得せずに卒業したことが新卒よりも不利になりやすく、中途採用では「社会人経験がない」という点でライバルとの差が生まれやすくなるでしょう。
ただし、既卒であることを強みとしてアピールするのも可能です。たとえば、卒業後に資格取得や語学学習に励んでいた場合は、そのスキルや努力の過程をアピールポイントにできます。また、アルバイトやボランティア活動などの経験も、自己PRに活用できるでしょう。
新卒を優先する企業はあるものの、既卒者の採用に対する考え方は徐々に変化してきているようです。特に若手人材の確保が課題となっている企業では、既卒者の採用に前向きな場合もあります。就活では、このような企業の特徴や採用方針をしっかりと研究することが重要です。
「就活が進まない」「内定がなかなか決まらない」など、就活に関するお悩みに関しては、「就活悩みあるある12選|よくある悩み・失敗談から学ぶ対処法もご紹介!」の記事をご一読ください。
かんたん1分!無料登録就活の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
既卒になったときの就活の進め方
卒業後に就職が決まらなかった場合も、既卒を歓迎している企業を探せば正社員として就職できる可能性は十分にあるでしょう。ここでは、既卒になった場合に就職のチャンスを掴むための方法を紹介します。
既卒歓迎の求人を探す
既卒者を積極的に採用している企業も存在するので、就職支援サイトやハローワークなどで、「既卒歓迎」の表記がある求人を探してみましょう。既卒を歓迎している企業では、応募者の現状を理解したうえで、その人のもつポテンシャルを評価する傾向にあります。
また、就活エージェントを利用するのも効果的な方法の一つです。エージェントは就職関連の悩みや希望をヒアリングしたうえで、適切な求人を紹介してくれます。さらに、面接対策や履歴書の作成支援など、実践的なアドバイスも受けられるため、就活をスムーズに進められるでしょう。
既卒になった場合も3年以内なら新卒枠を狙える
厚生労働省の「卒業後3年以内の既卒者は、『新卒枠』での応募受付を!」の資料にもあるように、「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づいた指針が出されているため、卒業後3年以内であれば、既卒者も新卒採用枠での応募が可能な場合があります。
新卒枠で応募する際は、卒業後の期間をどのように過ごしてきたか明確にすることが重要です。資格取得のための勉強やアルバイトでの実務経験など、自己成長につながる活動を行っていた場合は、それらを積極的にアピールしていきましょう。
面接では、高確率で卒業後の期間について質問されます。その時期に得た経験や学び、志望企業でそれらをどのように活かしていきたいのかを、具体的に説明できるよう準備しておくことが大切です。
「面接対策の基本を解説!当日の流れ・マナー・よく聞かれる質問13選」の記事で、面接対策について詳しく解説しています。面接に不安がある方は、合わせて参考にしてください。
参照元
厚生労働省
青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について
かんたん1分!無料登録就活の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
既卒になった場合の就活で企業に伝える3つのポイント
既卒になった場合、就活の際は企業に対して適切な説明をすれば、内定を目指すことは十分可能です。ここでは、既卒になった方が面接で聞かれる可能性が高い3つのポイントについて、効果的な伝え方を解説します。
1.既卒になった理由
企業の採用担当者が知りたいのは、既卒になった理由です。なぜ既卒になったか聞かれた際は、明確な説明を前向きにすることが重要でしょう。たとえば、「資格取得のための勉強に専念していた」「自己分析の時間を十分に取りたかった」など、ポジティブに伝えることが大切です。
また、家庭の事情や健康面などのやむを得ない理由がある場合にも、率直に説明しましょう。その場合は、現在は問題なく働ける状況にあることをあわせて伝えます。
どのような理由を説明する場合も言い訳のような表現は避け、その期間に何を学び、どのように成長したかを具体的に伝えましょう。
2.明確なキャリアプラン
既卒の就活では、将来のキャリアプランを明確に描けているかどうかが重要です。なぜその企業で働きたいのか、どのようなスキルを身につけていきたいのか、具体的なビジョンを示すことが求められます。
面接では、卒業後の期間で明確にした自分の進路について、筋道の通った説明ができるよう準備しておきましょう。特に志望企業での具体的な目標や、そこで実現したいことを明確に伝えれば、採用担当者に強い印象を残せます。
3.就職への熱意と意欲
既卒者の就活において、就職への熱意と意欲を企業に示すことが大切です。ただ「働きたい」という気持ちだけでなく、「なぜその企業で働きたいのか」「どのように貢献していきたいのか」を具体的に説明することが求められます。
企業研究を徹底的に行い、その企業の課題や将来性について、自分なりの見解をもっておくことも大切です。また、既卒期間中に培った経験や学びを、どのように業務に活かせるのかを具体例を交えて説明できれば、より説得力のあるアピールになるでしょう。
上記で紹介したポイントを意識しながら、自分の言葉で誠実に伝えれば、既卒を強みとしてアピールできます。焦らず、自分のペースで就活を進めていくことを心掛けましょう。
内定がない状態で卒業した方が内定を目指す場合には、「内定がないまま卒業したらどうなる?内定獲得に向けての方法を解説」の記事もおすすめです。
かんたん1分!無料登録就活の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
内定獲得のために今からできる7つのこと
「就活を始めるのが遅くなってしまった」「いまだに内定を獲得できない」と悩んでいる方も、諦めないことが大切です。今から就活で内定を獲得するために、以下で紹介できる準備や対策を行いましょう。
1.自己分析を徹底的に行う
自己分析は就活の土台となる重要なステップです。自分の価値観や強み・弱み、興味関心を明確にすることで、志望する業界や企業が明確になります。
過去の経験を振り返り、どのような場面で充実感を得たのか、どのような環境で力を発揮できたのかを具体的に書き出してみましょう。さらに家族や友人に自分の印象を聞けば、客観的な視点も得られます。
2.業界・企業研究を徹底的に行う
志望する業界や企業についての理解を深めることは、選考突破のカギとなります。企業のWebサイトやニュース、就活情報サイトなどを活用して情報収集を行いましょう。
業界研究では、市場規模や成長性、主要企業の動向などを把握します。企業研究では、事業内容や企業ならではの強み、課題、企業文化などを調べることが大切です。OB・OG訪問や会社説明会に参加すれば、より具体的な情報を得られるでしょう。
3.履歴書やESを丁寧に作成する
履歴書やESは、採用担当者に自分を理解してもらうための重要なツールです。学生時代の学業やアルバイト、サークル活動などの経験を、企業が求める人物像に合わせて効果的にアピールしましょう。
文章は簡潔で分かりやすく書き、具体的なエピソードを交えることで説得力が増します。また、第三者からの添削を受けると、より良い内容にブラッシュアップできるでしょう。
4.面接対策をする
面接では、自己PRや志望動機を論理的に説明できる準備が必要です。想定される質問に対する回答を事前に用意し、声に出して練習しましょう。
面接官の質問の意図を理解し、自分の経験や考えを分かりやすく伝える練習を重ねることが大切です。また、身だしなみや態度、表情なども重要な要素となります。就活仲間との模擬面接や、キャリアセンターでの面接練習を行うのもおすすめです。
5.就活サイトやエージェントを活用する
就活サイトや就職エージェントを活用すれば、効率的に情報収集や企業への応募を進められます。求人情報だけでなく、業界研究や面接対策など、多様なサポートを受けることが可能です。
就活サイトやエージェントは複数登録するのがおすすめ
一つの就活サイトやエージェントだけでは、得られる情報や応募の機会が限られてしまう可能性があります。複数のサービスを利用すると、より多くの選択肢を確保できるでしょう。ただし、管理が煩雑になり過ぎないよう、3~4社程度に絞るのをおすすめします。
目的ごとにサポート体制を比較検討しよう
就活サイトやエージェントごとに得意分野が異なります。たとえば、特定の分野に特化したエージェントや、面接対策に力を入れているサービスなど、特徴はさまざまです。自分の目的や課題に合わせて、適切なサービスを選択しましょう。
6.スケジュール管理を徹底する
就活を成功させるためには、計画的に進めるためのスケジュール管理が欠かせません。説明会や面接の日程、提出書類の締め切りなどをしっかりと把握し、準備の時間を十分に確保することが大切です。
スケジュール管理アプリやカレンダーを活用して、重要な予定や締め切りを可視化しましょう。また、企業ごとの選考進捗状況も記録しておくと、効率的に就活を進められます。余裕をもった計画を立てることで、慌てずに対策できるでしょう。
7.物事を前向きに考える
就職活動では、思うような結果が出ないときもあります。しかし、そのようなときこそ物事を前向きに考えることが大切です。不採用通知を受け取った場合も、その経験を次の選考に活かすチャンスと捉えましょう。
面接でうまく答えられなかった質問は、改めて準備し直すきっかけになります。また、選考を通じて得られたフィードバックは、自己理解を深める機会となるでしょう。一つひとつの経験を糧として、着実にステップアップしていく姿勢が大切です。
就職活動は長期戦になることもあります。周囲の進捗状況が気になるかもしれませんが、自分のペースを保ちながら、粘り強く活動を続けることが内定獲得への近道となります。困ったときは、就活エージェントや大学のキャリアセンターへの相談も検討してみてください。
「就活遅れているかも…」と焦りを感じている方は、「今から就活を始めて間に合う?スタートに遅れた人がすぐやるべき対策を解説」の記事もおすすめします。こちらもご一読ください。
かんたん1分!無料登録就活の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
諦めずに内定を目指して就活を続けよう
「就活のスタートが遅れてしまった」「このままだと内定がないまま卒業になりそう…」と悩んでいる場合も、諦めなければ道は開けます。焦りや不安を感じたら、一度立ち止まってこれまでの活動を振り返り、自己PRなどを見直しましょう。
一人で抱え込まず、友人やキャリアセンターに相談することも大切です。情報収集や企業研究を続け、セミナーなどにも参加してみましょう。
また、一人での就活が不安なら、就活エージェントを活用するのも一つの手です。キャリアチケットでは、アドバイザーによるマンツーマンのサポートを行っています。応募書類の添削や面接対策などを企業ごとに行うので、効率良く就活を進められます。就活の進捗に悩んでいるなら、キャリアチケットにご相談ください。
かんたん1分!無料登録就活の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら