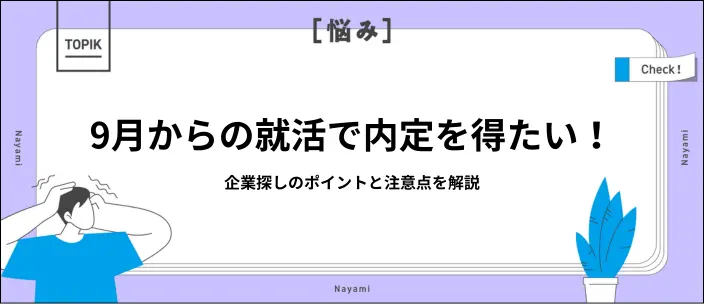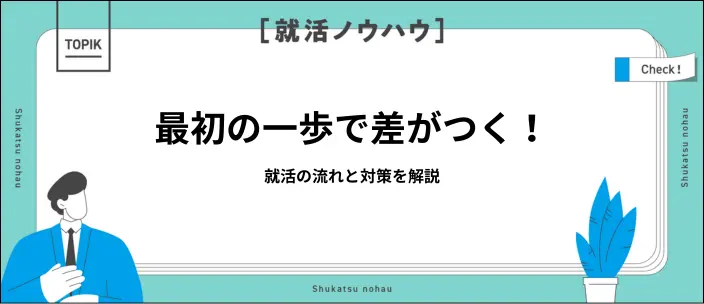このページのまとめ
- 一般的な6月の就活状況は、内定が出始める時期
- 就活を6月から始める方は、「今」行動することが大切
- 就活を6月から始めるためにやるべきことは、自己分析や模擬面接

「就活を6月からやっと始めたが、何から始めたらいいか分からない」「6月になっても内定がもらえず焦っている」このような悩みを持つ就活生の声が多く届きます。
就活時期が遅れてしまっていても、焦らずに丁寧に行動することが大切です。
この記事では、6月から就活を始める方に向けて、遅れてスタートした場合でも内定を獲得するためにやるべきことを紹介します。
また、知っておくべき就活状況と、内定獲得に向けたスケジュールの立て方も解説しました。内定がなく焦りを感じている就活生や、何をすればいいか分からない就活生はぜひ参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 就活開始が6月からは遅い?知っておくべき就活状況
- 一般的な就活スケジュールにおける6月の意味合い
- 6月に「全落ち」「内定なし」でも焦りすぎる必要はない
- 大手企業もチャンスがないわけではない
- 就活を6月から始めて内定を獲得するためのスケジュール
- 就活を6月から始めるときのおすすめスケジュール
- 就活を6月から始めた人のよくある失敗スケジュール
- 就活を6月から始める学生が内定獲得のためにやるべき5つのこと
- 1.自己分析で就活の軸や強みを明確にする
- 2.焦って沢山エントリーしすぎず、5社~8社ほどに絞る
- 3.募集状況に合わせて、複数の業界にエントリーする
- 4.本番同様の環境で模擬面接を行う
- 5.周りの人に客観的なアドバイスをもらう
- 就活を6月から始めて内定を獲得したいあなたへ
- 就活を6月から始める学生からのよくある質問
- Q. 就活を6月から始めるのは遅い?
- Q. 6月に就活が解禁ってどういうこと?3月から始まっているのでは?
- Q. 6月に内定をもらっている人が多いのはなぜ?
就活開始が6月からは遅い?知っておくべき就活状況
結論、6月から就活を開始することは、出遅れているといえるでしょう。しかし、スケジュールを立て、着実に1社を勝ち取りに行く気持ちで取り組めば内定獲得へ近づきます。
「選考に全落ちしてしまい6月になっても1社も内定がない」「何もしないまま気が付いたら6月になってしまっていた」という方にとって、6月は焦りが大きくなりやすい月です。
ここでは、企業側の採用スケジュールを解説するとともに、一般的な就活生の状況を解説していきます。
一般的な就活スケジュールにおける6月の意味合い
経団連は、企業が就活広報から内定発表を行う時期を以下のように定めています(2023年4月時点での情報)。なお、主導が経団連から政府に移った2021年卒以降も、当面の間は就活ルールに大きな変動はない見込みです。
・広報活動: 3月1日~
・選考活動: 6月1日~
・内定発表:10月1日~
6月ごろからは選考活動が始まるため、5月の末ごろにはエントリーを締め切っている企業もあります。また、経団連の就活ルールよりもかなり早い時期から採用活動を行い、6月には過半数以上の内定を出し切っている企業も多くあります。
そのため、6月から就活を始めるのは、遅めのスタートといえるでしょう。
参照元
一般社団法人 日本経済団体連合会
2023年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について
6月に「全落ち」「内定なし」でも焦りすぎる必要はない
4年生6月の時点で内定を持っている学生も多くいるように、多くの就活生が6月までに複数の面接を経験しています。そのため、6月の時点で全落ちもしくは内定がない場合は、限られた期間を有効に使う必要があります。
内定時期は6月がピークといえますが、実際の内定時期は業界や企業によって違います。業界ごとの内定時期は「就活生が知らない事実、内定時期は6月とは限らない?」を参考にしてください。
大手企業もチャンスがないわけではない
先ほどご紹介した経団連の就活ルールは、規則ではなく指針です。指針が適用されるのは経団連に加盟している企業のみ。非加盟の企業は従わなくても法的には問題ありません。
こういった背景があるため、一部の大手企業では追加募集や秋採用を行っている場合もあります。
このような募集には多くの応募が集まり非常に倍率が高くなるため、一点集中で応募することはおすすめできませんが、どうしても気になる企業がまだ追加募集をしていた場合は、希望をもってエントリーしてみましょう。
6月まで内定がなく、就活が長引いてしまった方は「6月で内定なしはまずい?長引く就活を終わらせる方法」も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活を6月から始めて内定を獲得するためのスケジュール
先述の通り、6月から就活を始めることが遅いとは言い切れません。経団連の就活ルールに従っている企業や、秋以降に採用活動をする企業に絞り、内定のために努力することで道は開けていくでしょう。
つまり、6月からのスケジュールの立て方が今後の勝敗の分かれ目になるともいえます。そこで、キャリアアドバイザーの目線で「失敗しやすいスケジュールの立て方」と「おすすめのスケジュールの立て方」を解説していきます。
就活を6月から始めるときのおすすめスケジュール
6月から就活を始める就活生は、下記のように進められることが理想です。
・6月前半~:企業選びの方針を固め、数社の企業説明会にエントリーする
・6月後半~:企業説明会に参加しながら、ESやテストの準備を進める
・7月前半:面接に進むことができた企業の選考対策を最優先にしながら、選考突破を目指す
・7月後半:内定間近の企業への意志決定の準備を進めつつ、落ちたら追加でエントリーする
・8月前半~:内定獲得、十分な企業理解の上で意志決定をする
・8月後半~9月:学生最後の夏休みを楽しむ
・10月1日~内定式参加
こちらはあくまでモデルケースです。余裕を持って意志決定をし、夏休みを過ごすためにも、6月の「今」、行動を始めましょう。
10月の内定式を見据えた就職活動を行う
多くの企業は、10月に内定式を行います。6月から就活を始めるとなると、約4ヶ月の間に企業からの内定が必要です。
6月の後半には、志望する企業を5~8社に絞り、企業説明会に参加しましょう。
8月の前半に内定獲得を目指すために、模擬面接と本番の面接を並行していきます。「内定をもらった企業であればどこでもいいや」と、焦って入社を決めずに、十分な企業理解をして意思決定することが大切です。
実戦的な面接対策を行う
6月から就活を始める場合、企業に合わせた実戦的な面接対策を行います。3月以前から就活を始めた人よりも少し出遅れているため、面接を突破するために行動しましょう。
面接は自己分析や企業研究、コミュニケーション能力が大切です。自己分析を徹底的に行うことで、回答への掘り下げられた質問にも答えられます。企業研究は、志望動機で自分の軸と社風が合致しているかの判断ができるでしょう。
また、面接での回答以外に、社会人としてのマナーを見られます。面接当日は、「スーツのしわがないか」「清潔感のある服装や髪型ができているか」を確認しましょう。
就活を6月から始めた人のよくある失敗スケジュール
下記は、よくある失敗スケジュールです。
・6月前半~:業界研究を始めて、志望企業を探す
・6月後半~:自己分析やESを作成する
・7月前半:会社説明会に行く
・7月後半:面接を詰める
・8月前半~:残りの面接をこなす
・8月後半~9月:内定がもらえたが、企業の情報を知らないまま入社を決意
・10月1日~内定式参加or納得が行かず就活続行
就活を6月から行う就活生の失敗スケジュールの特徴は、準備に時間をかけ、ゆっくりと就職活動を行っている点です。
スタートが遅れてしまっているため、今すぐ計画的に行動することが大切です。自分に合う企業から内定を獲得するために、失敗スケジュールの特徴を確認しましょう。
準備に時間をかけすぎていつまでもエントリーをしない
本来、就活は準備に多くの時間をかけて行うことが1番です。しかし、6月になって求人数が大きく減少していく中、何週間もかけて準備をすすめることはおすすめしません。
慎重になりすぎた結果、6月にエントリーのチャンスを逃してしまったり、途中で選考が打ち切られてしまったケースは例年非常に多くあります。
焦りすぎて手当たり次第にエントリーをしてしまう
「6月からでは遅い」と焦ってしまい、手当たり次第にエントリーをするのはおすすめしません。
ESを提出する際や面接の際に、自己PRや志望動機を熟考する時間がなく、統一感が欠ける恐れがあるからです。
その結果、思うように選考が進まずに就活期間が延びる可能性があります。仮に就職できたとしても、リサーチ不足によるミスマッチのため、早期退職となってしまう恐れもあるでしょう。
3月頃の進め方と6月以降の進め方を変えない
早くから就職活動を行っている場合、6月になっても志望の業界・職種を変えずに就活を進めてしまうのは大変危険です。
秋ごろになって他の企業を見てみようとしたときに、希望する業界はおろか希望する勤務条件が合う企業もなくなってしまう可能性があるでしょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
6月から就活を始める学生が内定獲得のためにやるべき5つのこと
6月から就活を始める場合でも、やるべきことは就活を早く始めた人と変わりありません。「出遅れた」と諦めず、下記のことを着実にこなしていきましょう。
1.自己分析で就活の軸や強みを明確にする
スピード感が求められる6月以降の就活でも、自己分析は最重要です。丁寧に自己分析を行い、就活の軸やアピールポイントとなるような強みを明確にしましょう。
就活の軸や自分の強みが分かっていれば、企業選びの方向性を明確にできるうえ、面接の受け答えやESの作成もスムーズに行えます。
自己分析は、効率アップのために就活関連の書籍やアプリを活用するのがおすすめ。これまでの経験を振り返り、達成したことや頑張ったことを整理していきましょう。
2.焦って沢山エントリーしすぎず、5社~8社ほどに絞る
先述のとおり、焦って大量にエントリーをしても対策の精度が下がってしまうため、十分な対策時間を確保できる数の企業に、優先順位をつけながらエントリーするようにしましょう。
具体的な社数は、学業の忙しさや体力、自宅から就活会場へのアクセスの良さなどによっても変わりますが、平均5社から8社ほどがおおよその目安として望ましいでしょう。
3.募集状況に合わせて、複数の業界にエントリーする
6月以降、業界によっては極端に募集人数が少なくなることも考えられます。その一方で、もともとの募集人数が多い、採用時期が比較的遅めなど、6月以降も積極的に内定を出す企業も。
そのため、6月以降は視野を狭めすぎることなく、柔軟に視野を拡げながら志望企業を見つけることを意識しましょう。
自分に適している仕事は、すぐには分からないものです。「興味がない」と思っていた業界や職種でも、実際にやってみると面白く感じる可能性もあります。
そのため、非常に重要になるのは「実際に説明会に参加し、企業説明を聞いてみること」です。インターネットの情報だけでは伝わらない、会社の雰囲気や具体的な業務内容を知ることができて、志望度がぐんとあがる就活生も多くいます。
スケジュール的に直接会場に出向くのが難しい場合や、効率よく企業分析を行いたい方は、対面の説明会ではなくWeb説明会を行っている企業を優先的に受けるのもおすすめです。
4.本番同様の環境で模擬面接を行う
1回1回の面接を確実にクリアするために何よりも大切なのは、「いかに本番に近い環境で実践練習し、客観的なアドバイスをもらうか」です。本番でスムーズに受け答えできるよう、必ず模擬面接で練習しておきましょう。
練習相手は家族や友人などの身近な人よりも、教授やバイト先の上司など、目上の社会人にお願いするのがおすすめです。緊張感を持って臨めるうえ、社会人目線の有益なアドバイスをもらえる可能性があります。
5.周りの人に客観的なアドバイスをもらう
模擬面接だけでなく、「自分にはどんな強みがあるのか」「今のままの企業選びでいいのか」など、様々なことに対して客観的なアドバイスをもらいフィードバックをもらうことが重要です。
面接や就活についての緊張感を持つために、模擬面接と同じく友人や親ではなく、年上の社会人や就活エージェントへの相談をおすすめします。
年上の社会人に相談することで、自身の体験談を交えてアドバイスをしてくれるでしょう。就活エージェントは企業探しから面接対策まで選考対策をサポートしてくれます。
自分では気付きづらい自己分析の甘さや面接のマナーに対し、周りの人がアドバイスをくれる環境が大切です。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活を6月から始めて内定を獲得したいあなたへ
6月から就活を成功させたい場合、エージェントを利用することは1つの有効な手段といえるでしょう。就活は、自分で行う自己分析や企業研究だけでなく、客観的な意見やアドバイスも大切です。
就活エージェントの中でも、キャリアチケットは就活のプロが、あなたが就職する上で大切にしたい価値観を明らかにし、それにあった企業を厳選して紹介します。
気軽に相談だけでももちろんOKなので、「6月から就活を始めるがなんとか内定を獲得したい」という方はぜひ登録してみてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活を6月から始める学生からのよくある質問
ここでは、大学4年の6月から就活を始める学生が抱きやすい疑問と、その回答をまとめています。不安を解消し、スピード感を持って就活に取り組む参考にしてください。
Q. 就活を6月から始めるのは遅い?
A. 就活を6月から始めるのは遅いといえますが、焦らずに1社ずつ丁寧に選考に進んでいけば、10月の内定式には間に合うでしょう。
Q. 6月に就活が解禁ってどういうこと?3月から始まっているのでは?
A. 就活が6月に解禁するということは、経団連が決めた「企業が就活広報から内定発表を行う時期就活ルール」に則ったものです。経団連のルールはあくまで参考程度ですので、優秀な人材を早めに確保したい企業は、早めに選考を開始します。
就活の解禁日については、「就活解禁日とは?企業の採用スケジュールをおさらい!」も参考にしてください。
Q. 6月に内定をもらっている人が多いのはなぜ?
A. 外資系や大手企業は選考開始時期が早いためです。大学3年生の夏からインターンに参加し、年度内に内定を獲得する人もいます。
就活のスケジュールについては、「就活スケジュールってどんな流れ?選考開始日と事前準備」も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。