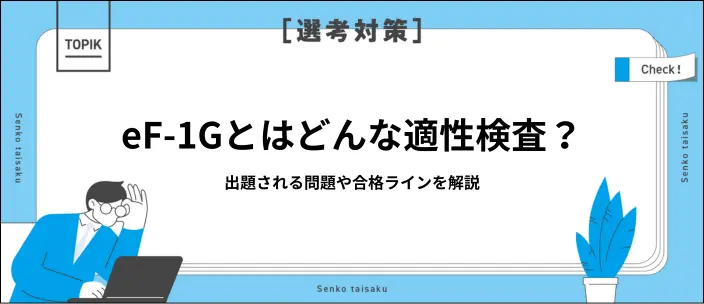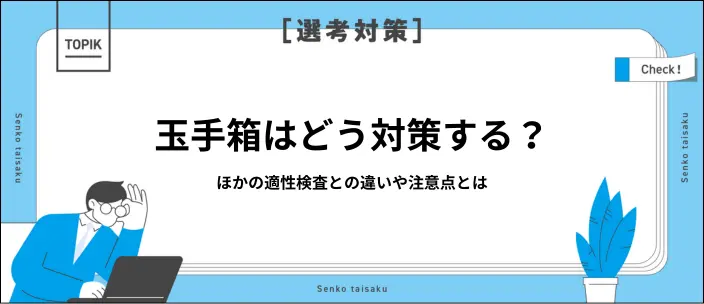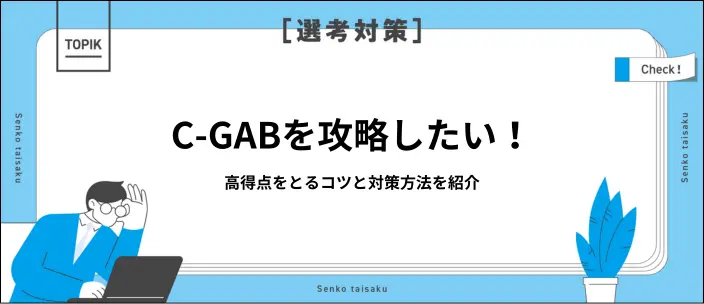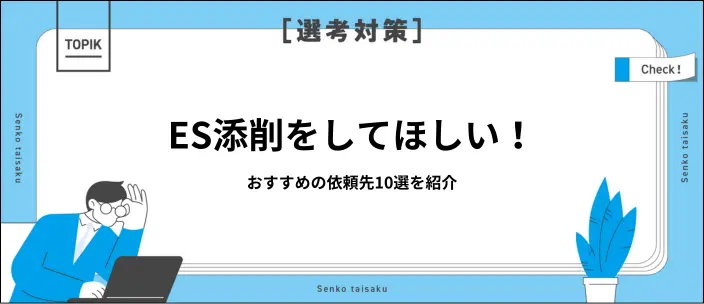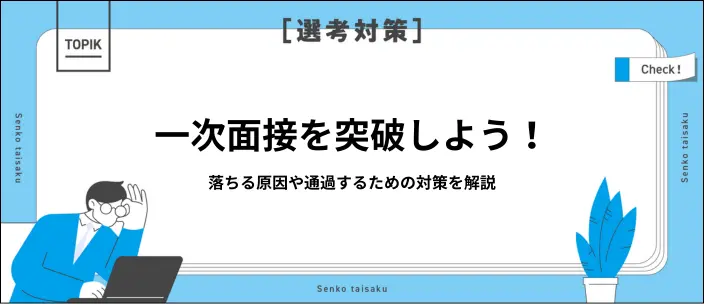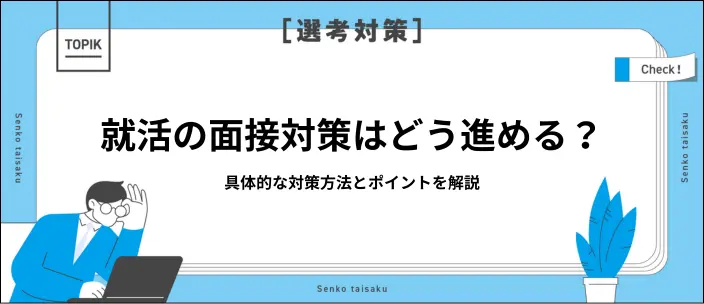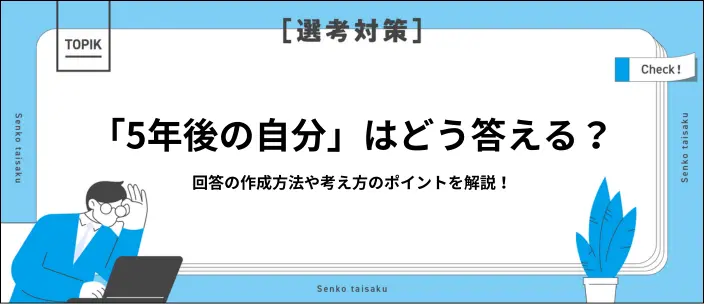このページのまとめ
- CABとは、コンピュータ職の適性があるかどうかを判断するテストのこと
- CABテストはペーパー形式とWeb形式で問題構成が異なる
- CABテスト問題集や模擬試験を繰り返し時間感覚や緊張になれることが大切
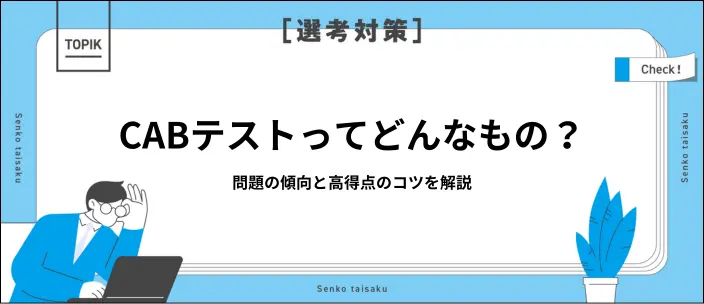
CABテストは、IT業界や論理的思考力が求められる職種の選考で多くの企業が採用する適性検査です。「問題形式が独特でどう対策すればよいかわからない」「時間内に全問解けるか不安」と悩む就活生は少なくありません。
この記事では、CABテストの基本情報から出題内容、形式別の特徴、具体的な事前対策や得点アップのコツまで、実践的に解説します。しっかりと対策をして、CABテストに備えましょう。
かんたん1分!無料登録就活の筆記試験について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- CABとは「コンピュータ職適性診断テスト」のこと
- CABテストとGABテストの違い
- CABテストとSPIの違い
- CABテストにはペーパー形式とWeb形式がある
- 筆記で受験するペーパー形式
- パソコンで受験するWeb形式
- CABテストの分野ごとの出題内容
- 基本的な四則演算をおこなう「暗算」
- 計算式の空欄を埋める「四則逆算」
- 複数の図形の法則を見つける「法則性」
- 指令に従って最適な図を導き出す「命令表」
- 2つの異なる図形の変動を推測する「暗号」
- 受験者の人格を把握する「性格検査」
- CABテストの対策が必要な人
- IT業界やSEを目指している人
- 論理的思考力が重視される業界や職種を目指している人
- CABテスト対策を始める時期と時間数の目安
- 受検の2週間〜1カ月前から始めるのが理想的
- 対策に必要な勉強時間は10〜20時間が目安
- CABテストの事前対策方法
- 1.問題集を繰り返し解く
- 2.自分の苦手な分野を知って対策する
- 3.時間配分の感覚を身につける
- 4.複雑な問題は図を想像して情報を整理する
- 5.本命企業の前に他社で練習する
- CABテストで高得点を取るための4つのコツ
- 1.1問に時間をかけ過ぎない
- 2.1問に使う目安時間を決めておく
- 3.全問正解より合格点以上を目指す
- 4.分からないときは潔くあきらめる
- CABテスト対策を始めたいと考えているあなたへ
CABとは「コンピュータ職適性診断テスト」のこと
CABとは、コンピュータ職の適性があるかどうかを判断するテストのことです。主に、IT企業の新卒採用で実施されます。
CABテストの構成は大きく分けて、コンピュータ職に必要とされる4分野の能力検査と、受験者の人間性を測る性格検査の2つ。CABテストを突破するためには、それぞれの分野に適した対策を取る必要があります。
Web適性検査については「就活の適性検査とは?検査の種類や特徴、受ける際のポイントをご紹介!」も参考にしてください。
CABテストとGABテストの違い
CABテストとGABテストは、どちらも日本エス・エイチ・エル株式会社が提供していますが、対象職種が異なります。GABテストは、言語・計数・論理など幅広い能力を測定。総合職や事務職などさまざまな職種で利用されています。
GABテストとは何か詳しく知りたい方は「GABテストとは?特徴や出題内容を解説!対策と注意点も把握しよう」も参考にしてください。
CABテストとSPIの違い
SPIは「Synthetic Personality Inventory」の略で、基礎的な計算力や言語理解力などの能力検査と、性格を把握する検査で構成されています。営業・企画・事務など幅広い職種で活用。基礎学力や性格面を幅広くチェックできます。
SPIテストの詳細を知りたい方は「SPI対策をご紹介!出題内容やポイントを把握して適性検査を突破しよう」もあわせてチェックしてみてください。
かんたん1分!無料登録就活の筆記試験について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
CABテストにはペーパー形式とWeb形式がある
CABテストの形式は、ペーパーとWebの2種類。この項目では、CABテストのペーパー形式とWeb形式の概要をご紹介します。
筆記で受験するペーパー形式
ペーパー形式のCABテストの場合は、実際に試験会場に行き、紙媒体で試験を受けます。具体的な構成は以下のとおりです。
・暗算:10分で50問
・法則性:15分で40問
・命令表:20分で50問
・暗号:20分で39問
・性格検査:30分で68問
ペーパー形式のCABテストでは、能力検査が計179問、性格検査が計68問出題されます。所要時間は、能力検査と性格検査を合わせて95分です。
パソコンで受験するWeb形式
Web形式のCABテストの場合は、自宅などから、パソコンを使用して試験を受けます。テストの具体的な構成は以下のとおりです。
・四則逆算:9分で50問
・法則性:12分で30問
・命令表:36分で15問
・暗号:16分で30問
・性格検査:30分で68問
Web形式のCABテストでは、能力検査が計125問、性格検査が計68問出題されます。所要時間は103分です。Web形式の場合は、能力検査の出題分野の1つが暗算ではなく、四則逆算となっています。
「Web-CABってどんなテスト?対策方法や合格ラインを解説!」でも、Web-CABについて詳しく紹介しているため、あわせてご参照ください。
かんたん1分!無料登録就活の筆記試験について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
CABテストの分野ごとの出題内容
この項目では、CABテストの出題内容を、分野ごとにご紹介します。どのような問題が出題されるのか事前に把握しておくことで、CABテスト本番に備えましょう。
基本的な四則演算をおこなう「暗算」
暗算の出題内容は、基本的な四則演算です。ペーパー形式のCABテストに出題されます。暗算はCABテストの中で最も簡単とされている問題。
ただし、簡単だからこそ、確実に点数を取る必要があるといえます。試験当日は電卓が使用できないため、速く、正確に解けるように練習しておきましょう。
計算式の空欄を埋める「四則逆算」
四則逆算とは、四則計算の逆算問題のこと。Web形式のCABテストに出題されます。式の空欄部分に当てはまる数字を、方程式を解くことで算出。5つの選択肢の中から答えを選びます。
問題が進むにつれて難易度が上がるため、最初の問題に時間をかけ過ぎないようにするのがポイントです。
複数の図形の法則を見つける「法則性」
法則性は、複数の図形に共通する法則を見つける問題です。4つの異なる図形から法則を見つけ出し、空欄に当てはまる図形を選びます。初見で解くのは難しいとされているため、事前に例題を解き、問題に慣れておきましょう。
指令に従って最適な図を導き出す「命令表」
命令表では、指示された内容どおりに図形を変化させ、答えを算出します。命令記号は10種類。問題ごとに命令内容や図形は変わるため、臨機応変に対応する必要があります。
事前に命令内容や、図形の変化の仕方を把握しておくことが重要といえるでしょう。
2つの異なる図形の変動を推測する「暗号」
暗号は、最初に明示される暗号を解読したうえで、設問の空欄に当てはまる答えを算出します。法則性の問題と性質が似ているため、代表的なパターンを知っておくことがポイントです。
受験者の人格を把握する「性格検査」
性格検査では、質問を通して、受験者がどのような人間性を持っているのかを判断します。回答内容から、どのような仕事に向いているのかを判断することも可能です。
性格検査の結果は、選考の際だけでなく、入社後の配置決定の際にも使用される可能性があります。自分にふさわしい仕事に携わるためにも、質問内容をよく読み、正直に回答しましょう。
性格検査については「性格検査とは何か?就活で受ける理由と効果的な対策法を解説」も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就活の筆記試験について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
CABテストの対策が必要な人
CABテストは、IT業界だけでなく論理的思考力が求められる業界で重要視される適性検査です。「自分はCABテストの対策が必要なのか?」と迷う就活生も多いでしょう。
ここでは、どのような人がCABテスト対策を優先すべきかを解説します。自分の志望業界や職種に照らして、効率よく対策を進める参考にしてください。
IT業界やSEを目指している人
IT業界やシステムエンジニア(SE)を志望する就活生は、CABテストの対策が必要になる可能性が高いでしょう。
CABテストは、論理的思考力や情報処理能力を測定する適性検査で、IT分野の業務適性を判断する指標として多くの企業で導入されています。特にプログラミングやシステム設計など、論理的な問題解決力が求められる職種では、CABテストの結果が選考に大きく影響するでしょう。
IT業界やSEを目指すなら、CABテストの出題傾向を理解し、十分な対策を行うことが内定への近道です。
論理的思考力が重視される業界や職種を目指している人
論理的思考力が求められる企業や業界を志望する場合、CABの対策は重要です。Web-CABでは、暗算・法則性・命令表・暗号などの問題を通じて、受験者の論理的思考力や問題解決能力が評価されます。
この能力はIT業界に限らず、コンサルティングや金融業界などでも高く評価されるスキル。論理的思考力が求められる職種を目指すなら、CABの出題傾向を理解し、適切な対策をしておくことが選考突破のポイントです。
なお、就活のどの段階で筆記試験が課されるかは、「就活のやり方と流れを解説!準備から内定までのポイントと相談先も紹介」の記事で確認いただけます。対策を行う場合は逆算して、試験に間に合うよう計画を立てましょう。
かんたん1分!無料登録就活の筆記試験について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
CABテスト対策を始める時期と時間数の目安
CABは独特な問題形式が多いため、事前準備をしているかどうかで得点に大きな差が出ます。ここでは、CABテスト対策を始める時期の目安と、必要な勉強時間について解説しますので、ぜひ対策を始めるタイミングの参考にしてください。
受検の2週間〜1カ月前から始めるのが理想的
CABテスト対策は、受検の2週間〜1カ月前から始めるのが理想的です。CABは暗算・法則性・命令表・暗号など独特の問題が多く、慣れるまでに時間がかかります。直前に詰め込みで対策しようとすると、時間配分や問題形式に慣れきれずに本番で実力を発揮できない可能性があるのです。
早めに始めれば、CAB以外の就活準備(自己分析・ES・面接対策など)との両立もしやすいでしょう。CABテスト対策は「直前に焦って詰め込む」よりも、「少しずつ慣れていく」ほうが効果的です。受検日から逆算して、2週間〜1カ月前には勉強を始めておきましょう。
対策に必要な勉強時間は10〜20時間が目安
ABテストの対策時間は、一般的に10〜20時間程度が目安です。CABはSPIと違い、暗算・命令表・暗号など特殊な形式の問題が多く、慣れることが得点アップに直結します。短期間でも集中して練習すれば、形式に慣れて突破できる可能性が高まるでしょう。
数学や論理が得意な人であれば、10時間程度でも十分に対応可能です。暗算や法則性が苦手な人は、15〜20時間、特に苦手分野に時間を割く必要があるでしょう。
CABテスト対策は「長時間の勉強」よりも「効率よく慣れること」が大切です。自分の得意・不得意を把握し、10〜20時間を目安に計画的に取り組みましょう。
かんたん1分!無料登録就活の筆記試験について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
CABテストの事前対策方法
ここでは、CABテストで高得点を取るための具体的な事前対策方法を解説します。問題集の活用法から苦手分野の克服、時間配分や図を使った解き方まで、実践しやすい5つのポイントを押さえて、効率的に対策を進めましょう。
1.問題集を繰り返し解く
まずは、市販の問題集や、Webサイトに掲載されている問題をひたすら解きましょう。CABテストを突破するためには、とにかく問題に慣れることが重要です。繰り返し問題を解くことで、CABテストの出題パターンを把握しましょう。
2.自分の苦手な分野を知って対策する
CABテストでは、得意な分野だけでなく、苦手な分野を把握して対策することが得点アップの鍵です。暗算や法則性、命令表や暗号など、分野ごとに求められるスキルが異なるため、自分がどこでつまずきやすいかを理解して重点的に練習しましょう。
暗算が苦手な場合:解くことに慣れる
暗算が苦手な人は、とにかくたくさんの問題を解き、計算に慣れることが重要です。
暗算のスキルは、即席で身につけるのが難しいといえます。CABテストでは、10分間で50問の暗算を解かなければなりません。テスト本番まで毎日コツコツと問題を解き、着実にスキルを身につけましょう。
また、暗算では、計算速度だけでなく正確性も重要なポイントといえます。計算速度とともに、正確に解くことを意識して、練習を重ねましょう。
四則逆算が苦手な場合:計算の基礎を理解する
四則逆算が苦手な人は、計算の基本を理解しておくことが重要です。計算の基礎は、大きく分けて「交換法則」と「分配法則」の2種類。交換法則とは、数字を入れ替えて計算しても答えが同じになる法則のことで、足し算とかけ算に利用できます。
分配法則は、カッコ付きの計算式を、カッコを外した計算式に変えても、答えが同じになる法則のことです。四則逆算では、交換法則や分配法則を利用して計算式を分解したり、逆に組み立てたりすれば、答えを導き出せます。
ただし、CABテスト本番では、9分間で50問の問題を解かなければなりません。計算することに慣れたら、速く解くことを意識して練習しましょう。
法則性が苦手な場合:法則を覚える
法則性が苦手な人は、CABテストに出題される問題の、基本的な法則を覚えましょう。CABテストの法則性の問題では、主に図形の「動き」「数」「形」「色」「向き」「大きさ」に、ある一定の法則が隠されています。
法則性の問題は、どの法則パターンに当てはまるかを常に意識しながら解くことが重要です。
命令表が苦手な場合:視覚化する
命令表が苦手な人は、頭の中で考えていることを視覚化することが重要です。命令によってさまざまに変化していく図形も、紙に書くことで簡単に整理できます。実際に答えを導き出すときも、紙に書き出した図形が役に立つはず。慣れてきたら、速く解くことを意識しながら練習しましょう。
暗号が苦手な場合:法則性を知る
暗号が苦手な人は、まず基本的な法則性を覚えましょう。CABテストの暗号の問題では、主に図形の「色」「大きさ」「数」「形」「向き」に一定の法則があります。どの法則性に当てはまるかを常に意識しながら、問題を解く練習をしましょう。
3.時間配分の感覚を身につける
CABテストを受けるにあたって、時間の感覚を身につけることは重要なポイントです。CABテストは、分野ごとに所要時間が決められています。所要時間と問題数から、1問あたりにかけられる時間を算出しておきましょう。
ただし、問題によって難易度は変わるため、簡単な問題には時間をかけ過ぎないのがポイントです。
4.複雑な問題は図を想像して情報を整理する
CABテストでは、複雑な問題に直面したら図を描いて頭の中を整理することが効果的です。複雑な図形問題や命令表の処理で、頭の中だけで考えると混乱して解答スピードが落ちるリスクがあります。特に難しい問題ほど、視覚的に整理するとミスを防ぎやすくなるでしょう。
たとえば、図形の変換や法則性の問題では、紙やノートに簡単な図や表を書いて考えます。命令表や暗号の手順も、矢印や番号を使って書き出しましょう。練習段階から図を使う習慣をつけると、本番でも焦らず対応できるようになります。
頭の中だけで複雑な問題を解こうとせず、図や表で視覚化することでミスを減らし、解答スピードも安定させましょう。
5.本命企業の前に他社で練習する
CABテストは、本命企業の受検前にほかの企業や模擬試験で練習しておくことが効果的です。CABは独特な問題形式に加え、時間制限も厳しいため、本番の緊張で普段の力を発揮できないケースが多くあります。そのため、模擬試験を受けて制限時間の感覚に慣れることが大切です。
本命以外の企業のCABを経験し、出題形式や雰囲気に慣れると良いでしょう。緊張感のある環境で経験を積むことで、本番でも落ち着いて取り組めます。
普段は解ける問題でも、本番では緊張で思うように解けないことも。だからこそ、本命企業の前に場数を踏み、慣れておくことがCABテスト突破の大きなカギになります。
かんたん1分!無料登録就活の筆記試験について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
CABテストで高得点を取るための4つのコツ
この項目では、CABテストで高得点を取るコツをご紹介します。ポイントをしっかりと押さえ、CABテスト突破を目指しましょう。
1.1問に時間をかけ過ぎない
CABテストでは、1問にかける時間を短くし、スピード重視で解くことが高得点のポイントです。CABは問題数に対して制限時間が厳しいため、1問に時間をかけ過ぎると後半の問題まで手が回らなくなります。
序盤から集中し、分からない問題に悩み過ぎず、次に進みましょう。練習段階から、素早く問題を理解して回答する感覚 を身につけておくと、本番でも落ち着いて解答でき、高得点につながります。
2.1問に使う目安時間を決めておく
CABテストでは、1問あたりに使う時間を事前に決めておくことが高得点のコツです。CABは制限時間が厳しく、時間配分が得点を左右します。時間を決めておくことで、後半の問題まで焦らずに解答できるようになるでしょう。
得意分野と不得意分野を把握して、1問あたりの解答時間を設定したり、10秒で答えが出ない問題は適当にチェックして次に進むとルールを決めたりするのがおすすめです。
練習段階でこの時間配分を体に染み込ませ、本番でも迷わず実行できるようにしましょう。CABテストでは、時間を決めて素早く判断する力が合格ラインを大きく左右します。得意・不得意に応じた時間配分ルールを作って練習しておきましょう。
3.全問正解より合格点以上を目指す
CABテストでは 全問正解を目指す必要はなく、合格点を確実に取ることが重要です。難しい問題に時間を使い過ぎると、得意な問題に回せる時間が減り、全体の正答率が下がる可能性があります。
そのため、分からない問題は潔く飛ばし、確実に解ける問題に集中し、「満点よりも合格点」を意識して解答することで、時間内に効率よく得点を稼げるでしょう。この考え方はCABだけでなく、SPIや玉手箱などほかのWebテストでも共通です。
4.分からないときは潔くあきらめる
答えが分からず悩んだときは、潔くあきらめることも大事です。CABテストで重要なポイントは、問題を速く正確に解くこと。苦手な問題で立ち止まってしまうと、本来解けるはずの問題に手を付けられなくなってしまう可能性があります。
限られた時間の中で、より多くのポイントを稼ぐためには、問題をコンスタントに解いていくことが重要です。
かんたん1分!無料登録就活の筆記試験について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
CABテスト対策を始めたいと考えているあなたへ
CABテストは、IT業界や論理的思考力が求められる職種を目指す就活生にとって、避けて通れない重要な適性検査です。この記事でご紹介したように、事前の対策方法や勉強のコツを押さえることで、本番で焦らず得点を稼ぐことが可能になります。
出題形式に慣れる:問題集や模擬試験を繰り返し解く
苦手分野を把握して重点的に対策:暗算・四則逆算・法則性・命令表・暗号など
時間配分を意識する:1問あたりの目安時間を決め、分からない問題は潔く飛ばす
合格点を確実に取る:全問正解よりも効率よく得点することを優先
効率的にCABテスト対策を進めることは、内定への大きな一歩。しかし、自己流で勉強するだけでは、どこから手を付ければよいか迷うこともあります。
そこで、就活支援サービス キャリアチケット を活用するのがおすすめです。キャリアチケットでは、プロによる面接・ES対策だけでなく、適性検査対策のアドバイスも受けられるため、効率よく得点力を伸ばせます。
自分に合った対策法をプロに確認してみましょう。CABテスト対策を計画的に進め、内定への自信を手に入れてください。
かんたん1分!無料登録就活の筆記試験について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。