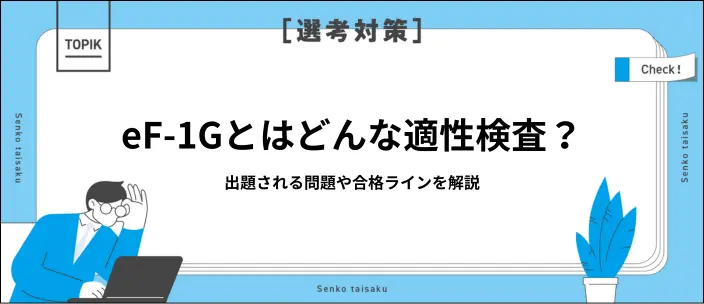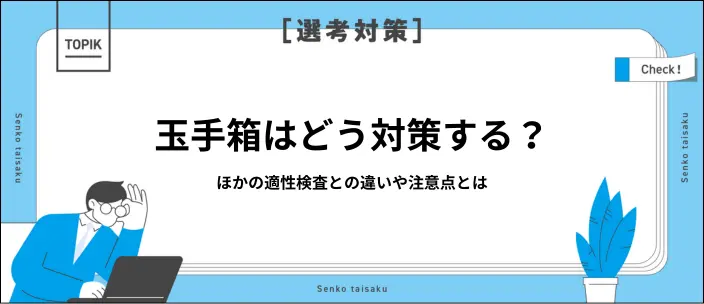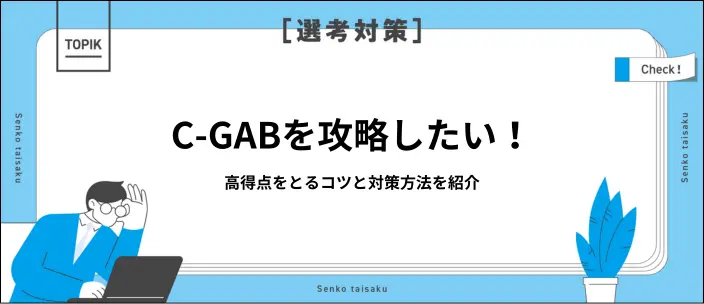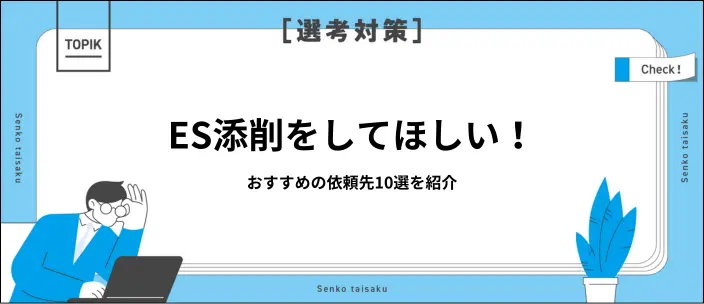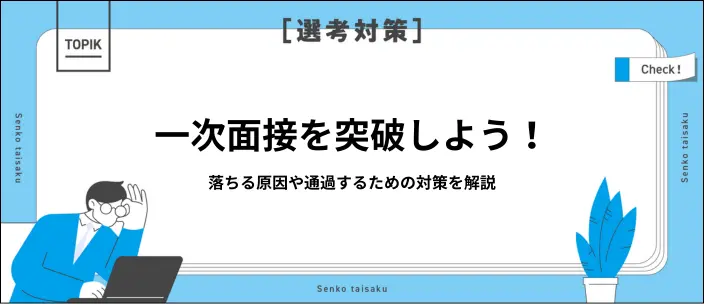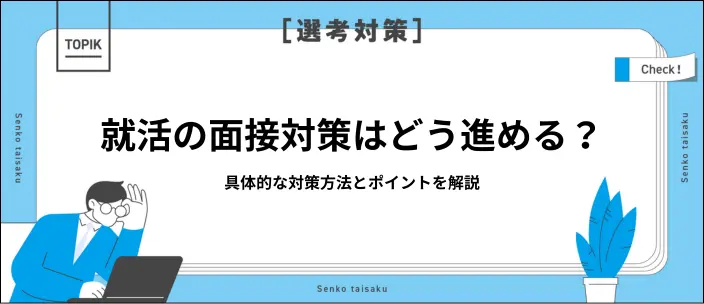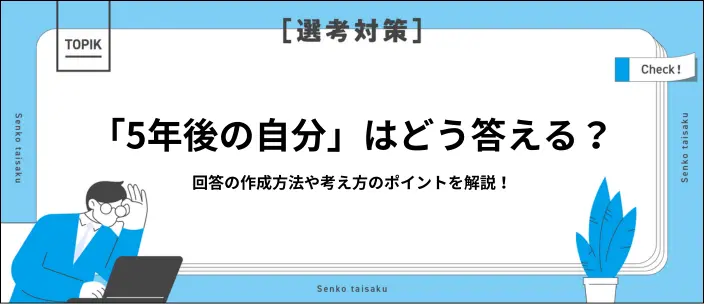このページのまとめ
- Webテストは企業の適性検査で、種類や受検形式によって特徴が異なる
- Webテストの受験形式にはWebテスティングやテストセンターなどの種類がある
- Webテストの種類を見分けるには、案内メールのURLを見るのがおすすめ
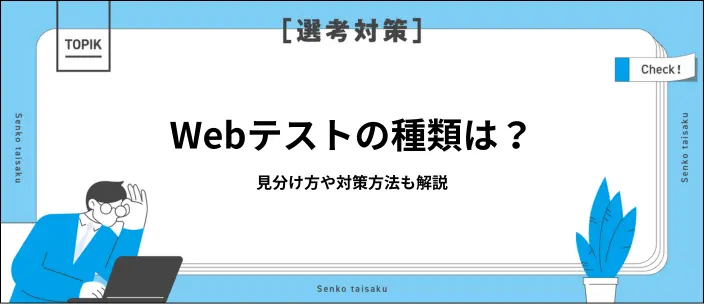
就活で「Webテストを受ける予定があるけど、どの種類か分からない」「SPIや玉手箱の違いが分からず不安」と感じる学生は多いでしょう。Webテストには、企業によって出題内容や受検形式が異なるさまざまな種類があります。
この記事では、Webテストの種類や特徴、受検形式、見分け方、効果的な対策法などを解説。これを読めば、Webテストで戸惑うことなく、自信を持って受検に臨めるでしょう。
かんたん1分!無料登録Webテスト対策を相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- Webテストとはパソコンで受検する適性検査
- 企業がWebテストを導入する理由
- 応募者を効率的に絞り込むため
- 自社に合った人材を見極めるため
- Webテストの受検形式の種類
- Webテスティング
- テストセンター
- インハウスCBT
- ペーパーテスト
- Webテストの種類の見分け方
- URLで見分ける
- Webテストの情報を調べる
- Webテストの種類20選と見分け方を解説
- SPI
- ENG
- 玉手箱
- Web-GAB
- Web-CAB
- TG-WEB
- SCOA
- CUBIC
- GPS
- TAP
- eF-1G
- 3E-IP
- TAL
- AIP
- 不適性検査スカウター
- BRIDGE
- ミキワメ
- GROW
- 内田クレペリン検査
- アドバンテッジインサイト
- Webテスト対策に効果的な4つの方法
- 1.参考書や問題集で繰り返し問題を解く
- 2.ほかの企業のWebテストや模擬試験を受ける
- 3.本番の時間配分を意識する
- 4.苦手な問題を優先的に勉強する
- 性格検査では正直に解答する
- Webテストを自宅で受ける際に気を付けること
- 期限に余裕をもって受ける
- 不正行為は絶対に避ける
- インターネット回線やPC環境を事前に確認する
- 就活のWebテストでお悩みのあなたへ
Webテストとはパソコンで受検する適性検査
Webテストとは、自宅や学校などのネット環境が整った場所で、パソコンを使って受検する適性検査のことです。就活でよく使われるWebテストには、「SPI」や「玉手箱」があります。
Webテストは企業によって、どの種類を採用しているかは異なるので注意しましょう。また、Webテストごとに出題内容や問題形式は違うため、それぞれ対策を行う必要があります。
Webテストと適性検査に関しては、受験方法が異なるだけで大きな違いはありません。適性検査については「就活の適性検査とは?検査の種類や特徴、受ける際のポイントをご紹介!」の記事を参考にしてください。
かんたん1分!無料登録Webテスト対策を相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
企業がWebテストを導入する理由
就活で多くの企業が取り入れているのがWebテストです。「なぜわざわざテストを受けるの?」と疑問に思う人もいるでしょう。Webテストには、応募者を効率良く選ぶ、自社に合った人材を見極めるといった目的があります。
応募者を効率的に絞り込むため
企業がWebテストを導入する理由の一つは、応募者を効率的に絞り込むためです。
新卒採用では、数百〜数千人規模の応募が集まることも珍しくありません。しかし、すべての学生と面接することは難しいのが現実といえるでしょう。そこでWebテストを活用し、基礎的な学力や適性を数値化することで、短時間で多くの学生を公平に評価できます。
Webテストは、企業が効率的に候補者を選び、面接の質を高めるためのフィルタリングツールとなっているのです。
自社に合った人材を見極めるため
Webテストを導入するもう一つの理由は、自社に合った人材を見極めるためです。
企業は応募者の能力や適性をテストで確認し、自社の業務や社風に合う人材を選びたいと考えています。適性に合った人材を採用できれば、入社後に長期的に活躍しやすく、早期離職のリスクも減らせるでしょう。
たとえば、Webテストの性格検査で「チーム志向」や「論理的思考力」が高いと判断された場合、面接ではその強みをさらに掘り下げる質問がされることがあります。こうした活用により、面接官は応募者の人柄や価値観をより正確に理解でき、採用のミスマッチを防げるのです。
Webテストは、単なる足切りのためだけでなく、企業が将来活躍できる人材を見つけ、採用の精度を高めるための重要なツールといえます。
かんたん1分!無料登録Webテスト対策を相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
Webテストの受検形式の種類
Webテストの受検形式には、「Webテスティング」「テストセンター」「インハウスCBT」「ペーパーテスト」の4種類があります。それぞれの受検方法について解説するので、参考にしてください。
Webテスティング
Webテスティングは、自宅や学校など自由な場所でパソコンを使って受けられるオンライン形式のWebテストです。指定期間内であれば好きな時間に受検できるため、テストセンターのように会場に行く必要がありません。
受検方法は、まず企業から送られてくる受検案内メールに記載されたURLとIDでログインします。受検開始前には、画面上で進捗バーや時計、タブの切り替え方法などの操作説明が表示されるため、きちんと確認することが大切です。
また、能力検査の言語問題・非言語問題は、最初に練習問題として提示され、画面操作を確認できます。Webテスティングはスマートフォンでは受検できないため、必ずパソコンを使用しましょう。さらに、インターネット環境やパソコンの動作に不具合がないか事前に確認し、落ち着いた場所で受検することも重要です。
Webテスティングは「場所や時間を選ばず受けられる便利さ」と「事前準備の大切さ」を理解して受検することがポイント。受検期限に余裕を持って準備し、安心してテストに臨めるようにしておきましょう。
テストセンター
テストセンターは、指定された会場で決められた日時に受ける形式のWebテストです。
会場での受検により、企業は公平な環境で学生の能力を評価できます。また、受検管理のために専用のIDが必要で、企業IDとは別に取得しなければならないので覚えておきましょう。
・試験会場や日時の候補から希望を選んで受検
・使用するIDは企業IDとは別で、今後ほかの試験にも使う可能性があるため管理が重要
・受検前に性格検査を完了していないと、能力検査の予約がキャンセル扱いになる場合も
テストセンターは指定の会場・時間で受ける形式で、ID管理や性格検査の事前完了などの準備が大切です。余裕をもってスケジュールを調整しましょう。
テストセンターについては、「テストセンターってなに?適性検査の種類と受検方法まとめ」の記事で詳しく解説しています。
インハウスCBT
インハウスCBTは、応募先の企業が用意したパソコンでWebテストを受ける形式です。受検する会場も企業側が指定し、テストは面接などの選考とセットで行われることが多いため、事前に準備しておきましょう。
ただし、この形式を導入する企業は少ないのが現状です。企業側は自社内でパソコンを用意し、監督者を配置する必要があるため負担が大きくなります。
インハウスCBTを受ける場合は、企業が指定する環境やスケジュールに従い、落ち着いて受検できるよう事前に準備しておきましょう。
ペーパーテスト
ペーパーテストは、マークシート方式で行う筆記試験です。企業が用意した会場に出向いて受検し、手書きで解答用紙に記入します。会社内や特設会場で行われることが多く、説明会のように大人数が集まる場で実施されるケースも。
一部の企業では、Webテストの代わりにペーパーテストを採用することもあります。たとえば、会社で1〜2時間程度の学生向け説明会を実施し、選考希望者は残ってペーパーテストを受ける、という流れで行われることがあるようです。
ペーパーテストは会場に直接出向く必要があるため、事前のスケジュール調整や会場までの移動時間の確認が大切。また、試験中は手書きで正確に回答することを意識しましょう。
就活ではWebテスト以外にもやるべきことが多くあります。「就活のやり方と流れを解説!準備から内定までのポイントと相談先も紹介」の記事で具体的に解説しているので、合わせて参考にしてください。
かんたん1分!無料登録Webテスト対策を相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
Webテストの種類の見分け方
応募先企業が導入しているWebテストの種類を事前に把握できると、効率よく対策ができるでしょう。ここでは、企業がどの種類のWebテストを導入しているか見分ける方法を解説します。
URLで見分ける
Webテストの種類は、企業から送られてくる案内メールのURLから見分けられます。以下のように見分けることができるので、チェックしておきましょう。
・SPI:URLに「arorua」が含まれる
・玉手箱:URLに「e-exam」「nsvs」「tsvs」が含まれる
・WEB-GAB:URLに「c-personal」「e-gitest」が含まれる
・WEB-CAB:URLに「e-exam」「nsvs」「tsvs」が含まれる
・TG-WEB:URLに「c-personal」「e-gitest」が含まれる
案内メールが届いてからWebテストを受けるまでの期限は、3〜7日前後が一般的です。時間は限られますが、事前にピンポイントで対策できます。
Webテストの情報を調べる
どのWebテストが行われるのか、自分で調べることもできます。企業によって行うWebテストは毎年同じ場合が多いので、過去の結果から想像しやすいでしょう。
たとえば、志望企業のWebテストを受けた人の口コミを参考に判断できます。OB・OG訪問で聞いてみるのも良いでしょう。
また、企業によって募集要項でどの適性検査を行うか公表している場合もあります。まずは募集要項をしっかりと確認することから始めましょう。
かんたん1分!無料登録Webテスト対策を相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
Webテストの種類20選と見分け方を解説
Webテストには多くの種類があり、その特徴はさまざまです。ここでは、主要なWebテストについて詳しく解説します。
SPI
適性検査と聞いて、まず思い浮かべるのが「SPI」ではないでしょうか。SPIはリクルート株式会社が提供している適性検査で、多くの企業が採用試験に導入しています。
企業から指定されたWebテストのURLが「http://arorua.net/」から始まる場合は、SPIを受けることになるでしょう。さまざまな企業がSPIを導入していますが、特に、銀行や商社、大手企業で採用されている傾向があります。
SPIの出題傾向
SPIの出題科目は、以下の2つです。
・能力検査(言語、非言語)※一部企業では「英語」「構造把握」が追加されることもある
・性格検査
SPIの能力検査では基礎的な知識や学力を測り、性格検査では応募者のパーソナリティを検査する問題が出題されます。能力検査の「言語」は国語、「非言語」は数学の問題だと覚えておくと分かりやすいでしょう。
「英語」「構造把握」に関しては実施しない企業もあるため、必須科目の「言語」「非言語」を中心に対策しておくのがおすすめです。
SPIの特徴
SPIのWebテストは、全体の試験時間だけでなく、設問ごとに解答の制限時間が設けられています。問題数は決められておらず、受検者が解答するスピードによって数が異なるのも特徴です。正答するだけではなく、スピーディーに解答することで高得点が狙えます。
また、次の問題に進むボタンを押した場合、前の問題には戻れないので注意してください。入力方式の問題が多く出題されるので、模擬テストを受けて入力形式に慣れておくと良いでしょう。
ENG
ENGはリクルート株式会社が提供している英語科目のテストで、SPIとセットで出題されることがほとんどです。SPIを受検しているときに英語の問題が出題されたら、ENGだと判断できるでしょう。主に英語力を必要とする外資系企業などで、学生の英語能力を測る目的で実施されています。
ENGの出題傾向
ENGの出題科目は「英語」で、リスニングはありません。和文英訳や長文読解をはじめ同意語や反意語、空欄補充などの問題が出題されます。
ENGの特徴
ENGで出題されるのは、英単語を暗記しただけでは解けない問題や、読解力と読解スピードを必要とする問題ばかりです。そのため、ENGの対策として取り組むよりも、日ごろから英語力を高めておくことが求められます。
玉手箱
玉手箱は、日本SHL株式会社が開発した適性検査です。企業から指定されたWebテストのURLが「https://web1.e-exams.jp/」「https://web2.e-exams.jp/」「https://web3.e-exams.jp/」から始まる場合は、玉手箱だといえるでしょう。
玉手箱もWebテストの代表格で、総合商社や専門商社、証券・投資銀行で多く採用されています。
玉手箱の出題傾向
玉手箱の出題科目は、以下の4つです。
・言語(論理的読解、趣旨判定、趣旨把握)
・計数(四則演算、図表読取、表推測)
・英語(論理的読解、長文読解)
・性格検査(パーソナリティ、モチベーションリソース)
玉手箱では、各科目につき1種類の分野のみが出題されます。たとえば、言語の科目で「論理的読解」が出題された場合、そのほかの「趣旨判定」「趣旨把握」の問題は出題されません。
また、各分野において問題形式のパターンが決まっています。応募先企業の出題傾向に合わせて分野ごとのパターンを把握しておくと、比較的スムーズに解答できるでしょう。
玉手箱の特徴
玉手箱は、ほかの適性検査と比べて問題数が多く、制限時間が短い傾向にあります。そのため、1問ごとの解答スピードを上げるよう意識して対策することが重要です。また、言語や英語の問題では長文問題が多いので、長い文章に慣れておくとよいでしょう。
Web-GAB
「Web-GAB」も玉手箱と同じく、日本SHL株式会社が開発、販売している適性検査です。企業から指定されたURLの最初が「http://assessment.c-personal.com/」や「http://assessment.e-gitest.com/」であれば、Web-GABだといえるでしょう。
Web-GABは、主に総合商社や金融業界をはじめ、日系大手企業や新卒総合職の採用活動でも多く導入されています。
Web-GABの出題傾向
Web-GABの出題科目は、以下の2つです。
・能力検査(計数、言語)
・性格検査
能力検査は、図やグラフなどを元に問題を解く「計数」、100字程度の長文から出題される「言語」の2分野です。難易度はそこまで高くありませんが、制限時間が限られているので、短時間で正確に問題を解く処理能力が必要とされるでしょう。
一方で、性格検査の目的はパーソナリティを測定し、職務の適性を判断することです。性格検査はすべての設問に解答しなければ終わらず、制限時間も特に設定されていません。
Web-GABの特徴
Web-GABは、下記のとおり混同しやすいので注意しましょう。
・自宅のパソコンから受検する「Web-GAB」
・テストセンターに出向き受検する「C-GAB」
・指定された会場で受検するマークシート形式の「GAB」
・エンジニア向けのテスト「CAB」
また、玉手箱と同じ日本SHL社が開発した適性検査なので、似た内容の問題が出題される傾向にあるようです。玉手箱の受検に慣れておくことで、Web-GAB対策にもなるでしょう。
Web-CAB
Web-CABも、日本SHL株式会社が開発・販売している適性検査の一つです。数ある適性検査の中でも対象を「コンピュータ職」に絞った限定的なテストといえます。
企業から指定されたWebテストのURLが「https://web1.e-exams.jp/」や「https://tsvs1.e-exams2.jp/」「https://nsvs1.e-exams4.jp/」から始まる場合は、Web-CABであると推測できるでしょう。主に、システムエンジニアやプログラマー職を募集している企業に多く導入されています。
Web-CABの出題傾向
Web-CABの出題科目は、以下のとおりです。
・能力検査(四則演算、法則性、命令表、暗号)
・性格検査(バイタリティ、ストレス耐性、チームワークなどを含む9特性について検査)
推理能力を重視した問題が出題されるなど、エンジニアをはじめとするコンピュータ職に必要な技術や論理的思考力が備わっているかを診断するテストだといえます。そのため、情報通信、ソフトウェア開発といったIT企業で多く導入される傾向があるようです。
Web-CABの特徴
CABにはWeb形式とペーパー形式の2種類があり、制限時間はそれぞれ72分、95分と異なります。制限時間に違いがあることを踏まえて対策しておきましょう。
また、受検内容がほかのWebテストと比べて特殊なので、初見で受検すると戸惑う方が多いようです。事前に対策していないと、得点を取ることが難しいテストといえるでしょう。あらかじめ参考書を繰り返し解いて、しっかり対策しておく必要があります。
TG-WEB
TG-WEBとは、株式会社ヒューマネージが開発している適性検査です。WebテストのURLが「http://assessment.c-personal.com/」または「http://assessment.e-gitest.com/」から始まる場合は、TG-WEBだといえるでしょう。
TG-WEBは、日系の大手金融や外資系のコンサルティング業界などの有名難関企業で導入されています。
TG-WEBの出題傾向
TG-WEBの出題科目は、以下のとおりです。
・言語(長文読解、空欄補充、並べ換えなど)
・計数(暗号、展開図、推論など)
・英語(長文読解)
・性格(項目は7種類以上)
TG-WEBは、ほかの適性検査と比べると難易度が高く、馴染みの薄い問題が出題されています。しかし、企業によっては、難易度は高くせず、短時間で問題数が多い形で出題される場合もあるようです。
TG-WEBの特徴
TG-WEBの問題は難しい一方で、解き方を身につけておけば比較的スムーズに攻略できるといわれています。きちんと対策に取り組み、解き方をマスターしておけば心配ありません。Webテストの場合は電卓が使用できるので、日ごろから使い慣れておくとよいでしょう。
SCOA
SCOAは、日本経営協会総合研究所(NOMA総研)が販売しているWebテストです。受検方式は、Webテスト形式とペーパーテスト形式、テストセンター形式があります。
URLが「https://apps.ibt-cloud.com/」であれば、SCOAだといえるでしょう。
SCOAのWebテストでは、基礎能力とパーソナリティの2構成で、基本的認知能力や行動パターンを判断する問題が出題されるのが一般的です。基礎能力では、言語や数理、英語、常識、論理といった5つの分野で構成されています。
CUBIC
CUBICは、株式会社AGPが提供しているWebテストです。受検方式は、Webテストとペーパーテストがあります。URLに「https://web-cubic.jp/」「https://assessment.cservice.jp/」が含まれていれば、CUBICだと判断できるでしょう。
試験科目は、基礎能力検査と性格検査の2つ。基礎能力検査の内容は、言語や数理、理論、図形、英語の5分野です。ほかのWebテストと比べて試験範囲が広く、「基礎」「応用」「総合」と難易度が段階別に分かれています。
そのため、企業がどれを実施するかによって難易度が異なるのが特徴です。
GPS
GPSは、株式会社ベネッセコーポレーションが提供するWebテストで、人材業界を中心に導入されています。受検形式はWebテスト形式のみで、URLに「https://www.gps-cbt.com/」が含まれるのがGPSだといえるでしょう。
GPSは、能力検査(思考力、基礎能力)と性格検査で構成されています。特に、思考力のテストにおける、音声や動画を使用した出題方法が特徴的です。
思考力のテストでは、問題解決能力を試す問題が出されるため、日ごろから行動や言動を意識してロジカルシンキングを鍛えておくと良いでしょう。
TAP
TAPは、日本文化科学社が提供しているWebテストです。受検方法は、Webテストかマークシート形式のペーパーテストがあります。
URLに「https://www.empweb21.com」が含まれるのがTAPです。
適性検査の種類は、総合タイプ(能力問題、性格検査)と性格タイプ(性格検査のみ)、短縮タイプ(総合タイプの時間が半分になったもの)の3種類があります。企業によっては、オプションとして、英語や事務適性、情報処理の問題が出題される場合もあるようです。
eF-1G
eF-1Gは、株式会社イー・ファルコンが提供するWebテストで、適性検査は難易度が高いといわれています。URLに「https://ef-1g.com」が含まれるのはeF-1Gです。
eF-1Gは、能力検査と性格検査の2つで構成されています。能力検査は、言語系(国語の問題)と非言語系(算数や数学の問題)の出題科目です。各設問で解答する制限時間が設けられているため、スピーディーに進める必要があります。
3E-IP
3E-IPは、エン・ジャパン株式会社が開発したWebテストです。受検形式は、Webテストとマークシート形式のペーパーテストがあり、受検時には「noreply-webtest@en-japan.com」からメールが届くとされています。
試験内容は、3E-i(知的能力テスト)と3E-p(性格・価値観テスト)の2構成で、英語や中国語、ベトナム語にも対応しているのが特徴です。
TAL
TALは、株式会社人総研が開発した脳科学・統計学系のWebテストです。TALでは、能力検査が実施されず、性格検査のみが行われます。URLが「https://.tal-sa.jp/talsqi/」であればTALだと判断できるでしょう。
出題科目は「性格診断」と「図形配置問題」の2種類です。TALはあくまで適性検査であるため、明確な正答はなく、Webテストでは正直に答えるしか方法はないともいえるでしょう。
AIP
AIPは、株式会社アドバンテッジリスクマネジメントが提供するWebテストです。受検方式は、Webテストかマークシート形式のペーパーテストがあります。
URLが「https://aip.armg.jp」であれば、AIPだといえるでしょう。
「EQ能力テスト」「ストレス耐性テスト」「知的能力テスト」の3つから出題されます。AIPの特徴は、「ストレス耐性」に焦点を当てた検査内容です。知的能力テストについては、主要なWebテストと似た問題が出題されるので、ほかの種類の対策をしていれば問題なく解けるでしょう。
不適性検査スカウター
不適性検査スカウターは、株式会社スカウターが提供するWebテストです。受検方式は、Webテストのほかにマークシート回答方式と回答用紙記入方式の2パターンのペーパーテストがあります。
URLに「https://tracs.jp」が含まれていれば、不適性検査スカウターです。
不適性検査スカウターは、資質検査「SS」や精神分析「SB」、定着検査「TT」、能力検査「NR」の4科目から出題されます。出題される問題は企業によってさまざまです。1種類のみ出題されたり、4種類すべての問題が出題されたりするケースもあります。
BRIDGE
BRIDGEは、株式会社リンクアンドモチベーション社が提供しているWebテストです。受検方式は、Webテストとペーパーテストがあります。
URLに「https://generator.cbt.jp」「https://www.cbt-s.jp」が含まれていればBRIDGEだと判断できるでしょう。
BRIDGEの出題科目は、能力テストと性格テストの2つ。能力テストは、計数分野のみで構成されており、制限時間に対して問題が難しい傾向にあるので注意が必要です。
BRIDGEでは、玉手箱やTG-WEBと似ている問題が出題されるため、これらのWebテスト対策ができていれば問題なく解けるでしょう。
ミキワメ
ミキワメは、株式会社リーディングマークが提供している適性検査で、受検方式はWebテストです。URLが「https://survey.career-base.jp」であれば、ミキワメだといえるでしょう。
受検科目は能力検査と性格検査の2つで、制限時間はそれぞれ、能力検査が20分で性格検査は10分です。問題数に対して制限時間が短く、すべての問題を解き終えることは難しいでしょう。1問ごとの制限時間がないため、解ける問題から確実に解くのが得点アップのポイントです。
GROW
GROWは、Institution for a Global Society株式会社が開発した、スマートフォンなどにアプリをインストールして受検する適性検査です。GROWは最新のAI技術を用いて作られており、嘘や過大評価が通用しないのが特徴だといえます。
GROWの出題科目は、「気質診断」「自己評価」「他者評価」の3つです。GROWは、自己評価だけでなく、他者5人の評価も一緒に送信する必要があります。そのため、受検の必要性があれば誰に依頼するか早めに検討しておくと良いでしょう。
内田クレペリン検査
内田クレペリン検査は、単純作業から就活生の行動や正確性をはかる試験です。Webテストではなく、ペーパーテストで行われるケースが一般的になります。
内田クレペリン検査の試験内容は、横並びの数字を左から右に1つずつ足していくだけです。単純作業だからこそ、正確さや作業の速さが評価されます。
アドバンテッジインサイト
アドバンテッジインサイトは、精神面の適性をはかる際に用いられる検査です。「EQ能力」「ストレス耐性」「知的能力」の3つを測定します。
EQ能力とは、自分の感情をコントロールできる能力のことです。仕事では対人関係を良好に築くために、必要な能力といわれています。知的能力テストでは、言語や論理などの国語能力、数理や推論などの数学能力が評価されるので勉強しておきましょう。
URLには「aip.armg.jp」が含まれているかどうかで、アドバンテッジインサイトを見分けられます。
就活における適性検査の種類については、「就活のWebテストとは?受検形式や出題科目、効果的な対策法を解説」の記事も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録Webテスト対策を相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
Webテスト対策に効果的な4つの方法
ここでは、Webテスト対策に効果的な方法を解説します。自分の状況に合わせて、必要な対策をしてみてください。
1.参考書や問題集で繰り返し問題を解く
まずは参考書や問題集を使い、繰り返し問題を解くようにしましょう。同じ問題を何度もとくことで、問題の解き方や公式に慣れることができます。
Webテストの参考書や問題集は、SPIや玉手箱などテストごとにまとめられているケースが一般的です。志望する企業が導入しているWebテストがどれかを把握しておくと、より対策を進められるでしょう。
2.ほかの企業のWebテストや模擬試験を受ける
Webテスト対策として、さまざまな企業の適性検査や模擬試験を受けるのも効果的です。Webテストの場数を踏めば、大体の問題形式や難易度を把握するのに役立ちます。
可能であれば、応募先企業が導入しているのと同じ種類のWebテストを受けるのがおすすめです。実際のWebテストや模擬試験を経験することで、自身の実力を客観的に把握できるでしょう。
3.本番の時間配分を意識する
Webテストの多くは解答するのに時間制限があるため、対策の段階から本番さながらの時間配分を意識することが大切です。対策時にもタイマーを使って時間制限を設け、できる限り本番と同じ環境を再現しましょう。
本番で必要なスピード感で問題を解いていけると、Webテストを受けるときも焦らず落ち着いて挑めるはずです。
4.苦手な問題を優先的に勉強する
自分の苦手な分野や問題形式があれば、集中的に取り組みましょう。苦手だと感じた問題があれば、そのままにせず、関連する参考書や問題集を使って解答方法の理解に努めてください。
Webテストは出題される範囲が広いため、得意分野を勉強するより苦手分野をなくす方が効果的です。優先的に苦手な問題に時間を割くことで、全体的な得点アップにつながります。
性格検査では正直に解答する
性格検査では、嘘をつかずに正直に答えることが効果的な対策です。
企業は性格検査の結果から応募者の価値観や行動傾向を把握し、面接での印象と照らし合わせています。ここで矛盾があると「一貫性がない」と判断され、評価が下がる恐れがあるでしょう。
たとえば、性格検査で「リーダーシップがある」と答えたのに、面接では主体性を全くアピールできないと不自然です。このズレがあると「信頼できない」と思われることもあります。
そのため、性格検査は自分をよく見せようとせず、素直に回答するのが良いでしょう。実際に練習問題を解いて形式に慣れておくと、落ち着いて回答できるようになります。
かんたん1分!無料登録Webテスト対策を相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
Webテストを自宅で受ける際に気を付けること
最近は、自宅で受けられるWebテストを導入する企業が増えています。自宅で受検できるのは便利ですが、ちょっとした不注意でトラブルが起きることも。ここでは、安心してWebテストを受けるための基本的な注意点をまとめました。
期限に余裕をもって受ける
Webテストは締切日ギリギリに受けず、余裕をもって受検しましょう。
最終日にアクセスが集中するとサーバーが重くなったり、突然のネットワークトラブルで受検が中断されたりする恐れがあります。場合によっては「受検が無効」になり、再受験できない可能性もあるでしょう。
このようなリスクを避けるために、Webテストは最低でも締切の2〜3日前までに受検しておくのが無難です。
不正行為は絶対に避ける
Webテストでのカンニングや替え玉受検、解答集の使用などの不正行為はやめましょう。
不正が発覚すると、選考中止や内定取り消しの恐れがあります。また、仮に入社できても、自分のスキルや特性と企業の期待にズレが生じ、長期的に活躍できないリスクもあるでしょう。
近年、多くの企業はオンライン監視型のWebテストを導入しています。画面やカメラで受検中の行動をチェックされるため、替え玉やカンニングは容易に見破られることがほとんどです。
Webテストは自分の力で正直に解答することが大切。オンライン監視型テストを受ける際は、事前に環境やルールを確認して、安心して受検できるよう準備しましょう。
インターネット回線やPC環境を事前に確認する
Webテストを受ける前には、回線やパソコン環境を必ず確認しておきましょう。
Webテストはオンラインで行われるため、通信環境やPCの不具合によるトラブルは自己責任です。回線が遅かったり、パソコンの動作が重かったりすると、解答時間に影響が出てやり直しができない場合があります。
受検前に、回線速度が推奨基準を満たしているか確認したり、不要なブラウザやアプリを閉じたりしておくと、スムーズにテストを進められるでしょう。また、できれば有線接続を使うと、より安定した環境で受検が可能です。
事前に回線やPC環境をチェックしておくことで、トラブルを防ぎ、落ち着いてWebテストに集中できるようになります。
Webテストの種類によっては、電卓を使用することも。電卓の使用は受検形式によって異なるため「SPIで電卓は使用できる?使える受検形式やおすすめの機能を解説」を参考に、事前に確認しておきましょう。
かんたん1分!無料登録Webテスト対策を相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活のWebテストでお悩みのあなたへ
「Webテスト対策をしたいけれど何から始めたら良いか分からない」「応募先企業のWebテストの種類を知りたい」といった悩みを抱えている就活生も多いのではないでしょうか。
就活におけるWebテストは、種類を見極めてからそれぞれの特徴に合わせて対策する必要があります。対策すべきWebテストの種類で悩んでいる場合は、就活エージェントへの相談もおすすめです。
就職エージェントのキャリアチケットでは、Webテスト対策の相談をはじめ、就活生のさまざまな悩みを解決するサポートをしています。Webテストについて悩んでいる方は、ぜひ利用してみてください。
かんたん1分!無料登録Webテスト対策を相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら