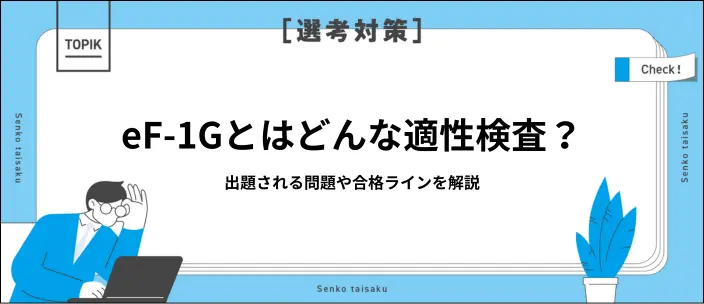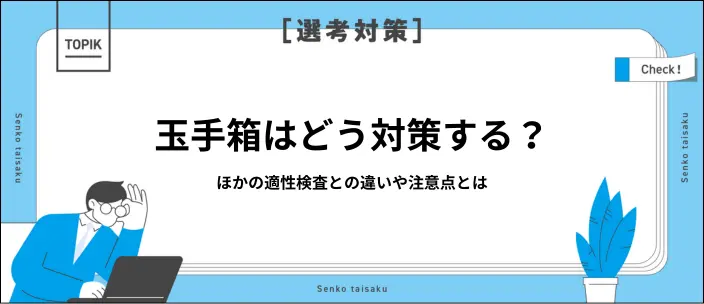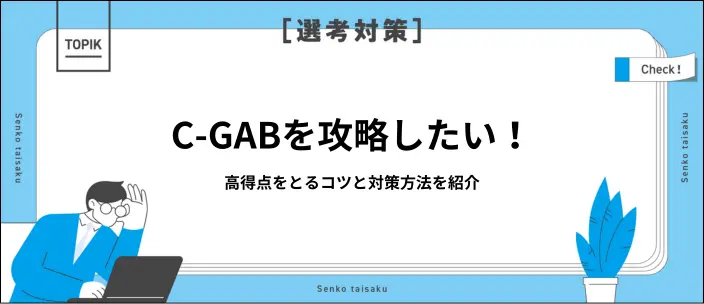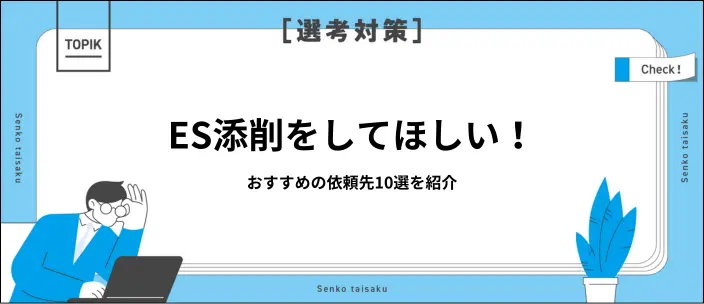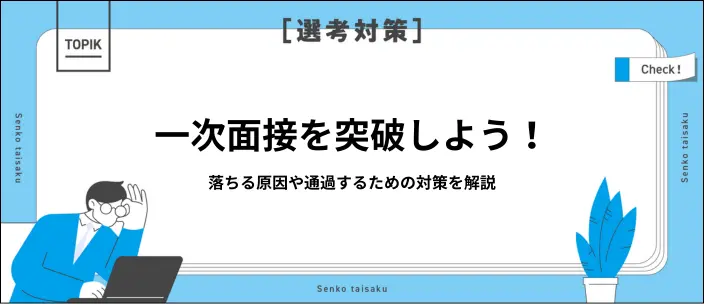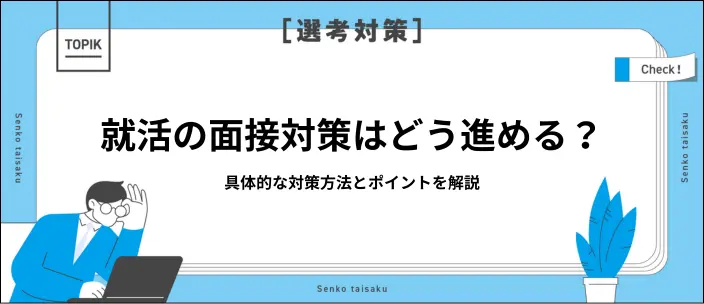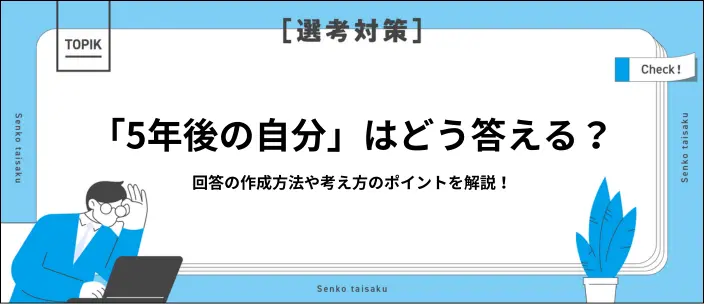このページのまとめ
- 適性検査には、SPIや玉手箱などいくつもの種類がある
- 適性検査の問題は、能力検査と性格検査の2種類で構成されるのが一般的
- 応募企業が使う適性検査をチェックして、種類ごとに対策を立てておくことが大切

「適性検査の種類が知りたい」「それぞれどんな違いがあるの?」などと気になる就活生も多いでしょう。適性検査ごとに出題内容や制限時間は違うため、違いを知って対策しておくことが欠かせません。
この記事では、就活でよく使われる適性検査の種類を22個解説します。就活でどのような適性検査が行われるか知りたい、高得点を取りたいなどと考えている方はぜひ参考にしてください。
かんたん1分!無料登録適性検査対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 適性検査とは?就活で使われる理由を解説
- 適性検査は2種類で構成される
- 能力検査
- 性格検査
- よく使われる適性検査の種類10選
- SPI
- 玉手箱
- TG-WEB
- GAB
- CAB
- ENG
- YG検査
- TAL
- ミツカリ
- 内田クレペリン検査
- 使われる頻度の少ないマイナーな適性検査12選
- SCOA
- ミキワメ
- BRIDGE
- CUBIC
- TAP
- eF-1G
- Talent Analytics
- GPS
- Compass
- アッテル
- GROW360
- デザイン思考テスト
- 適性検査の対策方法
- 適性検査ごとの特徴を把握する
- 問題集を繰り返し解く
- 苦手な分野を中心に練習する
- 制限時間を意識して練習する
- 適性検査の種類など就活に必要な情報を知りたいあなたへ
適性検査とは?就活で使われる理由を解説
適性検査とは、受検者の仕事の適性や能力を測定するためのテストです。就活では、どの就活生を面接に呼ぶかを決める目的で、選考の一つとして使用されます。
企業によっては志望者が数千人になることもあり、全員を面接することはできません。また、多くの企業は、能力が高い・仕事への適性があるといった就活生を採用したいと考えています。そのため、適性検査で就活生の能力などを確かめることで、選考をスムーズに行おうとしているのです。
適性検査がどのようなものかについては、「就活の適性検査とは?検査の種類や特徴、受ける際のポイントをご紹介!」の記事でも詳しく解説しています。
かんたん1分!無料登録適性検査対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
適性検査は2種類で構成される
適性検査は「能力検査」と「性格検査」の2種類で構成されています。それぞれの特徴を解説するので参考にしてください。
能力検査
能力検査とは、仕事に必要な思考力や知的能力を測定する検査です。能力検査には、「言語分野」と「非言語分野」の2種類があります。
言語分野では、国語に近い問題が出題される傾向です。以下のような内容が出題されるので覚えておきましょう。
・熟語
・語句の用法
・文の並べ替え
・長文読解
・二語関係
非言語分野とは、算数や数学に近い問題のことです。数的処理が正しくできるかを求められたり、論理的に物事を考えられるかを求められたりします。非言語分野で出題される内容は、以下のとおりです。
・推論
・組み合わせ
・順列
・損益算
・仕事算
・速度算
・集合
・割合
能力検査の内容や対策については、「SPIの能力検査は、いつから対策を始めればいい?」の記事を参考にしてください。
性格検査
性格検査とは、就活生の人柄や価値観を測定する検査です。「自社にマッチするか」「仕事への意欲はありそうか」などが測定されます。
基本的には問題が出題され、「あてはまる」「あてはまらない」などの選択肢を選ぶケースが一般的です。対策に時間をかける必要はありませんが、回答に慣れるために一度は練習問題を解いてみてもよいでしょう。
性格検査がどのような検査かについては、「性格検査とはどんなテスト?問題例や準備・対策方法を解説!」の記事で解説しています。回答のポイントや注意点も紹介しているので、ぜひご覧ください。
かんたん1分!無料登録適性検査対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
よく使われる適性検査の種類10選
適性検査には、SPIや玉手箱などいくつもの種類があります。就活で使われやすい適性検査の種類を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
SPI
就活場面で多く使用される適性検査が「SPI」です。SPIは何度もアップデートを重ねられており、現在では「SPI3」がメインに使われています。
SPIの試験内容は、能力検査と性格検査の2つです。能力検査には、言語分野と非言語分野があります。また、企業によっては英語を出題する場合もあるので覚えておきましょう。さらに、テストセンターで受検する場合には、「構造的把握力検査」が実施される場合もあります。
問題の難易度は中学・高校レベルであり、対策しておけば十分に解ける内容です。解き方や公式を忘れているケースも多いので、油断せずに勉強しましょう。
SPIがどのような試験かについては、「SPIの内容は?複数ある受検方法による違いを解説!」の記事で詳しく解説しています。
玉手箱
玉手箱の特徴は、能力検査に英語が含まれている点です。SPIとは異なり、どの玉手箱を受ける際にも、英語は必須となります。
また、ほかの適性検査と比べて出題される種類が少ない点も特徴です。言語問題と計数問題では3種類、英語問題では2種類しか出題されません。
SPIの場合は全部で30種類以上の問題が出題されるので、玉手箱の出題パターンは少ないといえるでしょう。ただし、一度の試験で同じ形式が何度も出題されるため、対策をしていないと点数が全く取れない状況に陥る点は気をつけてください。
TG-WEB
TG-WEBは適性検査のなかでも、難易度が高い検査です。外資系コンサルや証券会社などで使用される傾向にあります。
TG-WEBの特徴は、「従来型」と「新型」の2つがある点です。「従来型」は難易度の高い問題が多く、非言語分野には経路問題やサイクロイドなど珍しい問題もあります。
「新型」は従来型よりも難易度は下がりますが、その分問題数が多くなるのが特徴です。すばやく回答できなければ、高得点を取るのは難しいでしょう。
TG-WEBがどのような適性検査かについては、「TG-WEB試験って何?従来型と新型の特徴や対策方法を伝授!」の記事を参考にしてください。
GAB
GABは、新卒採用のなかでも総合職向けに行われる適性検査です。知的能力に加えて、バイタリティやチームワークなども測定できる特徴があります。
GABの対策のポイントは、長文読解をメインに行うことです。ほかの適性検査と比べて長文読解の問題が多く、加えて短時間で解かなければなりません。
GABがどのような適性検査かについては、「GABテストとは?特徴や出題内容を解説!対策と注意点も把握しよう」の記事を参考にしてください。
CAB
CABは、プログラマーやシステムエンジニアなどを目指す際に出題されやすい適性検査です。プログラミングへの適性があるか、パソコンを使用する仕事に向いているかなどを測定されます。
CABは数的処理が必要な問題を中心に出題されるので覚えておきましょう。以下のような問題の対策を行うのが大事です。
・暗算
・法則性
・暗号
・命令表
性格検査も実施されるので、少なくとも一度は練習しておくと安心でしょう。
ENG
ENGとは、SPIのなかでも英語に特化した適性検査のことです。テストセンターかペーパーテストのみで実施され、Webテストの場合は行われない検査になります。
ENGでは以下のような問題が出題されるようです。
・語彙力
・長文読解
・英文理解
特に、ペーパーテストは30分で40問を解く必要があるなど、問題数に対して制限時間が短い傾向にあります。すばやく回答するために、文章の読解力はもちろん、語彙力も高めておく必要があるでしょう。
YG検査
YG性格検査(YGPI)は、日本心理テスト研究所が提供する性格検査で、就職活動において企業が応募者の性格特性を把握するために活用されています。YG性格検査は、短時間で直感的に回答する形式のため、自分をよく見せようと考え過ぎず、素直な気持ちで回答することが重要です。
検査結果は、企業が応募者の性格特性を把握し、面接や配属の参考にするために活用されます。そのため、自己分析の一環として検査結果を見直し、自分の強みや改善点を把握することも有益です。
事前にYG性格検査のサンプル問題に触れておくことで、検査の形式や質問内容に慣れ、本番で落ち着いて回答できるようになります。公式サイトや就活支援サイトでサンプル問題が公開されている場合があるので、活用してみてください。
TAL
TALは人総研が提供する適性検査で、質問の意図が見抜きにくく、対策が難しいのが特徴です。コミュニケーション能力やストレス耐性など、面接では把握しづらい内面をデータ化できるため、企業側にとっては学生の本質を理解する手段となります。
回答に明確な正解がないため、受検時には素直に答えることが求められるでしょう。TALは受検者の直感や価値観を反映させる設問が多く、対策が難しい検査です。素直に答えることで、企業に自分の本質を伝えられます。
ミツカリ
ミツカリの適性検査は、学生だけでなくその企業で働いている社員も同じ検査を受けることで、「この会社はどんなタイプの人が多いのか」が分かる仕組みになっています。
まず企業の社員が検査を受け、その結果から「社風」や「仕事の進め方の特徴」を分析。そのうえで学生が同じ検査を受けると、自分がその会社に合っているかどうか、つまり「相性」が見えてきます。入社してから「思っていた会社と違った…」というミスマッチを防ぐのに役立つ検査です。
内田クレペリン検査
内田クレペリン検査とは、能力や行動面を測定する検査です。Webテストはなく、ペーパーテストのみで実施されるのが特徴。
横並びの数字が配置され、左から右にとにかく足し算を続けます。計算の正確性や作業の速さが測定されるのです。
かんたん1分!無料登録適性検査対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
使われる頻度の少ないマイナーな適性検査12選
前項で紹介した適性検査以外に、マイナーな適性検査もあります。ここでは、使われる頻度の少ないマイナーな適性検査12選を紹介し、それぞれの特徴や対策方法を解説します。これらの検査を把握しておくことで、ほかの就活生より一歩先に進むための準備を整えましょう。
SCOA
SCOAとは、「知」「情」「意」の3つを測定することを目的に作成された適性検査です。
・知:基礎的な知識
・情:持って生まれた気質
・意:性格や意欲など、後天的に得たもの
SCOAの特徴は、理科や社会の知識も測定される点です。ほかの適性検査では出題されにくい内容なので、対策しておく必要があるでしょう。
しかし、SPIなどに比べると問題の難易度は優しい傾向にあります。基礎的な知識が求められるので、問題集を繰り返し解き、知識を蓄えておきましょう。
ミキワメ
ミキワメは、採用後のミスマッチ防止を目的に使用される適性検査です。「採用後に自社で活躍できるか」「どの部署で採用すると相性が合うか」などを調べるために使われています。
ミキワメの能力検査では、一度にすべての問題が表示される点が特徴です。そのため、分かる問題から解いていくと点数を取りやすいでしょう。
制限時間は20分で、問題数は20問です。1問1分ペースで解く必要があるため、対策は十分に行うようにしてください。
BRIDGE
BRIDGEは適性検査のなかでも、難易度の高い検査です。数学の内容が多く、以下のような問題が出題されます。
・空欄推測
・図表の読み取り
・推論
・場合の数
・集合
難易度はSPIや玉手箱よりも難しいと言われており、対策が必須です。制限時間も1問あたり1分と少ないため気をつけてください。
CUBIC
CUBIC適性検査では、「あなたは何かを始めるとき、しっかり考えてから動くタイプですか?」といった、自分自身の性格や行動パターンに関する質問が出されます。回答は、「とてもそう思う」「あまりそう思わない」などの選択肢から、自分に近いものを選び、数字で記入。
この検査は、「どれが正しい答えか」を判断するテストではなく、「自分がどんな人か」を知るためのものです。そのため、どんな回答を選んでも間違いにはなりません。
また、「この答えを選んだから、この性格と判断される」という単純な仕組みではなく、1つの質問が複数の性格的な要素(因子)をチェックするように作られています。たとえば先ほどの例では、「慎重さ」だけでなく、「気分の変わりやすさ」や「積極性」なども同時に見られているのです。
TAP
TAP適性検査は、いわゆる「学力テスト」に近い形式で、認知力(ものごとを理解する力)や論理的思考力、コミュニケーション力などを幅広く測ります。検査にはいくつかのタイプがあり、受ける企業や職種によって出題される内容が変わることも。
TAPを受けるにあたっては、出題傾向や問題形式に慣れておくことが大切です。まずは過去問や練習問題を解いてみましょう。
eF-1G
eF-1Gで測定される項目は、194項目にもおよびます。eF-1Gの目的は、「今どんなスキルがあるか」だけでなく、将来どんな力を発揮できるかというポテンシャル(潜在能力)を測ることです。加えて、「この人の価値観や考え方は、うちの会社に合いそうか?」といった性格やマッチ度もチェックされるため、単なる学力テストではありません。
eF-1Gに関しては、対策問題集や過去問があまり出回っていないのが実情です。しかし、すでに受検した人の体験談や例題が、WebサイトやSNSで少しずつ紹介されるようになってきました。
・eF-1Gの出題形式や制限時間の情報を集める
・例題を掲載しているサイトで問題の傾向をつかむ
上記のような方法で、ある程度の準備は可能です。情報が少なくて不安なときは、eF-1Gを使っている企業にエントリーして、実際に受検してみるのも一つの手。本番の雰囲気を体験することで、次回以降の対策がしやすくなり、自分の今の実力を知るきっかけにもなります。
Talent Analytics
Talent Analytics(旧3E-IP)は、エン・ジャパンが提供する適性検査で、能力テストと性格テストを中心に構成されています。このテストの目的は、学歴に関係なく、企業にとって活躍できる人材を見極めることです。
加点方式で採点されるため、できるだけ多くの問題を解き、得点を稼ぐことが求められます。そのため、難しい問題でも躊躇せずに解くことが大切です。Talent Analyticsは、加点方式で素早く解くことが求められるため、問題を解くスピードと正確さを意識して臨みましょう。
GPS
GPSは、能力検査と性格検査の2つに分かれていて、能力検査では「思考力」と「基礎能力」が問われます。
思考力のパートは、「短い音声の問題」「動画・音声を組み合わせた問題」「文章で出題されるテキスト問題」の3種類。一方、基礎能力のパートでは言語力や数的処理力をチェックされます。SPIや玉手箱など、ほかのWebテストでも見かけるような推論や計算系の問題が中心です。
GPSでユニークなのは、やはり音声や動画を使った出題形式といえるでしょう。問題自体はそこまで難しくはありませんが、慣れていないと戸惑ってしまう可能性があります。そのため、できればインターンシップなどで実際にGPSを体験し、形式に慣れておくのが理想です。
Compass
Compassはジィ・ディー・エルが提供する適性検査で、情報量が少ないため、初めて受ける人にとっては難易度が高めとされています。Compassの検査内容は、能力検査と性格検査の2つで構成されているのが特徴です。特に能力検査は、19ブロック114問の問題が出題され、1問にかけられる時間は約10秒と非常に短いため、スピードと正確さが求められます。
Compassの能力検査は、SCOAの問題形式と似ている部分が多く、SCOAの練習問題を解いておくと形式に慣れられるでしょう。スピード感をつかむためにも、時間内に問題を解く練習をしておくのがおすすめです。
問題数が多く時間が限られているため、検査の流れや進行方法を事前にしっかりと確認しておくことが大切といえます。本番では焦らないように、どのように進めていくかをあらかじめイメージしておきましょう。
アッテル
アッテルは、トランスが提供する適性検査で、価値観やカルチャーに関する設問が多いのが特徴です。検査は約15分で完了し、短時間で終わるので、忙しい就活生にも負担が少ないといえます。
アッテルの特徴は、性格に優劣がつきにくい設問を用いている点です。これにより、学生が「この選択肢を選ぶとどう判断されるか」を予測しにくくなっています。そのため、作為的な回答が難しく、より自然な自分の価値観や考え方が評価されやすいといえるでしょう。
アッテルのようなマイナーな適性検査の場合、過去問や例題が少なく、対策が難しいことがあります。その場合は、一般的な適性検査で出題される問題形式や科目についての基本的な対策をしっかりと立てておきましょう。
たとえば、数的推理や言語理解、性格診断など、ほかのテストと共通する分野は幅広く対応することが可能です。
GROW360
GROW360は、Institution for a Global Societyが提供する適性検査で、学生の気質や行動特性と企業とのマッチ度を測ることが可能です。GROW360を使う企業は、学生の本当の価値観や性格が企業の文化に適しているかを見極めることを目的としています。
潜在性格診断であるIATを使用して、学生が答える内容から、意識的ではなく無意識のうちに表れる潜在的な性格や価値観を測るため、正直に答えることが重要です。
デザイン思考テスト
デザイン思考テストは、創る力と評価する力を問う、一般的な適性検査とは大きく異なるタイプのテストです。創造セッション(30分)と評価セッション(30分)の2つで構成されています。
デザイン思考テストは、創造性や柔軟な発想力を重視しているため、明確な正解がないテストです。また、問題の形式が特殊なので、あらかじめどんな内容なのかを把握しておくことが重要といえます。
時間内に質の高いアイデアをいくつ出せるかが評価のカギになるので、テストの流れや操作方法などを事前に確認しておくと安心です。アイデアを出すのに慣れていない方は、普段からニュースや日常の課題に目を向けて、自分の意見を考える練習をしておきましょう。
かんたん1分!無料登録適性検査対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
適性検査の対策方法
適性検査を突破するためには、事前の対策が重要です。ここでは適性検査の対策方法を解説するので、参考にしてください。
適性検査ごとの特徴を把握する
適性検査ごとに出題内容や時間制限などが違うため、特徴を把握しておきましょう。受検する適性検査に沿った対策をしないと、高得点はとれません。
たとえば、SPIは英語が出題される場合が少ないため、英語の対策は不要です。一方で、ENGを受検する際は、英語が必須なので対策が求められます。適性検査を受ける前に、どの適性検査が出題されるかを確認しておきましょう。
問題集を繰り返し解く
問題集は1冊を買い、繰り返し解くのがおすすめです。1冊の問題集を繰り返し解くことにより、問題の形式や解き方に慣れることができます。
適性検査は公式や解き方を覚えてしまえば、解ける問題が多く出てくるのが特徴です。複数の問題集を解くより、1冊の問題集を繰り返し解くほうが、公式や解き方のパターンを覚えやすいでしょう。
苦手な分野を中心に練習する
適性検査で高得点をとるためには、苦手な分野を中心に練習してください。得意分野を1つ練習し続けるより、苦手な分野を複数対策した方が高得点につながります。
適性検査では、複数の問題形式が出題されるケースが一般的です。苦手な分野が多いと解けない問題が増えてしまい、点数がとれなくなるでしょう。
苦手な分野を減らし、どの分野が出題されても安定して解けるようにしておくのがコツです。得意な分野ばかり練習しないように気をつけてください。
制限時間を意識して練習する
練習の段階から、制限時間を意識して問題を解くようにしましょう。適性検査は制限時間が短い場合が多く、何も考えずに解いていると時間が足りなくなってしまいます。
適性検査によっては、1問あたり1分も時間がないケースもあるでしょう。本番で「時間が足りない」と焦ってミスをしないためにも、普段から制限時間を意識して練習してみてください。
適性検査の対策方法については、「適性検査の対策方法をご紹介!種類や受検方法も解説」の記事でも詳しく解説しています。
今一度、就活の流れややり方を振り返りたいと考えている方には、「就活のやり方を徹底解説!基本的な進め方やスケジュールをご紹介」の記事がおすすめです。卒業年度ごとにおおまかなスケジュールも紹介しているので、ぜひご覧ください。
かんたん1分!無料登録適性検査対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
適性検査の種類など就活に必要な情報を知りたいあなたへ
適性検査など就活に不安を抱える場合は、就職エージェントのキャリアチケットにご相談ください。キャリアチケットでは、適性検査の情報提供はもちろん、対策のサポートも行います。どのように勉強すれば良いか分からず困っている場合も、ぜひ頼ってください。
適性検査だけではなく、エントリーシート対策や面接対策など就活に関わることは全面的にサポートしています。就活の不安や悩みをキャリアチケットで解消して、内定獲得を実現しましょう。
かんたん1分!無料登録適性検査対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。