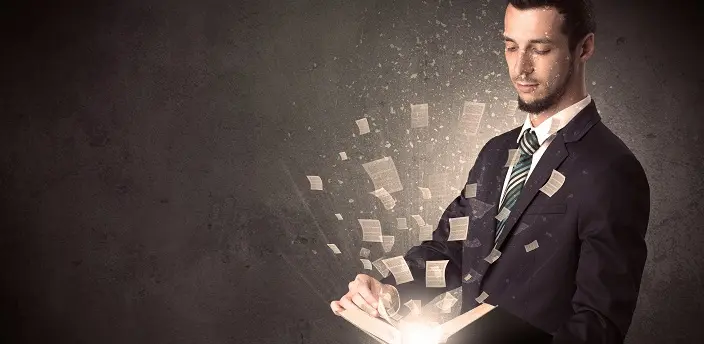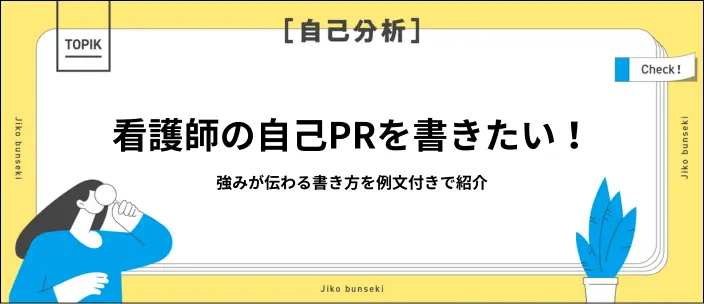このページのまとめ
- 就活におけるエントリーシートとは「選考を受けたい」という意志を企業に示す書類
- 企業はエントリーシートから、応募者のスキルやポテンシャルなどを見ている
- エントリーシートの書き方は、簡潔に伝える構成や具体的なエピソードを用いるのが重要

「就活で提出するエントリーシートを効果的に書けているか分からない」と悩む就活生は多いでしょう。エントリーシートで好印象を与えるためには、具体的な内容を記入したり、分かりやすく簡潔に表現したりすることが大切です。
この記事では、企業がエントリーシートで把握したいポイントや書き方のコツ、注意点を解説します。エントリーシートの項目ごとに例文も用意したので、参考にして選考通過を目指しましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 就活におけるエントリーシートとは
- 就活のエントリーシートの提出時期
- エントリーシートの仕様は企業によって異なる
- エントリーシートと履歴書の違い
- エントリーシートで代表的な質問と項目別のポイント
- 基本情報
- 自己PR
- 学生時代に力を入れた経験(ガクチカ)
- 志望動機
- 趣味・特技
- 長所・短所
- 就活のエントリーシートで写真を貼る際の注意点
- 就活のエントリーシートで企業が見ているポイント
- 応募者の性格や人柄
- 自社の求める人物像とマッチしているか
- 企業への入社意欲
- 仕事への熱意
- 内容の分かりやすさ
- エントリーシートの内容についてのキャリアアドバイザーのアドバイス
- 好印象を与えるエントリーシートの書き方のコツ6選
- 1.自己分析で自分のアピールポイントを言語化する
- 2.業界・企業研究で応募企業についての理解を深める
- 3.結論から述べて文章を構造的に組み立てる
- 4.具体的なエピソードや結果を伝え説得力を持たせる
- 5.文体の整合性を保つ
- 6.誰が読んでも分かる言葉を使う
- 就活のエントリーシート作成の注意点
- 話し言葉など公式な書類に合わない表現を使わない
- 空白が大きくならないように注意する
- 企業ごとに内容を変える
- 丁寧さを心がけて書く
- 待遇などについては記述しない
- 第三者に添削してもらう
- 就活におけるエントリーシートの項目別の例文
- 志望動機の例文
- 自己PRの例文
- ガクチカの例文
- インターンシップにエントリーする際の例文
- エントリーシートを企業に提出する際の確認ポイント
- 就活のエントリーシートをWeb上で提出する場合
- 就活のエントリーシートを郵送で提出する場合
- 就活のエントリーシートの書き方で悩むあなたへ
就活におけるエントリーシートとは
エントリーシート(ES)とは、選考を受けたい志望企業に対して提出する応募書類の一つです。応募者の基本情報に加え、志望動機や自己PRなどを記載する欄が設けられていることが多いです。
企業にとっては応募者について知るための資料であり、就活生にとっては自分をアピールする最初の機会であり、選考の第一関門と言えるでしょう。
また、企業はエントリーシートを面接時の参考資料としても活用するため、作成には入念な対策が必要です。ここでは、エントリーシートの提出時期や仕様について解説します。
就活のエントリーシートの提出時期
エントリーシートの提出時期は企業によって異なりますが、就活が本格化する3~5月が応募のピークです。
政府が公表した「2025年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方(1p)」によると、2025年度に卒業する新卒の採用活動について以下のスケジュールが示されました。
・広報活動開始:卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
・採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降
・正式な内定日:卒業・修了年度の10月1日以降
上記のスケジュールに沿って、広報活動を開始する3月から、選考を開始する前の5月中をエントリーシートの提出期限とする企業は多いでしょう。
ただし、企業によっては早期選考を行っている場合があるため注意が必要です。内閣府が公表した「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)(3p)」によると、採用面接を受けたピーク時期は4月が最も高い一方、大学3年次の1~2月の割合も増えている結果でした。

引用元:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)(3p)」
応募したい企業の選考時期を逃がして後悔しないためにも、エントリーの期限・方法などの情報を常にチェックして、締め切りまでにエントリーシートを提出してください。
参照元
厚生労働省
大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について
参照元
内閣府
学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査
エントリーシートの仕様は企業によって異なる
応募先によって求める人材や重視するポイントが異なるため、エントリーシートの記入内容は企業ごとに変わります。多くの企業が独自のフォーマットを保有しており、企業のWebサイトや特定のURLからのみ入手できるのが特徴です。
エントリーシートの提出方法も企業によって異なり、一般的にはWeb申し込みページやメールで送信したり、指定のエントリーシートをダウンロードして手書きしたものを郵送したりします。
なお、面接ではエントリーシートの内容を基に質問されるため、記入の際は仕様にかかわらず注意が必要です。また、インターンシップの選考で提出するエントリーシートには、インターンシップならではの質問もあります。それぞれ以下で詳しく解説するので、参考にしてください。
エントリーシートは面接での深掘りを想定して書く
就活のエントリーシートの内容は、面接で深掘りされることを想定して記載するのが大切です。
深掘りを想定せず思いついたままエントリーシートを記入すると、面接の際にうまく答えられない可能性が高まります。自己PRや志望動機といった主要な内容だけでなく、エントリーシートで聞かれる項目は、面接で深掘りされても答えられるように対策しておきましょう。
インターンシップでエントリーシートが必要な場合も
インターンシップへの応募でも、エントリーシートを提出する場合があるため、参加したい場合は準備が必要です。インターンシップに応募する際のエントリーシートも、基本的に就活のエントリーシートと同じ傾向にあります。
ただし、企業によっては「インターンシップで学びたい内容」を追加する場合があるため、自分が参加する目的を明確にしておきましょう。
また、「インターンシップで学びたい内容」はプログラム内容に合わせて具体的に記載するのが大切です。実施するインターンシップの内容に合っていない場合、「インターンシップへの参加意欲が低い」と捉えられかねないため気をつけてください。
エントリーシートと履歴書の違い
エントリーシートと履歴書のおもな違いは以下の通りです。
・エントリーシート:企業が選考で用いる書類
・履歴書:経歴などの人事データとして使う公的な書類
エントリーシートは独自のフォーマットを用いる企業が多い一方、履歴書は「JIS(日本工業規格)」という規格に基づき販売されているため、記載する内容は基本的に同じです。
履歴書は記載した氏名や住所などが人事データとして扱われ、公的書類にあたる重要な書類です。記載した内容に虚偽があった場合は、私文書偽造として不採用や解雇の原因にもなり得ます。
虚偽の内容を書くつもりがなくても、不確かな状態で記入すると誤って記載してしまう恐れもあるため、細部まで入念に確認しながら作成しましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
エントリーシートで代表的な質問と項目別のポイント
エントリーシートで問われる質問内容と特徴について解説します。項目は、「共通して聞かれる質問」と「企業独自の質問」の2種類に分けることができます。
基本情報
基本情報では、氏名や住所といった個人情報が共通的な記載項目です。記入するおもな項目や書き方のポイントは以下を参考にしてください。
| 基本項目 | 書き方のポイント |
| 日付 | ・Web応募や持参する場合:提出日を記載する ・郵送の場合:ポストへの投函日を記載する ・同時に提出する書類があれば日付を合わせる ・「△年△月△日」と正式な表記を用いる |
| 氏名 | 振り仮名の表記に注意する(フリガナ=カタカナ表記、ふりがな=平仮名表記) |
| 生年月日 | ・西暦、和暦の指定がない場合はどちらを使用しても問題ない ・年齢欄がある場合、応募時点の満年齢を書く |
| 住所 | ・都道府県から書き始める ・正式な番地を記載する ・マンション名なども必ず書く |
| 連絡先 | 日中に連絡の取れる連絡先を記載する |
| 学歴 | ・中学校卒業から書き始める ・「△△県立△△高等学校△△科 入学」など正式名称を記載する ・在学中は卒業予定の年月や大学名の後ろに「卒業見込み」と書く ・浪人や留年した期間、予備校、資格取得のためのスクールは記載しない ・生年月日を含め、年号の記載方法を統一する |
| 職歴 | 職歴欄は正社員としての経歴のみを書き、アルバイトは該当しない |
基本情報の内容は、履歴書と同じ傾向にあります。エントリーシートに押印を求められる場合もあるため、様式を入念に確認しましょう。
自己PR
就活のエントリーシートには、自己PRを書く欄があります。自己PRは、就活生のこれまでの経験・人柄から、入社後どのように活躍できるかという適性面やポテンシャルを評価する項目です。
自己PRで伝える強みや長所は、志望先企業の仕事内容に活かせるスキル、また、その企業が求める人物像にマッチしている資質を選択することが重要です。
自己PRの文章では、「結論(強み)→結論を裏付けるエピソード→強みをどのように企業で活かすか」という構成を用いることにより、採用担当者に伝わりやすくなります。
学生時代に力を入れた経験(ガクチカ)
就活のエントリーシートで質問されやすい項目として、「学生時代に力を入れたこと」も挙げられます。ガクチカとも呼ばれ、在学中に取り組んだ内容や経験から学んだことをアピールする項目です。
ガクチカでアピールできる内容には以下が挙げられるので、自身の経験を思い出す参考にしてみてさい。
・大学での勉強やサークル
・趣味や特技について
・アルバイト経験
・留学経験
・ボランティア経験
・日常で習慣にしていること
ガクチカの題材が見つからないと悩んでいる人は、「「ガクチカがない…」は勘違い!見つからない時の対処法や7つの例文を紹介」をご覧ください。
ただし、職種によって求められるスキルや経験が異なるため、効果的にアピールするためには適切なガクチカの題材を選ぶ必要があります。
志望動機
就活のエントリーシートで、必ずと言っていいほど質問されるのが志望動機です。企業は志望動機の内容から応募者の入社意欲や、就職に対してどのような価値観を持っているかなどを確認しています。
志望動機では、自分の就職に対する価値観が応募先のどのような点とマッチし、どのように自分の能力を向上させられるか明確にするのが重要です。そして、具体的にどのように活躍していくかを伝えれば、企業に自分が活躍するイメージを持ってもらいやすいでしょう。
趣味・特技
エントリーシートには、趣味や特技欄が設置されているケースも多いです。企業はエントリーシートの趣味・特技欄から、応募者が何に興味を持っているのかや自社の風土に合うかといったことを把握しようとしています。
趣味・特技欄では特別なエピソードを書く必要はなく、無理にアピールしようと背伸びしたり嘘の内容を伝えたりしないことが大切です。
自分が心から楽しんでいる趣味や、ささやかでも自信のある技術などを書けば、人柄が現れるエピソードになるでしょう。
長所・短所
就活のエントリーシートでは、長所や短所も質問されやすい項目です。企業は長所や短所から、応募者の性格や人間性が、自社の社風に合っているかを把握しようとしています。
長所は、人から感謝されたり褒められたりする自分の特徴などを書き出してみましょう。その中から、志望企業で活かせそうなものをピックアップし、理由とともにアピールするのがおすすめです。
短所の記入に関しては、言い換え表現を活用したり、克服するために努力していることを伝えるとプラスの評価につながりやすいです。短所の前向きな伝え方について詳しく知りたい人は、「短所一覧70選!効果的に伝える方法と長所への言い換えを例文付きで解説」の記事を読んでみてください。
就活のエントリーシートで写真を貼る際の注意点
企業によっては、エントリーシートに証明写真の添付を求める場合があります。選考時の第一印象に影響する可能性があるため、ビジネスマナーを守って提出しましょう。エントリーシートに添付する写真を用意する際は、以下の点に注意してください。
・身だしなみのマナーを守った服装で撮る
・清潔感のある髪型に整える
・口角を少し上げるなど、表情に気を配る
・姿勢を正す
・「△ヶ月以内に撮影したもの」「縦△cm×横△cmサイズ」など、応募要領に合わせる
・郵送の場合は写真の裏に氏名や大学名を記載する
就活用の写真撮影については、「就活写真はどこで撮影する?おすすめの撮り方や撮影のコツを解説」の記事にも記載されているので参考にしてみてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活のエントリーシートで企業が見ているポイント
ここでは、学生のエントリーシートの内容から、企業が評価するポイントを解説します。下記項目を意識することで、「選考通過できる」エントリーシートの作成を目指しましょう。
応募者の性格や人柄
企業はエントリーシートの項目から、応募者の性格や人柄を知りたいと思っています。応募者の人柄が自社の社風や文化に合えば、仕事のモチベーションも維持しやすいでしょう。
自己紹介や自己PRの欄では、志望する企業の社風や理念とマッチしていることを踏まえたうえで、それに沿った性格や長所をアピールするのが理想です。自己PRの書き方については、「自己PRの書き方は?就活で評価される構成と8つのコツを例文つきで解説」の記事も参考にしてみてください。
自社の求める人物像とマッチしているか
エントリーシートにおいて、応募者が、自社の理想とする人材像にどのくらいマッチしているかも見極めています。応募者のやりたいことと自社の業務内容が合っているか、自社の掲げる価値観や理念に同感してくれているかなどを把握することで、入社後のミスマッチを防ぐためです。
ガクチカや自己PRなどのエピソードにおいては、「自分の持っているスキルをどう活かし」「どんなキャリアプランを描いているのか」を明確にアピールしましょう。企業に、「この人と一緒に働きたい」と思ってもらえるかどうかが選考においては重要です。
企業への入社意欲
採用担当者はエントリーシートから、応募者の入社意欲も把握しようとしています。自社への愛着・興味が深い人は、企業の理念や事業内容に共感し生産性の高い行動をしてくれると考えるからです。
入社意欲が低い場合、採用してもすぐに転職したり、仕事への貢献度が低くなったりする可能性があるでしょう。
自社で長く活躍してくれる人材を採用するためにも、エントリーシートの内容から、業界・自社への理解度や応募者が持つ就職の方向性を確認し、入社意欲を見極めています。
仕事への熱意
仕事への熱意も、エントリーシートで企業が確認しているポイントです。仕事への熱意が高い場合、パフォーマンスを発揮しやすいと考えられます。
また、仕事に情熱を注げる人は主体的に行動したり、求められる以上の結果を出そうと工夫したりする傾向もあるでしょう。
熱意を持つポイントや熱量は人によって異なりますが、自社に貢献してくれる人材を採用するために、応募者が仕事への意気込みを持っているか確認しようとしています。
内容の分かりやすさ
エントリーシートでは、「自分の言いたいことを分かりやすく伝える力」「社会人として基本的な文章能力」があるかどうかも見られています。
メールや文書など、文章によるコミュニケーションが不可欠であるビジネスシーンにおいては、相手に分かりやすく伝える「伝達力」が重視されます。内容が不足していたり不明瞭だったりする場合、誤解やトラブルの原因になり得ます。
エントリーシートを提出する前に、質問に対して的確な回答ができているか、質問の意図が理解できているか、という視点で確認しましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
エントリーシートの内容についてのキャリアアドバイザーのアドバイス
エントリーシートの内容を考えるとき一番気を付けるのは、「書類選考で見られているポイントを理解すること」です。
ただ自分のアピールしたいポイントを述べるのがエントリーシートではありません。企業が求めていることを満たしているかどうか判断するために提出するので、目的を理解せず内容を考えてしまうのはNGです。まずは「エントリーシートを提出する理由や目的」を把握することから始めましょう。
また、企業が採用時に見ているのは、大きく分けて「カルチャーマッチしているか」「求める能力があるか」の2つです。つまり、自分が上記を満たしていることをアピールするのがエントリーシートです。
マッチ度や求められている能力を記載するためには、「会社のことを知る」からスタートする必要があります。会社について理解していなければ、どんなカルチャーなのか、どんな能力を求めているかが分からないでしょう。企業によって文化や求める人材は異なるので、すべての企業に同じエントリーシートで提出するのはもってのほか!しっかりと企業研究を行い、企業ごとに内容を変えるのがポイントですよ。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
好印象を与えるエントリーシートの書き方のコツ6選
ここでは、エントリーシートで効果的にアピールする書き方のコツを6つ解説します。
1.自己分析で自分のアピールポイントを言語化する
まずは、自己分析で自己理解を深め、アピールポイントを見極めて言語化しましょう。自分のアピールポイントを具体的に言語化しておけば、複数の企業にエントリーする際も役立ちます。
アピールポイントを見つけるには、以下のような点に着目して、これまでの人生を振り返ってみてください。
・チャレンジした経験
・成功した経験
・挫折した経験
・熱中したこと など
単にやってきたことを振り返るのではなく、5W1Hに沿って深掘りしていくと具体的に言語化できるためおすすめです。なお、5W1Hは以下の要素で構成されています。
| 5W | ・When:いつの出来事か ・Where:どのような場所で起こったことか ・Who:誰が関わったのか ・What:何を行ったのか、何を得たのか、何を感じたのか ・Why:なぜ取り組んだのか、なぜ考えたのか |
| 1H | How:どのように取り組んだのか |
要素に沿って言語化すれば経験を具体化できるため、相手に伝わりやすくなります。エピソードごとに共通する要素や考え方が出てきたら、アピールポイントにつながる可能性が高いです。
自己分析では、モチベーショングラフを作成するのもおすすめです。「自己分析に役立つモチベーショングラフとは?作成のコツや活用方法を解説」で詳しい分析方法を紹介しているので、ご覧ください。
2.業界・企業研究で応募企業についての理解を深める
就活のエントリーシートを書く際は、業界や企業研究を行い、応募先の事業・仕事内容などを理解しておくことも重要です。同業他社との違いや応募先の特徴に触れることで、「企業研究がしっかりできている」「自社への入社意欲が高い」という高評価につながります。
業界研究については「就活生が知っておくべき業界を紹介!絞り方のコツや方法も解説」の記事を参考にしてみてください。
また、会社説明会やインターンシップに参加したり、OB・OG訪問を行ったりして、社員に直接話を聞くことも企業研究に役立ちます。
3.結論から述べて文章を構造的に組み立てる
就活のエントリーシートで好印象を与えるために、結論から伝える構成を意識して作成しましょう。
最も伝えたい内容を先に書けば、これから何について述べるのかが明確になります。また、結論を述べてから根拠を説明すれば、主張を裏づけでき説得力が増すのでおすすめです。
採用担当者は多くのエントリーシートをチェックしているので、一つひとつの内容をじっくり読まないケースも少なくありません。内容を構造的に組み立てて簡潔かつ分かりやすいエントリーシートを作成すれば、採用担当者の目に留まり好印象を持ってもらえる可能性が高まります。
このような論理的な伝え方の展開方法をPREP法といい、自分の考えをうまく伝えられず悩む人は、応募書類の作成や面接などで積極的に活用してみてください。
・Point(結論)
・Reason(理由)
・Example(具体例)
・Point(まとめの結論)
ビジネスの現場で用いられる場合が多く、限られた時間の中で仕事の報告やプレゼンテーションを行う際、PREP法を活用すれば伝えたいことを簡潔に述べられます。
また、テンプレートとして活用できるため、文章を書くのが苦手な場合も、構成に当てはめれば簡単にエントリーシートを作成できるでしょう。
4.具体的なエピソードや結果を伝え説得力を持たせる
エントリーシートの自己PRや志望動機欄のエピソードは、できる限り具体性を持たせることが重要です。立てた目標や、その目標に向かって工夫・努力したこと、その結果何を得たのかなど詳しく伝えることで、相手にイメージしてもらいやすくなります。
また、より説得力のある内容にするには、成果や結果に関する具体的な数字を盛り込むことが効果的です。
5.文体の整合性を保つ
就活のエントリーシートは語尾の文体を整えることも重要です。文体に整合性がない場合、文章にまとまりがなく読みにくい印象を与えてしまいます。
なお、エントリーシートを記入する際、「です・ます調」「である調」のどちらを使用しても問題ありませんが、丁寧に見える「です・ます調」がおすすめです。「である調」は自信のある印象を持たせられますが、書き方によっては高圧的に捉えられるケースがあります。
エントリーシートの文章ルールについては、「ESの語尾は「ですます調」がおすすめ!文章ルールを意識した書き方を解説」の記事を参考にしてみてください。
6.誰が読んでも分かる言葉を使う
就活のエントリーシートでは、専門用語や略語を使用するのは避けましょう。応募する職種を専門とする人がチェックするとは限らないからです。
特に、研究職や専門職の場合、自分の能力・スキルをアピールするために専門的な用語を使用したくなる場合があるかもしれません。しかし、アピールしたいことを読み手が理解できなければ選考を通過しにくいため、誰が読んでも分かるような言葉や表現を選びましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活のエントリーシート作成の注意点
ここでは、就活のエントリーシートの作成の際に、注意しておくべき点について説明します。選考突破を目指すためにも、しっかり確認しておきましょう。
話し言葉など公式な書類に合わない表現を使わない
就活のエントリーシートを記入する際は、話し言葉や絵文字などの使用は避けましょう。ビジネス文書やメールなどでは書き言葉を使用するため、普段の会話で使っているような話し言葉が多い文章は、稚拙な印象を与えかねません。
たとえば、以下のような言葉が話し言葉として挙げられます。
・~なので、~だから
・決めれる(ら抜き)
・書き途中(略語)
・ちゃんと、もっと(カジュアルな表現)
・一番最初に(二重表現)
「社会人としてのマナーを備えている」と採用担当者に思ってもらうためにも、エントリーシートなどの選考書類を書く際は言葉遣いや表現が適切かチェックしてください。
空白が大きくならないように注意する
一般的に、エントリーシートに記入する各項目の文章量は8~9割が目安とされています。文字数制限や枠の大きさによりますが、基本的に300~500文字を目指して文章を書くとよいでしょう。
文字数が少ないと空白も多くなり、志望度が低いと判断される可能性もあるので注意が必要です。
企業ごとに内容を変える
就活のエントリーシートの内容は、企業ごとに変えるのが基本です。多くの企業に応募する場合、エントリーシートの作成にも労力や時間がかかります。その中で、ほかの応募先に提出したエントリーシートの内容を使い回したくなることもあるでしょう。
しかし、面倒だから、時間がないからといって内容を使い回すのは危険です。企業が変われば、求める人材や応募先の強み・特徴も異なります。
また、職種によっても求められる能力なども異なるため、エントリーシートの内容を使い回してしまうと、ズレたアピールになりかねません。エントリーシートで落ちないために、自己PRや志望動機は応募先に合わせた内容に整えましょう。
丁寧さを心がけて書く
就活のエントリーシートでは、内容だけでなく書き方の丁寧さも重要です。エントリーシートに記載した文字の丁寧さや言葉遣いから、社会人としてのマナーも評価されています。
応募者が多い企業の担当者は短期間に大量のエントリーシートに目を通すため、字や文章が雑だったり汚れがあったりすると印象を下げかねません。
また、摩擦で消えるボールペンも使用しないようにしましょう。たとえ丁寧に書いたとしても、記載した内容が消えてしまう恐れや、「マナーがなっていない」と採用担当者に捉えられてしまいます。エントリーシートで落ちないためにも、細かな点まで気を配り丁寧に作成しましょう。
待遇などについては記述しない
就活のエントリーシートを記載する際は、待遇面については触れないようにしましょう。
たとえば、「給料が高いから」「福利厚生が手厚いから」ということを志望理由にしてしまうと、「同じ条件なら他社でもよいのでは」「待遇面が悪くなるとすぐ退職するのでは」と採用担当者に懸念されかねません。
エントリーシートの志望動機で待遇面に触れることに関しては、「志望動機で給料に触れるのはNG?伝え方のコツや例文を解説」の記事でも紹介しているので読んでみてください。
第三者に添削してもらう
就活のエントリーシートを書き終えたら、第三者にもチェックしてもらうことをおすすめします。
自分で読み返すことはもちろん必要ですが、第三者にチェックしてもらうことで、自分では気付かなかった間違いに気付ける可能性が高まり、より確実性が増します。家族や先輩、また、大学のキャリアセンタースタッフや就活エージェントなど、プロに添削してもらうのもおすすめです。
エントリーシートの添削については。「【実際のESをプロが添削!ES書き方講座#8】~Sさん自己PR:ゼミ編~」の記事を参考にしてみてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活におけるエントリーシートの項目別の例文
ここでは、就活のエントリーシートの項目ごとに例文を紹介します。就活のエントリーシートは、自分が書いた内容を例文などと比較して、客観的に確認することが大切です。
志望動機の例文
私が貴社を志望した理由は「廃棄されるものを工夫して新しいものを生み出す」という理念に共感したからです。現代の社会では、食品や衣服などの大量生産・廃棄が後を絶ちません。
私は大学1年次から一人暮らしをしていますが、「もったいない精神」で負のサイクルを自分から止めるべく、食品を購入する際は賞味期限が近いものを選んだり、自身や友人の衣類をリメイクして着用したりするなどの工夫をしています。
より大きな活動に取り組みたいと考え始めた大学2年次に、報道番組で配信された貴社のインタビューを拝見し、捨てられる予定の衣類をリユースする技術に感銘を受けました。
貴社に入社後は、リユース製品の企画職としてアイディアを出し、より多くのお客様に製品を届けたいと考えております。
自己PRの例文
私の強みは、どのような環境にも溶け込める順応力です。私は大学時代、居酒屋のアルバイトをしておりました。複数の店舗を運営していたため、出勤日の2分の1は配属店以外の店舗の応援に行っておりました。
大学2年の頃、スタッフ間のコミュニケーションが薄く、応援に行っても歓迎されない店舗がありました。
しかし、お客様に気持ちよく利用してもらうためにもコミュニケーションが大切だと考え、自分からスタッフとの会話や細やかなサポートを積極的に行っていたところ、「△△さんが応援に来てから、コミュニケーションの機会が増えて雰囲気がよくなった」と店長からお褒めの言葉をいただけました。
貴社に入社後も、持ち前の順応力で職場に馴染み、円滑なコミュニケーションで業務をスムーズに遂行するよう努めて参ります。
ガクチカの例文
私が学生時代に最も力を注いだのは、ゼミの活動です。所属していたゼミでは事業者と連携を取り、地域の困りごとを解決するための統計調査を行っておりました。
大学3年次には、大学の所在地である△△市で、1週間かけて大規模なアンケート調査を行うことになりました。しかし、チームを編成して担当地域を決めたものの、私のチームが管轄するオフィス街では、アンケートに回答する時間がないと断られるケースが多発しました。
そこで、周辺の飲食店にアンケートのQRコードつきのポップを置いてもらうよう工夫したところ、回答を集めることに成功しました。
この経験から、相手の状況を理解してどのような行動を取るか想定することで、課題の解決につながると学びました。入社後も、課題を正面のみで捉えず多面的に見て解決方法を見つけ、貴社の発展に貢献して参ります。
インターンシップにエントリーする際の例文
私は今回のインターンシップで、広報の実務体験を通じて仕事への理解を深めたいと思ったため応募いたしました。
広報の仕事は企業をPRする華やかなイメージを持っておりましたが、地道な取り組みが必要だとOBから教えていただきました。そのため、広報職で活躍するために必要なスキルも把握したいと考えております。
インターンシップで実際に広報職の仕事内容を経験し、理解度を深めて自分が働くイメージを掴み、貴社への志望度を高める所存です。
インターンシップの志望動機を効果的に作成したい人は「「インターンシップに期待すること」をESや面接で答える方法と例文を解説」を参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
エントリーシートを企業に提出する際の確認ポイント
ここでは、Webまたは郵送でエントリーシートを提出する前に確認しておきたいポイントを解説します。ぜひエントリーシート提出前のチェックリストとして活用してください。
就活のエントリーシートをWeb上で提出する場合
Web上でエントリーシートを送信する前には、フォントの統一や写真のサイズが適切かなどを確認しましょう。具体的な確認点は以下の通りです。
・記入漏れがないか
・変換による誤字、脱字はないか
・フォントや文字の大きさは揃っているか
・指定の要領に沿って書けているか
・日付や名称の書き方、言葉遣いは適切か
・証明写真を送付する場合、サイズは適切か
・送信する内容を控えたか
Webエントリーシートの場合、確認前に送信ボタンを押してしまったという失敗を避けるためにも、ひと呼吸置いてから作業することをおすすめします。
就活のエントリーシートを郵送で提出する場合
就活のエントリーシートを郵送で送付する際は、読みづらい部分がないかや控えを取っているかなどをチェックしてください。具体的には、以下に着目して確認しましょう。
・記入漏れや不足がないか
・誤字や脱字、読みづらい部分はないか
・指定の要領に沿って書けているか
・日付や名称の書き方、言葉遣いは適切か
・証明写真のサイズは適切か
・証明写真は裏面に氏名などを書き、しっかり貼り付けられているか
・押印が必要な場合は忘れていないか
・使用した筆記具は適切か
・修正液や修正テープを使用していないか
・作成したエントリーシートの控えを取っているか
投函してから「間違えたかもしれない」と後悔しないように、入念に確認したうえで封筒を閉じるのがおすすめです。
就活のエントリーシートを郵送する際のマナーを知りたい人は「エントリーシートを封筒で送る際のマナーは?書き方や郵送方法を解説」を参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活のエントリーシートの書き方で悩むあなたへ
就活のエントリーシートは、就活生の人柄や入社意欲などを企業がチェックするための選考書類です。企業によってエントリーシートの様式は異なりますが、志望動機や自己PRなど共通している項目があります。
エントリーシートに記載する際は自分のアピールポイントを言語化し、効果的な構成や具体的なエピソードを用いて説得力を持たせましょう。
就活のエントリーシートを効果的に書けているかや、内容に不備がないか不安な人は、就活エージェントであるキャリアチケットを利用してみるのがおすすめです。
キャリアチケットでは、エントリーシートの書き方から面接対策まで、一貫したサポートを行っています。慣れない就活で発生するさまざまな悩みについてのアドバイスもできるため、ぜひ気軽に相談してください。
効果的な就活のエントリーシートで選考を通過し、幸先のよいスタートを切りましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら