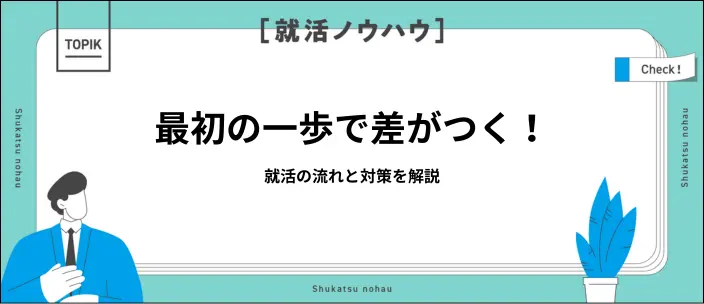このページのまとめ
- 就活生のプレエントリー数の平均は24社程度
- エントリーの定義に注意、実際に選考に進んでいるのは平均13社程度
- 就活の軸を正しく意識してエントリーを進めることは、面接の通過率アップにも役立つ

企業へのエントリー数は多いほうが良いのか少ないほうが良いのか、悩んでいませんか?このコラムでは、就活生のエントリー数の平均や、エントリー数が多い場合と少ない場合のメリット・デメリットなどを解説します。さらに、エントリーを進めるうえでの注意点も併せて解説します。これからエントリーをする人、選考中の企業が減って不安になってきた人は、ぜひ参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
プレエントリー数と選考に進む企業数の平均は何社?
就活には、エントリーの前段階の「プレエントリー」というものがあります。
プレエントリーは、興味のある企業に名前や住所、連絡先などの個人情報を登録し、説明会の案内や資料などを受け取れるようにすることです。
プレエントリー後に送られてきた資料を見たり、説明会に参加したりして企業への理解を深めていくため、本エントリー数は絞られていきます。
そのため、まずはプレエントリー数の平均から見ていきましょう。
プレエントリー数の平均は24社程度
のプレエントリー数の平均は、24社程度といわれています。プレエントリー数は年々減少傾向にあり、この段階である程度企業を絞り込んでいる就活生が多いようです。
実際に書類選考に進んだ数の平均は13社程度
就活生が実際に書類選考まで進んだ企業数の平均は、13社程度といわれています。プレエントリー数の平均と比較すると、半数程度に絞り込まれているのが分かります。
関連記事
エントリー数が不安な就活生必見!平均値やスケジュール管理方法を解説
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
エントリー数に正解はある?
エントリー数は何社が正解なのか、明確な正解はありません。ただし、エントリー数を考えるうえでの注意点として、内定までにかかる時間、就活状況に合わせた就活の進め方の2点をしっかりと押さえておくべきでしょう。それぞれ詳しく解説していきます。
1.内定までにかかる時間
内定までにかかる時間は1社あたり最低13時間、仮に20社エントリーすると、自己分析などの時間を含め最低でも400時間かかるといわれています。
また、就活にかかる時間のなかで、「選考や説明会そのものにかかる時間」よりも「自己分析や企業分析などの準備の時間」のほうが多いです。無造作にエントリーをしてしまうと、準備の時間を多く確保できないため、面接に行く時間はあっても十分な準備ができないでしょう。「自分は就活に何時間使えるのか」を事前に考えたうえで、エントリー数を考えて行くことが大切です。
たとえば週に3日ほど大学の講義に出ながら、ほかの時間を最大限就活にあてたとして、十分に選考対策ができる企業数の限界は5~6社といわれています。
2.就活状況に合わせた就活の進め方
エントリー数は志望する業界や企業、選考通過状況に合わせて調整すると良いでしょう。
希望する企業・業界が絞りきれていない時期は多めにエントリー
希望する企業や業界を絞りきれていない人は、ある程度就活の軸を定めたら、まずは企業数を絞り過ぎずに幅広くエントリーしましょう。
エントリーしたからといって、全ての企業の選考に進まなければいけないという決まりはありません。そのため、まずは自分の軸にあった企業を見つけることや、就活軸を具体化することを目的に少し多めにエントリーしましょう。
多めにといっても、やみくもにエントリーする必要はありません。就活にかかる時間をおさえたうえで、無理のない範囲でエントリーをしましょう。
1次・2次面接に通過したらエントリー数を絞る
1次・2次面接に通過した企業が出てきて、自分の軸や適性にあう企業が明確になってきたら、エントリー数を少しずつ絞りましょう。エントリーする企業を絞ればその分1つひとつをしっかり深堀りでき、志望動機や自己PRにも説得力を持たせられます。
また、最終選考段階まで進んでくると、エントリー数が多いことや複数の業界を見ていることは「志望度が低いのでは」と面接官に思われてしまい、かえって不利になることも。選考中の企業が最終段階まで進んできたら、今受けている企業に明確な優先順位をつけていきましょう。
関連記事
「エントリー」にはどんな意味がある?就活をスムーズに進めるには
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
エントリー数が多い場合、少ない場合のメリットとデメリット
エントリー数には「何社」と正解があるわけではなく、正しく注意点をおさえた上で自分の状況に合わせて考えていく必要があります。
ここでは、エントリー数が多い場合と少ない場合のそれぞれのメリットとデメリットを解説するので、参考にしてください。
エントリー数が多い場合
エントリー数が多い場合のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
メリット
エントリー数を多くすると、その分多くの企業や業界を知ることになるため、視野や選択肢が広がるでしょう。さまざまな企業の説明会に参加したり、選考を受けたりしていく中で、隠れ優良企業の発見に繋がる可能性もあります。
デメリット
エントリー数が多い場合のデメリットは、企業ごとのスケジュールが管理しにくくなることです。エントリー後は説明会への参加やエントリーシート提出、選考の対策など、やるべきことが多々あり、それらのスケジュールをすべて把握してこなさなければいけません。
また、1つひとつの企業に割ける時間や労力が限られてしまい、対策がなおざりになってしまう恐れもあります。
エントリー数が少ない場合
エントリー数が少ない場合、下記のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
エントリー数が少なければスケジュールに余裕ができ、1社1社の就活にじっくり取り組めます。企業研究や選考対策などを念入りに行えるため、企業への理解を深めることができ、選考本番も万全の状態で臨めるでしょう。
デメリット
エントリー数が少ない場合のデメリットは、万が一のための持ち駒が少なくなってしまうことです。そのため、選考にすべて落ちてしまった、説明会や選考の過程でミスマッチを感じたという場合に就活が行き詰まってしまう可能性もあります。
関連記事
就活のエントリーは平均何社?多ければ多いほど良いわけではない?
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
エントリーで失敗しないための3つの対策を解説
「スケジュール管理が思うようにできない」「ミスマッチばかりで意欲が下がる」など、エントリーでの失敗を防ぐための対策を3つご紹介します。
1.自分の「就活の軸」に沿った企業・業界を選ぶ
闇雲にエントリーするのではなく、自分の「就活の軸」に沿った企業や業界を選びましょう。たとえば、「接客のアルバイト経験を活かしたい」「人を楽しませる仕事がしたい」「社会貢献がしたい」というように、ある程度絞り込むと良いでしょう。
2.手帳と端末を活用してスケジュール管理
就活のスケジュール管理には、スマートフォンやタブレットなどの端末と手帳を活用しましょう。
端末と併用しやすいよう、手帳はカバンやポケットに入れて持ち運べるサイズのものがおすすめです。端末でのスケジュール管理はアプリを使用しましょう。検索機能がついているのもや、予定がある日をリスト化できるものだと、スケジュール確認が素早くできて便利です。
3.就活エージェントやキャリアセンターを活用する
一人で志望先を絞るのが難しいと感じているなら、就職エージェントやキャリアセンターなど、就活に詳しい第三者がいる機関を活用しましょう。
求人の紹介やセミナー、面接対策など、就活に関するサポートを受けられます。
悩み事も聞いてくれるので、「就活がうまくいかない…」と感じたときも気軽に相談できるでしょう。
就活エージェントの場合、進路がはっきり決まっていなくてもマンツーマンでカウンセリングや自己分析のフォローをしてくれます。
関連記事
【21卒 就活お悩み相談室 #6】優良企業に入りたい!どうやって探せばいいですか?
就活の開始時期はいつ?選考スケジュールと解禁前にやるべきことを解説!

本記事の執筆者
村上明日香(むらかみあすか)
大学3年生の秋に大手・ベンチャーともに複数内定を獲得し、レバレジーズ株式会社に新卒入社。インターン時代から就活セミナーの企画運営に携わり、1年目から支店の立ち上げのメンバーとして関西を中心に延べ1000名以上の就活支援に携わる。入社3年目の現在は新入社員向けの研修企画や育成業務を担当している。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら