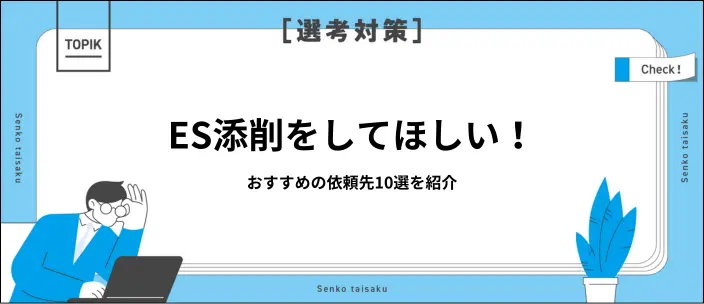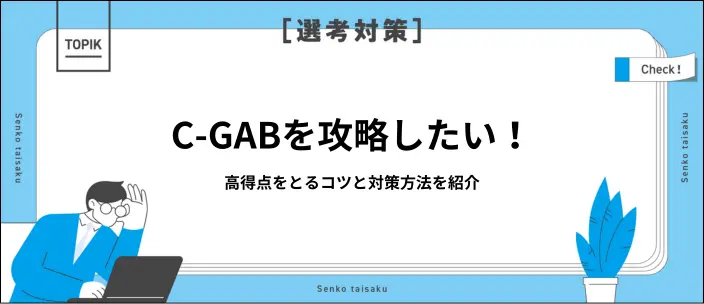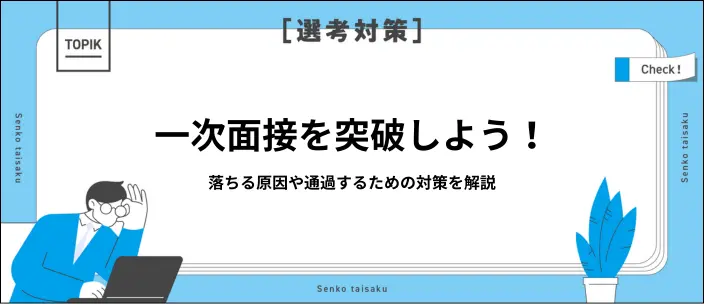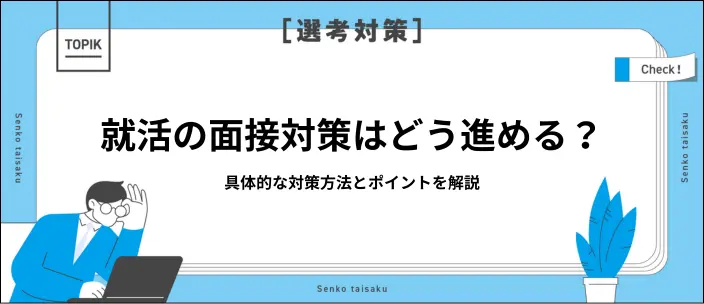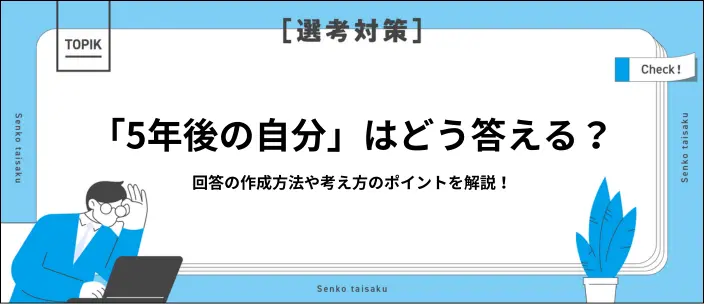このページのまとめ
- 早期選考は自己分析と企業研究が十分で、目的が明確な場合に挑戦するのがベスト
- 早期選考を受ける際は3~5社程度に絞り、本気で合格を目指して準備することが大切
- 早期選考を受ける場合は、夏休みから準備を始めて十分な対策時間を確保しよう
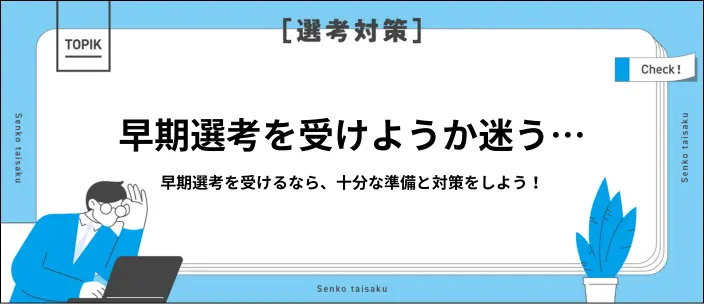
就活生の中には、早期選考を受けるべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。早期選考は一般選考より早い時期から始まるため、十分な準備が必要不可欠です。一方、早期に内定を獲得できるチャンスでもあり、就活を効率的に進められる可能性もあります。
本記事では、早期選考のメリット・デメリットや判断基準、準備のポイントなどを詳しく解説。早期選考を検討している方は、参考にしてください。
かんたん1分!無料登録早期選考の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- そもそも早期選考とは?
- 早期選考と一般選考の違い
- 早期選考を行っている企業や業界の傾向は?
- 早期選考のスケジュール
- 早期選考の合格率は?受かりやすいってホント?
- 早期選考を受けるべきか悩む人向けの3つの判断基準
- 1.準備期間を十分に確保できるか
- 2.自己分析や企業研究は深掘りできているか
- 3.早期選考を受ける目的は明確か
- 早期選考を受けるべき?メリットとデメリットを解説
- 早期選考のメリット
- 早期選考のデメリット
- 企業が早期選考を行う理由
- 早期選考はどうやって受ける?5つの見つけ方
- 1.インターンシップに参加する
- 2.早期選考イベントに参加する
- 3.逆求人サイトに登録する
- 4.就活エージェントを活用する
- 5.SNSをチェックする
- 準備不足を防ぐ!早期選考に向けた対策
- 自己分析を深める
- 企業や業界について情報収集を徹底する
- 模擬面接をする
- 早期選考を受けるべきか迷っている方へ
- 早期選考に関するよくある質問
- 早期選考はいつから始まる?
- 早期選考は何社受けるべき?
- 早期選考の内定は辞退できる?
そもそも早期選考とは?
早期選考とは、一般的な就活スケジュールよりも早い時期に実施される選考のことを指します。
早期選考は3月よりも前に選考が開始され、主に前年の秋から冬の時期にスタートするのが一般的です。学生にとっては、早期選考は早めに内定を獲得できるチャンスとなります。
早期選考と一般選考の違い
早期選考と一般選考には、実施時期以外にもいくつか違いがあります。一般選考よりも選考のフローが短縮されていたり、より丁寧な面接が行われたりすることが主な特徴です。また、一般選考よりも募集人数が少なく、募集方法も限定的な傾向があります。
一方で、一般選考は人材を広く募集している分、競争率が高めです。
下記の表に主な違いをまとめているので、早期選考を検討する際の参考にしてください。
| 早期選考 | 一般選考 | |
| 選考開始時期 | 前年の秋~冬 | 3月以降から |
| 選考フロー | 筆記試験や書類選考など、一部のフローが免除され簡略化されている | 書類選考から面接までフローに沿って行う |
| 募集範囲 | 限定的で少人数 | 広く募集 |
早期選考を行っている企業や業界の傾向は?
早期選考は、優秀な人材の獲得に力を入れている大手企業や、成長産業に属する企業が積極的に実施している傾向にあります。
業界としては、IT業界やコンサルティング業界、金融業界などが代表的です。これらの業界では人材の質が企業の競争力に直結するため、早期から採用活動を展開する傾向があります。また、ベンチャー企業や外資系企業なども、人材確保のための戦略として早期選考を実施するケースがあるようです。
早期選考のスケジュール
早期選考のスケジュールは企業によって異なりますが、一般的には前年の秋~冬に開始されるため、遅くとも前年の12月から準備を始めたほうが良いでしょう。
早期選考の主な流れとしては、以下のとおりです。
・10月~12月:早期選考開始、企業研究・自己分析
・1月~2月:ES提出、適性検査
・2月~3月:面接
・3月~:内定
ただし、企業によってはさらに早い時期から選考を開始する場合もあるため、志望企業の採用スケジュールはよく確認しておきましょう。
選考の準備を適切に行うために、一般的な就活の流れややり方も把握しておくと安心です。「就活のやり方と流れを解説!準備から内定までのポイントと相談先も紹介」の記事で、就活の流れや必要な準備などを解説しています。
かんたん1分!無料登録早期選考の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
早期選考の合格率は?受かりやすいってホント?
早期選考は応募者数が比較的少ないため、一般選考と比べて合格率は若干高めになる傾向にあります。ただし、一般選考より合格率が高めでも、「受かりやすい」というわけではないことを念頭に置きましょう。
企業側は早期選考において、志望動機の明確さや業界への理解度、コミュニケーション能力などを重点的に評価します。一般選考よりも早期に開始する分、早い段階から就活の準備を進め、十分な企業研究や自己分析が必要です。
準備を怠らず、自分の強みを明確に伝えられる状態で臨めば、早期選考での内定獲得の可能性が高まるでしょう。
早期選考の合格率については、「早期選考は受かりやすい?7つの対策で内定獲得を目指そう!」の記事でも触れています。こちらもあわせてご一読ください。
かんたん1分!無料登録早期選考の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
早期選考を受けるべきか悩む人向けの3つの判断基準
早期選考を受けるかを決める前に、自分の状況を客観的に確認することが大切です。ここでは、早期選考に挑戦すべきかどうかを判断するための3つの基準を紹介します。
1.準備期間を十分に確保できるか
早期選考では、一般選考より早い時期から準備を始める必要があります。そのため、サークル活動やアルバイトなどの予定も考慮しつつ、就活と学業の両立が可能かどうか、しっかりと検討しましょう。
準備期間の確保が難しい場合は、一般選考に向けてじっくりと対策することも賢明な選択です。焦って不十分な状態で早期選考に臨むより、自分のペースで着実に準備を進めたほうが、自分が納得できる結果につながるでしょう。
2.自己分析や企業研究は深掘りできているか
早期選考では、志望企業についての理解度や自己分析の深さが重視されるポイントです。自分の長所・短所、学生時代に力を入れたこと、将来のキャリアプランなどを明確にできているかが、早期選考を受けるべきか判断する際の材料となります。
企業研究については、業界動向や企業の特徴、求める人材像などの深い理解が必要です。表面的な情報収集だけでなく、企業の課題や将来性まで考察できている状態が望ましいでしょう。
これらの準備が不十分な場合は、一般選考も視野に入れることをおすすめします。
自己分析のやり方については、「自己分析のやり方おすすめ10選!正しく長所を理解するコツも解説」の記事もあわせてご覧ください。
3.早期選考を受ける目的は明確か
早期選考に挑戦する際は、「なぜ早期選考を受けたいのか」「なぜその企業で働きたいのか」が明確になっていることが大切です。「周りが受けているから」「とりあえず経験として」といった消極的な理由だけの場合は、早期選考は避けたほうが良いでしょう。
たとえば、「この企業の事業に強く共感している」「早期に内定を得て、残りの学生生活を有意義に過ごしたい」といった前向きな理由づけが必要です。目的が明確でない場合、面接で自分の想いを上手く伝えられない可能性もあるでしょう。
自分の目的や意志をしっかりと確認し、早期選考に挑戦する価値があるかどうかの見極めが大切です。
上記で解説した基準を満たしていない場合は、一般選考に向けてじっくりと準備を進めることも選択肢の一つとして考えてみましょう。
かんたん1分!無料登録早期選考の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
早期選考を受けるべき?メリットとデメリットを解説
ここでは、早期選考のメリットとデメリットを詳しく解説します。以下を踏まえたうえで、早期選考を受けるべきか検討してみましょう。
早期選考のメリット
早期選考には、就活生にとって複数のメリットがあります。内定を早期に獲得できる可能性があるだけでなく、就活スキルの向上にもつながるでしょう。
就活が早めに終わるので学生生活を有意義に過ごせる
早期選考で内定を獲得できれば、残りの学生生活を有意義に過ごせます。資格取得や卒業研究に注力したり、興味のある分野の勉強を深めたりする時間が確保できるでしょう。また、精神的な余裕も生まれ、充実した状態で卒業を迎えられる可能性があります。
本選考の練習機会になる
早期選考は、一般選考の前に面接やESの作成を経験できる貴重な機会にもなります。早期選考では不合格になったとしても、その経験を一般選考に活かせば、成長につながるでしょう。ひと足先に実際の選考を経験することで、企業が求める人物像や面接での受け答えのコツなどを掴めます。
自身の課題点を早めに見つけられる
早期選考を通じて、自分の強みや弱みを早い段階で把握できます。面接官からのフィードバックや、選考過程での気づきを通じて、改善すべき点が明確になるでしょう。
たとえば、業界に関する知識の不足に気付いたり、自己アピールの課題が分かったりするかもしれません。これらの課題を一般選考までに克服できれば、より良い結果につながる可能性が高まります。
心にゆとりをもてる
早期選考で内定を獲得すると、精神的な余裕が生まれます。就活に対する不安や焦りから解放され、落ち着いた気持ちで残りの学生生活を送れるでしょう。
また、一般選考を受ける際も、すでに内定を獲得しているという安心感から、リラックスして臨めます。余裕をもって自分の考えを伝えられるため、より良いパフォーマンスを発揮できる可能性が高まるでしょう。
内定が早期に決まるメリットについては、「就活を楽に終わらせる方法は?早期内定のメリットや難航する 原因を解説」の記事でも解説しています。
早期選考のデメリット
早期選考にはメリットだけでなく、注意すべき点もあります。以下で紹介するデメリットを理解したうえで、早期選考を受けるべきかを慎重に判断することが賢明です。
準備期間が短い
早期選考は、一般選考より早い時期に始まるため、自己分析や企業研究などの準備に充てられる時間が限られてしまうでしょう。特に一般的に早期選考が始まるとされる3年生の秋から冬にかけては、テストやレポートなどの学業も考慮しなければなりません。
限られた時間で十分な準備ができない場合、面接での受け答えが浅くなったり、志望動機が不明確になったりするリスクがあります。そのため、時間管理を徹底し、効率的に準備を進める必要があるでしょう。
本選考に影響が出る可能性がある
早期選考で不合格となった場合、同じ企業の一般選考に応募しづらくなる場合があります。また、早期選考での不合格が精神的なダメージとなり、その後の就活にマイナスの影響を与えてしまう可能性もあるでしょう。
このようなリスクを軽減するためには、早期選考を一般専攻のための練習と位置付けるのではなく、本気で合格を目指して準備することが重要です。
オワハラを受ける恐れもある
早期選考で内定を獲得した場合、企業から他社の選考を辞退するよう圧力を掛ける「オワハラ(就活終われハラスメント)」を受けるリスクもあります。
オワハラは正当性がなく、学生の就職の自由を妨げる行為です。企業から理不尽な要求を受けた場合は、毅然とした態度で断りましょう。また、大学のキャリアセンターや就職課に相談するなど、適切な対応も大切です。
オワハラについては、「知っておきたい!オワハラの意味と実態」の記事で詳しく解説しているので、不安な方はこちらも参考にしてください。
上記で紹介したデメリットは、十分な対策と心構えがあれば、ある程度回避することが可能です。早期選考に参加する際は、メリットとデメリットの両方を理解したうえで、自分なりの対応策を考えておくことをおすすめします。
かんたん1分!無料登録早期選考の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
企業が早期選考を行う理由
企業が早期選考を実施する主な目的は、優秀な人材を他社に先駆けて確保するためです。特に人材獲得の競争が激しい業界では、早い段階での採用活動が、良質な人材と出会う機会を増やすことにつながります。
また、じっくりと時間をかけて学生を評価できるのも、企業にとって魅力的なポイントといえるでしょう。一般選考では多くの応募者を短期間で選定する必要がある一方で、早期選考ではフローが簡略化される分、応募者とじっくり向き合う時間を確保できます。
早期に内定を出す企業については、「内定時期はいつごろ?早期に内定が出る業界や早めにもらうコツを解説」の記事をご覧ください。
かんたん1分!無料登録早期選考の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
早期選考はどうやって受ける?5つの見つけ方
早期選考の情報を入手するには、さまざまな方法があります。ここでは主な5つの方法を紹介するので、早期選考を検討している方はご一読ください。
1.インターンシップに参加する
インターンシップに参加することで、早期選考のチャンスを掴める可能性が高まります。企業によっては夏季や冬季に開催するインターンシップで、参加した学生の中から早期選考の対象者を選定している場合があるからです。
インターンシップでは、企業の実際の業務や社風を体験できるだけでなく、社員との交流を通じて企業への理解を深められます。また、インターンシップでの成果が評価され、そのまま早期選考へと進むこともあるようです。
早期選考を受けたいと考えている方は、「インターンシップは内定に直結する?参加経験を活かす7つのポイントを解説」の記事も参考に、インターンシップへの参加を検討してみましょう。
2.早期選考イベントに参加する
早期選考イベントは、複数の企業と一度に出会える貴重な機会となる場です。このようなイベントでは企業説明会や選考会が開催され、その場で面接に進めるケースもあります。
イベントに参加する際は、事前に参加企業の情報を調べ、興味のある企業についてある程度理解を深めておくことが重要です。また、当日の服装や持ち物にも気を配り、万全の準備をして臨みましょう。
3.逆求人サイトに登録する
逆求人サイトは、学生のプロフィールを企業側が閲覧し、興味をもった学生にアプローチする仕組みのサイトです。早期選考を実施する企業の多くが、逆求人サイトを通じて優秀な人材の発掘を行っています。
プロフィール作成の際は、自己PRや学生時代の経験を具体的に記載しましょう。また、定期的にプロフィールを更新し、常に最新の状態にしておくことをおすすめします。
4.就活エージェントを活用する
早期選考を行っている企業の情報を知りたい場合は、就活エージェントの活用も有効です。就活エージェントに登録すれば、独自の求人情報や選考に関する具体的なアドバイスを受けられるでしょう。
エージェントは学生一人ひとりの希望や適性を把握したうえで、マッチする企業を紹介してくれます。また、面接対策や企業研究のサポートも行っているため、効率的に準備を進められる点も魅力です。ただし、エージェントからの連絡や面談に対応する時間も必要となるため、スケジュール管理は慎重に行いましょう。
5.SNSをチェックする
企業の公式SNSアカウントでは、早期選考に関する情報が発信される場合があります。企業のSNSをフォローしておけば、タイムリーな情報をキャッチできるでしょう。また、投稿内容から企業の雰囲気や文化を知れるため、企業研究の一環としても有効です。
ただし、SNSの情報だけを鵜呑みにせず、企業のWebサイトや就職情報サイトなど、複数の情報源をチェックすることを心掛けましょう。
上記で紹介した方法を組み合わせることで、早期選考を実施している企業をより多く見つけられます。ただし、闇雲に応募するのではなく、自分の興味や適性に合った企業を選ぶことが重要です。また、早期選考の情報収集と並行して、一般選考の準備も進めておくと、より充実した就活につながるでしょう。
かんたん1分!無料登録早期選考の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
準備不足を防ぐ!早期選考に向けた対策
早期選考を成功させるためには、十分な準備が欠かせません。ここでは、早期選考に向けた効果的な準備について解説します。
自己分析を深める
自己分析は、早期選考の対策を行う際の大事な工程です。自分の強みや適性を明確に理解し、志望動機に結びつけることができれば、面接で説得力のある受け答えができます。
自己分析を進める際は、学生時代の経験を時系列で整理することからスタートしましょう。部活動や学業やサークル活動、アルバイトなど、それぞれの経験から得た学びや成長を具体的に書き出していきます。また、家族や友人、教授など、周囲の人に自分の印象を聞いて、新たな気づきが得られることもあるでしょう。
ただし、自己分析に時間をかけ過ぎると、ほかの準備がおろそかになる可能性があります。2週間程度を目安に集中的に取り組み、その後は企業研究や面接対策と並行して適宜ブラッシュアップしていくやり方がおすすめです。自己分析で洗い出した情報は、ESの作成や面接での質疑応答に活用できるため、しっかりとメモを取っておきましょう。
企業や業界について情報収集を徹底する
早期選考を成功につなげるために、企業研究を徹底的に行いましょう。志望企業の事業内容や強み、課題について理解を深めると、志望動機に説得力をもたせられます。
逆求人サイトや就活サイトを活用する
就活サイトには、企業の基本情報から詳細な採用データまで、豊富な情報が掲載されています。企業の売上高や従業員数といった基本情報のほか、福利厚生や社風などの働く環境に関する情報を得ることも可能です。
逆求人サイトでは、スカウトメッセージに企業の求める人物像が反映されている場合が多いため、採用のポイントを押さえる手掛かりになるでしょう。ただし、掲載情報は企業側が発信するものが中心となるため、より客観的な情報を得るためには、複数の媒体をチェックすることが重要です。
OB・OG訪問でリアルな情報を得る
OB・OG訪問は、企業の実態を知る貴重な機会です。実際に働いている先輩社員から、職場の雰囲気や仕事の実情について生の声を聞けます。
訪問する際は、事前に質問事項を整理しておきましょう。給与や休暇などの待遇面だけでなく、やりがいや苦労した点といった具体的なエピソードを聞くことで、より深い企業理解につながります。
模擬面接をする
模擬面接は、本番の面接を想定した実践的な練習ができる有効な手段です。キャリアセンターや就活エージェントに依頼して模擬面接を行えば、第三者からの客観的なフィードバックを得られます。
模擬面接では、質問への回答内容だけでなく、姿勢や話し方、表情なども意識することが大切です。また、想定外の質問にも柔軟に対応できるよう、さまざまなパターンを準備しておきましょう。
友人との練習も効果的ですが、できれば就活経験のある先輩や就活支援の専門家から指導を受けることをおすすめします。プロの視点からのアドバイスを取り入れれば、面接で好印象を与えられるようになるでしょう。
面接対策については、「面接対策の基本を解説!当日の流れ・マナー・よく聞かれる質問13選」の記事でも詳しく解説しています。
かんたん1分!無料登録早期選考の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
早期選考を受けるべきか迷っている方へ
早期選考を受けるかどうかは、自分の状況も踏まえたうえで慎重に検討する必要があります。志望する業界や企業が明確で、十分な準備時間を確保できる場合は、早期選考を成功につなげられる可能性が高いでしょう。
一方で、まだ進路に迷いがある場合や自己分析が不十分な段階では、焦って受ける必要はありません。インターンシップやOB・OG訪問を通じて、じっくりと業界研究を進めていきましょう。
大切なのは、自分の現状と目標を冷静に見つめ直すことです。早期選考は必須ではありません。キャリアセンターや就活エージェントに相談しながら、自分に合った就活の進め方を選択しましょう。
就活エージェントの利用を考えているなら、キャリアチケットに相談してみませんか?キャリアチケットでは、あなたに合った企業の紹介や、企業ごとの選考対策などの就活サポートをマンツーマンで実施しています。選考に関する悩みを抱えている方は、お気軽にお問い合わせください。
かんたん1分!無料登録早期選考の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
早期選考に関するよくある質問
就活生から寄せられる早期選考に関する疑問について、具体的に解説していきます。これらの情報を参考に、効果的な就活計画を立てていきましょう。
早期選考はいつから始まる?
早期選考は、前年の10月から12月にかけて選考を実施する企業が多い傾向にあります。ただし、業界や企業によって開始時期は異なり、夏のインターンシップから早期選考をスタートする企業もあるので、注意が必要です。
早期選考に参加する場合は、3年生の夏休みごろから準備を始めることをおすすめします。この時期から自己分析や企業研究を進めれば、余裕をもって選考に臨むことができるでしょう。
早期選考は何社受けるべき?
適切な応募社数は個人の状況によって異なりますが、3~5社程度を目安にするのがおすすめです。各企業の選考に十分な準備時間を確保しながら、複数の選択肢を持てる数だといえるでしょう。
ただし、闇雲に数を増やすのは避けるのが無難です。早期選考は一般選考と比べて準備に時間を掛けられるメリットがあります。自分が本当に興味を持てる企業を厳選し、それぞれの選考に全力で取り組みましょう。
早期選考の内定は辞退できる?
早期選考での内定も、一般選考と同様に辞退することが可能です。ただし、企業との信頼関係を考慮し、誠実な対応を心掛ける必要があります。
内定を辞退する際は、以下の点に注意しましょう。
・できるだけ早めに決断し、企業に連絡する
・電話で直接伝え、その後メールでも辞退連絡を行う
・辞退理由を明確に説明する
・企業に謝罪と感謝を伝える
なお、内定辞退を検討する場合は、必要に応じて大学のキャリアセンターに相談することをおすすめします。経験豊富な職員から適切なアドバイスを受けることで、円滑に辞退できるでしょう。
かんたん1分!無料登録早期選考の対策について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら