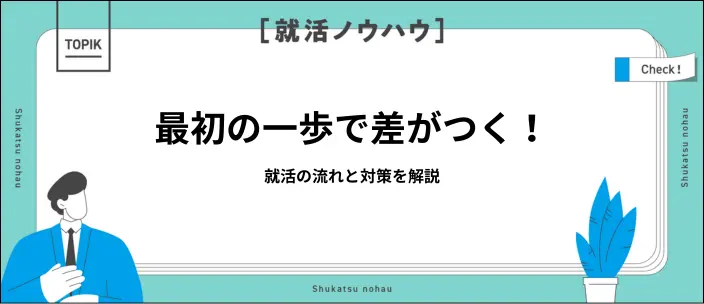このページのまとめ
- 私立大学の学費は年間の授業料で約93万円必要
- 私立大学に通う場合は学費以外にも「入学金」「交通費」「教科書代」などが必要
- 私立大学の学費無償化や奨学金などの制度を活用するのも大事
.jpg)
「私立大学の学費はどれくらい必要?」「年間の授業料はどれくらい?」と気になる方も多いでしょう。私立大学の学費は、国立大学や公立大学と異なるので確認しておくのが大事です。また、私立大学でも、学部ごとに違う点にも気を付けなければなりません。
この記事では、私立大学の学費や奨学金制度について解説しています。学費以外に必要な費用についても紹介しているので、大学進学の参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 私立大学の入学に必要な学費はどれくらい?入学料や授業料を解説
- 入学料は私立大学が安い
- 授業料は私立大学が高い
- 私立大学は学部によって学費が異なる
- 文科系学部は学費が少額な傾向にある
- 理系学部は文化系学部よりも学費が高い傾向にある
- 医歯系学部は入学金も授業料も高額な傾向にある
- 私立大学の学費以外にかかる費用
- 受験料
- 交通費
- 教科書代
- 資格取得
- 海外留学
- 一人暮らしの場合の家賃
- 休学
- 私立大学の学費が無償化対象になる2つの条件
- 1.住民税が非課税世帯およびそれに準ずる学生である
- 2.学ぶ意欲がある
- 私立大学の学費では奨学金制度も活用できる
- 給付型奨学金は返金が必要ないが条件が設定されている
- 貸与型奨学金は返金が必要だが利用しやすい
私立大学の入学に必要な学費はどれくらい?入学料や授業料を解説
文部科学省の調査によると、私立大学の入学金には「245,951円」、授業料には「930,943円」がかかっていると示されています。ここでは、国立大学や公立大学と比較しながら、私立大学の学費について解説するので参考にしてください。
入学料は私立大学が安い
入学料については、国立大学や公立大学に比べて私立大学が安い傾向にあります。文部科学省の「国公私立大学の授業料等の推移」「私立大学等の令和3年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」によると、「私立」「国立」「公立」大学の入学金は、それぞれ次のような金額です。
【入学金】
・私立大学 245,951円(令和3年度)
・国立大学 282,000円(令和元年度)
・公立大学 392,391円(令和元年度)
続いて、授業料についても見てみましょう。
授業料は私立大学が高い
授業料については、私立大学が高い傾向にあります。「国公私立大学の授業料等の推移」「私立大学等の令和3年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」によると、大学の年間授業料は次のとおりです。
【授業料】
・私立大学 930,943円(令和3年度)
・国立大学 535,800円(令和元年度)
・公立大学 538,734円(令和元年度)
私立大学の授業料が高い理由には、施設設備費の影響があるとされています。私立大学の施設設備費は約18万円ほどなのに対し、国立大学は数千円から15万円ほどです。
大学全体で考えた場合、授業料は増加傾向にあります。今後も値上がりする可能性があり、学生や保護者にとって懸念材料になるでしょう。
国公立大学の学費については、「国公立大学の学費はどれくらい?私立との平均額の差や奨学金の種類について」の記事で詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。
参照元
文部科学省
国公私立大学の授業料等の推移
私立大学等の令和3年度入学者に係る学生納付金等調査結果について
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
私立大学は学部によって学費が異なる
私立大学の場合、学部によって学費が異なるので覚えておきましょう。ここでは、それぞれの学部の学費について解説します。
文科系学部は学費が少額な傾向にある
文化系学部の場合、ほかの学部に比べて学費は安い傾向にあります。「私立大学等の令和3年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」によると、令和3年度の学費は次のとおりです。
・授業料:815,069円
・入学料:225,651円
・施設設備費:148,272円
・合計:1,188,991円
また、「理科系学部」「医歯系学部」「その他学部」と比較した表が、以下になります。
| 区分 | 授業料 | 入学料 | 施設設備費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 文化系学部 | 815,069 | 225,651 | 148,272 | 1,188,991 |
| 理科系学部 | 1,136,074 | 251,029 | 179,159 | 1,566,262 |
| 医歯系学部 | 2,882,894 | 1,076,278 | 931,367 | 4,890,539 |
| その他学部 | 969,074 | 254,836 | 235,702 | 1,459,612 |
| 全平均 | 930,943 | 245,951 | 180,186 | 1,357,080 |
引用元:文部科学省「(資料1)令和3年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について(p1)
文化系学部は、「授業料」「入学料」「施設設備費」ともに、ほかの学部と比べると低い状況です。
理系学部は文化系学部よりも学費が高い傾向にある
理系学部の学費は、次のとおりになります。
・授業料:1,136,074円
・入学料:251,029円
・施設設備費:179,159円
・合計:1,566,262円
入学料や施設設備費については、文化系学部とあまり差はありません。しかし、授業料が高額な分、学費が掛かる傾向にあります。
理系の場合、就活の進め方も文系と違うので覚えておきましょう。「多忙な理系学生も無理なくできる!失敗しない就活の進め方」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
医歯系学部は入学金も授業料も高額な傾向にある
最後に医歯系学部学費は次のとおりです。
・授業料:2,882,894円
・入学料:1,076,278円
・施設設備費:931,367円
・合計:4,890,539円
医歯系学部はほかの学部に比べて、「授業料」「入学料」「施設設備費」のすべてでほかの学部よりも金額が上がります。常に進歩する医学を学ぶために、高額な医療機器や薬品を扱うことが要因です。
参照元
文部科学省
(資料1)令和3年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
私立大学の学費以外にかかる費用
私立大学に通う場合、学費以外にも「交通費」「教科書代」「授業料」などが必要になります。大学に通う場合、1年間でどのくらい必要になるかを計算しておく必要があるので、参考にしてください。
受験料
受験料は、大学受験をする場合にかかる費用です。「一般入試」「AO入試」など入試方式に違いはありますが、1校を受けるたびに授業料が必要です。一般的には、次のような金額が必要なのでチェックしておきましょう。
・共通テスト(2教科):12,000円以上
・共通テスト(3教科):18,000円以上
・国立大学二次試験:1校17,000円程度
・私立大学一般入試:1校35,000円程度
また、私立大学の場合、願書の費用で別途1000円程度かかる場合もあります。志望校が遠方にある場合、受験会場までの交通費や宿泊費も必要になるので注意してください。
交通費
大学から家まで離れている場合、交通費も必要です。一般的には週5日、サークルや部活をする場合は土日も通うので、定期券を購入することになるでしょう。
定期券を購入する場合もまとまった金額が必要になるので、年間でどのくらい必要か計算しておくのがおすすめです。
教科書代
大学でも教科書代がかかるので覚えておきましょう。学部ごとや受ける授業によって金額が変わります。
特に、医歯科系で必要とされる医学書は、ほかの教科書に比べ高額です。解剖などの実習費用が必要になるケースも多いので注意してください。
資格取得
資格取得を目指す場合、取得費用が必要です。就活に備えて、取得を目指す人も多いでしょう。
たとえば、「TOEIC」「マイクロソフトオフィススペシャリスト」「ファイナンシャル・プランナー」などの資格が、大学生の取得する資格として一般的です。
大学生におすすめの資格については、「就職に有利な資格11選!取得するときの注意点も解説」の記事で解説しているので、こちらも参考にしてください。
海外留学
海外留学を検討している場合、留学費用も必要になります。現地の学校に通う場合は、追加で授業料を払わなければならないので覚えておきましょう。
学部によっては、留学が必須の場合もあります。入学前に確認し、どのくらいの費用がかかるか計算しておきましょう。
一人暮らしの場合の家賃
一人暮らしをする場合、家賃が掛かります。住む地域にもよりますが、4万円から8万円くらいはかかるでしょう。1年間で少なくとも50万、4年間通うと200万円が必要です。
また、家賃以外にも、食費や光熱費が掛かります。アルバイトをしながら、大学に通うことも視野に入れるといいでしょう。
休学
休学した場合、学費がかかるケースもあるので気を付けてください。
国立大学の場合、休学中の学費は免除になります。しかし、私立大学の場合では、授業料の一部を支払う必要があったり、授業料の変わりに在学費が必要になったりと、学校によってさまざまです。
休学する可能性に備えて、自分の大学や志望校の休学制度を調べておきましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
私立大学の学費が無償化対象になる2つの条件
ここでは、私立大学の学費が無償化対象になる2つの条件を解説します。文部科学省の「高等教育の修学支援新制度」を紹介するので、参考にしてください。
1.住民税が非課税世帯およびそれに準ずる学生である
私立大学の学費が無償化対象になる1つ目の条件が、「住民税が非課税世帯」および「準ずる学生」に該当することです。
文部科学省によると、支援の対象者と支援額は、次のとおりになります。
| 支援対象者 | 年収の目安(両親・本人(18歳)・中学生の家族4人世帯の場合) | 年収の目安(両親・本人(19~22歳)・高校生の家族4人世帯の場合) | 支援額 |
|---|---|---|---|
| 住民税非課税世帯の学生 | ~270万円 | ~300万円 | 満額 |
| 住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生 | ~300万円 | ~400万円 | 満額の2/3 |
| ~380万円 | ~460万円 | 満額の1/3 |
引用元:文部科学省「学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度」
家族形態はさまざまになるので、基準を満たすかどうかは別途確認が必要です。日本学生支援機構のWebサイトでも調べられるので、参考にしてください。
参照元
独立行政法人 日本学生支援機構
進学資金シミュレーター
2.学ぶ意欲がある
制度を受けるためには、学ぶ意欲も求められます。大学入学1年目には、次の要件が設けられているので確認しておきましょう。
高等学校在学時の評定平均値、または学修計画書(学修の意欲や目的、将来の人生設計等を確認)の提出などにより、学修意欲があると認められた人が対象となります。
また、大学入学2年目以降からは、次の要件が求められるので確認してください。
在学中のGPA(平均成績)等、または単位の取得状況と学修計画書(学修の意欲や目的、将来の人生設計等を確認)の提出などにより、学修意欲があると認められた人が対象となります。
大学に入学したから終わりではなく、入学後も勉強を続けるのが大切なので覚えておきましょう。
参照元
文部科学省
学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
私立大学の学費では奨学金制度も活用できる
私立大学の学費では、奨学金制度も活用できます。奨学金制度とは、大学資金の捻出が難しい場合、資金を交付してもらえる制度です。大学だけではなく、国や地方自治体、民間企業なども支援を行っています。
一般的な奨学金制度は、「給付型奨学金」「貸与型奨学金」の2種類です。それぞれについて詳しく解説します。
給付型奨学金は返金が必要ないが条件が設定されている
給付型奨学金とは、返金が必要ない奨学金です。ただし、「家庭の経済状況」「学業の成績」「学生の人格」「取得資格」など、複数の受給条件が設定されています。
交付する機関によって違いはありますが、条件を満たしていれば奨学金を受ける資格をもらえる仕組みです。金額は「国立大学か私立大学か」「自宅からの通学か自宅以外からの通学か」など人によって異なるため、確認しておきましょう
「給付型奨学金」と「授業料・入学金の免除または減額(授業料等減額)」の支援を同時に受ければ、学費をかけずに大学に通えます。
参照元
独立行政法人 日本学生支援機構
給付奨学金(返済不要)
貸与型奨学金は返金が必要だが利用しやすい
貸与型奨学金は、返金が必要な奨学金です。返金は卒業後から始まるのが一般的で、就職後に働きながら分割で返せます。
貸与型奨学金は、給付型奨学金とは違い、多様な受給条件が設定されていない点が特徴です。比較的利用しやすい奨学金といえるでしょう。
また、貸与型奨学金には、借りた金額だけを返金する利息料金がつかない「第一種」と、借りた金額に利息を足して返金する「第二種」の、2つがあります。
利息がない第一種貸与型奨学金は、「成績が特に優れた学生及び生徒で、経済的理由により著しく修学が困難な人」という受給条件があるので覚えておきましょう。利息がある第二種貸与型奨学金は、受給条件の規定が厳しくなく、多くの方が利用し修学を成功させています。
ただし、奨学金の継続的な返済のためには安定した収入が必要です。生活費に加えて、返済金額の確保ができるように、就職活動を成功させるのが重要になるでしょう。
就職活動の進め方については、「就職活動はどうやればいい?スケジュールとあわせて具体的な進め方や対策方法を解説」で解説しています。
参照元
独立行政法人 日本学生支援機構
貸与奨学金(返済必要)
教育ローンを使用する選択肢もある
奨学金だけではなく、教育ローンを使用する選択肢もあるので覚えておきましょう。教育ローンも奨学金同様に、大学の学費を支払うために、お金を借りられる制度になります。
奨学金との違いは、借りる人が違う点です。奨学金の場合、学校に通う学生がお金を借り、返済を行います。一方で、教育ローンでは「安定した収入」が求められるので、保護者が借りるケースがほとんどです。
奨学金と教育ローン、それぞれにメリットデメリットがあるので、比較して十分に検討するようにしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。