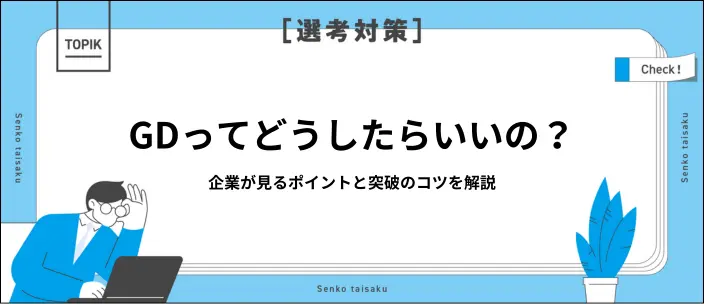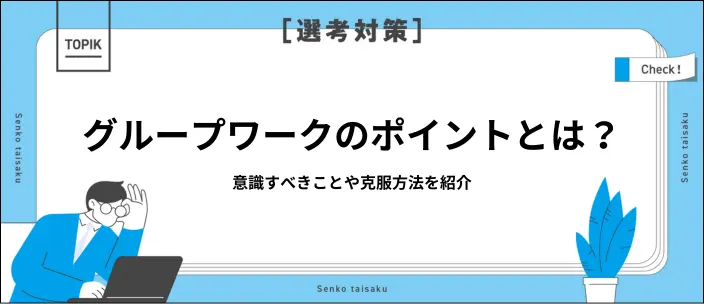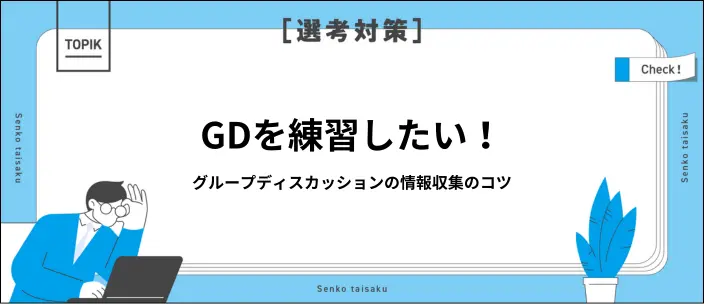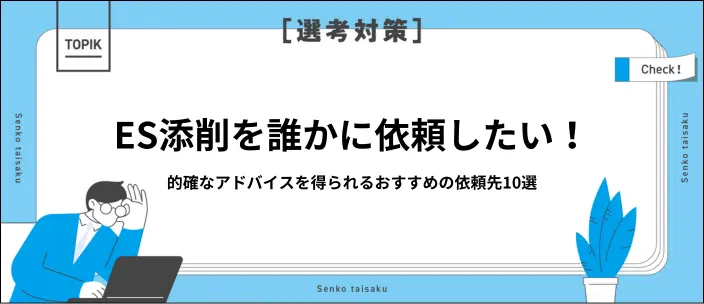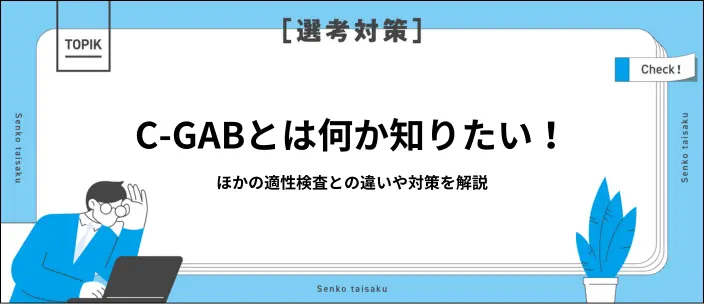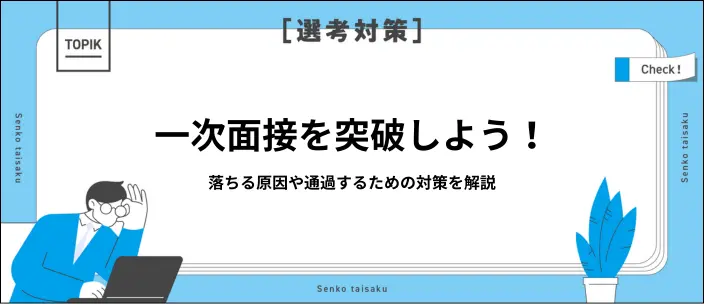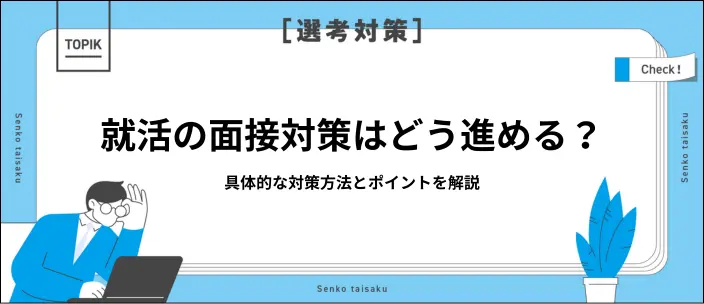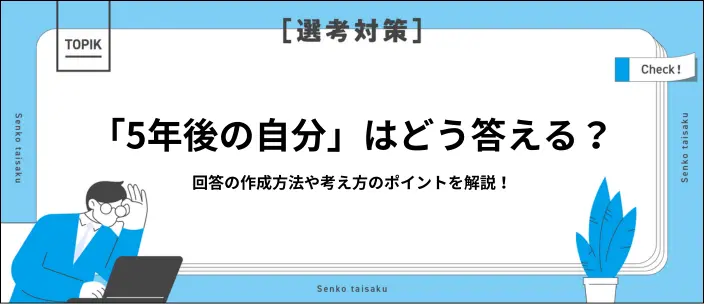このページのまとめ
- 企業がグループを行う目的の一つは、判断基準の正確性をみること
- グループワークはチームで成果を出す力を評価される場のため、協調性や役割分担も重要
- プレゼン型・作業型の特徴を把握し、出題形式に合わせた準備をする
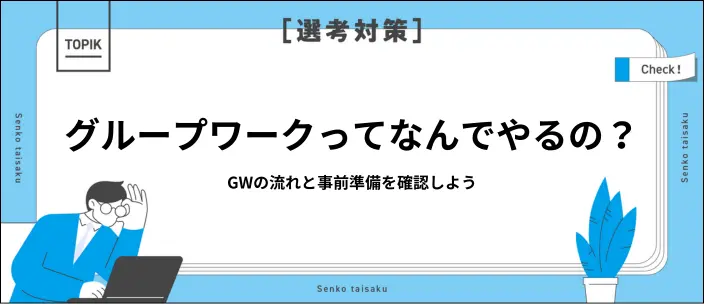
グループワークの目的を知りたい就活生も多いでしょう。選考のグループワークで「何を評価されるのかわからない」「どう準備すれば良いかわからない」と悩む学生も多くいます。
グループワークは主に総合職を中心に実施されていることが多い選考方法の一つです。
この記事では、グループワークの目的や種類、一般的な進め方、事前対策までを丁寧に解説。これを読めば、チームでの成果を出す力を効率的に高める方法がわかります。
かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- グループワークとは複数人で取り組む課題のこと
- グループワークとグループディスカッションの違い
- グループワークの種類
- グループワークで行われているゲーム例
- 企業がグループワークをする目的
- 判断基準の正確性をみるため
- コミュニケーション能力を図るため
- 将来を想像するため
- グループワークの基本的な流れ
- 自己紹介からスタートする
- 役割分担と時間配分を行う
- 言葉の定義や議論の方向性をすり合わせる
- 課題・論点を特定して議論を進める
- 議論をまとめる
- 事前にやっておきたいグループワーク対策
- 企業研究をしてテーマに備える
- 業界知識や時事の知識を身につける
- 物事に対して自分の意見をもつ癖をつける
- 自分の意見の発信・人の意見を傾聴する意識をもつ
- 就活イベントに参加して実践練習をする
- グループワーク対策のポイント
- グループワークの目的を理解し対策を進めたいあなたへ
グループワークとは複数人で取り組む課題のこと
グループワークとは、複数人で課題に取り組み、チームとして成果を出す活動です。就活では、チームでの協力やコミュニケーション能力を評価するために実施されます。
ビジネスの現場では、ほとんどのプロジェクトがチームで進められるもの。したがって、個人の能力だけでなく、他者と協力して成果を出せる力が求められるのです。
グループワークでは、チームの中でリーダーや進行役、書記などの役割を分担し、商品のローンチや事業戦略の課題に取り組みます。たとえば、企業の採用選考では、課題に対する意見交換の仕方やチーム内での協力姿勢が評価されるでしょう。
つまり、グループワークは「一人で成果を出す力」だけでなく、「チームで成果を出す力」を見られる場です。就活生は、事前にチームでの役割分担や話し合いの進め方を理解しておくと安心でしょう。
初めてグループワークを行う方は「初めてのグループワークを乗り越えるコツとは?進め方や評価ポイントも解説」で基本的なポイントを紹介しているため、あわせて参考にしてください。
グループワークとグループディスカッションの違い
グループワークとグループディスカッション(GD)は似ていますが、目的や評価の観点が異なります。この違いを理解しておくことが、就活で選考で有利になるポイントです。
・GD(グループディスカッション)
数人のグループで議論を行う作業。議論の進め方や意見交換がメインです。
・グループワーク
GDを含む場合もありますが、最終的に結論や成果物を作る活動全体を指します。
GDはグループワークの一部と考えると理解しやすいでしょう。また、GDは議論中の個人スキル、グループワークはプロセス全体が評価対象です。
GDで評価されるポイント
・傾聴力
・コミュニケーション力
・協調性
・リーダーシップ
グループワークで評価されるポイント
・議論の進め方
・チームでの役割分担
・成果物のクオリティ
・プロセス全体での協力姿勢
つまり、GDは「議論力」を見る場、グループワークは「チームで成果を出す力」を総合的に見る場といえます。就活生はこの違いを理解し、GDでは発言や意見の出し方、グループワークでは成果物作りや役割分担に注力することが重要です。
グループディスカッションの基本情報については「グループディスカッションとは?基本知識から落ちやすい就活生の特徴まで」や、「GDとは何か?基本的な流れや種類ごとの特徴を知って本番に備えよう!」もあわせてご覧ください。
グループワークの種類
選考の際に行われるグループワークには、大きく分けて2つの種類があります。1つは出題された課題を議論して発表する「プレゼン型」、もう1つはグループで課題に向けた作業を行う「作業型」です。
プレゼン型
プレゼン型には、自由討論型と選択(ディベート)型、課題解決型のディスカッションがあります。
どちらも出題されるテーマを基にグループ内で意見を述べて行うものです。
自由討論型では、他者の意見にも耳を傾けることができるか、自分の意見もしっかりと伝えることができるか、といった部分を見られます。
さらに、限られた時間の中で行うことも意識しながら、バランスよくディスカッションできているかもチェックポイントの一つ。進行させたり、意見をまとめたりするなどのリーダーシップ性を発揮することで評価UPにつながる可能性もあります。
選択(ディベート)型は、他者を納得させられる意見を述べるというディスカッション方法です。
これにより見られているのは、思考力とプレゼン力。道筋を立てて、選んだ答えの理由を説明できるかどうか、相手を納得させられる説得力があるかどうかなども評価されます。
課題解決型は、難易度が高いとされるディスカッション方法です。その内容は、出題されたテーマを解決するための方法を見つけ出す、というもの。
出題される問題が難問ばかりである点と、時間が限られているという点が難易度を高く感じさせるようです。ミッションとされる課題解決に向けてまず行うのは、課題点を見つけ出すこと。そして、議論するべきテーマを先に洗い出すことです。
プレゼン型の中には、実際のビジネスシーンを想定した「ビジネスケース型」の課題を出す企業もあります。
ビジネスケース型のテーマは、課題解決型の中でもさらにハードルが高めです。マーケティングの基礎知識やロジカルシンキングの能力を選考の判断材料としている業界や企業による採用が多いとされています。
どの型も自分自身をプレゼンしなければいけないことに変わりありません。そのため、事前に希望する企業が求めている人物像への理解を深めておく必要があるでしょう。
作業型
作業型のグループワークでは、チームワークを活かした課題が提示されること、短時間で行うことが特徴です。他者と協力しなければ完成までたどりつくことができないため、何よりもチームワーク力が求められます。
また、初対面同士という状況下でコミュニケーションを図る能力も必要です。時間配分も気にしつつ全員でゴールを目指す作業型では、チームへの貢献度や協調性、作業効率度、作業プロセス、リーダーシップ力など、さまざまなポイントが評価されます。
グループワークで行われているゲーム例
企業によって取り上げるテーマはさまざまです。プレゼン型や作業型といった種類によっても異なりますが、パズルやカードなどのアイテムを使ったゲーム感覚のグループワークを実施しているところもあります。
採用選考で使われているのは、以下のようなゲームです。
ペーパータワー
決められた枚数の紙を使って、制限時間内にできるだけ高い自立できるタワーを作るというゲームで、選考以外に企業の研修などで行われることもあるほどポピュラーなゲームです。
使用OKとされるアイテムは、紙とテープのみ。使用できる枚数は限られていますが、より少ない枚数で完成させたチームが高評価されます。
ペーパータワーゲームの目的は、企業経営を疑似体験すること。会社の売上(タワーの高さ)を出すために、どれほど原価(使用枚数)を抑えるか、という実際に仕事に活かせる能力を把握することが可能です。
タワーを建てるという内容に似た「マシュマロチャレンジ」というゲームもあります。マシュマロチャレンジは、乾麺のパスタとテープ、ひも、マシュマロを使って、どのチームがより高いタワーを建てられるか競う、という内容です。
ルール上の制限時間は18分。パスタが折れないように、マシュマロが潰れ過ぎてしまわないように試行錯誤しながらチームでチャレンジしていきます。
NASAゲーム
コンセンサスゲームという呼び名でも知られており、自分と他者との意見をまとめて合意形成するゲームです。
ゲーム内容は、月に不時着した宇宙船があると想定し、いくつか機体に破損した箇所があることと、無傷のアイテムが残っていることから、その中で最も必要とされる物の優先順位をつける、というもの。
このゲームの特徴は、NASAの模範解答が存在することです。高く評価されるのは、模範解答との誤差が少ないチーム。個人よりもチームで臨んだほうが生じる誤差が小さい、という面白い統計結果があるゲームとしても知られています。
脱出ゲーム
体を動かすゲームとしてリアルな体験ができる脱出ゲーム。
チームで謎を解きながら決められたフィールドから脱出を図ります。特徴は、情報は口頭のみで共有しあうこと、出口ではなぞなぞが出題されることです。このゲームでは、論理的思考力とコミュニケーション能力が求められます。
グループワークで出題される問題は多種多様です。ゲーム内容を見聞きした経験がなければ、参加当日にチームに迷惑をかけてしまう可能性があります。
スムーズに進めるためには、あらかじめ簡単なゲーム内容を把握しておくことが大切でしょう。
かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
企業がグループワークをする目的
選考方法でグループワークが行われる目的には、どのようなことが考えられるでしょうか。実施する目的には以下のようなことが挙げられます。
判断基準の正確性をみるため
面接は関わる人数が少ないため、判断基準がブレてしまう可能性があります。その判断基準の正確性をチェックし、基準ブレを避けるためにグループワークが行われます。
また、同じ状況下で一度に複数の学生を見極めることが可能な点もグループワークの特徴です。面接官との相性の不一致も防ぐことができ、企業にとってもメリットとなる選考方法として活用されています。
コミュニケーション能力を図るため
仕事をスムーズに進めるためにも、どの業界・企業においても必要とされるものがコミュニケーション能力です。人と人とのコミュニケーションは仕事をするうえで欠かせない能力といえます。
グループワークでは、その日初対面の参加者同士がその場で協力しあって課題に取り組む姿勢をみることが可能です。また、瞬発力や対応力など、コミュニケーション能力の高さを図ることもできるでしょう。
将来を想像するため
グループワークを通して、結論に至るまでの個々の活躍を見つつ、将来の姿を想像することができる点も目的の一つとされています。あるテーマに沿って、どのような行動や思考を見せるのか、またそれぞれの特性は何かなど、あらゆることが把握できるのも、グループワークの特徴です。
インターンでのグループワークの目的については「インターンの定番?グループワークの目的と攻略ポイント」で紹介しているため、あわせてご参照ください。
かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループワークの基本的な流れ
グループワークは、就活やインターンシップでよく行われる選考形式の一つ。複数人のチームで課題に取り組む中で、協調性やコミュニケーション能力、論理的思考力などが評価されます。
ここでは、就活でよくある一般的なグループワークの流れを、自己紹介から結論出しまでのステップ順にわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。
自己紹介からスタートする
グループワークでは、まず自己紹介を行うことが大切です。自己紹介は、緊張を和らげ、チームにスムーズに溶け込むための第一歩。
お互いのことを全く知らない状態で議論を始めるよりも、事前に基本情報や個性を共有しておくほうが、チーム内のコミュニケーションがスムーズになります。
・名前や大学名などの基本情報
・自分を表すキャッチフレーズや特徴
・得意分野や担当できそうな役割
これらを簡潔に伝えることで、チームメンバーが「この人にはどんな役割を任せられるか」を把握しやすくなるでしょう。また、自分の強みを共有することでチームの一員としての存在感も高まります。
自己紹介は緊張を和らげるだけでなく、チームの信頼関係を作る重要なステップです。就活のグループワークでは、簡潔かつ自分らしい自己紹介を心掛けましょう。
役割分担と時間配分を行う
グループワークでは、役割分担と時間配分を事前に決めることが効率的な議論を行うカギになります。限られた時間内で結論や成果物を作るには、誰が何を担当するかを明確にして進める必要があるためです。
また、時間管理ができるかどうかは、ビジネスの「納期を守る力」と同じように評価されます。
・リーダーや進行役、書記など、基本的な役割を決める
・立候補が重なった場合は、ほかの役割を率先して担当して協調性をアピール
・自分の希望がある場合は理由を添えてメンバーに伝える
・どの役割でも対応できるよう、事前に準備しておく
・持ち時間を各工程に割り振る
・議論に偏り過ぎず、成果物作成やまとめの時間も確保する
役割分担と時間配分を意識することは、議論をスムーズに進めるだけでなく、協調性や計画性をアピールする重要なポイントです。就活のグループワークでは、どの役割でも柔軟に対応できる準備が評価につながります。
言葉の定義や議論の方向性をすり合わせる
グループワークでは、言葉の定義や議論の方向性を事前にメンバーで共有することが、効率的で質の高い議論につながります。
事前に認識をそろえずに議論を進めると、メンバー間で齟齬が生まれ、議論がまとまらなかったり、振り出しに戻ったりする可能性が。方向性を確認することで、無駄なやり取りを減らし、結論までスムーズに進められます。
また、「効果的」「最適」など抽象的な表現は具体的に定義しましょう。言葉や前提をすり合わせることは、議論を効率化し、よりレベルの高い成果物や結論を出すための基本ステップです。就活のグループワークでは、この段階を丁寧に行うことでチームの評価も高まります。
ゴール設定で議論を効率化する
グループワークでは、議論のゴールを事前に設定し、メンバー全員で認識を合わせることが大切。ゴールを明確にすることで、議論の方向性がブレず、効率よく成果物を作れます。
ゴールが曖昧なまま議論を進めると、メンバー間で意見が散乱し、議論がまとまらないリスクがあるのです。ゴールを共有することで、全員が同じ目的に向かって意見を出せます。
課題・論点を特定して議論を進める
グループワークでは、議論のテーマとゴールが決まったら、まず課題や論点を特定しましょう。これにより、議論が具体的かつ効率的になります。
課題や論点が明確でないと、議論が抽象的になり、結論まで到達するのに時間がかかってしまうでしょう。特定することで、チーム全員がどこに意見を集中すべきか理解できます。
解決策を洗い出して全員で意見を出し合う
グループワークでは、積極的にチーム全員で意見を出し合い、多様な解決策を洗い出すことが成功のポイントです。初期段階でさまざまな意見を出すことで視野が広がり、最終的な結論や成果物の質が高まるでしょう。
また、全員が発言に参加することでチームとしての価値が最大化されます。
・発言を促す:「△△さんはどうですか?」など、互いに話を振り、発言しやすい環境を作る
・意見を否定しない:否定的な反応は避け、肯定的に受け止める
・全員参加の徹底:何もしないメンバーがいないように注意し、チーム全員が目標に向かう
他者の意見を尊重し、肯定的に対応することで、全員が意見を出しやすい環境が整い、グループワークの成果も向上するでしょう。解決策を洗い出す段階では、多様な意見を出し、全員が参加できる環境を作ることが欠かせません。
就活のグループワークでは、このステップでの協力姿勢やコミュニケーション力が高く評価されます。
議論をまとめる
グループワークでは、出された意見を整理・検討し、議論の方向性に沿ってまとめる作業が不可欠です。ただ意見を出すだけでは議論は前に進みません。5W1Hで設定した前提条件に沿って意見を整理することで、ズレた意見を排除し、効率的に結論に近づけます。
また、多数決で結論を決めるのは避けましょう。グループワークでは、結論そのものよりも議論のプロセスや主張の出し方が評価されるためです。就活のグループワークでは、意見を整理する力や論理的思考、チームでの協力姿勢がチェックされます。
結論出しと合意形成のポイント
グループワークでは、意見を整理・集約し、結論を出すと同時に全員で合意形成を図ることが重要です。
意見をただまとめるだけでは、評価につながりません。ジャンル別に意見を整理したり、似た意見を統一したりすることで、効率的に結論を導くと同時に、全員の理解や納得感を得られます。無理に1つの結論にまとめ過ぎると、チームの協調性や議論のプロセスが評価されにくくなるため注意が必要です。
・意見の整理方法:ジャンル別に分ける、似た意見を統合する
・意見が少ない場合:再度議論して、結論につながる意見がないか検討
・合意形成の工夫:意見がまとまらない場合は、対立意見と根拠を整理して結論として発表
・注意点:無理やり1つにまとめないことで、チームの評価を維持できる
結論出しは意見の整理・集約を行いながら、全員で納得できる形にすることがポイント。就活のグループワークでは、結論そのものよりも、議論のプロセスやチームでの協力姿勢が評価されます。
グループディスカッションのコツについては「グルディスの通過率をあげるためのコツを紹介!基本的な流れや役割の解説も」も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
事前にやっておきたいグループワーク対策
グループワークでは、議論の進め方や発言力だけでなく、事前準備や練習の有無も評価の対象に。準備ができていると、自分の意見をスムーズに出せるだけでなく、チーム全体の議論も効率的に進められるためです。
ここでは、就活生がグループワークに備えて事前に取り組むべき対策を具体的に紹介します。
企業研究をしてテーマに備える
グループワークでは、事前に企業研究を行い、出題されるテーマに備えることが大切です。特にプレゼン型やビジネス型のグループワークでは、新規事業やサービスの販促プラン、キャッチコピー作成など、企業の事業内容に関わる課題が出されることが多くあります。
企業を理解しておくことで、議論をスムーズに進められるでしょう。
・コーポレートサイトで沿革や事業内容を確認
・採用サイトの社員インタビューで業務内容を把握
・上場企業の場合はIR情報もチェックし、会社の戦略や市場動向を理解
企業研究を事前に行うことで、グループワークの議論に具体性を持たせ、チーム内で信頼感のある発言ができるようになります。就活生は、課題テーマに関連する情報を事前に整理しておくことが成功のカギです。
業界知識や時事の知識を身につける
グループワークでは、業界全体の構造や動向、最新の時事情報を把握しておくことが議論を有利に進めるポイントです。企業研究だけでなく、業界全体や市場動向を理解しておくと、課題に対して具体的で説得力のある意見を出せます。
特に、プレゼン型やビジネス型の課題では、業界のトレンドや課題を踏まえた議論が評価されるでしょう。
・業界研究セミナーや合同説明会に参加する
・就活ナビサイトの業界ページをチェックする
・日常的に新聞やニュースをチェックしてタイムリーな情報を入手する
業界知識や時事の知識を事前に身につけることで、議論に具体性と説得力を持たせ、チーム内で信頼感のある発言ができるようになります。就活生は、企業や業界の最新情報を整理しておくことがグループワーク成功のポイントです。
物事に対して自分の意見をもつ癖をつける
グループワークでは、自分の意見を積極的に持ち、発言できるようになることが重要です。日常的に意見を考える習慣をつけておくと、議論にスムーズに参加できます。
就活生の中には、普段から意見を求められる機会が少ないため、いざグループワークで発言する際に戸惑う人も多いです。日常から自分の考えを整理する癖をつけることで、発言への抵抗感が減り、議論の中で評価されやすくなるでしょう。
・興味のある分野や得意なテーマから始める
・ニュースや社会問題に意見を持つ
・1つのテーマで意見を持てるようになったら、次の興味分野も深掘りして考える
日常的に意見を考える習慣を持つことで、グループワークで自然に発言でき、議論に貢献できる力が身につくのです。就活生は、テーマを決めて考える時間を日常的に設けることが成功のコツとなります。
自分の意見の発信・人の意見を傾聴する意識をもつ
グループワークでは、自分の意見を発信する力と、他人の意見を傾聴する力の両方が大切です。日常からこれらの力を意識して練習しておくと、本番でスムーズに議論に参加できるでしょう。
意見を発信する力だけでなく、他者の意見を理解し受け入れる傾聴力も評価されます。両方の力をバランスよく身につけることで、議論に積極的かつ協力的な参加が可能です。
・友人と練習する:気軽に意見を出せる環境でアウトプットを練習する
・初対面の人と実施する:本番と同じ緊張感を再現する
・テーマを決めてアウトプット:前章で紹介したテーマ例を用い、意見をまとめて発表する練習をする
発信力と傾聴力を意識して練習することで、グループワークで自然に議論に参加し、評価されやすくなります。就活生は、テーマを決めてアウトプットを出す練習を日常的に行うようにしましょう。
就活イベントに参加して実践練習をする
グループワーク対策として、就活イベントに参加し、実践の場で練習することが効果的です。
就活イベントでは、実際のグループワーク形式で議論を行う機会があり、企業の人から直接フィードバックを受けられるため、自分の課題や改善点を客観的に把握できます。失敗を恐れず練習できる環境も、大きなメリットです。
就活イベントを活用することで、実践的にグループワークのスキルを磨き、評価されやすい力を身につけられます。就活生は、フィードバックを活かして日常的な練習と組み合わせることで、着実に成長できるでしょう。
「グループワークが苦手…就活で不利にならないための準備と対策を解説」でも、グループワークに向けた準備のポイントを紹介しているため、あわせてチェックしてみてください。
かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループワーク対策のポイント
チームワーク力が求められるグループワークに必要なのは、以下のような対策です。
・論理的に話す
・積極的に意見を述べる
・他者の意見にもしっかりと耳を傾ける
・自分に適した役割を担う
・すべての意見をまとめる
・対立点を明確にさせる
上記の対策ポイントを意識しながら、グループワークに臨むとよいでしょう。
選考方法は企業によって異なります。そのため、希望する業界や企業の研究を通して、選考方法への対策を講じておくことも重要です。
就活のどのタイミングでグループワークが課されるかは、「就活のやり方と流れを解説!準備から内定までのポイントと相談先も紹介」の記事でご確認いただけます。逆算して対策を行いましょう。
かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループワークの目的を理解し対策を進めたいあなたへ
グループワークは、単に「議論や発言力」を評価する場ではなく、チームで成果を出す力や協調性、論理的思考力を総合的に見られる場です。グループワークとグループディスカッションの違いや種類、一般的な流れ、事前準備の方法を押さえることで、当日の議論に自信をもって臨めるでしょう。
グループワークでの評価は、結論そのものよりも議論のプロセスやチームへの貢献度に重きが置かれます。そのため、ポイントを押さえた準備を行うことで、選考通過の可能性も大きく高まるでしょう。
グループワークに自信をつけたい、効率的に対策を進めたいあなたには、キャリアチケットの就職サポートがおすすめです。プロのキャリアアドバイザーがあなたに合ったグループワーク対策や模擬練習を個別に提供し、企業研究や発言力、チームでの立ち回り方まで徹底サポート。
一人で悩むより、実践的なアドバイスをもらいながら準備を進めることで、当日の自信につながります。グループワークを有利に進めたい就活生は、ぜひキャリアチケットを活用して、ほかの学生と差をつけましょう。
かんたん1分!無料登録26卒の就活について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。