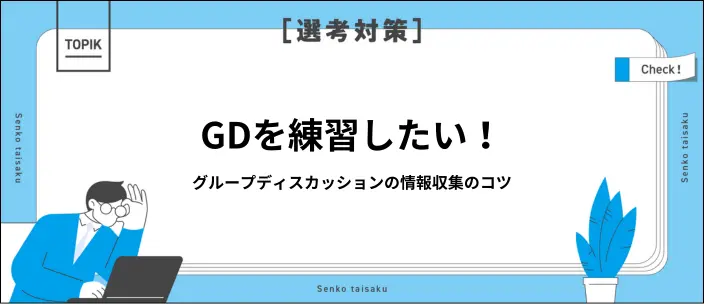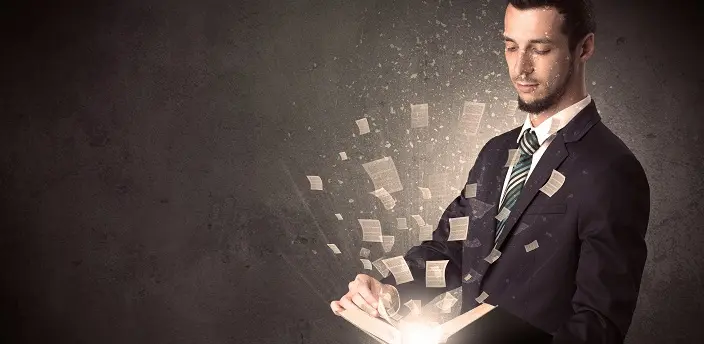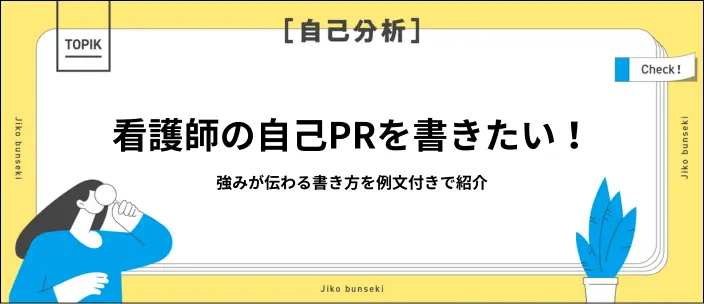このページのまとめ
- 企業がグループディスカッションをする理由は一度に複数の学生の選考を行えるから
- ディスカッションのテーマは価値観を問うものや社会や政治に関するものなど様々
- ディスカッションの種類には「課題解決型」「選択型」「討論型」「自由討論型」がある
- ディスカッションは種類やテーマによって評価ポイントが異なる
.jpg)
就活の選考で実施されるグループディスカッションに、苦手意識を持つ就活生も多いでしょう。このコラムではグループディスカッションの定義をはじめ、よくあるテーマ別に対策ポイントを解説ています。頻出テーマを把握し事前に準備をしておくことで安心して選考に望めます。「論議形式の選考が苦手…」という方はぜひご一読ください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションとは?
グループディスカッションとは、数人の就活生で構成されたグループで、あるテーマについて議論し、制限時間内に結論を出す選考方法です。結論を導き出すだけでなく、発表~プレゼンまで実施する場合も。企業側からは1グループにつき1~2名ほど社員が付き、参加者の言動や態度をチェックし、選考の判断材料にします。中小企業の選考で行われることは少なく、中堅~大手企業で実施される場合が多いようです。
企業がグループディスカッションをする理由
企業がグループディスカッションを実施する理由の一つは、一度に複数の学生の選考を行えるからです。大企業や人気企業になると、応募者が数千人~1万人を超えるケースも珍しくありません。
それだけ多くの志望者を個別に選考することは時間やコストといった面から厳しいのが実情です。
そのため、書類選考で人数を絞ってからディスカッションの場を設け、学生を一度にまとめて評価します。
また、面接だけでは分からない学生の特性を確認できるというメリットもあります。個人面接やグループ面接には学生同士が話し合う機会がなく、協調性の有無を測りづらいため、グループディスカッションを通してチームワークやチーム内での立ち回り方をチェックしている…というケースは多いようです。
さらに、論題を的確に捉えているか、議論すべき内容に即しているかといった「論理的な思考力」を見ていることも。発言だけでなく、他者との関わり方やチーム内での立ち位置もチェックされていることを覚えておきましょう。
グループディスカッションについては「グループディスカッションの4つの評価基準とは?重要なのは絶対評価」も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
カテゴリー別よくあるテーマ例
ここでは、グループディスカッションで頻出されるテーマをカテゴリー別にまとめました。事前に目を通して、自分なりの考えを発言できるようにしておくことをおすすめします。
発想力や価値観に対するテーマ
無人島に1つだけ持って行くならなにか
新しく国民の休日を制定するならどんな休日か
「幸せ」の定義はなにか
社会や政治に関するテーマ
サマータイム導入に対して賛成か反対か
自然災害が起きたときに企業ができることはなにか
義務教育の週休2日制を活用するにはどうしたら良いか
ビジネス感覚を問うテーマ
新規事業を立ち上げるならどんな事業にするか
◯◯(自社商品)の売上を2倍にするにはどうしたら良いか
効果的な企業PRを考えてください
就職活動に関するテーマ
就活でスーツの着用は必要か
就職するにあたって必要なものを3つ挙げてください
第一志望はどうやって決めるか
グループディスカッションは、積極的に発言するだけでは評価につながらないこともあります。テーマの趣旨をしっかりと掴む、形式ごとのポイントを把握する、よく出るテーマを事前にチェックしておくといった対策を行うことで、より効果的に企業にアピールできるでしょう。
次項からは、グループディスカッションの種類とそれぞれの対策方法を解説します。
グループディスカッションのテーマについては「就活のグループディスカッションで頻出するテーマとは?対策法も解説!」も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
課題解決型グループディスカッション
与えられた課題に対する解決方法を導き出すタイプのディスカッションです。資料やデータが配布され、それを元に論議を行うこともあれば、資料などはなく個々の考えだけで進めることもあります。
以下よりテーマ例と実施目的をチェックしていきましょう。
テーマ例
・売上を2倍にするにはどうしたら良いか
・少子化を解消するには?
・残業時間をゼロにするには?
・貧困差を無くす方法はある?
・出生率を上げるには?
実施する目的
課題解決型グループディスカッションでは、問題を客観的に把握する力や意見をまとめる力、論理的思考力がチェックされています。
課題解決型グループディスカッションの対策
課題解決型のテーマでは、「売上を2倍にする方法を求めているのに、いつの間にか売れる店舗の条件を話し合っていた…」といったように論点がすり替わりやすいので注意しましょう。話しながら趣旨がずれていないか、メンバーと認識をすり合わせながら進めることが重要です。
自分や周囲の意見をまとめる中で、違和感があれば適宜方向修正を行うよう意識してください。
また、出したアイデアに対して「なぜこれが最適か」を論理的に説明できているかも振り返りましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
選択型グループディスカッション
テーマとともに複数の選択肢が与えられ、その中から1つを選ぶ、あるいは順位付けることを目標とした議論です。誰でも意見を出しやすいテーマから専門知識を必要とするテーマまで、幅広い範囲から出題されます。
テーマ例
・このメンバーの中で内定を出すなら誰か
・小学校の教科から削除するなら「国語」「算数」「社会」のどれか
・「恋人」と「親友」どちらを優先すべきか
・「お金のない幸せ」と「お金のある幸せ」、選ぶならどちらか
・「やりがい」と「収入」どちらが大切か
実施する目的
選択型グループディスカッションではデータ収集能力や論理的思考力を図るのが目的。答えの選択肢があらかじめ決まっているため、それを選んだ根拠や裏付けを示せるかどうかが重要になります。
選択型グループディスカッションの対策
選択型グループディスカッションのテーマには正解がないので、一人ひとりの意見を尊重していると話がまとまらない傾向にあります。「こっちの方が好きだから」「自分はこう思う」など個人の価値観で話し合うのではなく、グループとしての判断基準を設けたうえで、選んだ理由を明確にすることが大切。
グループディスカッションの種類については「グループディスカッションの種類とお題の関係性」も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
討論・ディベート型グループディスカッション
テーマに対してグループの意見は賛成か反対かを決めるのが討論型のグループディスカッション。ディベート型ともいわれる形式です。テーマ例
・朝はパンとご飯のどちらが良いか・大企業と中小企業、どちらが良いか
・レジ袋有料化は取りやめるべきか
・消費税は減税すべきか
・男性専用車両を設置すべきか
実施する目的
討論型のディスカッションでは、最終的に結論を出しません。討論そのものが目的であり、選考では話し合いの内容が評価されます。討論型グループディスカッションの対策
討論型では対立意見も受け入れて議論を進めるのがポイント。勝つことを目指して相手を言い負かしたり否定したりするのではなく、別の視点からの考えを踏まえたうえで、自分の意見を展開しましょう。このとき、一人で意見を押し通さず、同意見のメンバーとフォローし合いながら進めるのがおすすめです。就活生向けのディベートテーマについては「就活生向けディベートテーマ30選!進め方や対策方法も解説!」も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
自由討論型
自由討論型はフリーディスカッションとも呼ばれ、多くの企業で行われています。1つのテーマに対してグループ内で自由に話し合う形式が一般的。専門知識を要するテーマよりも、誰でも自分の意見を発言できる一般的なテーマが出題されることがほとんどのようです。テーマ例
・働く意味はなにか・どんな会社を良い会社と呼ぶか
・30年後の世界はどんな社会になっているか
・タイムスリップできるとしたらいつの時代に行く?
・新しい国を作れるとしたらどんな名前にする?
実施する目的
自由型のディスカッションでは、相手を言い含める話術や分析能力よりも、周囲と円滑なコミュニケーションを取れているかどうかを見るのが目的。抽象的なテーマに対して「どんな考えを持っているのか」といった人柄や性格に基づく要素が評価されやすい傾向にあります。自由討論型の対策
選択型と同じく、自由討論型にも正解がありません。「結局答えがまとまらなかった」といった事態を防ぐためにも、最初にグループ内で定義や判断基準を決めておくことが大切です。たとえば「どんな会社を良い会社と呼ぶか」というテーマならば、まず「良い会社」の定義を決めましょう。「プライベートと両立ができる会社」なのか「売上を伸ばし続けている会社」なのか、グループによって定義はそれぞれ異なります。そのうえで、「良い会社」を実現するために、どんなアプローチをしたら良いかを話し合いましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。