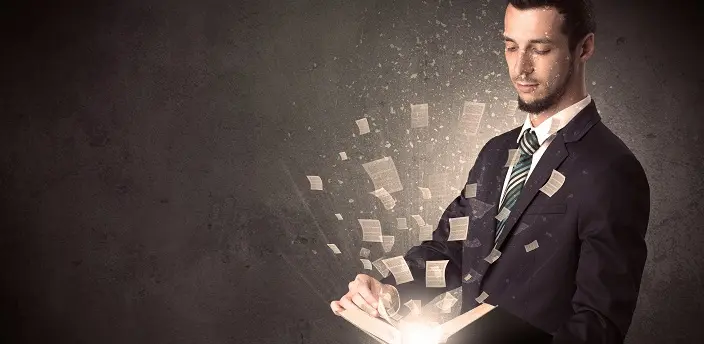このページのまとめ
- グループディスカッションは面接や書類選考ではみえない能力を評価するために行われる
- 就活のグループディスカッションには「抽象的テーマ型」や「課題解決型」などがある
- 人事担当者は「積極性」「協調性」「論理性」「発想力」をチェックしている
- グループディスカッション対策にはニュースを見たり模擬練習をしたりするのが有効
- グループディスカッションでは姿勢や動作、話し方に気をつけて好印象を与えよう
- オンラインディスカッションでは話し方や表情、動作などを分かりやすくしよう
.jpg)
採用試験のグループディスカッションに対して、苦手意識を持つ就活生も多いのではないでしょうか。具体的な流れや採用担当者の評価ポイントを知って、不安を解消しましょう。
このコラムでは、グループディスカッションの基本的な知識から、評価のポイント、不合格になりやすい就活生の特徴までを詳しく解説。近年増加中のオンライングループディスカッションのコツも紹介しています。事前に頭に入れて備えておきましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
ディスカッションとはどんなもの?
採用選考でよく取り入れられるグループディスカッションも「ディスカッション」の一つの形式です。まずは、「ディスカッション」について基本的な知識を深めましょう。
ディスカッションとは?
ディスカッション(discussion)とは、「特定のテーマに対して、参加者たちが自由に意見を出し合うこと」です。
グループディスカッションとは、数名単位で意見をまとめ、結論を導き出すためのもの。一方でパネルディスカッションは、聴衆の前でパネリストが公開討論を行います。「ショー」としての側面も持ち合わせている点が、大きな特徴です。
ディスカッションの目的
ディスカッションの目的とは、ディスカッションの参加者がお互いに情報の交換、共有をし、意見やアイデアを出し合うことで新しい発想が生み出すことです。よりクオリティの高い結論を出すことを目的として行われます。
グループディスカッションについては「グループディスカッションとは?進め方や評価されるポイントを解説!」も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
採用選考のグループディスカッションとは?
ここでは、グループディスカッションの概要や人数、所要時間ついて詳しく解説していきます。
グループディスカッションとは?
採用選考のグループディスカッションとは、就活生たちが同じ立場のメンバーとコミュニケーションを取りながら進めていく選考方法の一つです。面接や書類選考だけでは分からない学生の個性や能力をさまざまな観点から評価することができます。
また、短時間に多くの学生を選考できるというメリットもあるため、多くの企業の採用試験に取り入れられるようになりました。
グループディスカッションの人数
企業によりまちまちですが、おおよそ10名程度の学生で実施されることが多いようです。
グループディスカッションの所要時間
グループの構成人数により多少の差もありますが、大半の企業では30分前後で行われています。
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションの主な流れ
一般的なグループディスカッションは以下のような流れで進められます。流れを念頭に置いて本番に臨むと、気持ちに余裕が生まれるでしょう。
1.担当者から説明を聞く
採用試験の担当者が、テーマや設定時間、ルールなどについて説明を行います。その際、大切なことはメモをとるようにしましょう。
2.自己紹介
まずは学校名や氏名などを伝えます。簡単なあいさつを行いましょう。
企業によっては名札を使用しないケースもあるので、メンバーの名前と座席をメモしておくと、後に呼び掛けるときに間違えることを回避できて便利です。
3.役割分担・タイムスケジュールの決定
ディスカッションがスムーズに進行するよう、メンバー内でリーダー、書記、発表者などの役割を割り振ります。
また、このときにタイムスケジュールも決めましょう。
4.ディスカッションを行う
テーマについて、全員がそれぞれの意見や考えを述べ、しっかりと話し合います。
5.グループ内の意見をまとめる
グループ内で最終的な意見をまとめます。最後に発表をする必要がある場合は、発表者が指定時間内で発表できるように準備をしましょう。
6.発表する
発表者がグループとしての導き出した結論、意見を発表します。
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションの5つの形式と進め方
採用選考でのグループディスカッションの形式は、主に5パターンに分けられ、それぞれ進め方や評価のポイントも変わってきます。
1.抽象的テーマ型
抽象的なテーマを議題として、学生が1つの結論を出すグループディスカッションです。
軸を意識してディスカッションを進めよう
テーマが抽象的なため、誰でもすぐに意見を言いやすく結論がまとまらずに終わる、ということも頻発しがちになるのがこの形式です。
まずはテーマに対して一定の条件や定義付けをしたうえで、1つの結論を目指して議論を進めていくと良いでしょう。
重視されるのは過程と人柄
この形式では、結論よりも過程が重視される傾向にあります。グループディスカッションを進めていくなかで、円滑なコミュニケーションが取れているかなど、能力面よりも人柄面をチェックされることが多いようです。
2.課題解決型
与えられた課題について、より良い解決策を見出すことを目的としたグループディスカッション形式です。簡単な資料が用意されている場合もあります。
柔軟な発想力を大切にして議論を進めよう
まずは現状の問題点や原因を分析し、自由な発想で解決策を提案していきましょう。その後、実現の可能性が一番高いアイデアに絞り、詳細を議論していくようにしましょう。
大切なのは行動力と思考体力
課題解決型のグループディスカッションは、メーカーや広告系の企業で多く取り入れられていることからもわかるように、問題解決のためのリサーチ能力や柔軟な発想力でアイデアを出し続ける思考体力が評価される傾向にあります。
3.資料読み取り型
与えられた資料から問題点を見出し、最善と思われる解決策を導き出していく形式のグループディスカッションです。自由な発想で意見を出していく課題解決型とは異なり、意見の根拠は資料、または資料から読み解ける事実のみとなります。
グループディスカッションの前に、個人で資料を読み込む時間が設定される場合もあります。
論理的思考がカギ
資料読み取り型のグループディスカッションは、人柄以上に論理的な思考能力や仮説構築力といった能力が重要視されるようです。
発言は事実ベースを意識するこの形式では、事実や根拠を示すことを大前提として、議論を進めていくことが大切なポイントとなります。
ただ闇雲にアイデアを出すのではなく、物事を構造的に捉え、データに基づいた意見を出すようにしましょう。
4.ディベート型
賛成・反対の立場、または役割が与えられたうえで、テーマについてディスカッションする形式です。学生にそれぞれ異なる役割が与えられる場合は、自分の役割や状況が書かれた資料を渡されることがあります。
冷静に議論を進めよう
この形式では、自分に与えられた立場からの論理を構築するとともに、相手側の論旨の欠点、攻撃点を考える必要があります。また、お互いに立場が決められた状態で議論をするため、ヒートアップしやすく言い争いになってしまうこともしばしば。相手を説得するためのロジックや交渉で冷静な議論を成り立たせるように心がけましょう。
大切なのは柔軟な対応力と説得力
ディベート型のグループディスカッションでは、与えられた立場に柔軟に対応できるか、そして、グループ内での意見をまとめ、相手側を説得できる強力な論陣を張れるかが評価の対象になります。穏やかに交渉する能力も評価されるポイントです。
5.その他の特殊型
上記形式以外に多くはありませんが、「フェルミ推定型」や「ケーススタディ型」のグループディスカッションが行われるケースもあるようです。
フェルミ推定については「フェルミ推定とは?ケース面接でも使える基礎知識や例題・解答も解説」も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションで見られる4つのポイント
企業の人事担当者は、グループディスカッションでさまざまな観点から学生のことをみています。主にどんな点をチェックしているのかみていきましょう。
1.積極性
与えられたテーマに対し、積極的に発言したり行動することができるか、という点がもっとも多くの人事担当者がみているポイントです。
どの企業においても、仕事をするうえでは、まずは動く、発言するなどの積極性はとても大切なこととみなされています。
2.協調性・コミュニケーション能力
自分の意見ばかりではなく他人の意見もしっかりと聞けるか、グループ全体の活動を活発にできるか、という点も重要な評価ポイントの1つです。
そのほかにも、初めての相手ともしっかりと会話のキャッチボールができるか、全体の雰囲気を読むことができるかといった点もチェックされます。
3.論理性
ものごとを構造的に考える力や自分の考えを簡潔に説明できる論理性も大切な評価ポイントです。
また、発言内容について具体的な根拠を示し、理由をしっかりと説明できることも求められます。
4.発想力
これまでの知識だけでなく、斬新な発想やアイデアに期待している企業が多く、グループディスカッションにおいても発想力は重要な評価ポイントの一つとなります。
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションで落ちる就活生の3つの特徴
短時間で数多くの就活生の特徴や傾向を把握できるグループディスカッション。だからこそ、企業側は、「誰を通過させるのか」だけではなく「誰を落とすのか」も厳しくチェックしています。
「グループディスカッションを通過できない…」と悩んだら、以下の3つの条件に当てはまっていないか、確認してみてください。
1.チームメンバーを敵対視する
議論や討論に熱くなると、自分とは異なる意見を持つ他者を、排除・攻撃する就活生がいます。しかし、これは協調性に欠ける行動であり、マイナス評価につながりがちです。
積極的に議論するのは良いことですが、チームメンバーは「より良い結果を導き出すための味方」。「みんなで良い議論をして、一緒に合格しよう」という認識で、試験に臨むのがおすすめです。
2.議論に貢献しない
「グループディスカッションが苦手」と言う就活生もいますが、議論に貢献できなければ落とされてしまう可能性もあります。
・人の話を聞いているだけ
・意見を求められても発言できない
・ほかの人の意見に同調するだけで、自分の意見がない
これらの条件に当てはまる点があると、貢献度が低いとみなされるでしょう。
3.的外れな発言ばかりする
たとえ積極的に発言していても、的外れな内容ばかりでは、やはり評価は低くなります。テーマや議論の方向性を深く理解したうえでの発言を心掛けてください。
幅広いテーマに正しく対処するためには、事前の準備・対策が必須です。具体的な対策方法については、次項目で解説します。
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッション対策の4つのポイント
グループディスカッションで評価されるためには、事前準備・対策が必須です。採用選考を通過するために、以下の4つのポイントを意識してみてください。
1.ニュースをこまめにチェックする
グループディスカッションのテーマとしてよく扱われる時事問題のほか、業界に関係する話題や社会動向の多くは、ニュースをこまめにチェックすることで情報収集できます。日頃から知識や情報のアンテナをはるように心掛けましょう。
また、情報を得るだけではなく、自分の言葉で説明できるように練習してみることもおすすめです。
2.常に自分で考え意見を持つ
グループディスカッションでは自分なりの意見やアイデアが求められます。日常的に得たニュースや情報も知ったら終わりにせず、情報に対して「自分はどう思うか?」「賛成か?反対か?」など、自分の意見を持つ習慣をつけましょう。
ノートに意見やアイデアを書き出してみるのもおすすめです。
3.相手の意見を聞く
就活のグループディスカッションで重要視されるコミュニケーション能力や協調性は、選考本番のときだけ意識しても実行するのは難しいものです。日常会話においても、自分が話すだけではなく、意識的に相手の意見や話をしっかりと聞いたり、相手の立場を考えて行動したりするようにしてみましょう。
4.実際にグループディスカッションの練習をする
グループディスカッションをうまくこなせるようになるためには、練習あるのみです。事前に練習しておけば、「リーダー」「タイムキーパー」「発言者」など、自分にとってどの役割がしっくりくるのか、見つけやすくなります。
練習風景はビデオに録画して、ディスカッション後に見直してみましょう。自身の課題を見つけられるはずです。
グループディスカッションの対策については「グループディスカッション対策をご紹介!テーマ別にポイントと対策を解説」も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションで好印象を与える3つのコツ
グループディスカッション時に気をつけたほうが良いポイントをまとめました。
何気ないことのようで意外とできていないことも多いはず。コツをしっかり身につけてさらなる高評価を目指しましょう。
1.姿勢や動作に注意する
企業側は就活生の意見だけを評価するのではありません。姿勢や動作もチェックしています。
猫背や貧乏ゆすり、必要以上の身振り手振りなどは評価を下げることにつながりかねません。背筋を伸ばし、落ち着いた動作で好印象を与えられるように注意しましょう。
2.声の大きさやトーンに気を付ける
恫喝するかのように大きな声や聞き取りづらい小さな声、早口などは周囲の人が不快に感じるおそれがあります。
はっきりとした口調、聞き取りやすい速さ、適切な声量、落ち着いた声のトーンを保ち話すことで意見にも説得力が増すものです。心掛けるようにしましょう。
3.話し過ぎないようにする
積極性をアピールしたい気持ちから、つい自分の意見を数多く発言したくなるかもしれません。しかし、ディスカッションの場では全員がバランス良く話せるような周囲への配慮が必要です。
冷静になりグループ全体を見回してから発言するようにしてみましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションで困ったときの対処法
その場でテーマを出され、みんなと一緒に進めていくグループディスカッションだからこそ、試験の場で思わぬ事態に遭遇する可能性も。慌てずに対処するため、発生しがちなトラブル事例とその対処法を解説します。
議論の方向性を見失ってしまった
参加者それぞれの自由な発言によって、議論の方向性を見失ってしまった場合、早めの方向修正が重要です。基本となるのは、「そもそも前提は何か?」という点。一度原点に立ち返り、これまでに出た意見をまとめていきましょう。
参加者全員の共通認識を深めながら議論を進めていくことで、内容が深まり、評価につながりやすくなります。
全く分からないテーマが出題された
全く知見のないテーマが出題された場合に、「知ったかぶりをしてそのまま進める」のは辞めてください。
グループディスカッションの合否のポイントは、テーマについて正しい知識を有しているかどうかではありません。テーマに対する知識がないことを正直に伝えれば、知っている人が答えてくれることもあるでしょう。
仮説に基づき、論理的に議論を組み立て、一定の結論に至ることが、評価のポイントになります。
時間配分で失敗した
時間配分で失敗した場合、臨機応変に対応してください。議論が白熱して時間を使い過ぎてしまった場合、その後のプロセスを分業で進めることで、時間の節約につながります。全員が配分ミスを認識し、リカバーするための役割を果たせれば、評価アップにつながるでしょう。
反対に、時間が余ってしまったときも、状況に沿った対応を心掛けてください。より一層議論を深めたり、より分かりやすく伝えるため工夫したりすると良いでしょう。
時間配分のミスは、社会人になってからも、比較的よくあるトラブルです。柔軟な姿勢で適切に対処できることをアピールしてください。
グループディスカッションクラッシャーの対処ついては「グループディスカッションクラッシャーとは?遭遇したときの対策方法」も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
オンライングループディスカッションの特徴と対処法
近年、導入企業が増えているのがオンライングループディスカッションです。Web会議システムを使って、インターネット上でグループディスカッションを行います。
オンライングループディスカッションの場合、対面式よりも人数が絞られ、時間も短く設定されているケースが多いようです。ただし、企業の評価ポイントは対面式とほぼ同じなので、心配は要りません。
オンラインでは、言葉や表情、動きなどが、対面式よりも伝わりにくくなってしまいます。自分の意見はハキハキと伝え、表情や動きは、普段よりも大げさに動かすことを意識してみてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。