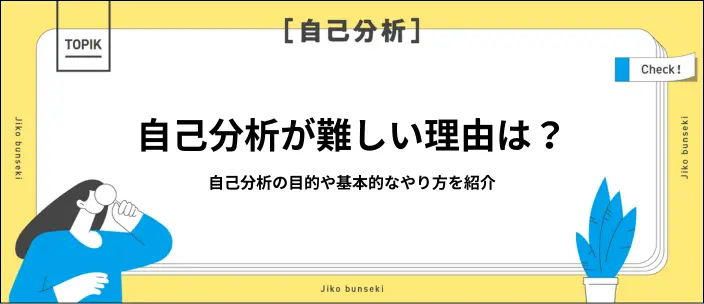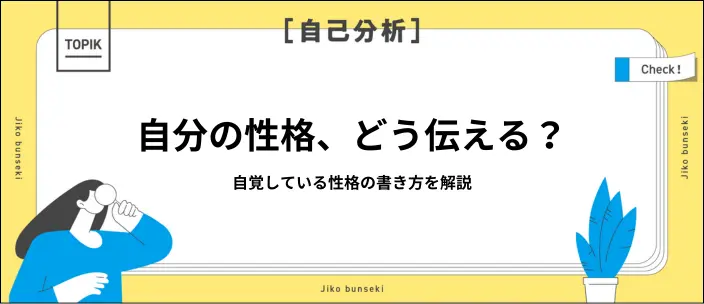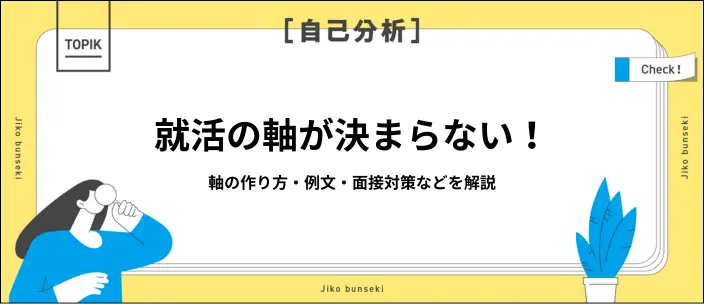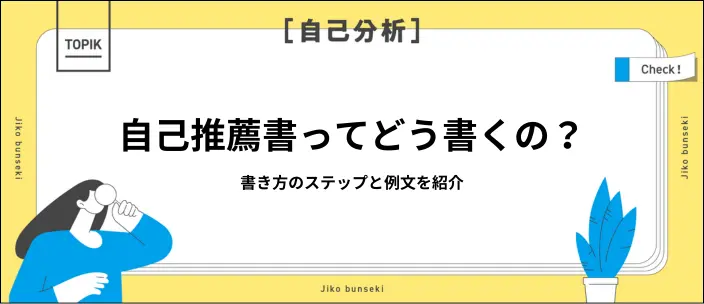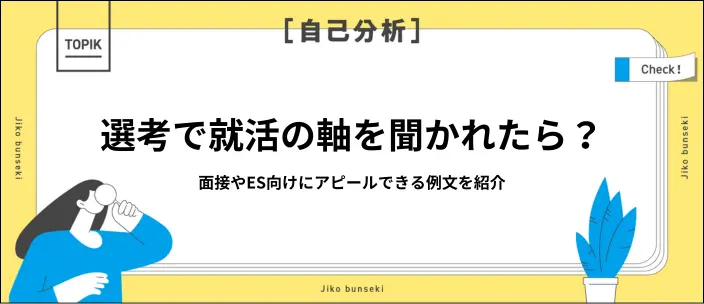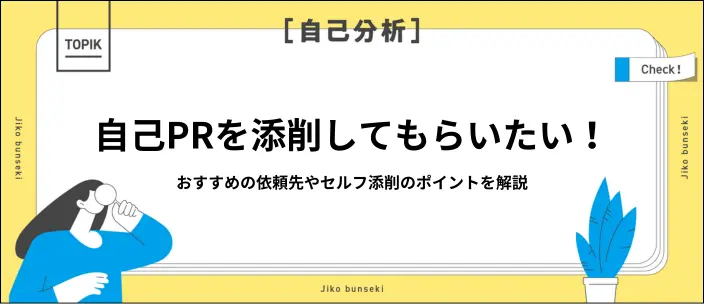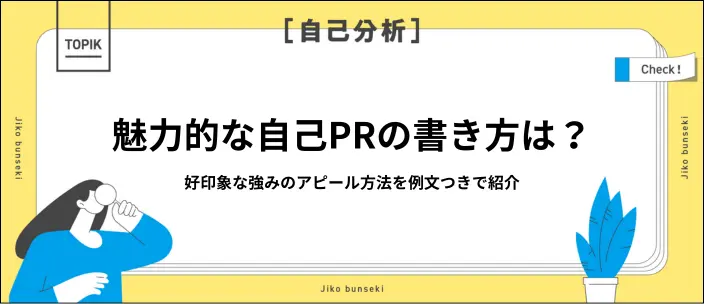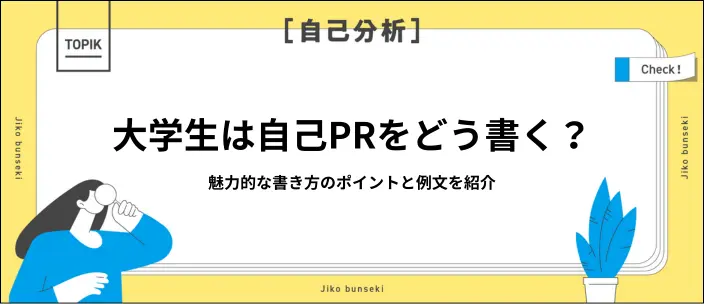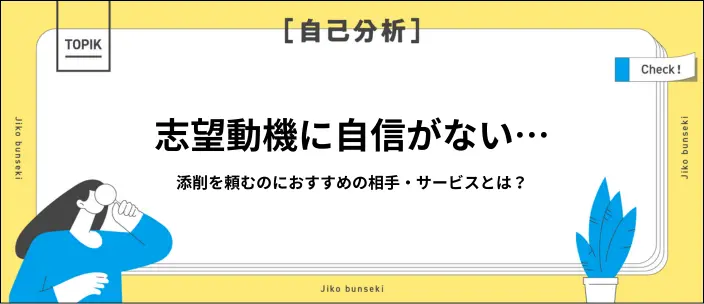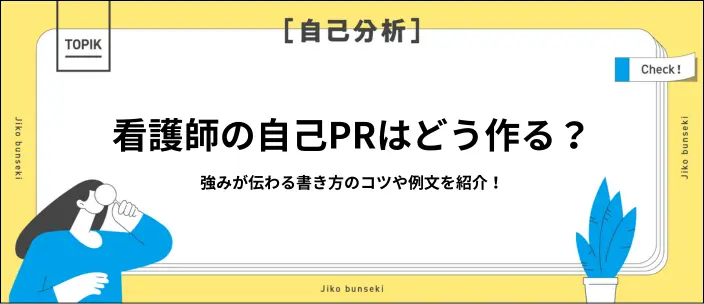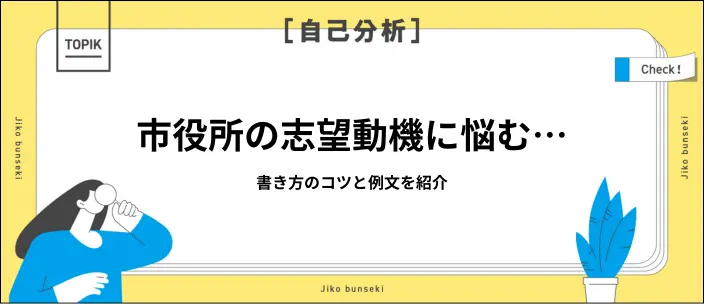このページのまとめ
- 自分史を書く際は、時系列にまとめた表を用意しよう
- 自分史の書き方で迷わないように、あらかじめテンプレートを用意しておくのが大事
- 就活では、自分史の書き方から就活生の人柄や考え方が評価されている

「自分史の書き方がわからない」「自分史をわかりやすくまとめる方法はある?」などと悩む就活生も多いでしょう。自分史を書く際は、テンプレートがあるとわかりやすくまとめられるのでおすすめです。
この記事では、自分史の書き方がわからない就活生に向けて、わかりやすくまとめられるテンプレートや書き方のポイントを解説します。最後まで読めば自分史の書き方がわかり、スムーズに作成できるはずです。
かんたん1分!無料登録自分史について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 自分史は就活に重要な「自分の歴史」をまとめたもの
- 就活で自分史をまとめる際の書き方
- 1.時系列で書き出す表を作成する
- 2.エピソードを思い出すまま書き出す
- 3.エピソードを深掘りする
- 4.モチベーショングラフに落とし込む
- 5.共通点をまとめる
- 就活に使える自分史の書き方のテンプレート例
- 印象深いエピソード
- 自分の行動と結果
- これまでの経験から学んだこと・感じたこと
- 自分の特徴
- 就活における自分史の書き方から評価されるポイント
- どのような人柄をしているか
- どのような経験を持っているか
- 企業との相性はよいか
- 就活に使う自分史の書き方の注意点
- 1.テンプレートを作成してから始める
- 2.嘘や誇張は使わない
- 3.客観性を持たせる
- 4.特別なことばかり思い出そうとしない
- 5.完璧な自分史を作ろうとしない
- 6.作成しただけで終わらない
- 7.始めた理由を振り返る
- 8.やめた理由を振り返る
- 就活で自分史をより活用する方法
- 履歴書やエントリーシート作成につなげる
- 面接で困った質問を自分史の項目に追加する
- 定期的に自分史を見返す
- 就活で一喜一憂したときに読み返す
- 就活の自分史に書く内容を思い出せないときの対処法
- アルバムや日記を読み返す
- 家族や友人に聞く
- 手紙を読み返す
- 就活における自分史の書き方例文
- 中学生時代の夏休みの宿題について
- 高校生時代のボランティア活動について
- 就活で自分史が書けず悩んでいるあなたへ
自分史は就活に重要な「自分の歴史」をまとめたもの
自分史とは、今まで生きてきた自分の歴史を時系列にまとめた一覧を指します。過去から現在まで、自分の人生で起きた出来事を思い出せる限り書き出すと、考え方や価値観が具体的になるでしょう。
自分史を作成すれば、就職活動に重要な就活の軸や方向性をより詳細に定めることが可能です。さらに、自分史の内容から自分のこれまでの経歴や経験を洗い出せるため、就活の企業選びから面接の回答まで幅広く活用できる強みや特徴を把握することもできます。
自分史が完成したら、それをもとに自己分析を進めてみてください。自己分析とは、過去の出来事から自分自身を知り客観的に自分の強みを探る手段です。一つひとつの経験や感情に着目し、選考でアピールにつながるエピソードや強み・長所といったポイントを探っていきましょう。
自分史を活用し自己分析で得た結果から、応募先を選んだり志望する企業とマッチする部分を確認したりできます。就活の提出書類や面接でもしっかりと活用し、アピールにつなげましょう。
自己分析のやり方を知りたい人は、「自己分析とは?おすすめのやり方8選や実施時の注意点を紹介」の記事も参考にしてみてください。
かんたん1分!無料登録自分史について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で自分史をまとめる際の書き方
自分史を書き出す効果的なやり方は、エピソードを選ばず思いつくまま書いたり、共通点をまとめたりすることです。ここでは、自分史の有効な書き方を5つのステップに分けて解説します。
1.時系列で書き出す表を作成する
自分史を作成する際は、まず専用のノートを1冊用意してください。縦軸は小学校1年生から1年ごとに刻み、横軸には以下の内容を書きます。
・印象深いエピソード
・自分の行動と結果
・その経験から学んだこと、感じたこと
・経験からわかる特徴
細かな学年を思い出せない場合は、「小学校・中学校・高校・大学」と簡易的に分けて始めるのもよいでしょう。簡易的な自分史のテンプレートを以下に用意しました。
| 印象深いエピソード | 自分の行動と結果 | 経験から学んだこと・感じたこと | この経験からわかる自分の特徴 |
| 小学校 | |||
| 中学生 | |||
| 高校生 | |||
| 大学生 |
2.エピソードを思い出すまま書き出す
自分史の表が作成できたら、自分への質問を繰り返し項目を埋めていきます。エピソードに書く内容は考え過ぎず、ふと思い出したこともメモしてください。
自分へ問いかける内容は、以下のような例が挙げられます。
・頑張ったこと
・特にこだわっていたこと
・どのような性格だったか
・家族との関係
・友人と何をして遊んだか
・趣味は何だったか
・部活や習い事、アルバイトはしていたか
・よかった、うれしかった出来事
・嫌だった、悲しかった出来事
・心に残った特別な経験
・人間関係や人のためにしたこと
・人から褒められたこと
・どのような人を尊敬していたのか
・勉強への取り組み方
・得意、不得意だった教科
・挫折した経験
・将来の目標や夢
この段階では、簡単な回答でも問題ありません。「1問につき△分間考えて、思い出せなければ次の質問に進む」など、自分なりのルールを決めて取り組むとスムーズに行えます。
3.エピソードを深掘りする
思いつく限り書き出したら、エピソードを深掘りしましょう。深掘りする際は、エピソードの根拠となる「なぜ印象に残っているのか」を追究するのがおすすめです。
たとえば、「△△を行ったことで喜んでもらえたから」と書いている場合、「どのような状況で、どのように考え行動した結果喜んでもらえたのか」を深掘りすれば、内容に信頼性が生まれます。深掘りした内容を基に、学んだことや感じたことも具体化してみてください。
4.モチベーショングラフに落とし込む
エピソードを深掘りできたら、モチベーショングラフを作成するのも大切です。
モチベーショングラフとは、人生の出来事についてモチベーションを基準にした波のようなグラフを指します。縦軸にはモチベーションの数値、横軸には学年を記載してください。
エピソードのなかから、自分の価値観がよく現れている内容や、頑張ったことといったプラスの内容と、辛かった経験・挫折したことなどのマイナスな出来事をピックアップしましょう。モチベーショングラフに落とし込めば、自分にとって重大な出来事や価値観が変わった時期などが可視化されます。
モチベーショングラフを作成すれば、自分に合った企業だけでなく避けたほうがよい仕事も明確になりやすいでしょう。
5.共通点をまとめる
最後に、深掘りしたエピソードやモチベーショングラフから共通点を見つけたら完成です。自分が輝けた経験の共通点を見つければ、強みや得意なことが明確になるでしょう。
また、自分が挫折した経験の共通点からは、苦手なことや不得意な環境などがわかります。
この内容をもとに、自分が持っている価値観への理解を深め、就活の軸を作成することが可能です。
なお、共通点が見つからない場合は、無理にまとめる必要はありません。ピックアップした内容から、特に傾向が強いと思うことを就活の軸の参考にするとよいでしょう。
自己分析には、自分史やモチベーショングラフ以外の方法もあります。具体的なやり方を知りたい人は、「自己分析のやり方おすすめ10選!正しく長所を理解するコツも解説」の記事を参考にしてみてください。
かんたん1分!無料登録自分史について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活に使える自分史の書き方のテンプレート例
就活にも使える、自分史のテンプレート例を紹介します。どのように自分史を作るか迷う方は参考にしてください。
印象深いエピソード
まずは印象に残っているエピソードを書き出しましょう。具体的に、情景がわかるように書き出すのがコツです。
自分の行動と結果
エピソードのなかで、自分がどのような行動をしたのか、その結果どうなったのかを書き出しましょう。この際、成功した部分も、失敗した部分も書き出しておくのがおすすめです。
就活で評価されるのは、結果よりも過程です。失敗であっても、学んだことや得たものがあるのであれば評価されるエピソードになります。
これまでの経験から学んだこと・感じたこと
経験を通して何を学んだか、感じたかを書き出しましょう。具体的に書き出すことで、このあとの分析に活用できます。
たとえば、「人と話すことが好きだと気づいた」「計画的に物事を進めるのが大事だと学んだ」のようにまとめておきます。
自分の特徴
最後に、経験を通して気づいた自分の特徴をまとめましょう。特徴に関しても具体的に深掘りするのがポイントです。
自分の特徴は長所や強みとなり、自己PRでアピールできるでしょう。たとえば、「リーダーシップがある」よりも「周囲をまとめるリーダーシップがある」のほうが、具体的でアピールにつながります。
自分史の段階から具体的な特徴を知っておくと、就活で活かしやすいのでおすすめです。自己PRについては「自己PRってなに?答え方のコツや注意点を例文付きで解説あ」の記事で紹介しているので、自己PRでの回答も意識しながら特徴を考えてみましょう。
かんたん1分!無料登録自分史について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活における自分史の書き方から評価されるポイント
就活では自分史を確認することで、就活生の人柄や経験が評価されています。自分史における評価ポイントを解説するので、ぜひ参考にしてください。
どのような人柄をしているか
自分史からは、就活生がどのような人柄をしているかが見られています。過去のエピソードから、「どのような考え方をしているか」「どのような価値観を持っているか」などが見えてくるからです。
人材を採用するにあたって、その人の性格や考え方が企業が求めるものかどうかを考えることは重要です。自己PRや志望動機などの質問項目だけでは、人柄を判断できないこともあるでしょう。採用してから「思っていた人物と違った」と思わないように、自分史からも人柄が確認されています。
どのような経験を持っているか
就活生がどのような経験をしているかも、自分史で評価されるポイントです。経験から得た強みや能力が何かを見極めています。
たとえば、チームで協力してきた経験があれば、仕事でも協力する姿勢を持ってそうだと評価されます。また、挫折を乗り越えた経験があれば、仕事の大変さも乗り越えてくれると想像できるでしょう。
企業は自分史から経験を確認することで、どのような能力を持っているかも確認しています。
企業との相性はよいか
自社との相性がよさそうかも、自分史で見ているポイントです。ミスマッチを起こさないように、就活生の人柄や能力を確かめています。
優秀な人材であっても、企業の方針と本人のやりたいことがずれていてはうまく活躍できません。また、持っている強みが仕事では活かせない強みの場合もあるでしょう。
企業は自分史を確認することで、就活生が持っているものが自社で活かせそうかを見ています。自分史を書く際は企業にアピールできる強みや考えを伝えているかも意識して書くことが大切です。
企業との相性を考えるためには、企業研究でどのような人材が求められているのかを確認しましょう。企業研究の進め方については、「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事で解説しているので参考にしてください。
かんたん1分!無料登録自分史について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活に使う自分史の書き方の注意点
自分史を書く際は、完璧にやろうとせず、思いつくまま書いてみるのが大事です。ここでは、自分史を考える際の注意点を解説します。
1.テンプレートを作成してから始める
自分史を書き出す前に、テンプレートを作成しておきましょう。テンプレートに沿って書き出すようにすると、内容をまとめやすくなります。
テンプレートを作成していない場合、時系列がバラバラになり、あとでまとめるのが大変になるかもしれません。「小学生」「中学生」のような時系列や、「考えたこと」「行動したこと」など大まかなわけ方でよいので、テンプレートを用意しておきましょう。
2.嘘や誇張は使わない
自分史を書く際は、事実をそのまま書いてください。嘘をついて自分をよく見せようとしても、実際のエピソードではないので内容が薄くなってしまいます。
また、自分史の内容は面接で聞かれることが多く、深掘りされた場合に苦しくなるでしょう。嘘がばれた結果、信頼をなくす可能性もあります。
就活で嘘をつくリスクについては、「就活で嘘をつくとどうなる?ばれる理由やリスクも解説」の記事で解説しているので参考にしてください。
3.客観性を持たせる
自分史を1人で作る際、客観性に欠けてしまう場合があるので注意しましょう。
エピソードの内容やアピールポイントなどについて、自分の視点と他人の視点では認識が異なる場合があります。また、自分では内容の整合性が取れているつもりでも、第三者が読むと意味が伝わらないケースもあるかもしれません。
そのため、自分史を作成したら、客観的な視点を取り入れるために家族や友人などに見てもらうのがおすすめです。自分の認識との差や、アピールにつながる内容かについてフィードバックをもらうとよいでしょう。
4.特別なことばかり思い出そうとしない
自分史に書く内容は、特別なエピソードでなくても問題ありません。記憶に残っていることをとにかく書き出してみましょう。日々の出来事だからこそ、学びにつながったり、成長につながったりしている場合もあります。就活で使うからといって、何か実績が必要なわけではありません。
大切なのは出来事の内容ではなく、自分が何を学んだかです。「周囲から褒められてうれしかった」「目立ってはいないが頑張った」のようなエピソードも書き留めましょう。
5.完璧な自分史を作ろうとしない
自分史を作る際は、完璧に作成しようと考えなくても大丈夫です。まずは思いついたことから書き出してみましょう。最初は下書き程度に考え、あとで時系列や内容別にまとめれば問題ありません。「完璧にしなきゃ」と考え、何も書けないほうが困ってしまいます。
また、自分史には正解がなく、自分のエピソードを自分らしくまとめる機会です。「アピールしなきゃならない」などと気負わず、とにかく書くことが自分史をまとめるコツといえます。
6.作成しただけで終わらない
自分史を作成しただけで満足せず、就活に活かしましょう。履歴書やエントリーシート作成に向けて、見返してみてください。
自分史を書き出すには労力や時間がかかるため、完成すると安心してしまうこともあるかもしれません。しかし、自分史の内容から自己PRを思いついたり、自分の価値観に気づけたりすることもあります。自分史が完成してからがスタートだと捉え、就職活動のアピール内容に落とし込んでみてください。
7.始めた理由を振り返る
自分史を考える際は、物事を始めた理由も思い出してみましょう。「なぜ始めたか」を振り返ることで、自分の価値観や考え方を明らかにできます。
何かを始める際には、その物事を選んだ理由があるはずです。ほかの行動ではなく、その行動を選んだ理由が思い出せれば、自分の価値観を自覚する材料になるでしょう。
8.やめた理由を振り返る
物事をやめた際は、その理由を振り返るのもおすすめです。やめた理由を振り返ることも、自分の価値観や考え方を明らかにする役に立ちます。
たとえば、「これ以上成長できなさそうだった」がやめた理由であれば、向上心が高かったり、成長を実感することが好きだったりするかもしれません。やめた理由からも自分の考えを分析できるので、自分史に書いておくのがおすすめです。
かんたん1分!無料登録自分史について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で自分史をより活用する方法
就活に自分史を活かすためには、内容をどの場面で使うか想定しておくのが大事です。ここでは、自分史の活用方法をまとめました。
履歴書やエントリーシート作成につなげる
自分史でわかった内容は、履歴書やエントリーシート作成に活かしましょう。強みや特徴、短所などをまとめておくことで、質問に答えやすくなります。
たとえば、自己PRの場面では、自分史で見つけた特徴や強みをアピールできます。長所短所が聞かれる場合も多いので、自分史で分析しておくとよいでしょう。
履歴書やエントリーシートの内容を確認し、「この項目で活かせそうだ」とイメージしておくと活用できます。エントリーシートの代表的な質問項目については、「就活のエントリーシートの書き方を一から解説!落ちないための注意点」の記事でまとめています。
面接で困った質問を自分史の項目に追加する
面接で聞かれて答えに困った質問があれば、自分史に書き足すのがおすすめです。過去のエピソードに材料がないか探してみましょう。
面接では、ある程度予想して回答を用意していても想定外の質問に困るケースがあります。「答えられなかった」で終わらず、聞かれた内容に対応するエピソードがないか思い出し、自分史を更新するのが大切です。エピソードを思い出しておけば、ほかの企業で同じ質問をされた際に役立つでしょう。
面接で想定される質問や対策を知りたい人は、「【プロ監修】新卒採用の面接で聞かれる40の質問と対策ポイント【質問シートあり】」の記事を参考にしてみてください。
定期的に自分史を見返す
自分史を作成したら、定期的に見返すようにしましょう。見返すことで過去を振り返る機会が増え、思い出せなかったエピソードを思い出したり、新たな発見をしたりすることもあるからです。
自分に合う仕事に就くためには、感覚の少しのずれや変化を見逃さずに軌道修正を行うことが大切です。多忙な就活中に自分と向き合う時間を作り、就活の軸やエピソードを確かめるためにも、定期的に自分史を振り返りましょう。
就活で一喜一憂したときに読み返す
就活中に浮足立ったり落ち込んだりした際に自分史を読み返すと、冷静さを取り戻せるのでおすすめです。たとえば、過剰なテンションによって失敗してしまったことを思い出せば、気を引き締め直す機会になるでしょう。
また、モチベーショングラフを見返して自分の落ち込みやすいポイントにはまっているとわかった場合、「以前も立ち直れたから大丈夫」と気持ちを立て直すことにつながります。
自分の状況を客観的に捉え、今何をすべきか見失わないようにするためにも、一喜一憂しやすいポイントを自分史で把握しておくのが大切です。
かんたん1分!無料登録自分史について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の自分史に書く内容を思い出せないときの対処法
就活で使う自分史に書く内容を思い出せない場合、日記や手紙を見返すのがおすすめです。ここでは、過去の出来事を思い出す3つの方法を紹介します。
アルバムや日記を読み返す
アルバムで写真を見返したり日記を読み返したりするのがおすすめです。忘れていたエピソードも、きっかけがあれば思い出せるでしょう。
たとえば、写真を見て「あんなこともあったな」と思い出せるケースもあります。また、日記には当時の感情や考えが書いてあるかもしれません。
昔になればなるほど思い出せなくなるのは仕方がないことです。アルバムや日記は貴重な記録なので、ぜひ確認してみてください。
家族や友人に聞く
家族や友人に自分の過去について聞いてみるのもおすすめです。自分は覚えていなくても、周りは印象に残っていたエピソードもあります。
また、自分のイメージと周囲から見たイメージが違う場合もあります。同じエピソードでも見え方が変わるので、第三者に聞くのがおすすめです。
手紙を読み返す
自分宛の手紙や年賀状を読み返してみてもよいでしょう。手紙は当時のエピソードや考えがわかる材料です。
また、年賀状には一言だけ近況が書いてあるかもしれません。当時のエピソードを思い出すきっかけにできるでしょう。
かんたん1分!無料登録自分史について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活における自分史の書き方例文
ここでは、自分史を書き出すやり方の例を2つ紹介します。これから自分史を作る人ややり方が不安な就活生は、ぜひ参考にしてみてください。
中学生時代の夏休みの宿題について
「中学生2年生のころ、友人とキャンプに行くために早めに宿題を終わらせた」という経験を深掘りします。
印象深いエピソード
中学2年生のころ、8月25日から2日間、友人4人と近所のキャンプ場に泊まる計画を立てた。両親に相談したところ、当日までに宿題を終わらせられるならよいと言われた。
自分の行動と結果
夏休み初日、どのようにすれば8月24日までに宿題を終わらせられるかスケジュールを立てた。まずは宿題の内容を全部書き出し、ボリュームや自分の得意・不得意から、それぞれにかかる時間を計算した。
また、塾の夏期講習や家族との帰省などの予定も書き出し、1日のうち勉強に充てられる時間を算出し、何をいつやるかすべて決めた。
予定を立ててからは、その日のノルマをクリアするまで遊びに行かないと決め、朝起きたらまず宿題を片付けるようにした。急な予定が入りスケジュールからずれることもあったが、その都度修正して無事に8月24日に宿題を終わらせ、キャンプに行くことができた。
経験から学んだこと・感じたこと
目的を達成するためには、事前に計画を立てることが大切であり、やみくもに手をつけていたら間に合わない可能性が高いと感じた。また、スケジュールを組むことでその日のノルマが明確になるので、「あとどのくらいやればよいか」と考えずに済み、宿題に集中できた。
この経験からわかる自分の特徴
目標達成のために、コツコツ努力を続けられる力がある。夏休みの間は友だちから急に遊びに誘われることも多かったが、「宿題が終わってから行く」と伝え、実際に有言実行できた意志の強さもある。
高校生時代のボランティア活動について
「高校2年生のころ、課外活動の一環として近隣の幼稚園でボランティア活動を行った」という経験について深掘りします。
印象深いエピソード
班にわかれ、それぞれ何をやるか役割を決めた。自分の班は折り紙担当となり園児と制作を行った。
自分の行動と結果
手先を使うのは苦手だったため、1週間前から練習をして、虫や動物などを折れるようにした。また、小さい子供と接するときに気をつけるポイントを親に質問した。
ゆっくり折り紙を折ることやこまめに褒めることなどを意識して、園児と一緒にたくさんの折り紙作品を作った。
経験から学んだこと・感じたこと
幼稚園児はこちらが思っているより理解力が低く、想定よりゆっくりしたペースで折る必要があると気づいた。また、褒められるとモチベーションが大きく上がることが途中からわかったため、「きれいに折れているね」「すごく上手だね」など、こまめに声をかけるようにした。
この経験からわかる自分の特徴
相手に合わせたコミュニケーションが取れる。行動スピードや会話の内容、どのようにすれば気持ちが上がるかなどを相手目線で考え、行動に移せる。
このようなエピソードは面接やESにも活用できます。
かんたん1分!無料登録自分史について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で自分史が書けず悩んでいるあなたへ
就職活動で活用するために自分史を作るなかで、「思ったように書けない」「自分だけでは昔のことを思い出せない」と悩む就活生も多いでしょう。自分史を作成するには、フォーマットに沿って思い出したことから書き出したり、過去の自分を知る人に客観的な視点で見てもらったりすることが大切です。
自分史の作成や内容に不安を抱く人は、就職エージェントに相談することも視野に入れてみてください。キャリアチケットでは、就活のプロが一人ひとりに寄り添い、過去のエピソードを思い出すきっかけを作ったり、エピソードのまとめ方や面接での効果的な伝え方などをアドバイスしたりします。
自分にマッチする企業から内定をもらえるよう、自分史を通じて効率よく自己分析を行い、アピールにつなげましょう。
かんたん1分!無料登録自分史について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。