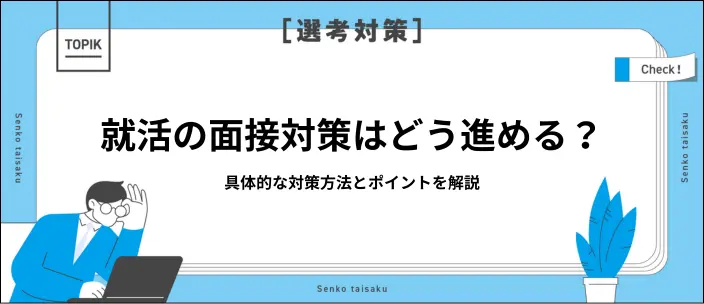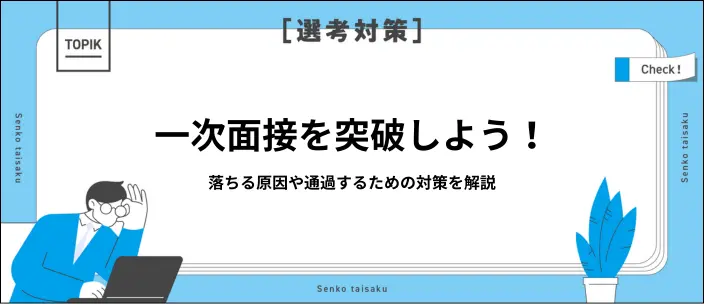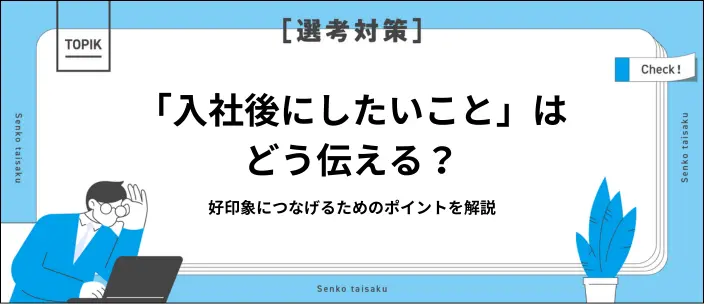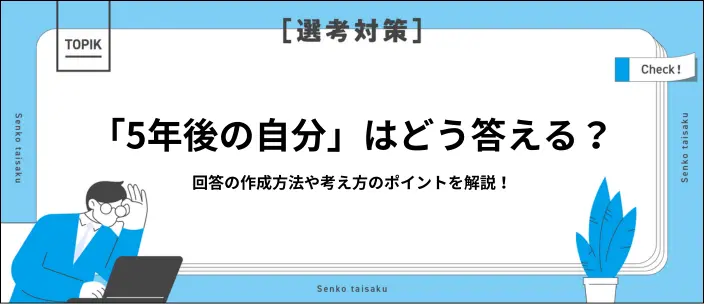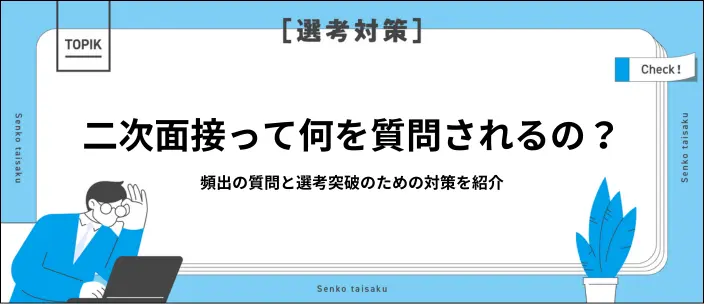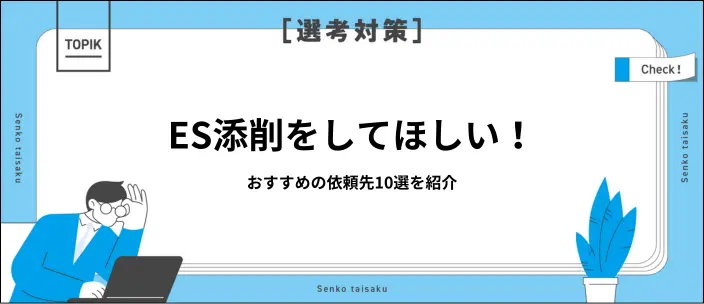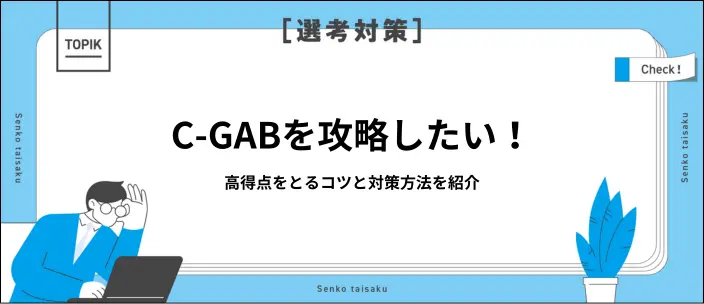このページのまとめ
- 面接に落ちるのは身だしなみや準備不足、企業との相性などの理由がある
- 面接の評価基準や落ちる理由は一次面接や二次面接、最終面接で異なる
- 面接に落ちる場合は、自己分析と企業研究を徹底してやり直そう

面接に落ちる理由を知って、対策を立てたいと考えている就活生も多いでしょう。就活を成功させるためには、面接に落ちたからといって落ち込まず、冷静に原因を分析することが重要です。
この記事では、面接に落ちる理由やフェーズごとの評価基準、面接に落ちないためにやるべきことなどを紹介。繰り返し面接に落ちて悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
かんたん1分!無料登録面接対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 面接に落ちる主な理由13選
- 1.基本的なビジネスマナーが身についていない
- 2.身だしなみに清潔感がない
- 3.態度に問題がある
- 4.事前の準備が足りない
- 5.就活に対する真剣さが足りない
- 6.質問の意図とズレた回答をしている
- 7.何を伝えたいのかが分かりにくい
- 8.会話のキャッチボールができない
- 9.話す内容にまとまりがない
- 10.自信が感じられない
- 11.入社意欲が感じられない
- 12.企業と相性が合わない
- 13.面接官が見ているポイントを知らない
- 「面接に落ちた=人格を否定された」わけではない
- 面接フェーズ別の評価基準
- 一次面接
- 二次面接
- 最終面接
- 面接で落ちる5つのフラグ
- 1.面接時間が予定よりも短い
- 2.回答に対して深掘りされない
- 3.面接官とあまり目が合わない
- 4.今後の案内が一切ない
- 5.面接官が就活の応援をしてくれる
- 面接に落ちると悩む人が今すぐやるべき8つの対策
- 1.自己分析を徹底する
- 2.企業研究をやり直す
- 3.よく聞かれる質問の回答を用意する
- 4.履歴書やESの内容と一貫性をもたせる
- 5.身だしなみを整える
- 6.面接マナーを身につける
- 7.大きな声でハキハキと話す
- 8.模擬面接で場慣れする
- 面接に落ちてうまくいかないとお悩みのあなたへ
面接に落ちる主な理由13選
まずは、面接に落ちる主な理由を解説します。あらためて面接に落ちたときのことを振り返り、心当たりがないかチェックしてみてください。
1.基本的なビジネスマナーが身についていない
面接に落ちてしまう原因の一つに、基本的なビジネスマナーが備わっていないことが挙げられます。面接は第一印象が非常に大切。
たとえば、面接室への入り方や挨拶の仕方、言葉遣いや身だしなみなど、基本的な所作ができていないと、それだけで「社会人としての自覚が足りない」と判断されてしまうこともあります。新卒採用では、企業は「将来の社員」として接しているため、礼儀がなっていないとマイナスの印象を与えてしまうのです。
ビジネスマナーは「できていて当たり前」と見られる部分。マナーが身についていないと、どれだけ能力があっても社会人としての信頼を得るのが難しいでしょう。事前に身につけておくことで、面接で本来の自分の良さや強みに集中でき、好印象につながります。
2.身だしなみに清潔感がない
面接に落ちる理由として、身だしなみが挙げられます。面接において、身だしなみは第一印象を決める重要な要素の一つです。身だしなみに清潔感がないと、面接官に不快感を与えるだけでなく、「社会人としての心構えができていない」「顧客対応してもらうときに不安」とマイナスイメージを抱かれてしまうでしょう。
面接の際にNGとされる身だしなみは、以下のとおりです。
・スーツにシワや汚れがついている
・スーツからタバコやきつい香水のにおいがする
・ワイシャツの裾や襟が汚れている
・ボタンが取れかかっている
・寝癖がついている
・前髪が目にかかっている
見た目の第一印象によって、面接官からの印象は大きく左右されます。面接に落ちた経験があれば、自分の身だしなみが整っていたか、今一度振り返ってみてください。
3.態度に問題がある
面接中の態度によっても、選考に落ちる可能性が高まります。企業イメージを保つために、社員一人ひとりの態度や振る舞いを重視する企業も珍しくありません。そのため、態度に問題がある場合は、自社が求める人材にふさわしくないと判断されて面接に落ちてしまいます。
具体的には、以下のような、面接官にマイナスの印象を与える態度は避けましょう。
・小さな声でぼそぼそと話す
・貧乏ゆすりをしている
・敬語を使わない
・面接官と一度も目を合わせない
・笑顔が少なく表情が暗い
ほかにも、「挨拶をしない」「会釈をしない」といった基本マナーを守る意識も大切です。選考に通過するためには、面接中の態度に気をつけて、面接官に「一緒に働きたい」と思われる必要があります。
4.事前の準備が足りない
面接に落ちる原因として、事前準備の不足は見逃せません。準備が不十分だと自分の強みや志望動機をうまく伝えられず、面接官に「熱意が感じられない」「自社と合わない」と判断されてしまう可能性があります。
たとえば、自己分析が浅いままだと、自分の価値観や適性が明確でないまま企業選びをしてしまい、結果的に相性の合わない企業ばかりにエントリーしてしまうかもしれません。また、企業研究を怠ると、面接で「なぜこの会社なのか」「どのように貢献できるのか」といった質問に説得力を持って答えられなくなってしまいます。
面接前の準備が不十分だと、努力がうまく伝わらず選考に通過できない可能性が高まるでしょう。自分の適性をしっかり理解し、企業ごとの特性を把握することが、的確なアピールにつながります。準備を怠らず、自信を持って面接に臨みましょう。
5.就活に対する真剣さが足りない
就職活動に対して真剣に取り組んでいない姿勢は、面接で大きなマイナス評価につながります。というのも、面接官は応募者の態度や言動から「この人は本気で働く気があるのか」を見極めており、その真剣さが欠けていると、どんなに経歴やスキルがあっても評価は下がってしまうためです。
たとえば、「御社で学ばせていただきたいです」といった受け身の姿勢を前面に出すと、主体性がないと見なされやすくなります。新卒採用では、スキル以上にポテンシャルや成長意欲が重視されるため、「どう成長し、どう貢献したいか」を伝えることが非常に大切です。
事前に業界研究を重ねた上で「御社の○○事業で、△△の経験を活かしながら□□に挑戦したい」と自分の目標を明確に語ると前向きな姿勢を見せられるでしょう。
このように、企業が求めているのは「自社に貢献したい」という主体的な意志を持つ人材です。就活に真剣に向き合い、自分の想いや意欲を具体的に言語化して伝えることが、面接突破には不可欠だといえるでしょう。
6.質問の意図とズレた回答をしている
面接では、質問の意図を正確に理解し、それに沿った回答をすることが非常に重要です。意図のズレた回答をしてしまうと、どれだけ話の内容が充実していても評価が下がる可能性があります。面接官は限られた時間の中で「この応募者は企業に適した人物か」を判断しようとしているため、質問の意図からズレていると「話が噛み合わない人」「意思疎通が難しい人」と受け取られやすく、コミュニケーション能力に疑問を持たれてしまうのです。
たとえば、「志望動機を教えてください」という問いに対して、「説明会での雰囲気がよかったからです」と企業の魅力だけを並べるのは、面接官の意図とはズレた答え方です。この場合、求められているのは「なぜその企業を選び、自分がどう貢献できるか」の説明。また、「自己紹介をお願いします」と言われた場面で、職務経歴や長所を延々と語るのも意図を外した例の一つです。
質問が聞き取れなかった場合や意味が曖昧に感じた場合は、素直に「もう一度お伺いしてもよろしいでしょうか」と聞き返す姿勢も大切。意図を的確に把握し、端的に回答することで、面接官に安心感を与えられます。質問の背景にある意図を読み取り、それに的確に答えることが、面接通過への大きな一歩です。
7.何を伝えたいのかが分かりにくい
面接で落ちる原因の一つに、「話の要点が伝わりにくい」という問題があります。結論を後回しにした話し方は、面接官にとって理解しづらく、結果的に評価を下げてしまうことがあるでしょう。なぜなら、面接では限られた時間の中で、端的かつ明確に自己PRや経験を伝える力が求められるからです。
結論を先に述べず、説明から入ってしまうと、聞き手は「何が言いたいのか」を探りながら話を聞くことになり、ストレスを感じやすくなります。たとえば、「あなたの強みは?」という質問に対して、「私は大学時代、○○サークルに所属していて…」と経緯から話し始めると、肝心の「強み」が見えにくくなってしまうでしょう。
要点を分かりやすく伝えることは、入社後の業務においても非常に重要です。面接の段階から「結論ファースト」を意識し、相手が理解しやすい話し方を身につけておくことが、選考通過の鍵となります。
8.会話のキャッチボールができない
面接では、質問に答えるだけでなく、会話のキャッチボールを意識することが大切です。一問一答のような受け答えだけでは、面接官との対話がスムーズに進まず、印象を下げてしまう可能性があります。
面接は一方的に話す場ではなく、相手とコミュニケーションをとる場です。面接官は質問の裏にある意図や、応募者の人柄、柔軟な受け答えができるかなども見ています。そのため、やりとりがぎこちなくなったり、質問に対して必要最小限の返答しかしなかったりすると、「この人は職場でも円滑なコミュニケーションが取れないのでは」と懸念されてしまうでしょう。
たとえば、「学生時代に頑張ったことは何ですか?」という質問に対して、「地域ボランティアです」とだけ答えると、会話が途切れてしまいます。ここで「地域に貢献したいという思いから活動に参加し、具体的には〇〇というプロジェクトで〇〇を達成しました」といったように、会話が広がるような答え方をすれば、相手も次の質問を投げかけやすくなるでしょう。
会話を続けるには、相手の話に耳を傾け、自分の発言が次のやりとりを生むかどうかを意識することがポイントです。会話のキャッチボールを意識することで、面接官との距離も縮まり、好印象につながります。
9.話す内容にまとまりがない
面接では、話の内容に一貫性とまとまりがあるかが非常に重要です。どんなに良い経験や実績があっても、伝え方にまとまりがないと面接官に響きません。面接官は限られた時間の中で多くの応募者と接しており、「この人は何を伝えたいのか」がすぐに分からなければ、印象に残りにくいもの。話があちこちに飛んだり、エピソードが長過ぎたりすると、評価されるべきポイントが埋もれてしまいます。
たとえば、「学生時代に力を入れたことは?」という質問に対して、部活動、アルバイト、ゼミなど複数の経験を並べて話してしまうと、聞き手は焦点が定まらず混乱してしまうでしょう。それよりも、「部活動のマネージャーとして〇〇の課題解決に取り組んだ経験」とテーマを一つに絞り、結果や学びを簡潔に伝えたほうが、説得力と印象が格段に上がります。
面接では「何を伝えるか」と同時に、「どう伝えるか」も評価対象です。話す内容は一つの軸を持ち、構成を意識して整理しておくことが、納得感のある受け答えにつながります。
10.自信が感じられない
面接で評価を下げる要因の一つに、「自信のなさ」が挙げられます。
どれだけ経歴やスキルが優れていても、自信のない受け答えでは、面接官に「この人は入社後に活躍できるのだろうか」と不安を与えてしまうでしょう。
企業が面接で見ているのは、能力だけでなく、前向きに仕事へ取り組む姿勢です。話す内容がネガティブだったり、声が小さく目線を合わせられなかったりすると、自信が感じられず、評価につながりにくくなります。
たとえば、「指示を待ってから行動します」と伝えると受け身な印象になりますが、「相手の意図をしっかり確認してから動くようにしています」と表現すれば、慎重で丁寧な姿勢が伝わります。
面接では、言葉だけでなく表情や姿勢も含めて「自分をどう見せるか」が問われるもの。話し方や態度に自信を持って臨むことで、あなたの意欲や可能性をしっかりアピールできるでしょう。
11.入社意欲が感じられない
面接で不合格となる要因の一つに、「入社意欲が十分に伝わっていない」という点があります。企業は、自社に対する関心や熱意があるかどうかを重視しており、それが感じられないと、他社志望なのではと判断されてしまう可能性があるのです。
その理由は、熱意のない応募者に対しては、入社後の定着率やモチベーションに懸念を持たれるため。志望動機が曖昧だったり、企業の事業内容や理念への理解が浅かったりすると、「この会社で働きたい理由が本当にあるのか?」と疑問を抱かれてしまいます。
入社意欲をしっかり伝えるには、企業研究を徹底し、「この企業だからこそ挑戦したい」「将来的にこういうポジションで貢献したい」といった具体的なビジョンを語ることが大切です。入社後のイメージが明確に伝わることで、面接官にも「長く活躍してくれそうだ」という安心感を与えられます。
12.企業と相性が合わない
面接に落ちる理由として、企業と自分の相性が合わないことが挙げられます。たとえ面接で素晴らしい回答をしても、企業の求める人物像や業務内容と自分のキャリアビジョンが一致していなければ、選考を通過することは難しいでしょう。
企業は、応募者がどれだけ自社の業務にフィットし、活躍できるかを重視しています。たとえば、自分の強みを「チームでの協力」を挙げた場合、その強みが志望する企業の文化や業務内容に活かせるかどうかが重要です。
そのため、面接の前に企業研究をしっかり行い、自分の強みやキャリアビジョンがその企業に適しているかどうかを再確認することが大切。自分の方向性と企業の方向性をしっかりマッチさせることが、選考突破への第一歩となるでしょう。
13.面接官が見ているポイントを知らない
面接に落ちる理由として、面接官が見ているポイントを理解していないことが挙げられます。面接官は、応募者が自社にとって適切な人材かどうかを見極めるために、いくつかの重要なポイントを見ています。たとえば、コミュニケーション能力や問題解決能力、そして企業にどれだけ貢献できるかという点です。これらのポイントを意識せずに面接を受けると、面接官が求める姿勢を伝えられません。つまり、面接の対策は主観的なものではなく、面接官の評価基準に基づいたものが必要です。
そのため、面接前に企業の求める人物像や評価基準をしっかり理解し、それに合わせたアピールを行うことが重要。自分の強みを企業が求める形で表現することで、より高評価を得られるようになります。
かんたん1分!無料登録面接対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
「面接に落ちた=人格を否定された」わけではない
志望する企業の面接に落ちたからといって、自分の人格まで否定されたと感じる必要はありません。なぜなら、面接はあくまでも「企業と応募者の相性を見極めるための場」であり、人間性の優劣を判断するものではないからです。
実際に、どれほどスキルや経験があっても、企業の社風や求める人物像と合わなければ内定に至らないことはよくあります。
面接の結果に過度に落ち込むのではなく、「今回は縁がなかった」と捉えることで、自分らしさを保ったまま次に進めるでしょう。改善点を見つけるための振り返りや実践は大切ですが、自分自身の価値まで疑う必要はありません。
自分に合った企業と出会うためのプロセスとして面接を位置づけることが、就職活動を前向きに進めるための第一歩でしょう。就活で落ち込みやすい場面と気持ちの切り替え方については、「就活で絶望したときの対処法7選!気持ちを切り替えるための考え方も解説」も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録面接対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
面接フェーズ別の評価基準
選考フェーズにおいて、一次面接と二次面接・最終面接は、それぞれ評価基準が異なります。以下で面接の各段階における評価ポイントを解説するので、参考にしてください。
一次面接
一次面接は人事部の採用担当者が面接官となるケースが多く、社会人としての基本的マナーやコミュニケーション能力が評価される傾向です。また、「自社について事前に調べているか」といった応募における最低ラインもチェックされるでしょう。
一次面接に落ちる主な理由として、以下が挙げられます。
・身だしなみが整っていない
・態度や言葉づかいに問題がある
・企業や職種について調べていない
・志望動機や自己PRの内容が薄い
・会話のキャッチボールが成り立たない
・入社したいという気持ちを感じられない
特に、応募者が多い大手企業などでは、一次面接の段階で学生の数をある程度絞り込む必要があるため、小さなマイナスポイントが不採用につながるケースも珍しくありません。
また、一次面接として、集団面接もしくはグループディスカッションを実施する企業もあります。そのため、事前の案内をよく確認して対策を練ることが大切です。集団で実施される場合は、ほかの学生の話を聞くときの態度も面接官に見られているので注意しましょう。
一次面接に通過できなくて悩んでいる場合は、「一次面接で落ちるのはやばい?選考突破できない原因と対策10選を解説」も参考にしてください。
二次面接
二次面接では、人事部の中堅社員や現場の管理者が面接官となるケースが多いといえます。一次面接と比べて、二次面接では、企業との相性や仕事への熱意が評価されやすい傾向です。
二次面接に落ちる主な理由として、以下が挙げられます。
・仕事に対する姿勢が受け身である
・企業が求める人物像とマッチしていない
・実際の業務に必要なスキルや知識が不足している
・業務への適性がない
一次面接が大量の応募者を一定の基準で絞り込む面接だとしたら、二次面接は「より優秀な学生を残す面接」だといえるでしょう。
最終面接
最終面接は社長や役員が面接官となり、経営者目線で将来的に事業を背負っていける人材であるかが評価されます。最終的に内定を出すか判断するため、経営理念への理解や共感も重要なチェックポイントの一つです。
一次面接と二次面接では「学生時代にどのような経験をしたか」といった過去に関する質問が多いのに比べ、最終面接では入社後のビジョンなど将来に関する質問が増えます。なぜなら、企業は質問に対する学生の回答から、「入社への熱意」や「将来のビジョンが自社の方向性と合致しているか」を見極めようとしているから。
そのため、以下のような場合は内定につながらない可能性が高いでしょう。
・会社の方向性と応募者のビジョンがズレている
・企業理解が足りない
・入社意欲が低いと感じられる
・社長や役員(面接官)との相性が悪い
最終面接において、一次面接や二次面接と同じ質問をされるケースも珍しくありません。志望動機やキャリアビジョンをブラッシュアップし、深掘りされても回答できるよう準備しましょう。
企業によっては上記の例に当てはまらず、一次面接から深い内容を質問するパターンも考えられます。そのため、応募先企業ごとに面接の傾向をあらかじめ把握しておくことが重要です。最終面接で落ちる理由については、「就活の最終面接で落ちる…理由と内定を勝ち取るための対策&質問例を紹介!」も参考にしてください。
また、就活全体のスケジュールについては「就活のやり方を徹底解説!基本的な進め方やスケジュールをご紹介」の記事にまとめているので、いつ面接が始まるか確認しておきましょう。
かんたん1分!無料登録面接対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
面接で落ちる5つのフラグ
面接で落ちる可能性が高いケースとして、以下のような状況が挙げられます。不合格フラグの状況に直面した場合でも、冷静に理由を特定して次に活かすことが大切です。
1.面接時間が予定よりも短い
面接時間が予定より短い場合は、選考に落ちる可能性が高いといえます。なぜなら、面接官が早く面接を終わらせようとするときは、学生に興味がなかったりコミュニケーションに不満を抱いていたりする可能性があるためです。
面接官が学生についてもっと知りたいと感じたときは、しっかりと時間をかけて質問するケースが多いといえるでしょう。一方で、面接官にあまりよい印象を与えられなかった場合には、面接時間が短くなる傾向です。
ただし、応募者が多い大手企業などの一次面接では、一定の評価ラインに達しているという理由で面接を早めに切り上げるケースもあるといわれています。
2.回答に対して深掘りされない
質問の回答に対して深掘りされない状況も、面接の不合格フラグの一つです。面接官が回答に対して深掘りせず簡単に流してしまう場合は、学生に興味がない可能性があります。
面接官は、候補者の回答をもとに、履歴書やESに書かれていない情報を得ようとするのが一般的です。しかし、質問の回答が抽象的過ぎたり回答にズレがあったりする場合は、さらなる深掘りがされないケースも考えられます。
3.面接官とあまり目が合わない
面接官に視線を向けてもあまりアイコンタクトがとれない場合は、面接に落ちる可能性が高いでしょう。メモを取りながら学生の話を聞く面接官もいますが、通常はできるだけ学生のほうを見て、話し方や仕草などを確認しています。
しかし、あまり興味がない学生に対しては、あえて目を合わせようとしないケースも珍しくありません。面接終了後に振り返ったときに、面接官とあまり目が合わなかったと感じられる場合は、結果を期待しないほうがよいでしょう。
4.今後の案内が一切ない
面接中に次の選考や入社に関する案内が一切ない場合は、不合格の可能性が高いといえます。実際に、面接中に次の選考や入社に向けた案内があるケースは少なくありません。なぜなら、目星をつけた学生がほかの会社に流れるのを防ぐ目的があるためです。
従って、次につながる案内がない場合は、合格ラインに達しておらず次の選考について伝える必要がないと判断されていると考えられます。
5.面接官が就活の応援をしてくれる
面接官が親身になって就活のアドバイスをくれる状況も、不合格フラグの一つだといえるでしょう。面接官から就活を応援するような言葉をかけられるのは、よい状況に思えるかもしれません。しかし、実際に採用につながる可能性は低いでしょう。
たとえ合格ラインに達していない学生であっても、できるだけ経験を次に活かして欲しいと考えて応援してくれる面接官も珍しくありません。応援だけをして自社のアピールなどがない場合は、不採用の可能性が高いと考えられます。
かんたん1分!無料登録面接対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
面接に落ちると悩む人が今すぐやるべき8つの対策
内定を勝ちとるためには、面接に落ちた理由を特定し適切な対策を講じることが大切です。ここでは、面接に落ちたときにやるべき具体的な対策を解説します。また、「就活の面接対策はどうする?よく聞かれる質問40選や選考突破のコツを解説」の記事でも面接対策についてまとめているので、併せて参考にしてください。
1.自己分析を徹底する
準備不足を理由に面接に落ちる場合は、自己分析からやり直すのがおすすめです。自己分析するときは、学生時代の経験を振り返り「頑張ったこと」「大変だったこと」「楽しかったこと」など、テーマ別にエピソードを書き出しましょう。
それぞれの経験を洗い出したら、次に「活動に取り組もうと思った理由」「生じた課題」「どのように課題を乗り越えたか」「経験から何を学んだか」といった視点で内容を深掘りします。
過去の経験に共通する考え方や行動パターンを分析すれば、自分の強みや弱み、大切にしている価値観が見えてくるでしょう。こうした自己分析の結果をもとに、企業選びの基準や自己PRの内容を考えてみてください。
自己分析の具体的な方法は、「自己分析シート作成で押さえるべきコツ|書き方のパターン・注意点も解説!」で詳しく解説しています。
2.企業研究をやり直す
面接に落ちる理由として準備不足がある場合は、あらためて企業研究に取り組むと効果的です。応募先企業のWebサイトや会社説明会で配布される資料、OB・OG訪問、業界地図などから、企業の情報を集めましょう。面接前に調べておくべき主な項目は、以下のとおりです。
・基本的な企業情報:企業理念、設立年、資本金、株式公開、事業拠点など
・代表取締役の情報:氏名、経歴、メッセージなど
・事業内容:サービスの詳しい内容、サービスの対象者など
・制度:人事、教育制度、休暇制度、福利厚生など
・採用情報:募集人数、募集職種、初任給など
応募先企業の基本的な情報を収集できたら、同業他社と比較した際の業界内における位置づけも把握しましょう。そうすることで、応募先企業の魅力や特徴を見出しやすくなります。また、、業態や規模、資本、商品の特徴などに着目し、ほかの企業とどのような違いがあるかを見ていくのがおすすめです。
企業情報を調べ終わったら、自分の価値観と企業の特徴がマッチしているか分析します。場合によっては企業選びから再考する必要もあるでしょう。企業研究を通して、志望動機につながるポイントが見えたり入社意欲が高まったりする効果が期待できます。
3.よく聞かれる質問の回答を用意する
面接の質問内容は企業によって異なるものの、定番の質問はほとんど変わらない傾向です。よく聞かれる質問については、あらかじめ回答を用意しておき、本番で自分の考えを伝えられるように準備しましょう。
面接でよく聞かれる質問は、以下のとおりです。
・自己紹介をしてください
・自己PRをしてください
・長所(短所)を教えてください
・周りからどのような性格だと言われますか?
・これまでに苦労したことと、それをどのように乗り越えたか教えてください
・尊敬する人は誰ですか
・10年後に何をしていたいですか
・志望動機を教えてください
・入社後どのような仕事をしてみたいですか
・あなたが考える弊社の強み(弱み)を教えてください
面接官は質問を通して、学生の人柄や価値観、自社の理解度、入社意欲を知りたいと思っています。「面接官は質問を通して何を知りたいのか」と考えることが、回答を用意するうえでのヒントになるでしょう。「面接で失敗談を聞かれたら?見つけ方や効果的な答え方・新卒向けの回答例文を解説」のコラムも併せてご確認ください。
逆質問を求められたときの回答例
面接の最後で、「何か質問はありますか」「最後にひと言ありますか」などと、面接官から質問されるケースがあります。逆質問を求められたときは、面接で自分をアピールできるラストチャンスと捉えて、積極的に回答しましょう。
具体例として、「貴社で活躍されている方々に共通する特徴はありますか」と仕事への前向きな姿勢を示したり、「本日の面接で貴社への入社意欲がより高まりました」と企業への熱意をアピールしたりすると効果的です。その際に、面接の機会をもらえたことへの感謝の気持ちもあわせて述べると、好印象につながります。
何も思いつかないからといって、「特にありません」と答えるのは避けましょう。なぜなら、面接官に「熱意に欠ける」「志望度が低い」などと懸念を抱かせる可能性があるためです。
また、逆質問やコメントの内容次第では評価を下げてしまう場合もあります。調べれば分かる内容を質問したり、長過ぎるコメントをしたりするのは控えましょう。その場の状況や面接官の立場を考慮したうえで、自分をアピールできるような逆質問を用意しておいてください。
4.履歴書やESの内容と一貫性をもたせる
面接で落ちないようにするためには、履歴書やESに書いた内容と一貫性ある回答をする必要があります。面接官は、提出された書類を元に質問するケースが多いので、履歴書やESに書いた内容を詳しく説明できるよう準備しましょう。
履歴書やESは提出する前にコピーを取っておき、面接前に内容を再確認するのがおすすめです。「自分をアピールするために何を強調したいのか」をあらためて考えておき、面接で焦点を当てるよう心がけましょう。
履歴書やESに書いた内容と面接の回答を矛盾させないためにも、嘘や誇張をせず、常に正しい情報を提供する姿勢が大切です。
5.身だしなみを整える
面接での第一印象をよくするためには、身だしなみを整える必要があります。就活の面接は基本的に短い時間しか与えられず、第一印象を面接が終わるまでに覆すのは非常に難しいからです。面接の際は、以下のような身だしなみに気を配ることが大切です。
・サイズの合ったスーツを着用する
・シャツはアイロンをかけてシワを伸ばす
・清潔感のある髪型にする
・靴は事前に磨いておく
就活において、身だしなみを整えることは基本マナーの一つだといえます。面接官に「一緒に働きたい」「仕事を任せても大丈夫そう」と思われるよう、清潔感のある身だしなみを心がけましょう。
6.面接マナーを身につける
面接を通過するためには、基本的なビジネスマナーを身につける必要があります。具体的な面接マナーは、以下のとおりです。
・面接会場には10分前までに到着する
・入室時はドアを3回ノックする
・面接官に指示されてから着席する
・面接官とアイコンタクトをとる
・背筋を伸ばして姿勢をよくする
・貧乏ゆすりをしない
面接では、挨拶や立ち振る舞いなどの面接マナーが評価を決めるケースも珍しくありません。そのため、面接マナーをしっかり身につけることで、面接官に好印象を与えられます。
7.大きな声でハキハキと話す
大きな声でハキハキと話すことも、面接対策として重要なポイントです。はっきりと話すことで面接官に自信がある印象を与えられるだけでなく、自分をしっかりとアピールできます。
また、会話のキャッチボールを意識して、相手の反応を確認しながら話すことも大切。面接官とのコミュニケーションがスムーズに進められるでしょう。面接に自信がない場合は、友人や家族に相手をしてもらって、何度も面接練習をするのがおすすめです。大きな声でハキハキと回答できれば、面接での印象アップも期待できるでしょう。
8.模擬面接で場慣れする
面接になると緊張して本来の力を発揮できない場合は、模擬面接で場慣れしておくと効果的です。模擬面接は大学のキャリアセンターのほか、友人や家族にもお願いできます。
面接官役の相手に評価項目を書いたチェックリストをあらかじめ渡しておけば、的確なフィードバックを受けられるでしょう。「話に矛盾はないか」「話すスピードや声の大きさは適切か」「身だしなみに清潔感はあるか」といった項目を重点的に確認してもらう必要があります。
模擬面接を気軽に頼める相手がいない場合は就活エージェントの利用もおすすめ。就活エージェントに相談すれば、応募書類の添削や面接対策など内定獲得に向けた幅広いサポートを受けられます。
就活生が身につけておくべき面接マナーについては、「面接マナーを知りたい就活生必見!質問例や持ち物もご紹介」も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録面接対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
面接に落ちてうまくいかないとお悩みのあなたへ
面接に落ちると「どうしたらよいのか分からない」と落ち込んでしまう就活生も多いのではないでしょうか。たとえ面接に落ちても、過度に自信をなくす必要はありません。
なぜなら、面接はあくまで企業と応募者の相性を確かめる場であり、面接に落ちたからといって人格を否定されているわけではないからです。
面接で落ちた理由が分からず、このまま就活を続けても内定がもらえるか不安な場合は、就活エージェントに相談してみましょう。
就職エージェントのキャリアチケットでは、自己分析や業界研究から面接対策まで、内定獲得に向けたサポートをしています。面接に落ちてうまくいかないと悩んでいる方は、ぜひ利用してみてください。
かんたん1分!無料登録面接対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら