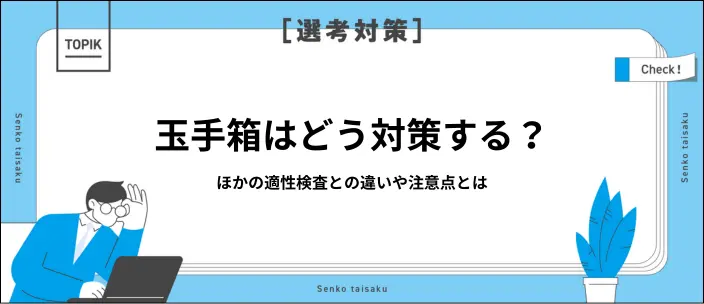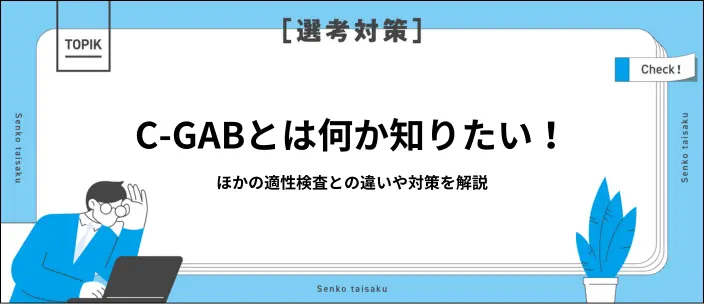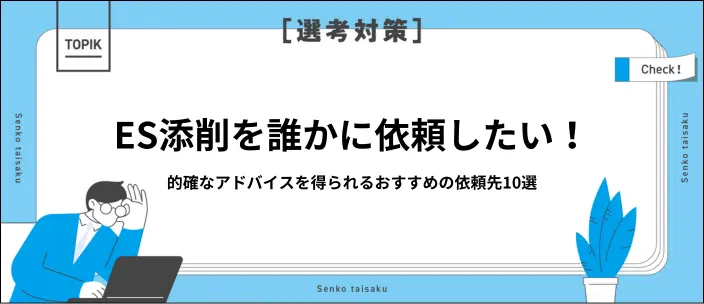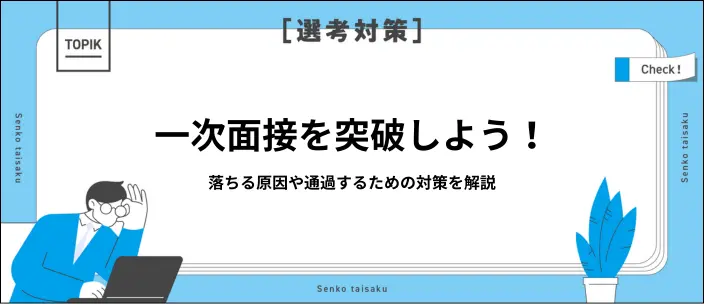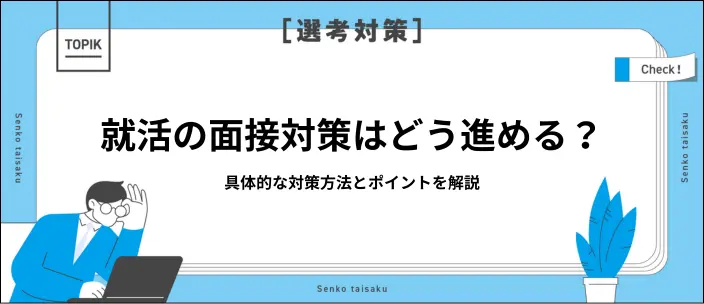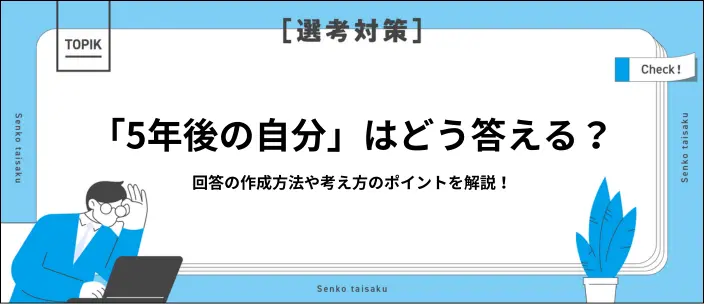このページのまとめ
- SPIは、就活で企業が応募者の能力や資質を測るために行われる適性検査の一種
- SPIの種類の中で、新卒の就活で用いられるのは「SPI-U」が最もポピュラー
- SPIの受検形式はWebやテストセンターなどの4種類がある
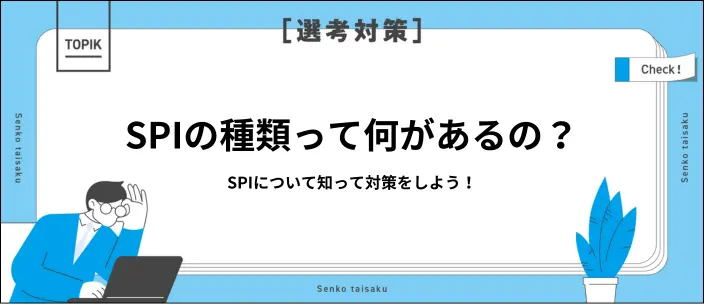
SPIの種類や受検形式が多くて、どのように対策をすれば良いか迷っている就活生は多いでしょう。一口にSPIといっても、その種類は企業の採用ニーズに合わせて数多くあります。就活生の中には、SPIの種類や特徴について知りたいという人もいるでしょう。
この記事では、それぞれの特徴や受検形式の違いを整理し、効率的にSPI対策を進める方法を解説。SPI以外で導入されることが多い6種類の適性検査も紹介します。
かんたん1分!無料登録SPI対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- SPIとは
- SPIの種類は大きく3つ
- SPI-U
- SPI-H
- SPI-G
- SPIの検査内容とは
- 能力検査
- 性格検査
- SPIの4つの受検形式
- 1.テストセンター
- 2.Webテスティング
- 3.ペーパーテスティング
- 4.インハウスCBT
- SPI受検に向けてやるべき準備
- 志望企業がどの適性検査を採用しているか確認する
- 模擬試験で実力を把握する
- 苦手分野を優先して理解する
- 繰り返し演習でスピードを上げる
- SPIの検査ごとの対策方法
- 能力検査の対策法
- 性格検査の対策法
- SPI以外の適性検査6種類の内容と対策
- 1.玉手箱
- 2.GAB
- 3.CAB
- 4.TG-WEB
- 5.eF-1G
- 6.内田クレペリン検査
- SPIの種類を把握し対策したいと考えているあなたへ
SPIとは
SPI(Synthetic Personality Inventory)とは、応募者の能力や資質を測るために行われる適性検査の一種です。就活で導入される適性検査は数多くありますが、その中でもメジャーな検査といわれています。定期的にバージョンアップが実施され、現在利用されているのは「SPI3」です。一般的にはバージョンに関係なく「SPI」と呼ばれています。
SPIは、性格検査と能力検査の2つで構成され、仕事への適性や応募者の人柄、どのような組織に馴染みやすいのかを判断することが可能。企業側は、検査結果を選考の採否や面接の参考にしたり、入社後の配属先を決めたりするときに使うようです。
SPIについては、「SPIとは?今さら聞けない出題内容や対策のコツを就活のプロが解説!」の記事でも解説しているので、あわせて参考にしてください。
かんたん1分!無料登録SPI対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPIの種類は大きく3つ
就活で多くの企業が採用しているSPIには、主に3つの種類があります。大学生が受けるSPI-U、高校生が対象のSPI-H、そして社会人向けのSPI-G。どの形式を受けるかによって出題範囲や特徴が変わるため、まずは種類の違いを正しく理解することが大切です。
SPI-U
大学生が就活で受けるSPIは、主に「SPI-U」です。特徴を理解すれば、効率よく対策できます。SPI-Uは新卒採用向けに作られており、大学・短大・専門学校・大学院の学生が受験することが多いテストです。性格検査と基礎能力検査のほか、英語能力や構造的把握力を測る問題も出題されるため、出題範囲が幅広くなっています。
SPI-Uを受けるなら、まずは出題範囲と形式を把握してから、問題集や模擬テストで練習することが大切です。
SPI-H
高卒採用の選考で使われるSPIは「SPI-H」で、主に高校生が受けることが多い適性検査です。SPI-Hは大卒向けのSPIとは異なり、出題範囲が狭く、基本的に「性格検査」と「基礎能力検査」の2種類だけで構成されています。そのため、大学生が就活で受けるSPI-Uと混同しないよう注意が必要です。
SPI-G
社会人のキャリア採用で使われるSPIは「SPI-G」で、基本的には中途採用向けの適性検査です。
SPI-Gは、性格検査と基礎能力検査を中心に構成されています。大学生向けのSPI-Uと異なり、「地図」「方角」に関する問題が出題される点が特徴です。さらに、企業によってはオプションで英語能力検査が追加される場合もあります。
大学生が就活で受けるのは原則として「SPI-U」なので、SPI-Gを特別に対策する必要はありません。ただし、種類の違いを知っておくと就活の情報収集がよりスムーズになり、不安を軽減できます。
SPI対策については「SPI対策をご紹介!出題内容やポイントを把握して適性検査を突破しよう」でも紹介しているため、あわせてチェックしてみてください。
かんたん1分!無料登録SPI対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPIの検査内容とは
SPIは、能力検査と性格検査の2つで構成されているのが特徴です。この項目では、それぞれの検査内容について解説します。
能力検査
能力検査は、働くうえで必要な基礎能力を測る検査で、内容は「言語分野」と「非言語分野」の2種類が主流。企業によっては、英語・構造的把握力が出題されるケースもあるようです。
言語分野
言語分野は、国語問題がメインです。具体的には、空欄補充や語句の意味、2語の関係、熟語の成り立ち、文の並び替え、長文読解など。言葉の意味や話の趣旨を掴んで理解する力を測る問題が出題されます。
非言語分野
非言語分野は、数学問題がメインとなります。出題内容は、推論や順列、組み合わせ、確率、割合と比、集合、損益の計算、料金の割引、代金の精算、仕事算、速度算など。数的処理や論理的思考力を測るものです。
英語
企業によっては、「ENG」と呼ばれる英語の問題が出題されることもあります。内容は、同意語や反意語、空欄補充、誤文訂正、英英辞書、和文英訳、長文読解など。難易度は中学・高校〜大学受験レベルです。
構造的把握力
企業によっては、構造的把握力検査があります。構造的把握力検査では、物事の共通点や関係性を整理して理解する力を測定。内容は、類似の問題構造の選択、文章計算問題のグループ分けなどがあります。
「SPIの非言語問題とは?回答のコツや対策方法を解説」では、SPIの非言語問題の対策を紹介しているため、あわせてご参照ください。
性格検査
性格検査は、応募者の人となりを掴むための検査。日ごろの行動や物事の考え方についての質問に答えることで、「どんな性格か」「どのような仕事に適しているか」といった傾向を判断するものです。質問には2つの選択肢が提示され、自分に当てはまる方を選択して回答します。
SPIとよく比較される一般常識問題との違いについては「SPIと一般常識問題の違いは何?それぞれの特徴や対策方法を解説」で紹介しているため、あわせてご確認ください。
かんたん1分!無料登録SPI対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPIの4つの受検形式
SPIには、4つの受検形式があります。
それぞれ進行の仕方や注意点が異なるので、形式ごとの違いを理解しましょう。志望する企業がどの受検形式でSPIを実施するのか、事前に確認しておくことも大切です。
1.テストセンター
テストセンターは、専用の会場でパソコンを使って受検し、結果を複数の企業で利用できるのが特徴の形式です。
テストセンターは、SPIを開発したリクルート社が全国に設けている会場で実施されます。就活生は都合の良い日程・時間・場所を予約し、専用のパソコンで受検。事前に自宅で性格検査を済ませておく必要がある点には注意が必要です。
テストセンター形式は、一度受験すると結果を1年間使い回せるメリットがあります。最初の試験でしっかり準備して高得点を取れば、以降の就活で繰り返し受ける必要がなくなり、効率良く活動を進められるでしょう。
2.Webテスティング
Webテスティングとは、インターネット環境に接続したパソコンから受検する形式のこと。試験を受ける場所や時間にとらわれないため、自宅や学校など、好きな環境を選べるのが特徴です。また、指定された期間内に行えば良いので、十分な対策をしてから受検できます。
ただし、スマートフォンからの受検は不可なので注意しましょう。
3.ペーパーテスティング
ペーパーテスティングは、応募企業が指定する会場でマークシートに記入して受ける筆記試験形式。4つの受検形式の中で唯一パソコンを使わない形式です。
ペーパーテスティングは、面接や会社説明会と同じ日に行われることもあり、効率的に選考を進めたい企業が導入しています。また、不正防止の観点からも利用されることも。ただし、実施する企業数はテストセンターやWebテスティングより少ないのが特徴です。
ペーパーテスティングは採用企業は少ないものの、対策自体はSPIの他形式と大きく変わりません。実施が決まった場合は、鉛筆や消しゴムなどの筆記用具を事前に準備し、当日に焦らないようにしておきましょう。
4.インハウスCBT
インハウスCBTは、応募先企業が用意したパソコンで受検する形式で、4つの受検形式の中でも最も導入が少ない方式です。
自社内に専用パソコンと監督者を用意する必要があり、実施する企業にとって負担が大きいため、導入している企業は多くありません。その一方で、結果をすぐに確認できるというメリットがあり、一部の中小企業や採用人数の少ない企業で利用されています。
インハウスCBTを導入する企業は少ないため、就活生が特別な対策をする必要はほとんどありません。ただし、もし案内があった場合は「企業のパソコンで受ける形式である」という点を理解し、落ち着いて受験できるよう心構えをしておきましょう。
「SPIの内容は?複数ある受検方法による違いを解説!」の記事でも、SPIの受検形式について触れています。
かんたん1分!無料登録SPI対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPI受検に向けてやるべき準備
SPIの種類や受検形式を理解したら、次は具体的な対策に取り掛かりましょう。効率良く高得点を狙うには、志望企業の出題形式を確認し、自分の実力を把握して、苦手分野を重点的に対策することが大切です。ここでは、SPIを受けるための準備方法を解説します。
志望企業がどの適性検査を採用しているか確認する
SPI対策を始める前に、まずは志望企業がどの適性検査を採用しているのかを必ず調べましょう。
SPIは受検形式によって出題内容が変わるほか、志望企業がSPI以外の適性検査を実施している場合もあります。形式を知らずに勉強を始めてしまうと、当日に「やっていない範囲が出た」「不要な分野を勉強して時間を無駄にした」といった事態になりかねません。
適性検査の種類を調べる方法は以下のとおりです。
・企業の採用ページや募集要項を確認する
・口コミサイトで先輩の体験談を探す
・OB・OG訪問で直接質問してみる
もし情報が見つからない場合は、最も利用されるテストセンター形式のSPIを想定して準備すると安心でしょう。具体的には「基礎能力検査」「英語能力検査」「構造的把握力検査」を網羅して学習すれば、他形式にも応用しやすく効率的に対策できます。
やみくもに勉強を始めるのではなく、まずは「志望企業がどの適性検査を実施するのか」を調べることがSPI対策の近道です。正しい情報を集めて、自分に必要な範囲を効率良く勉強しましょう。
模擬試験で実力を把握する
SPI対策を始めるときは、まず模擬試験や参考書の実践問題を解いて、今の実力を確認することが大切です。
事前に模試を受けることで、自分の得意分野と苦手分野を把握でき、重点的に勉強すべきポイントが明確になります。
SPIは幅広い分野が出題されるため、まず模擬試験を通じて全体を一度体験しましょう。自分の弱点を把握したうえで、限られた時間を効率的に使うことが合格への近道です。
苦手分野を優先して理解する
SPI対策では、模擬試験で見つけた苦手分野を優先し、まずは解法を理解することが効果的です。問題をたくさん解くだけでは、解き方を知らないまま間違いを繰り返してしまい、効率が悪くなります。先に正しい解法を理解すれば、短期間で得点力を伸ばすことが可能です。
苦手分野は「量より質」で攻略するのがSPI対策の近道です。解法を理解してから演習を重ねることで得点につなげられるので、最初は参考書の解説を徹底的に活用しましょう。
繰り返し演習でスピードを上げる
SPIで高得点を目指すなら、問題を繰り返し解いてスピードを上げることが重要です。SPIの問題は中学~高校レベルですが、1問あたり数十秒~1分程度で回答する必要があり、単に解けるだけでは時間内に全問解答できません。スピードと正確さの両方が求められるでしょう。
繰り返し演習することで、問題に慣れ、自然と回答スピードが上がります。一冊の参考書を完璧にすることを優先し、毎日少しずつ積み重ねる学習を習慣化しましょう。これがSPIで安定して高得点を取る秘訣です。
SPIの勉強を効率的に進めるなら、「SPIのコツを知っておこう!突破するための基礎から勉強法をご紹介」の記事もあわせてご覧ください。
かんたん1分!無料登録SPI対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPIの検査ごとの対策方法
SPIは「能力検査」「性格検査」それぞれの特徴を理解したうえで対策することが大切です。
検査ごとの効果的な対策方法を紹介します。
能力検査の対策法
能力検査は、出題範囲や出題パターンがある程度決まっているため、問題集を何度も解く対策法が効果的です。問題集は2〜3冊に絞るのがポイント。同じ問題集を繰り返し解き、苦手分野や問題の考え方を理解しておけば、本番でも素早く回答できます。
また、練習をするときには、時間を測りましょう。SPIは問題数に対して、制限時間が短いのが特徴です。練習の段階から時間を測り、1問あたりにかかる時間を把握しておきましょう。自分のペースが分かっていれば、本番でも焦らずに検査に臨むことができます。
性格検査の対策法
性格検査では、直感に従い、素直に回答することが一番の対策法です。
自分らしくない回答をしても、その後の面接で矛盾が生じる恐れがあります。自分をどのように見せたいかではなく、自分がどのような人物であるかを伝えるためにも、正直に回答しましょう。
SPIの性格検査が不安な方は、「SPIの性格検査から分かることとは?目的と特徴を知って対策しよう!」の記事もご一読ください。SPIの性格検査の対策について詳しく解説しています。
また、就活ではSPIだけでなく、あらゆる選考過程の対策や準備が必要です。「就活のやり方と流れを解説!準備から内定までのポイントと相談先も紹介」の記事を参考に、万全の態勢で就活に臨めるようにしましょう。
かんたん1分!無料登録SPI対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPI以外の適性検査6種類の内容と対策
就職活動で行われる適性検査は、SPI以外にも玉手箱やGABなどさまざまな種類があり、出題される傾向や問題数、制限時間が異なります。
この項目では、適性検査の中でも比較的導入されることが多い6種類を紹介するので、参考にしてください。
1.玉手箱
玉手箱も、新卒の就活選考では導入頻度が高い検査です。
SPIと同じく、能力検査と性格検査の2つで構成され、能力検査の出題内容は「言語」と「計数」に分かれます。企業によってはさらに「英語」が追加されることもあるようです。
玉手箱は、1問あたりにかけられる時間が短く設定されていることと、同じ形式の問題が続けて出題されることが特徴。苦手な形式にあたると、正答率が伸びづらくなってしまうので、対策で苦手な形式を把握し、慣れておくことがポイントです。
2.GAB
GABは総合職用の適性検査で、総合商社や金融、コンサルなどの業界で用いられることが多いです。
検査内容は、性格検査と能力検査からなり、能力検査は「言語」と「計数」の2科目。ほかの適性検査と比べ、難易度が高いといわれています。
GABの受検形式はペーパーテスティングとWebテスティングがあり、形式により制限時間や難易度が異なるため、受検前に確認しておくと良いでしょう。
3.CAB
CABはIT関連職を対象とした適性検査のこと。専門職の適性やバイタリティ、ストレス耐性を明らかにするもので、IT企業の選考で多く導入されています。
受検形式は、GABと同様にペーパーテスティングとWebテスティングの2種類ありますが、Webテスティングが主流のようです。
検査内容は、「暗算」「法則性」「命令表」「暗号」といった、コンピュータ関連の専門職に必要な知的能力を試す科目からなる能力検査と性格検査で構成されています。問題の難易度は比較的高く、制限時間も短いため、問題集を活用した対策をしっかりとしておくことが大切です。
4.TG-WEB
TG-WEBは、SPIや玉手箱に比べるとマイナーですが、大手金融や外資系企業で実施されることもある検査です。
検査内容は、ほかの多くの適性検査と同様に性格検査と能力検査で構成され、能力検査は「言語」と「計数」の2科目。ほかの適性検査では見られない図形などの独特な問題が含まれるため、注意が必要です。また、企業によっては、能力検査に「英語」科目が加わることもあるので確認しておきましょう。
TG-WEBは、「従来型」と「新型」の2つのパターンがあり、パターンごとに問題数や難易度が異なります。特に、主流とされる「従来型」は難解な問題が多いようです。応募先企業がTG-WEBを行う場合は、受験前にパターンごとの対策をしておくと良いでしょう。
5.eF-1G
eF-1Gは、数ある適性検査の中でも、難易度が高いことで知られる検査です。近年、幅広い業界の有名企業で導入されるケースが増えています。
性格検査と能力検査の2つで構成されている点は、ほかの多くの適性検査と同様です。しかし、能力検査の内容は独特で、連想ゲームのような問題や記号を数え上げるような問題が出題されます。1問あたりの制限時間も短く、回答には柔軟な思考力や発想力が必要です。
6.内田クレペリン検査
内田クレペリン検査は、日本で最初の心理テストとされる検査で、簡単な作業から受検者の能力や資質をみるものです。
検査は独特で、一列に並んだ1桁の数字の足し算を、1分ごとに行を変えながら繰り返すという内容。休憩をはさんで前半15分、後半15分で実施されます。検査内容の特性から、受検形式はペーパーテスティング形式のみです。
内田クレペリン検査では、作業能率から能力面の特徴を、作業をするときの癖から性格面の特徴を判定します。理想とする結果は企業により異なりますが、誤答が多かったり、1分間の作業量の増減が激しい場合、不採用になることもあるようです。一定時間、同じ作業をムラなく正確に繰り返す練習や、アプリなどを活用した対策をして、検査に慣れておくと良いでしょう。
SPIだけでなく、あらゆる適性検査が導入されている可能性を念頭に置き、適切な対策をしましょう。「就活の適性検査とは?検査の種類や特徴、受ける際のポイントをご紹介!」の記事も一読し、それぞれの適性検査の種類や特徴をチェックしてみてください。
かんたん1分!無料登録SPI対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPIの種類を把握し対策したいと考えているあなたへ
SPIは就活で多く導入されている適性検査であり、種類や形式、出題内容を正しく理解することが合格への第一歩です。大学生が受けるSPI-Uを中心に、能力検査(言語・非言語・英語・構造的把握力)や性格検査の特徴を押さえ、受検形式の違いも把握して適切な対策をしましょう。
SPIや適性検査の対策に不安を感じている方は、プロのキャリアアドバイザーに相談するのもおすすめです。キャリアチケットでは、一人ひとりの就活状況や志望業界に合わせたアドバイスを受けられるので、効率良く準備を進められます。
無料で登録でき、オンラインでもサポートを受けられるため、忙しい学生も活用しやすいのが魅力です。SPIや就活に関する悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
かんたん1分!無料登録SPI対策について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の執筆者
梶川沙綺(かじかわさき)
新卒でレバレジーズ株式会社に入社。年間1000名以上の就活生の支援を行い、入社3年目で神戸支社の立ち上げに携わる。現在は本社でサービスの向上にも関わりながらキャリアコンサルタント国家資格取得に向けてスキルアップ奮闘中。