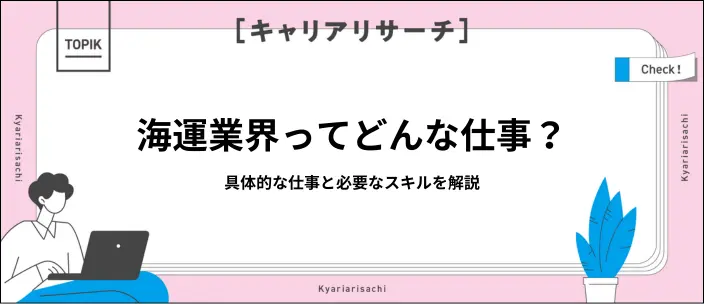このページのまとめ
- 出版業界は書籍や雑誌などの出版物を制作する業界
- 出版業界の職種には「編集者」「ライター」「出版営業」などがある
- 出版業界のなかでも電子書籍の市場規模は拡大傾向にある

「出版業界について詳しく知りたい!」「どんな職種や仕事内容があるの?」と気になる就活生も多いでしょう。就職活動を成功させるためには、業界について詳しく知っておくのが重要です。どのような業界なのか、どのような職種があるのか学びましょう。
この記事では、出版業界の現状や今後、仕事内容などについて解説しています。内定獲得に向けて重要な内容なので、ぜひ参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 出版業界とは?基本的な構造も解説
- 出版社
- 出版取次
- 書店
- 出版業界の主な職種と仕事内容
- 編集者
- ライター
- 制作・校閲
- フォトグラファー
- 広告
- 出版営業
- ブックデザイナー(装丁家)
- 書店員
- 出版業界が抱える4つの課題
- 1.紙媒体の市場縮小
- 2.返品率の高さ
- 3.オンラインメディアへの展開
- 4.電子書籍化にともなう権利処理とコスト
- 出版業界が力を入れる6つの取り組み
- 1.電子書籍
- 2.クロスメディア
- 3.書籍の付録の強化
- 4.インターネット書店への注力
- 5.定額読み放題サービス
- 6.オーディオブック
- 出版業界と関わりの深い業界
- 印刷業界
- 広告業界
- 通信業界
- アパレル業界
- 出版業界に就職するためのポイント
- 自分にあう職種を選ぶ
- 企業の規模にこだわらずに選ぶ
- 想像力を鍛える
- 出版業界に向いている人によくある特徴
- トレンドに敏感である
- 雑誌や本などの活字が好き
- 柔軟な発想やアイデアを持っている
- こだわりをもって努力できる
- 出版業界への就職を目指すあなたへ
出版業界とは?基本的な構造も解説
出版業界とは、書籍や雑誌などの出版物を社会に送り出す業界です。出版業界を大きくわけると、「出版社」「出版取次」「書店」の3つに分類できます。それぞれについて詳しく解説するので、参考にしてください。
出版社
出版社とは、書籍や雑誌の制作、および発行を行う会社です。出版社も、ジャンルを問わずに手掛ける「総合出版社」と、特定の分野に特化した出版社に分類できます。
出版社が行う仕事は幅広く、「出版物の企画」「ライターや作家への執筆依頼」「印刷会社への依頼」「校正・検閲」「製本」なども対象です。
また、扱うジャンルもさまざまであり、次のような内容が扱われています。
・ビジネス書
・絵本
・参考書
・雑誌
・地図
就職活動で出版社を目指す際には、どのような範囲の仕事を行っているか、どのようなジャンルを扱っているか、明確にしておくのが重要です。
出版取次
出版取次とは、出版社と書店の取り次ぎを行う会社を指します。出版社が制作した書籍を全国の書店に届けるのが仕事です。また、書店で売れ残った書籍を回収し、出版社に返品する仕事も担います。
書店
書店とは、制作した書籍を販売する店です。ジャンルを問わずに扱う書店もあれば、特定の分野に特化した書店もあります。
また、店舗にどのような書籍を置くか、どの書籍をPRするかを考えるのも書店の仕事です。出版取次や営業と話をしながら、書籍の販売を行います。
出版業界について詳しく知るためには、業界研究セミナーがおすすめです。業界研究セミナーについては「業界研究セミナーとは?気になる内容と参加するメリットを解説!」も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
出版業界の主な職種と仕事内容
ここでは、出版業界の主な職種と仕事内容について紹介します。就職活動を進めるためには、どのような職種があるか調べておくのが欠かせません。
自分にあう仕事を見つけるためにも、参考にしてください。
編集者
編集者とは、書籍や雑誌などの編集を行う職種です。内容の企画や取材、撮影のディレクションなど、書籍を作成するための全工程に関わります。
編集の仕事範囲は広く、書籍や出版についての幅広い知識が求められるのが特徴です。また、仕事の進捗が遅れている場合は、担当に催促する必要もあり、コミュニケーションが求められるのを知っておきましょう。
ライター
ライターは、制作物の執筆を行う仕事です。書籍やインターネットなどを用いて情報を集め、執筆を行います。企画内容によっては、取材やインタビューを行うケースもあるので覚えておきましょう。
制作・校閲
制作とは、書籍の作成やデザイン編集を行う仕事です。校閲では、誤字脱字がないかの確認や、内容に間違いがないかの確認などを行います。
制作と校閲については、担当が同一の場合と、わかれている場合があります。企業ごとに違うので、あらかじめ確認しておきましょう。
フォトグラファー
フォトグラファーの仕事は、出版物に掲載する写真を撮ることです。インタビュー先やイベント会場での撮影はもちろん、スタジオ内での撮影を担当するケースもあります。
広告
広告は、出版物を消費者に知ってもらうために、宣伝を行う職種です。プレリリースを用いて広告したり、イベントを実施したりします。近年では、SNSを使用した広告活動も盛んです。
優れた出版物も、消費者に知ってもらえなければ売上が出ません。企業の売上を左右する、重要な仕事なので覚えておきましょう。
出版営業
出版営業は、出版物を書店に置いてもらうために、営業活動を行う職種です。宣伝や広報、制作に携わる場合もあります。
また、書店の売上を増やすために、サポートを行うのも出版営業の仕事です。出版物の並べ方やポスターの提案などを行い、自社の出版物を置いてもらえるように働きかけます。
ブックデザイナー(装丁家)
ブックデザイナーは、本の装飾を行う職種です。装丁家とも呼ばれます。
ブックデザイナーの仕事は、本の表紙やカバー、帯なども含めた、出版物の外観全体の装飾です。デザインによっても売上が変わるので、消費者の注目を集めたり、購買意欲を高めるためにも欠かせない仕事になります。
書店員
書店員とは、書店で働く店舗スタッフのことです。書店員は、次のような仕事を担っています。
・検品
・レジ打ち
・清掃
・POP作り
・お客さまの案内
書店員は消費者に直接本を届ける存在です。また、対応1つで売上が変わる場合もあるので、消費者のニーズに対してどのように応えるか考えるのが欠かせません。
企業によっては、作家イベントやサイン会のサポートをする場合もあり、幅広い対応が求められる職種といえます。
出版業界の職種について知るためには、業界研究が欠かせません。業界研究の進め方については「【21卒 就活お悩み相談室 #5】業界研究ってどう進めればいいの?」も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
出版業界が抱える4つの課題
出版業界は、これまでメインに扱われていた紙媒体の市場縮小など、複数の課題を抱えています。就職活動を行うにあたって、出版業界がどのような課題を抱えているかも知っておきましょう。
1.紙媒体の市場縮小
出版業界では、紙媒体の市場縮小が課題です。「娯楽の多様化」「インターネットの発達」「活字離れの加速」など、複数の要因が影響しています。
また、フリーマーケットアプリの成長も市場縮小の一因です。フリーマーケットアプリでの販売は中古の出版物扱いになり、販売者が価格を自由に設定できます。
書店に向かうよりも手軽で、かつ安く販売されている状況です。そのため、「欲しい書籍はまずフリマアプリでチェックする」という方も多いでしょう。
また、読み終えた本を手軽に売れることも、出版業界にとっては大きな脅威になっています。
2.返品率の高さ
出版業界では、返品率の高さも課題になっています。
出版業界で使用されている制度に、「委託販売制度」があります。委託販売制度とは、「出版社が消費者に直接書籍を販売するのではなく、出版取次と書店に販売を委託する制度」です。委託しても売れなかった書籍は返品され、その負担は出版社が請け負います。
委託販売制度での返品率は、30%から40%と高い数値が出ている状況です。返品が増えると、売上の減少や配送費などのコストがかかることから、出版業界の抱える課題とされています。
3.オンラインメディアへの展開
オンラインメディアへの展開をどのように進めるかも、出版業界の課題です。インターネットやスマートフォンの普及により、オンラインメディアが当たり前の時代になってきました。
紙媒体の市場が縮小していることもあり、出版業界はオンラインメディアの運営に力を入れています。しかし、収益化をどのように進めるかについては、対策が遅れている状況です。
コンテンツを充実させて広告収入を増やしたり、有料会員や有料コンテンツで収益化を図るなど、売り上げ増加に向けた取り組みが求められています。
4.電子書籍化にともなう権利処理とコスト
電子書籍化にともなう、権利処理とコストについても課題です。現在では、紙の書籍を発行する際に、電子書籍についての契約がされていないと、再度契約を締結しなければなりません。
また、著作者が複数いる場合、処理をする手間とコストが見合わず、電子書籍化が見送られるケースもあります。電子書籍化を進めてオンラインメディアに参入する一方で、どのようにして効率化を進めるかは課題になるでしょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
出版業界が力を入れる6つの取り組み
出版業界は課題解決に向けて、電子書籍への注力やオーディオブックなど、新しい取り組みも行っています。どのような取り組みを行っているかを詳しく解説するので、参考にしてください。
1.電子書籍
出版業界は電子書籍に力を入れており、年々市場規模が広がっています。経済産業省の「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)(p.70)」によると、2014年には1,276億円だった市場規模は、2020年には4,569億円になりました。
出版業界全体の規模は縮小傾向にありますが、電子書籍の分野は今後も伸びが期待されるでしょう。
また、電子書籍化が進むメリットには、次のような点が挙げられます。
・データファイルのため在庫が必要ない
・自由に価格設定ができる
・世界中に販売ができる
電子書籍の場合、出版社にとってもユーザーにとっても手軽な点が魅力です。
さらに、電子書籍で購読した後に、紙書籍を購入する方もいます。紙媒体への足がかりとしての役割も果たしているといえるでしょう。
参照元
経済産業省
令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)
2.クロスメディア
クロスメディアとは、発行されている書籍が、「アニメ」「映画」「ゲーム」などの媒体化されることです。クロスメディアを期待して、書籍の宣伝に力を入れるケースもあります。
クロスメディアにより期待できる成果は、次のような内容です。
・原作を知らない人が書籍を手に取るきっかけづくりになる
・映像化によって国外へのアピールにもつながる
クロスメディアに成功すれば、出版業界全体の利益につながります。既存の方法にこだわらず、クロスメディアを用いて新しい企画をしていくのも重要です。
3.書籍の付録の強化
書籍の付録を強化し、購買意欲を高めようとする動きもあります。
たとえば、女性向けのファッション誌では、付録を豪華仕様にし、売上増加を狙う取り組みが行われている状況です。アパレル業界やコスメ業界とタイアップし、バックやポーチ、化粧品などの付録をつけるケースがあります。
その結果、雑誌の内容だけでなく、付録を目当てに購入する顧客も増加しました。
そのほかにも、雑誌のサイズを小型化して手に取りやすくしたり、同じ月の雑誌でも2種類の表紙を展開したりするなど、さまざまな工夫がなされています。
4.インターネット書店への注力
インターネット書店に注力し、オンラインに対応する動きも増加している状況です。インターネット書店とは、インターネット上で書籍を購入できる本屋を指します。
近年は、実店舗に通わず、インターネットを通じて購入する消費者も多く見られる状況です。そのため、実店舗のある書店が、インターネット書店に参入するケースも増加しています。
5.定額読み放題サービス
雑誌や書籍、コミックなどが定額で読み放題になるサービスも注力されている取り組みです。電子書籍で実施されている場合が多く、紙媒体への足掛かりとしても期待されています。
6.オーディオブック
オーディオブックとは、書籍を朗読した音声を聞けるサービスです。「聴く本」と呼ばれる場合もあります。
オーディオブックは、本を読む習慣がない人でも、音声なので入りやすい点がメリットです。また、移動中や手がふさがっている最中など、本を読みにくい環境でも利用できる点が評価され、利用されています。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
出版業界と関わりの深い業界
出版業界と関わりの深い業界には、「印刷業界」「広告業界」などがあります。出版業界への理解を深めるためにも、関連する業界について知っておきましょう。ここでは、出版業界と関わりの深い、4つの業界を紹介するのでチェックしてください。
印刷業界
印刷業界は、書籍などの製本、印刷を行っています。出版物を作るためには、欠かせない業界です。
印刷会社のなかには、デザイナーを用意し、デザインの作成から製本までを一貫して行うケースもあります。
広告業界
広告業界は、雑誌を刊行する出版社と、雑誌に広告を掲載したい企業をつなぐ役割を担うケースが多い業界です。雑誌にある広告枠は、広告代理店を介して購入が行われています。
広告代理店の仕事には、原稿の作成や媒体の選定が含まれる場合も。出版社と話し合いを行い、内容の精査を受けてから、広告の掲載が行われるケースが一般的です。
通信業界
出版業界と通信業界は、主に電子書籍のサービスでつながっています。通信業界と提携を行えば、より多くの消費者に書籍をアピールできるからです。
通信業界にとっても、電子書籍サービスを利用するために、端末の買い替えが行われるメリットがあります。文字や絵が見やすい、大きな画面の端末が好まれるので、よりよい読書体験のために端末を買い換えるユーザーも多いでしょう。
アパレル業界
近年では、アパレル業界とタイアップする出版社が増加しています。雑誌の付録にアパレル商品を付けることで、売上向上を狙えるからです。またアパレル業界にとっても、ブランドのアピールにつながります。
就職活動では、志望する業界だけではなく、関係する業界について調べておくのも大切です。社会全体で、志望業界がどのような立ち位置にいるか調べておきましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
出版業界に就職するためのポイント
ここでは、出版業界に就職するためのポイントを解説します。就職活動で重要なポイントになるので、参考にしてください。
自分にあう職種を選ぶ
出版業界の仕事のなかでも、自分にあう職種を選びましょう。出版業界のなかには、編集者だけではなく、「ライター」「校正」「検閲」など複数の職種があります。
また、文章に関わる仕事だけが出版業界ではありません。「営業」「書店員」「デザイナー」「マーケター」など、多種多様な仕事があります。自己分析を行い、自分にあった職種を選ぶようにしてください。
自己分析の方法については「「自己分析のやり方がわからない」と悩む人へ」も参考にしてください。
企業の規模にこだわらずに選ぶ
出版業界での就職活動では、企業の規模にこだわらずに選びましょう。規模が大きくなくても、出版業界で働くうえで必要な知見が習得できる企業があるからです。
大企業や有名企業は志望者が多く、倍率は高くなります。規模にこだわらず探しておけば、出版業界で就職できる確率があがるでしょう。
想像力を鍛える
出版業界で勤めるために、想像力を鍛えるのも重要です。「編集」「デザイナー」「営業」どの職種でも、新しいアイデアや企画力が求められます。
出版業界で成果を出すためには、いいコンテンツを企画する力が欠かせません。また、アイデアをどのように収益化するか、手法まで想像する力が必要でしょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
出版業界に向いている人によくある特徴
ここでは、出版業界に向いている人によくある特徴を紹介します。
トレンドに敏感である
出版業界では、トレンドに敏感な人が向いています。社会でどのようなニーズがあるかを察知し、企画して世に出す力が求められるからです。
ジャンルを問わずに扱う総合出版社であれば、幅広いトレンドに興味を持てるほうがいいでしょう。分野に特化した出版社であれば、専門分野について深く興味を持てる人の方が向いています。
雑誌や本などの活字が好き
雑誌や本などの活字が好きな点も、出版業界に向きやすい特徴です。出版社は活字に触れる機会が多いので、仕事に興味を持ちやすいでしょう。
ただし、「本が好き」だけでは内定につながらないので注意しましょう。出版業界を志望する就活生の多くが、本を好きな傾向にあるからです。
本好きをアピールするのではなく、どのようにして収益化できるかをイメージする点が、重視されるので覚えておきましょう。
柔軟な発想やアイデアを持っている
柔軟な発想やアイデアを持っているのも、出版業界に向いている特徴です。消費者に評価されるためには、既存にはない新しいアイデアが必要になります。
出版業界の企業には、「これまでの考えにとらわれない」「今までにない発想でチャレンジできる」などの人物を求めるケースもあるので、覚えておきましょう。
こだわりをもって努力できる
出版物を形にするために、こだわりをもって努力できる点もポイントです。企画から完成まで、妥協せずにやりぬく力が求められます。
出版物は締め切りがある場合も多く、期日までに完成するように、肉体的にも精神的にも強さが必要です。諦めずに努力し続けられる特徴があれば、出版業界でも評価されるでしょう。
出版業界での就職活動を成功させるためには、企業研究も重要です。企業ごとでも、求める人物像は違うので調べるようにしてください。
企業研究の進め方については「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
出版業界への就職を目指すあなたへ
「出版業界に就職したいけど、どうすればいいんだろう」と悩んでいませんか。目標とする業界があっても、どのように就職活動を進めればいいかは難しいですよね。また、業界が決まっても、自分にある企業を探し、内定を獲得するのは大変です。
就職活動で困ったなと感じたら、ぜひキャリアチケットに相談してください。キャリアチケットでは、専任のアドバイザーが、内定獲得に向けてマンツーマンでサポートします。
これから就職活動を始める方も、始めたけどうまくいかない方も大丈夫。あなたに合わせてサポートを実施するので、ぜひ相談してください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。