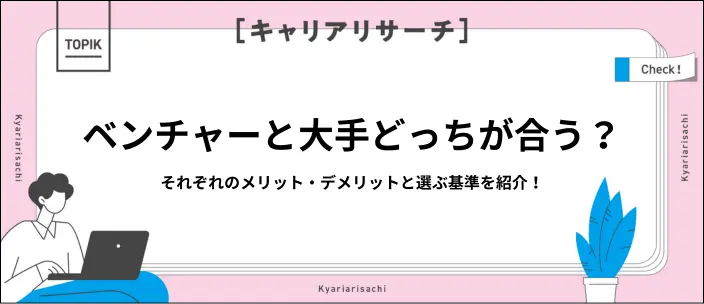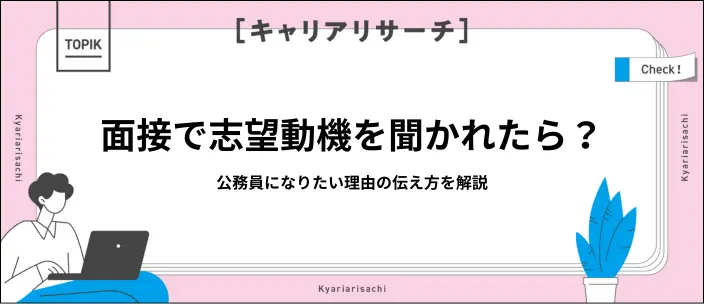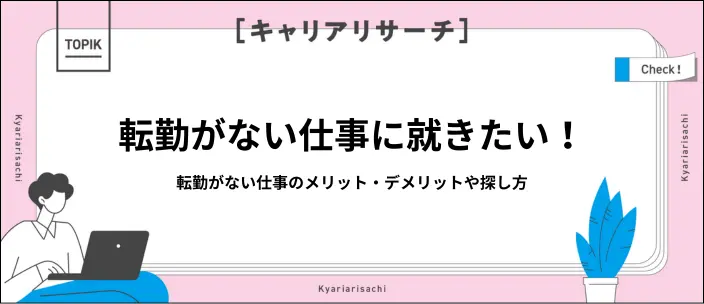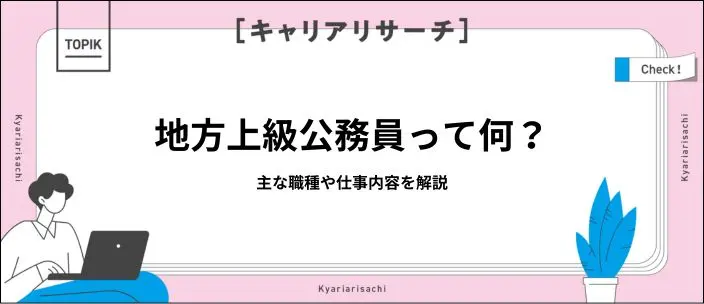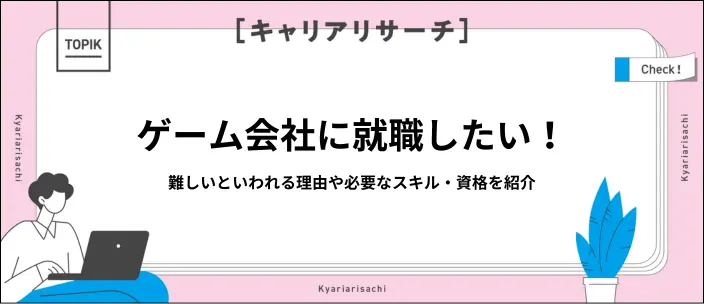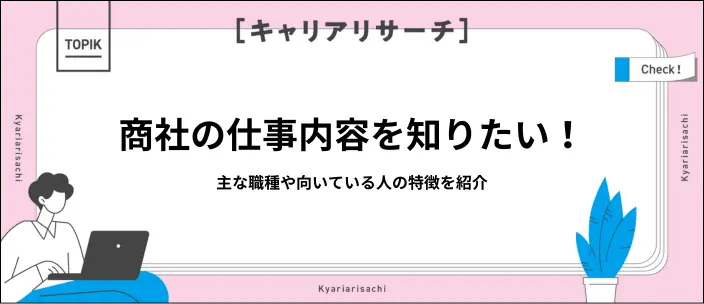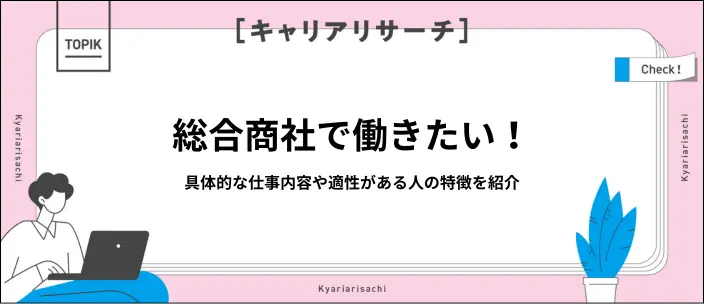このページのまとめ
- 公務員の種類は、大きく「国家公務員」と「地方公務員」に分けられる
- 公務員は「行政系」「心理系」「福祉系」など、仕事内容によっていくつかの職種がある
- 公務員試験は目指す種類によって内容や科目が異なり、難易度もさまざま
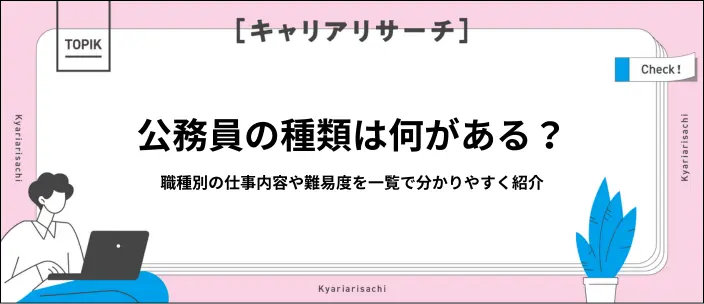
「公務員にはどのような種類があるか知りたい」と考えている就活生も多いでしょう。公務員は国家公務員と地方公務員に分けられ、仕事内容も多岐にわたります。自分の適職を見極めるためにも、まずは公務員の種類について理解を深めることが大切です。
この記事では、公務員の種類や職種について分かりやすく解説します。公務員試験の難易度一覧や適職を見つけるポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
無料で相談!適職を一緒に探してもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 公務員の種類を理解するための5つのポイント
- 1.国家公務員と地方公務員がある
- 2.特別職と一般職がある
- 3.事務系と技術系に区分が分かれている
- 4.区分によって試験科目が異なる
- 5.危険が多い公務員の種類もある
- 公務員と民間企業で悩むあなたへキャリアアドバイザーのアドバイス
- 国家公務員の種類
- 国家総合職
- 国家一般職
- 国家公務員専門職
- 地方公務員の種類
- 都道府県庁職員
- 市役所職員
- 政令指定都市職員
- 特別区職員
- 公務員の主な種類と仕事内容
- 1.行政系
- 2.心理系
- 3.福祉系
- 4.技術系
- 5.公安系
- 6.専門職系
- 7.資格免許職系
- 種類別|公務員試験の難易度一覧
- 難易度が最も高い種類
- 難易度が次に高い種類
- 平均的な難易度の種類
- 難易度が低めの種類
- 公務員のどの種類が自分に向いているか知ることが重要
- 国家公務員の職種に向いている人の特徴
- 地方公務員の職種に向いている人の特徴
- 公務員の各種類にはそれぞれメリット・デメリットがある
- 種類別|公務員になるメリット
- 種類別|公務員になるデメリット
- 志望する公務員の種類を見つけるための4ステップ
- 1.自己分析をして自分の強みを把握する
- 2.公務員の志望理由を書き出す
- 3.理想のキャリアプランを具体化する
- 4.求める条件に優先順位をつける
- 公務員の種類から自分の適性を見極めたいあなたへ
- 公務員の種類に関するよくある質問
- Q.人気のある公務員の種類は?
- Q.なりやすい公務員の種類は?
- Q.公務員のどの種類が自分に合っているか知りたい…
公務員の種類を理解するための5つのポイント
公務員といっても、種類や職種、仕事内容はさまざまです。ここでは、公務員の種類を理解するための5つのポイントを解説します。
1.国家公務員と地方公務員がある
公務員には、国家公務員と地方公務員の2種類があります。それぞれの違いは以下のとおりです。
| 国家公務員 | ・国家機関や行政執行法人などで働く公務員 ・国家公務員試験(総合職・一般職・専門職)に合格して採用される |
| 地方公務員 | ・県庁や市役所などの地方機関で働く公務員 ・地方公務員試験(上級・中級・初級)に合格して採用される |
国家公務員は財務省や外務省など、国家機関に所属して働く公務員で、国全体の行政に携わります。一方で、地方公務員は各都道府県に所属して働く公務員です。市や町など自治体ごとの採用となり、地域に密着した仕事ができる特徴があります。
公務員の種類についてさらに詳しく知りたい方は「国家と地方で違う?公務員の職種について解説します!」の記事をご覧ください。
2.特別職と一般職がある
国家公務員と地方公務員は、さらに法律によって「特別職」「一般職」の2種類に分けられます。特別職とは、選挙などによって選ばれる公務員の職種のことです。
国家公務員と地方公務員それぞれの特別職を以下にまとめました。
【国家公務員の特別職】
・内閣総理大臣
・国務大臣
・人事官
・検査官
・裁判官
・国会職員 など
【地方公務員の特別職】
・知事
・市町村長
・自治体議員
・地方公営事業の理事長 など
特別職には、国家公務員法や地方公務員法が適用されません。その立場から、特別職の任命や解任においては、厳格な手続きや審査が行われます。
なお、特別職以外の国家公務員および地方公務員は、すべて一般職の分類です。
3.事務系と技術系に区分が分かれている
公務員は、大きく事務系と技術系の種類に分類できます。仕事内容によってさらに立場が分かれるため、どのような区分があるか押さえておきましょう。
事務系職種における区分は、以下のとおりです。
・行政
・司法
・立法
・事務
技術系職種は、以下のように区分されます。
・土木
・工学
・建築
・機械
・電気
公務員試験は、職種別に実施されるのが一般的です。公務員について理解を深めるためには、どのような職種があるかを把握する必要があります。
4.区分によって試験科目が異なる
公務員試験の科目は大きく分けると「教養・基礎能力」と「専門科目」の2種類です。
教養・基礎能力では、以下の項目について出題されます。
<教養・基礎能力>
| 項目 | 出題内容 |
| 一般知能 | ・数的処理(判断推理、数的推理、資料解釈) ・文章理解(現代文、英文) |
| 一般知識 | ・人文科学(世界史、日本史、地理、思想、文芸) ・自然科学(数学、物理、化学、生物、地学) ・社会科学(政治、法律、経済、社会) ・時事問題 |
専門科目は、事務系職種と技術系職種で出題内容が異なります。
<専門科目>
| 区分 | 出題内容 |
| 事務系職種 | 憲法、民法、行政法、ミクロ経済学、マクロ経済学、財政学、経営学、会計学、統計学、政治学、行政学、社会学、国際関係論、労働法、刑法、商法 |
| 技術系職種 | 土木、工学、建築、機械、電気等各専門分野別の専門科目 |
専門科目の出題内容は、区分や職種によってさまざまです。なお、教養・基礎能力のみの試験もあります。
公務員試験に合格するための試験対策については、「公務員試験の勉強時間は?合格するための試験対策のポイントも解説」の記事もチェックしてみてください。
専門科目がない職種がなりやすいわけではない
公務員試験のなかには教養・基礎能力科目のみで受験できる種類もあります。しかし、受験科目が少ないからといって、合格しやすいわけではありません。
市役所や警察官、消防官などの種類は、教養・基礎能力科目のみで受験が可能です。勉強する範囲が狭くなる分、試験勉強の負担は減るでしょう。しかし、その分倍率が高い傾向にあります。
また、専門科目の試験勉強をしない分併願できる公務員試験が減る点や、面接の結果が重視される点にも注意が必要です。
5.危険が多い公務員の種類もある
公務員の職種には、業務に危険をともなう種類もあります。警察官や消防官、自衛官などの公安系職種がその代表格です。これらの社会秩序や安全の維持に関わる仕事は、ほかの行政職より給与が高く設定される傾向にあります。
公務員の仕事の種類を選ぶ際は、給与や安全性、やりがいなどの要素を総合的に見て決めましょう。
公安系職種の一つ、警察官の給与については「警察官のリアルな年収は?学歴別・年代別の違いを解説」の記事で詳しくまとめています。
無料で相談!適職を一緒に探してもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員と民間企業で悩むあなたへキャリアアドバイザーのアドバイス
公務員と民間企業で迷っている場合、どのような基準で決めれば良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。
公務員と民間企業で選択に迷っている場合でも、民間企業2社で選択に迷っている場合でも、選び方は大きくは変わりません。「自分自身が最高のキャリアスタートを切れる企業はどこなのか?」という問いが選択基準になるでしょう。
上記を考えるときに1点だけ注意したいのは、給与や福利厚生、制度など「入社してすぐに手に入れられるもの」だけを基準にしないことです。それらを基準に選んでしまうと、入社してすぐに期待が満たされてしまい、働くやりがいを見つけるのに苦労する可能性があります。
大切なのは、基準を考えるときに「自分の強みを活かせるのか?」「そこで成長していくことで、理想の自分に近づけるのか?」を考えることです。
入社してすぐの離職を念頭に企業を選ぶ人はいません。だからこそ、少し先の未来も見越したうえで仕事の種類を意思決定できると、後悔のない選択になるでしょう。
公務員と民間企業の違いについて理解を深めたい方は、「民間企業と公務員の違いは何?特徴や仕事内容をご紹介!」の記事をご覧ください。
無料で相談!適職を一緒に探してもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
国家公務員の種類
ここでは、公務員試験に合格して採用される国家公務員の一般職の種類を解説します。国家公務員の一般職とは、国務大臣や国会職員などの特別職以外のすべての公務員のことです。
国家公務員の一般職は、仕事内容によって主に以下の3つに分けられます。
国家総合職
一般職のなかでも、将来の幹部候補生とされる種類が国家総合職です。行政の中枢である中央省庁で、主に政策の企画や立案、予算の編成などに携わります。いわゆるキャリア官僚と呼ばれる国家公務員で、大きな裁量を持って仕事ができる点が特徴です。
国家総合職試験は、院卒区分と大卒程度区分に分けられ、さらには専門科目によって細分化されます。一次試験と二次試験があり、一次試験で行われるのは多肢選択式の基礎能力試験と専門試験です。二次試験では、専門試験と政策論文試験、個別面接による人物試験が行われます。
国家総合職試験に合格すると、主に中央省庁の幹部候補生として採用され、中央省庁がある東京で勤務するのが一般的です。ただし、省庁によっては2〜3年間隔で地方への出向を命じられるケースもあります。
国家一般職
国家一般職は、事務処理をはじめとする定型業務を担う公務員です。国家総合職が立案した施策を実行・運用する、一般行政職員や外交官、税務職員として働く人たちが該当します。
国家一般職試験は大卒以上で受験でき、事務系と技術系のどちらも専門科目ごとに区分が設定されている点が特徴です。一次試験と二次試験があり、一次試験では多肢選択式の基礎能力試験と専門試験に加えて、一般論文試験があります。
二次試験は、個別面接を実施して人柄や対人能力をみる人物試験です。また、二次試験に合格すると、官庁訪問と呼ばれる希望官庁の面接があります。
国家一般職の仕事内容は、政策を実行したり企画立案を支えたりするバックオフィス業務が基本です。勤務先は、中央省庁以外の地方機関も含めて選択できますが、基本的には採用された地域内での勤務が多い傾向にあります。
国家公務員専門職
国家専門職は、特定の分野に関わる一般職です。以下のような専門性が高い知識を求められ、資格や技能の習得が必要とされる職種が該当します。
・財務専門官
・国税専門官
・労働基準監督官
・刑務官
・入国警備官 など
国家専門職試験は、学歴によって受験できる区分が異なる試験です。財務専門官や国税専門官、労働基準監督官などは院卒者や大卒程度、刑務官や入国警備官などは高卒程度の学歴があれば受験できます。
なお、国家総合職や国家一般職は合格した時点で配属が決まるのに対し、国家専門職はあらかじめ勤務先官庁を限定して職員の募集が行われるのが特徴です。自分が目指すキャリアパスやライフスタイルを明確にしてから、志望する公務員の種類を検討すると良いでしょう。
公務員になるために必要な資格については、「公務員に資格は必要?職種の違いや採用までの流れを解説」も参考にしてください。
無料で相談!適職を一緒に探してもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
地方公務員の種類
ここでは、地方公務員の一般職について解説します。地方公務員の試験は、大卒程度の「上級」と短大卒程度の「中級」、高卒程度の「初級」にレベルが分けられているケースが一般的です。
ただし、自治体によって試験の正式名称は異なるため、詳細については各自治体の公式Webサイトを確認しましょう。
都道府県庁職員
都道府県庁職員は、地方公務員のなかでも比較的規模が大きい仕事を担います。主な業務は、以下の3種類です。
・都道府県レベルで統一すべき業務
・市町村を越える広域的な業務
・国と市町村、業者との連携業務
都道府県庁職員になるためには、大学卒業レベルの地方上級試験に合格する必要があります。採用後は、都道府県庁や都道府県の出先機関などに勤務します。地域住民と接する機会は少ないものの、スケールが大きい仕事ができる点が特徴です。
市役所職員
市役所職員は、地域住民に最も近い立場で行政サービスを提供する地方公務員です。地域住民の行政窓口として、主に以下の種類の業務を担います。
・住民生活の基礎手続(戸籍住民登録、諸証明の発行など)
・住民の安全、健康確保、環境保全(消防、上下水道の整備、公園や緑地の整備など)
・まちづくり(公共施設の建設および管理など)
・各種施設の運営(保育所、小中学校、公民館といった施設の建設および管理など)
採用後は市役所や市町村の出先機関などに配属され、基本的に転居を伴う異動はありません。地域住民と接する機会が多く、携わった仕事の成果を直接感じやすい特徴があります。
なお、市役所職員になるための公務員試験は、自治体ごとに試験内容や採点比率などが異なる点に注意が必要です。
政令指定都市職員
政令指定都市職員とは、都道府県と市町村の機能をあわせ持つ人口50万人以上の都市で働く公務員の種類です。主な仕事内容は市役所職員と共通しているものの、都市の規模が大きいため都道府県に代わって都市計画を担うケースもあります。
政令指定都市職員になるには、都道府県庁職員と同様に地方上級試験に合格する必要があります。自治体によって異なるものの、採用後は市役所や区役所、または関連施設に勤務し、窓口業務から始めるのが一般的です。
なお、多くの自治体において都道府県庁職員と政令指定都市職員の試験が同日に実施されているため、併願受験はできません。
特別区職員
特別区職員とは、東京都の23区で勤務する公務員の種類です。東京都の23区をまとめて「特別区」と呼び、東京都全体ではなく区ごとの行政運営を担います。
特別区人事委員会が統一的に採用試験を実施しており、複数の採用区分が用意されているのが特徴です。ただし、内定は区ごとに出され、採用された区の関連施設で働くことになるため、市町村職員と同様に転居を伴う異動はありません。
地方公務員になるための上級試験について詳しく知りたい方は、「地方上級公務員とは?職種や仕事内容から試験の難易度まで解説」の記事もチェックしてみてください。
無料で相談!適職を一緒に探してもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員の主な種類と仕事内容
公務員の種類は、担う仕事内容により7つの種類に大別されます。以下でそれぞれの役割や仕事内容を解説するので、公務員を目指すうえでの参考にしてください。
1.行政系
行政系の公務員は、「一般事務」や「行政事務」とも呼ばれます。各省庁や出先機関、県庁、市役所などで行政全般の業務に幅広く携わる種類です。
ただし、国家公務員と地方公務員では、業務の規模に違いがあります。たとえば、国家公務員の場合、主に国家総合職が企画立案や予算の作成などを担当し、国家一般職は文書作成や会議の運営といった事務作業を担うのが一般的です。
また、行政系の地方公務員であれば、都道府県庁や市役所などで施策の企画から立案、執行まで携わるほか、市役所での窓口対応も担います。
2.心理系
心理系の公務員は、心理学の専門知識やスキルを活かした職種です。個人や家族が抱える問題に対し、カウンセリングや支援を通じて心身の健康をサポートする役割を担います。
国家公務員であれば法務省矯正局や家庭裁判所の調査官など、相談専門員として働くケースが一般的です。また、地方公務員の多くは、児童相談所などでの相談専門員として勤務しています。
心理系の公務員は基本的に無資格で公務員試験の受験が可能です。ただし、種類によっては臨床心理士などの専門的な資格が求められる場合もあります。
3.福祉系
福祉系の公務員は、福祉事務所や児童相談所、厚生労働省職業安定局で相談員や指導員として働くのが一般的です。主に、高齢者や障害者、児童などへ福祉ニーズに応じたサービスや支援を提供する役割を担います。
福祉系の職種は国家公務員での採用数が限られており、多くの職員は地方公務員としての採用です。なお、福祉系の公務員試験を受けるためには、都道府県や自治体によって社会福祉士や児童指導員といった種類の資格が必要な場合もあるため、事前に確認しましょう。
4.技術系
技術系の公務員は、都市計画やエネルギー開発といった人々の生活を支える種類の仕事に携わります。「理系公務員」とも呼ばれ、土木や建築、機械、電気といった各分野の専門的な知識が求められる職種です。
技術系職種の分野は、国家公務員と地方公務員で共通しているものの、所属先や役割がそれぞれで異なります。
国家公務員の場合は、基本的に各省庁や自治体の出先機関に所属し、各分野のスペシャリストとして業務にあたります。技術系職種の地方公務員は、現場の監督責任者として公共施設やインフラの整備、環境保全に貢献するのが主な役割です。
技術系職種の公務員には分野ごとに専門的な知識が求められるため、大学での選考も職種選択に影響するでしょう。
5.公安系
公安系職種の公務員は、人命や安全を守る仕事に携わる役割を担います。主な職種は以下のとおりです。
・皇宮護衛官(国家公務員)
・法務教官(国家公務員)
・刑務官(国家公務員)
・公安調査官(国家公務員)
・入国警備官(国家公務員)
・警察官(国家公務員・地方公務員)
・消防官(地方公務員) など
警察官は、交番・派出所で勤務する地域警察や交通違反の取り締まりをする交通警察、犯罪や事件を捜査する刑事警察など、幅広い任務を担当します。警察官は階級や試験の種類によって一部は国家公務員とされますが、多くは地方公務員です。
消防官は火災の消火活動や事故現場での救助にあたります。公安系の主な役割は、社会の安定と秩序を維持し、市民の安全を保障することです。
なお、公安系職種には身体的要件(視力や聴力など)や体力・体格要件が設けられている種類もあります。職種や自治体によって求められる基準は異なるので、受験する職種を決める前に自分が基準を満たしているのか確認してみましょう。
6.専門職系
専門職系職種は、専門的な知識やスキルを必要とする国家公務員です。具体的には、以下のような種類が該当します。
・国税専門官
・財務専門官
・労働基準監督官
・食品衛生監視官
・航空管制官 など
専門職系職種の国家公務員になるには、あらかじめ勤務先の官庁を限定して応募し、職種ごとの特色に応じた試験を課せられる点が特徴です。
専門職系職種の国家公務員は、各分野の専門的な知識やスキルを活用して、行政の中核的な業務を担います。ほかにも、行政所有の建造物の管理維持や事業者への指導に加えて、研究や開発に携わるケースもあります。
7.資格免許職系
資格免許職とは、特定の資格や免許を必要とする仕事に携わる地方公務員です。具体的には、以下の種類が資格免許職に該当します。
・公立学校の教員
・管理栄養士
・看護師
・保健師
・保育士 など
資格免許職の地方公務員は、専門的な資格を活かして教育や医療といった分野で働くのが一般的です。近年は、福祉施設に勤務するケースワーカーや、児童や保護者へのカウンセリングを行う児童心理士といった資格免許職へのニーズが高まっています。
公務員試験の年齢制限については、「公務員に年齢制限はある?受験資格や民間企業との併願のコツも解説」の記事で詳しく解説しています。
無料で相談!適職を一緒に探してもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
種類別|公務員試験の難易度一覧
公務員の難易度は、求められる学力や採用人数などから判断可能です。ただし、公務員試験は年度によって採用人数や受験者数が変動し、倍率も都度変わります。そのため、「倍率が低いから採用される可能性が高い」「難易度が低いから簡単に合格する」のように一概にいえるものではありません。
以下で紹介する試験の種類と難易度の一覧はあくまで参考程度に考え、目指す職種に合わせてしっかりと対策しましょう。
難易度が最も高い種類
公務員試験の難易度が最も高いのは、主に以下の種類です。
| 国家公務員総合職 | 国家公務員 | ・中央官庁で働くため高度な学力と広範な知識が求められる ・国家公務員のなかでもトップクラスの難易度 |
| 裁判所職員総合職 | 国家公務員 | ・司法制度に関する専門知識が求められる ・特に総合職試験は難易度が高い |
| 外務省専門職員 | 国家公務員 | ・国際関係や外交に携わる職種 ・外国語や国際的な視野を求められる |
難易度が次に高い種類
最難関の職種に次いで難易度が高い職種は、以下の種類です。
| 国家公務員一般職 | 国家公務員 | ・政策実行のための事務処理を担う一般的な職種 ・幅広い分野の知識が求められる |
| 国税専門官 | 国家公務員 | ・国税庁や税務署で就労する ・法律や経済、会計などの専門的な知識が求められる |
| 財務専門官 | 国家公務員 | ・財務局で就労する ・金融機関の検査や国有財産の管理、予算執行調査などを行う |
| 地方上級公務員 | 地方公務員 | ・地域の行政全般に携わる地方自治体の上級職 ・地方上級試験に合格する必要がある |
平均的な難易度の種類
平均的な難易度とされている公務員資格には、以下の種類が挙げられます。
| 市役所職員 | 地方公務員 | ・地域の行政業務を担当する一般的な職種 ・各自治体が実施する採用試験に合格する必要がある |
| 消防官 | 地方公務員 | ・火災の消火活動や救助活動を行う職種 ・身体検査や体力試験も実施される |
| 警察官 | ・国家公務員 ・地方公務員 |
・犯罪防止や治安維持に従事する職種 ・体力と判断力が求められる |
難易度が低めの種類
比較的難易度が低いとされるのが以下の種類です。なお、公務員のなかでは比較的難易度が低いとはいえ、誰でも受かるというわけではありません。試験にはしっかり対策をして臨みましょう。
| 入国警備官 | 国家公務員 | ・不法入国者の事件調査や入国者収容所の施設警備などを行う職種 ・高卒程度の教養が求められる |
| 刑務官 | 国家公務員 | ・少年刑務所や拘置所などの防衛および治安維持に関する職種 ・高卒程度の教養が求められる |
| 自衛官 | 国家公務員 | ・18~33歳未満の人が受験できる ・自衛官になる訓練を受けるための試験に合格する必要がある |
| 都道府県庁職員(高卒) | 地方公務員 | ・高卒程度の学力で応募できる職種がある ・各自治体が実施する採用試験に合格する必要がある |
公務員試験の難易度や合格率について詳しく知りたい方は、「公務員の難易度はどのくらい?試験別の合格率や対策のコツを解説」の記事もご覧ください。
無料で相談!適職を一緒に探してもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員のどの種類が自分に向いているか知ることが重要
公務員の仕事にはさまざまな種類があるため、就職を検討する際は自分の適職を見つけることから始めましょう。
ここでは、国家公務員・地方公務員それぞれに向いている人の特徴を紹介します。
国家公務員の職種に向いている人の特徴
国家公務員は「国を良くしたい」「課題を解決したい」といった使命感のある人に向いている仕事です。
国家公務員の仕事の種類はさまざまですが、国民全体の生活に関わっていくという部分は共通しています。目先の成果や報酬に囚われず、長期的な視点で国や国民の生活を良い方向に持っていきたいという気持ちを持ち続けられる人に適性があるでしょう。
また、法律や規則が重視される世界なので、ルールを厳守して仕事を進められる人の適性があります。
地方公務員の職種に向いている人の特徴
地方公務員の仕事の種類は、地域住民の生活に直結したものが中心です。そのため、働く地域の出来事に関心を持ち、住民の気持ちに寄り添える人に向いています。地元はもちろん、地元以外でも働く自治体に愛着があり、地域発展に貢献したいという気持ちがあれば、使命感を持って働けるでしょう。
また、地方公務員は不正防止や能力開発のため3~4年周期で部署移動をするのが一般的です。業務内容が大きく変わることもあるので、適応力が高い人に向いています。
自分に向いている仕事を見つけるためには、丁寧な自己分析が効果的です。「自己分析の質問100選を活用して強みを見つけよう!やり方と注意点を解説」の記事を参考にして、適職を探してみましょう。
無料で相談!適職を一緒に探してもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員の各種類にはそれぞれメリット・デメリットがある
公務員の仕事の種類はさまざまですが、それぞれ共通したメリット・デメリットがあります。民間企業と公務員で迷っている人は、以下の内容を職業を選ぶ際の参考にしてください。
種類別|公務員になるメリット
国家公務員・地方公務員にどちらの種類にも共通しているメリットは、収入や雇用が比較的安定していることです。倒産の心配もないうえ、真面目に働いていれば解雇されることも通常はありません。
国家公務員ならではのメリットは、国を支える大きな規模の仕事に携われることです。スケールの大きい仕事をしたい人は、やりがいをもって働けます。また、国に身分を保証されているため、社会的信用を得られる点も大きなメリットでしょう。
地方公務員のメリットは、仕事の種類にもよりますが一部の国家公務員と比較すると大規模な転勤が少ないことです。地域のために働く仕事のため、転勤があっても同じ自治体内に留まります。
種類別|公務員になるデメリット
国家公務員・地方公務員のどちらの種類にも共通しているデメリットは、実績が収入や待遇に反映されにくい点です。年功序列の制度が残っているため、頑張りをすぐに評価してもらいたいと考える人はストレスが溜まりやすい環境といえます。
国家公務員ならではのデメリットは、頻繁な転勤が発生することです。仕事の種類にもよりますが、国家総合職の場合は全国各地に転勤する可能性があります。また、扱う仕事の規模から、プレッシャーや精神的負担が大きくなりやすいのもデメリットです。
地方公務員のデメリットには、住民と直に接する機会が多く、クレームや無理な要求に対する対応スキルが求められる点が挙げられます。要望があっても、裁量が少ないため自分の力では物事を動かせないのもストレスになりうるでしょう。また、災害や大規模な事故などがあった際には、自分や家族よりも住民優先で動かなければならない可能性もあります。
メリット・デメリットを知ったうえで、それでも民間企業と公務員で悩む人は、「【就活お悩み相談室 #6】公務員を目指すか民間企業に就職するか迷っています」の記事をご覧ください。
無料で相談!適職を一緒に探してもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
志望する公務員の種類を見つけるための4ステップ
数ある公務員の種類から自分に合った職種を選ぶためには、自己理解と業務理解の両方が欠かせません。ここでは、「どの種類の公務員を目指すべきか」と悩んでいる学生向けに、適性を見極めるための4つのステップを紹介します。
1.自己分析をして自分の強みを把握する
自分に合った公務員の種類を見つけるために、まずは自分の性格や価値観、強みなどを客観的に整理しましょう。公務員の仕事は、国家公務員と地方公務員で業務内容や働き方が大きく異なります。そのため、どのような仕事が向いているか、自分の強みと職種の特性を照らし合わせることが大切です。
2.公務員の志望理由を書き出す
志望する公務員の種類を明確にするためには、公務員になりたい理由を書き出すことも効果的です。公務員を目指すきっかけになったエピソードがあれば、深掘りしてみましょう。志望理由が明確になれば、志望職種を絞る軸になります。
志望理由としては、「祖母を連れて市役所を訪れた際に職員の丁寧な対応を目の当たりにし、自分も地域貢献したいと思った」「世界で活躍する外務省職員について知り、興味を持った」など、どのようなエピソードでも構いません。自分の経験や価値観に基づく公務員の志望理由を書き出しましょう。
国家公務員になりたい理由をうまく言語化するポイントは、「公務員になりたい理由に使える6例文を紹介!考え方のポイントや手順を解説」の記事で詳しく解説しています。
3.理想のキャリアプランを具体化する
公務員の適職を見つけるためには、理想のキャリアプランを描くことも大切です。
採用後、どのような働き方やキャリアを築きたいのか具体的に想像してみましょう。たとえば、「5年後は△△課でリーダーとして働きたい」「長期にわたって地元で貢献したい」など、将来像を描くことで選ぶ仕事の種類が自然に絞られていきます。
4.求める条件に優先順位をつける
志望理由やキャリアプランをふまえ、勤務地や安定性、やりがい、専門性の活かし方など、公務員として働くうえで必要な条件をリストアップしましょう。すべての条件を書き出したら、最も優先したいことから優先順位をつけてみてください。
公務員の仕事を理解したうえで、国家公務員か地方公務員か、あるいは特定の機関で働きたいかを検討していくとスムーズです。
たとえば、勤務地を重視する場合は、国家公務員よりも地方公務員のほうが転勤の心配がない分、ストレスなく働けるでしょう。また、安定性を重視する場合は、定年まで働きやすい公務員の種類を選ぶのがおすすめです。
条件を決めるためには、仕事内容を詳しく知ることが重要となります。「業界・企業・職種の研究はなぜ重要?就活を効率的に進めるための基礎知識」や「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事では、企業研究のやり方を紹介しています。民間企業向けの内容ですが、公務員就職でも役に立つでしょう。
無料で相談!適職を一緒に探してもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員の種類から自分の適性を見極めたいあなたへ
公務員を目指してはいるけれど、「仕事の種類がよく分からない」「自分に合った職種を見つけられない」と悩んでいる就活生も多いでしょう。明確な目的もなく公務員だけの就活に絞ってしまうと、万が一失敗した際に就職浪人になってしまう可能性がある点に気をつけてください。
公務員志望の学生であっても、場合によっては民間企業に視野を広げたほうが良いケースもあります。公務員を目指すうえで就活の方針をどうすべきか悩んだら、就活エージェントに相談してみましょう。
就職エージェントのキャリアチケットでは、自己分析や面接対策など、一人ひとりの状況にあわせた公務員試験対策を支援しています。また、公務員試験と並行して民間企業の就活サポートを行うことも可能です。就活をどのように進めれば良いか悩んでいる方は、ぜひキャリアチケットにご相談ください。
無料で相談!適職を一緒に探してもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員の種類に関するよくある質問
ここでは、公務員の種類に関するよくある質問をまとめました。
Q.人気のある公務員の種類は?
A.国家公務員では、国の重要な業務に携わる国家公務員総合職の倍率がとりわけ高くなっています。
地方公務員では、都道府県庁職員や市町村職員、警察官、教員などの種類が人気です。
公務員の種類についてさらに詳しく知りたい方は「公務員の仕事内容とは?種類と職種別でご紹介!」の記事をご覧ください。
Q.なりやすい公務員の種類は?
A.国家公務員のなかでは、入国警備官や刑務官、自衛官、地方公務員では都道府県庁職員(高卒)が比較的なりやすい種類といえます。とはいえ、公務員試験対策は必須なので、油断せずに準備をしましょう。
Q.公務員のどの種類が自分に合っているか知りたい…
A.公務員のどの種類が自分に合っているか分からなければ、自己分析をやり直してみましょう。自分についての理解が深まれば、将来やりたいことが自ずと見えてきます。そのうえで、将来やりたいことが公務員の職種になければ、民間企業への就職を検討するのも一つの方法でしょう。
自己分析のやり方については「自己分析は難しい?できないと感じる理由や効果的なやり方を解説」の記事をご覧ください。
無料で相談!適職を一緒に探してもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。