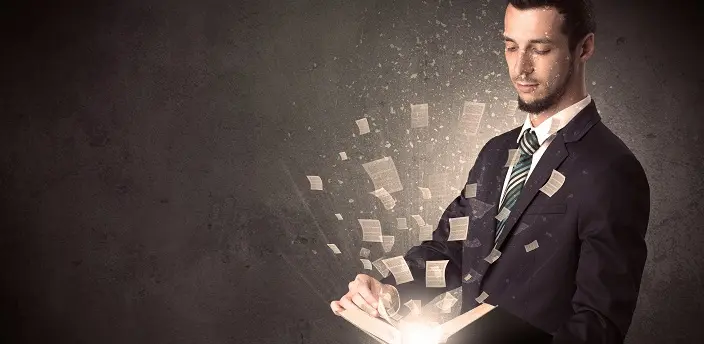このページのまとめ
- グループディスカッションの目的は、企業が就活生を総合的に評価すること
- グループディスカッションにおける役割ごとに求められるスキルや評価ポイントが異なる
- 練習と準備を重ねてスムーズな議論進行を心掛けることが大切

グループディスカッションの目的を理解して選考を通過したい就活生へ。企業が何を見ているのか、その目的を理解することが選考通過への近道です。
この記事では、グループディスカッションの流れから目的、評価されるポイントまでを詳しく解説します。さらに、司会や書記、タイムキーパーなど7つの役割の特徴や役割ごとの立ち回り方も紹介。これを読めば、自信を持ってグループディスカッションに臨めるようになるでしょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションの流れ
グループディスカッションとは、数人のグループで与えられたテーマについて討論し、時間内に意見をまとめて発表する就活における選考方法の一つ。
その方法は企業によって違いはありますが、一般的な流れは以下のとおりです。
・企業側からテーマやルール、制限時間などの発表
・メンバーの簡単な自己紹介
・役割を決める
・資料を読み個人の意見をまとめる
・議論開始
・グループとしての結論をまとめる
・発表
企業側が必ずしも進め方を提示してくれるとは限らないため、資料をよく読み流れを把握しておくことが重要です。
グループディスカッションでよく取り上げられるテーマを知りたい方は「グループディスカッション対策をご紹介!テーマ別にポイントと対策を解説」もあわせて参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションの目的
企業がグループディスカッション(GD)を行うのは、就活生の「協働力」や「実践的なスキル」を総合的に評価するためです。
個人面接では見えづらい、他者との関わり方・チーム内での立ち振る舞い・実践的な思考力を確認するのが目的といえるでしょう。グループディスカッションでは限られた時間の中で、意見を出し合いながら結論を導く必要があります。実際の仕事に近い状況下での行動が見られるのが大きなポイントです。
グループディスカッションは単なる会話の場ではなく、「一緒に働けるかどうか」を企業が見極めるための重要な選考手段。目的を正しく理解したうえで、自分らしい強みを発揮できるように準備しておきましょう。
「就活のグループディスカッションを成功させるコツとは?」のコラムでは、グループディスカッションをうまく進めるためのコツを紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションの評価ポイント
就職活動の選考ステップの一つとしてよく取り入れられるグループディスカッション。グループディスカッションでは、ただ意見を言うだけでは評価されません。企業はあなたの発言内容やチームでの立ち振る舞いなど、複数の観点から総合的にチェックしています。
ここでは、企業がグループディスカッションで重視している主な評価ポイントを解説。どこを見られているかを理解して、本番に自信をもって臨みましょう。
論理的思考力
論理的思考力は、グループディスカッションで企業が重視する基本的な評価ポイントです。
社会人になると、物事を筋道立てて考え、相手にわかりやすく伝える力が求められます。論理的な説明ができなければ、相手に誤解を与えたり信頼を損ねたりする原因にもなりかねません。
グループディスカッションでは、自分の意見に「なぜそう考えたのか」という根拠を添えて説明する力が求められます。たとえば、「Aという施策が効果的だと思う。なぜなら~」というように、結論→理由→補足という流れで話す学生は、企業から「思考が整理できている」と評価されやすくなるでしょう。
また、ほかの参加者の意見を聞いたうえで、「△△さんの意見にはこういうメリットがある」と、客観的な視点で整理・補足できる力も、論理的思考力の一部です。
グループディスカッションでは、「なんとなく話す」ではなく、筋道を立てて意見を組み立てられるかが評価されます。論理的な考え方を意識することで、企業に「一緒に仕事ができる人材」として好印象を与えられるでしょう。
話し合いへの積極性
積極的に発言できるかどうかは企業がチェックしているポイントです。
ビジネスの現場では、ただ指示を待つのではなく、自ら行動し、意見を伝える姿勢が求められます。グループディスカッションでは、周囲の様子を伺うだけの受け身な態度よりも、主体的に議論に参加しているかどうかが見られているのです。
たとえば、ほかの人の発言に対して「それは面白い視点ですね。こういう点も加えるとどうでしょうか?」と話を広げられたりする学生は、仕事でも積極的に動ける人材と評価されやすいでしょう。
ただし、単に話す量が多いだけではなく、チームの目的に向けて建設的な発言ができているかが重要です。積極性は、企業が求める基本的なビジネススキルの一つ。グループディスカッションでは、自分の意見を恐れずに発信し、周囲と協力しながら主体的に関わる姿勢が評価されます。
リーダーシップ
状況に応じてリーダーシップを発揮できるかどうかも、企業が注目している重要な評価ポイントです。
現実の仕事でも、チームで動く中で周囲をまとめる力や、方向性を示す力が必要になります。必ずしもリーダー役を務める必要はありませんが、「周囲を気遣いながら全体を前進させる姿勢」がリーダーシップとみなされるでしょう。
たとえば、議論が脱線したときに「一度、結論に向けて整理しましょう」と声をかけたり、発言の少ない人に「△△さんはどう思いますか?」と促したりできる人は、状況判断力と調整力のあるリーダーシップを発揮していると評価されます。このように、目立つ発言よりも、「グループ全体の進行を支える行動」が、企業にとって重要な要素となるでしょう。
グループディスカッションでは、単に議論をリードするだけでなく、周囲と連携しながら全体を前に進められるかどうかが見られています。役割に関係なく、状況に応じたリーダーシップを発揮する意識を持ちましょう。
コミュニケーション能力
協調性やコミュニケーション能力が備わっているかどうかも重要な評価基準です。
実際の職場では、どんなに優れたスキルがあっても、周囲と円滑に連携できない人材は組織に馴染めず、成果も出にくいと考えられています。そのため、企業はグループディスカッションを通じて「人とどう関わるか」を慎重に見極めているのです。
たとえば、ほかの参加者の意見をしっかり聞いたうえで「それは確かに一理ありますね」と一度受け止めたり、「△△さんの意見に加えて、こういう視点もあると思います」とつなげたりする姿勢は高く評価されます。また、バランス良く議論に参加しているかどうかも、協調性の指標になるでしょう。
グループディスカッションでは「話す力」だけでなく、「聞く力」と「周囲との連携力」も求められます。協調性とコミュニケーション能力を発揮することで、一緒に働きたいと思われる人材として好印象を与えられるでしょう。
斬新な発想力
斬新な発想の有無も、しっかり見られているポイントといえるでしょう。
企業は、これからの変化の激しい時代に対応できる、柔軟な思考と新しいアイデアを持つ人材を求めています。グループディスカッションでは、創造性や独自性を発揮し、チームに新たな視点をもたらせるかが評価されるのです。
たとえば、「このテーマに対して、こういう切り口で考えてみませんか?」といった、ほかの人が思いつかないアイデアを提案できる人は、「視野が広く、課題解決に貢献できる人」として印象に残ります。もちろん、奇抜なだけで実現性がない意見では意味がありません。重要なのは、論理的な根拠を持って独自の意見を述べられるかというバランスです。
自由で斬新な発想は、組織に新しい風を吹き込む重要な要素。グループディスカッションでは、アイデアの質や視点のユニークさも選考における強みになるため、自分なりの視点でテーマにアプローチしてみましょう。
グループディスカッションの種類や流れを知りたい方は「GDのメリットは?議論のコツや選考への対策を解説!」のコラムもチェックしてみてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションでの役割の種類
ここでは、グループディスカッションでよく登場する7つの役割の特徴と評価ポイントを解説します。自分に合った役割を理解し、本番で自信を持って臨めるよう準備しましょう。
進行役の「司会・ファシリテーター」
グループディスカッションで「司会・ファシリテーター」になったときに求められるのは、議論全体を冷静にコントロールする力です。
企業がこの役割を重視するのは、社会人としての全体俯瞰力・論理的思考力・傾聴力など、チームをまとめる資質が問われるため。ただ目立てば良いというものではなく、周囲の意見を引き出しつつ、議論のゴールまで導くバランス感覚が必要です。
たとえば、意見が割れて話が進まない場面では、「まず△△さんの案について確認しましょう。その後△△さんの視点を照らし合わせて考えます」といったように、優先順位をつけながら全体を整理し、自然に合意形成へとつなげると高く評価されます。
司会に求められるのは、リーダーシップというより周囲に配慮しながら議論を支える力。目立つポジションではありますが、目立ち方よりも議論を円滑に進めることができたかどうかが評価のポイントです。
司会はグループディスカッションの「顔」とも言える存在。積極性があるだけでなく、周囲を思いやる配慮やまとめる力を発揮できる人に向いています。自分が前に出ることにばかり集中せず、周りと協調しながら進められるかがポイントです。
議論の要点を整理する「書記」
「書記」は、議論の要点を整理し、発表内容をわかりやすくまとめるグループディスカッションにおいて重要な役割です。
企業は情報整理力や論理的思考力、聞き取った内容を正確に要約する力が社会人に欠かせないスキルと考えているため、書記に注目しています。見逃されがちですが、チームの結論を形にする責任を担うポジションです。
たとえば、発言が多くなったときでも、共通点や対立点を抽出してメモし、論点を見える化できれば、チーム全体の議論がスムーズになります。話の流れを追いながら、発表を前提とした「整理されたメモ」を作れると、高評価につながるでしょう。
また、議論の質をさらに高めることができるサポート役としての力もアピールできます。
書記は表に出る機会が少ないかもしれませんが、チームの成果を「見える形」にするキーパーソン。情報を整理するのが得意な人や、構造的に物事をまとめるのが好きな人にはぴったりです。地味でも評価される役割なので、自信を持って挑戦してみましょう。
議論の時間管理をする「タイムキーパー」
「タイムキーパー」は、時間をただ読み上げるだけではなく、議論全体を時間内にまとめる影の指揮役といえます。
企業がグループディスカッションにおいてタイムキーパーを評価する理由は、社会人にとって「時間内に成果を出す」能力が重要視されているからです。限られた時間の中で何を優先し、どう配分するかといった判断力や臨機応変な対応力が試されます。
たとえば、意見出しに時間が掛かっているときに、「残り時間を考えて、次のフェーズに進みましょう」と促せると、チーム全体の進行がスムーズになり評価ポイントになるでしょう。議論の流れを読み取りながら、自然に時間配分を調整する柔軟性が大切です。
また、タイムキーパーはほかの役割(書記・アイデアマンなど)と兼任することも多いため、複数の役割を意識して立ち回れる器用さもアピールポイントになります。
議論の軌道修正をする「監視役」
グループディスカッションにおける「監視役」は、議論がテーマから逸れないように軌道修正する、いわば議論の軸を守る役割です。
企業がこの役割に注目するのは、全体を客観的に見て必要なときに的確なひと言を入れる力を見られるため。通常の業務でも、議論が盛り上がるほど話がずれたり感情的な人が出てきたりするので、冷静な視点を持つ人材は重宝されます。
たとえば、話が本題から離れ始めたときに「この議論は少し論点がずれているかもしれません。一度、テーマに立ち返りましょう」とやんわり修正できると、落ち着いていて論理的な人物として高く評価されるでしょう。
監視役はタイムキーパーと兼任するケースも多いため、裏方的な役割を複数こなす柔軟性が問われるポジションでもあります。
議論を活性化させる「アイデアマン」
「アイデアマン」は、議論に新しい視点や柔軟な発想を加え、場の空気を活性化させる力が求められます。
ビジネスでは、問題を多角的に捉える力や、既存の枠にとらわれず発想する力が欠かせません。特に企画職やマーケティング職など、創造性が求められる業種では重要な評価軸になります。
たとえば、グループディスカッションで誰もが「当たり前」と考える方向とは違う意見を出し、「その視点はなかった」とほかの参加者の発想を刺激できれば、議論のブレイクスルーを生む存在として高く評価されるでしょう。ただし、アイデアが多くても、テーマや目的からズレた発言では逆効果になりかねません。常に「目的を見据えた自由な発想」であることが大切です。
プレゼンスキルが試される「発表者」
グループディスカッションの発表者は、話し合いの結果をわかりやすくまとめて、面接官やほかのグループに伝える役割を持ちます。
企業が発表者に期待するのは、ただ書記の内容を読み上げるだけでなく、自分の言葉でわかりやすく伝えられるプレゼンスキルや、堂々と話す度胸です。これにより、コミュニケーション力や積極性をアピールできます。
たとえば、声のトーンや話すスピードに変化をつけたり、表情やジェスチャーを交えたりすることで、聞き手の興味を引けるでしょう。
大勢の前で話す場面に慣れている人や、人前での自己表現が得意な人に特に向いている役割です。
サポートの姿勢が大切な「役割なし」
グループディスカッションで「役割なし」になった場合でも、積極的に議論に参加し、グループのサポートをする姿勢が重要です。
企業は、役割が与えられていなくても臨機応変に行動し、チームの一員として協力できるかどうかを見ています。ただ黙っているだけではなく、自分から意見を出したり、役割を持つメンバーを助けたりする姿勢が評価されるのです。
たとえば、議論が停滞したときに新しい視点を提案したり、発表者や書記の準備を手伝ったりすることで、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献できます。これにより、協調性や柔軟な対応力をアピールできるでしょう。
グループディスカッションに苦手意識がある方は「人事の評価を上げる!苦手な人でもできるグループディスカッションの取り組み方」のコラムで紹介している取り組み方のコツをご参照ください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションではどの役割が有利になる?
グループディスカッションにはさまざまな役割があります。内定を得るために「有利な役割に就きたい」と考えている人もいるでしょう。
しかし、企業側は担当の役割で評価を行っているわけではないため、「どの役割が有利」ということはありません。大切なのは自分に合った役割に就くことです。自分をアピールしたいがために苦手な役割になってしまうと、かえって評価が下がる場合もあります。
自分と向き合い、どんな役割が向いているのか、どの役割に就いてどんな働きができるのかをシュミレーションしておくと良いでしょう。
また、やりたい役割に就けなくても落ち込む必要はありません。決まった役割に就かなくても、議論の中で積極的にアイディアを出したり、場の雰囲気をまとめたり、司会のサポートを行なったり、できることはたくさんあります。評価されるのは役割ではなく「いかに議論に貢献し役割を果たしたか」です。議論の中で自分が今できることを探し、その役割を全うしましょう。
グループディスカッションの中で、自分がグループにどう貢献できるのかを最後まで考えることが大切です。
グループディスカッションの雰囲気に慣れるために練習をしたいと考えている方は「グループディスカッション練習10選!選考で評価されるポイントも解説」のコラムで紹介している練習法をぜひ試してみてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションをうまく進めたい方へ
グループディスカッションは、ただ意見を言い合うだけでなく、チームとして協力しながら問題解決に向かう場です。今回ご紹介した役割や評価ポイントを理解し、自分に合った立ち回り方を意識することで、自然と議論がスムーズに進み、良い印象を残せるでしょう。
グループディスカッションの対策や面接練習を効率良く進めたいなら、プロのキャリアアドバイザーに相談できる「キャリアチケット」へお気軽にお問い合わせください。あなたの強みや改善点を的確にアドバイスし、就活成功まで二人三脚でサポートします。
無料で相談できるので、まずは気軽に登録してみてください。あなたの就活がより自信に満ちたものになるよう、全力で応援します。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら