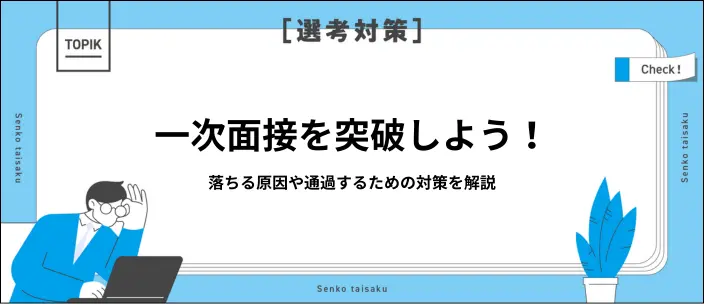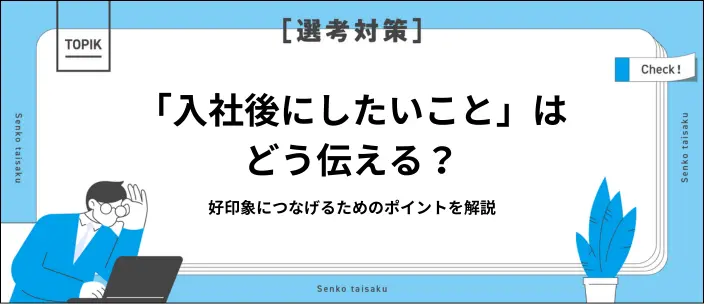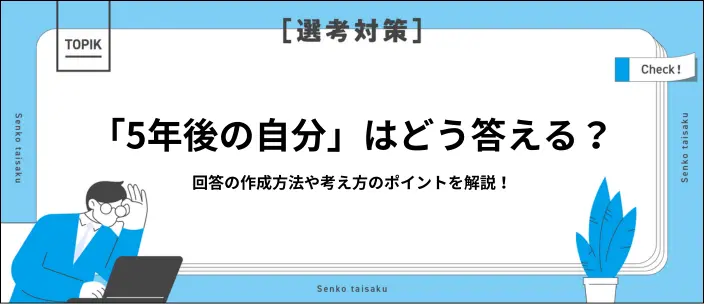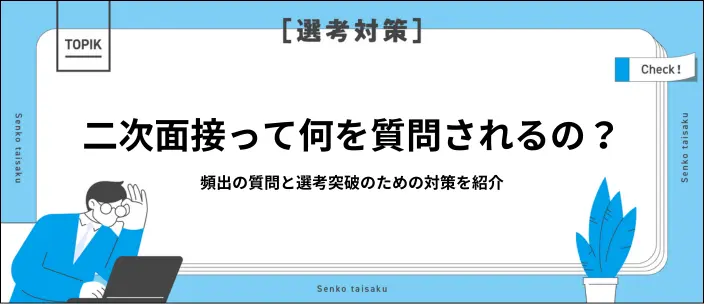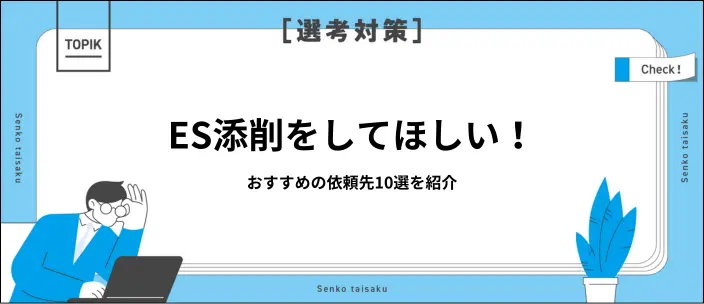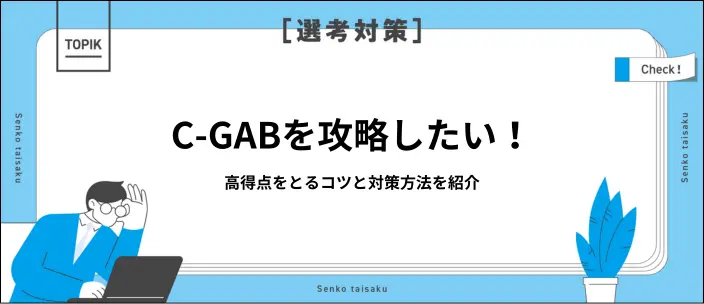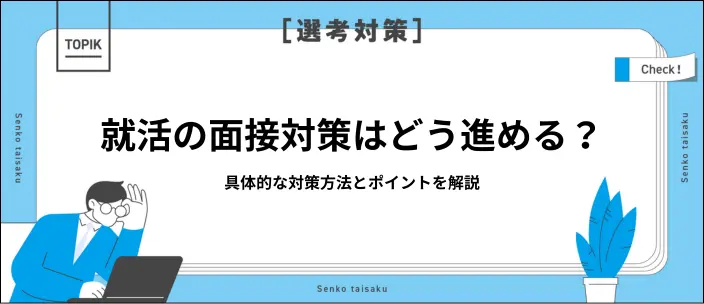このページのまとめ
- 技術面接とは理系の就活で実施される、大学での研究内容を発表する面接のこと
- 技術面接の質問では研究テーマや専門的な知識を深掘りされるため、対策が必要
- 技術面接では柔らかい口調かつ自分の言葉で回答し、逆質問で入社意欲を伝えよう
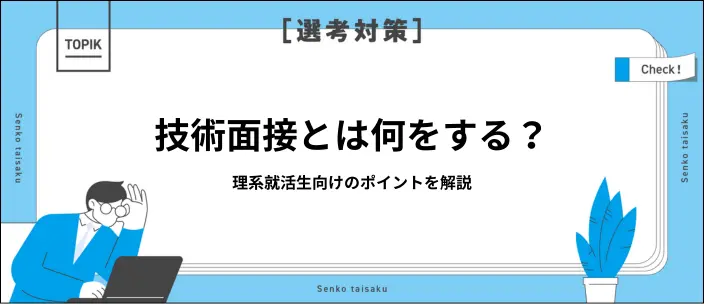
技術面接とは、大学での研究結果を発表し、それに対する質疑応答が行われる理系就活の面接です。技術面接では、専門的な知識を深掘りする質問が多く、基本的な面接対策に加え、技術面接向けの対策を行うことが大切となります。
この記事では、理系で多く行われる技術面接の概要やよくある質問例、面接対策の注意点、面接官のチェック項目、逆質問についてまとめました。大学での研究を活かした就活を志している方は、参考にしてください。
かんたん1分!無料登録技術面接の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 技術面接とは研究内容の発表の場
- 技術面接の目的
- 面接官の多くは技術職員
- 学部生でも技術面接の場合がある
- 技術面接はメーカーやIT企業の技術職に多い
- 技術面接でチェックされる6つの項目
- 1.分かりやすく伝えるプレゼンテーション能力
- 2.研究に必要な技術力や専門性
- 3.問題が起きた際の課題解決力
- 4.柔軟性のある論理的思考力
- 5.コミュニケーション力
- 6.仕事への応用力
- 技術面接が難しいと感じる就活生に向けた6つのコツ
- 1.テンプレートではなく自分の言葉で伝える
- 2.堅い口調になり過ぎない
- 3.面接官の反応をみて専門知識があるか判断する
- 4.面接官からの深堀りを想定して準備する
- 5.具体的なエピソードを交えて説明する
- 6.基本的な面接対策やマナー対策も行う
- 技術面接前に準備しておくこと
- 社会情勢や業界の動向チェック
- 志望企業の研究
- 自分の研究内容に関するスライドの作成
- 技術面接で高評価をもらうためのスライド作成
- スライドの枚数は10枚前後
- 基本的なスライド構成
- 情報を絞り簡潔にまとめる
- 視線誘導を活用して分かりやすい配置にする
- デザインやカラーを整えて見やすくする
- 技術面接に落ちてしまう理由
- 研究内容が伝わりづらい
- 企業が求める技術力が不足している
- 研究内容と企業の事業がマッチしていない
- 研究を成功させる具体的な方法をアピールできていない
- 技術面接でよく聞かれる6つの質問例
- 1.研究テーマについて教えてください
- 2.興味や関心を抱いたきっかけはなんですか?
- 3.研究のオリジナリティはなんですか?
- 4.研究で得たものはなんですか?
- 5.あなたの研究は入社後にどう活かせますか?
- 6.なぜ博士課程や研究者の道に進まなかったのですか?
- 技術面接を受ける際の注意点
- 人事担当にも分かるように説明する
- プレゼンは制限時間内にまとめる
- 読みやすいプレゼン資料を意識する
- 逆質問を準備しておく
- 技術面接における逆質問への対処法
- 「特にありません」といった回答は避ける
- 待遇面やWebサイトに記載されている内容は避ける
- 研究してない学生が技術面接を乗り越える考え方
- 技術面接では研究職への適性や人物像がみられる
- 研究成果の有無は採用に影響しにくい
- 計画性や協調性についてアピールする
- 技術面接を乗り越えて内定獲得を目指したいあなたへ
技術面接とは研究内容の発表の場
「技術面接」とは、技術職や研究職の採用に行われる面接のことで、主に大学や大学院での研究について質問をされます。
理系企業の就活で実施されるのが特徴であり、プレゼン形式で行うのが一般的です。面接の内容はプレゼン内容に関する質疑応答がメインで、一般的な面接によくある質問も行われます。
主なプレゼン形式は以下のとおりです。
・スライドを使った発表
・ホワイトボードや紙の資料を使用した発表
・自由形式
そのため、技術面接の前は通常の面接対策だけでなく、理系の専門知識や研究内容の振り返りなどの対策が必要となるでしょう。理系学生の面接対策に関しては、「理系就活はいつから始める?スケジュールや選択肢、就活の進め方を紹介」も参考にしてください。
技術面接の目的
技術面接は主に「自社で働けるだけのポテンシャルがあるか」「チームワークや協調性があるか」「即戦力となるスキルや経験があるか」を確認するために行われます。技術面接を受ける際には、これらの目的があることを念頭に対策を進めていきましょう。
面接官の多くは技術職員
技術面接ということもあって、面接官は人事ではなく企業の技術職員であるケースが多いようです。就職面接なので、志望動機など一般的な質問もされますが、研究に焦点を当てた内容も問われます。かなり専門性の高い内容を深掘りされることも珍しくありません。理系の専門的な能力やアピールすべき点は事前にまとめておき、面接で焦らず回答出来るように準備しておくことが大切です。
学部生でも技術面接の場合がある
技術面接は大学院生だけでなく、学部生にも実施されるケースが増えています。これは、企業が学部卒の中から優れた技術力や研究姿勢を持つ人材を積極的に採用するようになったためです。
近年は、即戦力としての技術職・研究職に対するニーズが高まり、大学で学んだ専門知識や実験・演習などの経験が問われる傾向があります。企業側は、学部段階でどれだけのことを吸収し、どう活かしてきたかに注目しているのです。
たとえば、研究経験が浅い場合でも、「卒業研究で工夫した点」や「得意な科目をどのように深めたか」などを具体的に説明出来ると高評価につながるでしょう。加えて、通常の面接と同様にガクチカ(学生時代に力を入れたこと)や自己PRも聞かれることがあるため、事前準備は欠かせません。
学部生であっても、専門性や学びに対する姿勢をアピールすることで、技術面接を突破出来るチャンスは十分にあります。
技術面接はメーカーやIT企業の技術職に多い
技術面接は、特にメーカーやIT企業の技術系職種でよく行われます。専門的な知識や論理的思考力を持つ人材が求められる傾向にあり、実践的なスキルや理解度を確かめるために技術面接を導入しているのです。
メーカーでは、設計・開発・生産技術などに配属される技術職が対象となります。IT業界では、プログラミングスキルやシステム構築の経験について具体的に問われるでしょう。
実際の面接では、「どんなアルゴリズムを使っているか」「なぜその構造にしたのか」といった技術的な問いが投げかけられます。単に知識を並べるだけでなく、自分の考えを論理的に伝える力が求められるでしょう。
かんたん1分!無料登録技術面接の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
技術面接でチェックされる6つの項目
技術面接でチェックされる項目を紹介します。研究者や開発部門で活躍出来る人材を見つけるための面接が多く、前述したように専門的な項目もチェックされるでしょう。
1.分かりやすく伝えるプレゼンテーション能力
技術面接では、分かりやすく相手に伝えられるプレゼンテーション能力があるか否かを確認しています。
質問に対する適切な回答のほか、知識が浅い人に対しても分かりやすく話せているかどうか、論理的に説明できているかどうかも重要です。また、面接官は、「資料をうまくまとめてあるか」「時間内に説明出来るか」などの項目もチェックされるでしょう。
自己PRをプレゼン形式で行うコツについては「自己PRをプレゼン形式で行う場合のコツは?準備や注意点を解説」の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
2.研究に必要な技術力や専門性
技術面接では、志望企業で必要な技術・専門性が問われます。入社後には大学で習得した知識だけでなく、新たな分野への対応力や基礎的な技術力も求められるからです。企業は、自社の業務にスムーズに適応出来る素養があるかを見極めたいと考えています。
そのため、面接では現在の知識だけでなく、関連分野に対する応用力や学習意欲も評価の対象です。プレゼン内容が面接官の専門分野と重なる場合、技術的に深掘りされた質問が飛んでくることもあるでしょう。
たとえば、「なぜその手法を選んだのか」「代替案を検討したか」など、専門知識と論理的思考の両方を問われることがあります。こうした場面では、自分の研究に対する理解の深さと、それを他分野に活かす姿勢を示すことが重要です。
技術力と専門性のアピールだけでなく、新しい技術を柔軟に学ぶ姿勢も伝えることで、企業からの評価を高められます。
3.問題が起きた際の課題解決力
研究の中で生じた課題に対してどのように解決したかというのも非常に重要なポイントです。質問を通して「この学生は入社後に課題に直面しても乗り越えることが出来るか」をチェックしています。課題解決力があるかをアピールするためにも、トラブルや課題に直面した場面から解決に至るまでの過程を整理しておきましょう。
たとえば、「データが予想どおりに得られなかったが、装置の調整や測定条件を見直すことで安定した結果が得られた」といった具体的なエピソードを交えると、説得力が増します。また、その経験を通して得た学びを伝えることで、成長意欲のある人物であることもアピール出来るでしょう。
課題解決の姿勢やプロセスを丁寧に伝えることが、面接官にポジティブな印象を与えるポイントです。
4.柔軟性のある論理的思考力
論理的思考力とは、研究を進めるうえで必要な基本的素養です。具体的には下記のような力が問われます。
・課題をどのように特定するか
・解決のためにどのような仮説を立て、アプローチするか
・結果をどのように捉え、次に繋げていくか
これらは、失敗することも多い研究に、前向きに邁進していく原動力ともいえるでしょう。論理的思考力は自分の専門分野でなくても、思考やアプローチ次第で解決へ導ける柔軟性のアピールにもつながります。
5.コミュニケーション力
研究職やエンジニアなどの理系職では、高いコミュニケーション力が必要とされます。研究を行う際は、共同研究者や教授とのディスカッションや認識のすり合わせ、報連相が欠かせないからです。
そのため、技術面接では質問の受け答えや質問の意図を理解しているかなどをチェックして、コミュニケーション力があるかを確認します。説得力のある伝え方について「コミュニケーション能力をアピール!面接での伝え方とは」の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
6.仕事への応用力
仕事では、大学での研究活動と全く同じことを行うことはほとんどありません。そのため、面接官は「研究活動を通じて得た力」がどのようにして自社の仕事へ活かせるかをチェックしています。
理系就活生は、自分の研究で培った力がその仕事でどう活かせるか、仕事への応用力をアピールすることが必要。
そのためには、以下のことが重要です。
・企業の仕事内容を具体的に理解する必要がある
・自分の研究活動を振り返り、どのような力がその企業の仕事のシーンで活かせるかを考える必要がある
技術面接を受ける際は、「仕事へどう活かせるか」の観点も意識して取り組みましょう。
かんたん1分!無料登録技術面接の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
技術面接が難しいと感じる就活生に向けた6つのコツ
技術面接を成功させるために、アピールのポイントを知っておきましょう。6つのコツを紹介するので参考にしてください。
1.テンプレートではなく自分の言葉で伝える
面接ではテンプレートの言葉ではなく、自分の言葉で伝えるようにしましょう。「一緒に働きたい」と思ってもらうためには、自分らしい言葉で、親しみやすさや人間味を感じてもらうことがポイントになります。
企業にとって面接は、ともに働く仲間を採用する場です。そのため、研究内容だけでなく、就活生の人となりを知り、職場に合っているかも重要視しています。テンプレートや丸暗記した言葉では、あなたの人柄はうまく伝わりません。自分なりに考え、面接に臨むようにしましょう。
2.堅い口調になり過ぎない
技術面接では固い口調になっていないか意識しましょう。研究内容を話す際は専門用語が多く、固い口調になってしまいがちだからです。
あまりにかしこまった口調にしてしまうと、面接官に自分の人柄や魅力を伝えきれません。話しやすい雰囲気になるように、柔らかい口調を意識することも面接対策です。
面接での話し方については、「面接での話し方には重要マナーが!就活生なら知っておくべき好印象を与えるコツとは」も参考にしてください。
3.面接官の反応をみて専門知識があるか判断する
技術面接では、面接官の理解度に応じて伝え方を柔軟に変えることが大切です。技術面接の担当者が必ずしも自分の研究分野に精通しているとは限りません。たとえば、生物系の研究者が機械工学の内容を評価する場合もあります。そのようなときに、専門用語を多用した説明をしてしまうと、面接官が内容を正しく把握できず、評価につながりにくくなるでしょう。
重要なのが、話しながら面接官の表情やうなずきなどの反応を見て、説明の深さを調整することです。具体的には、「話が伝わっていないかも」と感じたら図や例を交えて平易に説明し、「理解が深そう」と判断出来る場面では踏み込んだ話をして専門性をアピールする、というように対応すると良いでしょう。
相手に合わせて説明の仕方を変える姿勢は、技術力だけでなくコミュニケーション力の高さも示せます。
4.面接官からの深堀りを想定して準備する
面接では回答への深掘りをされることが多いため、行われるであろう質問は事前に想定しておきましょう。技術面接の場合には、プレゼン内容に関する深掘りをされる傾向にあります。特に、面接官が同じ分野に詳しい場合には、研究手法の選定理由や実験結果の考察など、細部にわたる質問をされることもあるでしょう。
質問に回答できないと、「熱心に研究していないのではないか」「専門性を高めることが苦手なのではないか」と捉えられる可能性があるので気をつけてください。こうした問いにしっかり答えるためには、研究内容を自分の言葉で整理し、何を追求されても説明出来るように準備しておくことが重要です。
もし、質問への適切な回答が分からない場合は、素直に「分からない」と伝えるのが無難。無理にごまかそうとすると、印象を悪くする恐れがあります。
5.具体的なエピソードを交えて説明する
研究内容や学生生活について聞かれた場合は、具体的なエピソードを盛り込んで伝えましょう。詳しいエピソードを提示することで、面接官があなたの学生生活をイメージしやすくなるからです。
具体的なエピソードを伝えることは、自分を印象付けることにつながります。珍しいエピソードや印象的なエピソードを伝えられれば、「△△の学生だ」と覚えてもらえることもあるでしょう。
6.基本的な面接対策やマナー対策も行う
技術面接でも、基本的な面接対策やマナー対策を怠ってはなりません。技術面接でも社会人としての基本的な立ち振る舞いは評価されています。
技術面接と普通の面接で、求められるマナーは変わりません。普通の面接と同じように、ビジネスマナーや話し方、入退室のマナーなどを覚えておきましょう。面接対策や準備に関しては、「面接対策!前日までに準備しておきたいこと」の記事で解説しているので、こちらも参考にしてください。
かんたん1分!無料登録技術面接の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
技術面接前に準備しておくこと
ここでは、技術面接の前に押さえておきたい具体的な準備ポイントを紹介します。技術面接は、単に研究成果を説明するだけの場ではありません。面接官は「企業で活躍出来る人材かどうか」を見極めるため、プレゼンの内容はもちろん、受け答えや視野の広さ、準備の丁寧さまでを細かくチェックしています。そのため、事前の準備が大切です。
社会情勢や業界の動向チェック
技術面接で評価を上げたいなら、社会全体や業界の動きにもアンテナを張っておきましょう。なぜなら、企業は単に技術力のある学生よりも、広い視野で物事をとらえ、変化に対応出来る人材を求めているからです。
たとえば、研究内容が再生可能エネルギーに関するものであれば、「脱炭素」や「GX(グリーントランスフォーメーション)」といったキーワードを押さえ、それに対する業界の取り組みを知っておくと、面接での説得力が高まります。実際に、企業が現在取り組んでいる事業や研究開発と結びつけて話せれば、「この学生は企業理解も深く、即戦力になりそうだ」と好印象を与えられるでしょう。
日ごろからニュースや業界誌、企業のプレスリリースなどに目を通しておくことが、説得力のある受け答えにつながります。
志望企業の研究
技術面接では、企業ごとの特徴に合わせてプレゼンを工夫することが差をつけるポイントです。企業にはそれぞれ異なるミッションや強みがあり、「どんな人材がフィットするか」の基準も違ってきます。
たとえば、同じ半導体業界であっても、ある企業は製造工程の効率化に力を入れている一方、別の企業は先端技術の研究開発に注力していることもあります。そのため、志望先のビジョンや重点領域に合わせて、研究のどの部分を強調するかを調整することが重要です。
スライドの構成を変えるのが難しい場合でも、「冒頭の説明で企業の事業と自分の研究の関連性を述べる」といった工夫なら取り入れやすいでしょう。企業理解を深めた上でプレゼンに臨む姿勢が、志望度の高さと柔軟な対応力をアピールする材料になります。
自分の研究内容に関するスライドの作成
技術面接の印象を大きく左右するのが、プレゼンに使うスライドの完成度。スライドは単なる補助資料ではなく、自分の研究を正しく、分かりやすく伝えるための大切なツールだからです。
たとえば、図やグラフが分かりにくかったり、専門用語だらけの文字ばかりのスライドだったりすると、せっかくの研究内容が伝わらずに評価が下がる可能性もあります。逆に、視覚的に整理されたスライドと端的な説明が組み合わされれば、「伝える力」や「論理的思考力」の高さも印象づけられるでしょう。
作成にあたっては、先輩の資料を参考にしたり、大学のキャリア支援センターでチェックしてもらったりするのがおすすめです。また、企業によっては紙の資料やホワイトボードを求める場合もあるので、事前に指定がないかも確認しておきましょう。
かんたん1分!無料登録技術面接の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
技術面接で高評価をもらうためのスライド作成
技術面接で好印象を残すためには、分かりやすく構成されたスライドが欠かせません。ただ研究内容を並べるだけでは、面接官に伝わりにくく、せっかくの努力が正当に評価されない可能性もあります。短時間で自分の研究と考察を的確に伝えるには、「何を、どう見せるか」を意識した資料作りが重要です。
ここでは、技術面接で高評価を得るためのスライド作成のポイントを紹介します。
スライドの枚数は10枚前後
スライドの枚数は、10枚前後を目安にするのが効果的。技術面接では1人あたりのプレゼン時間が10分前後に設定されているケースが多く、それに合わせて「1分で1枚のスライドを説明する」ペースで構成するのが一般的だからです。
もちろん企業ごとに面接時間は異なるため、時間の長さに応じてスライドの枚数や各スライドでの説明のボリュームは調整が必要。たとえば、5分のプレゼンなら5~6枚程度、15分ならやや詳細に展開する形で構成を考えると良いでしょう。
時間内で的確に伝えるためにも、あらかじめ想定される時間に合わせてスライドの数を調整し、練習を重ねることが成功のポイントです。
基本的なスライド構成
スライドには一定の構成パターンを持たせると、論理的で分かりやすいプレゼンになります。なぜなら、構成が整理されていれば、面接官も内容を順を追って理解しやすくなるからです。
一般的には、以下のような構成が効果的といわれています。
・導入:研究テーマとその背景
・目的:何を解明したいか、既存研究との差別化
・方法:どのように研究・実験を進めたのか
・結果:実験・分析結果を図表などで簡潔に提示
・展望:得られた知見の意義や今後の発展可能性
この流れを踏まえてスライドを構成すれば、自分の研究がどのような目的を持ち、どんな結果を導いたかをスムーズに伝えられるでしょう。基本構成を押さえたうえで、企業や面接官の視点を意識した説明を添えることが、高評価への近道です。
情報を絞り簡潔にまとめる
限られた時間の中で印象を残すには、情報を取捨選択してスライドを簡潔にまとめることが重要です。スライドを作成する際は、つい多くの情報を詰め込みたくなりがちですが、情報量が多過ぎると本当に伝えたいことが埋もれてしまう可能性があります。
たとえば、研究の全過程を細かく説明したくても、10分程度では時間が足りません。そのため、スライドには要点だけを盛り込み、口頭で補足するスタイルが効果的です。また、「1スライドにつき1メッセージ」を心掛けることで、内容がより明確になります。
思い切って情報を絞ることで、聞き手にとっても理解しやすい、説得力あるプレゼンになるでしょう。
視線誘導を活用して分かりやすい配置にする
スライドの情報配置は、視線の流れを意識することで格段に伝わりやすくなります。人の目は自然と「左上から右下」へと動くため、この流れに沿って情報を配置すると、内容が頭に入りやすくなるからです。
たとえば、重要なポイントはスライドの左上に置き、補足情報を右下に配置すると、無理なく読み取れる構成になります。時系列で並べる場合は、「過去→現在→未来」の順に左から右へ配置すると自然です。また、写真や図表は左側に置くことで、視覚的にも印象づけやすくなります。
視線の動きに沿った配置を意識することで、スライド全体の理解度が大きく向上するでしょう。
デザインやカラーを整えて見やすくする
視認性の高いスライドデザインは、内容理解のスピードを高め、面接官の印象にも大きく影響します。内容が素晴らしくても、色使いがバラバラだったり文字が読みづらかったりすると、それだけでマイナスの印象を与えることも。
そのため、あらかじめ「背景色」「文字色」「メインカラー」「アクセントカラー」の4色を統一しておくことがポイントです。たとえば、背景は白、文字は黒といったように、基本的な配色はシンプルに保ち、メインカラーには赤や青など印象に残る色を使用すると良いでしょう。アクセントカラーはメインカラーと対照的な色を選ぶことで視認性が高まります。
また、色弱の方への配慮やモノクロ印刷でも意味が伝わるデザイン(点線や網掛けなど)も意識すると、より丁寧な資料として評価されるでしょう。見た目が整っているスライドは、それだけで「準備力」や「配慮力」が伝わり、好印象を与えられます。
かんたん1分!無料登録技術面接の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
技術面接に落ちてしまう理由
ここでは、技術面接でよく見られる失敗例を紹介し、事前に対策しておくべきポイントを明らかにします。
研究内容が伝わりづらい
技術面接で不合格になる大きな理由の一つが、研究内容の伝わりにくさです。面接官に内容が理解されないと、学んだことや自分の強みも伝わらなくなってしまいます。
たとえば、専門用語を前提に話してしまったり、背景説明が不十分だったりすると、相手が研究の全体像を掴めないまま終わってしまうことも。だからこそ、専門外の人にも通じるような分かりやすい表現と構成を意識し、伝わるプレゼンを心がけましょう。
企業が求める技術力が不足している
技術面接では、最低限の技術力が備わっているかどうかが問われます。企業は新卒にポテンシャルを期待しますが、基礎的なスキルが欠けている場合は不合格になる可能性が高まるでしょう。
たとえば、プログラミング知識が必須の職種で基本的な文法さえ理解していない場合、ポテンシャルを評価しづらくなってしまいます。そのため、応募企業がどのようなスキルを求めているのかを確認し、面接前に自分の技術力を棚卸ししておくことが重要です。
研究内容と企業の事業がマッチしていない
どれだけ素晴らしい研究を行っていたとしても、その内容が企業の事業と結びつかないと評価は難しくなります。企業は、採用した学生が自社で活躍出来るかどうかを重視しており、研究テーマとの親和性も重要なポイントです。
たとえば、AI技術を強みにしている企業に対して、有機合成の研究をアピールしても即戦力としての魅力は伝わりにくいかもしれません。だからこそ、企業の事業内容や技術領域を事前にリサーチし、面接では「自分の専門性がどう活かせるか」を明確に伝える必要があります。
研究を成功させる具体的な方法をアピールできていない
研究成果だけでなく、その過程で何をどう考え、どんな工夫をして課題を乗り越えたかを語れることが大切です。技術面接では「どんなプロセスで研究を進めたのか?」という視点が重視されます。
たとえば、予期せぬ実験失敗に対してデータを分析し、新しい方法を模索して改善したエピソードなどがあると、問題解決力を印象づけられるでしょう。成功に至るまでの思考の道筋を具体的に説明することで、あなたの技術者としてのポテンシャルが伝わります。
かんたん1分!無料登録技術面接の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
技術面接でよく聞かれる6つの質問例
この章では、技術面接でよくある質問例をご紹介します。下記を参考に、具体的な回答例を考えてみましょう。
1.研究テーマについて教えてください
技術面接で質問されるのは、主に大学での研究内容について。この質問では、研究内容を分かりやすく説明出来るかどうかがポイントです。
面接には研究について知識がない人も同席する可能性もあるため、誰にでも伝わるように話すことを意識してください。
また、研究について深掘りされた際に曖昧に回答すると、「真面目に取り組んでこなかったのでは?」と判断されてしまう可能性もあります。
研究の概要を話すだけでなく、深掘りした質問にも対応出来るよう、質問を想定して回答を用意しておきましょう。
回答例
私の研究テーマは、環境に優しいバイオプラスチックの開発です。具体的には、再生可能な植物由来の材料を使用して、従来の石油由来のプラスチックと同等の性能を持つ新しい材料を作ることを目指しています。
この研究は、プラスチックごみを減らし、環境保護に役立つと考えています。
2.興味や関心を抱いたきっかけはなんですか?
自分が研究テーマを選択した理由を明確に説明出来るようにしましょう。どのような事柄に興味を持ち、どのように研究と向き合ってきたかをしっかりと回答することが大切です。
就活生の探究心が面接官に伝わりプラス評価へとつながります。
回答例
私がバイオプラスチックの研究に興味を持ったきっかけは、高校時代に見たドキュメンタリー番組でした。
そこで、プラスチック廃棄物が海洋生態系に与える深刻な影響を知り、環境問題を解決するために自分が出来ることは何かを考えるようになりました。大学で化学を専攻し、教授の勧めもあってこのテーマに取り組むことを決めました。
3.研究のオリジナリティはなんですか?
研究の独自性に関する質問も、技術面接では多く見受けられます。大学の研究内容は代々引き継がれているものも多いため、「独自性が分からない」という就活生もいるでしょう。
しかし、質問に対しうまく答えられないと、面接官から「理系大学で与えられた研究テーマに取り組んだだけなのか」と思われる可能性があります。自分なりのアプローチ方法や手順の違いなど、オリジナリティを見出して回答するようにしてください。
回答例
私の研究のオリジナリティは、使う素材の選び方と、作り方の工夫にあります。一般的な研究では素材として木や草が使われていますが、私は未利用資源である階層を使うことでコストを削減し、高い生分解性を実現しました。また、作り方もエネルギー消費を抑える新しい方法を導入しました。
4.研究で得たものはなんですか?
知識や技術力だけを説明するのではなく、どのように困難を乗り越えてきたかを話すことが重要です。困難があっても諦めずに果敢に取り組んできたということをアピールできれば、企業は「課題解決力や業務遂行力がある」と判断し、就活生の入社後の活躍をイメージしやすくなります。
回答例
研究を通して、問題解決力と忍耐力を身につけることができました。研究を進める中で、実験結果がうまくいかない時期がありました。その時、何度も試してみたり、関連する文献を一度調べ直したりして、教授や同僚と話し合うことで問題を特定し、解決策を見つけました。この経験を通じて、問題を解決する力とあきらめずに続ける力を身につけることができました。
5.あなたの研究は入社後にどう活かせますか?
研究を通して得た課題解決能力をアピールすることで、入社後に難題に直面しても乗り越えられる力をアピールできます。また、設備や装置の使い方に慣れている場合は、理系特有のスキルを伝えることで、プラスの評価がされやすいでしょう。
回答例
私の研究で学んだバイオプラスチックの知識と技術は、御社の新しい材料を開発するプロジェクトに役立つと考えています。また、実験装置の使い方やデータの分析も得意です。たとえば、御社が取り組んでいる「環境に優しいパッケージ開発プロジェクト」では、私のこれまでの研究で得た知識やスキルを活かすことが出来ると思います。
6.なぜ博士課程や研究者の道に進まなかったのですか?
技術面接では、博士課程に進学しなかった理由を尋ねられることがあります。この質問に対しては、明確な理由を述べることが重要です。
経済的な理由や早く実務経験を積むことを理由とする人が多いですが、技術面接では自分自身の具体的な理由を説明することが求められます。この質問に答える際には、自分がなぜ就職を選んだのか、どのようなキャリア目標を持っているのかを明確に伝えましょう。
回答例
私は博士課程に進むよりも、早く実務経験を積みたいと考えました。大学での研究を通じて、環境に優しいバイオプラスチックの開発に取り組む中で、製品開発や実際のプロジェクトに携わることに強い興味を持ちました。
入社後にしたいことの回答に関しては、「入社後にしたいことの例文13選!見つけ方や伝え方のコツと注意点も解説」も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録技術面接の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
技術面接を受ける際の注意点
技術面接では、分かりやすく伝えたり、時間内に伝えたりすることを意識しましょう。技術面接で失敗しやすい注意点をまとめたので参考にしてください。
人事担当にも分かるように説明する
技術面接でプレゼンを行う場合、人事担当にも分かるような言葉で説明しましょう。人事担当が専門的な知識を持っているとは限らないためです。
人事担当は、就活生の採用や人事評価を行うことがメインの仕事になります。そのため、開発職などが扱っている内容や、学生の研究内容については詳しくないことも。
技術面接でアピールするためには、事前知識がなくても分かりやすく伝える内容を準備することが大切です。「専門用語を使わない」「研究内容よりも自身の考えをメインに伝える」などを工夫してください。
プレゼンは制限時間内にまとめる
プレゼンを行う場合には、制限時間内にまとめましょう。ルールを守って、分かりやすく伝えられるかも評価ポイントです。
社会人になると、限られた時間で同僚に説明する機会は多くなります。ダラダラと分かりにくい説明よりも、端的で分かりやすい説明のほうが評価されるでしょう。
選考ではプレゼンを通して、仕事でどのように活躍できそうかも見られています。制限時間が指定されている場合は、必ず守るようにしてください。
読みやすいプレゼン資料を意識する
プレゼン資料を用意する場合、読みやすさにも気を配りましょう。内容が伝わりやすくなり、評価が上がる場合もあります。
読みやすいプレゼンにするには、図や写真を使ったり、表やグラフなどの表記を使ったりするのがポイントです。ただ文字でまとめるのではなく、視覚的に分かりやすい資料を意識してみるとアピールにつながるでしょう。
逆質問を準備しておく
逆質問を聞かれても良いように、あらかじめ聞きたいことを2つ3つ用意しておきましょう。逆質問とは、「何か質問はありますか?」と企業が学生に対して聞きたいことを質問することです。
逆質問には、次のような内容があります。
・入社前に勉強しておくべきことはありますか?
・研究分野以外で△△も勉強していますが、御社で活かせる場面はありますか?
・成果を出している人の共通点を教えてください
・仕事で大変な部分を教えてください
逆質問の内容が良ければ、面接官からの印象アップにつながります。技術面接中に思い浮かんだ疑問を伝えても良いでしょう。
ただし、給料や福利厚生などのように、「すべきではない質問」もあります。逆質問の例や注意点は「就活の逆質問例50選!質問を考える際のポイントや準備方法も解説」の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
かんたん1分!無料登録技術面接の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
技術面接における逆質問への対処法
通常の面接と同様、技術面接でも「何か質問はありますか?」という逆質問に備えておく必要があります。逆質問の対処法では、注意点も紹介。あらかじめ質問を用意し、本番に備えましょう。
「特にありません」といった回答は避ける
技術面接の逆質問では、「特にありません」という返答は避けましょう。面接官が逆質問をする理由は、自社への志望度や意欲のチェックだけでなく、入社後のミスマッチ防止といった目的もあるためです。
どうしても逆質問の内容が思いつかない場合は、「質問とは違いますが」と前置きをしたうえで、感謝や入社意欲を伝えましょう。面接に時間を割いてくれたことへの感謝の言葉や、入社意欲を示す言葉を述べると印象ダウンを避けられる可能性があります。
待遇面やWebサイトに記載されている内容は避ける
逆質問は、ただ質問をすれば良いというものではありません。逆質問の内容にも注意が必要です。
技術面接の逆質問では、待遇面やWebサイトに記載されている内容を避けてください。企業のWebサイトにも掲載されている内容を聞くと、「自社についてきちんと理解していない」「企業研究ができていない」という印象を与える恐れがあります。
また、給料や休日、福利厚生など、待遇についての質問に終始するのも望ましくありません。仕事への意欲を疑われてしまうでしょう。
かんたん1分!無料登録技術面接の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
研究してない学生が技術面接を乗り越える考え方
「技術面接を控えているけど、大学で研究していない」「研究の成果が得られなかった」という就活生もいるでしょう。研究してない場合に技術面接を乗り越える考え方を紹介します。
技術面接では研究職への適性や人物像がみられる
技術面接では、研究職への適性や人物像がチェックされます。研究職の適性では、「一つのことを深く突き詰め知識を身につけられるか」「失敗しても諦めずに続けられるか」などが重要です。また、企業が求める人物像かどうかは、就活生の性格や強みなどで判断されるでしょう。
何らかの理由から研究してない場合は、理由を正直に伝え、希望する職種への熱意や意気込みをアピールしてください。また、研究内容や職種に関する資格取得も大切です。研究していない場合でも、専門性や技術力を証明できます。
研究成果の有無は採用に影響しにくい
技術面接において、研究成果の有無は採用には影響しにくい場合が多いです。研究成果は大学生のうちに出せるケースは少なく、面接官は最初から成果を重要視していないケースもあります。
選考突破に大切なことは、成果の有無よりも、研究の過程を分かりやすく伝える能力が大切。また、「一緒に仕事したいかどうか」も大切な要素の1つです。
研究成果がなくても、一緒に仕事をしたいと思ってもらえるようにしましょう。面接官の目をみて分かりやすい言葉で研究内容を説明し、円滑なコミュニケーションをとるように心がけてください。
計画性や協調性についてアピールする
何らかの理由で研究してない場合は、計画性や協調性をアピールすると効果的でしょう。計画性は、目標に向かって計画を立てて実行する力を指します。協調性は、周りの人と協力して物事を遂行する力です。
研究は、1人で行うというよりは、多くの人の協力を得て取り組むケースが多いでしょう。また、研究に取り組む際は、調査や実験の前に前もって研究計画を立てることが一般的です。
仕事で研究職や開発部門に配属された場合、社員と協力し、計画を立てて遂行する力が必要。入社への熱意や意気込みだけでなく、計画性や協調性のアピールを行いましょう。計画性をアピールしたいと考えている場合は、「【例文】自己PRで計画性をアピールしたい!効果的な方法と向いている職種」の記事を参考にしてください。
かんたん1分!無料登録技術面接の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
技術面接を乗り越えて内定獲得を目指したいあなたへ
技術面接では、研究内容に関するプレゼンテーション能力や課題解決力、論理的思考能力などがチェックされます。また、「研究してない」「研究成果がない」といった就活生は、協調性や計画性をアピールし、入社意欲や熱意を示すことが大切です。
しかし、「技術面接でうまく話せるか不安」「そもそも面接自体苦手」という理系の就活生も少なくないと思います。そんな方にはキャリアチケット就職エージェントがおすすめです。
キャリアチケットでは、技術面接だけでなく、面接の質問に対する回答のアドバイスや模擬面接を実施。そのほか、面接の受け答えに重要な自己分析の仕方やESの添削など、就活に関するサポートをすべて無料で行っています。
技術面接を控えていて不安に感じている就活生は、ぜひ一度ご相談ください。
かんたん1分!無料登録技術面接の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。