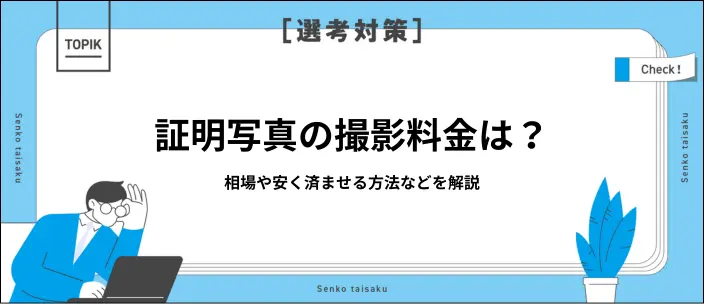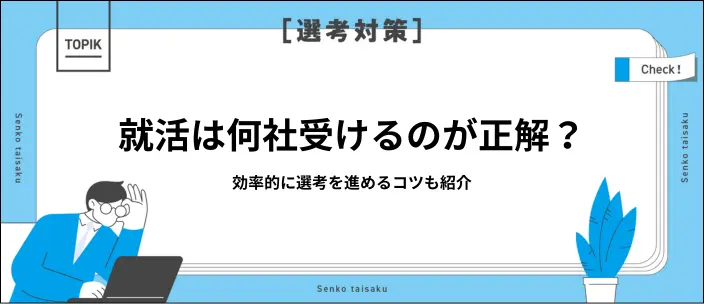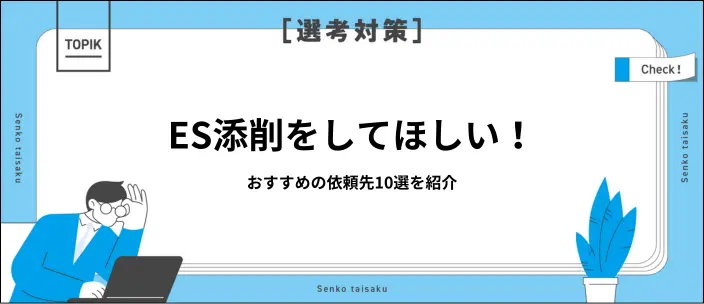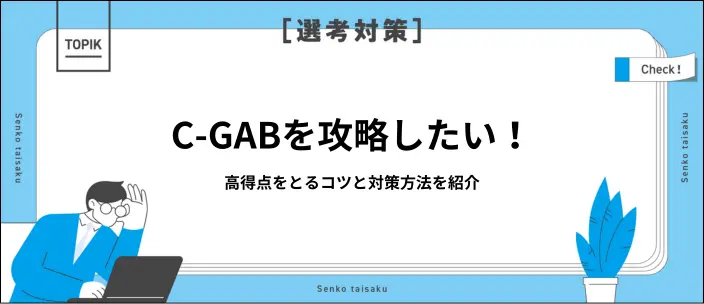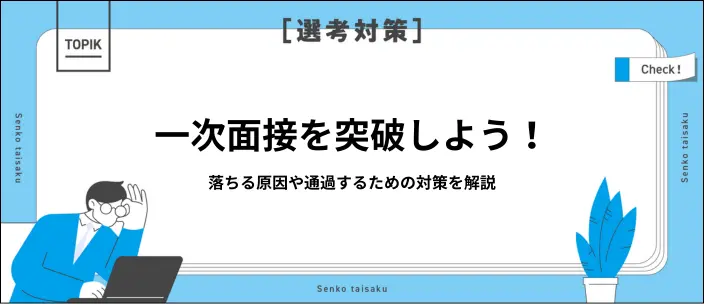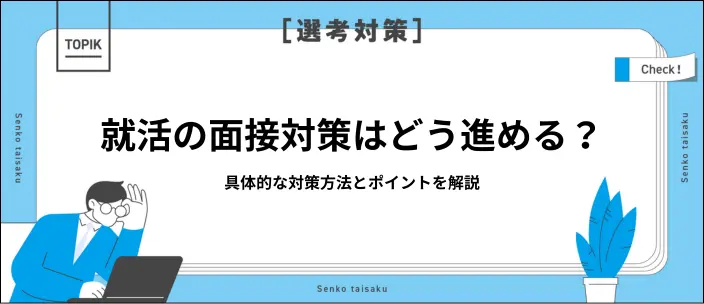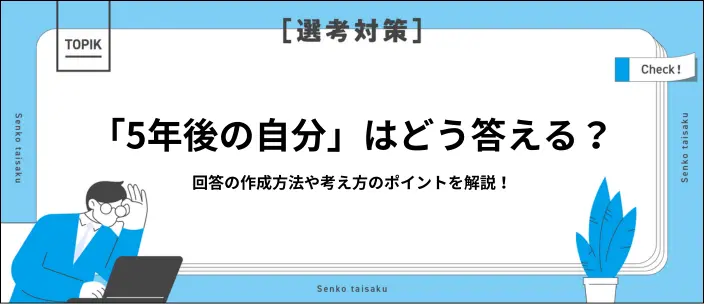このページのまとめ
- 就活ノートには「就活スケジュール」「自己分析」「企業情報」などをまとめる
- 就活ノートを作るとスケジュールを管理しやすく、就活を効率良く進められる
- 就活ノートは1冊でコンパクトにまとめ、自分の考えや意見も書くのがおすすめ

「就活ノートは必要なの?」と、就活ノートの作成に悩む就活生も多いでしょう。就活ノートがあると効率良く就職活動を進められるので、作成することをおすすめします。
この記事では、就活ノートにまとめたい内容やおすすめの作り方を解説しています。作成時のポイントや使い方、おすすめのサイズと種類もまとめたので、就活準備をスマートに進めたい人はぜひ参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就活ノートについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 就活ノートとは?就職活動を成功させるためには必須
- 就活ノートは今日から作成しよう
- 就活ノートのまとめ方は?書くべき9つの内容
- 1.就活のスケジュール
- 2.自己分析
- 3.他己分析
- 4.業界研究の内容
- 5.企業の情報
- 6.インターンシップに参加した感想
- 7.OB・OG訪問の記録
- 8.採用担当者や面接官の発言内容
- 9.選考過程や結果の振り返り
- 就活ノートを作成する5つのメリット
- 1.スケジュール管理がしやすくなる
- 2.これまでの就活の振り返りができる
- 3.企業理解がしやすくなる
- 4.就職活動を効率良く進められる
- 5.読み直してモチベーションを保てる
- 就活ノートを書く際のキャリアアドバイザーからのアドバイス
- スケジュール
- 企業のこと
- 選考のこと
- 自分のこと
- 就活ノートのおすすめの作り方
- 選考スケジュールをノートの前方に書く
- スケジュールの次に企業情報を書く
- 自己分析はノートの後ろのほうに書く
- 目次を見やすい位置に書く
- 就活ノートを作る6つのポイント
- 1.1冊にまとめる
- 2.情報は簡潔にまとめる
- 3.自分の意見や考えも書く
- 4.情報の種類ごとに記載する場所をまとめる
- 5.情報ごとにペンやマーカーで色分けする
- 6.情報を追加できるように余白を作る
- 就活ノートの使い方
- 面接前に企業情報を見返す
- 自分の考えにブレがないか見直す
- 就活ノートの大きさは?サイズ選びのポイントも解説
- 就活ノートにおすすめしたい4つのタイプ
- 1.ポケットサイズの手帳
- 2.ルーズリーフ
- 3.スマホやタブレット端末
- 4.市販の就活ノート
- 就活ノート作成に役立つ4つのアイテム
- 1.付箋
- 2.消せるボールペン
- 3.蛍光ペン
- 4.スマホアプリ
- 就活ノートの作り方に悩むあなたへ
就活ノートとは?就職活動を成功させるためには必須
就活ノートとは、自分の就職活動に関するあらゆる情報をまとめたノートのことです。就職活動に関する情報や考えを1冊のノートにまとめることで、内定獲得に向けた対策を効率良く行えるようになります。
就職活動では、業界・企業研究や自己分析などを通じてさまざまな情報を入手しますが、それぞれが一貫性もなく乱雑にまとまっていると、せっかくの情報を有効活用できません。また、就職活動を進めるなかで考え方に変化があったり、選考を通じて気づきを得たりすることもあるでしょう。
ノートにメモしておけば、必要な情報や自分の考えを瞬時に振り返れます。情報を整理することは内定獲得に向けても重要なので、就活ノートを作成してみましょう。
就活ノートは今日から作成しよう
就活ノートは、夏のインターンシップ申込みが始まる大学3年生の6月ごろに作成を開始するのが一般的なようです。就活準備は早く始めて損をすることはないので、就活ノートの作成がまだであれば、今日から取り掛かるのがおすすめです。
就職活動の一般的なスケジュールや進め方は「就活のやり方を徹底解説!基本的な進め方やスケジュールをご紹介」の記事を参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就活ノートについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活ノートのまとめ方は?書くべき9つの内容
就活ノートには、選考のスケジュールや自己分析結果、業界・企業研究といった各種の選考対策で得られた情報をまとめるとよいでしょう。
ここでは、効率良く就職活動を進めるためにまとめておきたい内容を9つ紹介します。以下の項目を参考に、就活ノートに何を書くかイメージしてみてください。
1.就活のスケジュール
就活ノートに必ずまとめておきたいのが、各種選考のスケジュールです。具体的には、以下のような内容を参考にするとよいでしょう。
・会社説明会の日程
・セミナーの日程
・エントリーシートの締切日
・Webテストの日程
・面接日時と会場
スケジュール管理は就職活動をスムーズに進めるのに欠かせないため、すべてを集約させるのがおすすめです。企業によってはマイページにログインするケースもあるので、IDやパスワードをメモするページを別途用意しておいてもよいでしょう。
2.自己分析
就活ノートには、自己分析の結果もまとめておきましょう。以下のように、項目別で分けておくのがおすすめです。
・就活の軸
・長所と短所
・自己PR
・自己紹介
・学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)
・趣味
・特技
・理想のキャリアプラン
・将来の夢
応募書類の作成や面接で自信を持って回答するには、徹底した自己理解が欠かせません。就活ノートに自分の考えや価値観がまとまっていれば、ブレがないか定期的に振り返ることもできます。
モチベーショングラフや自分史を作成しよう
自己分析の進め方に悩む場合は、過去の出来事の振り返りに便利な「自分史」、出来事におけるモチベーションの波をグラフにした「モチベーショングラフ」の作成がおすすめです。これらを作成することにより、自分の得意分野や力を発揮できる環境などを視覚化でき、自分を客観視しやすくなります。
自分史やモチベーショングラフの作り方について知りたい就活生は、「自分史は就活に役に立つ!作り方のポイントや選考への活かし方を解説」の記事や「自己分析に役立つモチベーショングラフとは?作成のコツや活用方法を解説」の記事をご覧ください。
3.他己分析
自己分析の結果だけでなく、友人や家族などから自分の印象を尋ねた「他己分析」の結果もまとめておきましょう。
・第一印象
・長所
・自分の性格を一言で表すと
・自分は友人のなかでどういう役割だと思うか
上記のような質問に対する回答をまとめておくと、振り返った際に自分を客観視しやすくなります。ノートにまとめる際は、質問への回答だけでなくその根拠も書いておきましょう。
他己分析のやり方について知りたい就活生は、「他己分析とは?有意義かつ効率的なやり方のポイントや質問例30選を紹介」の記事を参考にしてみてください。
4.業界研究の内容
就活ノートには、業界研究の結果や内容もまとめておきましょう。書籍やインターネット記事、セミナーなどで調べた情報を項目ごとに整理してみてください。
・業界の特徴
・業界の市場規模
・業界の将来性
・業界の課題
・業界の主要企業やシェア
・BtoBかBtoCか
・関連する業界
・業界に対するイメージや興味関心の度合い
上記の項目を中心に、業界ごとに同じ情報をピックアップして整理することで、それぞれの比較がしやすくなります。関心のある業界だけでなく、関連業界も含めて幅広く調べれば、社会の仕組みの理解にもつながるでしょう。
5.企業の情報
業界研究の結果と同様に、企業研究の内容もノートに整理しましょう。以下のような項目を一覧にしてまとめることで、企業の比較をスムーズに行えます。
・事業内容
・代表者名
・経営理念
・企業の歴史
・本社や営業所の所在地
・社内制度
・年間休暇
・福利厚生
・同業他社との違い
・企業のどこに魅力を感じるか
・志望する職種や仕事
・入社後、どのように企業に貢献できるか
企業研究は、採用サイトや企業のWebサイトをチェックするのが基本です。また、インターンシップへの参加やOB・OG訪問をすると、企業への理解がより深まるのでおすすめです。
6.インターンシップに参加した感想
インターンシップに参加した場合は、その感想や印象に残っている出来事なども就活ノートにまとめましょう。どのような職場や雰囲気であるかや、実際に働く社員の姿を見れる機会はほとんどないため、自分の足で稼いだ情報は、忘れないうちにノートに記載することをおすすめします。
インターンシップに参加することで、その企業が所属する業界への適性や向き不向き、どのような雰囲気の企業が肌に合いそうかイメージが湧くでしょう。インターンシップの参加経験は応募書類の作成時などにも役立つので、あとから振り返った際に参照できるようにまとめておいてください。
インターンシップに参加すべきか迷っている就活生には、「内定が欲しいなら、企業が開催するインターンに参加するべき」の記事がおすすめです。
7.OB・OG訪問の記録
OB・OG訪問へ行った際の記録も、就活ノートに残しておきましょう。企業研究のページに追記するなどしてまとめておくと、見返した際も効率良く振り返れるはずです。
どのような質問をして、それぞれに対してどのような回答を得られたか、話を聞いた感想などをまとめておいてください。
8.採用担当者や面接官の発言内容
各種説明会での採用担当者や面接官の発言内容も、就活ノートに集約しておきましょう。
・説明会の会場でしか話されない内容
・社員の方のリアルな声
・入社した感想
・入社する前後で印象が変化したか
採用サイトやパンフレットに記載されていない内容はメモを残しておかないと忘れてしまうため、少しでも気になったことはノートに記載しておくことをおすすめします。
会場で配布されるパンフレットにメモを残すと、どこに書いたか忘れてしまうかもしれません。情報は一ヶ所に集約させることをルールにしておくとよいでしょう。
9.選考過程や結果の振り返り
選考が本格的にスタートして面接を受けるようになったら、毎回の結果や反省点などもノートに残しておいてください。具体的には、以下のようなポイントを記録しておくと次につなげやすいのでおすすめです。
・面接の状況(人数や時間など)
・面接で出た質問
・面接で答えた内容
・企業に対する印象
・面接での反省点
就活の選考では、毎回の面接を振り返ることも重要です。失敗から学んだことは次回の選考に活かせるとともに、同じ失敗を防ぐこともできます。
かんたん1分!無料登録就活ノートについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活ノートを作成する5つのメリット
就活ノートに情報をまとめておくと、就職活動をスムーズに進めやすくなります。ノートを書くメリットを5つ紹介するので、ぜひ参考にしてください。
1.スケジュール管理がしやすくなる
就活ノートを作ることにより、スケジュール管理が楽になります。スケジュールをメモできるページを用意しておくとよいでしょう。
就活ノートにスケジュールをメモできる場所を残しておくと、急に選考日程の連絡が来た際も、すぐに予定を伝えられます。手帳を忘れてしまった、スマートフォンのカレンダーを確認できないなどの状況でも安心です。
面接日だけではなく、エントリーシートや履歴書の提出期限を書いておくのもおすすめです。手帳には面接や説明会のスケジュール、就活ノートにはエントリーシートなどの提出期限、のように使い分けることもできます。
就職活動が本格的にスタートする大学3年生の3月以降は、やるべきことが多く忙しくなります。就活ノートにスケジュール管理をメモしておくと、冷静に行動できるでしょう。
2.これまでの就活の振り返りができる
就活ノートに振り返りメモを残して、いつでも読み返せるようにしておくのもおすすめです。説明会や面接の感想、手応え、面接官の反応といった印象的な出来事をメモしておくとよいでしょう。
その時々の状況を書き残しておくことで、就活が思うように進まないときに原因を考えるヒントになります。面接の質問や回答内容などを、その日のうちに日記のようにまとめておくのがおすすめです。
3.企業理解がしやすくなる
就活ノートに業界や企業情報についてメモしておくと、企業理解も行いやすくなります。就活は数社から数十社の企業を受けるのが一般的であり、各企業の情報を記憶しておくのは難しいでしょう。
企業ごとにページを分けておけば、競合他社との比較がしやすく、志望動機も考えやすくなります。企業説明会に参加した際の社員や採用担当者の発言もまとめておけば、面接直前に見直す際などにも便利です。
就活ノートに企業ごとの特徴や強みなどをメモして、いつでも振り返れるようにしておきましょう。企業研究の進め方について知りたい就活生は、「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事もぜひ参考にしてください。
4.就職活動を効率良く進められる
重要な情報をノートにメモしておけば、就職活動を効率良く進められます。必要な情報は毎回メモするように習慣づけておきましょう。
たとえば、就活ノートに自己分析の内容をまとめておけば、履歴書やエントリーシート作成に役立ちます。面接対策に向けて、模擬面接での改善点を残しておくなどもよいでしょう。
情報がバラバラになっていると、何がどこに書いてあるのか、そもそもメモをしているのかなど、探すところから始めなければなりません。ノートに情報を集めておくことで、就職活動をスムーズに進められるでしょう。
5.読み直してモチベーションを保てる
就活ノートを読み直すことで、モチベーション向上にもつなげられます。自分の努力や頑張った証になるのでおすすめです。
就活ノートの中身が充実していることは、これまで本気で就職活動に向き合ってきた証拠です。良かったことも悪かったことも含めて、ノートにメモしておきましょう。
就職活動は思うようにいかないことも多く、挫けそうになる場面にも遭遇します。落ち込んだときは就活ノートを見返してこれまでの努力を振り返り、モチベーションの維持につなげてください。
かんたん1分!無料登録就活ノートについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活ノートを書く際のキャリアアドバイザーからのアドバイス
就活ノートを書く際のポイントを、「スケジュール」「企業のこと」「選考のこと」「自分のこと」に分けて紹介します。
スケジュール
エントリーのピークになる3〜4月ごろは、締め切り日が重なります。計画的に就活を進めるためにも、スケジュールを書き出しておきましょう。心配な人は、「本来の締め切りよりも3日前倒しで書くようにする」など、自分なりのルールを作ってみてください。
企業のこと
どれだけエントリーや選考を受けても、最終的に入社するのは1社だけです。面接では、競合との違いや企業理解を問う質問をされることが多いので、比較できるようにまとめておきましょう。その際、同じ項目でまとめると見やすくなりますよ。
選考のこと
選考に関しては、「エントリーシートや面接の設問」と「それぞれ回答した内容」を企業ごとにまとめるのがおすすめです。
エントリーシートや面接で伝えた内容を忘れたり、就活を進めていくうちに自己PRの内容が変わったりすることは珍しくありません。設問と回答内容を書き出しておくことで、面接時に「前回はこのようにお伝えしましたが」と一言添えたり、前回の面接と矛盾しないように伝え方を工夫したりできるでしょう。
自分のこと
就活を進めるうちに業務理解や仕事への考え方が変わることも多いでしょう。ノート作成に時間をかけ過ぎて、ノートを作っただけで満足しないよう注意してください。
「ノート作成に時間がかかってエントリーシートに時間が取れない…」となっては本末転倒です。ノートは作ることがゴールではなく、あくまでも就活を上手く進めるためのツール、ということを頭に入れておきましょう。
かんたん1分!無料登録就活ノートについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活ノートのおすすめの作り方
ここでは、就活ノートのおすすめの作り方を紹介します。作り方のルールを最初に決めておくとあとから見返しやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
選考スケジュールをノートの前方に書く
就活ノートの冒頭に、応募書類の提出日や面接の日程を書けるようにしましょう。現状の把握や予定を確認したいときに、冒頭にスケジュールがまとまっているとすぐに開けるためです。
就職活動が本格化すると、面接中に次の選考の日程調整が入ったり、採用担当者から急に電話が掛かってきたりすることもあります。このような場合も、ノートの前方にスケジュールがまとまっていればスムーズに対応できるでしょう。
スケジュールの次に企業情報を書く
就活スケジュールを冒頭にまとめたら、次のスペースに業界研究や企業研究の結果を記載するのがおすすめです。
スケジュールに記載された企業について、その情報をすぐに見つけられるよう、ページ間を近づけておいたほうがよいでしょう。業界と企業の情報も混合しやすいので、自分が区別できるよう工夫してまとめておくのがコツです。
特に、企業情報に関しては選考が進むほど情報量が増えるため、フリースペースを多めに確保しておくことをおすすめします。
自己分析はノートの後ろのほうに書く
自己分析の結果は、業界・企業研究の内容よりも後ろにまとめましょう。自己分析も定期的に行うのが一般的なため、ページには余裕を持たせておいてください。
製本されたノートを使う場合は、最後のページから遡るように自己分析の結果をまとめるのもおすすめです。そうすることで、企業研究の内容が増えた際の追記スペースがなくなる可能性を避けられるでしょう。
自己分析の方法が知りたい就活生は、「自己分析とは?おすすめのやり方と8つの注意点を解説」の記事を参考にしてみてください。
目次を見やすい位置に書く
必要な情報をすぐに見つけられるよう、目次の作成もおすすめです。目次を作る際は、ノートの最初の見開きや最後のページに書くのがよいでしょう。
目次がないと、どこにどの情報をまとめたか分かりづらくなってしまい、せっかく書いた内容を見返さなくなってしまう恐れもあります。目次を作成する代わりに、項目ごとに付箋をつけるのもおすすめです。
かんたん1分!無料登録就活ノートについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活ノートを作る6つのポイント
ここでは、就活ノートを作る際のポイントを6つ紹介します。どれもちょっとした意識で実践できるものなので、ぜひ参考にしてください。
1.1冊にまとめる
就活ノートを作る際は、すべての情報を1冊にまとめることをおすすめします。複数冊のノートを作成すると、持ち運びが大変なのはもちろん、情報を探す際に時間がかかるためです。
自己分析や企業研究など、目的や用途で分けるのも管理が面倒になりがちです。いつでもすべての情報を見返せる手軽さを優先させて、1冊にまとめましょう。
2.情報は簡潔にまとめる
就活ノートに内容をまとめる際は、極力シンプルに記載するのが理想です。情報を詰め込み過ぎると見にくくなり、見返す際に苦労してしまいます。
重要なポイントを箇条書きにしたり、できる限り余計な情報は削減してコンパクトに記載したりするのが賢明です。
3.自分の意見や考えも書く
就活ノートには自分の意見や考えもまとめておきましょう。実際にどのように感じたかは振り返るのが難しく、貴重な意見になるからです。
特に、説明会や面接に参加した際の感想などは、そのときにしかない感情なども含めて当時を振り返る貴重な資料となり得ます。当時の心境をリアルに残しておくことで、自己分析の手がかりにもなるでしょう。
就職活動ではさまざまな企業や人に触れるため、考え方や価値観の変化が起こりやすいもの。そのとき感じたことを記録しておくことで、就活の軸を見直す際にも参考にできるでしょう。
面接官の印象に残る就活の軸について知りたい就活生は、「面接官に伝わりやすい『就活の軸』の作り方とは?」の記事を読んでみてください。
4.情報の種類ごとに記載する場所をまとめる
見やすい就活ノートを作成するには、情報のグルーピングが欠かせません。思いついた内容を順番に書くのではなく、見返すことを意識してノートをまとめるのが大切です。
説明会や面接のスケジュール、企業や選考、自分についてなど、それぞれの記載箇所をまとめることで見返しやすいノートになり、頭のなかを整理しやすくなるでしょう。
5.情報ごとにペンやマーカーで色分けする
就活ノートの見やすさをアップさせるためのルール作りも事前に行いましょう。たとえば、以下の基準で色分けするのがおすすめです。
・青色:志望企業のよい点
・赤色:志望企業のネックな点
・面接日程:赤色
・書類の提出:緑色
色数を増やし過ぎると逆に見にくいので、3色程度を限度に色分けしましょう。
6.情報を追加できるように余白を作る
就職活動を続けるうちに書きたい情報は増えるため、余白やフリースペースは多めに確保しておいてください。
ある企業について複数箇所に情報を記載してしまうと、どこに何を書いたか探しにくくなってしまいます。「ノートの表裏でまとめる」「見開き2ページでまとめる」などを意識すると、より使い勝手のよいノートを作れるでしょう。
なお、就活生が就職活動を効率良く進めるには、常に最新の就活情報にアンテナを貼っておくことも大事です。「トレンドの就活情報を効率的に集めたい方必見!就活に役立つおすすめサイトまとめ」の記事で便利なWebサイトを紹介しているので、あわせて参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就活ノートについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活ノートの使い方
ここでは、就活ノートの使い方として一般的なシーンを紹介します。「就活ノートを実際にどのように活用すればよいかイメージが湧かない」という人は、ぜひ参考にしてください。
面接前に企業情報を見返す
就活ノートは、面接前に企業情報を見返すために使ってみましょう。企業情報はいつも覚えているものではないので、面接前に再確認しておくのがおすすめです。
企業のWebサイトを見直しても、「どこに情報があるかわからない」「競合他社との違いがわからない」などの問題が発生します。面接前は時間に余裕がないことも多く、情報を探しきるのは大変でしょう。
就活ノートに情報を残しておけば、面接に必要な情報だけを即座に把握できます。自分なりのメモも残しておくと、より面接に必要な情報を確認できるでしょう。
自分の考えにブレがないか見直す
就活ノートを見直せば、自分の考えが変わっていないかも見直せます。記入してから何度も見直すようにしましょう。
たとえば、就活を始めて間もないころに行った自己分析と、企業研究や選考などを何度も経験した状態で行った自己分析では、考え方に変化が生まれるケースもあります。就活ノートに自己分析の内容をメモしておけば、違いに気づけたり、企業選びの軸がブレていないことを再認識できたりするでしょう。
特に、就活に行き詰まりを感じた際は、過去の自分は働くことをどのように捉えているのか、何を強みだと思っているのかなどの振り返りが欠かせません。可視化できた自分の軸を定期的に見直すことで、志望動機や自己PRをより具体化できます。
かんたん1分!無料登録就活ノートについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活ノートの大きさは?サイズ選びのポイントも解説
就活ノートのサイズは、基本的に持ち運びしやすい大きさを選ぶのがおすすめです。なかでも、A6サイズは文庫本ほどのコンパクトサイズなので、スーツの内ポケットにも収まるでしょう。
コンパクト過ぎて書けるスペースが足りないと感じる人は、A5サイズもおすすめです。就活用のカバンに入れても持ち運びやすく、不自由さもほとんどないでしょう。
また、就活中は立ったままメモをとる場合もあるため、書きやすさも重視してみてください。使い勝手の良さは人によって異なるので、複数サイズのノートを手に取り、利用シーンを具体的に想定しながら扱いやすいサイズを探しましょう。
就活ノートの作り方だけでなく、就活全体の進め方を知りたい人は「就活は何から始める?時期別の対策・効率アップのコツを解説」の記事を参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就活ノートについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活ノートにおすすめしたい4つのタイプ
ここでは、就活ノートにおすすめしたいノートの種類を4つ紹介します。それぞれの特徴を踏まえて、ストレスなく使えるノートを見つけましょう。
1.ポケットサイズの手帳
スケジュール管理をメインに就活ノートを利用したい場合は、ポケットサイズの手帳がおすすめです。
なかでも、月・週単位単位でスケジュールが書き込めて、フリースペースが多いタイプの手帳を選ぶと、就活ノートとして使いやすいでしょう。カバーにペンホルダーがついている手帳なら、さらに使い勝手が良くなるのでおすすめです。
就活生向けの手帳はいろいろな種類が販売されているため、実物を見ながらチェックすると良いでしょう。手帳の選び方を詳しく知りたい就活生は、「就活におすすめ!手帳の選び方とポイント」の記事もご一読ください。
2.ルーズリーフ
就活ノートのカスタマイズ性の高さを重視するなら、ルーズリーフの利用がおすすめです。製本されたノートではページ数が足りない可能性もあり、複数冊のノートを作成することになりかねません。
ルーズリーフなら項目ごとでページの追加や入れ替えも簡単で、ボリュームが増えても対応できます。
3.スマホやタブレット端末
クラウドサービスを使って各種デバイスで就活ノートを見られるようにしたい場合は、スマホやタブレット端末の利用もおすすめです。ページを追加しても物理的にかさばることがなく、複数端末からアクセスできる利便性の高さが魅力といえます。
ただし、スマホやタブレット端末をメインで利用すると企業からの目線が気になる点は否めないため、サブ的に使うことをおすすめします。
4.市販の就活ノート
市販されている就活ノートも各商品で工夫を凝らしているため、利用シーンを想定して使い勝手がよければ利用してみましょう。市販の就活ノートは、項目ごとに書くべき内容が明示されていることが多いのも特徴です。
かんたん1分!無料登録就活ノートについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活ノート作成に役立つ4つのアイテム
ここでは、就活ノートの作成に便利なアイテムを4つ紹介します。それぞれを参考にしながら、見返しやすい就活ノートを作成しましょう。
1.付箋
付箋は、就活ノートのスペース不足を補ったり重要な箇所を目立たせたりする際に役立ちます。
・目次と該当箇所のページを対応させて視認性を高める
・志望度の高い企業の情報が目立つように貼る
・変更するかもしれない情報を記入して入れ替えできるようにする
付箋の色自体で情報を分けることもできるため、ルールを決めて使ってみてください。
2.消せるボールペン
就活ノートに情報を整理する際は、消せるボールペンを使ったほうがよいでしょう。
消せるボールペンなら修正テープや修正ペンよりもきれいに修正でき、消すための筆記具も必要ありません。使い勝手の良さを踏まえると、消せるボールペンを利用するメリットは大きいでしょう。
3.蛍光ペン
付箋とセットで使いたいのが蛍光ペンです。特定の箇所を目立たせるのはもちろん、企業研究の結果で特に印象に残った箇所にマーカーを引いておけば、企業同士を比較する際にも役立ちます。
ただし、付箋の利用と同様、使い過ぎるとかえって見づらくなるため、色数は抑えて重要な箇所だけに使うようにしましょう。
4.スマホアプリ
就活ノートにスマホアプリを併用させると、使い勝手をさらに向上させられます。リマインド機能やToDoリストなどを活用することで、より効率的に情報を整理できるでしょう。
ただし、企業の説明会や選考の場でスマホを頻繁にチェックしていると、採用面接官にマイナスな印象を与えてしまいます。スマホを確認するのは、選考会場に付く前に済ませておくのがよいでしょう。
内定獲得までにはさまざまな準備が欠かせませんが、その過程をゲーム感覚で捉えると、肩の力が抜けるかもしれません。「就活はゲーム感覚で楽しもう!内定までの5つのステージと攻略のコツを解説」の記事を参考に、就活を違った捉え方で進めるのもよいでしょう。
かんたん1分!無料登録就活ノートについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活ノートの作り方に悩むあなたへ
就活ノートの作り方に決まりはないため、「何をどのように書けばよいか分からない」「どのような形式で作ればよいか分からない」と悩む就活生は多いようです。就活ノートの作り方に困ったら、キャリアチケットにご相談ください。
就職エージェントのキャリアチケットは、就活ノートの作り方はもちろん、自己分析やESの添削、面接対策などのあらゆる悩みに対するアドバイスをしています。
就活ノートを作成できれば、就活に必要な情報を整理でき、客観的な振り返りが可能です。キャリアチケットで就活ノートの作成をスムーズに進めて、就職活動を成功させましょう。
かんたん1分!無料登録就活ノートについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら