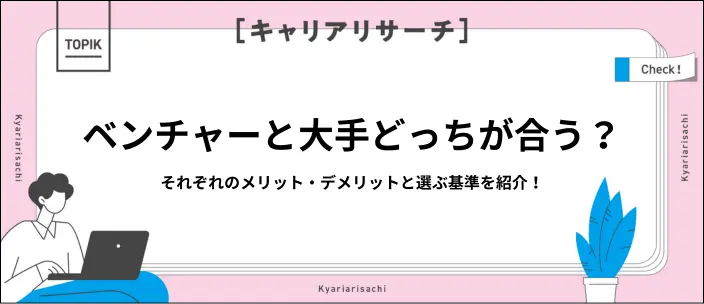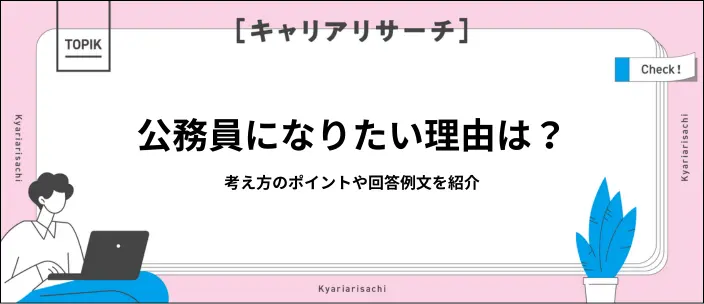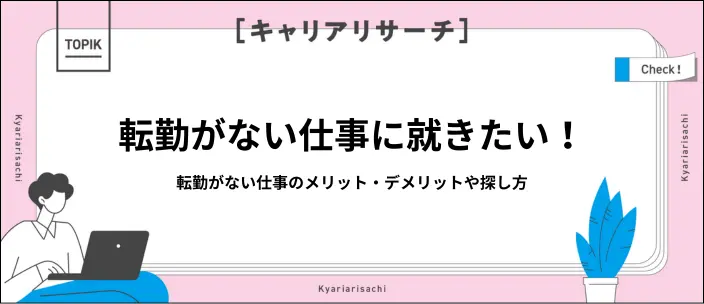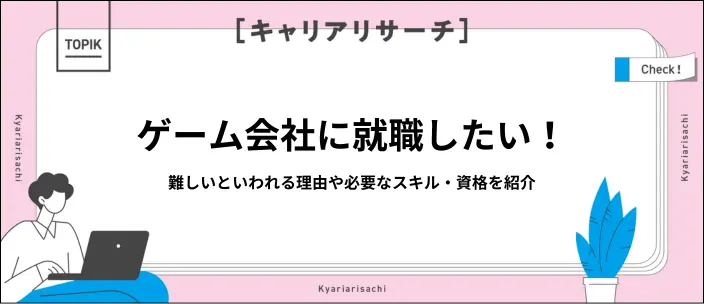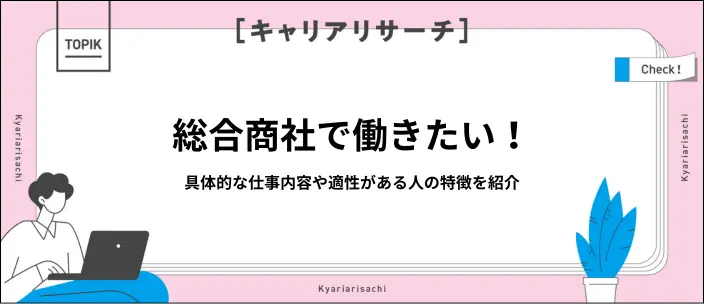このページのまとめ
- 銀行への就職を考えるときは、まず業界の実態や将来性を知ることが重要
- 銀行に就職するメリットは、社会的信用が高まる点や金融知識が身につく点
- 銀行に就職するデメリットは、業務の拘束時間が長い点や常に勉強し続ける必要がある点

「銀行業界に就職したい」「銀行に就職するには何が必要?」などと気になる就活生も多いでしょう。銀行への就職を目指すなら、まずは業界や仕事の特徴を理解し、自分に合うかを考えることが大切です。
この記事では、銀行業界の特徴や仕事内容、就職するメリットデメリットを解説します。最後まで読めば銀行業界への理解が深まり、自分に合う業界かどうかを明確にできるはずです。
かんたん1分!無料登録企業の選び方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 銀行へ就職するときは業界の実態を知ることが重要
- 銀行に就職する難易度は高い
- IT技術の進歩が銀行の将来性に影響を与えている
- 就職に向けて知っておきたい銀行の種類
- 1.都市銀行
- 2.地方銀行
- 3.信託銀行
- 4.ネット銀行
- 銀行員の主な3つの仕事内容
- 1.預金業務
- 2.貸出業務
- 3.為替業務
- 銀行員の平均年収
- 銀行に就職するメリット
- 金融分野のスキルや知識が高まる
- 安定した業界で働ける
- 社会的な信用を得やすい
- 福利厚生が整っている
- ワークライフバランスを整えやすい
- 銀行に就職する3つのデメリット
- 1.ノルマが発生する場合がある
- 2.拘束時間が長い
- 3.常に勉強する必要がある
- 銀行への就職に向いている人の特徴
- 経済に関心がある
- 責任感が強い
- ストレス耐性がある
- 銀行への就職に向いていない人の特徴
- 注意や指摘を素直に受け取れない
- プライベートの時間も大切にしたい
- 銀行で働く際に求められる5つのスキル
- 1.コミュニケーション能力
- 2.提案力
- 3.柔軟性
- 4.金融知識
- 5.英語力
- 銀行へ就職するのに有利な資格4選
- 1.日商簿記検定
- 2.社会保険労務士
- 3.ファイナンシャルプランナー
- 4.TOEICやTOEFL
- 銀行への就職を目指しているあなたへ
銀行へ就職するときは業界の実態を知ることが重要
銀行への就職を考えるときは、業界の現状や今後の動向を知ることが重要です。何も知らずに就職を決めてしまうと、入社後にミスマッチを起こす可能性があります。
ここでは、銀行に就職する難易度や将来性を解説するので、業界の実態を把握するのに役立ててください。
銀行に就職する難易度は高い
一般的に、銀行への就職は難易度が高めだといわれています。近年は、銀行でもIT技術の導入が進んでおり、新卒の採用人数が減らされたり採用基準が高まったりしている印象です。
そのため、最初は銀行への就職を目指していても、結果として銀行へ就職を諦める就活生も少なくありません。一方で、より専門的な知識を要する分野に挑戦したい就活生ほど、銀行への就職を強く希望している傾向です。
採用人数の減少
銀行に就職する難易度が高まる背景として、採用人数の減少が挙げられます。最近では、メガバンクを中心に、店舗人員の採用数が大幅に減っているようです。銀行が採用数を削減する主な要因は、金融サービスとIT技術を組み合わせた「FinTech」やAIといった新たな技術の導入が挙げられます。
実際に、IT技術の導入によってパソコンやスマートフォンからの決済が可能になり、店舗における銀行員の出番は減りました。こうした状況に伴って、店舗人員の新規採用数が減少していると考えられます。
採用基準の高まり
近年は、銀行員の採用基準も上昇しているようです。店舗人員を担う一般職が減り、銀行員の仕事の多くは、法人向けの融資営業や個人向けの金融商品販売などに移行しています。
融資営業や金融商品の販売などは、より専門的な金融知識が求められるため、一般職に必要な知識だけでは仕事を担うのは難しいでしょう。そのため、以前と比べて専門性の高い人材が求められるようになり、採用基準が底上げされたと考えられます。
IT技術の進歩が銀行の将来性に影響を与えている
AIの発達により人がしている仕事の多くが今後はなくなっていくと予想されているなか、銀行員の仕事も例外ではありません。店舗人員が長年担当してきた業務のうち、単純な仕事ほど、AIに取って代わられるでしょう。
たとえば、窓口業務や書類チェックといった事務作業は、機械のほうが正確性も高く、人による作業は不要になると考えられます。また、単純作業に限らず、資産運用や資金調達などの仕事でも、情報分析能力が高いAIやFinTechなどに移行していく可能性があるでしょう。このように、IT技術の進歩は銀行の将来性に大きな影響を与えています。
金融業界に関する知識を深めたい就活生は、「10分で分かる金融業界(銀行編):3大メガバンクの特徴を徹底解説」も参考にしてください。
銀行に就職するのは社会科学系学部の出身者が多め
銀行に就職しやすいといわれる学部は、主に法学部や経済学部、商学部などの社会科学系学部です。実際に、銀行員の採用試験では、以下の知識が必要とされます。
・金融
・経済
・財務
・税務
・不動産
そのため、こうした分野に強い法学部や経済学部出身の人が多く採用される傾向にあるようです。なお、最近では、FinTechの導入や銀行のデジタル化などによって、理数系の人材や柔軟な発想力を持つ人材も求められています。
金融や経済といった知識を活かせる就職先については、「経営学部におすすめの就職先は?就活時のポイントや評価される資格も解説」も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録企業の選び方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就職に向けて知っておきたい銀行の種類
銀行にも種類があるので覚えておきましょう。就職に向けて知っておきたい4つの銀行を解説します。
1.都市銀行
都市銀行とは、日本全国で店舗を展開している規模が大きい銀行を指します。法律上は、「都市銀行」という定義が存在しないため、実質は普通銀行と同じ扱いです。
また、都市銀行の中でも特に巨大な資産や規模を誇る銀行やグループは「メガバンク」とも呼ばれます。都市銀行と似たような意味合いで使われることが多いため、あわせて覚えておくとよいでしょう。
2.地方銀行
地方銀行とは、各地方や都道府県内を営業の基盤としている銀行です。分かりやすい特徴として、「全国地方銀行協会」の会員であることが挙げられます。都市銀行と同様に、法律上の定義では普通銀行と同様の扱いです。
地方銀行の主な取引対象は、地元の中小企業や個人で、小口取引を主体としています。各都道府県に地域を代表とする地方銀行が存在するため、都市銀行と並んで身近な銀行という方もいるでしょう。
3.信託銀行
信託銀行は、通常の銀行業務に加えて「信託業務」と「併営業務」を行っています。
信託業務とは、主に金銭や有価証券など、個人や法人から信託を引き受け、目的にあわせて運用・管理することです。また、併営業務では、不動産の仲介や相続に関する業務において、財産の管理や処分を行います。
信託銀行の業務領域は幅広く、顧客のさまざまなニーズに対応できるのが特徴です。信託銀行と普通銀行の違いについては、「信託銀行とは?業務内容や普通銀行との違いを解説」も参考にしてください。
4.ネット銀行
ネット銀行とは、店舗を持たずにインターネット上でサービスを提供する銀行のことです。パソコンやスマートフォンを使うことで、入金や出金などのサービスを利用できます。
ネット銀行は店舗に行かなくても利用できるため、若者を中心に利用者が広がっている傾向。24時間利用できるサービスが多い点も特徴でしょう。
仕事内容はシステム開発や保全を中心とした業務になります。ほかの銀行とは違い、直接的な接客を行わない点もネット銀行ならではの特徴です。
かんたん1分!無料登録企業の選び方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
銀行員の主な3つの仕事内容
ここでは、銀行員の主な3つの業務について、具体的な仕事内容を解説します。
1.預金業務
預金業務とは、個人や法人の顧客から資金を預かる業務です。預金口座には、普通預金や定期預金、小切手や手形の支払いに利用される当座預金など、いくつかの種類があります。
預けられた資金は保護され、仮に銀行が破綻しても預金の引き出しが可能です。顧客は目的に合わせて預金口座を開設し、お金を預け入れることで資金を安全に保管できます。
2.貸出業務
貸出業務とは、資金を必要としている企業や個人にお金を融資する業務です。たとえば、企業が事業を拡大するために必要な設備投資の資金だけでなく、個人が家を建てたり車を購入したりするときにも必要な資金も貸し付けます。
銀行は、基本的に貸し付けたお金の利率から利益を得ており、融資先が倒産したり自己破産したりしてお金の回収ができないと大きな損害につながりかねません。そのため、銀行では、融資先の業績や将来性を細かく審査したうえで、融資するかどうかを決定しています。
3.為替業務
為替業務とは、債券や債務を決済するために、振込みや送金を行う業務です。人々の生活になじみがあるものでは、電気やガス、水道といった公共料金の口座振替が挙げられます。
為替業務の特徴は、現金を直接やり取りする必要がないことです。なお、為替業務は国際的な決済取引にも不可欠で、外国為替部門では外貨への交換や外国への送金などを行います。
銀行の仕事内容について詳しく知りたい方は、「銀行業務とは?主な仕事内容や銀行員に求められる5つのスキルを解説」も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録企業の選び方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
銀行員の平均年収
厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、銀行業界が属する金融・保険業の平均年収は約393万円でした。男性は約497万円、女性は約306万円です。
年収は年齢ごとにアップしていき、45歳から49歳になると約470万円でピークを迎えます。50歳以降は、平均年収が下がっていく状況です。
ただし、金額はあくまでも平均額なので気をつけましょう。企業や個人の成果などによって、給料が変わることは意識しておいてください。なお、「20代の平均年収はいくら?年齢や業界ごとの詳細を紹介」の記事も参考にしてください。
参照元
厚生労働省
令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況
かんたん1分!無料登録企業の選び方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
銀行に就職するメリット
ここでは、銀行に就職する主なメリットを解説します。
金融分野のスキルや知識が高まる
銀行に就職することで、金融分野のスキルや知識を高めることができます。どの仕事もお金に関する仕事のため、働きながら金融に関するさまざまな知識を習得できるでしょう。
たとえば、融資を行う際は決算書を読み解いたり、企業の財務状況を分析したりできるスキルが身につきます。実務を通して金融に関する知識を高められる点は、銀行ならではのメリットでしょう。
安定した業界で働ける
銀行は人々の生活に欠かせないサービスであり、安定している点も特徴です。経済活動に欠かせないものであり、業界がなくなったり、衰退したりする可能性は低いでしょう。
また、銀行業界は経済状況が悪くなった場合でも、それほど打撃を受けない業界でもあります。国や中央銀行などのサポートを受けながら、事業を続けられる点も特徴です。
社会的な信用を得やすい
銀行で働いていると、社会的な信用を得やすいメリットがあります。お金を扱う仕事は誠実さや責任感が必要であり、信頼できる仕事で働いていると評価されるでしょう。
社会的な信用は周囲の評価が高まるだけではなく、車や家のローンを受けやすいメリットもあります。もし、転職を行うとなった場合でも、評価されやすい仕事だといえるでしょう。
福利厚生が整っている
銀行業界は安定している企業が多く、福利厚生を期待できる点もメリットです。福利厚生が充実していると生活が安定し、仕事へのモチベーションにもつながります。
たとえば、大手銀行であれば家賃補助があったり、社員寮が準備されていたりします。また、育児休暇や介護休暇などを手厚くする企業もあるでしょう。
福利厚生が整っているホワイト企業の特徴については、「ホワイト企業とはどんな企業?特徴や探し方を解説」の記事で解説しているので参考にしてください。
ワークライフバランスを整えやすい
銀行は休日が多い傾向にあり、ワークライフバランスを整えやすいメリットがあります。土日祝日は基本的に休みであり、仕事とプライベートのメリハリをつけられるでしょう。
企業によっては夏季休暇や長期休暇を取得しやすい場合もあります。銀行の店舗勤務であれば休みを取得しやすく、プライベートの充実につなげられます。
育児中も働きやすい環境が整っている
銀行は、育児中でも働きやすい環境が整っている場合が多いようです。働きやすい環境の一例としては、短時間勤務や育児休暇、テレワークなどが挙げられます。
実際に、産後に職場復帰して、再び銀行員として活躍を続けている女性も少なくありません。子育てのサポート体制が整っていることは、育児と両立して働きたい方にとって、大きなメリットだといえるでしょう。
かんたん1分!無料登録企業の選び方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
銀行に就職する3つのデメリット
銀行への就職は少なからずデメリットもあります。よい部分だけでなく悪い部分にも目を向けておくことで、入社後のネガティブなギャップを減らせるはずです。
1.ノルマが発生する場合がある
銀行の仕事はノルマが発生する場合もあるので気をつけましょう。たとえば、支店勤務では貸付目標や預金獲得目標、口座獲得目標などが存在することも。
ノルマを達成するためには、企業や個人宅を訪問して口座や預金を獲得するなど、目標達成に向けて行動数を増やさなければなりません。ノルマのある仕事が苦手な場合はデメリットとなるでしょう。
一方で、ノルマを達成したり、実績を上げたりすれば表彰や昇進につながることもあります。ノルマ達成がモチベーションにつながる場合は向いているでしょう。
2.拘束時間が長い
銀行の仕事は、拘束時間が長くなる傾向にあります。営業時間を終えたあとでも、報告書や稟議書などの作成業務があるためです。
特に、決算時期となるタイミングは仕事が増え、残業を行う場合もあるでしょう。休日はしっかりととれますが、拘束時間が長くなりやすい点には気をつけてください。
3.常に勉強する必要がある
銀行員は覚える知識が多く、常に勉強を続けなければなりません。銀行で扱う金融商品や社会経済の動向など、学び続けるのを大変に感じる人もいるでしょう。
銀行によっては、課題やテストを実施したり、研修を行ったりする場合があります。新しいことを学ぶのが苦手な場合は、仕事を大変に感じるかもしれません。
自分に合った仕事を見つけるためには、どのような業界なのかを詳しく調べておくことが大切です。業界研究の方法を「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事で解説しているので、参考にしてください。
かんたん1分!無料登録企業の選び方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
銀行への就職に向いている人の特徴
銀行への就職には、向いている人と向いていない人がいるのは事実です。ここでは、銀行就職に向いている人の特徴を解説するので、入行後に後悔しないためにも、自分の適性を事前に確かめてみてください。
経済に関心がある
経済に関心を持つ人は、日々の社会変化に対応しやすく、銀行業務が向いているでしょう。銀行の仕事は経済の動きと大きく関わりがあり、日々のアップデートが欠かせないためです。
社会経済に普段から関心を持っている人であれば、自然と情報を確認し、自分の知識へと変えていけるでしょう。新しいことを覚える際にも苦にならないため、知識が求められる銀行業界も向いているといえます。
責任感が強い
資金や顧客の資産を預かる銀行員は、責任感が必要です。資金の横領や個人情報の流出などの不正はもちろん、仕事でのミスを起こさない責任感が求められます。
たとえば、「報告書の数字が間違っていた」「資産管理を誤ってしまった」のようなミス1つで、銀行全体の信頼が失われてしまいます。自分の仕事が銀行全体のイメージにつながることを理解し、真面目に仕事ができる責任感がある人は向いているでしょう。
ストレス耐性がある
銀行業務はストレスのかかる仕事も多く、ストレス耐性のある人が向いています。ノルマへの対応や人間関係などのストレスに対し、うまく対処していくことが必要でしょう。
ストレスが溜まると仕事でのミスが増えたり、体調不良を引き起こしたりと仕事を続ける際の支障がでてきます。ストレスに強いのはもちろん、うまくストレス発散をして自分でストレス管理できる人は銀行に向いているでしょう。
自分にどのような特徴があるかは、自己分析をして自己理解を深めるのがおすすめです。自己分析の方法は「自己分析とは?おすすめのやり方8選や実施時の注意点を紹介」の記事で解説しているので参考にしてください。
かんたん1分!無料登録企業の選び方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
銀行への就職に向いていない人の特徴
銀行に向いていない特徴を持つ場合、仕事でのストレスがかかる可能性があるので気をつけましょう。ここでは、どのような人が向いていないかを解説します。
注意や指摘を素直に受け取れない
銀行業務はミスが許されない業務が多く、素直に反省して改善する姿勢が求められるため、注意や指摘を素直に受け取れないと業務を辛く感じてしまう可能性があります。。
入社してすぐは初めての業務に慣れず、ミスをしてしまうこともあるでしょう。その際に指摘を素直に受け止め、改善できればミスは減っていきます。
一方で、指摘を嫌がったり、改善できなかったりする場合は、ミスが増えて大きなトラブルを引き起こすかもしれません。自分の失敗を認め、改善につなげられるかどうかは銀行業務で重要です。
プライベートの時間も大切にしたい
プライベートの時間を自由にとりたい場合は、銀行への就職を再検討してもいいでしょう。ワークライフバランスは保ちやすいものの、残業する時期があったり、仕事の勉強をしたりする時間があるからです。
決算時期は忙しくなりやすく、店舗の営業が終了したあとも残業する銀行は多いでしょう。また、銀行業務に必要な情報は、業務以外の時間を使って自主的に勉強しておく必要があります。「毎日残業なしで帰りたい」のように考えている場合は、銀行業務を大変と感じるかも知れません。
自分に合う就職先を探すには、業界の動向や仕事内容をしっかりと調べておく必要があります。自分に合った就職先を選ぶコツは「就活における職種の一覧とは?自分に合う仕事の見つけ方も紹介」の記事を参考にしてください。
かんたん1分!無料登録企業の選び方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
銀行で働く際に求められる5つのスキル
銀行員として働くには、以下の5つのスキルが求められます。
1.コミュニケーション能力
銀行業務で欠かせないのが、コミュニケーション能力です。顧客との信頼関係を築くほか、同僚や上司と協力して業務を進めるためにも、円滑なコミュニケーションが大いに役立ちます。
銀行業務は顧客とのコミュニケーションが中心です。そのため、コミュニケーション能力の有無は、採用活動において見極められている点でもあります。顧客の話をよく聞いて、ニーズや要望を適切に理解することで、安心感を与えられるでしょう。
2.提案力
銀行員には、ニーズに合わせて最適な提案をする能力も求められます。顧客の状況や抱えている課題に対して、よりよい銀行商品やサービスを提案するのが銀行員の役割です。
また、提案力を活かして顧客の資産を最適に運用できれば、銀行の収益増加にもつながるでしょう。
提案力を高めるためには、顧客のニーズを的確に把握するほか、仮説を立てて提案を組み立てる必要があります。そのため、銀行員には聴く能力だけでなく、分かりやすく整理して伝える能力が不可欠です。
3.柔軟性
銀行員に求められるスキルの一つとして、柔軟性が挙げられます。銀行業界は世の中の動きにあわせて、変化が多い業界です。
具体的には、新たな法規制やITの進歩、市場のトレンド変化など、常に新たな課題が待ち受けているともいえるでしょう。そのため、柔軟性を持って変化に対応できる人材ほど成功しやすく、組織の一員としての貢献度も高まります。
4.金融知識
銀行で働くには、資産形成や保険など、金融知識が不可欠です。顧客に適切なアドバイスをしたりリスク管理したりする際には、金融知識がなければ対応しきれません。
こうした金融知識は、実際の銀行業務を通して身につけられるため、新卒の就活時に金融知識が求められるケースはあまりないでしょう。また、金融知識を増やしていくためには、就職後も継続して学習を続ける必要があります。
5.英語力
銀行の仕事内容によっては、英語力も求められる傾向です。グローバル化が進んでいる現在は、海外進出を図る企業も珍しくなく、銀行における国際金融業務も増えています。
英語力を身につけておけば、就活において有利になるだけでなく、海外事業を担当できるチャンスが得られるなど、キャリアアップにもつながるはずです。
大学生のうちにさまざまな経験をしてスキルを身につけたい方は、「大学生のうちにやるべきこと30選!将来や就活にもつながる内容を解説」も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録企業の選び方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
銀行へ就職するのに有利な資格4選
銀行に就職する際に、必須の資格はありません。しかし、大学生のうちに関連する資格を取得しておけば、就活を有利に進められるでしょう。
ここでは、銀行業務に役立つ資格を解説します。資格がなくても銀行に就職することも可能なので、無理に取得する必要はないと頭に入れておいてください。
1.日商簿記検定
日商簿記検定の資格は、銀行に就職する際に役立つとされています。なぜなら、取引先の財務諸表を深く読み込むうえで、簿記の知識は必須といえるからです。
日商簿記検定の資格を保有していれば、企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績や財政状態を明らかにするスキルがあることを証明できます。
日商簿記検定は、最低でも3級、できれば2級を取得しておくとよいでしょう。また、大手企業や上場企業で活躍するには1級レベルの知識が求められることもあるため、入行前に勉強を進めておくのがおすすめです。
2.社会保険労務士
労働や社会保険に関する法令に関する知識をもとに、顧客企業の見極めをより幅広い視点で行える点で、社会保険労務士の資格が銀行業務に役立つでしょう。
また、社会保険労務士は、人事や総務といった職種でも重宝される資格です。そのため、学生のうちに取得しておいて損はありません。
3.ファイナンシャルプランナー
銀行に就職するために活かせる資格として、ファイナンシャルプランナーも挙げられます。銀行業務における投資信託や保険の販売などに活かせるのが、ファイナンシャルプランナーの資格です。
入行後、ファイナンシャルプランナー2級の取得が、昇進や昇格の要件になっているケースも珍しくありません。そのため、銀行員としてより幅広い業務に携わりたい場合には必須の資格です。
なお、2級を受験するには、「2年以上の実務経験」や「3級技能検定に合格」といった条件があるため、早い段階で3級を取得しておくとよいでしょう。
4.TOEICやTOEFL
銀行への就職を目指すうえでは、英語力を証明するために、TOEICやTOEFLといったテストを受験しておくのもおすすめです。
TOEICとは「国際コミュニケーション英語能力テスト」の略で、ビジネスシーンを想定した英語によるコミュニケーション能力を評価します。また、TOEFLは、主に英語圏の大学で学びたい人や研究したい人を対象とした、英語能力を評価するテストです。
就活で英語力の高さをアピールするためにも、こうしたテストで高得点を取っておくとよいでしょう。
就活でアピールできるおすすめの資格については、「大学生のうちに取るべきおすすめの資格14選!文系・理系・業種別に紹介」で詳しく解説しています。
かんたん1分!無料登録企業の選び方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
銀行への就職を目指しているあなたへ
銀行への就職を目指していても、「将来性はどうか」「やめとけと言われるほど仕事が大変なのか」と不安な気持ちを抱えている就活生も多いのではないでしょうか。
銀行への就職は社会的な信頼を得られるほか、長く続けやすいメリットもありますが、ノルマが多く銀行員として評価を得るのは決して簡単なことではありません。
銀行に就職したいけれど不安という方は、エージェントへの相談もおすすめです。就職エージェントであるキャリアチケットでは、就活のプロがマンツーマンで向き合い、業界研究や志望動機の作成などを細かくサポートします。すべてのサービスを無料で活用できるため、ぜひお気軽にご相談ください。
かんたん1分!無料登録企業の選び方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。