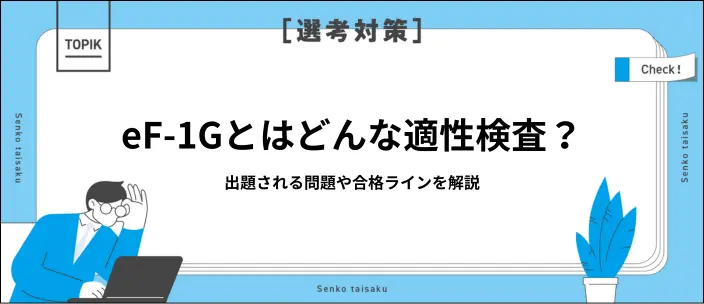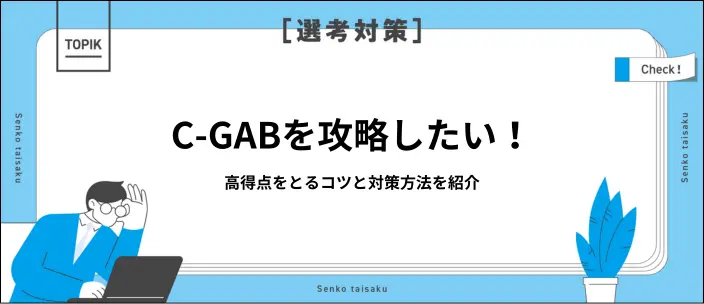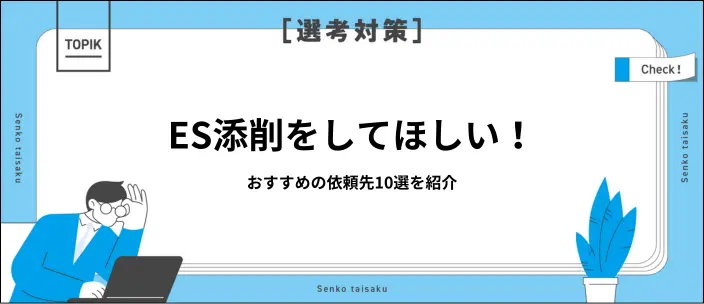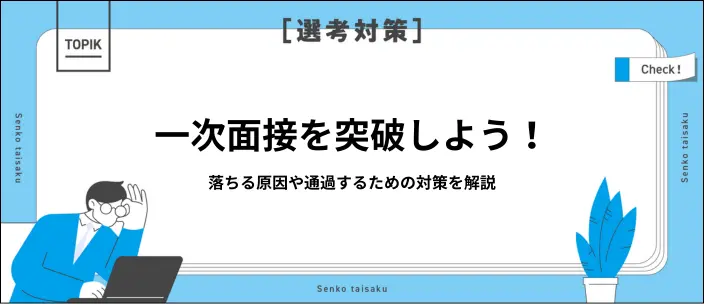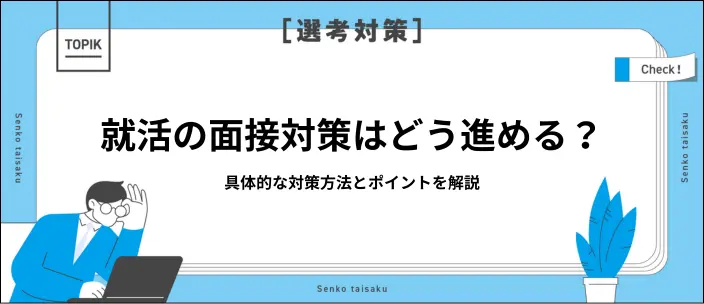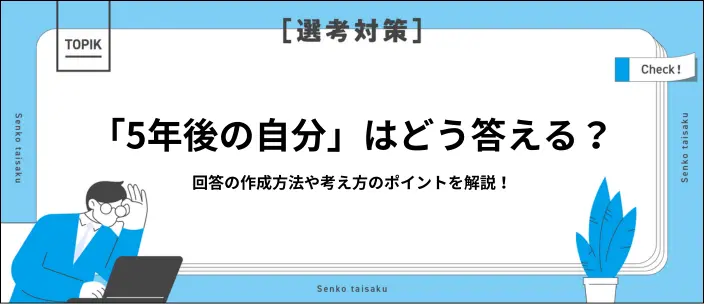このページのまとめ
- 玉手箱とは就活の適性検査の一つで、能力テストと性格適性検査で構成されている
- 玉手箱は時間制限が少ないので素早く解けるように対策が必要
- 玉手箱対策は、就活が本格化する前に早めに始めるのがおすすめ
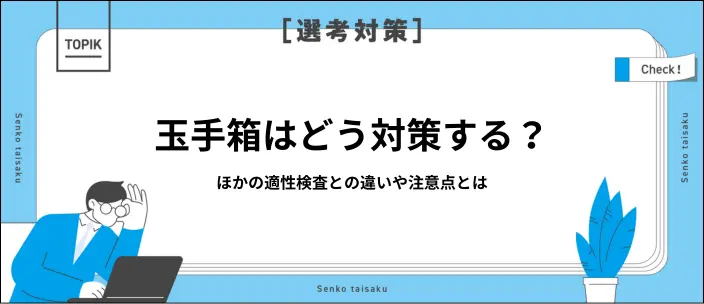
「玉手箱とはどのような適性検査なのか」「どのように対策したら良いのか分からない」など、疑問を持っている就活生も多いでしょう。玉手箱は、就活のWebテストのなかでも採用している企業が多く、事前の対策が不可欠です。
この記事では、玉手箱の特徴や問題形式、対策方法を解説します。攻略のポイントや対策を始める時期の目安もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
無料で相談!玉手箱対策でプロの手を借りる
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 就活の玉手箱とは?テストの概要
- 受検方法
- 見分け方
- 出題内容
- 合格目安
- 企業の導入目的
- 採用している企業
- 難易度
- 玉手箱の4つの特徴
- 1.1問あたりに使える時間が少ない
- 2.受検者によって出題される問題が異なる
- 3.同じ分野の問題が連続して出題される
- 4.前の問題には戻れない
- 玉手箱とほかのテストの違い
- 玉手箱とSPIの違い
- 玉手箱とTG-WEBの違い
- 玉手箱とWeb-CAB・Web-GABの違い
- 玉手箱の問題形式
- 言語理解
- 計数理解
- 英語理解
- 性格適性検査
- 玉手箱対策はインターンシップ選考前に始めよう
- 玉手箱対策を効率的に進めるコツ9選
- 1.制限時間を意識して対策を進める
- 2.対策本を繰り返し解いて問題形式に慣れる
- 3.Webサイトやアプリを活用する
- 4.苦手分野は重点的に対策する
- 5.電卓とメモ用紙で計算できるようにする
- 6.筆算でも解けるように練習する
- 7.模擬テストを受ける
- 8.性格適性検査の矛盾を無くす
- 9.第一志望以外の企業の選考も受けてみる
- 玉手箱試験本番の注意点
- 気持ちを落ち着けて臨む
- 分からない問題に時間をかけ過ぎない
- 不正行為をしない
- 玉手箱対策を徹底して選考に臨みたいあなたへ
- 玉手箱に関するよくある質問
- Q.玉手箱の対策はどのくらい前から始めるべき?
- Q.玉手箱とSPIどちらが難しい?
- Q.玉手箱の性格検査の対策とは?
就活の玉手箱とは?テストの概要
玉手箱とは、日本エス・エイチ・エル株式会社が運営する総合適性テストです。「能力テスト」と「性格適性検査」の2種類が出題されます。
大手企業や人気企業の新卒採用で導入されており、選考通過のためには対策が重要です。ここでは、玉手箱の概要や受検方法、出題内容などを解説するので、玉手箱とはどのようなものテストなのか知りたい方は参考にしてください。
受検方法
玉手箱の受検方法には、自宅や学校のネット環境が整ったパソコンから受検する「Webテスト方式」と、テストセンターで受検する「テストセンター形式」の2種類があります。
Webテスト方式とは、企業から送られてくるURLにアクセスし、受検期間内の好きなタイミングで受検する方法です。Webテスト方式の場合、計算問題では電卓の使用が認められています。
一方テストセンター形式とは、自宅ではなく指定されたテストセンターに出向いて受検する方法です。テストセンター形式の場合、会場に電卓を持ち込めないため、筆算で計算問題を解く必要があります。
見分け方
Webテスト方式の場合、企業から送られてくるURLから「玉手箱かどうか」を見分けることが可能です。URLに以下の文字が含まれている場合は、Webテストが玉手箱である可能性が高いでしょう。
・「e-exam」
・「nsvs」
・「tsvs」
玉手箱のほかにも、就活のWebテストにはさまざまな種類があります。応募先の企業が玉手箱を導入していると事前に分かれば、限られた時間で効果的な対策が可能です。
出題内容
玉手箱は、「能力テスト」と「性格適性検査」の2つで構成されています。
能力テストは、「言語」「計数」「英語」の3つの教科です。計数は数学や算数、言語は国語をイメージすると良いでしょう。
性格適性検査は、心理テストのような問題で、自分に当てはまる選択肢を選ぶ形式です。就活生の価値観や思考といった人間性を判断する質問が出題されます。
合格目安
玉手箱を導入している企業の多くは、合格目安を公開していません。一般的には6〜7割程度が合格の目安とされていますが、大手企業や人気企業、難関企業では、8割以上の正答率が求められる可能性もあります。
玉手箱は誤謬率(ごびゅうりつ)を測定しないテストです。誤謬率とは、解答した問題のうち、間違えた割合のこと。間違えた答えが多くても減点されないので、分からない問題があっても積極的に解答することが得点アップにつながります。
企業の導入目的
企業が選考の一環として玉手箱を実施するのは、主に以下の目的があるためです。
・就活生の基本的な学力を測る
・自社とのマッチ度を判断する
・応募者のなかから優秀な人材を選抜する
特に大手企業や人気企業には応募者が殺到するため、玉手箱を通して採用基準を満たした応募者をふるいにかける狙いがあります。
採用している企業
玉手箱は広く採用されており、業界を問わず大手企業から中小企業までさまざまです。なかでも、コンサルティングや金融、保険などの業界の企業が玉手箱を多く採用しています。
企業によって採用している適性検査の種類が異なるため、それぞれの対策が必要です。就活でよく見られるそのほかの適性検査については、「就活の適性検査とは?検査の種類や特徴、受ける際のポイントをご紹介!」の記事を参考にしてください。
難易度
玉手箱の言語・計数・英語の問題は、それぞれ中学〜高校レベルとされており、難易度はそれほど高くありません。事前に対策しておけば、高い正答率を狙えるでしょう。
ただし、難易度が高くないからといって何もせずにいると、大幅に点数を落とす可能性があります。本番の焦りや不安にも繋がるので、油断せずに玉手箱の対策をしっかり行いましょう。
玉手箱をはじめとした適性検査についての理解を深めたい方には、「テストセンターってなに?適性検査の種類と受検方法まとめ」の記事がおすすめです。
無料で相談!玉手箱対策でプロの手を借りる
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
玉手箱の4つの特徴
玉手箱の対策をする前に、特徴について知っておきましょう。主な特徴は「1問あたりに使える時間が少ない」「受検者によって出題される問題が異なる」などです。
ここでは、玉手箱の特徴を4つ解説するので、ぜひ参考にしてください。
1.1問あたりに使える時間が少ない
玉手箱は時間制限が厳しく、素早い解答が求められます。たとえば、問題によっては15分で32問の解答が必要です。この場合、1問あたりに使える時間は30秒程度しかありません。
解答速度を上げるためには、あらかじめ玉手箱の問題形式に慣れておく必要があります。問題集を解いたり、模擬テストを受けたりするなどして、対策を進めましょう。
2.受検者によって出題される問題が異なる
玉手箱は、受検者によって出題される内容が変わります。そのため、たとえ玉手箱を受検した就活生から、「このような問題が出た」と聞いても再び同じ問題が出るとは限りません。
同じ企業の玉手箱を受検する場合でも、問題は変わるので気をつけましょう。どの範囲が出題されても困らないよう、幅広い問題形式の対策をしておくことが大切です。
3.同じ分野の問題が連続して出題される
玉手箱は1つの分野において、1種類の問題形式しか出題されません。以下に、問題の分野と種類をまとめました。
【言語】
・論理的読解/GAB形式(32問/15分または52問/25分)
・趣旨判定/IMAGES形式(32問/10分)
・趣旨把握(10問/12分)
【計数】
・四則計算(50問/9分)
・図表の読み取り(29問/15分または40問/35分)
・表の空欄の推測(20問/20分または35問/35分)
【英語】
・論理的読解/GAB形式(24問/10分)
・長文読解/IMAGES形式(24問/10分)
たとえば、計数の分野の1問目が四則計算だった場合、あとの49問すべてが四則計算の問題になります。1問目が図表の読み取りであれば、残りもすべて同じ種類の問題形式です。
ほかの適性検査では複数の分野にわたって出題されるケースが多く、苦手な分野があっても得点を取れます。一方で、玉手箱は対策していない分野が出ると得点を取れないリスクがあるので、全分野の対策が必要です。
4.前の問題には戻れない
玉手箱は、前の問題に戻って解答を修正できません。一度「次に進む」のボタンを押すと、戻ることはできない仕様になっています。
分からない問題を後回しにしてあとから回答するという、テストでよく使われる手法を取れない点に注意が必要です。
玉手箱は加点式のテストのため、正解率が低くても評価は下がりません。どうしても分からない問題も、解答を埋めてから次に進みましょう。
各適性検査の特徴は、「適性検査の対策方法をご紹介!種類や受検方法も解説」でまとめているので、参考にご覧ください。
無料で相談!玉手箱対策でプロの手を借りる
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
玉手箱とほかのテストの違い
企業が採用試験で実施する適性検査の種類はさまざまです。ここでは、玉手箱とほかのテストの違いとは何かを知りたい方に向けて、特徴を紹介します。
玉手箱とSPIの違い
SPIは、株式会社リクルートマネジメントソリューションズが取り扱っている総合適性テストです。
受検方法は、「Webテスティング」「テストセンター」のほか、企業が用意する指定会場で受検する「ペーパーテスティング」、応募先企業のパソコンを使用する「インハウスCBT」があります。
SPIの出題内容は、「言語分野」「非言語分野」に分かれており、企業によっては「英語力」「構造的把握力」が追加されるのも特徴です。
適性検査のシェアとしてはSPIが最も多くなっており、ポピュラーな適性検査といえるでしょう。
SPIについてさらに詳しく知りたい方は「SPIのWebテストとは?受かるための対策や練習方法を解説」をご覧ください。
玉手箱とTG-WEBの違い
TG-WEBは、ヒューマネージ社が提供する適性検査で、自宅受検型がメインのWebテストです。問題は、「言語」「非言語」「英語」「性格適性」の4つの分野から出題されますが、英語を採用している企業はそう多くありません。
出題形式は従来型と新型の2種類があり、それぞれと特徴は以下のとおりです。
・従来型(旧型):難易度が高く出題数が少ない
・新型:問題数が多く回答時間が少ない
難易度は適性検査のなかで最も高いといわれています。なお、2021年からはAI監視型の「TG-WEB eye」の提供も始まりました。
TG-WEBについては「TG-WEB試験とは?試験概要・出題傾向・効果的な対策法を解説」で詳しくまとめています。
玉手箱とWeb-CAB・Web-GABの違い
Web-CABとは、玉手箱と同じ日本エス・エイチ・エル株式会社が提供するWebテストです。同じ会社が提供しているとはいえ、内容は全く異なります。
玉手箱は、一般的な適性検査と同様の問題が出題される総合職向けのテストといえるでしょう。一方、Web-CABはIT系職種での選考に多く用いられます。能力検査でも、「四則逆算」「法則性」「命令表」「暗号」といった、IT業界で必要とされる論理的思考力を測る問題が出されるのが特徴です。
Web-GABとは、玉手箱と同じく日本エス・エイチ・エル株式会社が提供するWebテストです。「言語」「計数」「性格検査」があり、どの企業でも出題範囲が固定されている特徴があります。
なお、Web-GABはGABの受検方式の一つで、自宅などで受検する種類の名称がWeb-GABです。このほかに、テストセンターで受ける「C-GAB」とペーパーテスト型の「GAB」があります。
就活のWebテストの種類はさまざまです。Webテストの種類や特徴について知りたい方は、「適性検査の種類22選を紹介!就活で使われる理由や対策も解説」の記事を参考にしてください。
無料で相談!玉手箱対策でプロの手を借りる
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
玉手箱の問題形式
玉手箱は、言語と計数が3種類ずつ、英語が2種類の全8種類で構成されています。問題数や制限時間は、企業によって異なる点に注意しましょう。
ここからは、それぞれの分野と問題形式について紹介します。
言語理解
言語理解は長文を読んで解答するもので、主に国語の能力を判断する問題です。「論理的読解(GAP形式)」「趣旨判定(IMAGES形式)」「論旨把握」の3つのうち、どれか1つが出題されます。
論理的読解(GAP形式)
論理的読解は600字程度の長文を読み解き、選択肢のなかから正しいと思うものを選んで解答する問題です。本文に対する設問文の内容が、正しいか・間違っているか・判別できないかを判断します。
制限時間は15分で、8つの長文に各4つの問題があり全32問です。または、制限時間が25分で、13の長文に各4つの設問で全52問が出題されます。解答時間は、1つの長文に対して1〜2分程度です。
趣旨判定(IMAGES形式)
趣旨判定は400〜600字程度の長文が出され、それに対する設問文が趣旨として正しいかどうかを選択肢から選びます。論理的読解と同様、8つの長文に各4つの設問があり全32問の構成です。
しかし、制限時間が10分と短く、1つの長文に対して1分30秒前後しか時間をかけられないため、迅速な解答が求められます。
論旨把握
論旨把握は1000字程度の長文を読み、4つの選択肢のなかから解答を選ぶ問題です。設問数は10問で、12分の制限時間が設けられています。
1問あたり1分程度で解答しなければならず、文章を素早く読み、理解する力が不可欠です。
計数理解
計数理解は、「四則逆算」「図表の読み取り」「表の空欄の推測」の3種類の問題形式で構成されています。Webテスト方式の場合は電卓が使えるので、あらかじめ用意しておきましょう。
四則計算
四則計算は式の一部に空欄があり、方程式を完成させる問題です。全50問で9分の制限時間が設けられています。
1問あたり10秒程度で解答しなければ間に合わないので、事前に出題形式に慣れておくのがポイントです。
図表の読み取り
図表の読み取りでは、表やグラフなどの図表を読み取って法則を見つけて設問に答えます。計算する桁の数が多いのが特徴です。
制限時間が15分で全29問、または35分で全40問に解答する2つのパターンがあります。
表の空欄の推測
表の空欄の推測は、図表に記入されているほかの数値から法則を読み取って、空白に当てはまる数字を解答する問題です。表の要素を比較して法則を見出す必要があるため、やや難易度が高いといえます。
制限時間は20分で全20問、または35分で全35問を解く構成です。
英語理解
英語は主に長文問題で構成され、基本的に単語の出題はありません。言語理解の「英語版」と考えておくと良いでしょう。玉手箱では、中高生レベルの基礎的な英語力が試されます。
論理的読解(GAP形式)
論理的読解は文章を読み、選択肢のなかから適切だと思うものを答える形式です。言語の論理的読解と同様に、正しいか・間違っているか・判別できないかを解答します。
制限時間は10分で、問題数は長文8つに対し各3つの設問で全24問です。
長文読解(IMAGES形式)
長文読解では、長文を読んで正しい選択肢に答えます。1つの長文に対して設問が3問あり、全24問の構成です。制限時間は10分で、英語の長文を読み解く力が求められます。
英語理解の対策方法を詳しく知りたい就活生は、「玉手箱の英語対策とは?特徴と出題傾向を押さえて完全攻略!」の記事を参考にしてください。
性格適性検査
性格適性検査は、選択肢のなかから自身の考えに合うものを選ぶ形式です。テストというよりも、性格診断のような側面が強いといえます。
性格適性検査の具体的な項目は、以下のとおりです。
・行動特性
・意欲
・情緒
・ライスケール
選択肢の数は2択や3択、4択など、企業によって異なります。質問の数は68問程度で、制限時間は20分です。性格適性検査の結果は、企業が「社風に合っているか」「入社後に活躍できる人材か」といった適性を判断するために利用されます。
無料で相談!玉手箱対策でプロの手を借りる
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
玉手箱対策はインターンシップ選考前に始めよう
玉手箱対策は、インターンシップ選考前にあたる大学3年生の5〜7月から始めましょう。企業によっては、インターンシップの選考で玉手箱を採用するところもあるためです。
内閣府の「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書」によると、インターンシップの参加時期は大学3年生の7月〜9月ごろがピークでした。

引用元:内閣府「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(11p)」
なお、インターンシップの選考と比べて、本選考ではより多くの企業が玉手箱を実施します。
玉手箱は選考の初期段階で採用されるケースが多く、情報解禁に合わせて実施する企業も少なくありません。インターンシップ選考でWebテストの実施がなかった学生も、本選考が始まる大学4年の6月までには、玉手箱の対策を済ませておきましょう。
一次面接と適性検査の関連性については、「一次面接と適性検査に関係はある?検査の内容や受検に向けた対策を解説!」の記事で詳しく解説しています。
参照元
内閣府
学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査
無料で相談!玉手箱対策でプロの手を借りる
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
玉手箱対策を効率的に進めるコツ9選
玉手箱対策を効率的に進めるためには、本番を想定した練習が不可欠です。ここでは、玉手箱対策の方法を9つ紹介するので、参考にしてください。
1.制限時間を意識して対策を進める
玉手箱は、対策の段階から制限時間を意識して解くのがポイントです。玉手箱は1問あたりの解答時間が30秒から1分程度しかないため、スピードが求められる傾向にあります。
練習のときから制限時間を意識すると、本番でも同様のペース配分で解答できるでしょう。練習段階ではタイマーやストップウォッチを使用し、自分がどの程度の時間で解答できるか確認しておくのがおすすめです。
2.対策本を繰り返し解いて問題形式に慣れる
対策本や問題集を用意し、繰り返し解くようにしましょう。玉手箱は、過去に出た問題から数字のみを変えたものが出題されるケースも珍しくありません。問題の傾向をつかみ、設問を見ただけで解き方が分かるようになれば、本番でも素早く解答できます。
玉手箱の対策本や問題集は、書店やオンラインショップなどの市販で購入可能です。レイアウトや解説の分かりやすさなどから自分に合う1冊を選び、繰り返し解くようにしてください。
3.Webサイトやアプリを活用する
玉手箱対策には、Webサイトやアプリの活用もおすすめです。Webサイトのなかには、本番同様の問題を体験できるものもあります。また、アプリであれば、通学中や外出先でのスキマ時間を有効に使いやすい点がメリットです。
対策本を一度解いてから、理解度をチェックするためにWebサイトやアプリを活用すると良いでしょう。また、Webサイトやアプリは対策本の問題をすべて解く余裕がないときにも、概要をつかむために役立ちます。
4.苦手分野は重点的に対策する
玉手箱における自分の苦手分野が特定できたら、重点的に時間をかけて対策しましょう。苦手な分野や間違えた問題には付箋やマーカーをつけ、スムーズに解けるようになるまで繰り返し取り組むのがおすすめです。
練習のときは時間をかけたり、解説を読んだりして問題を解けたとしても、本番では制限時間のなかで思うように解答できないことも少なくありません。苦手な問題を重点的に対策すると、本番でも落ち着いて解答できるでしょう。
5.電卓とメモ用紙で計算できるようにする
玉手箱の計算問題で使う電卓は、日頃から使い慣れたものを用意しましょう。電卓によって操作方法やボタン配置が異なるため、本番で違う物を使用すると混乱する可能性があります。練習段階から電卓を使用すると、本番でもスムーズな計算が可能です。
また、練習段階からメモを残すよう意識しましょう。本番でメモが必要になった場合に、「メモに集中し過ぎて時間をオーバーしてしまった」といったミスを減らせます。
6.筆算でも解けるように練習する
玉手箱をテストセンターで受検する場合は、電卓を使用できません。電卓がなくても計算できるように、筆算の練習もしておきましょう。
電卓に頼り切ってしまうと、いざというときに計算ができず、点数を下げる要因になります。また、計算に時間がかかると、制限時間が足りなくなる可能性もあるでしょう。
Webテストなのかテストセンター形式なのかは、企業によって異なります。電卓でも筆算でも問題ないように準備しておくと安心です。
テストセンターでの電卓の扱いについては、「テストセンターで電卓は使える?持ち込み禁止物を確認しよう」の記事も参考にしてください。
7.模擬テストを受ける
選考前に玉手箱の模擬テストを受検しておくと、解答方法や試験の雰囲気をつかめます。本番の一連の流れを想定したうえで、本番も落ち着いて臨めるでしょう。
模擬テストの結果を振り返ると、自分の得意不得意が分かります。また、テスト結果を苦手な分野の対策に役立てられると、どの内容が出題されても安定して点数が取れるようになるでしょう。
8.性格適性検査の矛盾を無くす
玉手箱の性格検査は、矛盾がないように答えることが重要です。
性格検査で企業からの印象を良くしようと、本心とは異なる答えを選ぶ人も少なくありません。しかし、適性検査は似たような趣旨の質問がいくつか出題されるため、虚偽の回答をするとどこかで矛盾が出やすくなります。
性格検査であまりにも矛盾が多くなると企業からの印象が悪くなり、不採用の原因にもなりかねません。
自己分析をしっかり行ったうえで、答えを統一させることを意識しましょう。
9.第一志望以外の企業の選考も受けてみる
第一志望以外の企業の選考で玉手箱を受検してみるのもおすすめです。一度、本番の適性検査を受けておくと、本命企業のときに過度に緊張せずに済みます。模擬試験も効果的ですが、実践を積むことでより改善点を見つけやすくなるでしょう。
就活を成功させるには、流れを把握しておくのが重要です。「就活のやり方と流れを解説!準備から内定までのポイントと相談先も紹介」では、就活の流れや進め方をまとめています。
無料で相談!玉手箱対策でプロの手を借りる
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
玉手箱試験本番の注意点
玉手箱の試験本番では、時間配分や不正行為など、注意すべきポイントがあります。ここでは、特に注意すべきポイントをまとめているので、参考にしてください。
気持ちを落ち着けて臨む
玉手箱を受検する直前は、気持ちを落ち着けることを意識しましょう。
中学〜高校レベルと難易度はそこまで高くありませんが、緊張し過ぎてしまうと頭が真っ白になり、本来解けるはずの問題が解けなくなる可能性があります。リラックスすることで、本当の力を発揮しやすくなるでしょう。
たとえば、深呼吸や軽いストレッチをすると、緊張がほぐれやすくなります。自分なりのリラックス方法を見つけて実践してみてください。
また、準備不足のまま本番を迎えると不安から緊張しやすくなるので、対策をしっかり行うことも重要です。
就活での気持ちのコントロールの方法は「就活でメンタルがボロボロのときの対処法|ストレスを溜めないコツも紹介」を参考にしてください。
分からない問題に時間をかけ過ぎない
試験の本番でどうしても分からない問題が出てきたら、時間をかけずに回答して次の問題に進みましょう。
玉手箱は、誤謬率(ごびゅうりつ)を測定しておらず、正しく解答した数のみをカウントしています。そのため、時間が足りなくなり未回答の問題が出るよりも、間違ってでもすべての問題に回答するほうが高得点を狙いやすくなるでしょう。
不正行為をしない
Webテストであっても、解答を検索したり解答集を活用したりするなど、不正とみなされる可能性がある行為はやめましょう。
不正行為が発覚した場合、該当する試験だけでなく、ほかの企業からも内定を取り消される可能性があります。場合によっては、玉手箱を採用している企業の選考に参加できなくなる場合もあるため、非常にリスクの高い行為です。
玉手箱を受検するときは、事前に注意事項をよく読み、不正を疑われる行為はしないように注意してください。
無料で相談!玉手箱対策でプロの手を借りる
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
玉手箱対策を徹底して選考に臨みたいあなたへ
玉手箱をはじめとする適性検査の対策に、焦りや不安を感じている就活生は多いでしょう。玉手箱は難易度がそれほど高くはないものの、解答スピードが求められる適性検査です。そのため、事前に対策して問題形式やパターンに慣れておく必要があります。
「自分に合った玉手箱の対策方法を知りたい」「対策を始めたものの、手応えを感じられない」といった悩みがある場合は、就職エージェントへの相談がおすすめです。就職エージェントのキャリアチケットでは、玉手箱対策に限らず、エントリーシート(ES)や面接など、就活全般のアドバイスをしています。
多くの不安を抱える就活は、精神的な負担も大きくなりがちです。就活に対して不安や悩みがあるときは、ぜひキャリアチケットにご相談ください。
無料で相談!玉手箱対策でプロの手を借りる
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
玉手箱に関するよくある質問
ここでは、玉手箱についてよくある質問をまとめました。
Q.玉手箱の対策はどのくらい前から始めるべき?
A.玉手箱の対策は、受検の3ヶ月前から始めると良いでしょう。たとえば、インターン選考で玉手箱を受検する場合は、大学3年生の5〜7月からの対策がおすすめです。玉手箱の対策には約60時間程度が必要といわれているため、選考を受ける時期に合わせてスケジュールを組みましょう。
「27卒の就活スケジュールをチェックしよう!いつ何をすべきか解説」では、一般的な就活スケジュールを紹介しているので、ご参照ください。
Q.玉手箱とSPIどちらが難しい?
A.難易度は、玉手箱のほうがSPIよりも上といえるでしょう。玉手箱は企業ごとに出題内容が異なり対策が難しいうえ、回答するスピードも求められるためです。とはいえ、問題そのもののレベルはそこまで高くないので、事前に対策をしておけば十分対応できます。
それぞれの違いについて詳しく知りたい方は「SPIと玉手箱の違いとは?適性検査の種類や特徴をチェック」の記事もご覧ください。
Q.玉手箱の性格検査の対策とは?
A.玉手箱の性格検査の対策として、自己分析を丁寧に行い自分自身についてよく知っておきましょう。また、企業研究を行い、企業で求められている人材の特徴を理解するのも効果的です。
自己分析については「自己分析とは?就活におすすめの簡単なやり方10選や活用例を解説」の記事で詳しくまとめています。
無料で相談!玉手箱対策でプロの手を借りる
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。