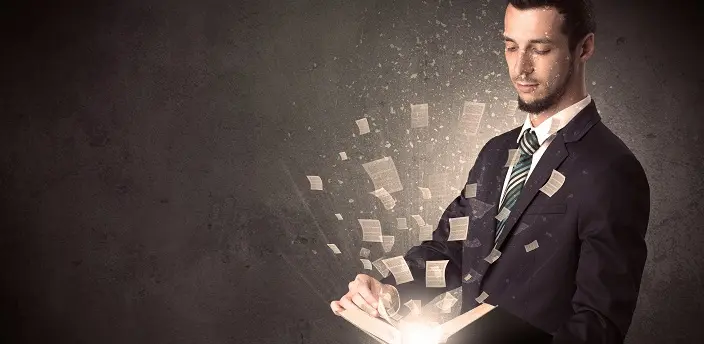このページのまとめ
- SPIのボーダーとは、合格するための最低ラインのこと
- SPIのボーダーに明確な点数はなく、偏差値で決まる
- SPIのボーダーは正答率60%以上や80%以上など、企業ごとに違う

「SPIのボーダーはどのくらい?」「具体的に何点取れば合格するの?」などと気になる就活生も多いでしょう。実はSPIのボーダーに明確な点数はなく、周囲の就活生よりも点数がとれているかどうかで決まります。
この記事では、SPIにおけるボーダーの考え方や、突破に向けた対策方法を解説。最後まで読めばSPIのボーダー突破のコツがわかり、志望企業の内定獲得を実現できるはずです。
自分の価値観とあった企業に出会える!25卒のスカウト登録はこちら
- SPIのボーダーとは合格の最低ライン
- SPIのボーダーは偏差値で決まる
- ボーダーラインは足切りに使用される場合が多い
- SPIのボーダーラインは企業によって異なる
- SPIのボーダーラインを重視しない企業もある
- 能力検査と性格検査どちらを重視するかは企業次第
- SPIのボーダーラインはどのくらい?業界業種の目安を解説
- ボーダーライン90%以上の業界業種
- ボーダーライン80%以上の業界業種
- ボーダーライン70%以上の業界業種
- ボーダーライン60%以上の業界業種
- SPIテストセンターでのボーダーライン超えの見極め方
- 「言語」問題の場合の目安
- 「非言語」問題の場合の目安
- 「英語」問題の場合の目安
- 「構造的把握力」問題の場合の目安
- SPIのボーダーラインを超えるための対策
- 出題される内容を把握しておく
- 頻出問題を練習しておく
- 苦手分野を徹底的に練習する
- 模擬試験にチャレンジする
- 短期間に何度も受検する
- よい点数が出たら使いまわす
- SPIのボーダーラインを超えるための勉強法
- SPI用の問題集を解く
- Webの問題集を使う
- 解説動画を見る
- スマホアプリを使う
- SPIのボーダーを超えるための問題集の選び方
- 受検形式に合う問題集
- 最新版
- 解説が充実した問題集
- 苦手分野に特化した問題集
- SPIのボーダーライン突破を目指す際の注意点
- ボーダーの明確な点数はわからない
- 実現可能な点数を目指す
- 問題の内容や難易度で気を抜かない
- わからない問題は飛ばす
- 性格検査に向けて自己分析をしておく
- SPIのボーダーライン突破など就活対策を学びたいあなたへ
SPIのボーダーとは合格の最低ライン
SPIのボーダーとは、選考を通過するための最低ラインのことです。SPIは点数で評価される試験であり、企業の基準を満たさないと落ちてしまう場合があります。
ここでは、SPIのボーダーラインについて詳しく解説するので、ぜひ確認してください。
SPIのボーダーは偏差値で決まる
SPIのボーダーは、偏差値で決まるケースが一般的です。自分の点数だけではなく、周囲の点数によって自分が合格できるかどうかが決まります。
SPIの選考を通過するためには、周囲よりも高い点数を取ることが欠かせません。受検する企業のレベルやほかの就活生に左右されることは知っておきましょう。
ボーダーラインは足切りに使用される場合が多い
SPIでボーダーが決められるのは、足切りにするラインを決めるためです。大手企業や人気企業は応募する就活生が多く、全員を面接することができません。
そのため、企業はSPIのボーダーを設定し、「上位80%以上の就活生だけを面接に呼ぼう」のように足切りを行います。SPIがある場合は点数が低いと足切りにあうことを理解し、徹底的に対策を行うことが大切です。
企業が選考でSPIを導入する理由については、「SPIとは?今さら聞けない出題内容や対策のコツを就活のプロが解説!」の記事をご覧ください。
SPIのボーダーラインは企業によって異なる
SPIのボーダーは企業によって違うことを知っておきましょう。60%以上で通過できる企業もあれば、80%以上が求められる起用もあります。
特に金融やコンサルティングなどの企業は就活生に求める能力が高く、90%以上でないと選考に合格できないといわれることも。しかし、すべての企業で高いボーダーラインを設けているわけではありません。一般的な合格ラインは60%〜70%以上であり、80%以上の正答率があればSPIを通過できる可能性が高いでしょう。
SPIのボーダーラインを重視しない企業もある
SPIを選考に取り入れているものの、点数をあまり気にしていない企業もあります。適性検査の結果だけではなく、エントリーシートや面接などもふまえて判断したいと考えるためです。
SPIでわかるのは、あくまでも就活生の基礎的な学力や、おおまかな性格・適性。実際に面接を行うことでしか、わからない特徴や雰囲気もあるため、面接やエントリーシートなども徹底的に対策を進めてください。
能力検査と性格検査どちらを重視するかは企業次第
SPIでは能力検査を重視する企業もあれば、性格検査を重視する企業もあります。どちらを重視するかは、企業次第です。
一般的には、ボーダーラインが高い企業は能力検査、低めの企業は性格検査を重視しているともいわれています。ただし、どんなに能力検査の結果がよくても、性格検査の結果が企業の価値観に合わなければ評価は下がります。「能力は高くても社風に合わない」と判断されるからです。
反対に、性格検査が企業の求める人物像に合っていても、能力検査の点数が低すぎては問題です。SPIでは能力検査と性格検査、どちらもバランスよく正答率を高める必要があります。
自分の価値観とあった企業に出会える!25卒のスカウト登録はこちら
SPIのボーダーラインはどのくらい?業界業種の目安を解説
SPIのボーダーラインがどのくらいになるのか、大体の目安を紹介します。得点数の割合ごとに解説するので、参考にしてください。
ボーダーライン90%以上の業界業種
ボーダーライン90%以上が必要なのは、日本銀行や外資系のコンサルティング企業です。応募する学生のレベルが高いことから、合格に必要な点数も高くなっています。
受検者の中で90%以上を目指すには、正解率はもちろん、問題の回答数も必要になります。どれだけ素早く、正確に解けるかがポイントになるでしょう。
ボーダーライン80%以上の業界業種
80%以上ないと足切りになってしまうのは、以下のような企業です。
・総合商社
・新聞社
・テレビ業界
・メーカー
・大手銀行
誰もが知るような大手企業や有名企業は、優秀な学生が多く集まります。また、そもそもの受験者数が多く、ライバルが増えるのも特徴です。足切りにあわないためにも、80%以上の獲得を目指したほうがよいでしょう。
ボーダーライン70%以上の業界業種
ボーダーライン70%以上となると、次のような業界や業種があてはまります。
・通信業界
・銀行
・メーカー
・インフラ業界
・エネルギー業界
合格ライン70%以上は、事前に対策さえ行っておけば十分に合格可能な範囲です。安定して合格点数を取れるように勉強しておきましょう。
ボーダーライン60%以上の業界業種
ボーダーライン60%以上の場合、次のような業界業種があてはまります。
・不動産業界
・航空業界
・保険業界
60%は十分取得可能な範囲であり、足切りよりも対策を行っているかが見られています。ボーダーラインによって勉強する時間は変わってくるので、志望企業がどのくらいの合格ラインを引いているかは確かめておきましょう。
SPIボーダーが高いといわれる企業を受けると就活で有利な理由
SPIのボーダーラインが高い企業を受けた方がいいといわれるのは、自分の実力が明確になるからです。ボーダーラインの高い企業を受験し、選考に突破できれば、高得点が獲得できていることがわかります。
また、高得点さえとってしまえば、ほかの企業にも使いまわせるのがメリット。SPIは獲得した点数を明確に教えてもらえるわけではないので、自分のレベルを把握するために、ボーダーラインの高い企業も受けた方がいいといわれるのです。
ただし、就活ではSPIだけではなく、一般常識問題を出す企業もあります。事前に出題内容を確認し、必要な対策を行いましょう。
一般常識問題については、「SPIと一般常識問題の違いは何?それぞれの特徴や対策方法を解説」の記事で解説しています。どちらも対策をしていないと高得点は難しいので、事前に勉強しておきましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!25卒のスカウト登録はこちら
SPIテストセンターでのボーダーライン超えの見極め方
テストセンターでSPIを受ける場合、正解数が多いと後半で難しい問題が出題され、正解数が少ないと問題のレベルは一定という特徴があります。問題の傾向によって、ボーダーラインを超えているかどうかがある程度見極められるでしょう。
ここでは、「言語」「非言語」「英語」「構造的把握力」でのSPI高得点の目安を紹介します。
「言語」問題の場合の目安
言語分野では、語彙や文章読解などが出題される問題です。正答率が高いと推測される場合、以下の3つの傾向がみられます。
・長文読解の出題数が多い
・チェックボックス形式が出てくる
・抜き出し問題がある
長文読解の出題数が2問、3問と複数ある場合は、高得点が取れている可能性が高いです。また、長文問題の中の小問にチェックボックス形式の問題がある場合も、正答率が高い傾向にあります。
チェックボックス形式とは、あてはまるものすべてを選択するという問題形式です。正しいものをすべて答えなければ正解にならず、難易度が高くなります。
また、長文問題の中で「当てはまる語句を抜き出しなさい」などの語句や文章を抜き出す問題が出された場合は、高得点の可能性が高いでしょう。
「非言語」問題の場合の目安
非言語分野では、基礎的な計算や推論の問題が出されます。正答率が高い場合、以下の3つの傾向です。
・非言語分野の始めに4タブ形式問題がある
・推論問題の出題数が多い
・推論でチェックボックス形式が出される
言語分野での正答率は、非言語分野でも引き継がれます。そのため、非言語分野の始めに4タブ形式の問題が出題された場合は、言語分野での正答率が高いと予想可能です。
4タブ形式問題とは、ひとつの設問に対して小問が4つあるものを指します。通常は2タブ問題が多いので、3または4タブ問題が現れた場合は、高得点である可能性が高いでしょう。
また、推論問題は他の問題形式と比べて難易度が高い問題です。推論問題が多く出題される場合や、推論問題の中に正しいものをすべて選択するチェックボックス形式の問題が出てきた場合は、正答率が高いことが推測されます。
「英語」問題の場合の目安
SPIで英語を求める企業は多くはありません。そのため、自分が受けるSPIに英語があるのかどうか、必ず事前に確認しておきましょう。ほとんどの企業が言語・非言語分野のみの試験ですが、英語も高得点と推測できるポイントがあります。
英語は言語分野と同様、長文問題の出題数が多いほど高得点が期待できるでしょう。英語は単語など基礎的な知識がないと正解するのは難しいため、早い段階からの対策が欠かせません。
「構造的把握力」問題の場合の目安
構造的把握力の問題は、正解不正解に関わらず、同じ問題が出題されます。そのため、問題の内容で正答率を見極めることはできません。
高得点を取るための対策は、ひたすら問題集で練習することです。同じ問題が複数回出題されることもあり、ひたすら経験を積むことが有効になります。
自分の価値観とあった企業に出会える!25卒のスカウト登録はこちら
SPIのボーダーラインを超えるための対策
SPIのボーダーラインを超えるために、問題集を用いて対策を行いましょう。ここでは、SPIの対策法を紹介するので、参考にしてください。
出題される内容を把握しておく
SPIでどのような問題が出題されるのか、事前に問題を確認しておきましょう。SPIはある程度出題される範囲や形式が決まっているので、内容を覚えておくことが大切です。
たとえば、非言語問題は数学的な内容が多く、解くためには公式を覚えておく必要があります。事前に範囲を勉強して公式を覚えておけば、本番で問題なく回答できるでしょう。問題集を解き、どのような問題があるか知っておけば安心です。
なお、選考で使用される適性検査はSPIだけではありません。「就活の適性検査とは?検査の種類や特徴、受ける際のポイントをご紹介!」の記事でSPI以外についてまとめているので、参考にしてください。
頻出問題を練習しておく
SPIは頻出問題があるので、どの問題が出そうか予想しておきましょう。頻出問題を安定して解けるようになると、合格ラインに近づきます。
どのような問題が出るかについて、企業側は基本的に公開していません。しかし、これまでの就活生がどのような問題が出たかを口コミなどで残している場合があります。問題集にも頻出問題の予想が掲載されていることがあるので、よく確認して対策を進めてください。
苦手分野を徹底的に練習する
得意分野を伸ばすより、苦手分野を徹底的に練習しましょう。狭く深くよりも、広く浅くのほうがボーダーラインを超える確率は高まります。
SPIは出題範囲が広く、本番でもさまざまな形式の問題が出題されます。得意分野だけを頑張っても、本番で出題されず合格ラインまで届かない場合も出てくるでしょう。
同じ形式の問題ばかり出るわけではないので、苦手を減らして解ける範囲を増やすことが大切です。どこから勉強するか迷ったら、苦手な分野を中心に勉強してください。
1冊の問題集を何度も解いて慣れるのがおすすめ
SPIの対策を行うためには、1冊の問題集を何度も解くのがおすすめです。同じ問題集を解くことで、自分の得意分野と苦手分野がわかり、対策を行いやすくなります。
また、出題傾向はある程度決まっているので、問題の形式に慣れるのが大事です。初見では難しくても、解き方さえわかっていれば解答できる問題も多いので、とにかく数をこなして慣れるようにしましょう。
模擬試験にチャレンジする
模擬試験を行い、本番の環境に慣れておくのがおすすめです。問題の傾向はもちろん、時間制限に慣れる目的もあります。
また、模擬試験の結果を振り返り、問題の対策を行うのも大切です。「どの分野の点数が低かったのか」「どの問題に手間取ったのか」などがわかるため、SPI対策の指針が立てられるでしょう。
模擬試験は無料で受けられるものもあるので、インターネットで探してみてください。1度模擬試験を受けておけば、テストの雰囲気をつかむこともできます。
短期間に何度も受検する
対策がある程度できたら、実際に受検をしましょう。選考を行う企業さえ違えば、SPIを複数受けることも可能です。
期間が空いてしまうと、勉強した内容を忘れてしまうこともあるでしょう。できるだけ短期間に、何度も受けておくことをおすすめします。
よい点数が出たら使いまわす
よい点数を獲得できたら、その結果を使いまわしましょう。SPIの場合、ほかの企業の選考にも点数結果を使用できます。
もし、点数が希望するボーダーラインに届かなければ、もう一度チャレンジすればOKです。ボーダーラインを超えていると思えば、使いまわすことで効率的に選考を突破できるでしょう。
SPIのテストセンター対策についてもっと知りたい方は「テストセンターではどんな問題が出る?SPI対策を紹介」を参考にしてください。対策をしていないと選考に落ちることは十分あり得るので、きちんと勉強しておきましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!25卒のスカウト登録はこちら
SPIのボーダーラインを超えるための勉強法
SPIのボーダーラインを超えるには、問題集やアプリを活用するのが大切です。4つの勉強方法を紹介するので、合格に向けてぜひ参考にしてください。
SPI用の問題集を解く
SPIで合格ラインを超えるため、まずはSPI用の問題集を解きましょう。書店などで販売されているものを使えば問題ありません。また、前述したように複数購入せず、まずは1冊に絞って解き進めるとよいでしょう。
Webの問題集を使う
Webでも問題集が公開されているので、活用するのがおすすめです。問題をまとめたWebサイトや、就活サイトで公開されているので確認してみましょう。
また、就活サイトではSPIの模擬テストを行っている場合もあります。全国順位を確認したり、得意分野と苦手分野を発見できたりするので受けてみるのもよいでしょう。
解説動画を見る
SPIの問題をどのように解くか、解説動画を見るのもおすすめです。自分で勉強していてわからない問題も、動画でわかりやすく学べます。
特に、非言語の図形や推論など、問題集の解説だけではわかりにくい範囲もあります。さまざまな動画があがっているので、自分に合うものを探してみるとよいでしょう。
スマホアプリを使う
スマホアプリを活用して、SPI対策を行うのもおすすめです。外出中やすきま時間にも勉強しやすいでしょう。
就活が始まると説明会や選考に参加したり、異動したりでまとまった時間がとりにくくなります。スマホアプリであれば、電車に乗りながら勉強したり、少しの空き時間に問題を解いたりできるので便利です。
問題集を持ち運ぶのはなかなか大変で、しっかりと勉強できる場所がないケースもよくあります。スマホアプリをうまく活用して、SPI対策を徹底的に行ってください。
SPIの効率的な勉強法は、「SPIの効率的な勉強法とは?時間がない人もできる対策方法をプロがご紹介」の記事でも解説しています。
自分の価値観とあった企業に出会える!25卒のスカウト登録はこちら
SPIのボーダーを超えるための問題集の選び方
SPIでボーダーラインを超えるためには、問題集も大切です。自分に合う問題集を選べるかどうかで、対策のレベルと速度が変わります。ここでは、問題集の選び方を4つ紹介するので、参考にしてください。
受検形式に合う問題集
受検形式で問題の傾向は変わるため、受験形式に合った問題集を選びましょう。SPIの場合は、SPIは、次の4つの受検形式があります。
・テストセンター
・Webテスティング
・ペーパーテスティング
・インハウスCBT
志望企業する企業の選考について確認し、どの形式で受検することになるのか確かめておきましょう。記載されていない場合は、就活生の口コミを確認するのもおすすめです。
もし、志望企業が決まっていない場合は、複数のテスト形式に対応した問題集を選びましょう。
最新版
SPIの問題集を選ぶ際は、最新版を選ぶようにしましょう。SPIの傾向は毎年変わるため、古い問題集だと傾向に対応できない場合があります。
書店などで問題集を探す際は、年度が最新版かどうかを確認してください。また、先輩から問題集をもらった場合も、別途最新版の問題集を用意しておくのがおすすめです。
解説が充実した問題集
問題集を選ぶ際は、解説が充実しているものを探してください。解説がないと問題の解き方がわからず、苦手なまま終わってしまう可能性があるからです。
問題集によっては解説がなく、回答だけしか書いていないものもあります。なぜ間違えたか、どのように回答するかがわからないため、自分にとってわかりやすい解説のある問題集を選びましょう。
苦手分野に特化した問題集
問題集を解いて苦手分野が見えてきたら、苦手分野に特化した問題集も解いてみましょう。SPIは幅広い範囲が出題されるため、苦手分野をなくすことで点数の底上げにつながります。
最初は分野に特化せず、SPIの問題全体を解ける問題集から始めましょう。解いていくなかで、苦手な分野が見えてくるはずです。
SPIは得意分野を伸ばすより、苦手分野をなくしてどの分野も解けるようにしておくと、安定して点数を取れるようになります。
SPIが難しいと感じる方には、「「SPIが難しい」と感じるあなたへ!オススメの対策や難易度を解説」の記事がおすすめです。なぜ難しいと感じるかを理解したうえで、対策を進めましょう。
対策に悩む場合は、キャリアチケット就職エージェントにも相談してください。あなたの悩みに応じて、専任のアドバイザーがサポートします。
自分の価値観とあった企業に出会える!25卒のスカウト登録はこちら
SPIのボーダーライン突破を目指す際の注意点
SPIのボーダーを突破して合格するためには、準備段階から注意したいこともあります。合格に向けた注意点を解説するので参考にしてください。
ボーダーの明確な点数はわからない
SPIのボーダー突破を目指す場合、ボーダーの明確な点数はわからないことを知っておきましょう。ボーダーは周囲の就活生の点数によって変わるものであり、明確に決められるものではないからです。
また、企業の基準や求めるレベルによっても、ボーダーは大きく変わってきます。60%以上で合格できる企業もあれば、90%以上ではないと合格できない企業もあるためです。
「練習段階で△点だから大丈夫」などのように、ボーダーは予想できないので気をつけましょう。周囲の就活生のレベルにも影響するため、自分が高得点を取れるように徹底的に対策を進めてください。
実現可能な点数を目指す
SPI対策を行う場合、実現できそうな点数を目指して勉強しましょう。理想が高すぎるとSPI対策ばかりに時間を使ってしまい、ほかの就活対策ができない場合があるからです。
たとえば、「SPIで満点を目指す」と考えて対策をしても、実現は難しいでしょう。SPIの対策に時間をかけすぎて、エントリーシートや面接などの選考に落ちてしまうケースもあります。
まずは自分の実力を確かめ、どの程度のレベルであれば対策できるか考えることが大切です。ほかの選考対策との兼ね合いも考えて、実現できる点数を目指してください。
就活でやっておきたい対策については、「就活は何から始める?時期別の対策・効率アップのコツを解説」の記事で紹介しています。
問題の内容や難易度で気を抜かない
受検中の問題の内容や難易度を見て、油断したり安心したりしないようにしましょう。SPIは正答率が高いと問題の難易度が上がる傾向にありますが、必ずボーダーを超えているとは限りません。
問題が難しくなったからといって油断していると、後半で点数が伸びず、不合格になるケースも考えられます。一問一問丁寧に対応し、最後まで油断せずに回答してください。
わからない問題は飛ばす
わからない問題が出てきたら、考えすぎずに次の問題に進んでください。時間をかけたうえに間違えてしまうと、ほかの問題に使う時間がなくなってしまうためです。
特に、ペーパーテストは自分で回答する問題の順番を選べるため、得意な問題から解くことができます。苦手な問題は後回しにしておくと、安定して点数を獲得できるでしょう。
ただし、テストセンターやWebテスティングは問題ごとに時間制限があるため、時間をかけすぎると無回答で進んでしまう場合もあります。わからないときはとりあえず回答を選んでおき、無回答にならないように気をつけるのもポイントです。
性格検査に向けて自己分析をしておく
性格検査を効率的に解くために、自己分析を終えておきましょう。性格検査は時間のわりに問題数が多いので、じっくり考えていると時間切れになってしまいます。
性格検査は問題に対し、「あてはまる」「あてはまらない」などを選ぶ形式です。自己分析さえできていれば、直感的に解答できるでしょう。
自己分析はSPIだけでなく就活全体にとって必要な作業です。「就活のやり方を徹底解説!基本的な進め方やスケジュールをご紹介」の記事では就活の全体像についてまとめているので、自己分析を行うタイミングを確認しておきましょう。
SPIの時間配分の目安
SPIの時間配分は、受験形式によって変わります。問題数や制限時間が変わるためです。受験形式ごとに時間配分の目安を紹介するので、確認しておきましょう。
Webテストやテストセンターで受験する場合、次のような制限時間と問題数になります。
【能力検査】
・制限時間:約35分
・出題数:解答状況によって変わる
【性格検査】
・制限時間:約30分
・問題数:約300問
能力検査の場合、1問ごとに制限時間が決められています。時間が過ぎると自動的に次の問題に移動してしまうので気を付けましょう。特に性格検査の場合は、1分で10問ほど解かなければなりません。考えている時間はあまりないので、選択肢を見て直感的に答えてください。
ペーパーテストの場合、次のような制限時間と問題数になります。
【能力検査】
・制限時間:約70分、言語問題約30分・非言語問題約40分
・出題数:70問、言語問題約40問・非言語問題約30問
【性格検査】
・制限時間:約40分
・問題数:約300問
能力検査では、1問あたり1分で解く必要があります。その代わり、テストセンターと違って自分で自由に時間配分ができるのがポイント。冊子が配られる形式のため、自分で解答する問題と時間を選べるのです。
ペーパーテストの特徴については、「SPIのマークシート形式「ペーパーテスト」の特徴や対策方法を解説」の記事で解説しています。受験形式ごとに特徴も変わってくるので、それぞれの違いを確認しておきましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!25卒のスカウト登録はこちら
SPIのボーダーライン突破など就活対策を学びたいあなたへ
SPIの準備方法や対策などを就活のプロにお願いしたいという方もいるのではないでしょうか。そんなあなたには、就職エージェントのキャリアチケットがおすすめです。
キャリアチケットでは、SPIをはじめとする適性検査の対策やボーダーライン突破に向けたサポートを実施しています。また、SPI対策だけではなく、あなたに合った企業紹介のほか、エントリーシートや履歴書の添削、模擬面接などひとりでは難しい選考対策をサポート。
さらに、「自己分析セミナー」や「業界研究セミナー」などのセミナーも豊富にご用意。「なかなか面接まで進まない」という方も選考対策をプロが監修するため、スムーズな就活を後押しします。キャリアチケット就職エージェントとともに、内定獲得に向かって走り抜けましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!25卒のスカウト登録はこちら