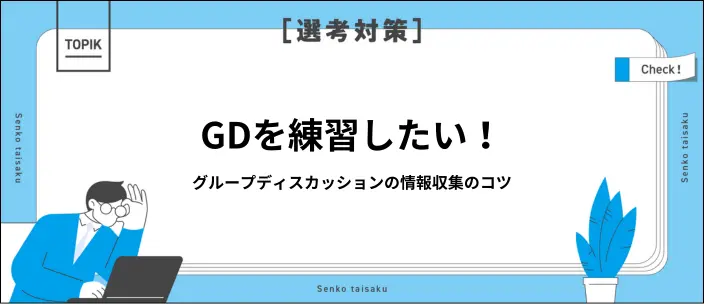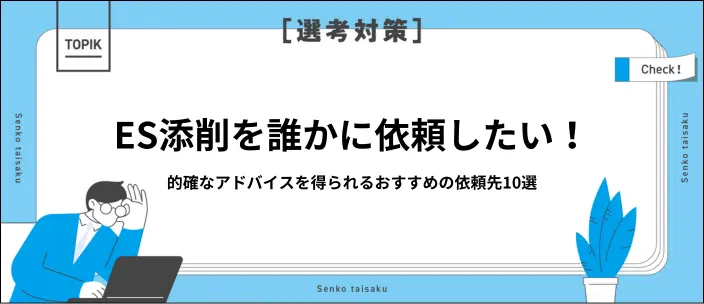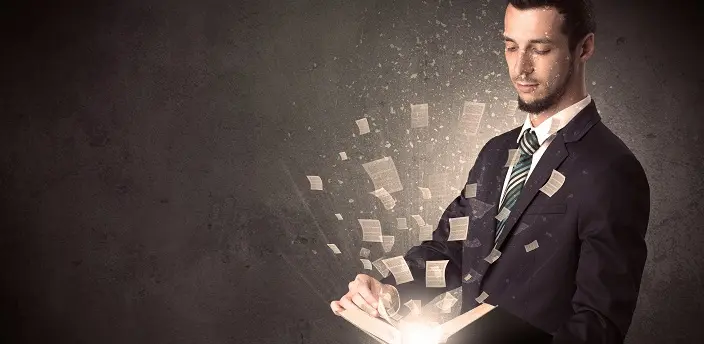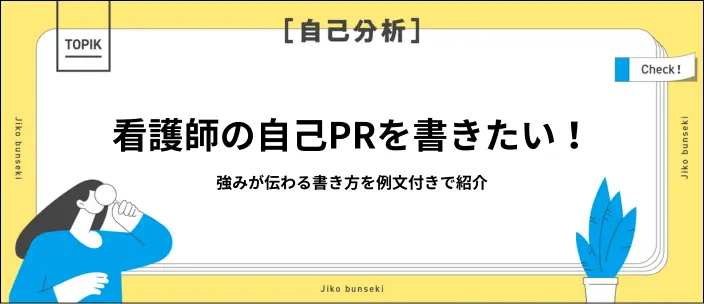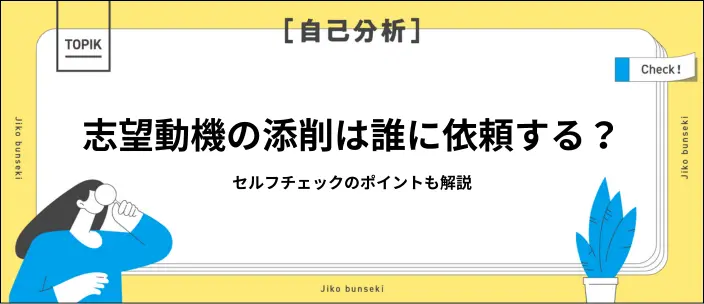このページのまとめ
- 企業はGDでコミュニケーション力・協調性・論理的思考力などを評価している
- GDのコツは課題の定義・結論から話す・脱線修正などを意識すること
- 司会・書記・タイムキーパーなど役割ごとの注意点を理解し適切に行動する
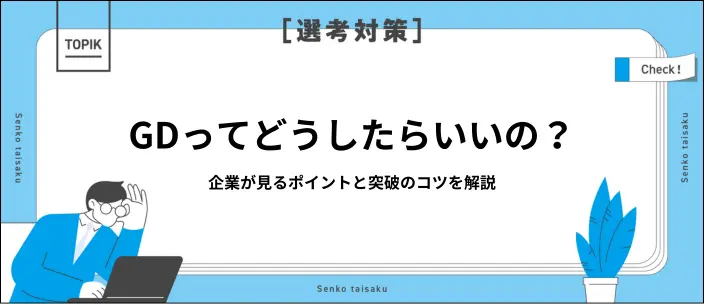
グループディスカッションのコツを知りたい就活生は多いでしょう。グループディスカッションは特別なスキルが必要なイメージがありますが、実はコツを押さえて準備すれば誰でも通過できる選考です。
この記事では、グループディスカッションの種類や企業が見ているポイント、発言のコツ、準備方法などを解説します。初めてのグループディスカッションでも自信を持って臨めるよう、しっかり対策していきましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- グループディスカッションは主に2種類ある
- 課題解決型
- 自由討論型
- グループディスカッションで企業が見ているポイント
- コミュニケーション能力
- 協調性
- 論理的思考力
- 発想力
- 積極性
- グループディスカッションの役割ごとの注意点
- 司会(進行役・リーダー)
- 書記
- タイムキーパー
- グループディスカッションのコツ(発言編)
- 課題を定義する
- 結論から述べる
- 大きな声で発言する
- 人の意見を補足する
- 議論が脱線したら一声掛ける
- グループディスカッションのコツ(コミュニケーション編)
- ほかの人の意見をまとめる
- 反対意見を一度受け止める
- 相手の話をよく聞く
- 発言していない人に発言を促す
- グループディスカッションに向けた準備のコツ
- 新聞やテレビでニュースをチェックする
- 動画を見て本番のイメージをつかむ
- キャリアセンターや民間サービスで練習する
- グループディスカッションのコツを知りたいあなたへ
グループディスカッションは主に2種類ある
就活のグループディスカッション(GD)は、5〜10人程度の学生が集まり、企業側が提示したテーマについて議論し、時間内に結論を出す選考形式です。
グループディスカッションは面接とは異なり、以下のようなスキルを見るために実施されます。
・協調性・コミュニケーション能力
・論理的思考力
・リーダーシップ・主体性
周りと協力しながら、自分の意見を伝えられるかが評価されるため、ただ話すだけではなく「議論の進行と結論に貢献する姿勢」が大切です。
グループディスカッションのテーマは大きく次の2つに分かれます。
課題解決型
課題解決型グループディスカッションとは、社会や企業が抱える具体的な課題に対し、グループで解決策を導き出す形式のグループディスカッションです。課題解決型では、論理的思考力や現実的な解決策を出す力、チームで協力する姿勢などが見られています。
実際の業務でも必要な「課題発見・課題解決力」があるかを評価するため、ただアイデアを出すだけでなく、実現可能性や具体性も求められるでしょう。
課題解決型では以下のようなテーマが頻出です。
・新規事業の売り上げを伸ばすには?
・若者の投票率をアップさせるには?
・女性の社会進出を後押しするには?
・男性の育休取得率を上げるには?
時事問題や社会課題、企業が抱える課題がテーマになることが多く、ニュースをチェックしておくことや業界研究などの対策をしておきましょう。課題解決型では、限られた時間の中でチームと協力し、現実的な結論をまとめる姿勢が選考通過のポイントとなります。
自由討論型
自由討論型グループディスカッションとは、正解のないテーマについて各自の意見を出し合い、グループとしての結論を導き出す選考形式です。論理的に自分の意見を伝える力や、相手の意見を聞く傾聴力、異なる価値観の中で結論をまとめる協調性などが求められます。
自由討論型は「自分の考えを分かりやすく言葉にする力(言語化能力)」が特に重視され、議論の流れを読みながら適切に意見を出す姿勢が評価されるでしょう。
自由討論型では以下のようなテーマがよく出題されます。
・学生と社会人の違いとは?
・仕事ではうさぎとかめ、どちらであるべき?
・社会人としての心構えとは?
・理想の上司に欠かせない条件
・就活を楽しくするには?
・代理母出産の是非
・安楽死の是非
価値観や倫理観が問われるテーマが多いため、自分の意見を持っておくことが大切です。自由討論型で意識したいのが、自分の意見をしっかり伝えつつ、他人の意見も取り入れながら議論を前に進めること。
また、相手の意見にただ同調するだけではなく、自分なりの理由を添えて賛成・反対の立場を示すことが通過のポイントになります。
グループディスカッションの基本的な概要を知りたい方は「GDとは何か?基本的な流れや種類ごとの特徴を知って本番に備えよう!」を、グループディスカッションの種類やテーマについてさらに詳しく知りたい方は「グループディスカッション対策をご紹介!テーマ別にポイントと対策を解説」をご参照ください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションで企業が見ているポイント
グループディスカッションは、単に意見を述べ合う場ではなく、企業が採用したい人材を見極めるための重要な選考ステップです。ここでは、グループディスカッションを通じて企業がどのようなポイントを評価しているのかを解説します。
コミュニケーション能力
グループディスカッションでは、ほかのメンバーと円滑に議論を進め、自分の意見を明確に伝えるコミュニケーション能力が評価のポイントです。
グループディスカッションでは発言内容の良し悪しだけでなく、チーム全体の雰囲気を良くし、話しやすい空気をつくる力が重視されます。社会に出てもミーティングで意見を述べたり、相手と協力したりしながら物事を進めたりする場面は多く、その素養を選考の中で見られているのです。
当日は、議論が始まる前の待機時間から積極的に周囲とコミュニケーションを取り、議論開始時には「よろしくお願いします」などのあいさつを自分から言い出すことが大切。誰かが話し始めるのを待つのではなく、自ら議論を切り出す姿勢が好印象につながります。また、話す際は結論から簡潔に伝えることを意識し、相手に伝わりやすい話し方を心がけましょう。
グループディスカッションで高評価を得るためには、自信がなくても最初のひと言を出す勇気を持つことが大切です。その小さな行動が場の空気を温め、議論が活発に進むきっかけとなります。
協調性
協調性とは、チームメンバーと協力しながら共通の目標に向けて議論を進める姿勢のことです。グループディスカッションは、自分の意見を言う場と思われがちですが、それだけではなく、ほかのメンバーの意見を尊重し、議論を前進させることが求められています。
協調性を発揮する場面は、ほかのメンバーの意見に賛同するときと、反論・修正をするときの2つ。賛同する場合は、「それ良いですね! さらに〇〇についても考えるとよさそうです」と具体的に肯定的なフィードバックを加えることで、相手も議論に前向きになれます。
一方で、反論や修正が必要な場合も必ずしも避ける必要はなく、建設的な議論のためには意見を述べましょう。ただし、頭ごなしに否定するのではなく、「確かに〇〇という考えもありますね。ただ、私は△△だと考えています」という形で相手の意見を尊重しつつ、自分の意見を述べることが大切です。
また、グループディスカッションでは発言が少なくなっているメンバーに意見を求めるなど周囲への気配りも評価されます。全員が参加できる雰囲気をつくることで議論が活発化し、グループ全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。
論理的思考力
論理的思考力とは、議題に対して一貫性のある解決策を提案し、議論を進める能力を指します。結論に至るまでの理由や根拠を明確に示せることが重要で、単なる感情論や思い込みではなく、客観的なデータや具体例を用いて説得力を高めることが求められるでしょう。
論理的思考力が評価される理由は、企業が業務で問題解決をする際に、筋道立てて考え説明できる人材を重視しているからです。グループディスカッションはその能力を測る絶好の場であり、結論だけでなくその過程も評価対象になります。
実際の発言では、「結論→根拠」の順で話すと聞き手に伝わりやすいです。たとえば「この方法が効果的だと思います。なぜなら、過去のデータで売上が〇%伸びた実績があるからです」と説明すると、相手も納得しやすくなります。
論理的思考力を磨くためには、普段からニュースや資料を読み、理由と結果をセットで考える習慣をつけることが効果的です。グループディスカッション本番では冷静に論点を整理し、わかりやすく説明することを心掛けましょう。
発想力
グループディスカッションにおいて発想力は、新しい視点やアイデアを提供し、議論を活性化させる重要な評価ポイントです。特に議論が行き詰まったときに斬新な提案ができると、ほかのメンバーや面接官に強い印象を残せます。
発想力が評価される理由は、企業が常に新しい課題に対して柔軟に対応し、イノベーションを生み出せる人材を求めているからです。グループディスカッションはそうした能力を見極める機会であり、単なる答えではなく独自の視点や工夫を加えることが期待されます。
ただし、アイデアを出し過ぎると議論が散漫になり、逆効果になる場合も。タイミングを見て適切な数のアイデアを出し、チームの流れを乱さないことが大切です。たとえば、議論が停滞しているときや、ほかの意見が出尽くしたあとに新しい視点を提案すると良いでしょう。
発想力は日々の学習や経験によって鍛えられます。ニュースを見たり、多様な分野に触れたりすることで、視野が広がり新しいアイデアを生み出しやすくなります。グループディスカッションでは焦らず、質の高いアイデアを適切なタイミングで提供することを意識しましょう。
積極性
グループディスカッションにおいて積極性とは、自ら進んで役割を引き受けたり、意見を積極的に発信する姿勢を指します。役割決めの際に誰も手を挙げなかったり、議論中に沈黙が続いたりすると、消極的な印象を与えてしまい選考通過が難しくなることもあるでしょう。
積極性が評価される理由は、社会人になっても会議やミーティングで主体的に意見を述べ、チームをリードできる人材が求められているからです。グループディスカッションはその素養を見極める場であり、行動力や意欲の高さを示す絶好の機会となります。
具体的には、役割決めでリーダーやタイムキーパーに進んで立候補したり、議論の場で自分の考えをしっかり発言したりすると良いでしょう。ただし、独りよがりにならず周囲の意見も尊重しながらバランス良く発言することがポイントです。過剰に前に出過ぎると逆効果になるため注意しましょう。
積極性は、場の空気を盛り上げ議論を活性化させるためにも大切な要素です。グループディスカッションで積極性をアピールしたいときは、適度に自分から話す機会を作り、チームの雰囲気を良くする行動を心掛けてください。そうすることで、採用担当者からの評価が高まります。
グループディスカッションの評価ポイントや注意点を詳しく知りたい方は「グルディスの通過率をあげるためのコツを紹介!基本的な流れや役割の解説も」もあわせて参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションの役割ごとの注意点
グループディスカッションでは役割を決めて議論を進めるやり方が一般的です。自分に合った役割につくと議論に貢献でき、グループディスカッションを有利に進められます。
一方で、苦手な役割は自分にとって負担になり、実力を発揮しきれません。役割につかなくても議論をサポートしたり積極的に発言したりすることで評価は得られるため、何の役割につくかは自分の得意・不得意を考えた上で判断しましょう。
ここでは役割ごとの注意点を解説していきます。
司会(進行役・リーダー)
司会は限られた時間の中でメンバーの意見を集め、議論を整理しながら結論を出していく役割。人の意見をしっかりと聞いた上で、欠けている視点を指摘したり、発言していない人に話をふったりして、議論が活性化するように働きかけます。ある程度意見が出たら、今までの意見をまとめて結論に導くのも司会に期待される役目です。
ただ、このとき、時間がないからといって多数決で無理やり意見をまとめようとしたり、チームの意見を無視して自分1人で結論を出そうとしたりしてはいけません。皆が納得できる形で結論が出せるように尽力しましょう。
書記
出された意見の要点を記録し、必要があればメンバーと共有するのが書記の役割です。書記が陥りがちなのが、メモに没頭して発言者の方を全く見ていない、記録をするだけでメンバーと共有しないというミス。
書記の役割についたら、全体の意見を把握している立場を活かして、意見の種類を分類したり、対立点を見つけたりしましょう。「発言するのが苦手だから書記になる」という人がいますが、書記だからといって発言しなくて良いわけではありません。メモをとる間をぬって、議論のプラスとなるような発言をするよう心がけてください。
タイムキーパー
グループディスカッションでは、「意見を出す時間」「意見をまとめる時間」「発表練習する時間」という風に、タイムスケジュールを立てて議論を進めることで、効率的に結論にたどり着けます。
タイムキーパーの役目は司会に経過時間を知らせ、進行を手助けすること。注意したいのは、タイムキーパーはただ時計を眺めるのではなく、どの工程にどれだけ時間がかかるか予測し、的確な時間配分をする必要があるという点です。
最初に考えた時間配分が予定どおりにいくとは限らないため、時間が足りなくなったら議論を急がせる必要も出てくるでしょう。タイムキーパーは、予定どおりにいかなくても焦ることなく、冷静に対処できる人に向いています。
グループディスカッションの役割と向いている人の特徴を詳しく知りたい方は「グループディスカッションの役割と向いている人の特徴は?評価されるコツも」もあわせてご覧ください。
以上がグループディスカッションの役割と注意点でした。もちろん人数によっては全員が役割に就くとは限りませんが、役割がなくても積極的に発言したり意見をまとめたりし、議論を活性化させましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションのコツ(発言編)
グループディスカッション中は、次のような点を意識して発言すると良いでしょう。
課題を定義する
たとえば「飲食店の売り上げを2倍にしなさい」というテーマがあったとして、いきなり議論に入るのは間違い。というのも、対象となるお店が駅前にあるのか、それとも地方郊外にあるかで、考えるべき対策が違ってくるからです。
グループディスカッションでは、議論に入る前に課題の条件を確認することが必要になります。前提条件を全員で確認すれば、議論の方向性がぶれず、具体的な案が出やすくなるでしょう。
前提確認の段階で積極的に発言すると「リーダーシップのある人」と評価されやすく、後の議論を引っ張っていきやすいメリットがあります。リーダーシップをアピールしたいのであれば、1番に話を切り出してはいかがでしょうか。
結論から述べる
意見を言うときは、結論から述べるのが鉄則です。「私は○○と考えます。理由は○○だからです」のように、結論を述べた後に具体的な理由を説明することで、簡潔で要点を得た発言ができます。就活中はグループディスカッションでも面接でも、結論から話し始めることを心がけましょう。
また、発言するときは自分が話す時間が長くなり過ぎないように注意が必要。ほかの人が発言する時間も考え、内容は簡潔にまとめてください。
大きな声で発言する
せっかく良いことを言っていても、企業の担当者の耳に入らなければ評価につながりません。発言するときはいつもより大きめの声で、はきはきと話すことを意識しましょう。
人の意見を補足する
アイデアがなかなか浮かばないからと何も発言しないでいると、議論に参加できないまま時間が過ぎてしまいます。自分から発信できる案がないときは、誰かの意見に対して、「そうしたら、○○ということも言えますよね」という形で、補足の発言をすることもできます。意見を出し合う段階ではアイデアは多いほど良いので、何かしらの案を出しましょう。
議論が脱線したら一声掛ける
議論を客観的に見られる人が「脱線していますよ」と声を掛けることで、議論を正しい方向へ戻すようにしましょう。グループディスカッションでは、議論が白熱するとテーマから脱線しやすくなるものです。話が盛り上がるのは良いことですが、肝心の議題から外れてしまうと、貴重な時間が無駄になってしまいます。
さらに「〇〇という点について話し合った方が良いのでは?」と具体的な戻るべきテーマを示すと、グループ全体がスムーズに結論に近づけるため、リーダーシップや全体把握力のアピールにもつながるでしょう。脱線をただ指摘するだけでなく、建設的に議論の軌道修正ができることが高評価を得るコツです。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションのコツ(コミュニケーション編)
グループディスカッション中の行動や態度を通して、コミュニケーション能力をアピールしましょう。グループディスカッションでは自分の意見を言うばかりではなく、周囲の人に配慮し、議論をサポートする動きが評価されます。
ほかの人の意見をまとめる
「AとBの意見を合わせて考えると、○○と言えますよね」という風に、複数の意見をまとめて議論を整理してみましょう。アイデアを出す段階であっても、その都度意見をまとめることで、議論の方向性を導くことができます。
グループディスカッションでは自分の意見を押し通すのではなく、皆の意見を聞いた上で結論を導くことが重要です。
反対意見を一度受け止める
たとえ自分と反対の意見が出ても、相手を真っ向から否定する発言をしてはいけません。グループディスカッションでは相手を尊重する協調性も重視されるポイントです。
反対意見に対しても、一度は「なるほど」と言って受け入れたり、代替案を提案したりすると良いでしょう。どんな意見に対しても感情的になることは避け、あくまで論理的に自分の考えを示すようにしてください。
相手の話をよく聞く
相手の意見に耳を傾け、必要があればメモをとりましょう。人の話を聞く姿勢は評価の対象となっている可能性がありますし、ほかの人にきちんと向き合うことで、自分が発言したときも真剣に話を聞いてもらえるようになります。
話を聞くときは、時々うなずいたり、相手の目を見たりすることで、「あなたの話に耳をかたむけていますよ」というメッセージを伝えられます。
発言していない人に発言を促す
発言していない人はいたら、「○○さんはどう思いますか?」と尋ねて発言を促しましょう。周囲に目を配り、全員が議論に参加できるよう配慮することで、コミュニケーション能力をアピールできます。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションに向けた準備のコツ
グループディスカッションは、ただ当日参加するだけでは十分に実力を発揮できません。事前の準備が合否を分ける大きなポイントです。ここでは、グループディスカッションに向けて効率よく準備を進めるためのコツを紹介します。
新聞やテレビでニュースをチェックする
グループディスカッションでは、時事問題に関連したテーマがよく出題されます。たとえば「SDGsに関する自社施策を提案せよ」といった議題があったとき、そもそもSDGsを知らなければ、具体的なアイデアを出すことは難しいでしょう。
そのため、日ごろから新聞やテレビで社会情勢、政治、経済などの最新情報をしっかりチェックしておくことが大切。ニュースのコメンテーターや新聞の社説などの意見も参考にして、自分なりの考えをまとめておくと、GDの場でも自然とアイデアが浮かびやすくなります。
準備段階で時事問題に強くなっておくことで、GD中に説得力のある発言ができ、周囲からの評価アップにつながるでしょう。
動画を見て本番のイメージをつかむ
グループディスカッションに初めて挑戦する人にとって、実際の雰囲気や流れが分からないと緊張してしまいがちです。動画を見ることで、発言のタイミングや伝え方、議論の進め方を具体的に学べるため、自分がどう動くべきかがわかりやすくなります。
具体的にイメージするために、動画サイトで「グループディスカッション」「GD 進め方」などのキーワードで検索してみましょう。また、大学のキャリアセンターや図書館で関連ビデオを借りられる場合もあるので、一度問い合わせてみるのもおすすめです。
事前に動画で学び、実際の場面を想像して準備することで、グループディスカッション本番で自信を持って発言できるようになります。
キャリアセンターや民間サービスで練習する
多くの大学のキャリアセンターでは、グループディスカッションの模擬練習を実施しています。本番さながらの環境で練習できるため、初心者でも安心して選考に臨めるようになるでしょう。
さらに、民間のオンラインサービスやグループワーク講座では、グループディスカッション対策の指導や模擬練習後の細かいフィードバックを受けられるものもあります。しっかりと準備を進めたい人は、こうしたサービスを活用してスキルアップを図るのもおすすめです。
実際に体験しながら学ぶことで、グループディスカッションの流れやマナー、発言のコツを身につけ、自信を持って本番に臨めるようになるでしょう。
「グループディスカッションの対策の仕方!形式別にコツを解説!」でも、グループディスカッションで良い印象を残すためのコツを紹介しているため、あわせて参考にしてください。また、「就活のやり方を徹底解説!基本的な進め方やスケジュールをご紹介」の記事では、就活全体のスケジュールについてまとめています。グループディスカッション対策をいつまでに終えればいいか、スケジュールの参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
グループディスカッションのコツを知りたいあなたへ
グループディスカッションでは「自分だけが高い評価をもらう」という気持ちではなく、全員で協力して合格する、という意識を持つと良い議論ができるのではないでしょうか。
選考対策に自信がないという人は、新卒支援のキャリアチケットにご相談ください。キャリアチケットでは専任のアドバイザーがカウンセリングを行い、就活の不安や希望をヒアリング。ご希望と適性に合った求人をご提案し、応募先が決まったら徹底した選考対策でサポートいたします。
ご紹介するのは実際に取材した企業の求人に限られるので、応募前に詳しい仕事内容や社内の雰囲気を知れるのがメリット。選考対策も企業に合わせて行うので、就活が不安な方はぜひ相談してください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら