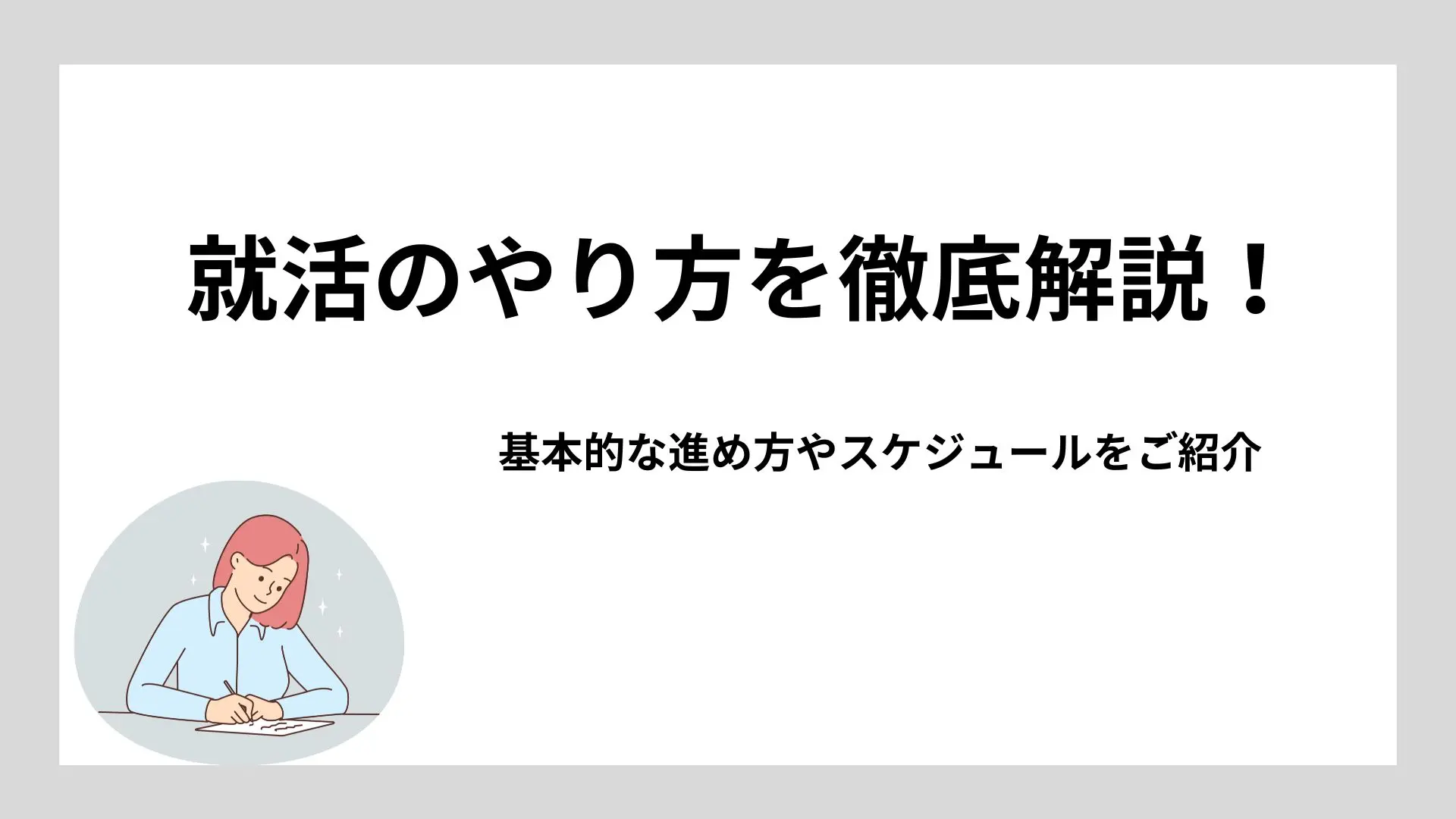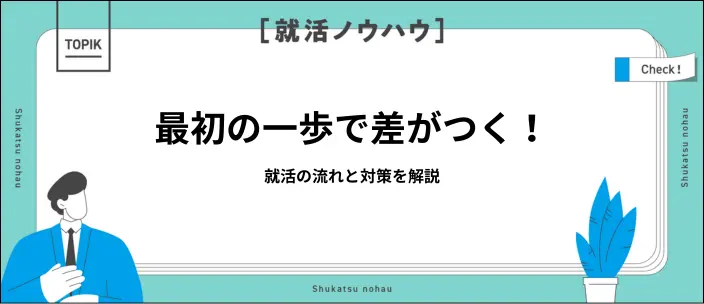このページのまとめ
- 就活をいつから始めるか迷う場合には大学3年生からがおすすめ
- 就活がいつからいつまで行うのかスケジュールの確認が大事
- 就活をいつから始めるか不安な場合は、今すぐに動き出すと安心できる

「就活はいつからいつまで実施するの?」「どのタイミングで始めれば良い?」と考える就活生も多いでしょう。就活は大学3年生の6月ごろからスタートする就活生が増えてきます。就活に向けた準備はさらに早くから始めることも。
この記事では、就活をいつから始めれば良いか、具体的に何をすれば良いかについて解説します。最後まで読めば就活を始めるタイミングがわかり、スタートダッシュを決められるはずです。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 就活はいつから始めた?アンケートをもとに時期を解説
- 26卒は大学2年生の3月までに始めている学生が多い
- 大学3年生の6月ごろから動き出す学生も多い
- 就活はいつからいつまで?基本的なスケジュールを解説
- 大学3年生の7月~3月:インターンシップへの参加
- 大学3年生の3月以降:合同説明会や企業説明会への参加
- 大学4年生の4月以降:エントリーシートや履歴書の提出
- 大学4年生の6月以降:筆記試験や面接などの選考開始
- 大学4年生の10月以降:内定の発表
- 企業別一般的な就活スケジュール
- 大手企業は経団連ルールをチェック
- 中小・ベンチャー企業は早めスタートも
- 外資系・マスコミはスタートが早い
- 就活がいつからいつまでかは人によって認識が異なる
- 就活のスタートに該当するタイミング
- 就活のゴールに該当するタイミング
- 就活を早めにスタートするメリット
- 自己分析や業界研究を深く行える
- 早期選考を実施している企業に応募できる
- インターンやキャリアイベントを経験できる
- 就活スタートが遅れたときのデメリット
- 準備が足りないと焦ってしまう
- 第一志望の選考時期を見逃すリスクがある
- ほかの学生に遅れをとる可能性がある
- 就活スタートまでに始められる準備
- 自己分析
- 業界研究
- 企業研究
- 職種研究
- オープンカンパニー
- OB・OG訪問
- ガクチカの準備
- 就活準備サイトへの登録
- Webテスト対策
- 書類選考対策
- 面接対策
- 就活を成功させるためのポイント
- 早めに就活を始める
- 目指す仕事に必要なスキルや資格を取得する
- インターンシップに参加する
- エントリー数を増やしチャレンジする
- 就活はいつからいつまで行えば良いか気になるあなたへ
- 就活のスケジュールに関するよくある質問
- Q.大学生の就活はいつからいつまで?
- Q.もうすぐ就活だけど何もしていないのはやばい?
- Q.大学3年生はいつから就活を始めれば良い?
就活はいつから始めた?アンケートをもとに時期を解説
就活をいつから始める学生が多いのか、実際のアンケートをもとに見てみましょう。
26卒は大学2年生の3月までに始めている学生が多い
キャリアチケットの「2026年入社予定学生の就活状況に関する調査」によると、大学2年生の3月までに始めている就活生が29.9%いました。
同調査によると、大学3年生の4月時点で就活情報を集め始めている学生が約72.9%。また、自己分析を始めている学生は51.6%、イベントやインターンシップに参加している学生が約29.9%います。
大学3年生の6月ごろから動き出す学生も多い
大学3年生の6月ごろから動き出す学生も増えてきます。大学3年生の夏にはインターンシップがはじまり、その準備が必要になるためです。
インターンシップに参加する企業を探すため、自己分析や企業研究を行う学生が増加します。また、インターンシップで選考を行う企業もあるため、履歴書やエントリーシート作成に乗り出す学生も増えてくる時期です。
大学3年生の参加が多いサマーインターンについては、「夏に行われるインターンシップ「サマーインターン」とは」の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活はいつからいつまで?基本的なスケジュールを解説
大学生の就活は、大学3年生の7月ごろから始まり、大学4年生の10月には内定式に参加して終えるのが一般的です。基本的な就活スケジュールを知り、どのように動くと良いのか把握しておきましょう。
大学3年生の7月~3月:インターンシップへの参加
大学3年生の7月ごろになると、サマーインターンが始まります。就活生は、この段階から就活を始める傾向があるので覚えておきましょう。
インターンシップは、秋のオータムインターン、冬のウィンターインターンなども開催されています。志望企業がどのタイミングでインターンシップを行っているか確認しておきましょう。
大学3年生の3月以降:合同説明会や企業説明会への参加
大学3年生の3月になると、合同説明会や企業説明会に参加するタイミングです。就活サイトも解禁され、プレエントリーも始まります。
合同説明会や企業説明会には積極的に参加し、興味のある業界や企業を増やしましょう。志望企業が決まるまでは合同説明会で多くの企業の話を聞くのがポイントです。
また、少しでも興味のある企業の個別説明会にも参加しましょう。説明会に参加しなければ、選考に参加できない企業もあるので注意してください。
合同説明会については、「合説ってどんなもの?参加するメリットと有益に過ごすコツ」で解説しています。
大学4年生の4月以降:エントリーシートや履歴書の提出
大学4年生の4月以降は、エントリーシートや履歴書を提出する期間です。企業によって提出のタイミングは違うので、必ず確認しておきましょう。経団連に加入していない企業の場合、4月よりも早い段階で提出を受け付けている場合があります。
エントリーシートや履歴書も選考に影響するため、対策を行うようにしましょう。セミナーに参加して、添削をしてもらうのもおすすめです。
エントリーシートの書き方については、「エントリーシートとは?履歴書の違いや基本を押さえて選考を突破しよう」で解説しています。
大学4年生の6月以降:筆記試験や面接などの選考開始
大学4年生の6月以降では、筆記試験や面接などの選考が開始されます。発言内容だけではなく、身だしなみやマナーなども注意しましょう。
選考では、1対1の面接以外にも、集団面接やグループディスカッションなどがあります。それぞれ対策方法が違うので、準備するようにしてください。
面接対策については、「就活の面接対策はどうする?よく聞かれる質問40選や選考突破のコツを解説」の記事で詳しく解説しています。
大学4年生の10月以降:内定の発表
大学4年生になると、内定の発表や内定式が行われます。それまでは、あくまでも内々定として扱われるので覚えておきましょう。
内定をもらったからと安心せず、「内定はもらったけれども卒業できない」とならないように、学業にも真剣に取り組むことが重要です。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
企業別一般的な就活スケジュール
新卒採用には基本的なスケジュールがありますが、企業によって実際の動きはさまざまです。ここでは、経団連に所属している場合、していない場合、外資系・マスコミなどの一般的なスケジュールを紹介します。
大手企業は経団連ルールをチェック
大手の日本企業は、経団連のルールに沿って就活スケジュールを決めています。このルールでは、大学3年生の3月に会社の情報が解禁されて、大学4年生の6月から本格的に選考が始まるのが基本です。
しかし、エントリーシート(ES)やWebテストの提出・実施時期は企業ごとに違います。なかには、情報解禁前から準備が始まっているところもあるので、早めに動き出すのがおすすめです。
中小・ベンチャー企業は早めスタートも
経団連に入っていない企業は、決まった就活ルールに縛られないため、大学3年生の2月ごろから選考をスタートするケースが多い傾向です。早い企業だと、3〜4月の時点で内定を出すことも。
こうした企業には、中小企業やベンチャー企業のほかに、IT系のメガベンチャーなども含まれています。会社の規模が大きかったり、名前をよく聞くような企業だったりしても、自分たちでスケジュールを決めていることがあるのです。
「まだ大丈夫」と油断せずに、興味のある企業があれば、早めに動いて情報をチェックしておきましょう。
外資系・マスコミはスタートが早い
外資系企業も、就活のスタートが早いのが特徴です。多くの企業が、大学3年生の10〜11月ごろから選考を始め、秋〜冬のインターンを通じてそのまま選考に入るケースもあります。なかには、11月以降に内定を出して、年内に選考を終える企業もあるため、スケジュールを知らないと「気づいたら募集が終わっていた…」ということも。
外資系を目指している人は、大学3年の前半からしっかり情報収集して、早めに準備を始めることがとても大切です。マスコミ業界でも、一部の企業は大学3年の12〜1月ごろに選考を行い、すぐに内定が出ることもあります。こちらもスケジュールが独自なので、行きたい企業がある場合は早めにチェックしておきましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活がいつからいつまでかは人によって認識が異なる
前述のとおり就活にはおおまかなスケジュールはありますが、明確に「いつから始まっていつに終わる」とは決まっていません。人によって、就活のスタート・ゴールの時期は認識が異なることも覚えておきましょう。
就活のスタートに該当するタイミング
就活のスタートとして捉えられるのは、以下のタイミングです。
・大学3年に進級したら
・インターンシップが始まったら
・情報が解禁されたら
・説明会に参加したら
大学3年になると同時に就活を意識する人もいれば、具体的な活動が始まってから就活のスタートと捉える人もいます。
就活のゴールに該当するタイミング
就活のゴールとして捉えられるのは、以下のタイミングです。
・内々定をもらったら
・内定をもらったら
・内定式を終えたら
就活のゴールは、「内定」が目安になります。ただし、内定の確約状態といえる内々定という人もいれば、労働契約を結ぶ内定、内定者が確定して一堂に会する内定式と、捉え方は人それぞれです。
なかには、内定式を終えても入社式までは就活は終わらない、と考える人もいるでしょう。多くの方が就活のゴールと捉える内定については、「就活における内定とは?獲得から入社までの流れや採用との違いを解説」で解説しています。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活を早めにスタートするメリット
早めに始めることで、自分が本当にやりたい仕事や向いている職種をじっくり考える時間が増えます。また、企業の早期選考にも参加するチャンスが広がるでしょう。インターンシップやキャリアイベントにも積極的に参加できるようになります。
ここでは、就活を早くから始めるメリットをより具体的に紹介。少しでも早く行動を始めることが、結果的により良い就職活動につながります。
自己分析や業界研究を深く行える
早めに就活を始めることで、じっくりと自己分析や業界研究に時間を掛けられ、納得のいく選択をするための準備が整います。
自己分析や業界研究は、簡単に終わるものではありません。「自分のことはよく知っている」と思っていても、実際に客観的に見るのは意外と難しいものです。また、業界はたくさんあるので、どの業界が自分に合っているのかを調べ、さらにそのなかから気になる企業を見つけて研究するとなると、時間が掛かります。
早くから始めておけば、急いで決めることなく、自分にピッタリの仕事や企業を見つけられるのが大きなポイントです。
早期選考を実施している企業に応募できる
最近の就活トレンドの一つが、「早期選考」です。就活が本格的に始まる3月1日より前に行われる選考のことで、企業が「優秀な学生を早く採用したい」と考えて実施しています。特に、外資系企業やコンサル、ベンチャー企業などでよく行われている方式です。
早期選考を受けると、第一志望の企業の選考を受ける前に面接に慣れることができ、その後の就活がぐっと楽になります。最初から内定を持っていることで、ほかの選考も焦らずに進められるので、心の余裕が生まれるでしょう。
インターンやキャリアイベントを経験できる
インターンやキャリアイベントに早めに参加すると、業界や企業のことをより深く知れるのがメリットです。
早い段階で「どの業界が自分に合っているのか」や「どんな職場環境が自分に向いているのか」を理解できます。実際に働いてみたときに「思っていたのと違った…」というミスマッチを減らし、効率的に就活を進められるでしょう。
また、インターンシップでは、参加者だけを対象にした早期選考を行う企業も。参加することで内定をもらえるチャンスも広がります。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活スタートが遅れたときのデメリット
就活は遅くに始めてしまうとさまざまなリスクが生まれます。
ここでは、就活スタートが遅れたときの具体的なデメリットを紹介。就活を遅くに始めることのデメリットをしっかり理解し、早めに行動を起こしましょう。
準備が足りないと焦ってしまう
就活を遅くに始めると、選考までの時間が足りなくなり、十分に準備ができなくなります。準備が不十分だと焦りが生まれ、自分の本来の力をうまく発揮できないかもしれません。
しっかり準備して、自分の強みを最大限にアピールしましょう。
第一志望の選考時期を見逃すリスクがある
就活解禁日(3月1日)は、経団連に加盟している企業にとってのスタート時期ですが、実際には企業によって選考のタイミングが異なります。経団連に属していない企業では、早くから選考を始めていることが多いので、遅れて就活を始めると「気づいたら第一志望の選考が終わっていた…」なんてことにもなりかねません。
自分が行きたい企業の選考スケジュールをチェックして、早めに動き出すことが大事です。
ほかの学生に遅れをとる可能性がある
就活に早くから取り組んでいた学生と、遅れて始めた学生では、いろいろな部分で差がついてしまいます。たとえば、自己分析や企業研究がしっかりできているかどうかでエントリーシートの質が変わり、それが合否に影響を与えることも。
早めに始めた学生は、選考を有利に進められる準備が整っています。早く始めることが、最終的な結果に大きく影響してくるのです。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活スタートまでに始められる準備
就活が本格的にスタートするまでに、自己分析や企業研究などの準備をしておきましょう。学年に関係なく実施できる準備を解説するので、参考にしてください。
自己分析
自己分析とは、自分の過去を振り返り、強みや考え方などを整理する作業です。履歴書やエントリーシート作成、面接対策などの基礎となるため、最初に実施しましょう。
自己分析はインターンシップ参加前までに行うのがおすすめです。インターンシップでも自己PRや志望動機が求められることが多く、自己分析で考えを整理しておくのが大事になります。
また、インターンシップでどの企業を選ぶかも、自己分析で知った自分の価値観や就活の軸に沿って考えることになるでしょう。自己分析をしていないと就活は動き出せないので、最初に取り組んでください。
自己分析の進め方については、「自己分析とは?就活におすすめの簡単なやり方10選や活用例を解説」の記事で解説しています。
業界研究
業界研究とは、世の中にどのような業界があるかを調べ、自分の志望業界を決める作業です。まずは興味のあるなしに関わらず、どのような業界があるかを知っておきましょう。
業界研究を行うメリットは、ミスマッチを防ぎやすくなる点です。自分の強みや特徴を活かせる業界を志望できるようになります。
企業研究
企業研究とは、志望企業の仕事内容や職種、方針などを調べる作業です。企業研究により、自分に合う企業を見つけられます。
また、企業研究は、評価される志望動機を作成するためにも欠かせません。同業他社との比較を行い、違いを志望動機に反映するのも、志望動機作成のコツになります。
職種研究
大学1〜2年生のうちから、気になる仕事や職種について調べておくのは大切です。まずは、「この仕事は何をするんだろう?」という視点で、仕事内容や求められるスキルを見てみましょう。
さらに、その職種で働いている人が、どんな経験を積んでキャリアアップしていくのか(=キャリアパス)を知ることで、自分がその仕事をしたときの未来の姿をイメージしやすくなります。
自分の得意なことや大切にしたいことと比べてみて、「自分に合いそうかな?」と考えてみましょう。早いうちから職種について理解を深めておくと、就活本番での業界研究や企業探しがスムーズに進みます。
オープンカンパニー
大学1年生、2年生の間は、オープンカンパニーに参加しましょう。オープンカンパニーは企業の説明を聞いたり、業務を体験できたりする機会です。
実際に企業で働く方の話を聞けば、企業や業界についての理解を深められます。また、実際に業務を体験することにより、自分に合う合わないを見極めやすくなるでしょう。
OB・OG訪問
OB・OG訪問を行い、志望企業で働く人の話も聞いてみましょう。会社説明会やオープンカンパニーよりもラフな雰囲気で質問できるメリットがあります。
会社説明会などの場合、ほかの就活生もいるため詳しく話を聞けない場合も。OB・OG訪問は一対一になりやすく、聞きたい質問を複数できる点もポイントです。
ガクチカの準備
ガクチカとは、「学生時代に頑張ったこと」を略した言葉です。エントリーシートや面接で聞かれることが多いので、答えられるように経験を積んでおきましょう。
ガクチカで話す内容には、以下のようなものがあります。
・学業
・サークル
・アルバイト
・ボランティア
・留学
一つでも力を入れているものがあれば、学んだことや困難を乗り越えた経験などをアピールできるでしょう。就活が本格化する前に、本気で取り組めることを見つけておくのも大事です。
就活準備サイトへの登録
大学1〜2年生のうちに、就活準備サイトに登録しておくと、業界や職種の情報、インターンやキャリアに関するニュースを早くからチェックできます。「まだ早いかも?」と思うかもしれませんが、企業や仕事について知るにはちょうど良いタイミングです。
たとえば、就活サイトによっては、大学1・2年生向けに作られていて、社会人のリアルな働き方や企業の取り組みを紹介する記事、自己分析に使えるツールなどが揃っています。自分の興味を広げたり、将来を考えたりするヒントが見つかるでしょう。
Webテスト対策
就活では、書類や面接だけでなく「Webテスト」と呼ばれる筆記試験もよく使われています。SPI、玉手箱、CAB、性格診断など、テストの種類は企業によってさまざまです。
これらのテストでは、言葉の理解力や計算力、性格の傾向などがチェックされます。「自分ってどんなタイプ?」「仕事に向いてる?」といった部分を見られるのです。
志望する業界や企業によって出されるテストが違うこともあるので、早めに調べておくのがポイント。苦手分野がある人は、少しずつ練習しておくと安心です。時間に余裕があるうちに対策を始めて、自信をつけておきましょう。
書類選考対策
多くの企業では、面接の前にエントリーシート(ES)や履歴書による「書類選考」が行われます。ここでは、「あなたがどんな人なのか」「どんな思いでその会社を目指しているのか」を、しっかりと言葉で伝えることが大切です。
主に、以下のような内容を記入することになるでしょう。
・自己PR
・志望動機
・学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)
就活の定番項目なので、自分の経験や考えをもとに、説得力のある内容にまとめることが重要です。自己分析で見つけた強みや、企業研究で知ったことを活かして、「自分らしさ」が伝わる文章を考えてみてください。早めに準備しておくと、実際の選考でも焦らず対応できます。
面接対策
面接は、企業が応募者を知る場であると同時に、自身も企業との相性を見極めるチャンスです。自分がどんな人なのか、どんな思いでその会社を目指しているのかを、しっかりと言葉で伝えられるように準備しておきましょう。
とはいえ、面接では緊張して頭が真っ白になってしまうこともよくあります。だからこそ、「企業が面接でどこを見ているのか?」を事前に知ることが大切です。よくある質問を想定して答えを考えておいたり、模擬面接をしてみたりすることで、自信を持って本番にのぞめるようになります。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活を成功させるためのポイント
就活を成功させるためには、早めに就活を始めたり、インターンシップに参加したりするのが大切です。ここでは、就活成功にむけたポイントを解説するので、参考にしてください。
早めに就活を始める
就活を成功させるためには、動き出しを早めにしましょう。インターンシップが始まる少し前の、大学3年生の5月から6月ごろには動き出すのをおすすめします。
企業が採用活動をスタートするのは、大学3年生の3月ごろです。しかし、そのタイミングで動き出すと、自己分析や業界分析の時間が足りず、ほかの就活生に遅れを取ってしまいます。就活を成功させるためには、早めに動き出し、自己分析や企業研究に時間を費やすのがポイントです。
目指す仕事に必要なスキルや資格を取得する
大学1〜2年生のうちから、将来やってみたい仕事や入りたい業界で必要とされるスキルや資格を調べて、今から少しずつ準備を始めるのがおすすめです。
たとえば、ITエンジニアを目指すなら、プログラミングを勉強したり、関連する資格を取得したりすると良いでしょう。営業職に興味があるなら、人前で話す力を伸ばすためにディベートやプレゼンの活動にチャレンジするのもおすすめです。
早いうちからスキルや資格を身につけておけば、就活のときに「自分にはこんな強みがあります!」と自信を持ってアピールできます。
インターンシップに参加する
インターンシップに参加し、企業理解を深めるようにしましょう。夏休みに開催される、サマーインターンへの参加がおすすめです。
インターンシップには、1週間から1ヶ月以上の長期のものもあれば、1日で終わる短期のものもあります。開催内容が違うため、目的に応じて参加を決めてください。インターンシップについては、「インターンシップとは?行う意味や期間別の特徴をご紹介」で詳しく解説しています。
エントリー数を増やしチャレンジする
就活を成功させるためには、エントリー数を増やし、チャレンジし続けるのが重要です。気になる企業には、積極的にエントリーしましょう。
就活では、エントリーシートの書き方や、面接に慣れるのが重要です。経験を積むには、エントリー数を増やし、数を重ねることが欠かせません。
エントリー数が少ないと、落ちてしまった場合の選択肢がなくなり、精神的に追い込まれてしまいます。慌ててエントリーした結果、準備不足で再度受からないケースも考えられるので、エントリー数を意識して就活を行いましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活はいつからいつまで行えば良いか気になるあなたへ
就活はいつから始まり、いつまで行えば良いか気になる人もいるでしょう。スタートするタイミングが遅れないか、ほかの就活生が就活を終えているのに自分だけ続けていないか、不安になるものです。
就活をいつから始めるかなど不安になる場合は、就職エージェントのキャリアチケットに相談してください。スタート時期の相談はもちろん、実際にどのように動けばよいかもサポートします。
キャリアチケットでは就活の進め方はもちろん、自己分析の指導や面接対策なども実施しているため、効率良く就活を進めて成功できるように、ぜひ登録してみましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活のスケジュールに関するよくある質問
就活のスケジュールに関するよくある質問に回答します。
Q.大学生の就活はいつからいつまで?
A.大学生の就活は、大学3年生の7月ごろに始まり、大学4年生の10月ごろまでに終えるケースが一般的です。基本的なスケジュールは、次のような流れになります。
・大学3年生の7月~3月:インターンシップへの参加
・大学3年生の3月以降:合同説明会や企業説明会への参加
・大学4年生の4月以降:エントリーシートや履歴書の提出
・大学4年生の6月以降:筆記試験や面接などの選考開始
・大学4年生の10月以降:内定の発表
ただし、自己分析や業界研究のように、時期に関係なく実施できる就活もあります。早めに動いても損はないので、前もって準備を進めておくと良いでしょう。
Q.もうすぐ就活だけど何もしていないのはやばい?
A.就活を直前に控えて何もしていない場合は、すぐに動き出しましょう。自己分析や企業研究など、必要な対策を行ってください。
これから就活を始める場合には、「就活は何から始める?時期別の対策・効率アップのコツを解説」を参考に進めましょう。
また、もうすぐ就活が始まる場合は、効率的に準備を進めるのが重要です。エージェントに相談し、進め方を教えてもらうようにしてください。キャリアチケットでも、就活のアドバイスを送っています。
Q.大学3年生はいつから就活を始めれば良い?
A.大学3年生の場合、5月・6月ごろに就活を始めるのがおすすめです。7月にはサマーインターンが始まるので、インターンに向けて準備をしておきましょう。
就活サイトが解禁される大学3年生の3月から始めた場合、周囲と比べて遅れてしまう恐れもあります。余裕をもって就活をできるように、早めの準備を心がけてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら