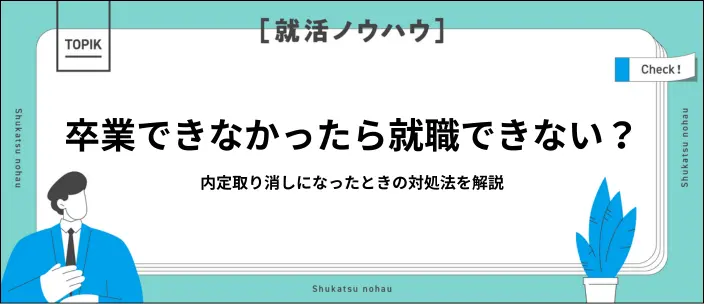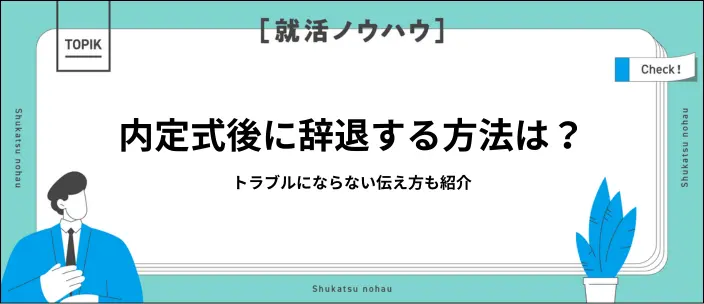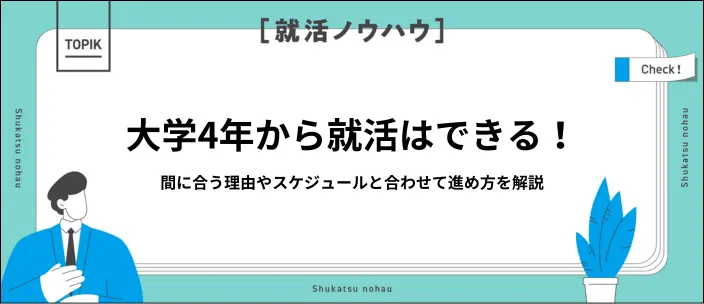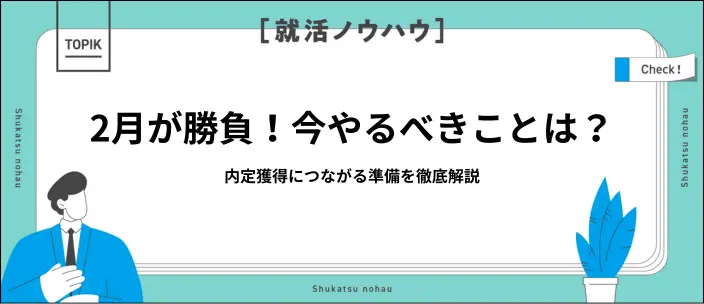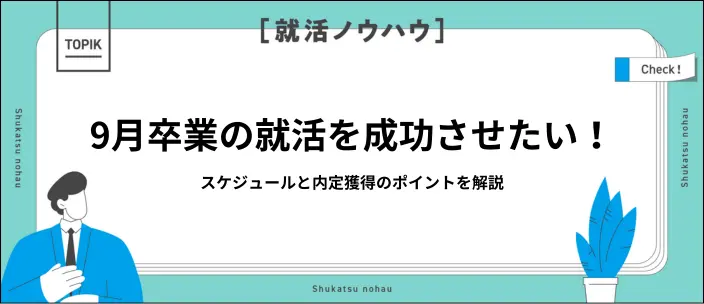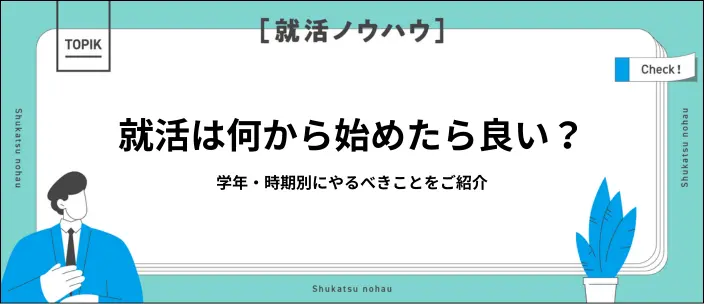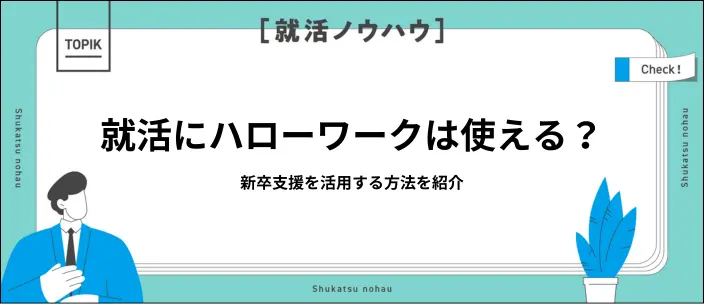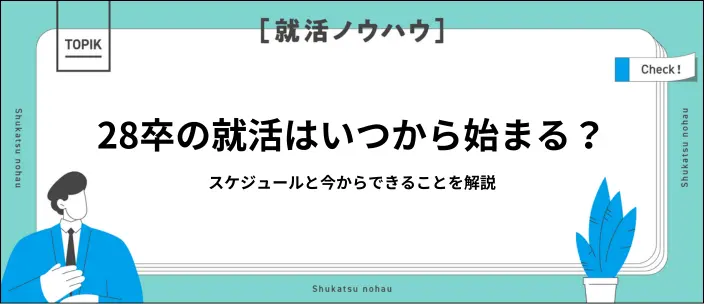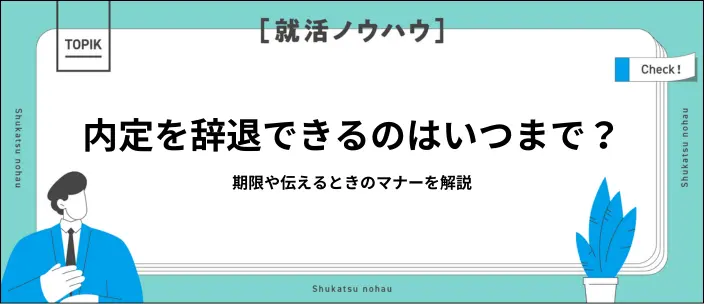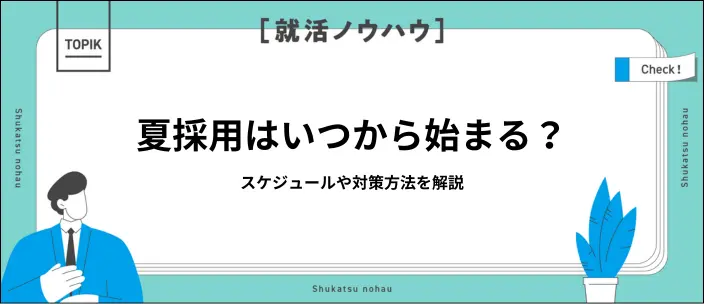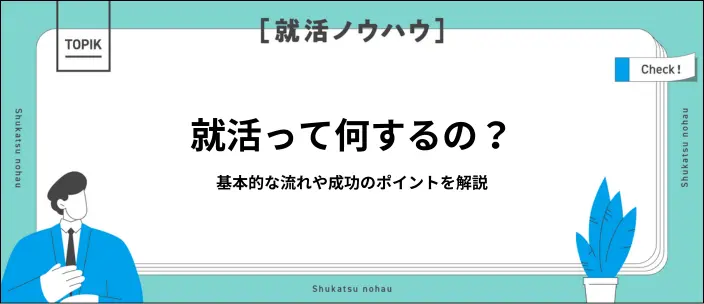このページのまとめ
- 「どこでも良いから内定が欲しい」という思いは企業に見抜かれやすい
- 内定が欲しいなら、就活の軸を明確にして企業研究や面接の練習をすることが大切
- 早期に内定が欲しい場合は、就職エージェントやスカウト型求人サイトの利用がおすすめ
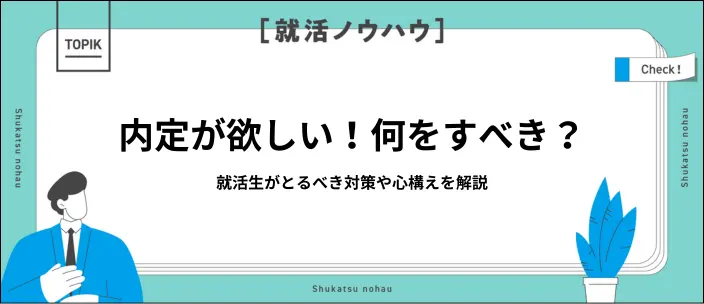
「内定が欲しいのにうまくいかない…」と悩んでいる就活生も多いようです。効率的に内定を獲得するには、これまでの選考の振り返りを行い、落ちた原因に合わせて対策をとる必要があるでしょう。
この記事では、内定がもらえない主な理由と対策方法、就活生がもつべき心構えについて解説します。また、おすすめの就活法や面接のポイントについてもまとめているので、ぜひ就活を効果的に進めるためにお役立てください。
就活のプロに無料で相談!内定獲得のコツを教えてもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 「どこでも良いから内定が欲しい感」を出すのはNG
- 「どこでも良い」は採用担当者に伝わる
- 焦らずに内定獲得を目指すことが大切
- 内定が欲しい人におすすめの就活方法9選
- 1.就職エージェントを利用する
- 2.学内のキャリアセンターに相談する
- 3.スカウト型求人サイトを活用する
- 4.選考直結型イベントに参加する
- 5.インターンシップに参加する
- 6.OB・OG訪問をする
- 7.推薦応募を利用する
- 8.人脈を活用する
- 9.リクルーター面談を狙う
- 内定が欲しいのにもらえない12の理由
- 1.就活の軸が定まっていない
- 2.自己分析ができていない
- 3.業界・企業研究が不十分
- 4.大手企業にこだわり過ぎている
- 5.エントリーシートの書き方が分かっていない
- 6.企業にアピールできる実績やスキルがない
- 7.自己PRに具体性がない
- 8.行動量が足りない
- 9.第一印象が良くない
- 10.面接に慣れていない
- 11.他責思考になっている
- 12.客観的視点が足りない
- 内定が欲しい就活生がやるべき対策15選
- 1.自己分析で就活の軸を明確にする
- 2.業界・企業研究に力を入れる
- 3.優良な中小企業にも目を向ける
- 4.募集人数が多い企業を狙う
- 5.秋・冬採用をしている企業を探す
- 6.選考回数の少ない企業を狙う
- 7.自分に適性がある企業かを見極める
- 8.適切な数の企業にエントリーする
- 9.エントリーシートに力を入れる
- 10.適性検査の対策をする
- 11.第一印象にこだわる
- 12.面接練習を繰り返す
- 13.選考の振り返りをする
- 14.志望動機や自己PRは都度見直す
- 15.第三者に客観的な意見をもらう
- 内定が欲しい方へキャリアアドバイザーのアドバイス
- 内定が欲しい就活生に必要な面接対策6選
- 1.結論から話し始める
- 2.大きな声でゆっくりと話す
- 3.質問の意図を理解して答える
- 4.回答を丸暗記しない
- 5.面接マナーを学んでおく
- 6.逆質問を効果的に使う
- 内定が欲しい就活生が大切にすべき心構え5選
- 1.自信をもてるまで努力する
- 2.周囲と自分を比べ過ぎない
- 3.相手の視点に立って考える習慣をもつ
- 4.リラックス時間を大切にする
- 5.就職以外の選択肢もあると考える
- 「内定が欲しい…」とお悩みのあなたへ
- 内定が欲しい方によくある疑問
- Q.就活で1社目で内定獲得は可能?
- Q.内定をもらえる気がしないです…
- Q.就活で内定欲しいオーラを出すのは良くない?
「どこでも良いから内定が欲しい感」を出すのはNG
就職活動で焦るあまり「どこでも良いから内定が欲しい」と思ってしまうことがあります。しかし、この考え方は内定獲得の妨げとなってしまいます。採用担当者は、自社を本当に志望している学生を見極めようとしているからです。内定獲得を目標にしてしまうと、就活の軸がぶれ、選考でもうまく自分をアピールできなくなってしまいます。
「どこでも良い」は採用担当者に伝わる
「どこでも良いから内定が欲しい」という気持ちは、企業の採用担当者に伝わってしまうものです。たとえば、「企業研究が表面的」「志望動機が具体性に欠けている」「質疑応答で会社の特徴を踏まえた回答ができない」といった様子から、すぐに見抜かれてしまいます。
採用担当者は長年の経験から、本気で自社を志望している学生とそうでない学生を見分ける目を持っています。焦りから生まれる投げやりな態度は、結果として内定獲得の機会を逃してしまう原因となるでしょう。
仮にバレずに内定を獲得したとしても、企業とのミスマッチを起こす可能性も高まります。自分には合わない企業であると入社後に気づき、結果として早期退職を選ぶ人もいるでしょう。
焦らずに内定獲得を目指すことが大切
内定獲得への近道は、焦らずに着実に準備を進めることです。自己分析を深め、自分の強みや価値観を明確にすることが重要。また、企業研究を徹底し、企業の特徴や強みを理解し、自分との相性を慎重に見極めることも欠かせません。
焦りを感じた時は、一度立ち止まって自分の就活状況を振り返ることをおすすめします。じっくりと準備を重ね、自信をもって面接に臨むことで、採用担当者にも熱意が伝わるはずです。
内定獲得までのステップについては、「就活とは何か?内定を得るために必要な準備とステップ」の記事で解説しています。ぜひチェックしてみてください。
就活のプロに無料で相談!内定獲得のコツを教えてもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
内定が欲しい人におすすめの就活方法9選
就活に決まった方法はありませんが、早めに内定をもらうために利用できる手段として、就職エージェントや大学のキャリアセンター、スカウト型求人サイトなどが挙げられます。ここでは、少しでも早く内定が欲しい方におすすめの就活方法を解説するので、ぜひご覧ください。
1.就職エージェントを利用する
早く内定を獲得したい方におすすめの就活法の一つとして、就職エージェントの利用があります。就職エージェントは、さまざまな観点から就活生をサポートしてくれるサービスです。自分の希望にマッチする企業の紹介を受けられるだけでなく、履歴書・エントリーシートの書き方や添削、面接練習など就職に役立つ支援を受けられます。
就職エージェントの多くは基本的には無料で利用できるため、新卒の就活生にとって活用するハードルが低い点も特徴です。就活のプロから的確なフィードバックをもらいながら選考を受ければ、早期の内定獲得を目指せるでしょう。
2.学内のキャリアセンターに相談する
新卒の就活生は、学内のキャリアセンターに相談するのもおすすめです。大学によっては企業から学校側に直接求人がきている場合もあり、自分で探すよりスムーズに選考を進められるケースもあります。
地域を限定して大学へ求人票を送る企業や、活躍している社員の出身大学へ求人票を送る企業もあり、キャリアセンターでしか得られない求人情報があるでしょう。利用している就活サイトに加えて、在学している大学だからこそ得られる限定的な求人も、ぜひチェックするようにしてください。
3.スカウト型求人サイトを活用する
少しでも早く内定が欲しい場合は、スカウト型求人サイトの利用もおすすめです。スカウト型求人サイトとは、企業側から選考のオファーが来る仕組みのサイトで、自分のプロフィールを登録することで利用できます。
企業側は就活生の経験や能力、価値観などを見てからオファーを出すため、自分と相性の良い企業に出会いやすいでしょう。効率的に内定をもらいたい方は、ぜひ登録してみてください。
4.選考直結型イベントに参加する
選考直結型イベントとは、複数の企業が参加して説明会を行い、その場で面接を受けられるイベントを指します。説明会と選考がセットになっているので、効率良く就活を進められるでしょう。
また、一度に複数企業の面接を受けられるのもメリットの一つです。面接の結果によっては、特別ルートでその先の選考に進める場合もあり、内定までの期間が比較的短く済みます。
5.インターンシップに参加する
早く内定が欲しい方は、積極的にインターンシップに参加するのもおすすめです。企業によっては、インターンシップに参加した優秀な学生に対して、優先的に選考を案内することもあります。
志望する業界や企業がインターンシップを実施している場合、積極的に参加すれば就活を有利に進められる可能性があるでしょう。
6.OB・OG訪問をする
OB・OG訪問は、単なる情報収集の場ではなく、場合によっては早期内定につながる貴重な機会です。OB・OG訪問をきっかけに、リクルーターをつけてもらえたり特別な選考ルートに進めたりする可能性があります。
リクルーター制度や社員による推薦制度がない場合でも、OB・OG訪問は効果的です。OB・OGから直接聞ける経験談やアドバイスは、内定獲得に向けて有益な情報になるでしょう。
OB・OG訪問をするメリットについては、「OGとOBの違いは?OB・OG訪問をするメリットとマナーを解説!」の記事にて解説しているので、こちらもあわせてご参照ください。
7.推薦応募を利用する
推薦応募とは、学校や研究室側に推薦状を用意してもらいエントリーする応募方法を指します。推薦応募は、書類選考や一次面接が免除されることも多く、自分で企業選びをしてエントリーする方法と比べて合格率が高いといったメリットがあります。
希望する業界や企業、職種に推薦枠があれば、積極的な利用をおすすめします。
8.人脈を活用する
大学や親族の人脈は、可能な範囲で活用しましょう。大学の教授や親族が人脈をもっている企業の場合、通常よりもスムーズに選考を進められる可能性があるためです。
就活で活かせる人脈を作るのは簡単ではないため、誰にでも利用できる方法ではありませんが、検討してみる価値はあります。
9.リクルーター面談を狙う
内定を早期に獲得する方法として、リクルーター面談を狙うことも考えられるでしょう。リクルーターとは、企業の窓口となる採用担当者以外の社員を指します。リクルーターとの面談で高評価を得られれば、選考で有利に働くこともあります。通常の面接よりもカジュアルな場ではあるものの、しっかりと対策をしておきましょう。
ただし、リクルーター面談は希望者全員が利用できる制度ではありません。企業からの連絡があって初めて利用できるので、説明会やOB・OG訪問など、リクルーター面談につながる機会を逃さないようにしましょう。
就活のプロに無料で相談!内定獲得のコツを教えてもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
内定が欲しいのにもらえない12の理由
内定が欲しいのにもらえない背景には、就活への準備や行動量の不足などが原因として考えられます。ここでは、内定がもらえないときによくある12の理由を紹介するので、自分が当てはまっていないか考えてみましょう。
1.就活の軸が定まっていない
内定がもらえない理由の一つとして、就活の軸が定まっていないことが挙げられます。就活の軸とは、志望業界や企業を選ぶうえで判断の基準になるものです。
就活の軸を定めれば、自分の適性に合う企業や希望条件とマッチする企業が見つけやすくなります。また、就活の軸に沿って選んだ企業には、自分の明確なビジョンや熱意を伝えられるので、選考もうまくいく可能性が高いでしょう。
一方で、就活の軸が定まっていないと、どのような基準で選考を受ける企業を選べば良いか分からず、熱意をもてないまま選考を受けることになってしまいます。面接でも、自分の思いをアピールできずに不採用になってしまうかもしれません。
2.自己分析ができていない
自己分析ができていない場合も、内定を獲得しにくくなります。自分の強みや考え方について整理ができておらず、アピール不足になりやすいためです。
たとえば、強みの理解が足りていないと、自己PRでうまくアピールできません。また、自分の考えが整理できていないと、志望動機をうまく伝えられないでしょう。
さらに、面接で深掘りされた際に、考えがまとまっていないので明確な答えが出てきません。書類選考でも面接でもアピール不足になりやすく、内定獲得につながりにくくなります。
3.業界・企業研究が不十分
内定が欲しくてもなかなか得られない場合は、業界・企業研究を十分にできていない可能性があります。内定が欲しいからといって、よく知らない企業にエントリーしても、「自社についてよく調べていないのでは」とマイナスイメージにつながりかねません。
選考には、就活生が「自社の仕事に適性があるか」を判断する目的があります。企業が求める人物像をしっかりと理解していなければ、内定にはつながりにくいでしょう。
4.大手企業にこだわり過ぎている
内定が欲しいのに獲得できない理由としては、「大手病」も挙げられます。大手病とは、大手企業への就職に執着している状態を示す造語です。
一般的に、人気の大手企業は倍率が高く、応募する就活生のレベルも高い傾向があります。そのため、大手企業だけにエントリーしていると内定獲得の確率は低くなりやすいでしょう。
大手病になる原因の一つは、自己分析や業界研究の不足です。「どのような仕事をしたいのか」「どのような職種が向いているのか」が不明確だと、「とりあえず大手企業なら良いだろう」と考えてネームバリューのある大手企業を選んでしまいます。
5.エントリーシートの書き方が分かっていない
エントリーシートの基本的な書き方を理解できていなければ、内定獲得にはつながりません。エントリーシートの提出は、大半の企業で求められるためです。
せっかく志望業界や企業で求められているスキルや強みをもっていても、エントリーシートでうまくアピールできなければ、採用担当者の目に留まりにくいでしょう。また、誤字脱字が多かったり、文章が読みにくかったりする場合も、「丁寧に準備しなかったのでは?」と判断されて選考に落とされてしまう可能性があります。
6.企業にアピールできる実績やスキルがない
企業にアピールできる実績やスキルがない点も、内定獲得がなかなかできない場合の特徴に挙げられます。採用担当者から、「これまでに何もしてこなかったのでは?」と思われれば、内定獲得は困難でしょう。
しかし、企業の担当者が納得するような実績やスキルをもっている就活生は少数です。新卒採用では就活生にポテンシャルを中心に評価しているため、自分が今後成長する可能性を示せれば内定に近づけるでしょう。
7.自己PRに具体性がない
自己PRに具体性がないと、説得力に欠けるとみなされて内定につながらない可能性が高まります。企業にとって、自己PRは学生が入社後に活躍できる人材かどうかを判断するための材料です。
たとえば、「コミュニケーション能力がある」のように抽象的な言葉では、具体性に欠けていて入社後の活躍をイメージできません。「初対面の人とも話せるコミュニケーション能力がある」「相手の話をじっくりと聞ける傾聴力がある」のように、どのようなコミュニケーション能力なのか具体的にすると評価につながりやすくなるでしょう。
8.行動量が足りない
就活準備やエントリー数などの行動量が足りない就活生は、内定が欲しくても獲得にはつながりにくいでしょう。行動しなければチャンスは狭まり、内定獲得の可能性を減らしてしまいます。
内閣府の「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書」によると、2024年度に卒業した新卒者のエントリーシートの提出数は、10社から19社が約26.9%で最も多い数値でした。

引用:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書(66p)」
平均よりもエントリーシートの提出数が少なく、かつ内定が獲得できていない場合は、まだ行動量が足りていない可能性があります。多くの企業の選考を受けるのは負担が大きいかもしれませんが、内定のためにできる限り提出量を増やす工夫をしてみましょう。
参照元
内閣府
学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査
9.第一印象が良くない
髪型や服装に清潔感がなかったり、表情や声が暗くネガティブな印象を与えたりするなどで第一印象が良くないと、内定をもらうのが難しくなります。面接の限られた時間で評価を得るためには、第一印象が重要です。
第一印象が良くない場合、面接中に挽回するには時間が足りず、何を話してもなかなか評価につながらない事態も考えられます。
面接では、短い時間で人柄や考え方を判断されます。そのため、自分の話し方や身だしなみが相手にどういった印象を与えるのかを意識しておく姿勢が大切です。
10.面接に慣れていない
書類選考を突破できても、面接に慣れていないために内定をもらえない人もいます。面接で自分を効果的にアピールするには、十分な面接対策が必要です。
面接対策が不十分だと、その場で答えを考えながら話さなくてはいけません。そうすると、伝えたい内容がまとまらなかったり、緊張してうまく言葉が出てこなかったりする可能性があります。また、面接では内容だけでなく、声のボリュームや話し方への配慮も必要です。うつむき加減でぼそぼそと喋っているようでは、声が聞き取りづらく自信がないと思われてしまうでしょう。
11.他責思考になっている
他責的な志向になっているために、内定を獲得できていない可能性もあるでしょう。他責思考とは、「うまくいかない原因は自分以外にある」と考える傾向を指します。
たとえば、面接で落ちた際に、「面接官の見る目がない」「面接官が緊張させるからうまく話せなかった」のような考え方をする場合があるでしょう。
他責思考のままだと自分の行動を反省できず、改善しないまま次の選考に臨むことになります。そのため、いつまでたっても成長がなく、内定獲得につながりません。
12.客観的視点が足りない
客観的な視点が足りないために、内定の獲得につながらない可能性もあります。就活は、多くの学生にとって初めての経験です。そのため、就活の振り返りをしていても具体的に何を改善すべきかが分からない場合もあるでしょう。
客観的な視点が不足している状態で1人で頑張り過ぎてしまうと、努力の方向性を見誤ってしまう恐れもあります。そうすると、努力してもなかなか内定がもらえない悪循環に陥りやすいので、注意が必要です。
内定を獲得できない理由については、「無い内定とは?負のループに陥る8つの原因と対策ポイント」の記事でも解説しています。こちらもあわせてご一読ください。
就活のプロに無料で相談!内定獲得のコツを教えてもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
内定が欲しい就活生がやるべき対策15選
内定が欲しい就活生は、自己分析や企業研究などの基本的な選考対策に取り組みつつ、内定獲得を目指しやすい企業を見極める必要があります。効率的に内定をもらうためには、やみくもに就活を進めるのではなく、ポイントを押さえて対策することが大切です。
ここでは、内定が欲しい就活生が実践すべき15の対策について解説します。
1.自己分析で就活の軸を明確にする
内定を獲得するためにまず大切なのが、自己分析を念入りに行う姿勢です。自己分析を徹底して行えば、自ずと就活の軸が明確になります。就活の軸を基準に企業選びをすれば、自分の価値観に合う企業を見つけやすくなるでしょう。企業と就活生の価値観が合えば、内定につながる可能性も高まります。
自己分析のやり方で行き詰まったときは、診断ツールやアプリを活用したり、就活仲間と他己分析をしたりするのもおすすめです。「就活の軸一覧100選!納得がいく決め方や面接での答え方を例文付きで解説」の記事も参考に、就活の軸を定めてみてください。
2.業界・企業研究に力を入れる
内定が欲しい場合は、これまで以上に業界・企業研究に力を入れる必要があります。業界や企業についての情報を取り入れ、知識を深めることで、これまで知らなかった企業や職種と出会える可能性もあるでしょう。
企業分析にあたって効果的なのが、OB・OG訪問やIRなどを活用した、企業における最新ニュースの把握です。OB・OG訪問では、表向きに発信されていないリアルの声を聞けます。また、企業が出す投資家や株主向けの企業情報であるIR(インベスター・リレーションズ)に目を通せば、詳細な企業情報を把握可能です。
しっかりとした業界・企業研究は、就職の選択肢を広げるだけでなく、内定への近道になるでしょう。業界・企業研究のやり方は、「業界研究のやり方は?効率的に進めるコツや行う目的を解説」も参考にしてみてください。
3.優良な中小企業にも目を向ける
これまでの就活で、有名企業や大手企業ばかり受けていた場合は、優良な中小企業にも選択肢を広げると良いでしょう。人気の大手企業と比べると倍率が下がるため、内定がもらいやすくなる可能性があります。
中小企業と聞いて、名前を知らない会社だからと敬遠してしまう方もいるかもしれません。しかし、日本経済の土台を担う中小企業の中には、世界でもトップのシェアを誇る優良な企業が多くあります。
企業選びに悩んだときは、経済産業省が公表している「グローバルニッチトップ企業100選」を参考にするのもおすすめです。日本の優良企業が分野別にリスト化されていて、大手企業だけでなく中小企業も名を連ねています。就活生には馴染みのない企業も多くあるので、内定が欲しいとお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
参照元
経済産業省
2020年版グローバルニッチトップ企業100選
4.募集人数が多い企業を狙う
募集人数が多い企業を狙うのも、内定を獲得するための方法の一つです。募集人数が多ければ、それだけ倍率は低くなります。
ただし、募集人数が多い理由がネガティブである可能性に注意が必要です。たとえば、従業員の離職率が高く、新たに多く採用しようとしている企業には、十分に気を付けなくてはいけません。一方で、業績が好調で事業拡大のために多くの人材を求めている場合は積極的に狙っていくと良いでしょう。
募集人数が多い企業に応募する際は、直近における事業展開や売上、利益などの情報を事前に確認してみてください。
5.秋・冬採用をしている企業を探す
就活でなかなか内定がもらえない場合は、秋・冬採用を実施している企業にも目を向けてみましょう。
厚生労働省の「令和7年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表します」によると、2024年10月時点で内定を獲得している2025卒学生の割合は72.9%です。その後、2025年4月時点では98.0%まで割合が高まっており、秋以降の採用でも内定獲得は可能であると判断できるでしょう。
近年では、大手企業のグループ会社やベンチャー企業、中小企業を中心に、夏以降も採用活動を実施しています。大手企業のグループ会社であれば、待遇や福利厚生の面でも大手企業に近い水準が保たれている企業もあるでしょう。待遇や福利厚生の面で大手企業に魅力を感じていた方は、秋・冬採用を実施しているグループ企業も視野に入れてみてください。
参照元
厚生労働省
令和7年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表します
6.選考回数の少ない企業を狙う
エントリー先を選ぶにあたって、選考回数の少ない企業を狙うのも一つの方法です。選考回数が少なければ、内定までに超えるべきハードルが少ないといえます。
選考回数は多い場合で5回以上、少ない場合では2回で終了するなど企業によってさまざまです。選考回数は企業の採用ページで確認できることが多いので、事前にチェックしてみましょう。
7.自分に適性がある企業かを見極める
内定が欲しい場合、自分に適性がある企業かどうかを見極めたうえで応募することも大切です。自分の強みやスキルと企業の求める人物像がマッチしている企業に応募するなら、選考でも高い評価を受けやすくなります。また、事前に自分と企業との相性が良いことが分かっていれば、自信をもってアピールでき、気持ちに余裕が生まれやすい点もメリットです。
8.適切な数の企業にエントリーする
内定が欲しい場合は、適切な数の企業にエントリーする必要があります。多くの企業に応募することで、内定獲得のチャンスを得やすくなりますが、あまりにエントリー数を増やし過ぎると、一社ごとの選考対策に割ける時間が少なくなってしまいます。そのため、自分が就活に割ける時間を考慮し、エントリー数のバランスを保つことが大切です。
公益社団法人全国求人情報協会の「2025年卒学生の就職活動の実態に関する調査」によると、2025年卒の大学生1人あたりの平均プレエントリー社数は14.8社でした。その内、本エントリーしたのは10.2社で、最終面接を受けたのは4.4社です。
また、内定(内々定)取得数は2.4社である点から、プレエントリーした企業のうち約7社に1社の割合で内定を獲得している計算になります。
参照元
公益社団法人全国求人情報協会
2025年卒学生の就職活動の実態に関する調査
9.エントリーシートに力を入れる
エントリーシートの作成も、内定が欲しいときに力を入れて行うべき対策の一つです。エントリーシートは、就活生が企業に対して最初にアプローチするポイントだといえます。分かりやすく具体的な内容のエントリーシートに仕上げれば、採用担当者に好印象を与えられるでしょう。
志望動機や自己PRなどの内容は、以下の構成を意識して作成してみてください。
・結論(Point)
・理由(Reason)
・具体例(Example)
・結論(Point)
上記は「PREP法」と呼ばれる、相手に伝わりやすい文章の基本です。この構成で文章を作成することで、採用担当者に伝えたいことを印象的に記述できるでしょう。
また、エントリーシートを作成する場合は、誤字脱字はもちろん字の丁寧さにもこだわる姿勢が大切です。内容をどれだけ磨き上げても、文字に丁寧さを感じられないと好印象につながらない可能性があります。
エントリーシート作成の基本については「エントリーシートとは?履歴書の違いや基本を押さえて選考を突破しよう」の記事でも紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
10.適性検査の対策をする
選考に通過して内定を獲得するためには、適性検査の対策もしておきましょう。最近では、選考プロセスの一環として適性検査を実施する企業も増えてきました。適性検査は、応募者の能力や性格特性の客観的な評価を主な目的としています。
適性検査の内容は、企業によって多種多様です。まずは、応募先企業がどのような種類の適性検査を実施しているか確認しましょう。一般的には、言語能力や論理思考力を評価する能力検査と、性格特性を分析する性格検査などがあります。
対策方法としては、参考書や問題集を活用して問題を繰り返し解くのがおすすめです。また、模擬テストを定期的に行ったり、苦手な分野に集中して取り組んだりすると効果的に対策できます。
適性検査の対策のやり方については、「就活の適性検査とは?検査の種類や特徴、受ける際のポイントをご紹介!」の記事も参考にしてみてください。
11.第一印象にこだわる
内定が欲しいなら、第一印象に意識を向けることも大切です。第一印象は、面接の結果にも影響を与えます。そのため、面接の基本マナーを押さえたり清潔感を意識したりして、第一印象を良くする必要があるでしょう。
採用担当者は服装や髪型の清潔感だけでなく、入室時の所作や面接中の姿勢、表情などもチェックしています。服装や身だしなみには常に気を配り、清潔感のある印象を与えられるようにしましょう。
12.面接練習を繰り返す
面接対策は、内定をもらうための重要なポイントです。面接の練習を何度も繰り返しておくと、本番での緊張が和らぎスムーズな受け答えができるようになります。
面接対策においては、就活のノウハウを参考に1人で鏡に向かって話をするのも一つの方法です。しかし、できれば相手がいる状態で練習するほうが効果的な対策ができるでしょう。
たとえば、友達同士で面接練習したあとにフィードバックを伝え合ったり、面接に特化した就活セミナーで模擬面接を受けたりするのも効果的です。
13.選考の振り返りをする
長期化する就活で内定をもらうためには、選考後の振り返りが大切です。自分では、「エントリーシートを完璧に仕上げた」「面接で受け答えができた」と思っていても、内定につながらないことも少なくありません。自分の感覚で振り返るのではなく、具体的なチェックを行ってみましょう。
たとえば、面接のあとには以下のような点に注目し、相手に伝わったかどうかを振り返ってみてください。
・どのような点が良かったか
・どういった質問に答えづらさを感じたか
・相手の反応はどうだったか
うまく相手に伝えられなかったと感じる部分があれば、文章の構成や言葉選び、エピソードなど、アプローチの方法を変えてブラッシュアップしてみましょう。
14.志望動機や自己PRは都度見直す
内定が欲しいなら、志望動機や自己PRは企業ごとに見直すことが大切です。就活では、一般的に1社だけでなく複数企業にエントリーします。そのため、就活を始めてから時間が経つにつれて、志望動機の内容が薄いものになったり他社と同じ内容を書いてしまったりすることも多いでしょう。
志望動機や自己PRは、自己分析と業界・企業研究を繰り返しながら、エントリー数を重ねるごとに完成度を高めていけると理想的です。完成度が上がるにつれて、採用担当者に熱意や意欲が伝わりやすくなり、内定につながる可能性を高められます。
15.第三者に客観的な意見をもらう
内定をもらうためには、家族や友人、大学のキャリアセンターの職員など、第三者の客観的な意見にも耳を傾ける必要があります。これは、書類選考にも面接対策にも有効な方法です。
たとえば、自分が書いたエントリーシートを第三者に見てもらえば、誰が読んでも伝わりやすい内容にブラッシュアップできるでしょう。面接対策も第三者と行うことで、自分では気づけなかった改善点を指摘してもらえる可能性があります。
内定が欲しいのにもらえず悩んでいる場合も、思い切って周りに意見を求めてみてください。内定がもらえない理由に気づけたり、就活を終えた友人から成功体験を聞けたりするので、内定をもらうための近道となるはずです。
就活のプロに無料で相談!内定獲得のコツを教えてもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
内定が欲しい方へキャリアアドバイザーのアドバイス
早く内定が欲しい人が、特に優先してやるべきポイントは、以下のとおりです。
・適性がある職種、業界を受ける
・インターンや早期選考などに参加する
・適性検査の対策をする
・面接対策をする
・周囲の人に相談をする
「適性のある職種や業界が分からない」「面接対策を手伝ってほしい」といった就活生は、就職エージェントのキャリアチケットの利用がおすすめです。キャリアアドバイザーが、内定獲得までマンツーマンでサポートいたします。
就活では、内定獲得後の流れを把握しておくことも大切です。「就活における内定とは?獲得から入社までの流れや採用との違いを解説」の記事で内定獲得から入社までにすべきことを解説しているので、ぜひご参照ください。
就活のプロに無料で相談!内定獲得のコツを教えてもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
内定が欲しい就活生に必要な面接対策6選
内定が欲しい就活生には、面接対策も欠かせません。大きな声でゆっくり話すことや、結論から話し始めることなど、面接で意識すべき点は多くあります。ここでは、面接を突破して内定を獲得するために必要な6つの対策を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
1.結論から話し始める
面接で質問をされたら、結論から伝えるように心掛けましょう。結論から伝えれば回答が明確になり、意図するとおりの内容を伝えられます。
結論ファーストは、企業や質問の種類を問わず共通して意識したい姿勢です。変な前置きを入れてしまうと、何について話したいのか分からず、効果的なアピールにつながりにくくなります。
2.大きな声でゆっくりと話す
面接での印象を良くするためには、大きな声でゆっくりと話すのもポイントです。堂々とした印象を与えやすく、自信のある話し方になります。小さい声は自信がなく、準備不足の印象を与えるでしょう。面接場所によっては部屋が広い場合もあり、声が小さいと何を話しているか聞こえない恐れもあります。
また、面接では緊張してしまい、早口になる就活生も多くいるようです。普段よりも意識してゆっくりと話すようにすると良いでしょう。
面接での話し方については「面接での話し方には重要マナーが!就活生なら知っておくべき好印象を与えるコツとは」で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。
3.質問の意図を理解して答える
面接を突破するには、質問の意図を理解するのも大切です。意図から外れた回答をしてしまうと、低評価につながってしまうので気をつけましょう。
たとえば、「学生時代に力を入れた経験を教えてください」と聞かれたら、学生時代に力を入れたエピソードと、その経験から学んだポイントを伝えます。企業が主に知りたいのは「経験から何を得たか」であり、「どのような活動をしていたか」ではありません。
「学生時代はサークルに力を入れていました」も回答にはなっていますが、質問の意図を理解できているわけではありません。「なぜこのような質問をするのか」「企業は何を知ろうとしているのか」を考えるのが、面接対策のコツです。
質問の意図を理解するために、面接でよく聞かれる質問をあらかじめ対策しておきましょう。
4.回答を丸暗記しない
面接で効果的に自分をアピールするため、履歴書やエントリーシートを丸暗記するのはNGです。書類と同じ内容を伝えても、追加のアピールにはなりません。また、丸暗記をして話してしまうと、内容を思い出そうとして棒読みになる恐れもあります。話し方が不自然になり、暗記した内容を話しているだけだとバレてしまうので注意しましょう。
面接で自然に回答するポイントは、要点だけを押さえて、面接ごとに話す文章を変えることです。面接官の反応を見ながら話せるようになれば、評価も上がり選考を通過しやすくなります。
5.面接マナーを学んでおく
事前に面接マナーを学んでおき、印象を良くする意識も大切です。入退室のマナーや敬語の使い方、言葉遣いなどに注意しましょう。
受け答えの内容が良くても、マナーが悪ければ社会人としてふさわしくないと思われ、評価が下がってしまいます。面接マナーを勉強している就活生は多く、マナーが守れていないと悪い意味で目立ってしまうので気をつけてください。
6.逆質問を効果的に使う
面接では、逆質問の時間を効果的に使うことも大切です。面接の最後に「何か質問はありますか?」と聞かれたら、企業に対する関心度や意欲をアピールするチャンスとして考えましょう。
企業の事業内容や社風、キャリアパスなど、事前に調べて疑問に思ったことや、入社後の自分の成長につながるような質問を用意してみてください。ただし、ホームページを見ればすぐに分かるような質問や、待遇に関する質問は避けるのがおすすめです。
これらの対策をしっかりと実践することで、面接に対する不安を軽減し、自信をもって臨むことができるでしょう。
就活のプロに無料で相談!内定獲得のコツを教えてもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
内定が欲しい就活生が大切にすべき心構え5選
就職活動を進めるうえでは、内定獲得につながりやすい考え方を身に付けると有利です。周囲と自分を比べ過ぎないことや、就活を離れてリラックスする時間を大切にすることなどを心掛けましょう。以下で、就活生が大切にすべき心構えを5つご紹介するので、1つずつチェックしてみてください。
1.自信をもてるまで努力する
就活で内定を得るためには、自信のある姿を見せるよう心掛けましょう。面接では、自信のない姿がマイナスイメージを与えます。
自信をもって選考に臨むためには、入念な準備が欠かせません。なかなか自信がもてない場合は、練習を何度も繰り返して選考に臨みましょう。自分にできる努力を続ければ、成長を感じ自信をもって面接に臨めるようになります。
2.周囲と自分を比べ過ぎない
就活を進めるにあたっては、周囲と自分を比べ過ぎない姿勢も重要です。周囲と自分を比較しても、状況が良くなる訳ではありません。特に、内定がなかなか出ない状態で周囲と自分を比べると、焦りにつながりやすいでしょう。
焦ったまま就活に臨めば、本来の実力を出し切れなくなります。精神的に追い詰められてしまえば、就活の続行自体が困難になるでしょう。
就活の目的は、自分に合った1社を見つけることです。他人より早く・多く内定を獲得することに大きな意味はありません。周囲と自分を比べるのではなく、現状で自分にできる行動は何かを常に考えましょう。
3.相手の視点に立って考える習慣をもつ
選考を突破するには、相手の視点に立って考える習慣作りも大切です。採用担当者が何を考えているのか分からなければ、効果的な対策を選択できません。どのような就活生を求めているのか、どのような返答が欲しいのかを常に考える姿勢をもちましょう。
企業は採用にて自社の成長に貢献してくれる人材や長期間安定して働ける人材を求めています。志望動機や自己PRを作成する際には、自分がどのようにして貢献できるのかを意識しましょう。
4.リラックス時間を大切にする
就活を上手に進めるには、選考について考えずリラックスできる時間も必要です。「内定が欲しい」と思っている場合、寝ても覚めても就活について考えてしまう方もいるでしょう。しかし、常に気持ちが張り詰めていると、精神的にもちません。
一時的にでもリラックスできれば、また気持ちを切り替えて就活に臨めるようになります。就活を前向きな姿勢で進めるために、以下のような息抜きを取り入れてみてください。
・休む日を決めて旅行の予定を入れる
・友人と食事に行く約束をする
・好きな香りの入浴剤を買ってゆっくりと湯船に浸かる
・1日就活を頑張った日は帰りにコンビニでスイーツを買う
就活に追われているときは、意識的に時間を取らないとリラックスできません。心にも身体にも余裕をもって就活を進めるために、自分なりにリラックスできる時間を作り出しましょう。
5.就職以外の選択肢もあると考える
「内定が欲しい」と必死に思いながら就活を頑張っていると、「内定がもらえないと終わり」だと思い、焦りや不安を感じてしまう可能性もあります。しかし、内定がもらえなくても就職以外の選択肢はあり、終わりなどでは決してありません。
内定を獲得できなくても、以下のような選択肢があります。
・大学院に進学する
・卒業後既卒として就活する
・フリーターやフリーランスになる
・留学する
・起業する
上記の選択をするには、明確な理由や目的が必要です。しかし、今内定がもらえず不安な就活生も、就職以外の選択肢を知れば、心に余裕をもって就活を進めていけるでしょう。
就職以外の選択肢については、「就活を辞めるとどうなる?迷ったときの判断基準や対処法を紹介」の記事でも紹介しているのでぜひご一読ください。
就活のプロに無料で相談!内定獲得のコツを教えてもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
「内定が欲しい…」とお悩みのあなたへ
「内定が欲しい…」と思って就活に取り組んでいても、思うような結果が得られず悩んでいる就活生も多いでしょう。内定をもらうためには、これまでの就活を振り返って分析し、内定を獲得できていない原因を明らかにする必要があります。また、原因に合わせて、適切な対策をとることも大切です。
しかし、「適切な対策や分析を自分だけで行うのは難しい…」と感じている就活生も多いでしょう。そんな方には、就職エージェントへの相談がおすすめです。
就活にお悩みの学生支援に特化した就職エージェントのキャリアチケットでは、経験豊富なキャリアアドバイザーが、あなたにピッタリの企業をご紹介します。企業の基本情報だけでなく、社風や職場の雰囲気、選考を受ける際のアドバイスなども提供しているので、効率的に就活を進めたい方におすすめです。
また、自己分析や業界・企業研究のサポート、書類添削、面接対策、スケジュール管理、内定後のフォローなどのサービスも充実しています。すべてのサービスを無料で受けられるので、まずはお気軽にキャリアチケットへお問い合わせください。
就活のプロに無料で相談!内定獲得のコツを教えてもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
内定が欲しい方によくある疑問
ここでは、「内定が欲しい」とお悩みの方が抱えがちな疑問にQ&A形式でお答えします。
Q.就活で1社目で内定獲得は可能?
A.はい、十分に可能です。しかし、そのためには徹底的な準備が不可欠です。
まず、自己分析で自分の強みや弱みを明確に把握し、次に企業研究で自分の価値観と企業の理念が合致するかを確認します。そして、企業の求める人物像を理解したうえで、自己PRや志望動機を効果的に伝える準備をしましょう。
早い段階での内定獲得は、運だけでなく、周到な準備と戦略によって左右されます。焦らず、着実に準備を進めることが成功への鍵です。
Q.内定をもらえる気がしないです…
A.悲観的になる前に、まずは原因を分析しましょう。書類選考で通過しない場合は、自己PRや志望動機の書き方を見直し、面接でうまくいかない場合は、話し方や回答内容を改善する必要があります。
また、内定の獲得には企業との相性も重要です。自分に合わない企業ばかりを受けている場合は、視野を広げてほかの業界や企業にも目を向けてみましょう。
「内定がもらえない原因は?8つの対策と就活を続けるマインドセットも紹介」の記事も参考にしつつ、就活の振り返りを行ってみてください。
Q.就活で内定欲しいオーラを出すのは良くない?
A.内定が欲しいという気持ちは自然ですが、それが前面に出過ぎると逆効果になることがあります。
内定が欲しいという気持ちが強過ぎると、企業への貢献意欲や熱意が伝わりにくくなり、自己中心的な印象を与えてしまう可能性があるでしょう。
面接では、内定が欲しいという気持ちを抑え、企業の求める人物像に合致していることをアピールすることが重要です。自分の強みや経験を具体的に伝え、企業に貢献できることを積極的にアピールしましょう。
就活のプロに無料で相談!内定獲得のコツを教えてもらう
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら