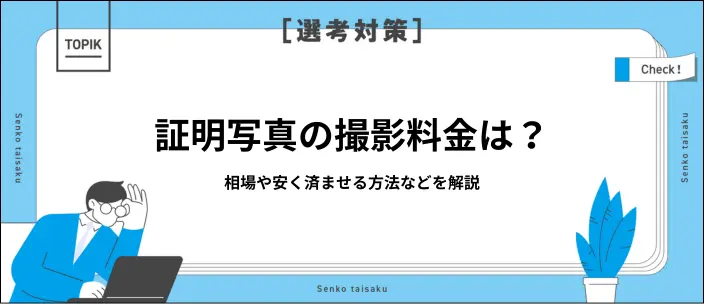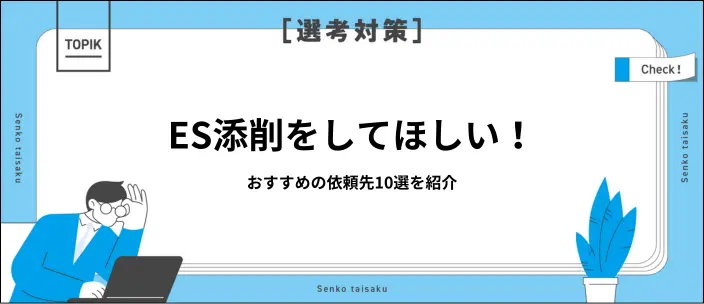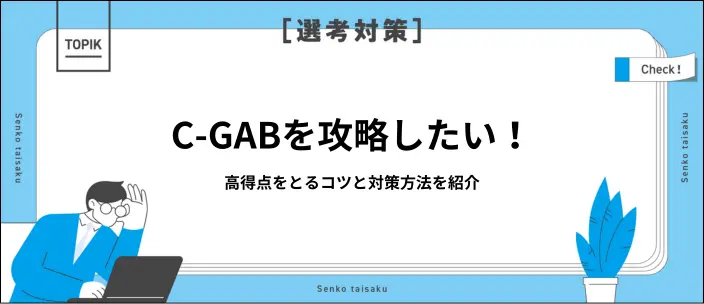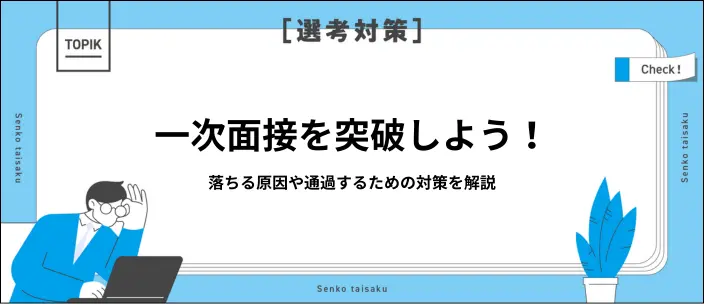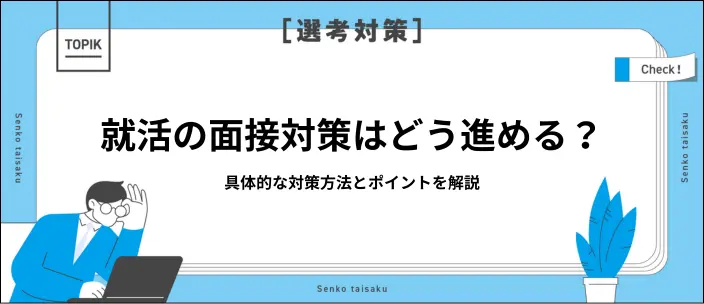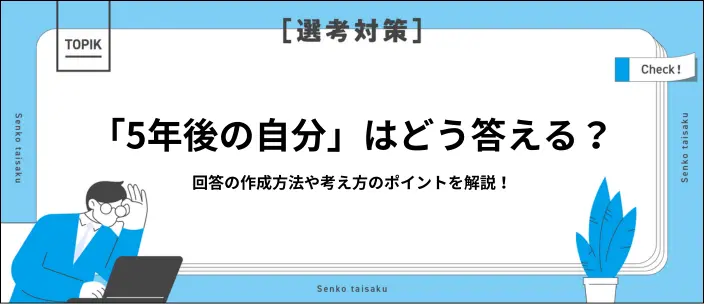このページのまとめ
- 就活で受ける企業数の平均は文系で約19社、理系で約12社
- 企業を多く受けると選択肢が広がるが、準備や管理の負担も増える
- 受ける企業を絞れば対策の質は高まるが、チャンスが減る可能性もある
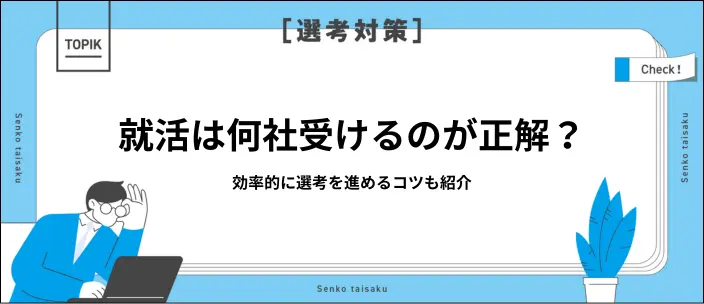
「就活って、何社くらい受ければ良いの?」これは多くの就活生が最初に感じる悩みでしょう。受け過ぎて疲れてしまわないか、逆に少な過ぎて内定がもらえないのではと、不安になるものです。
本記事では、文系・理系別の平均社数、企業を多く受けるメリット・デメリット、効率よく就活を進めるコツなどをわかりやすく解説します。自分に合った受ける社数を考えるためのヒントがきっと見つかるはずです。
かんたん1分!無料登録就活のエントリー数について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 就活では何社受ける?平均を解説
- 文系の平均エントリーは約19社
- 理系の平均エントリーは約12社
- 就活市場の動向にも注意が必要
- 就活で何社も受けるメリット
- 多くの企業から比較できる
- 持ち駒が多く気持ちに余裕ができる
- 選考経験を多く積める
- 就活で何社も受けるデメリット
- 1社ごとに使える時間が減る
- スケジュール管理が難しくなる
- 就活の軸がぶれやすくなる
- 就活で受ける企業を絞るメリット
- 自己分析・企業研究の質が上がる
- 焦らず冷静に判断ができる
- スケジュール管理がしやすくなる
- 就活で受ける企業を絞るデメリット
- 自分の選択肢を狭めてしまう
- ぶっつけ本番で選考を受けることになりやすい
- 持ち駒がなくなってしまうリスクがある
- 就活で何社も効率的に受けるためのポイント
- 選考の応募期間を確認しておく
- 志望企業の選考日程を確認しておく
- 志望企業に優先順位をつけておく
- 就活で何社受けるか迷ったときにおすすめの行動
- 改めて自己分析をしなおす
- 幅広い業界に視野を広げてみる
- 就活スケジュールを確認する
- インターンに参加してみる
- 合同企業説明会に参加しておく
- 就職エージェントに相談する
- 就活で何社も受ける際の注意点
- 自分に合う企業を選ぶ
- 量より質を重視する
- 内定獲得を目的にしない
- 就活で何社も選考を受けて落ちたときに考えるべきこと
- 自分に合った業界・企業を受けていたのか見直す
- 基本的なマナーを見直す
- 選考対策が十分だったか見直す
- 就活で何社受けるか迷っているあなたへ
就活では何社受ける?平均を解説
就活で受ける企業数は、10社以上のケースが一般的です。文系理系でも何社受けるかは変わってくるので確認しておきましょう。
文系の平均エントリーは約19社
公益社団法人全国求人情報協会の「2024年卒学生の就職活動の実態に関する調査」によると、文系の平均エントリーは約19社でした。その内約17社で企業説明会に参加し、約11.5社で書類選考を受けています。
理系の平均エントリーは約12社
同調査によると、理系の平均エントリー件数は約12社でした。その内約11社で企業説明会に参加し、約7社で書類選考を受けています。
文系と比べると、理系のほうがエントリー数の少ない状況です。理由として、教授推薦などの利用が予想できるでしょう。理系の学生がよく使う教授推薦については「教授推薦とは?理系就活で利用する際のメリット・デメリットを解説」の記事で解説しているので、参考にしてください。
就活市場の動向にも注意が必要
就活をする時期が売り手市場か買い手市場かによっても、エントリー数の平均は変わります。売り手市場とは、採用したい企業の需要に対して学生の数が少ないこと。つまり、学生にとっては就職に有利な状況です。
売り手市場では企業が人材確保のため、積極的に学生に内定を出します。このため、多くの企業にエントリーしなくても内定がとれる可能性が高まるため、平均エントリー数は下がる可能性があるのです。
一方、買い手市場とは、企業の需要に対して学生の数が多い市場のこと。企業は多くの学生の中から優秀な人材を選べますが、学生にとっては就職のハードルが上がる状況です。
買い手市場では優秀な学生は内定を得られる一方、スキルが未熟だったり強みが弱かったりする学生はなかなか内定を得られません。内定を得るために多くの企業の選考に参加するため、就活生の平均エントリー数は増えると考えられるでしょう。
参照元
公益社団法人全国求人情報協会
2024年卒学生の就職活動の実態に関する調査
かんたん1分!無料登録就活のエントリー数について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で何社も受けるメリット
就活で何社も受けることで、多くの選択肢から比較できるメリットがあります。何社も受けるメリットについて詳しく解説するので参考にしてください。
多くの企業から比較できる
就活で何社も受けることにより、多くの企業を比較して進路を選べます。比較することによって、「この条件は自分に合う」「この仕事は合わない」などのように、自分なりの基準ができるようになります。どのような企業がよいのか自分で明確に理解し、企業にエントリーできる点はメリットでしょう。
持ち駒が多く気持ちに余裕ができる
何社も受けることで持ち駒が多くなり、気持ちに余裕ができる点もメリットです。もし、選考に落ちてしまっても、「まだ選考中の企業がある」と安心できます。
選考に落ちて持ち駒が減ってくると「もう失敗できない」「落ちたらどうしよう」などと追い込まれて、実力を発揮しにくくなることも。
選考で実力を発揮するには、気持ちに余裕をもって臨むことも大切です。何社も受けておくことにより、焦らず就活と向き合えるでしょう。
就活で持ち駒がなくなるリスクについては、「就活の持ち駒がなくなったら?全滅する5つの原因や効果的な増やし方を解説」の記事を参考にしてください。
選考経験を多く積める
何社も受けることで、書類選考や面接などの経験を多く積めます。経験が増えれば増えるほど、学びも増えて対策しやすくなるでしょう。
たとえば、面接の場合、受ける回数が増えることで場の雰囲気に慣れるメリットがあります。エントリー数が少ないといきなり第一志望の面接に参加することになり、実力を発揮できないこともあるでしょう。
選考経験が増えるほど、「何がよかったのか」「何がよくなかったのか」を振り返って改善できます。選考を受けるにつれてよりよいアピールを行える点も、就活で何社も受けるメリットです。
かんたん1分!無料登録就活のエントリー数について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で何社も受けるデメリット
就活で何社も受ける場合、スケジュール管理が大変になるなどデメリットもあります。デメリットも把握して、何社受けるのか考えてみてください。
1社ごとに使える時間が減る
就活で何社も受けることにより、1社ごとに使える時間が減ってしまいます。複数企業の企業研究や選考対策を行おうとした結果、対策が不十分になるリスクがあるのです。
就活では企業ごとに選考対策をしないと、思うように評価されず内定にはつながりません。多く受けたにもかかわらず、選考には全く通過しない場合も出てくるでしょう。
受ける企業数が増えれば増えるほど、より効率的に対策を進める必要があります。企業研究の方法は「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
スケジュール管理が難しくなる
就活で受ける企業数が増えることで、スケジュール管理が難しくなります。説明会や選考の日程が被ってしまうこともあるでしょう。
また、エントリー数が増えることで、エントリーシートや履歴書の提出数も増加。必要書類を準備する時間や提出期限の管理が求められます。
スケジュール管理を問題なく行うためには、就活ノートを作るのがおすすめです。就活ノートの作り方を「就活ノートの作り方は?まとめたい内容やポイント・サイズも解説」の記事で解説しているので参考にしてください。
就活の軸がぶれやすくなる
就活で受ける会社の数が増えると、就活の軸がぶれやすくなります。たとえば、とにかくエントリーしようと考えると、業種や業界に関係なく企業を選んでしまう可能性も。その結果自分に合わない企業を選んでしまい、入社してから後悔することもあるでしょう。
就活で何社も受ける場合は、就活の軸に沿っているかを考えるのが大事です。業界も多く選ぶのではなく、自分なりの基準で選べているかどうか考えたうえで2つか3つ程度に絞り、エントリーしましょう。
かんたん1分!無料登録就活のエントリー数について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で受ける企業を絞るメリット
就活では、多くの企業にエントリーすると忙しくなりがちです。そのため、受ける企業を絞ることで、効率よく準備に時間を使えたり、自分の目標がはっきりしてモチベーションを保ちやすくなったりするメリットがあります。
ここでは、企業数を絞ることで得られる具体的なメリットを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
自己分析・企業研究の質が上がる
受ける企業を絞ることで、自己分析や企業研究に時間をかけられるという大きなメリットがあります。たとえば、20社に応募する場合は、すべての企業に対して深く調べるのは難しく、どうしても浅い理解のまま面接に臨んでしまいがちです。
しかし、受ける企業を5~10社に絞れば、それぞれの企業についてしっかり調べる時間が取れます。企業の特徴や社風、自分との相性などをじっくり見極められることで、「本当に自分に合う会社なのか?」という判断がしやすくなるでしょう。
また、企業研究が深まることでESや面接での発言に説得力が増し、「この学生はうちのことをよく理解している」と面接官からの評価も高まりやすくなるのもポイントです。
焦らず冷静に判断ができる
受ける企業を絞ることで、就活全体のスケジュールに余裕が生まれ、精神的にも落ち着いて選考に臨めるようになります。
多くの企業へ同時に応募してしまうと、選考が重なったり、ESや面接の締切に追われたりして、常に焦りが生まれてしまうでしょう。結果として、企業の違いを見極める余裕がなくなり、「とにかく受かれば良い」と本来の目的を見失ってしまうことも。
企業数をある程度絞っておくことで、1社ごとの情報を整理しながら冷静に判断できる時間と心の余裕が生まれます。また、早期に内定が出た場合でも、他社の選考と比較しながらじっくり進路を考えられるので、「勢いで決めて後悔した…」というリスクも減らせるでしょう。
焦らず冷静に、自分にとっての本当に行きたい企業を選ぶためにも、受ける社数を絞るのは有効な手段といえます。
スケジュール管理がしやすくなる
受ける企業数を絞ることで、スケジュール管理がしやすくなるというのも大きなメリットの一つです。就活中は説明会やエントリーシートの締切、面接など、短期間にさまざまな予定が重なりがち。あまりに多くの企業にエントリーしてしまうと、日程の調整に追われ、準備が中途半端になるリスクがあります。
しかし、企業を厳選すれば、予定が過密になりにくくなり、一つひとつの選考にしっかり向き合う余裕が生まれるでしょう。また、就活は単なる内定獲得がゴールではありません。自分を見つめなおし、成長するプロセスでもあります。
スケジュールに余裕があれば、選考のたびに振り返りができ、自己分析の深掘りや改善につなげる時間も確保できるでしょう。こうした計画的に進められる環境は、焦りや不安を減らし、結果的に納得のいく就活につながるのです。
かんたん1分!無料登録就活のエントリー数について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で受ける企業を絞るデメリット
受ける企業を絞ることには注意すべきデメリットもあります。選択肢が狭まったり、経験不足から本命企業の選考で緊張しやすくなったり、持ち駒がなくなるリスクもあるため、バランスを考えた計画が重要です。
ここでは、企業数を絞ることで起こり得る主なデメリットを詳しく紹介します。
自分の選択肢を狭めてしまう
受ける企業数を絞ることで起こりうるデメリットの一つが、自分の選択肢を狭めてしまうことです。
就活では、最初はあまり興味がなかった企業や業界に触れてみたことで、「意外と自分に合っている」と気づくケースも少なくありません。説明会や面接を通して初めて分かることも多く、視野を広げる機会として数を打つことには意味があります。
しかし、最初から選考数を絞り過ぎてしまうと、そういった発見のチャンスを逃してしまい、結果的に自分の可能性を狭めてしまうおそれがあるでしょう。
就活は単に内定をとることではなく、自分の価値観や適性を見直すプロセスでもあるのです。そのため、最初から厳しく絞り込み過ぎるのではなく、ある程度の幅を持たせたうえで、選考を進めながら徐々に絞っていくとよいでしょう。バランスよく企業を選ぶことで、より納得のいく就職活動につながります。
ぶっつけ本番で選考を受けることになりやすい
選考数を絞り過ぎると、第一志望の企業の選考をぶっつけ本番で受けることになりやすいというデメリットがあります。
就活では、エントリーシート(ES)、適性検査、グループディスカッション、面接など、企業によってさまざまな選考方法が用意されているため、これらの選考を事前に経験しておくことは、自信を持って本番に臨むために重要です。
たとえば、第一志望の企業の選考にグループディスカッションが含まれている場合、事前に経験がなければ進行の仕方や発言のタイミングに不安を感じることもあります。しかし、似たような選考をほかの企業で経験していれば、大まかな流れがわかり、冷静に対応できるようになるでしょう。
そのため、選考数をあまりにも絞り過ぎると、練習の機会が減り、本番での緊張や焦りにつながるリスクが高まります。志望度の高い企業に全力で臨むためにも、適度に選考経験を積みながら準備を進めるのがおすすめです。
持ち駒がなくなってしまうリスクがある
選考数を絞ることで、「持ち駒」がなくなってしまうリスクもあります。企業ごとにしっかり対策を立てられるのはメリットですが、採用倍率が高い企業が多いため、どれだけ準備をしても選考に落ちることは避けられません。
その結果、受ける企業が少ないと、選考に落ちたときに持ち駒が減ってしまい、「内定がもらえないかもしれない」という不安や焦りが増し、精神的な負担が大きくなることがあります。さらに、就活が進むと多くの企業が募集を締め切るため、持ち駒がゼロになった段階で新たに応募できる企業が限られてしまい、就活がさらに厳しくなるおそれがあるでしょう。
そのため、リスクを分散する意味でも、ある程度の数の企業にエントリーしておくことが大切です。持ち駒を適度に確保しつつ、計画的に就活を進めることを心がけましょう。
かんたん1分!無料登録就活のエントリー数について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で何社も効率的に受けるためのポイント
就活で複数の企業に効率よくエントリーし、選考を進めるためにはいくつか押さえておきたいポイントがあります。ここでは、企業ごとのエントリー期間の確認や選考日程の管理、志望度による企業の分類方法など、忙しい就活を無理なく進めるコツを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
選考の応募期間を確認しておく
企業によってエントリーの受付期間は異なります。3月に締め切る企業もあれば、6月まで受付可能なところもあるため、志望企業のエントリー期間は必ず事前に確認しましょう。
受付期間が後に設定されている企業は「まだ時間があるから」とエントリーを後回しにしがちですが、うっかり締め切りを過ぎてしまうことも。受けると決めた企業は、期間に関わらずその場でエントリーすることをおすすめします。
志望企業の選考日程を確認しておく
企業によって選考期間はさまざまです。早ければ夏までに採用活動を終える企業もあれば、冬ごろまで続ける企業もあります。特に人気企業は早期に採用を完了する傾向があるので注意が必要です。
また、エントリーはあくまで興味があるという意思表示であり、自動的に選考へ進めるわけではありません。エントリー後に提出するES(エントリーシート)や適性検査の受付期間が別に設けられていることが多いため、選考の締め切り日を必ずチェックしましょう。
「エントリーしたけどESの提出期限が過ぎていた」といった事態を避けるためにも、各企業の選考スケジュールをしっかり把握し、期限が近いものから優先的に対応することが大切です。
就活の全体スケジュールは、「就活のやり方を徹底解説!基本的な進め方やスケジュールをご紹介」の記事でご確認ください。
志望企業に優先順位をつけておく
エントリーする企業を志望度で事前に区分けしておくと、就活のスケジュール管理が楽になります。たとえば、第一志望群、第二志望群、第三志望群のようにグループ分けをしておくと、優先的に取り組むべき企業がはっきりするでしょう。
面接日やESの提出期限が重なることも多いので、すべての企業の選考を完璧にこなすのは難しい場合があります。そのようなとき、志望度による区分けがあれば「まずは第一志望群の選考を最優先に対策しよう」といった判断が素早くでき、時間を効率的に使えるでしょう。
かんたん1分!無料登録就活のエントリー数について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で何社受けるか迷ったときにおすすめの行動
就活でのエントリー数に悩んだら、自己分析を改めて行い自分の志望先について把握しましょう。ここでは、何社受けるか迷ったときの対策を紹介します。
改めて自己分析をしなおす
何社エントリーするべきか迷っている人は、「どの企業を受けるか」ではなく、「何社受けるか」で考えている可能性があるため、改めて自己分析をし直しましょう。
就活で大切なのは、企業数を数多く受けることではありません。自分に合う企業を見つけ、内定を獲得することです。
自己分析をしなおすことで「本当に志望したい企業はどこなのか」を見つめなおしましょう。受ける企業と受けない企業の選択基準を明確にすれば、何社受けるかも決まるはずです。
自己分析の進め方については、「自己分析とは?就活におすすめの簡単なやり方10選や活用例を解説」の記事で解説しているので参考にしてください。
幅広い業界に視野を広げてみる
エントリー数に迷っている人は、幅広い業界に視野を広げてみると良いでしょう。視野を広げることで、新しく興味のある業界や企業が見つかる可能性があります。
見つからなかった場合でも、現時点で興味のある業界や企業に対する納得感が増すので視野を広げることは大切です。
就活スケジュールを確認する
何社エントリーするか迷ったら、就活スケジュールを確認しましょう。就活は大まかに以下のスケジュールで進みます。
・大学3年生6月ごろ〜 インターン参加、業界研究、企業研究
・大学3年生3月ごろ〜 会社説明会参加、業界研究、企業研究、エントリー
・大学4年生6月 就活のピーク終了
スケジュールを考えることで、何社の選考を受ける時間があるかを考えられます。自分のキャパシティと相談し、エントリー数を決めてください。
インターンに参加してみる
就活の初期段階で企業のことを深く知るには、インターンに参加するのが有効です。インターンでは実際に働く体験ができるため、企業の雰囲気や仕事内容をリアルに感じられます。
大学1年生から3年生のうちに参加できるインターンも多く、特に長期インターンでは業務にじっくり関われることも。そうした経験は企業研究の大きな助けとなりますし、実際に「ここで働きたい」と感じたら、その企業へのエントリーを検討してみましょう。
合同企業説明会に参加しておく
就活で効率よく多くの企業情報を集めたいときに役立つのが合同企業説明会です。一度に多くの企業が集まるため、短時間で幅広い業界や企業をチェックできます。
合同企業説明会とは、一つの会場に多くの企業が集まって合同で開催される説明会のことです。通常の企業説明会は1社あたり半日ほどかけて行われますが、合同説明会では、1日に5~10社程度の説明をコンパクトに聞けるため、時間を効率的に使えます。
気になった企業にはチェックを入れておき、帰宅後にじっくり検討してエントリーするのがおすすめです。
就職エージェントに相談する
何社受けるか迷ったら、就活のプロである就職エージェントに相談しましょう。就職エージェントと話し合いながら進めることで、自分のペースを守って就活と向き合えます。
就活は初めての経験であり、「何社受ければ良いか」「どの程度の数の選考なら受けられるか」などはわからなくても当然です。困ったときは就職エージェントに教えてもらい、何社受けるかを考えてみましょう。
かんたん1分!無料登録就活のエントリー数について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で何社も受ける際の注意点
就活で何社も受ける場合には、質を重視して自分に合う企業を選びましょう。エントリー時の注意点を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
自分に合う企業を選ぶ
就活で受ける企業を選ぶ際には、自分に合う企業を選ぶことが大切。合わない企業を選んでしまうと、入社できてもミスマッチに悩まされてしまいます。
企業選びを始める前に、自分なりの譲れない基準を決めておきましょう。基準に合う企業が選べていれば、エントリー数が増えてもミスマッチを防ぎやすくなります。
どのように企業を選べばよいかわからず不安な方は、「失敗しない企業の選び方10選!あなたに合う企業選びのポイントを解説」の記事をぜひ読んでみてください。
量より質を重視する
何社も受ける場合でも、量より質を重視しましょう。やみくもにエントリー数を増やしても、内定をもらえるわけではありません。
企業は就活生を評価する際、「自社にマッチするか」の基準で選んでいます。自分の特徴や強みに合わない企業にエントリーしても、書類選考で落とされてしまうでしょう。
エントリーしても選考に通過しなければ、エントリーシートや履歴書の作成の時間、説明会参加の時間を使っただけになります。何社も受ける場合であっても、質を意識してエントリーを行ってください。
内定獲得を目的にしない
内定獲得を目的にすると、就活で失敗しやすくなります。ただ内定獲得だけを目指すと、「どの企業でも良いから内定がほしい」となってしまいがち。内定をもらってから後悔し、就活をやり直す就活生もいます。
就活はただ内定を獲得する時期ではなく、自分の将来を決める時期です。入社後の未来も見据えて就活を進めてください。
かんたん1分!無料登録就活のエントリー数について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で何社も選考を受けて落ちたときに考えるべきこと
「多くの企業を受けたけど内定が出ない…」という人は、以下のポイントを見直してみましょう。
自分に合った業界・企業を受けていたのか見直す
どの企業にも落ちてしまう人は、本当に自分に合った業界・企業を受けているのか見直しましょう。
企業は学生を採用するにあたって、自社との相性を重視しています。たとえ優秀な人材であっても、企業の社風との相性が悪かったり、仕事の適性がなかったりすれば、内定は得られません。
選考になかなか通らないときは、もう一度自己分析をやり直し、自分の適性を洗い出しましょう。
基本的なマナーを見直す
一次面接といった選考の初期段階で落ちている場合は、挨拶や身だしなみなどの基本的なマナーに問題がある可能性があります。
面接では限られた時間で評価が決まるので、第一印象が重要です。スーツの着こなしはもちろん、靴の汚れや髪型の清潔感、メイクの濃さにも気を配ってください。
また、はきはきとした声で話すこと、アイコンタクトをとることも忘れないように。着席するときは「本日はよろしくお願いいたします」、面接が終了したら「ありがとうございました」というなど、基本の挨拶ができているか振り返りましょう。
選考対策が十分だったか見直す
選考対策が不十分だと、何社受けても内定は得られません。これまでの選考を振り返り、改善点を探しましょう。たとえば、志望動機は、応募した企業だからこその理由になっているかが大切です。自己PRは強みに十分な裏づけがあるかを考えましょう。
面接の質問内容は企業によって異なりますが、定番の質問は決まっています。面接でよく聞かれる質問を「就活の面接で聞かれる質問集40選!答え方のポイントや回答例も解説」の記事で紹介しているので参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就活のエントリー数について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で何社受けるか迷っているあなたへ
就活で何社受ければよいかに、明確な正解はありません。そのため、何社受ければよいか、どの企業にエントリーすればよいか悩む方も多いでしょう。
就活への不安を解消するためには、就職エージェントへの相談がおすすめです。抱えている不安を解消し、前向きな気持ちで選考に臨めるようになりましょう。
就職エージェントのなかでもおすすめなのがキャリアチケット。マンツーマンでサポートを行うため、あなたの悩みや不安解消に向けてアドバイスができます。
また、あなたの希望や特性を見極め、ピッタリの企業の求人も紹介。ES添削や模擬面接など選考対策もしっかりサポートするので、就活をどうするか悩んだらぜひご相談ください。
かんたん1分!無料登録就活のエントリー数について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら