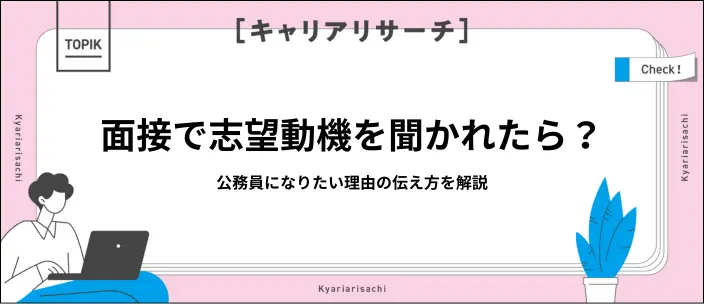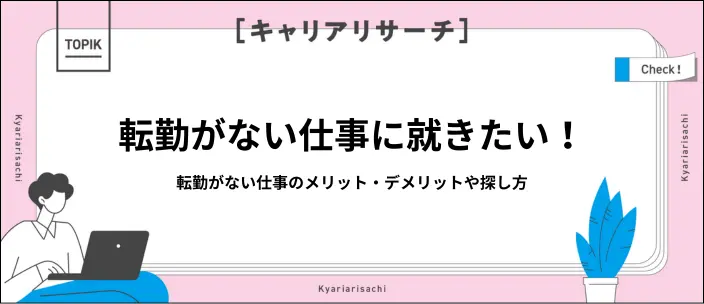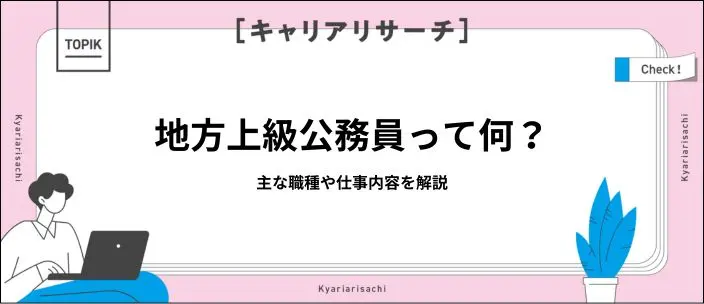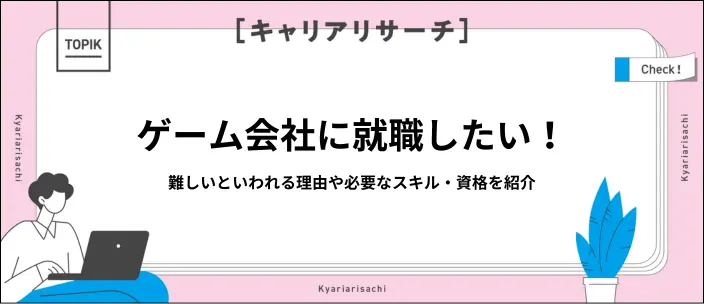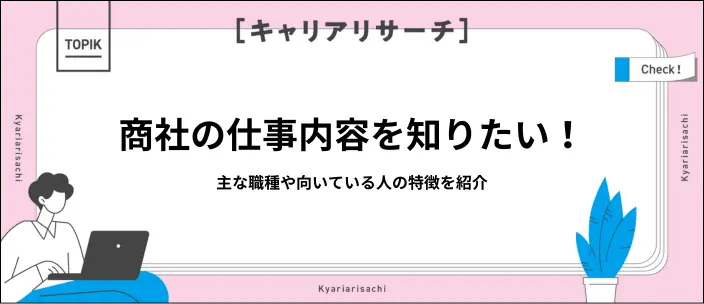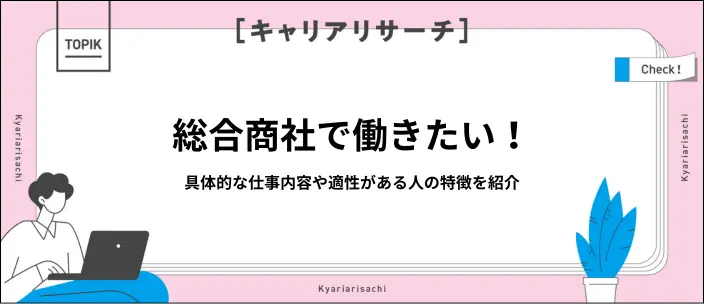このページのまとめ
- 海運業界とは物資や人の輸送を行う業界
- 海運業界には「物資輸送」「船舶の賃貸や売買」の2つの事業がある
- 海運業界は世界中で働くので英語力やコミュニケーション能力が求められる

「海運業界とはどういう業界?」「海運業界にはどのような仕事があるの?」などと気になる就活生もいるでしょう。海運業界は人や物資の輸送を行う業界であり、国内外問わず活躍できる仕事です。
この記事では、海運業界の概要や働くメリット、就職に向けてのポイントを解説します。最後まで読めば海運業界がどのような業界なのかを理解でき、業界を比較する際の役に立つはずです。
かんたん1分!無料登録業界研究について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
- 海運業界とは?ビジネスモデルを解説
- 物資や貨物の輸送
- 船舶の賃貸や売買
- 内航海運と外航海運
- 海運業界の職種と仕事内容
- 海上職
- 陸上職
- 海運業界の課題
- 世界情勢に左右されやすい
- 人手やコンテナが不足している
- 従業員の高齢化が進んでいる
- 経済安全保障の強化
- 脱炭素化の推進
- デジタル化への対応
- 海運業界で働くメリット
- グローバルに仕事ができる
- 携われるビジネスが大きい
- 人々の生活を支える仕事ができる
- 海運業界で求められるスキル
- 海技士のような専門知識
- 英語力
- 責任感
- リーダーシップ
- コミュニケーション能力
- 海運業界への就職に向けて必要な準備
- 海運業界の状況を理解する
- 企業ごとの違いを明確にしておく
- 英語などの語学力を身につける
- 海運業界の志望動機で伝えたい内容
- 海運業界を選んだ理由
- 海運業界のなかでも志望企業を選んだ理由
- 入社後にどのように貢献できるか
- 海運業界への就職を目指すあなたへ
海運業界とは?ビジネスモデルを解説
海運業界とは、物資や人の輸送を行う業界です。国土交通省の「外航海運の現状と課題」によると、日本の貿易量の99.6%を海運業界が占めており、日本の貿易になくてはならない業界になっています。
海運業界のビジネスモデルには、「物資や貨物の輸送」「船舶の賃貸や売買」の2種類があります。それぞれについて詳しく解説するので、海運業界がどのような業界かを学んでみましょう。
参照元
国土交通省
海事分科会 第38回(2020年5月22日)
物資や貨物の輸送
海運業界のメインになる事業が、物資や貨物の輸送です。船を使い、日本国内や海外に物資を運びます。日本国内での輸送は「内航海運」、海外での輸送は「外航海運」と呼ばれるので覚えておきましょう。
海運業界の輸送する物資や対応する企業は多岐にわたり、「食品」「アパレル」「エネルギー」「自動車」など、生活に必要なさまざまな製品が輸送の対象です。貿易や輸送を行う企業にとって、海運業界は欠かせない役割を果たしています。
船舶の賃貸や売買
輸送に必要な船舶の賃貸、売買も海運業界の事業です。船舶の所持数が大きいほど事業の規模が大きくなり、事業の競争力も高まります。
しかし、自社で所持できる船舶には限りがあり、船舶の扱いを考えなければならないことも。その場合に賃貸や売買を行い、船舶数を調整して対応しています。なかには、船舶のリースを行い、事業収入を得ている企業もあるので覚えておきましょう。
内航海運と外航海運
海運業界のビジネスは、「内航海運」と「外航海運」の2つに分類できます。内航海運とは、国内で海上輸送を行うこと。国土交通省によると「国内貨物輸送全体の約4割」を支えており、重要な輸送手段です。
外航海運とは、国外に向けて海外輸送を行うこと。資源エネルギーや食料などを外国と貿易する際に使用される方法です。一般社団法人日本船主協会によると、輸出入貨物の海上輸送率は99.6%。日本の生活を支えるうえで、欠かせない手段です。
海運業界についてさらに詳しく知るため、業界研究も行いましょう。業界研究の進め方については、「業界研究、おすすめの方法は?これから就活を始める人へ」の記事を参考にしてください。
参照元
国土交通省
第1回 航空燃料供給不足への対応に向けた官民タスクフォース
一般社団法人 日本船主協会
我が国海運の競争力強化に向けた課題と展望-次期海洋基本計画に求めるもの-
かんたん1分!無料登録業界研究について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
海運業界の職種と仕事内容
海運業界の職種には、大きくわけて「海上職」「陸上職」の2種類があります。それぞれの職種で、どのような仕事が行われているかを解説するので、海運業界を志望する場合は参考にしてください。
海上職
海上職とは、船の中で働く職種のことです。「船長」「航海士」「船員」などが該当します。
船長は、船の責任者として船の進路の決定権を持ち、ときには操縦も行います。
航海士は船の操縦を行う職種。商船の場合は通常3名が乗船しています。等級によって仕事がわかれており、1等航海士は荷物の積み下ろし、2等航海士はレーダーなどでの海図管理が担当です。また、3等航海士は救命設備の整備や、書類記録などを行います。
機関長は、船の機械設備を管理する職種。機関士の責任者を担当しており、船の機械設備の管理を行います。商船には3名の機関士が乗船し、「エンジンやプロペラなど船を動かす装置」「発電機」「ボイラー」「冷蔵庫」などを24時間管理しています。
なお、「船員」は航海士や機関士を支えるスタッフを指すケースが一般的。役割によって「甲板部員」「機関部員」「事務部員」の3つにわかれます。
甲板部員は、航海士の指示のもと舵取りを行ったり、荷物の積み下ろしをしたりするのが仕事です。機関部員機関士の指示に従って機関の整備を行います。また、事務部員は乗組員の食事を作ったり、乗客サービスを行ったりするのが役割です。
陸上職
陸上職は、陸から輸送などの事業を支える仕事です。「事務職」「技術職」「営業職」の3つに分かれます。
事務職は、航路の運営や運行管理を行う職種です。港の管理や情報システムの対応も仕事になります。技術職は、技術面で船を支える職種です。造船や船舶の保守を行います。営業職は、輸送する貨物を集めるためにメーカーへ営業をかける仕事です。取引先に対して、輸送プランの提案を行う場合もあります。
就活を成功させるには、自分に合う職種を見つけてエントリーすることも大事です。職種を比較し、どの職種が自分の強みを活かせるか考える時間を作りましょう。自分に合う職種の見つけ方は、「就活における職種の一覧とは?自分に合う仕事の見つけ方も紹介」の記事を参考にしてください。
かんたん1分!無料登録業界研究について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
海運業界の課題
海運業界を目指す就活生に向けて、業界の課題を解説します。
世界情勢に左右されやすい
海運業界は、世界情勢の影響を受けやすい業界です。
たとえば、業績が好調な時期に入社しても、不景気で数年後には業績が悪くなる場合があります。反対に、入社時の業績が悪くても、経済の状況で好転するかもしれません。海運業界への入社を考える際は、会社の業績だけではなく、世界経済についてもチェックしておくのが大切です。
人手やコンテナが不足している
海上輸送の需要が増していることから、人材不足やコンテナ不足が海運業界の課題になっています。しかし、人材はすぐに集まるものではありません。輸送に使うコンテナの積み下ろし業務が回らずに、輸送スケジュールに遅れが出ている企業もあります。
さらに、コンテナは世界中の船で共有しているため、人材がいてもコンテナが足りない場合も。人手不足とコンテナ不足の影響から運賃は高騰しており、事業への対応が求められている状況です。
従業員の高齢化が進んでいる
海運業界は、従業員の高齢化が課題になっています。国土交通省の「船員の現状等」によると、50歳以上の船員が46.4%。約半数を占めている状況です。

参考:国土交通省「船員の現状等」
30歳未満の若手船員も増えているものの、まだまだ高齢化への対策は必須。若手人員の確保が求められています。
業界についてより詳しく知るために、業界研究セミナーに参加するのもおすすめです。業界の情報はもちろん、企業の情報についても入手できる場合があります。業界研究セミナーについては、「業界研究セミナーとは?気になる内容と参加するメリットを解説!」の記事で紹介しているので参考にしてください。
参照元
国土交通省
第120回人口・社会統計部会
経済安全保障の強化
冒頭で述べた通り海運業界は貿易量の99.6%を担っており、経済面での対策が重要です。海運業界での問題がおきてしまうと、国民への生活や経済活動に大きな影響を与えてしまいます。
2022年には、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」が試行され、船舶の部品の安定確保が重要だと指定されました。また船舶の安定運行に関する技術が経済安全保障重要技術育成プログラムに選定されるなど、経済安全保障の強化が進んでいます。
脱炭素化の推進
環境を守るために、脱炭素化の推進も課題です。輸送を行う船は化石燃料を使って運行するケースが多く、二酸化炭素の排出が課題となっています。
日本は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出をゼロにしようとする動きです。日本の2021年度の二酸化炭素排出量は1億2,200万トンあり、そのうち運輸部門からの排出量は17.4%。カーボンニュートラルを進め、環境に配慮する動きも求められています。
参照元
環境省
2021年度(令和3年度)の温室効果ガス排出・吸収量(確報値)について
デジタル化への対応
人材不足に対応するため、デジタル化を進める企業もあります。デジタル化で作業負担を減らしたり、コンピューターで積み荷の積み方を効率化してより多く運んだりしようとする取り組みなどです。
データを活用して進路を効率化し、使用する燃料を少なくすることに成功した企業もあります。今後もデータを活用し、より効率的な事業を行うことが求められるでしょう。
かんたん1分!無料登録業界研究について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
海運業界で働くメリット
海運業界で働くメリットには、「グローバルな仕事ができる」「事業の規模が大きい」などがあります。ここでは、海運業界で働く3つのメリットを紹介するので、海運業界に興味がある方は参考にしてください。
グローバルに仕事ができる
日本国内だけではなく、海外も含めて仕事を行えるのは海運業界のメリットです。「グローバルに働きたい」「英語力を生かして仕事をしたい」などと考える就活生に向いているでしょう。
企業によっては輸出入だけではなく、海外拠点を持っている場合もあります。海外に住みながら働きたいと目標を持つ学生にもおすすめです。
携われるビジネスが大きい
事業の規模が大きい点も、海運業界で働くメリットです。扱う商材によっては、国単位の生活に影響する場合があります。
たとえば、エネルギー業界や電機業界は市場規模が大きく、ビジネスの規模も大きくなります。国民の生活に影響するケースも多く、やりがいを実感できるでしょう。
人々の生活を支える仕事ができる
人々の生活を支えられる点も、やりがいを感じられるポイントです。生活に欠かせない貨物を運ぶケースが多く、自分が社会に貢献できていると実感できます。
海運業界のニーズは高まっており、今後も継続して必要とされる業界です。長く働くためにも、人々の生活や社会を支えている実感は、仕事へのモチベーションになるでしょう。
自分が何に対してモチベーションを感じるかを比較して、企業選びにつなげるのもおすすめです。モチベーションを保てる仕事を選べば、仕事への満足度があがり、やりがいにもつながります。
自分のモチベーションを分析する方法は、「自己分析に役立つモチベーショングラフとは?作成のコツや活用方法を解説」の記事も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録業界研究について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
海運業界で求められるスキル
海運業界で働くためには、「英語力」「責任感」「コミュニケーション能力」などが求められます。ここでは、海運業界を目指す就活生が身につけておきたいスキルを5つ紹介するので参考にしてください。
海技士のような専門知識
海運業界で働くためには、専門知識が求められる場合もあります。たとえば、海上職で働く場合は、「海技士免許」が必要なため、海技士免許に合格できるレベルの「海」「船」「気象」についての知識が求められます。
ただし、以前は海技士免許をとるために専門学校に通うパターンが一般的でしたが、現在では自社で海技士免許取得まで教育を行う企業もあります。未経験の大卒でも問題ないので安心してください。
船員や陸上職の場合は、資格がなくても採用されますが、海や船などの知識は所持しておいた方がいいでしょう。
英語力
海外の人とやり取りする場合があるので、英語力が重要です。正確にコミュニケーションがとれる程度の英語力があれば、評価につながるでしょう。
日常会話よりも、船にまつわる専門用語などビジネス英語が必要になる点には注意してください。TOEICなど英語力をアピールできる資格を獲得するのもよいでしょう。
責任感
海運業界は船の上で働く場合が多いため、少数でも仕事をやり遂げる責任感が重要です。また、長期間船に乗り込んだままになるので、1つの仕事を最後までやり遂げる責任感も重要になるでしょう。
責任感をアピールする就活生は多いので、差別化を意識するのがポイント。責任感をアピールする際は、「自己PRで責任感の強さをアピールするときのポイントを例文とともにご紹介」の記事も参考にしてください。
リーダーシップ
海上職では同じ船に乗る乗組員たちをサポートし、業務を遂行する力やリーダーシップが求められます。リーダーシップは船内に関わらず、どのような仕事でも活かしやすい強みです。リーダーや部長などグループをまとめた経験があれば、アピールするとよいでしょう。
就活で評価されるリーダーシップについては、「自己PRでリーダーシップを伝えるには?アピールのコツや例文を紹介」の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
コミュニケーション能力
荷物のやり取りをスムーズにするために、コミュニケーション能力が求められます。日本国内だけではなく、海外でのやり取りも行えるようになるとよいでしょう。
また、海上職は船の上にいる時間が長く、電話やメールでしかコミュニケーションが取れない場合もあります。直接のコミュニケーションではなくても、問題なくやり取りができるスキルも必要になるでしょう。
コミュニケーション能力のアピールについては「自己PRでコミュニケーション能力を伝える方法は?具体化のポイントを解説」の記事も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録業界研究について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
海運業界への就職に向けて必要な準備
海運業界への就職を目指す場合、業界研究や企業研究などの準備が大切です。どのような準備をしておくと就職活動を有利に進められるか解説するので参考にしてください。
海運業界の状況を理解する
業界研究を行い、海運業界がどのような状況なのかを知っておきましょう。海運業界は社会情勢に左右されることが多く、前年と現在でも状況が変わっている場合があるからです。
たとえば、燃料費が高騰することで、会社の業績に影響することもあります。また、世界各国の環境への取り組み方が変わり、運行に影響が出る場合もあるでしょう。業界の最新情報を知っておけば、グループディスカッションのテーマになったり、面接で質問されたりしても落ちついて対応できます。
企業ごとの違いを明確にしておく
海運業界に属する企業ごとに、どのような違いがあるのかを調べておきましょう。同じ海運業界でも取り組んでいる内容や企業方針などに違いがあるためです。
また、就活では「なぜ他社ではなく自社なのですか」と聞かれる場合もあります。会社ごとの違いを理解しておかないと、自分なりの考えを回答できないでしょう。
企業研究を行えば企業の違いを理解し、「なぜその会社がよいのか」を明確にできます。企業研究の進め方については、「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事で解説しているので参考にしてください。
英語などの語学力を身につける
海運業界はグローバルに働く可能性があるため、語学力を身につけておくのがおすすめです。英語をはじめとする語学力があれば、活躍できる幅が広がるでしょう。
英語力をアピールしたい場合は、TOEICの受験がおすすめです。業務で英語をあまり使わない場合は600点以上、業務で英語を使う場合は800点以上を目安にするとよいでしょう。就活でTOEICをアピールする場合の目安については、「TOEICは就職活動で評価される?アピールの目安点数や勉強法を解説」の記事で紹介しているので参考にしてください。
かんたん1分!無料登録業界研究について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
海運業界の志望動機で伝えたい内容
海運業界の志望動機では、「なぜ海運業界なのか」「なぜ志望企業なのか」「入社後に貢献できるか」の3つを伝えることが大切です。海運業界の志望動機で伝えたい内容と伝え方について解説するので参考にしてください。
海運業界を選んだ理由
海運業界の志望動機では、まず「なぜ海運業界を選んだのか」を伝えましょう。数々の業界があるなかで、なぜ海運業界なのかを明確に整理してください。
特に、陸運業界や航空業界など、同じように荷物を運ぶ業界と比較し、違いを整理しておくことが大切です。「私が海運業界を志望するのは△△だからです」のように、最初に伝えておきましょう。「業界分析とは?目的や正しい方法を解説!」の記事を参考に業界分析を行うのもおすすめです。
海運業界のなかでも志望企業を選んだ理由
海運業界のなかでも、なぜ志望企業なのか伝えることも大切です。企業同士を比較し、違いを明確にしておきましょう。
企業は志望動機から、「なぜ自社がよいのか」を見極めようとしています。海運業界であればどの企業でもあてはまる内容だと、「企業比較ができていない」「志望度が低そう」などと思われるかもしれません。
海運業界は事業内容が似る傾向にあるため、企業の特色や違いを自分なりに整理しておくことが大切です。ほかの企業では実現できないことがあり、志望企業を選んだことを伝えましょう。
入社後にどのように貢献できるか
もし、自分が入社できた場合、会社に対してどのように貢献できるかも志望動機で伝えます。入社への熱意や意欲だけでは、内定につながるアピールはできません。
就活で企業が求めているのは、自社で活躍し、成果を出せる人材です。「入社したい」「頑張りたい」のような熱意だけでは、活躍できるとは限らないでしょう。
志望動機では企業の業務内容を調べ、自分の強みがどのように活かせるかをアピールしてください。評価される志望動機作成に向けては、「志望動機の書き方のコツを例文付きで解説!企業に響くポイントを押さえよう」の記事を読んでおくのがおすすめです。
かんたん1分!無料登録業界研究について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら
海運業界への就職を目指すあなたへ
海運業界は社会的にニーズが高まっている業界です。生活に欠かせないため、今後も必要とされるでしょう。国内外でのコミュニケーションが必要になるため、コミュニケーションスキルはもちろん、英語力も求められます。
海運業界への就職を目指す際には、業界の特徴をとらえ、必要とされる能力を自己PRするのが大切です。ほかの就活生よりもアピールできるように、就活のプロにアドバイスをもらってみましょう。
就職エージェントのキャリアチケットでは、内定業界を目指す就活生のサポートを行っています。面接対策やエントリーシート対策はお任せください。
また、これから就活に取り組む就活生や、もう一度準備をやり直したい就活生は自己分析から一緒に始めてみましょう。キャリアチケットが就活スタートから内定獲得までサポートするので、自信をもって就活に取り組んでください。
かんたん1分!無料登録業界研究について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!26卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。