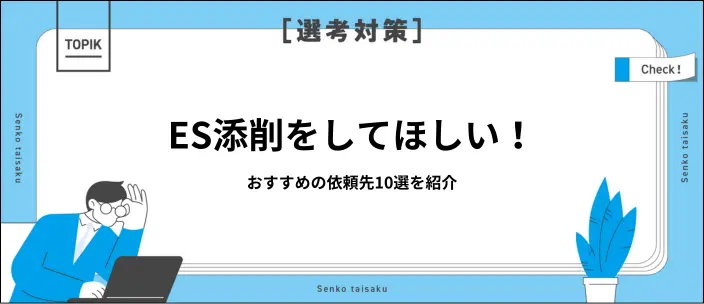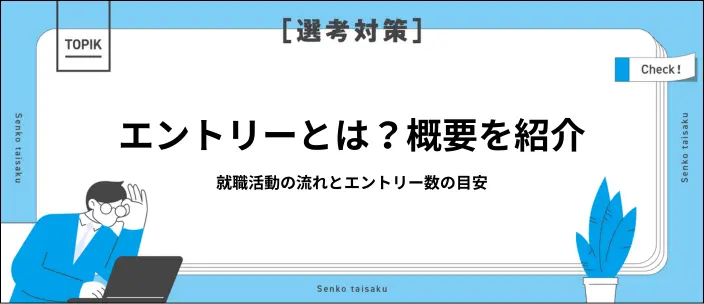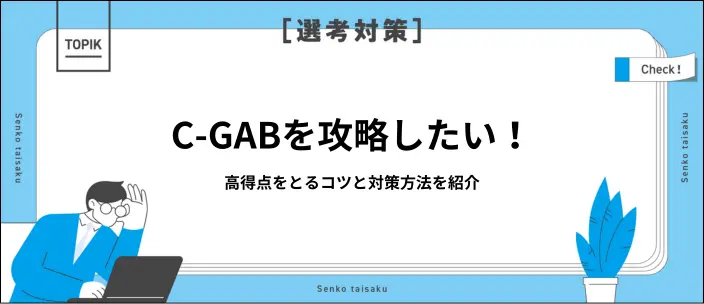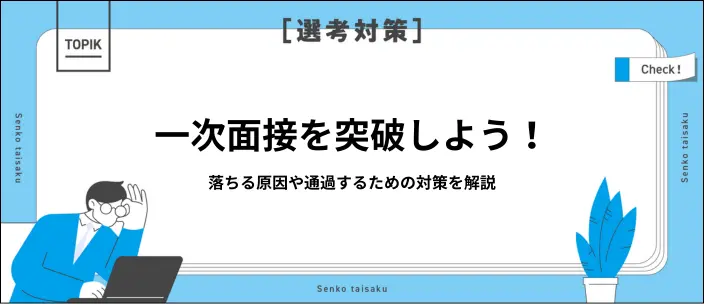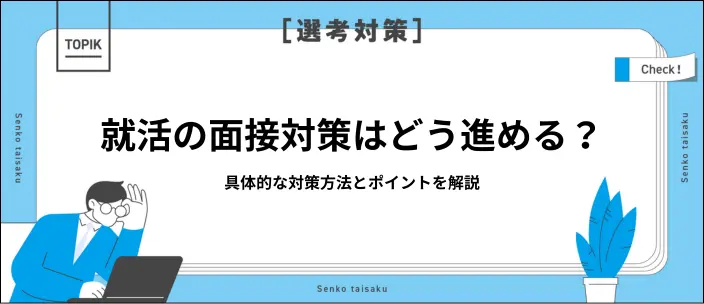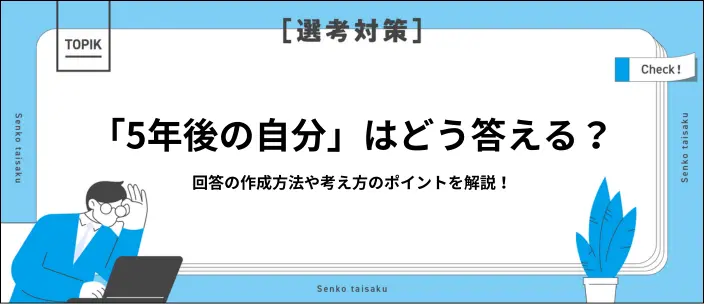このページのまとめ
- 書類選考通過率は平均30〜50%程度で、企業や業界によって大きく異なる
- 書類選考の通過率を上げるには複数社同時応募を行い、応募先を絞り過ぎないことが大切
- 事前に自己分析や業界研究を行うと、書類選考通過率を上げられる可能性がある
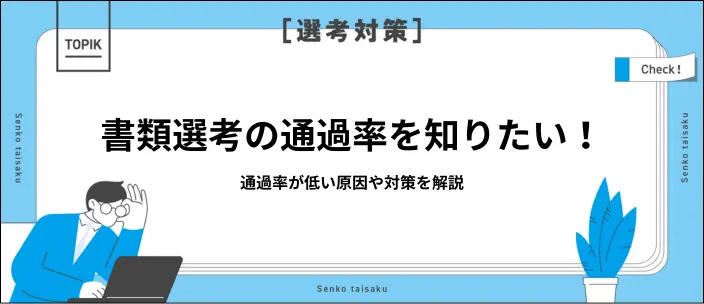
「書類選考の通過率はどれくらいが普通?」「どうすれば通過率を上げられるの?」と就活が思うように進まずに悩む人は多いでしょう。
この記事では、書類選考の通過率の目安や落ちる原因、通過率を上げるための具体的なポイントを就活生向けに解説します。これを読めば、書類選考で落ち続ける状態から抜け出し、内定に一歩近づく行動を取れるようになるでしょう。
かんたん1分!無料登録応募書類の書き方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 書類選考の通過率は企業によって異なる
- 書類選考通過率から考える応募社数
- 書類選考通過率を上げるなら1社ずつの応募は避ける
- 同時応募は何社まで大丈夫?
- 書類選考で「ほぼ内定」が決まることはない
- 書類選考が行われる目的
- 面接に参加できる応募者を絞るため
- 面接時の判断材料にするため
- 書類選考で企業が見る4つのポイント
- 1.志望度の高さ
- 2.入社後のビジョン
- 3.求める人物像とのマッチ度
- 4.ビジネスマナー
- 書類選考で通過率が上がらない原因
- 求人要件とスキル・経験が合っていない
- 自己PRで魅力が伝えきれていない
- 誤字脱字・書式の乱れ・記載漏れがある
- 応募先が競争率の高い企業ばかり
- 書類選考の通過率を上げるためのコツ
- 企業の求める人物像を把握する
- 過去のエピソードや経験をもとに書く
- 何度も添削を繰り返す
- 第三者に添削してもらう
- 書類選考の前にやっておきたい就活対策
- 自己分析
- 業界研究・企業分析
- 就活イベントへの参加
- OB・OG訪問
- インターンシップ
- 書類選考で少しでも内定に近づきたい人へ
書類選考の通過率は企業によって異なる
書類選考の通過率は企業によって異なります。一般的な書類選考通過率の目安は、30〜50%程度です。しかし、大企業や有名企業など多くの就活生が集まる企業の場合、通過率が10%程度になることも。応募者の多い企業ほど書類選考の通過率は下がり、少ない企業ほど通過率は上がります。
就活では書類選考の時点から厳しく評価されており、十分な対策が必要なことを覚えておきましょう。書類選考で必要になる履歴書の書き方については、「新卒就活用の履歴書の正しい書き方は?必要な準備や提出時のポイントも解説」の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
かんたん1分!無料登録応募書類の書き方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
書類選考通過率から考える応募社数
内定を得るためには、最低でも6〜10社への応募が必要と考えておきましょう。
就活では、企業ごとに書類選考通過率が異なります。大手企業や人気企業は応募者数が多く、通過率は10%以下になることも。一方で中小企業やベンチャー企業では通過率が高くなる傾向がありますが、それでも100%通過するわけではありません。
また、書類選考後には筆記試験や複数回の面接がある企業も多く、内定までのステップごとに辞退や不合格の可能性があります。そのため、そのため、「書類選考を通過したから安心」ではなく、面接まで進める応募数を確保するのが大切です。
第一志望の企業から内定を得られるとは限らないからこそ、複数の企業に応募し選べる状態を作ることが重要です。そのためにも、書類選考通過率を意識しながら、同時期に複数社へ応募する戦略を立てましょう。
書類選考通過率を上げるなら1社ずつの応募は避ける
「1社ずつ応募」は就活を長引かせるリスクが高く、書類選考通過率を上げるためにも複数社への同時応募が必要です。就活では、書類選考通過率は平均30〜50%程度が多く、どんなに準備しても落ちることは珍しくありません。1社ずつ応募していると、落ちるたびに振り出しに戻り、時間だけが過ぎてしまう可能性が高くなります。
特に在学中は授業や研究、バイトなどで就活に使える時間が限られるため、選考が終わるのを待ってから次に応募していると、いつまでも内定が決まらない状況になりかねません。一方で、同時期に複数社へ応募すれば、選考結果を待ちながら他社の選考も進められ、時間を効率的に使えます。
だからこそ、書類選考通過率の低さを前提に、複数社へ同時応募し、面接で実際に比較しながら「自分に合う企業」を見つけることが大切です。内定を得るためだけでなく、納得のいく企業選びをするためにも、「同時応募×比較検討」の姿勢で就活を進めていきましょう。
同時応募は何社まで大丈夫?
就活で同時に応募できる企業数に制限はありません。しかし、書類選考通過率を踏まえると「6〜10社」を目安に同時応募するのがおすすめです。
ただし、むやみに応募社数を増やすと、以下のリスクがあります。
・応募書類を丁寧に作り込む時間がなくなり、通過率が下がる
・面接準備が不十分になり面接通過率も下がる
・スケジュール管理が破綻し、面接を辞退することになる
そのため、ただ数を増やすだけではなく、質と量のバランスをとることが大切です。
かんたん1分!無料登録応募書類の書き方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
書類選考で「ほぼ内定」が決まることはない
書類選考だけで、内定がもらえることはほぼありません。履歴書やエントリーシートだけで分かる範囲は少なく、企業側も内定は出しにくいでしょう。面接で実際に話すことにより、伝わる人柄やスキルなどもあるためです。
反対に、書類選考だけで選考に落ちることはよくあります。書類の内容から企業が「自社の求める人材ではなない」と感じた場合、面接にすら参加できないケースもあるので気をつけましょう。
内定までには、書類選考のほかにも適性検査や面接などの選考フローがあります。具体的な流れやおおまかな時期を知りたい方は「27卒大学生の就活スケジュールと流れは?26卒の動向や準備のコツを解説」を参考にしてください。
かんたん1分!無料登録応募書類の書き方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
書類選考が行われる目的
書類選考が行われる理由は大きく2つ、「面接に呼ぶ応募者を絞るため」と「面接時の判断材料にするため」です。
企業側は膨大な数の応募者すべてと面接するのは現実的ではなく、効率良く自社に合う人材を見つけるために書類選考を行っています。また、書類選考で提出された履歴書やエントリーシート(ES)は面接時にも活用され、質問や評価の基準となるため、単なる通過儀礼ではありません。
ここでは、企業が書類選考を実施する具体的な目的を2つ紹介します。なぜ書類選考が行われるのかを理解したうえで、書類作成の質を上げることが書類選考通過率アップ、面接突破力アップにつながるでしょう。
面接に参加できる応募者を絞るため
書類選考の目的の一つは、面接に呼ぶ応募者を絞り込むことです。
企業には多くの学生が応募しますが、すべての応募者と面接するのは時間・コストの面で現実的ではありません。そのため、書類選考を通じて「自社で活躍できそうな人材」や「求める人物像に近い人材」を見極め、面接に進む学生を選んでいます。
たとえばIT業界の企業が「プログラミング経験者」を募集している場合、書類の中で経験の有無、どの言語を使えるのか、具体的にどのようなことを学び何をアウトプットしたのかが見られるでしょう。この際、「自分のスキルをただアピールする」のではなく、「その企業でどう活かせるか」という観点でアピールすることが大切です。
書類選考は、「企業が面接したいと思える応募者かどうか」を見極めるために行われています。「この学生なら自社で活躍できそうだ」と企業に思わせる書類作りが、書類選考通過率を高めるポイントです。
面接時の判断材料にするため
書類選考のもう一つの目的は、面接時の質問や評価の判断材料とするためです。
提出した履歴書・エントリーシート(ES)は、ただ合否を決めるだけでなく、面接での質問内容を決める基礎資料になります。志望動機や自己PR、学生時代に頑張ったこと(ガクチカ)など、書類に書かれた内容は面接で必ず聞かれるでしょう。
書類内容と実際の回答がずれていると説得力がなくなり、準備不足と判断される可能性があるため、しっかり考えて書かなくてはなりません。
たとえば、「チームでの目標達成のためにリーダーとして行動した」とESに記載した場合、面接では具体的な状況、役割、工夫したこと、結果、学びなど詳細を問われます。このときスムーズに具体的なエピソードを語れれば、「準備ができている」「自己分析ができている」と高評価を得られますが、逆に曖昧な答えしか返せないと印象は大きく下がるでしょう。
書類は「面接で何を話すか」の土台です。書類選考通過後も活用されることを意識し、内容を深掘りする準備や具体的なエピソードの整理、想定質問への回答練習などを徹底することで、面接の通過率も引き上げられます。
書類選考で提出を求められる代表的な書類がエントリーシート(ES)です。ESの基礎知識については「エントリーシートとは?履歴書の違いや基本を押さえて選考を突破しよう」を参考にしてください。
かんたん1分!無料登録応募書類の書き方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
書類選考で企業が見る4つのポイント
書類選考を行っている企業は、就活生の提出した書類をさまざまな観点からチェックし、合否を決めています。ここでは、主だった4つのポイントを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1.志望度の高さ
企業側は、就活生の志望動機や、企業に対する理解を通じて、就活生の志望度の高さを見ています。
競合他社でも通じるような志望動機では、「志望度が低い」と判断されてしまうかもしれません。好印象を与えるためにも、企業分析や業界研究で1社1社の特徴をつかみ、個別に志望動機を考えるようにしましょう。
2.入社後のビジョン
入社後のビジョンが企業側と一致しているかどうかも、書類選考では見られています。自分のやりたいことが企業方針と合っているかを考えましょう。
学生のやりたいことが企業では実現不可な場合、企業側は採用しても活躍できそうな場面がないと考えます。ただ自分のやりたいことをアピールするのではなく、志望企業で実現できるかどうかをしっかり意識する必要があります。
3.求める人物像とのマッチ度
企業は、就活生の書いた長所・短所や、学生時代に力を入れたことなどを通じて、就活生の能力と求める人物像のマッチ度を測っています。
たとえば、企業が新卒採用でプログラマーを増やしたいと考えている場合、いくらそのほかの能力が高くてもプログラミング知識が全くない状態では、書類選考の突破は難しくなるでしょう。
企業研究などを通じ、事前に企業がどのような人材を求めているのかを考え、自分の経験やスキルの売り込み方を練っておくこと必要があります。
4.ビジネスマナー
書類選考では、基本的なビジネスマナーも見られています。そのため、応募書類は、マナーを守って書くことが大切です。
日付は提出する日になっているか、西暦・和暦は統一されているか、住所や学校名は省略されていないかなど、細部までチェックされます。提出の前には、誤字脱字がないかしっかり確認しましょう。書き間違えたら修正液や修正テープで訂正せず、書き直すこともマナーの一つです。
書類選考に限らず、就活では社会人としてのマナーを守ることが求められます。マナーについてより詳しく学びたい方は「社会人としての心構えとは?具体例10選や面接での答え方を解説」を参考にしてください。
かんたん1分!無料登録応募書類の書き方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
書類選考で通過率が上がらない原因
書類選考で通過率が上がらないのは「原因の把握不足」が最大の理由です。原因を理解することで、書類選考通過率を確実に上げる対策が可能になります。ここでは、具体的な原因と改善ポイントを解説しますので、確認して対策を行いましょう。
求人要件とスキル・経験が合っていない
求人要件とスキル・経験が合っていないと書類選考で落ちる大きな原因になります。
求人票に記載されている条件は「絶対条件」と「歓迎条件」が混在していますが、企業はどの程度のレベル感であるのかを重視しているのです。
たとえば、「マーケティング経験者歓迎」という求人でも、SNS運用レベルと広告運用・分析を伴う経験では期待される内容が異なります。また「マネジメント経験歓迎」とあっても、1名の進捗管理レベルと5名以上のプロジェクト管理ではレベル感が異なるでしょう。
書類選考通過率を上げる第一歩として、求人要件と自分のスキル・経験が本質的に合っているか、確認してから応募することが大切です。
自己PRで魅力が伝えきれていない
自己PRで魅力が伝えきれていないと、書類選考で落ちる原因になります。
魅力の伝わらない自己PRの例は以下のとおりです。
・抽象的で具体性がない(例:「協調性があります」だけ)
・実績・成果を数字で示していない
・求められている内容とズレた自己PRをしている
また、自信過剰な表現や自己評価が低過ぎる表現も、評価を下げる要因になります。たとえば「リーダーシップがあります」と書くだけでは伝わりません。具体的に「10人のチームで進捗管理を行い、納期短縮率を20%改善した」など成果を数字で示すと良いでしょう。
誤字脱字・書式の乱れ・記載漏れがある
誤字脱字・書式の乱れ・記載漏れは書類選考落選の原因です。
誤字脱字は注意力の不足や仕事の正確性が低いという印象を与え、細かいミスが許されない職種では特に評価を落とします。また、書式が乱れていたり日付や会社名が誤っていたりといった不備も、書類の信頼性を失わせるでしょう。
書類提出前には以下を徹底します。
・誤字脱字チェック(声に出して読む、ツールで確認)
・経歴・日付・会社名の整合性確認
・指定書式・文字数・ファイル形式の遵守
・書式やフォントの統一、読みやすいレイアウトの確認
こうした基本的な部分を整えるだけでも、書類選考通過率の向上につながるでしょう。
応募先が競争率の高い企業ばかり
書類選考通過率が低い原因は、自分の書類の内容だけでなく「競争率の高い企業ばかり応募していること」にある場合があります。
人気企業や有名企業には多くの応募が集まり、自然と通過率は低くなるでしょう。また、募集人数が少ない企業も倍率が高くなるため、どんなに書類を改善しても落ちる可能性が高いままになってしまいます。
そのため、最初から応募先を絞り過ぎず、競争率の高い企業だけでなく幅広く応募することが大切です。最初は興味が薄かった企業でも、説明会や面接を通じて仕事内容や社風を知る中で魅力を感じることは珍しくありません。
人気企業だけでなく幅広く応募し、書類選考通過の経験を積むことで、就活の経験値を高めつつ書類選考通過率を確実に上げることが可能です。
かんたん1分!無料登録応募書類の書き方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
書類選考の通過率を上げるためのコツ
書類選考の通過率を上げるためには、企業側にとって魅力的な書類を作成する必要があります。ここでは、採用率を上げるために重要なポイントを4つ紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
企業の求める人物像を把握する
はじめに、企業の求める人物像を把握し、その人物像に当てはまるような自分の長所や経験をアピールしていくようにしましょう。
企業が求める人物像を考えるには、企業研究をしっかり行うことが重要です。以下のような情報を調べて、応募書類に反映しましょう。
・業界でどのような立ち位置にいるのか
・どのような商材に力を入れているのか
・今後どのような展開を考えているのか
企業の求める人材は、採用ページや企業説明会で明確に伝えられる場合もあります。どのような人物が求められているかを知っておくと、書類選考のアピール内容も考えやすいでしょう。
過去のエピソードや経験をもとに書く
エントリーシートや履歴書を書く際には、過去のエピソードや経験をもとに、具体的な記述をするようにしましょう。
たとえば、「コミュニケーション能力がある」と書くのと、「飲食店のカウンター席で隣に座った人とすぐに仲良くなれる」と書いてあるのでは、受ける印象や説得力が大きく異なります。
具体的なエピソードや経験がもとになっていると、面接に進んだ場合に面接官が質問をしやすいため、好印象を与えやすくなるでしょう。過去の体験を具体的な言葉にするためには、書類作成の前に入念な自己分析を行うことがポイントです。
何度も添削を繰り返す
提出書類は何度も添削を繰り返し、内容を良くしていきましょう。書類選考や面接での反応を見て、内容を変えていくのがおすすめです。
たとえば、書類選考に通過しないケースが多いのであれば、大きく内容や文章を変更しなくてはなりません。また、面接での印象が良くない場合は、内容が伝わっていない部分を考え、より伝わるように変える必要があります。
うまく書けたと思った文章も、時間を空けて読み直すとわかりにくい表現があると気づくことは珍しくありません。書いただけで満足せず、何度も添削を行ってより良い内容にブラッシュアップしましょう。
第三者に添削してもらう
提出する書類が完成したら、親や友人など第三者に添削してもらうこともおすすめです。第三者に読んでもらうことで、自分では気付けない文章のミスや論理の破綻を指摘してもらえます。
他人のESを読むことも勉強になるため、就活生同士でESを添削するのもおすすめです。友人同士声を掛け合って、就活対策を進めましょう。
書類選考の通過率を上げるためのコツをより詳しく学びたい方は「ESの通過率を上げるにはどうする?アピールのコツを解説!」を参考にしてください。
かんたん1分!無料登録応募書類の書き方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
書類選考の前にやっておきたい就活対策
書類選考に向けてESや履歴書を作成する前に、入念な就活対策を行っておくことが第一志望への内定の鍵です。ここでは、特に取り組んでおくべき対策を紹介します。
自己分析
就活対策の基本、自己分析は必ず取り組んでおきましょう。自己分析のやり方はさまざまで、自分の経験を年表などで整理する「自分史」の作成やマインドマップの作成が代表的なものです。
自己分析をやり込むことで、過去の経験を整理したり、自分の価値観や考え方がどう育まれたのかを言葉にできたりするようになります。抽象的な表現ではなく、具体的なエピソードや言葉を使ってESや履歴書を書けるようになるでしょう。
志望動機や自己PR、ガクチカ(学生時代に力を入れていたこと)などを書く際にも、自己分析で得た情報は重要です。就活対策を何から始めれば良いか悩んでいる方は、まず自己分析から始めてみましょう。
業界研究・企業分析
自己分析で自分の経験や価値観についての理解を深めたら、興味のある業界や企業について調べましょう。いわゆる「業界研究」や「企業分析」です。
業界研究は、興味のある業界に関する動向やニュース、各社の規模などを横断的に調べること。各出版社から出版されている「業界地図」などを見ると、業界内のパワーバランスや資本関係などについて理解できます。
企業分析は、一つの企業にスポットライトを当てて、情報を集めることです。新卒の募集要項はもちろん、公開されている情報には一通り目を通し、企業がどのような強みを持っていて、今後どのようにビジネスを展開しようとしているのか考えを深めておきましょう。
特に上場企業の場合は、投資家向けに積極的な情報公開を行っています。志望度の高い企業については事前にチェックすると良いでしょう。
就活イベントへの参加
ある程度志望業界や企業が定まってきた後は、就活イベントに積極的に参加しましょう。個別企業が主催する説明会などはもちろん、特定の業界や関連企業が集まる合同説明会も視野を広げるのに有効です。
近年、特に注意しておきたいのがインターンシップ。これまでは採用に直結していないとされてきましたが、25卒以降は採用直結型インターンが正式に認められるようになりました。
志望度の高い企業がインターンを開催している場合、できる限り参加に向けて準備を進めるようにしましょう。
OB・OG訪問
志望度が高い企業には、OB・OG訪問も行うのがおすすめです。OB・OG訪問とは、実際に企業に勤めている社会人のもとを訪れ、新卒採用の経験や、実際に入社したあとの感想などを聞くことを指します。
年の近いOB・OG訪問なら、実際の選考がどのように進んでいったのかを話を聞けるのがポイントです。また、キャリアのあるOB・OGなら入社後のキャリアパスについて聞くことができます。
大学によっては、進路指導を担当する部署やゼミ・研究室でOB・OG訪問先を紹介しているケースもあるため有効活用しましょう。OB・OG訪問の始め方がわからない方は「OB訪問ってどうやるの?アポ取りから進め方まで徹底解説!」を参考にしてください。
インターンシップ
企業への理解度を高めるため、インターンシップにも参加してみましょう。企業説明会やWebサイトだけではわからない、企業の雰囲気を知ることができます。
企業について詳しく知りたい場合は、業務内容を体験できるインターンシップがおすすめです。業務内容はもちろん、社員の方や会社の雰囲気を知れるため、ESや履歴書に書ける内容も増えるでしょう。
かんたん1分!無料登録応募書類の書き方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
書類選考で少しでも内定に近づきたい人へ
書類選考でほぼ内定を固めることは難しいものの、完成度の高いESや履歴書を作成することでその後の選考を有利に進めることは可能です。
書類選考から少しでも内定に近づきたいと考えている人は、「キャリアチケット」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
キャリアチケットは、あなたの就活を全面的にサポートする就職エージェントサービスです。書類選考に提出するESや履歴書の書き方はもちろん、その後の選考で行われるグループディスカッションや面接対策などもプロのアドバイザーが丁寧に指導します。
人生の大きな節目となる就活では、多くの就活生がさまざまな不安や悩みを抱えることになるでしょう。ネガティブな気持ちに一人で立ち向かっていくことは、想像以上に消耗するもの。
そんな時、キャリアチケットを利用していれば、自分が感じている不安や悩みをいつでも相談できるようになります。悩みや不安を一人で抱え込まず、効率的に就活を進めるためにも、キャリアチケットを利用してみませんか。
かんたん1分!無料登録応募書類の書き方を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。