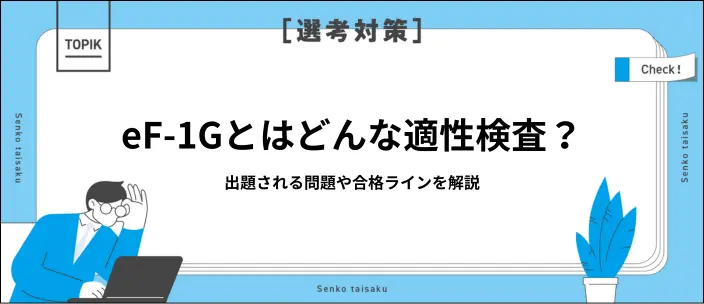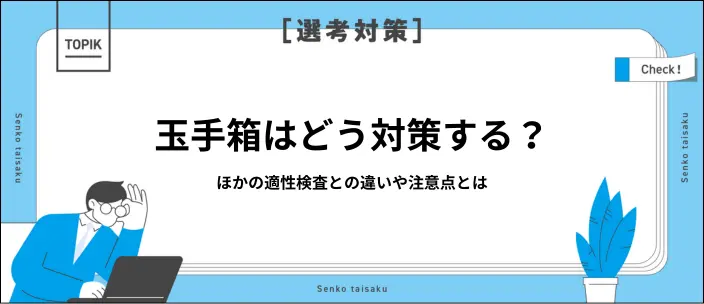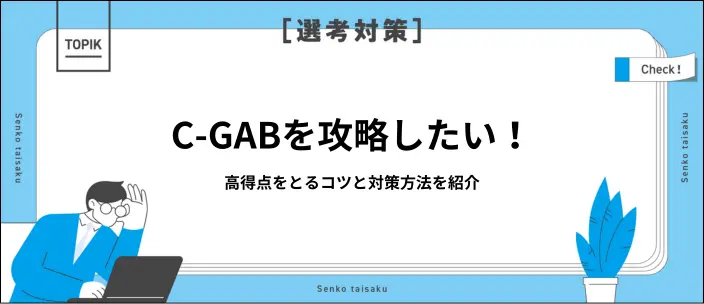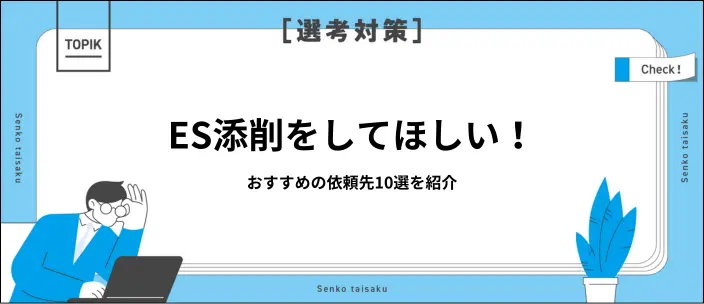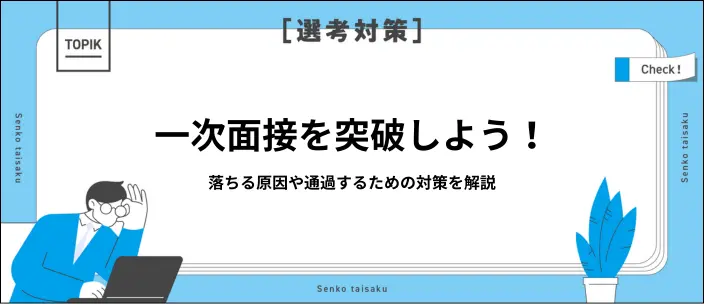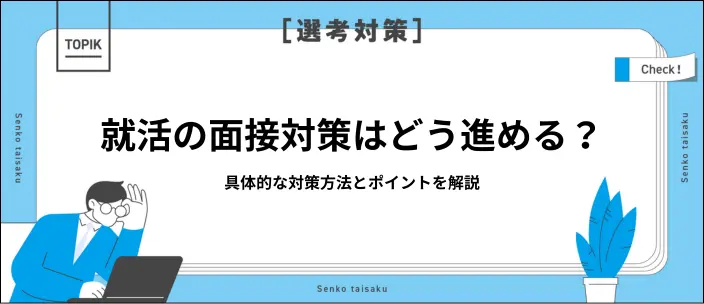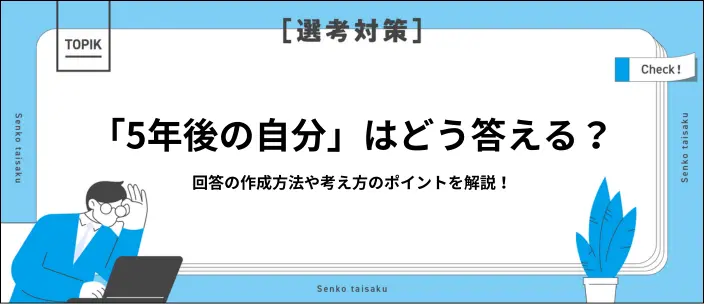このページのまとめ
- SPI3とは新卒採用の選考で使用される能力検査と性格検査からなる適性試験
- SPI3の問題には「言語問題」「非言語問題」「英語問題」「構造的把握力」がある
- SPI3で高得点を取るには問題集を繰り返し解いて苦手を克服するのが大切
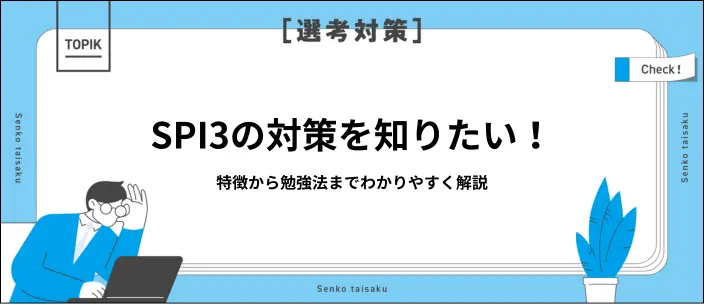
「SPI3とは?どんなテスト?」「出題される問題はどのような内容?」などと気になる就活生も多いでしょう。SPI3は多くの企業の選考で使用されている試験です。試験の内容や難易度、対策方法をしっかり理解しておくと、合格に近づけるでしょう。
この記事では、SPI3の出題内容や、解くためのポイントを解説しています。おすすめの勉強法も紹介するので、就活時の参考にしてください。
かんたん1分!無料登録SPI対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- SPI3は新卒採用で使われる適性検査
- 能力検査
- 性格検査
- SPI3の難易度
- SPI3-H
- SPI3-U
- SPI3-B
- SPI3-N
- SPI3-R
- 「SPI」「SPI2」とSPI3の違い
- SPI3とほかの適性検査の違い
- SPI3を企業が導入する理由
- 応募者を絞り込むため
- 応募者の基礎的な学力を見るため
- 履歴書ではわからない特徴や能力を見るため
- ミスマッチを防ぐため
- 適切な人材配置を行うため
- SPI3の受検方法
- テストセンター
- Webテスト
- インハウスCBT
- ペーパーテスト
- SPI3の能力検査の出題内容と解くためのポイント
- 言語問題
- 非言語問題
- 英語問題
- 構造的把握力
- SPI3の性格検査の出題内容と解くためのポイント
- 矛盾した回答を避ける
- 極端な回答や曖昧な回答に注意する
- SPI3で高得点を取るための勉強法
- 受検する企業や業界の出題傾向を調べる
- 苦手な問題を繰り返し練習する
- 頻出する問題を練習する
- 時間を計りながら練習する
- 問題集を繰り返し解く
- アプリで隙間時間をうまく使う
- SPI3対策に向けたスケジュールの目安
- 50時間以上の勉強が必要になる
- 大学3年生の1月には対策を始めたい
- インターンシップで必要になる場合もある
- SPI3の対策をして選考を突破したいあなたへ
SPI3は新卒採用で使われる適性検査
SPI3は、新卒採用の選考で使われる適性検査です。正式名称を「Synthetic-Personality-Inventory(総合適性検査)」といい、採用場面では40年以上にわたって使用されています。
SPI3の検査内容は、言語問題と非言語問題からなる「能力検査」と、受検者の考え方を問う「性格検査」の大きく分けて2種類です。
能力検査
SPI3の能力検査は、就活生の基礎学力を測るために実施される適性検査です。企業はこの結果を見て「入社後に仕事をこなすための基礎的な能力があるか」を確認しています。
国語(言語分野)、数学(非言語分野)を中心に中学〜高校レベルの基礎問題が出題されるのが一般的です。問題そのものの難易度はそこまで高くありませんが、限られた時間で正確に解く処理速度が問われます。
一般的に大手企業では各科目7割以上の正答率を目指すのが安全圏。合格ラインは企業ごとに異なり、「△点で合格」とはいえませんが、7割を目標にすることで不合格リスクを下げられます。
ポイントは出題パターンを理解し、解説が充実した問題集で繰り返し演習することです。勉強が苦手でも、毎日少しずつ取り組めば本番で点数を積み上げられます。「出題形式に慣れること」がSPI3の能力検査突破の鍵です。
性格検査
SPI3の性格検査は、就活生の人柄・性格が企業の社風や職種にマッチするかを測る検査です。約300問の質問に30分ほどで回答します。性格検査で大切なのは素早く迷わず答えること。性格検査に正解・不正解はなく、自分の本来の価値観を回答することが前提です。
「良く見られたい」と虚偽の回答をする人がいますが、SPI3には回答の一貫性や矛盾を検知する仕組みがあります。矛盾が多いと「信頼できない人物」と判断され、通過率が下がる可能性が高いでしょう。
本来の自分と合わない職種や環境で入社後に苦労しないためにも、素直な気持ちで一貫性を意識しながら回答することが重要です。SPI3性格検査は就活の合否を分ける重要な項目であるため、「正解はない」という前提で臨みましょう。
かんたん1分!無料登録SPI対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPI3の難易度
SPI3の問題難易度は中学~高校レベルです。難易度が高過ぎるわけではないので、事前に練習問題を解いておけば十分に対応できるでしょう。
ただし、問題数が多いため、回答の素早さが求められます。問題には傾向があるので、繰り返し問題を練習し、素早くミスなく解けるようにしておきましょう。
SPI3-R
SPI3-Rは主に一般職や事務職の採用で利用される適性検査で、短大卒や大卒向けに設計されています。SPI3-Rの難易度は中程度で、基礎的な学力と適性をバランス良く測る内容です。
SPI3-Rは基礎的な知識や能力に加え、仕事に対する適正や性格も評価し、企業が求める職場で安定して働ける人材かどうかを見極めるための検査といえます。
SPI3-N
SPI3-Nは短大生・高校生向けのSPI適性検査で、一般職や事務職採用時によく利用されています。SPI3-Nの難易度は比較的易しく、基本的な漢字・計算・読解など高校レベルの問題が中心のため、基礎学力があれば対応可能です。
SPI3-Nは「事務処理能力・正確性・文章理解力」などを短時間で測り、採用担当者が「職場での業務をミスなく行えるか」「学んだことをきちんと活用できるか」を確認するために使います。
SPI3-H
SPI3-Hは高卒学生向けに実施されるSPI3の適性検査で、企業はこの試験を通じて「社会人として最低限必要な基礎学力・処理能力が備わっているか」を確認します。具体的には、中学〜高校基礎レベルの国語・数学の問題が中心で、難易度は比較的低めです。
学校で学んだ基礎知識が理解できていれば十分対応可能であり、「就活でSPI3-Hが不安」という人も、焦る必要はありません。ただし、油断するとミスを連発し得点を落とす可能性もあります。短時間でも毎日問題演習を続けることが、SPI3-H突破のポイントです。
SPI3-U
SPI3-Uは大卒学生向けに実施されるSPI3適性検査で、SPI3-Hに比べて難易度が高く、より高い論理的思考力・問題解決能力が求められます。多くの企業が総合職採用試験にSPI3-Uを導入しており、言語・非言語問題ともに大学レベルの基礎学力と「時間内に処理する力」が合格のポイントです。
SPI3-B
SPI3-Bは転職者向けに実施されるSPI適性検査で、幅広い職種・年齢層の中途採用で利用されています。SPI3-BはSPI3-U(大卒用)より出題範囲が広く、縮尺・方角など独自の非言語分野問題が出題されるのが特徴です。
SPI3の問題数や時間配分については「SPIの非言語問題とは?回答のコツや対策方法を解説」も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録SPI対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
「SPI」「SPI2」とSPI3の違い
「SPI」「SPI2」は、SPI3と受検方式や検査内容が異なる適性検査です。
「SPI」のときは、受検がマークシート形式で行われていました。その後、2005年には「SPI2」にバージョンアップし、テストセンターやWebテストでも受検できるように変更されています。
2013年には「SPI3」にバージョンアップされ、その際に性格検査が追加されました。「SPI」は廃止されていますが、「SPI2」「SPI3」は現在も使用されています。
かんたん1分!無料登録SPI対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPI3とほかの適性検査の違い
SPI3以外にも、玉手箱やGABなど数々の適性検査があります。出題内容や制限時間などは異なるため、違いを知っておきましょう。
| SPI3 | ・能力検査と性格検査がある ・就活では最も一般的な適性検査 |
| 玉手箱 | ・幅広い業界で採用される検査 ・受検者によって問題がランダムになる ・制限時間が短い |
| GAB | ・適性検査のなかでも高難易度 ・言語・係数が出題される |
| C-GAB | ・テストセンターで受検する ・商社や金融業界での使用が多い ・問題傾向はGABに似ている |
| Web-GAB | ・自宅で受検する ・制げ時間は80分 ・問題傾向はGABに似ている |
| CAB | ・システム系の会社で出題されやすい ・「暗算・法則性・命令表・暗号」がある |
| TG-WEB | ・計数・言語・英語・性格テストがある ・どの問題も難易度が高い |
代表的な適性検査は「就活の適性検査とは?検査の種類や特徴、受ける際のポイントをご紹介!」の記事で紹介しているので、あわせて参考にしてください。
かんたん1分!無料登録SPI対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPI3を企業が導入する理由
SPIを企業が導入する理由は、応募者の基礎的な学力を確認したり、履歴書ではわからない能力を確認したりするなどさまざまです。SPI3を導入する理由について、詳しく解説します。
応募者を絞り込むため
企業がSPI3を導入する大きな理由の一つは、応募者を効率的に絞り込むためです。特に大手や有名企業では、毎年何千人、場合によっては1万人以上もの応募者が集まります。全員と面接を行うのは時間もコストも掛かり、実質的に不可能です。
一定の基準点をクリアした応募者だけを次の選考段階に進めることで、採用活動をスムーズに進められます。また、性格検査の結果からは、企業の社風や業務内容にマッチした人材かどうかを見極めることができるため、ミスマッチによる早期離職を防ぐ効果も期待できるでしょう。
このように、SPI3は単なる学力テストだけでなく、応募者の「適性」や「企業との相性」まで評価できる点が企業にとって大きなメリットです。
応募者の基礎的な学力を見るため
企業がSPI3を導入する理由の一つに、応募者の基礎的な学力を把握するためがあります。SPI3では、入社後に必要となる言語能力や数的処理能力を客観的に測定できるため、企業は応募者が業務を遂行するための最低限の能力を持っているかどうかを判断できるでしょう。
特に大学生の場合、学部や専攻によって学ぶ内容が大きく異なるため、大学の成績だけでは能力を正確に比較することは困難です。しかし、SPI3を使えば、異なる大学や学部の学生であっても同じ基準で能力を評価できるため、公平な選考ができます。
また、結果が点数や数値として出るため、採用担当者が感覚的ではなく、客観的なデータに基づいて合否を判断できることも大きなメリットです。
履歴書ではわからない特徴や能力を見るため
書類選考の段階で履歴書を確認するだけでは、志望者の性格や本当の能力を正確に把握するのは難しいでしょう。SPI3は、そうした履歴書だけでは見えない個性や適性、スキルを数値や結果として客観的に判断できるツールとして活用されています。
性格検査では、応募者の価値観や行動パターンを把握できるため、企業は自社の社風や業務内容にマッチした人材を見極めやすくなるでしょう。また、能力検査の結果からは、問題解決能力や論理的思考力を知ることができ、採用ミスマッチを減らすことにもつながります。
つまり、SPI3は履歴書だけでは伝わりにくい「本質的な能力や適性」を補う重要な判断材料なのです。
ミスマッチを防ぐため
SPI3を導入する大きな理由の一つに、企業と応募者のミスマッチを防ぐことがあります。SPI3によって得られる性格や適性の分析データをもとに、自社の社風や業務内容に合う人材を選べるため、入社後に長く活躍してもらいやすくなるでしょう。
これにより、早期退職や職場でのストレスを減らし、企業側は採用コストの削減、応募者は自分に合った職場でのキャリア形成が可能になります。SPI3は企業と応募者双方にとって、良好なマッチングを実現するための有効なツールなのです。
適切な人材配置を行うため
SPI3は、応募者の能力や性格を把握することで、社員一人ひとりに適した部署や役割を見極めるためにも使われます。SPI3の結果を活用してミスマッチを防ぐことで、社員が働きやすく、パフォーマンスを発揮できる環境をつくることが可能です。
ただし、SPI3の結果だけで合否が決まるわけではありません。履歴書や面接でのアピールも重要なので、しっかり準備を進めましょう。
履歴書でのアピール方法については「履歴書の余白って何割埋めるべき?基本マナーや書き方も解説」も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録SPI対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPI3の受検方法
SPI3の受検方法には、「テストセンター」「Webテスト」「インハウスCBT」「ペーパーテスト」の4種類があります。それぞれの受検方法を解説するので、どのような形式で行われるのかを知っておきましょう。
テストセンター
テストセンターとは、決められた受検会場でSPI3を受ける形式です。テストセンターは以下の都市に常設されています。
・東京
・大阪
・名古屋
・札幌
・仙台
・広島
・福岡
受検者が多い時期には、臨時のテストセンターが各都道府県に設置されるので、最寄りの会場を選ぶと良いでしょう。
テストセンターでの受検には、企業からの案内が必要です。メールが届くので、受検会場を予約して参加しましょう。過去1年以内にテストセンターの受検経験がある場合には、試験結果を使いまわせます。
テストセンター受検については「SPIテストセンターを初めて受ける人必見!受検の流れや注意点を解説」も参考にしてください。
Webテスト
Webテストは、インターネットを使用し、パソコンから受検する方法です。自宅や大学など、インターネット環境があればどこでも受検できるメリットがあります。
また、受検時間も決められておらず、期間内であればいつでも受けることが可能です。忙しくなる就活期でも受検しやすい形式でしょう。
インハウスCBT
インハウスCBTとは、志望企業が用意した会場で行うSPI3です。会場が応募先の企業になる場合も多く、面接と同日に受検することもあります。
回答はパソコンで行うので、普段パソコンをあまり使わない方はキーボード入力を練習しておきましょう。
ペーパーテスト
ペーパーテストは、マークシート形式で行うSPI3です。企業説明会のあとに実施されることが多い傾向にあります。
ペーパーテストの特徴は、不正行為が行われにくい点です。ただし、現代はパソコンで回答するSPI3が普及しているので、ペーパーテストを利用する企業は少なくなっています。
かんたん1分!無料登録SPI対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPI3の能力検査の出題内容と解くためのポイント
SPI3の能力検査では、言語問題と非言語問題があります。そのほかにも、海外企業との取引など英語を使う企業では「英語問題」が出されたり、企業によっては構造的把握力の問題が出題されたりする場合があるので覚えておきましょう。
ここでは、SPI3の能力検査の問題にどのような種類があるかと、解くためのポイントを解説するので参考にしてください。
言語問題
言語問題は国語の問題であり、語彙力や文章読解力が出題されます。問題例は以下のとおりです。
・二語の関係
・語句の意味
・語句の用法
・文の並び替え
・空欄補充
・熟語の成り立ち
・文節の並び替え
・長文読解
言語問題は言葉の意味を問う問題が多いので、単語について勉強しておきましょう。特に、「二語の関係」「語句の意味」「語句の用法」などは、単語についての知識がなければ正解が難しい問題です。出題の傾向は毎年変わらないので、問題集を解いて対策しておきましょう。
また、長文読解については、制限時間との戦いになります。素早く回答できるように、出題される長文の傾向に慣れておきましょう。
言語問題の特徴や対策については、「SPIの言語分野は事前対策でバッチリ!選考を突破できる勉強方法」の記事で解説しています。高得点をとるために、確認しておきましょう。
非言語問題
非言語問題は、数学の内容が出題されます。中学・高校レベルの問題になるので、内容を忘れている人は復習しておきましょう。SPI3の非言語問題では、次のような問題が出題されます。
・推論
・場合の数
・確率
・集合
・損益算
・速度算
・表の読み取り
・資料の読み取り
・長文読み取り計算
・代金の精算
・料金の割引
・割合の計算
・分割払い
・装置と回路
・物の流れと比率
・不等式と領域
・年齢算
・通過算
・整数の推理
・仕事算
SPI3の非言語問題はパターンが多いので、問題ごとの解き方を覚えておくのが重要です。たとえば、「推論」や「確率」は出題される場合が多いので、対策を行うようにしましょう。
また、定価・原価・売価の計算をする「損益算」や、距離と速さの公式が必要となる「速度算」などの解き方を覚えておくのもおすすめです。「表の読み取り」のように、資料やデータから答えを導き出す問題もあります。情報の取捨選択が必要になるので、データの読み方も練習しておきましょう。
なお、テストセンターやペーパーテストで受検する場合、電卓は使用できません。暗算や筆算の練習もしておくと安心です。
英語問題
SPI3の英語問題は、テストセンター、またはペーパーテストの場合のみ出題されます。Webテストでは実施されないので覚えておきましょう。英語問題では、次のような問題が出題されます。
・同意語
・反意語
・空欄補充
・語文訂正
・和文英訳
・長文読解
英語問題の場合、単語や文法の問題と長文読解にわけられます。「同意語」や「反意語」は単語の意味を知っておけば回答できるので、単語も覚えるようにしましょう。
「空欄補充」や「長文読解」については、総合的な英語能力が必要です。英検やTOEIC用の問題集を利用し、長文に慣れておくのもおすすめします。
構造的把握力
構造的把握力は、情報の関係性や共通性を読みとる検査です。テストセンターでのみ出題されます。
構造的把握力の問題は、言語問題と非言語問題の2種類です。
言語問題の場合、文章の構造を見て、グループごとにまとめる形式になります。非言語問題も文章を見てグループにまとめますが、計算や数学の知識が含まれているので注意しましょう。
構造的把握力の問題は意図がつかみにくく、初見では苦労します。問題集を解き、パターンに慣れておくことが大切です。
かんたん1分!無料登録SPI対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPI3の性格検査の出題内容と解くためのポイント
ここでは、SPI3の性格検査の出題内容と解くポイントを解説します。
まず、SPI3の性格検査は、提示される複数の考え方から1つを選んで回答する検査です。たとえば、文章Aと文章Bが提示され、「Aに近い」「どちらかといえばAに近い」「どちらかといえばBに近い」「Bに近い」のように4択から回答します。
また、文章が5つ提示され、一番あてはまる内容を選ぶタイプもあるので、指示に従って回答しましょう。問題数が多いので、深く考えずに直感に従って解くのが大切です。
矛盾した回答を避ける
PI3の性格検査では、矛盾した回答を避けるようにしましょう。たとえば、1問目で「チームで協力するのが得意」と回答したとします。その後、別の問題で「チームワークに自信がない」と回答すれば、矛盾が発生し、一貫性がないと思われてしまうでしょう。
性格検査では、似たような内容を問う問題もあります。矛盾した内容にならないように、正直に答えるようにしましょう。
極端な回答や曖昧な回答に注意する
曖昧な回答や極端な回答にも注意してください。企業から注視されてしまうかもしれません。
たとえば、「どちらともいえない」ばかり回答していると、どのような人物かがわからなくなります。まじめに答えていないと思われる場合もあるでしょう。
極端な回答や曖昧な回答は、「自分の意思がない」「自己主張が激し過ぎる」などと捉えられる場合もあります。自分を良く見せようとはせずに、思ったとおりに回答をしましょう。
SPI3の性格検査については、「性格検査とはどんなテスト?問題例や準備・対策方法を解説!」でも詳しく解説しています。
かんたん1分!無料登録SPI対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPI3で高得点を取るための勉強法
SPI3で高得点を取るためには、受検する時期から逆算して早めに対策をスタートすることが重要です。ここでは、SPI3で高得点をとるための勉強法を解説します。
受検する企業や業界の出題傾向を調べる
SPI3は受検方式が複数あるので、受検する企業や業界の出題傾向を調べて対策してください。試験時間や問題数も変わるので注意しておきましょう。
たとえば、英語問題や構造的把握力は、企業によって出題される場合とされない場合があります。また、テストセンターは電卓が使用できませんが、Webテストは使用可能です。
受検する企業や業界の出題傾向を知っておけば、問題や受検方式にあわせた対応ができます。対策内容が変わってくるので、本番を想定して勉強を行うようにしてください。
苦手な問題を繰り返し練習する
自分の苦手な分野を把握した上で対策に取り組むことが大切です。苦手な問題を見つけるためには、まずは問題集を1冊解きましょう。苦手な問題を重点的に解くことで、弱点を克服できます。
SPI3は問題数が多く範囲が広いので、苦手分野を減らして多くの問題を解けるようにしておくのが大切です。
練習して解けるようになったと思っても、時間が経つと忘れてしまう可能性があります。定期的に復習し、解き方を忘れないようにしましょう。
頻出する問題を練習する
高得点を取るために、頻出する問題を練習するのもおすすめです。SPIでは、毎回出題される問題もあれば、あまり出題されない問題もあります。
問題集によっては、頻出問題を示してくれている場合があるので参考にしましょう。対策があまりできておらず、試験まで時間がない場合は、頻出問題を優先して練習すると効率的です。
時間を計りながら練習する
SPI3の勉強では、時間を計りながら行いましょう。受検時に、時間が足りなくて失敗する就活生が多いからです。
SPI3は制限時間のわりに問題数が多く、効率的に解答しなければなりません。1問あたりどのくらいの時間が使えるか、実際に計って練習してみましょう。
SPI3の場合、テストセンターは35分、ペーパーテストは70分の制限時間があります。受検方式によっても変わるので、それぞれ対策するようにしましょう。
問題集を繰り返し解く
SPI3で高得点を取るためには、問題集を繰り返し解きましょう。SPI3の出題傾向やパターンに慣れることで正答率が上がります。
たとえば、非言語問題の「推論」や「確率」の問題は、数字が変わっても解き方は同じです。解き方のパターンさえ知っておけば、慌てずに解答できるでしょう。
問題の傾向はあまり変わらないので、問題集を1冊練習すれば十分です。1冊を繰り返し解き、問題に慣れておきましょう。
SPI3の時間配分については「SPIの時間配分はどうすればいい?試験形式ごとのポイントや対策を解説」も参考にしてください。
アプリで隙間時間をうまく使う
スマホアプリを使い、空いている時間で効率的に勉強しましょう。電車での移動時間、授業の空き時間など、隙間時間を効率的に使うのが勉強のコツです。
参考書で勉強する場合、荷物も増えるうえある程度まとまった勉強時間を確保しなければなりません。スマホアプリであれば参考書を持ち歩く必要もなく、外出時でも勉強できて便利です。
かんたん1分!無料登録SPI対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPI3対策に向けたスケジュールの目安
SPI3の勉強は、いつから始めるかも知っておきましょう。必要となる時期を考え、逆算して勉強を始めてください。
50時間以上の勉強が必要になる
SPI3の対策には、50時間以上が必要だとされています。50時間勉強すれば、ある程度の合格水準まで到達できるでしょう。
ただし、50時間勉強したからといって、必ず合格するわけではありません。「苦手が克服できていない」「志望企業は必要な得点数が高い」などの場合は、追加で勉強しておきましょう。
大学3年生の1月には対策を始めたい
大学3年生の1月には、勉強を始めるのがおすすめです。大学3年生の3月ごろになるとエントリーをし始める就活生が多く、SPIが必要になってきます。
50時間ほど勉強すると考えると、2〜3ヶ月は必要です。遅くても大学3年生の1月には勉強をスタートし、選考に備えておきましょう。
インターンシップで必要になる場合もある
インターンシップに選考がある場合、SPIが求められる企業もあります。参加したいインターンシップの選考にSPIが含まれているか確認しておきましょう。
キャリアチケットの「2026年入社予定学生のサマーインターン参加意識に関する調査」によると、9割の学生がインターンシップに参加予定です。SPIが必要になる学生も出てくるので、事前の準備を欠かさないようにしましょう
インターンシップの時期については、「インターンシップの申し込みはいつから?参加方法やメールの書き方を解説」の記事で解説しています。
かんたん1分!無料登録SPI対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
SPI3の対策をして選考を突破したいあなたへ
SPI3の対策をしっかり行って、選考を突破したいと考えていませんか。対策を入念に行いたい場合は、ぜひキャリアチケットに相談してください。
キャリアチケットでは、SPI3突破に向けたアドバイスを実施しています。これから対策を始めようとしている人も、一からサポートするので安心してください。
また、キャリアチケットは就活生をサポートする就活エージェントです。SPI3の対策だけではなく、面接対策やエントリーシートの添削も行っています。就活のプロがあなたの内定獲得を支えるので、ぜひ活用してください。
かんたん1分!無料登録SPI対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。