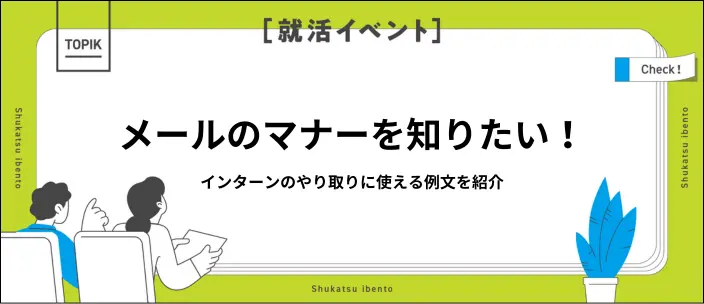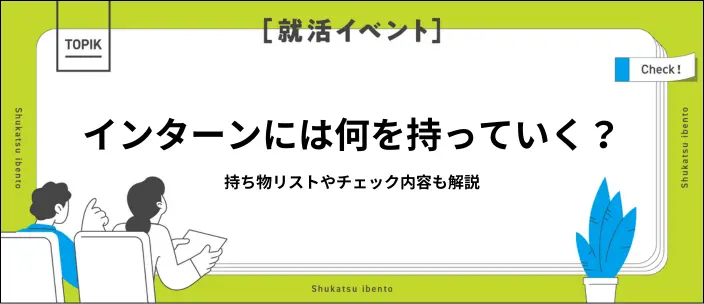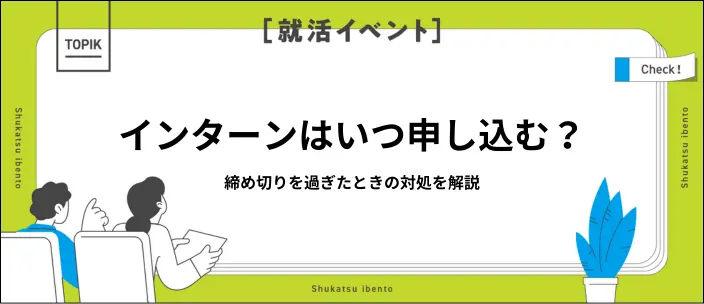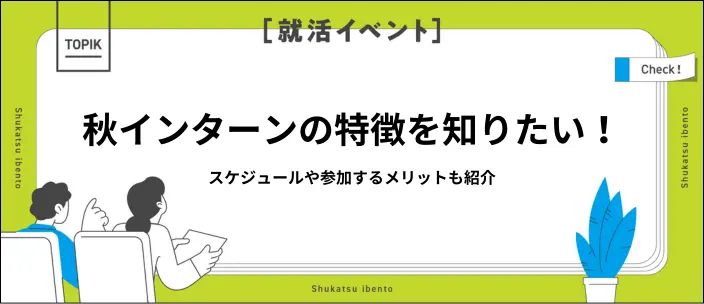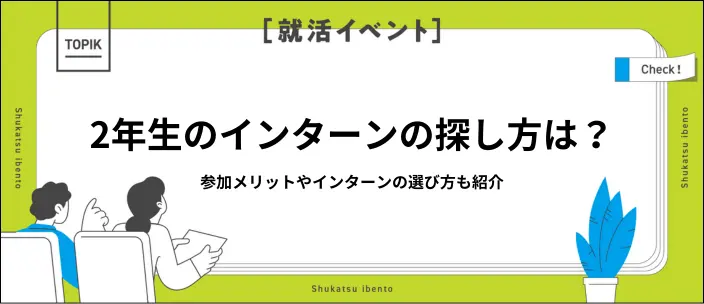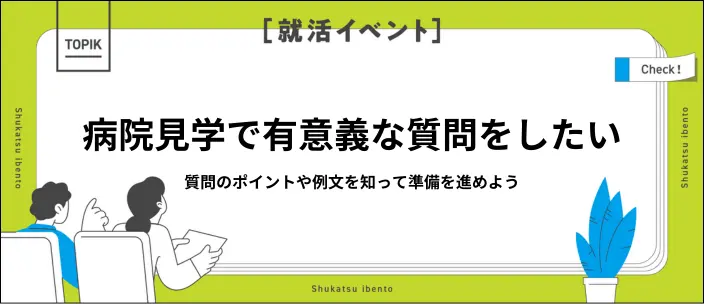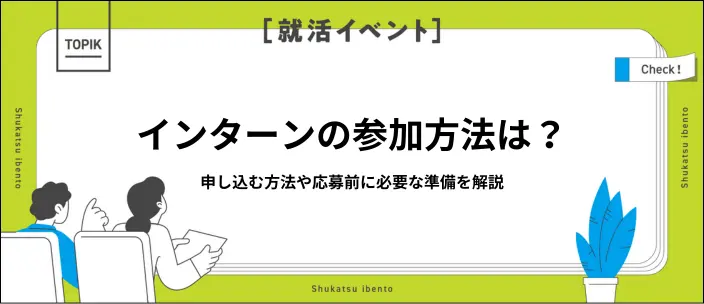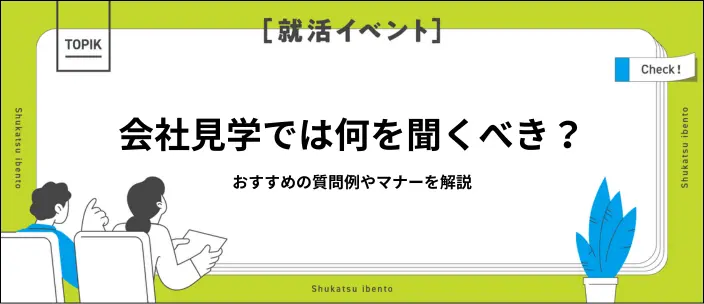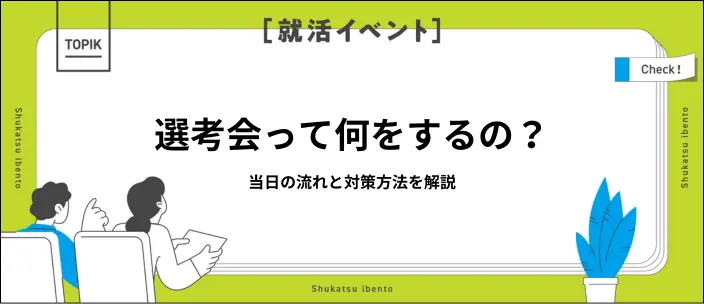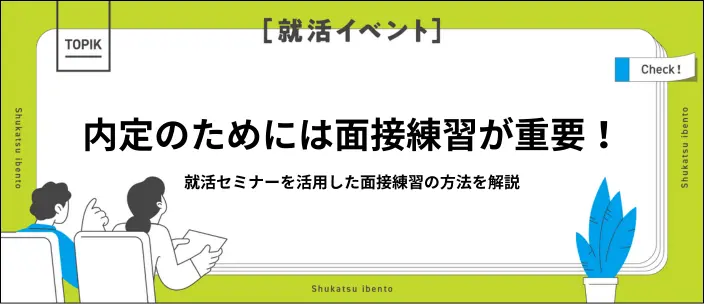このページのまとめ
- 公務員インターンシップは、行政の仕事を体験できる貴重な機会である
- 公務員インターンシップは、志望動機の具体化や人脈形成など就職活動にも役立つ
- 実施時期は夏・冬が中心で、大学経由や自治体の公式サイトから申し込みできる

公務員のインターンシップは、実務を体験し業務理解を深める貴重な機会です。公務員のインターンシップは、中央省庁や地方自治体が実施しており、業務内容の理解だけでなく、将来の進路を考えるうえで関心を持つ方は多いでしょう。
この記事では、インターンシップに参加する5つのメリットと注意点を解説します。また、志望動機の構成や例文もあわせて紹介するので、応募を検討している方はぜひ参考にしてください。
かんたん1分!無料登録インターンシップについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 公務員インターンシップとは?民間との違いを解説
- 公務員インターンシップの種類
- 国家公務員
- 地方自治体
- 公務員インターンシップの実施内容
- 体験型
- 座学型
- 公務員インターンシップのスケジュールと流れ
- 公務員インターンシップの実施時期と申し込み方法
- 公務員インターンシップ参加までの流れ
- 公務員インターンシップの探し方
- 大学の就職支援課に聞く
- 省庁や自治体の公式サイトで調べる
- 公務員インターンシップに参加する5つのメリット
- 1.公務員の仕事を体験できる
- 2.志望動機に活かせる
- 3.職場の雰囲気が分かる
- 4.人脈づくりができる
- 5.試験勉強のモチベーションが上がる
- 公務員インターンシップに参加する際の注意点6つ
- 1.厳しい選考に勝ち抜く必要がある
- 2.報酬・交通費が支給されないケースが多い
- 3.希望部署に配属されるとは限らない
- 4.情報の取り扱いに注意する
- 5.内定には直結しない
- 6.大学の推薦状を求められる場合がある
- 公務員インターンシップ選考の通過率を高めるコツ6つ
- 1.インターンシップに参加する目的を明確にする
- 2.なぜ民間企業ではなく公務員なのか理由を述べる
- 3.志望する省庁・自治体を選んだ理由を見つける
- 4.自分の強みをどのように活かせるかを伝える
- 5.説明会やセミナーに参加して情報収集する
- 6.小論文対策をする
- 公務員インターンシップの志望動機構成
- 結論
- 根拠
- 将来どうなりたいか
- 結論
- 公務員インターンシップの志望動機理由
- 市民の支援
- 地域の活性化
- 都市の発展
- 公務員インターンシップに応募する志望動機の例文
- 1.官公庁向けの例文
- 2.官公庁向けの例文
- 3.県庁向けの例文
- 4.地元の市役所向けの例文
- 5.地元以外の市役所向けの例文
- 公務員インターンシップに参加したい方へ
公務員インターンシップとは?民間との違いを解説
公務員のインターンシップとは、中央省庁や地方自治体が主催する実務体験型プログラムです。国家公務員(中央省庁職員や自衛官など)と地方公務員(市役所職員や警察官など)の両方の業務を体験でき、進路検討に役立ちます。
キャリアチケットの「2026年入社予定学生のサマーインターン参加意識に関する調査」では、サマーインターンの希望参加数で最も多かったのは2〜4社で約半数でした。1社と答えた学生は2.6%のみで、ほとんどの学生が複数社のインターンシップ参加を予定しています。
公務員のインターンシップは、夏季や冬季に開催され、期間は数日〜2週間が一般的。座学または体験型での実施が基本ですが、長期間のインターンシップでは業務への参加機会が増え、職員との関わりを通じて職場の雰囲気をより深く理解できます。
公務員のインターンシップは内定に直結せず、大学などを通じて申し込む必要がある場合もあるので、事前に募集要項の確認が欠かせません。また、スケジュールや提出書類の準備に時間を要する可能性もあるため、早めの行動が大切です。
一方、民間企業のインターンシップは「内定につながる可能性がある」「個人で申し込める」「参加にあたって選考がないケースもある」などが特徴。民間企業と公務員の違いについては、「民間企業と公務員の違いは何?特徴や仕事内容をご紹介!」の記事も参考にしてください。
また、インターンシップについては「インターンシップとは?行う意味や期間別の特徴をご紹介」の記事をご覧ください。
参照元
キャリアチケット
2026年入社予定学生のサマーインターン参加意識に関する調査
かんたん1分!無料登録インターンシップについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員インターンシップの種類
公務員のインターンシップは、国家公務員と地方公務員に分類され、それぞれ実施機関や体験できる業務内容が異なります。国の政策に関わるものから、地域住民に寄り添った行政まで幅広く、関心のある分野や将来の進路に応じて選ぶことが重要です。
ここでは、それぞれの特徴や実施内容について紹介するので、参考にしてください。
国家公務員
国家公務員のインターンシップは外務省や財務省などの省庁で実施され、日本全体の政策や制度設計に触れられます。期間は1日〜2週間程度で、業務説明や職員との座談会が中心です。各省庁で開催されるインターンシップは、行政の仕組みに関心があり、広い視野で社会課題に取り組みたい学生に適しています。
地方自治体
地方自治体のインターンシップは、都道府県や市区町村が主催し、地域に密着した行政サービスを体験できる点が特徴です。子育て支援や福祉、防災などの実務に触れながら、地域課題への理解を深められます。地方自治体で開催されるインターンシップは、「地元で働きたい」「地域貢献をしたい」と考える学生に向いているでしょう。
公務員の種類については、「公務員の種類とは?主な職種や試験の難易度を一覧で分かりやすく解説」の記事も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録インターンシップについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員インターンシップの実施内容
公務員のインターンシップでは、参加する機関や実施期間によって体験できる内容が異なります。主な形式は、実際の業務に関わる体験型と業務説明や座談会を中心とした座学型の2種類です。
ここでは、それぞれの特徴や違いについて詳しく解説します。自分に合ったインターンシップを選ぶ際の参考にしてください。
体験型
体験型のインターンシップでは、実際の業務の一部に関われるだけでなく、職員のサポートや資料作成などを通じて、実際の業務と現場の雰囲気を体感できます。働き方や組織の動きが具体的に見えるため、公務員としての実務に対する理解を深めるのに適しているでしょう。
体験型は配属される部署によって体験できる内容が異なるため、事前に詳細を確認しておくことが重要です。
座学型
座学型のインターンシップでは、職員による業務説明や講話、質疑応答などを通じて行政の役割や政策決定の流れを学べます。業務の背景や仕組みを体系的に理解できるため、公務員の仕事全体を把握したい学生に適した内容といえます。
座学型は、短期間で公務員の業務概要をつかみたい場合にも有効なプログラムといえるでしょう。
インターンの種類については「インターンの種類はどれを選ぶ?目的・時期別に解説」の記事で解説しています。公務員だけでなく一般企業のインターン参加を検討している方は参考にしてください。
かんたん1分!無料登録インターンシップについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員インターンシップのスケジュールと流れ
公務員のインターンシップは、夏季や冬季の長期休暇にあわせて実施されます。参加を希望する場合は、事前にスケジュールを確認し、余裕を持って準備を進めることが重要です。
ここでは、インターンシップの実施時期や申し込み方法、当日までの流れについて詳しく解説します。
公務員インターンシップの実施時期と申し込み方法
公務員のインターンシップは、各機関が独自に日程を設定しています。個人応募と大学経由での応募の2種類があり、省庁によっては所属大学を通じた応募しか受け付けていない場合もあるため、希望する機関の募集要項をよく確認し、適切な手続きで申し込みましょう。
また、実施時期は、長期休暇にあたる夏季や冬季を中心に実施されます。開催時期や期間、申し込み方法は実施機関によって異なるため、インターンシップを希望する場合は、情報を早めに確認しておくことが大切です。
申し込み時の注意点
公務員のインターンシップでは部署ごとに応募条件が定められている場合があります。学部や学年が限定されるケースもあるため、条件の確認が大切です。
また、インターンシップ期間中は終日拘束される日程もあるため、事前にスケジュールを調整し、学業やほかの予定との重複がないよう注意しましょう。参加に向けた準備をスムーズに進めるには、早めの情報収集が欠かせません。
公務員の仕事内容については、「公務員の仕事内容とは?種類と職種別でご紹介!」の記事を参考にしてください。また、「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事もご覧ください。
公務員インターンシップ参加までの流れ
公務員のインターンシップへの参加には、応募から参加決定までにいくつかのステップがあります。一般的には、まず大学を通じて応募し、書類選考を経て結果が通知され、正式に参加が決定。省庁や自治体によって詳細は異なるため、募集要項の確認が必要です。
かんたん1分!無料登録インターンシップについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員インターンシップの探し方
公務員のインターンシップは、民間企業のように一括で掲載されているわけではなく、各省庁や自治体が個別に情報を発信しています。そのため、希望する機関の情報収集が大切です。
ここでは、公務員のインターンシップを探すための方法について解説するので、ぜひ参考にしてください。
大学の就職支援課に聞く
公務員のインターンシップについては、大学の就職支援課を通じて情報を得られるケースが多いため、最初に確認しておくと安心です。過去の参加実績や申込方法に関する情報を得られるほか、自分の志望に合った機関を紹介してもらえる可能性もあります。
大学を通じた応募が必要なインターンシップもあるため、早めの確認が重要です。迷ったときは相談窓口を積極的に活用するとよいでしょう。
省庁や自治体の公式サイトで調べる
公務員のインターンシップの情報は、各省庁や自治体の公式サイトでも随時公開されています。最新の募集情報を見逃さないよう、興味のある機関の公式サイトは定期的に確認しましょう。
たとえば、内閣官房の「国家公務員 CAREER GUIDE」では、内閣府や警察庁など、複数省庁のインターンシップ情報が掲載されています。
しかし、応募期間が短く設定されている場合もあるため、こまめな確認が必要です。希望する分野や地域が明確であれば、優先的に対象機関の情報を探すと効率的に探せるでしょう。
参照元
内閣官房
国家公務員CAREER GUIDE 職場体験イベント情報特設サイト
かんたん1分!無料登録インターンシップについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員インターンシップに参加する5つのメリット
公務員のインターンシップは、実際の行政業務に触れながら将来の進路を考える貴重な機会です。職場の雰囲気や仕事の理解を深めるうえで多くのメリットがあります。
ここでは、公務員のインターンシップに参加することで得られる5つのメリットを解説するので、ぜひ参考にしてください。
1.公務員の仕事を体験できる
公務員のインターンシップに参加するメリットとして、公務員の仕事を実際に体験できる点があります。公務員といっても、窓口業務や現場対応、行政委員会など、配属先によって仕事内容はさまざま。そのため、「公務員=安定」といったイメージだけで進路を決めてしまうと、配属後にミスマッチを感じる可能性もあります。
普段の生活では触れることの少ない業務内容を知ると、自分に合っているかを具体的に判断できます。業務内容と自身の適性とのギャップをなくすといった意味でも、公務員のインターンシップへの参加は有意義といえるでしょう。
就活では企業研究や業界研究が欠かせません。その理由を「業界・企業・職種の研究はなぜ重要?就活を効率的に進めるための基礎知識」の記事でまとめているので、併せてご覧ください。
2.志望動機に活かせる
公務員のインターンシップに参加すると、志望動機の完成度に活かせる点もメリットの一つです。実際の業務を体験した感想や職員の声から得た気づきを志望動機に盛り込むことで、自分だけの具体的なエピソードを含んだ内容に仕上がります。
公務員試験においても、志望動機は多くの場面で質問される項目の一つです。「どの部署で、どのような仕事に携わりたいか」「その理由は何か」といった問いに対して、インターンシップでの経験があると説得力のある回答がしやすくなります。
Webサイトや説明会では得られない現場の情報を取り入れることで熱意が伝わる志望動機が作成しやすくなり、よりよい評価も期待できるでしょう。
3.職場の雰囲気が分かる
公務員のインターンシップに参加すると、職場の雰囲気が分かる点もメリットです。職場の雰囲気や働く人々の人柄が自分に合うかは、就職先を選ぶうえで重要な要素の一つです。しかし、公務員の場合は民間企業に比べてOB・OG訪問や職場見学の機会が限られており、実際の職場環境を知る手段が少ない傾向にあります。
公務員のインターンシップでは、職員とともに実務を経験するなかで、職場の雰囲気や業務の進め方を肌で感じることが可能です。また、他部署との連携の様子を間近で見る機会もあり、組織内での関係性や異動の傾向など、外部からは見えにくい内部の事情も理解しやすくなります。
関心のある省庁や自治体があれば、積極的に情報を収集し、応募を検討するとよいでしょう。
4.人脈づくりができる
公務員のインターンシップに参加すると、人脈を築ける可能性があります。現場で働く職員と直接関わるなかで、就職活動に役立つ情報を得られることもあるでしょう。
また、インターンシップ中に接点のあった職員が、採用面接で面接官を務めるケースもあります。知っている相手が面接官であれば、緊張が和らぎ、自分の考えを落ち着いて伝えやすくなるかもしれません。事前に顔を知っている担当者がいることで、試験本番でも安心感を得やすくなるでしょう。
5.試験勉強のモチベーションが上がる
公務員のインターンシップへの参加は、公務員試験の勉強を続けるうえでの意欲向上にもつながります。公務員試験は難易度が高く、長期間にわたる学習が求められるため、途中で気力が続かなくなることも少なくありません。
そのような状況で、インターンシップを通じて理想のキャリア像を具体的に描けるようになると、目標に向かって努力を続ける意識が自然と高まります。「公務員になりたい」といった想いを明確に持ち続けるうえでも、インターンシップはよいきっかけとなるでしょう。
インターン以外にも就活に関するイベントは開催されています。「就活イベントのメリット・デメリットとは?参加前に知っておくべきこと」の記事もご覧ください。
かんたん1分!無料登録インターンシップについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員インターンシップに参加する際の注意点6つ
公務員のインターンシップは、職場の雰囲気や業務内容を実際に体験できる貴重な機会ですが、民間企業とは異なる点にも注意が必要です。
ここでは、公務員のインターンシップに参加する際の注意点を6つ紹介するので、ぜひ参考にしてください。
1.厳しい選考に勝ち抜く必要がある
公務員のインターンシップに参加するためには、選考を通過しなければなりません。特に国家公務員の場合は応募倍率が高く、省庁によっては受け入れ人数に限りがある可能性も。
また、地方公務員であっても、自治体によって受け入れ枠が限られており、希望者が多い場合には選考が行われるのが一般的。国家公務員や人気自治体のインターンシップは、希望すれば誰でも参加できるわけではないので、あらかじめ募集要項を確認し、早めの準備が大切です。
インターンシップの選考対策については、「インターン選考とは?基本的な情報や突破に向けて対策を解説!」の記事も参考にしてください。
2.報酬・交通費が支給されないケースが多い
公務員のインターンシップは、基本的に無報酬で実施されることが一般的です。実施機関である官公庁や自治体の運営は税収に支えられており、インターンシップに対して給与や交通費、食事代などが支給されることはほとんどありません。
民間企業でも無報酬のインターンシップはありますが、交通費や昼食代を一部補助するケースも。そのため、公務員のインターンシップは自己負担が大きくなる傾向があります。
特に遠方からの参加を検討している場合には、交通費や宿泊費なども考慮したうえで、無理のない範囲で参加計画を立てることが重要です。
3.希望部署に配属されるとは限らない
公務員のインターンシップは、必ずしも希望する部署で勤務できない点に留意しましょう。民間企業では「△△コース」や「△△職種」など、インターンの内容があらかじめ明示されている場合が多く見られます。
一方で、公務員の場合は「全体△名募集」といった形で、官公庁や自治体単位でまとめて募集されるケースが一般的。業務内容が多岐にわたることから、希望が考慮されることはあっても、希望どおりの職種や部署に配属されるとは限りません。
そのため、インターンに申し込む際は、どのような部署で受け入れがあるのか、希望がどの程度反映されるのかを含め、募集要項を事前によく確認しておくことが大切です。
4.情報の取り扱いに注意する
公務員のインターンシップに参加する際は、個人情報などの機密情報の取り扱いに十分な注意が必要です。特に自治体では戸籍謄本やマイナンバー、住民票など、地域住民の重要な個人情報を日常的に扱っています。
基本的に、インターンシップ生が直接情報に関わる業務を担当する可能性は低いと考えられますが、業務上で知り得る機会が生じてもおかしくないでしょう。
そのため、多くの自治体ではインターンシップ開始時に誓約書を交わし、法令遵守や情報漏洩防止に対する意識を高めることが求められます。インターンシップに参加する際は、公務員としての責任を理解し、慎重な姿勢で取り組むことが重要です。
5.内定には直結しない
公務員のインターンシップは、民間企業と異なり内定に直結するものではありません。参加中の姿勢や取り組みが好印象を与えることはあっても、採用の合否はあくまで公務員試験の結果に基づいて決定されます。
インターンシップで得た経験や知見は、公務員志望の学生にとって貴重な財産となります。選考へ直接の影響はありませんが、業務理解を深め、自分の適性を見極めるよい機会として前向きに活用するとよいでしょう。
6.大学の推薦状を求められる場合がある
公務員のインターンシップでは、大学からの推薦状の提出を求められることがあります。特に、「大学公募型」と呼ばれる形式では、推薦状の提出が前提となっているケースも少なくありません。
推薦状が必要になった場合には、大学のキャリアセンターへの相談が大切です。発行には一定の手続きや日数がかかるため、余裕を持って準備を進めておくと安心です。
かんたん1分!無料登録インターンシップについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員インターンシップ選考の通過率を高めるコツ6つ
公務員のインターンシップは、希望者が多い一方で受け入れ人数が限られているため、書類選考などでふるいにかけられることがあります。選考を通過するためには、応募時の工夫や準備が重要です。
ここでは、通過率を高めるために意識しておきたい6つのコツを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
1.インターンシップに参加する目的を明確にする
公務員のインターンシップに申し込む際は、参加の目的を明確にしておくことが重要です。目的が不明確なままでは、選考書類や面接で熱意や意図を十分に伝えることが難しくなります。自分の意志を整理するために、次のような問いを自分に投げかけてみるとよいでしょう。
・なぜ公務員になりたいのか
・どの分野や業務に関心があるのか
・インターンを通じて得たい経験やスキルは何か
これらの質問に対する答えを具体的に持っておくと、選考の場でも説得力のある志望理由やキャリアの展望を示せます。
2.なぜ民間企業ではなく公務員なのか理由を述べる
公務員のインターンシップ選考では、「なぜ民間企業ではなく公務員なのか」といった視点を明確に伝えることが求められます。志望理由が曖昧な場合、「その目的なら民間のインターンでも実現できるのでは」と受け取られる可能性があるためです。
そのため、志望動機を伝える際には、「公務員として人々の暮らしに貢献したい」「特定の政策分野に関心があり、その現場で経験を積みたい」といった、社会貢献への思いや行政施策への関心を具体的に示すとよいでしょう。
民間との違いをふまえたうえで、公務員として働く意義を言語化できているかが、選考通過のカギとなります。
3.志望する省庁・自治体を選んだ理由を見つける
公務員を志望する理由が固まった後に「なぜその省庁や自治体を選ぶのか」と考えることが重要です。
国家公務員を目指す場合、各省庁にはそれぞれ異なる役割や政策分野があります。自分が関心のある領域と省庁の業務がどのように結びつくかを明確にし、その組織で働く意義を言語化する必要があります。
地方公務員の場合は、共通する業務がある一方で、地域ごとの課題や独自の施策にも違いがあります。ほかの自治体と比較しながら、その自治体を志望する理由を明確にすると、より説得力のある志望動機が生まれるでしょう。
4.自分の強みをどのように活かせるかを伝える
公務員のインターンシップの選考を通過するためには、熱意や関心だけでなく、業務に活かせる自分の強みを伝えることが大切です。応募者の多くが熱意を持っているため、差別化を図るには「どのように貢献できるか」を具体的に示す必要があります。
たとえば、リーダーシップやコミュニケーション能力、課題解決力などを通じて、自身がどのように現場で役立てるかを明確に伝えるとより印象に残りやすくなります。あわせて、強みが発揮された具体的なエピソードを示すと説得力が高められるでしょう。
自己PRのコツについては、「自己PRで強みを伝える例文25選!アピールする際のポイントと一覧も紹介」の記事も参考にしてください。
5.説明会やセミナーに参加して情報収集する
公務員のインターンシップの選考対策として、関連する説明会やセミナーへの積極的な参加が大切です。このような場では、申込方法や選考プロセスといった具体的な情報を得られるだけでなく、実際に働く職員の話を直接聞ける貴重な機会です。
自ら情報を収集し、得た知見をもとに準備を進めると、インターンシップ選考の通過率を高めることが期待できます。
6.小論文対策をする
公務員のインターンシップ選考では、エントリーシートや面接に加えて、小論文の提出を求められることがあります。本番の公務員試験では、小論文が課される場合が多く、その対策を兼ねて実施されます。
小論文では、独自性よりも文章の論理性や明快さが重視されるので、限られた字数の中で要点を的確にまとめることが大切です。分かりやすく伝える力が問われるため、書き方や構成を事前に学び、繰り返し練習しておくとよいでしょう。選考で小論文が課されなかったとしても、公務員試験に向けた有益な準備となります。
書き方のポイントについては、「就活の小論文を書くコツは?上達のための6つの方法を例文とあわせて解説」の記事も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録インターンシップについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員インターンシップの志望動機構成
公務員のインターンシップ選考では、志望動機が評価の大きなポイントとなります。公務員ならではの志望理由やキャリアへの意識を具体的に伝えるだけでなく、動機の構成も重要です。
ここでは、志望動機を作成するために押さえておきたい構成の流れとポイントについて解説するので、ぜひ参考にしてください。
結論
志望動機の冒頭では、インターンシップに応募する理由を明確に伝えることが重要です。たとえば、「公務員として地域や社会に貢献したい」といった思いや「行政の現場を体験し、業務の実態を知りたい」といった意欲がある場合は、その気持ちを端的に表現しましょう。
将来の進路選択に向けて、自分の適性を見極めたいといった意図もあわせて記載すると、目的意識のある印象を与えられます。
根拠
次に、そのような志望動機に至った背景を具体的に記述します。大学で学んだ公共政策の内容や、地域活動を通じて行政の仕事に触れた経験がある場合は、志望の理由を結びつけると、説得力のある背景を示すことが可能です。
実際に現場で働く公務員の姿を見て、「自分もこのような立場で地域の役に立ちたい」と感じた経験を交えると、志望動機に説得力が生まれます。これまでの学びや体験と志望理由がつながるように意識するとよいでしょう。
将来どうなりたいか
志望動機では、インターンシップ後のビジョンや将来的な目標にも触れておくと、目的意識の高さが伝わります。たとえば、「行政の実務を体験し、自分に合った分野を見極めたい」といった姿勢は前向きな印象を与えます。
また、「地域の課題に向き合い、住民の声を政策に反映できる職員を目指したい」といった具体的な将来像を示すと、公務員として働く意欲を伝えられるでしょう。
結論
最後に、「インターンシップに参加したい強い意志を改めて表現すると、志望動機としての完成度を高められます。「実践を通じて積極的に学び、公務員として必要な視点を養いたい」といった意欲を明示し、「将来の進路にこの経験を活かしたい」といった姿勢を伝えましょう。
「インターンシップを単なる体験で終わらせず、自らの成長につなげたい」といった前向きな意志が伝わるようにまとめることが大切です。志望動機の作成方法については、「就活の志望動機はどう作る?基本的な構成や例文を解説」の記事を参考にしてください。
かんたん1分!無料登録インターンシップについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員インターンシップの志望動機理由
インターンシップの志望動機を作成するうえで、「なぜ参加したいのか」といった理由の明確化が大切です。ここでは、志望理由を考える際に意識したい視点や内容に深みを持たせるポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
市民の支援
市民の暮らしを支える行政の役割に強く関心を持ち、その現場を体験したいといった思いからインターンシップへの参加を志望する方は少なくありません。
公務員は、福祉・教育・医療など生活に密着した多様な分野で、住民と直接向き合いながら業務に取り組んでいます。インターンシップでは、窓口対応や相談業務を通じて、市民と行政の関係性や信頼構築のあり方を学べるでしょう。
インターンシップの志望動機は、実務の現場に触れ、自分が社会にどのように貢献できるかを考える貴重な機会となります。
地域の活性化
「地域の持続的な発展に貢献したい」といった思いから、公務員のインターンシップに関心を持つ方も多くいます。人口減少や産業の衰退など、地域が抱える課題を解決するために、自治体では観光振興や地場産業の支援、地域イベントの企画など多様な取り組みが行われています。
さまざまな施策の裏側を実際に体験できることは、実務理解を深めるうえで、有意義です。事業の企画や運営に関わる職員の姿に触れ、自分が地域に貢献できるのかを具体的に考える機会となるでしょう。
都市の発展
都市の発展に関わる行政の仕事に興味があり、公務員のインターンシップへの参加を志望する方もいます。都市計画やインフラ整備、防災対策など、都市の安全性と利便性を高める取り組みに関心を持つことは、志望理由として自然です。
インターンシップでは、まちづくりに携わる職員の仕事を間近で見ながら、都市行政に必要な視点や考え方を学べます。現場を体験すると、自分が将来どのように貢献できるのかを考えるよい機会になります。
公務員の志望理由の書き方については、「公務員になりたい理由の書き方は?考える際のポイントや例文を解説」の記事を参考にしてください。
かんたん1分!無料登録インターンシップについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員インターンシップに応募する志望動機の例文
志望動機は、公務員のインターンシップ選考において重視されるポイントの一つです。ここでは、志望する分野別に5つの例文を紹介します。自分の関心や体験に照らしあわせながら、志望動機作成の参考にしてください。
1.官公庁向けの例文
私は、日頃からこの国で暮らす人々の生活を豊かにしたいと考えており、公務員であればこの目標を実現できるのではないかと思い、インターンシップに応募しました。
特に、△△省が推進している政策は、自分が大学で学びを深めている分野と重なるところがあります。そのため、インターンシップを通じて実務的な視点を身につけたうえで、将来的に即戦力として人々の生活に直結する取り組みに携わりたいと考えています。
インターンシップに参加し、実務を体験し、業務内容を理解したうえで自分に何ができるかを考え、少しでも貢献したいと考えております。
2.官公庁向けの例文
私は地域社会の発展に貢献したいといった思いから、公務員を目指しています。そのため、今回インターンシップに応募しました。
大学では都市計画を専攻しており、地域振興について学んできました。△△省が行っている地域活性化の取り組みは、私の学んできた内容と深く関連しているため、実際の現場でどのように政策が実行されているのかを体験したいと思っています。
インターンシップを通じて、政策がどのように立案され、実際に地域にどのような影響を与えているのかを学び、自分の知識を実践に活かしたいと考えています。また、この経験を通じて自分の視野を広げ、より実践的なスキルを身につけたいと思っています。
3.県庁向けの例文
私が△△県庁を志望する理由は、生まれ育った△△県の発展に貢献したいと思ったからです。
△△県は美しい自然環境や豊富な観光資源を持ちながら、その魅力が十分に広まっていないと感じています。名産品もまだまだ知られていないなど、もっとアピールできる部分がたくさんあります。
私は△△県で育ち、その魅力を日々感じてきましたが、全国的にはその価値が十分に伝わっていないことが残念です。もっと県全体での魅力発信や観光資源の活用を進め、△△県のブランド力を高めていきたいと考えています。
具体的には、県庁の取り組みを学びながら、地元の活性化や観光振興に寄与するプロジェクトに関わりたいと思っています。インターンシップを通じて県庁の業務を理解し、地域の発展にどう貢献できるかを具体的に学びたいと思い、△△県庁でのインターンシップに応募させていただきました。
4.地元の市役所向けの例文
私は、自身が生まれ育った△△市がこれまでどのように開発され、今後はどのような未来を目指していくのかに興味があり、インターンシップに応募しました。
特に、商店街の活性化を中心とした町おこし事業にとても興味があり、将来は地域資源の活用による魅力的な観光地の創出に取り組んでいきたいと考えています。
インターンシップでは、実際の仕事を通して、現在行われている施策への理解を深めながら、地元である△△市に少しでも貢献したいと考えております。
5.地元以外の市役所向けの例文
私が△△市役所を志望する理由は、この市が進めている環境保護の取り組みに惹かれたためです。
大学で環境科学を学び、持続可能な都市づくりに興味を持つようになりました。△△市は、再生可能エネルギーの導入やごみの分別推進など、先進的な環境対策を実施していることで知られています。特に、市民と一緒に取り組む環境イベントやワークショップは、市全体で環境意識を高める素晴らしい機会だと感じました。
インターンシップの案内で、環境プロジェクトに参加できると知り、現地での具体的な活動を学びながら、自分の知識を役立てたいと思いました。大学で学んだことを実践し、△△市の環境改善に少しでも貢献できればと考えています。
公務員試験における自己PRの例文については、「公務員試験の自己PRはどう書く?10の例文や評価されるポイントを解説!」も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録インターンシップについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員インターンシップに参加したい方へ
公務員のインターンシップに参加するべきか迷う就活生は少なくありません。インターンシップは、行政の現場を体験できる貴重な機会であり、志望動機の説得力を高める材料にもなります。そのため、公務員を志望している方にとって、インターンシップへの参加はおすすめです。
「志望動機がうまく書けない」「選考を突破できるか不安」といった悩みがある場合は、就職エージェントを活用するのも一つの方法です。
キャリアチケットは、新卒向けに特化したエージェントで、公務員志望の相談にも対応しています。自己分析や業界研究のサポートも受けられるため、不安を抱える方はぜひ相談してみてください。
かんたん1分!無料登録インターンシップについて相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。