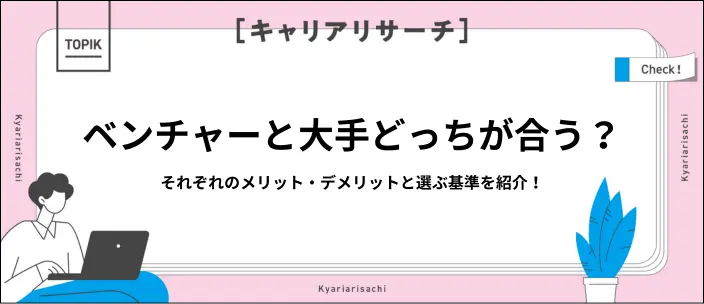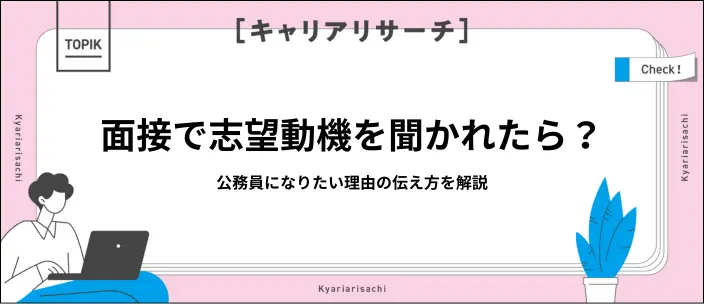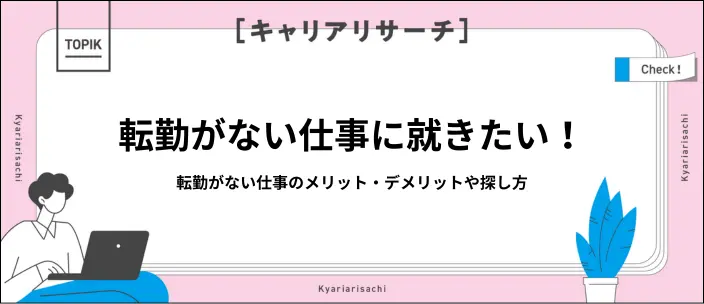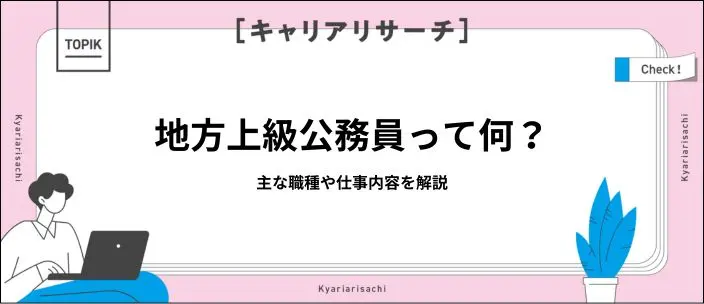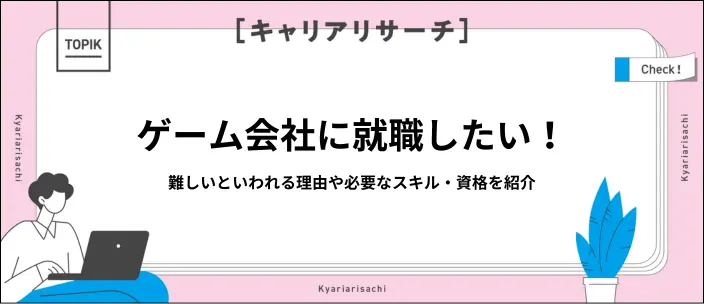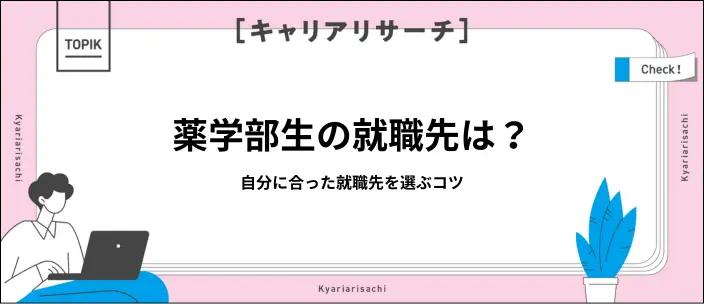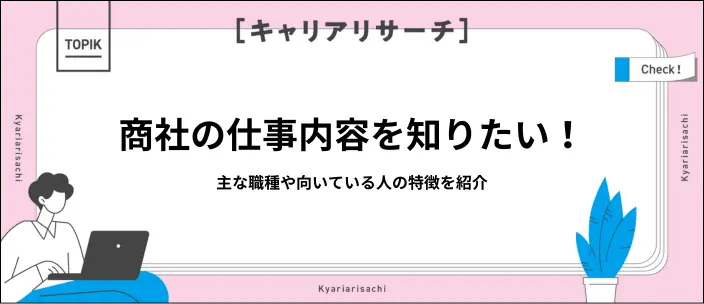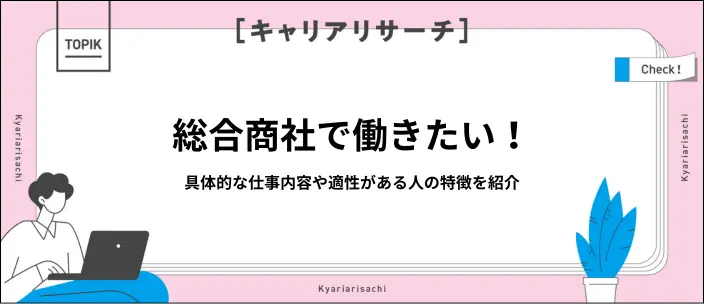このページのまとめ
- 公務員試験合格に必要な勉強時間の目安は1000時間
- 国家公務員を目指す場合、勉強時間は1500時間が目安になる
- 公務員試験の勉強時間を確保するためには、スキマ時間の活用が大事
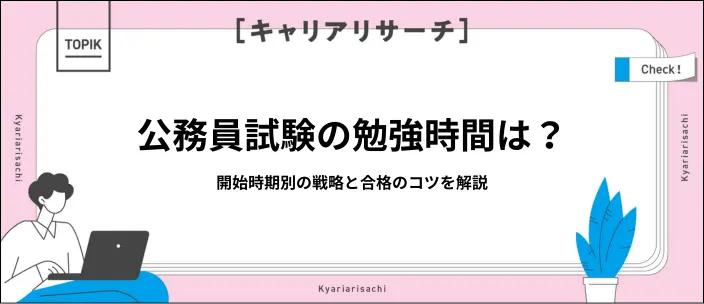
「公務員試験合格には勉強時間はどれくらい必要?」「試験対策はどうすれば良い?」などと悩む学生も多いでしょう。公務員試験合格に必要な勉強時間は1000時間といわれています。試験日までの時間を考え、一日にどの程度勉強すべきか考えてみましょう。
この記事では、公務員試験合格に必要な勉強時間の目安や、試験対策の方法について解説しています。公務員合格を目指したい方は、参考にしてみてください。
かんたん1分!無料登録公務員試験の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 公務員試験に向けた勉強時間の目安
- 公務員試験の勉強時間は1000時間が目安
- 国家公務員の勉強時間は1500時間が目安
- 1年後に試験がある場合の1ヶ月の勉強時間
- 公務員試験の出題科目一覧
- 教養科目
- 専門科目
- 論文試験
- 面接
- 公務員試験を在学中から勉強する場合のポイント
- 大学2年生までは単位取得に注力する
- アルバイトやサークル活動にも参加する
- メリハリをつけて勉強する
- 大学3年生から公務員試験の勉強を始める
- 公務員試験の勉強を始めるのが遅れたときの対策
- 大学4年生になってから開始した場合
- 大学3年生の冬から開始した場合
- 大学3年生の秋から開始した場合
- 公務員試験に向けて勉強時間を確保する方法
- スキマ時間を勉強に使う
- 勉強時間を先に確保しておく
- 試験日から逆算してスケジュールを立てる
- 公務員試験に独学が向いている人
- 公務員試験を独学で突破するための対策
- 問題集を繰り返し解く
- 苦手分野はなくしておく
- 配点の高い問題を優先して対策する
- 集中力アップのためにタイマーを活用
- モチベーションを維持できるようにする
- 試験の最新情報を入手する
- 公務員試験に向けた独学以外の勉強法
- 勉強時間の自由度が高い「通信講座」
- 学習計画が立てられる「通学講座」
- 公務員と民間企業を併願する場合のポイント
- 試験勉強の時間を確保できるように動く
- 民間での面接経験を公務員でも活かす
- スケジュールミスがないように確認しておく
- 公務員試験に必要な勉強時間を知り内定を獲得したいあなたへ
公務員試験に向けた勉強時間の目安
試験区分によって、公務員試験に合格するために必要な勉強時間が異なります。自分が目指す試験に応じた学習計画を立てることが、合格への近道です。
公務員試験の勉強時間は1000時間が目安
公務員試験に合格するためには、約1,000時間の勉強時間を確保するのが目安とされています。これは、地方公務員上級や国家公務員一般職といった大卒程度の試験では、出題レベルが大学入試や大学の専門科目と同程度に位置付けられているためです。
地方公務員上級の教養試験は大学入試レベルの学力が求められ、専門科目では大学で学ぶ分野と同じ水準の問題が出題されます。国家公務員一般職(大卒程度)の試験も、ほぼ同じ難易度と考えて良いでしょう。そのため、基礎知識の理解に加え、過去問演習を繰り返して実践力を養うための学習時間が必要になります。
国家公務員の勉強時間は1500時間が目安
国家公務員総合職試験に合格するには、おおよそ1,500時間の勉強時間を確保することが目安です。
総合職試験は公務員試験の中でも特に難易度が高く、教養試験や専門試験に加え、論文や面接もあります。特に専門試験や論文では、ほかの試験よりも高度な知識や思考力が求められるため、計画的に学習を進める必要があるでしょう。
早めに学習計画を立て、毎日コツコツ取り組むことが合格への近道となります。
難易度が高いとされている地方上級公務員については、「地方上級公務員とは?職種や仕事内容から試験の難易度まで解説」の記事を参考にしてください。
1年後に試験がある場合の1ヶ月の勉強時間
「公務員試験合格に1000時間必要」といわれても、どのくらい勉強すれば良いのか実感が湧かない就活生も多いでしょう。たとえば、1年後の公務員試験合格を目指す場合は、1ヶ月あたり83時間の勉強が必要です。
1日あたりで考えると2時間45分。毎日コツコツと積み重ねていけば、無理なく確保できる勉強時間といえるでしょう。
試験までの期間が短くなるほど、1日に必要な勉強時間は増えていきます。受験までの期間に余裕をもち、計画的に勉強を進めましょう。
かんたん1分!無料登録公務員試験の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員試験の出題科目一覧
公務員試験での出題内容は、大きくわけて「教養科目」「専門科目」「論文試験」「面接」の4つに分けられます。それぞれどのような内容が出題されるのか、合格に向けて確認しておきましょう。
教養科目
教養科目は、「一般知能分野」と「一般知識分野」の2つに分けられます。
| 一般知能分野 | 一般知識分野 |
| 文章理解(現代文・英文・古文) | 社会科学(政治・経済・法律・時事問題) |
| 数的処理(判断推理・数的推理・資料解釈・空間把握) | 自然科学(数学・物理・化学・生物・地学) |
| 人文科学(日本史・世界史・地理・文学・芸術・思想) |
出題レベルは大学入試と同じレベルです。範囲が広いため、優先順位をつけて勉強しましょう。
専門科目
専門科目は国家公務員や都道府県、政令指定都市の公務員試験で必須科目になります。一部の市役所職員でも出題されるケースがあるので、受験前に確認しておきましょう。
・政治、国際
・法律
・経済
・人間科学
・デジタル
・工学
・数理科学、物理、地球科学
・化学、生物、薬学
・農業科学、水産
・農業農村工学
・森林、自然環境
専門科目では、大学の専攻レベルの問題が出題される傾向にあります。「マークシート形式」と「記述式」の2つがあるので、どちらの形式にも対応できるように勉強しておきましょう。
参照元
人事院
2023年度 総合職試験(大卒程度試験)教養区分以外
論文試験
社会や経済などのテーマに対し、自分の意見を伝える論文試験も行われています。解答時間については「60分から80分」、文字数は「800文字から12000文字」が目安です。
論文試験では分かりやすく簡潔に伝えるのが大切になります。自分なりの考えや切り口から論述し、論理的な文章で伝えましょう。なお、論文試験での対策では、自分の書いた文章を読んでもらい、添削を受けることが有効です。何度も文章を書き、より分かりやすく、具体的な内容を伝えられるように練習しておきましょう。
面接
公務員試験でも、面接が実施されます。筆記試験に合格した受験者のみに行われるケースが多いので、まずは筆記試験の対策を行いましょう。
面接では、以下のような質問が聞かれる傾向です。
・公務員を志望するのはなぜですか?
・△△市(△△県)を選んだのはなぜですか?
・どのような業務に取り組みたいですか?
・自己PRをお願いします
・学生時代に力を入れたことを教えてください
面接対策のポイントは、「就活の面接対策は何をする?具体的な方法とよく聞かれる質問50選」の記事で詳しく解説しています。身だしなみやマナーなども、民間企業と同じようにチェックされるので確認しておきましょう。
かんたん1分!無料登録公務員試験の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員試験を在学中から勉強する場合のポイント
公務員試験を大学在学中から勉強する場合、大学3年生から始めることをおすすめします。ここでは、公務員試験の勉強に取り組むタイミングやポイントを解説するので、合格を目指す方は参考にしてください。
大学2年生までは単位取得に注力する
大学入学時から公務員を目指そうと考えている学生も、まずは単位の取得を目指しましょう。単位が取得できなければ、公務員試験に合格しても卒業できなくなってしまいます。
大学2年生までにある程度単位を取り終えておけば、3年生以降は卒業までに必要な単位数に余裕が生まれるでしょう。公務員試験に向けての勉強時間を確保しやすくなります。
アルバイトやサークル活動にも参加する
学業と両立しながら、アルバイトやサークル活動にも力を入れておきましょう。面接では、「学生時代に力を入れたことは何ですか?」と聞かれるケースもあるからです。
公務員試験だけに注力していると、大学で何に力を入れてきたかを答えづらくなってしまいます。勉強以外の経験も積み、スキルアップや自身の強みを身につけることにも力を入れておきましょう。
「学生時代に力を入れたこと」を答えるコツは、「学生時代のボランティア活動はアピールできる?伝え方のコツと例文を解説」の記事で詳しく解説しています。民間企業でもよく聞かれる内容なので、併願希望の方もアピールに使えるエピソード作りを意識しておきましょう。
メリハリをつけて勉強する
在学中から公務員試験の勉強を始めるには、メリハリをつけて学習することが大切です。たとえば、1週間に1日だけ勉強を完全に休む日を設けたり、1日の中でも気分転換の時間を設けたりすることで、集中力を持続させながら学習を続けることができます。
また、朝の集中しやすい時間帯に重要な科目を学ぶなど、効率を意識した勉強方法もメリハリをつけるコツの一つです。計画的に休憩を取り入れながら、学習を続けましょう。
大学3年生から公務員試験の勉強を始める
公務員試験の勉強は、大学3年生からでも十分に間に合います。公務員試験の勉強時間の目安は、約1000時間。大学3年生から試験勉強を始める場合、前述したように1日3時間程度の勉強で到達できるでしょう。
もし、継続的に勉強を続けるのが苦手なら、「勉強する日を減らし、代わりに勉強する日は1日4時間以上にする」「授業が減ったタイミングで1日5時間勉強し、半年を目安にする」など、短期集中で勉強する方法もあります。自分の特性にあわせて勉強しやすい方法を選んでください。
また、公務員試験の勉強を効率的に進めたい場合は、公務員の種類を把握しておくことも大切です。「公務員の種類とは?職種別の仕事内容や難易度を一覧で分かりやすく紹介」の記事で公務員の種類や試験について解説しているので、あわせてご一読ください。
かんたん1分!無料登録公務員試験の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員試験の勉強を始めるのが遅れたときの対策
公務員試験の勉強開始が遅れても、学習計画や工夫次第で十分に間に合う可能性があります。重要なのは、限られた時間で効率良く得点を稼ぐ方法を考えることです。
公務員試験には目安となる勉強時間がありますが、開始時期によって必要な1日の学習量は変わります。遅れて始める場合は、優先順位を決めて勉強することや、集中できる時間を最大限活用することが試験合格のポイントです。
大学4年生になってから開始した場合
大学4年生になってから公務員試験の勉強を始める場合、通常の勉強時間では足りない可能性が高いため、効率的な方法で学習を進めていくことがポイントです。
たとえば、4月から6月の国家一般職や地方上級試験を目指して勉強を始めても、1日8時間取り組んだとしても合計で約500時間しか確保できません。目安となる1,000時間に比べて半分程度の学習時間にとどまり、周りと同じやり方では合格が難しくなる可能性があります。
試験勉強のポイント:
・全科目をまんべんなく勉強するのではなく、捨て科目を作る
・頻出問題に絞って学習し、効率的に得点を稼ぐ
・過去問や予備校の速習カリキュラムを活用する
これらの工夫によって、限られた時間でも合格に必要な得点を確保できます。大学4年生からでも、公務員試験に間に合わせることは可能です。時間が足りない前提で学習計画を立て、優先順位を明確にして効率的に勉強することが成功のポイントとなります。
大学3年生の冬から開始した場合
大学3年生の冬からでも、公務員試験の勉強は春休みなどの長期休暇を活用すれば十分に間に合う可能性があります。
1,000時間程度の学習時間を確保するには、効率良く時間を使うことが重要です。大学の授業と両立するだけでは必要な時間を確保するのが難しいため、長期休暇を活用してまとまった学習時間を確保することがポイント。
試験勉強のポイント:
・1月から勉強を始める場合、1日6〜7時間の学習が必要
・春休み(2月~4月上旬)に1日10時間勉強すれば、600時間程度を確保可能
・残りの期間(1月・4月・5月)は1日4〜5時間の学習で、合計1,000時間を達成できる
大学3年生の冬からでも、効率的な学習計画と長期休暇の活用、速習カリキュラムの併用によって、公務員試験に間に合う可能性は十分にあります。開始時期が遅くても、工夫次第で合格は十分に狙えるでしょう。
大学3年生の秋から開始した場合
大学3年生の秋から公務員試験の勉強を始めても、十分に合格を目指せる時間があります。10月から翌年6月の試験に向けて計画的に学習すれば、必要な勉強時間を確保できるためです。
試験勉強のポイント:
・1日4〜5時間の学習を継続することで、約1,000時間の勉強時間を達成可能
・半年程度で合格を目指せる速習カリキュラムを提供している予備校や通信講座も活用できる
・限られた期間でも、科目の優先順位を明確にし、効率的に学習することで合格ラインを狙える
大学3年生の秋からでも、公務員試験に間に合わないということはありません。効率的な学習計画と適切な教材・講座の活用によって、十分に合格可能です。
公務員の勉強が遅くなり、どうしても間に合わせるのが難しそうな場合は「公務員試験に失敗したら?その後の選択肢をご紹介」の記事もあわせてご覧ください。
かんたん1分!無料登録公務員試験の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員試験に向けて勉強時間を確保する方法
公務員試験の勉強時間を確保するには、先に勉強時間を確保したり、スキマ時間を活用したりと工夫が必要です。ここでは、勉強時間を確保する方法を3つ紹介します。
スキマ時間を勉強に使う
公務員試験に向けて効率的に勉強するには、移動時間や就寝前などのスキマ時間を有効活用することが大切です。まとまった時間が確保できない場合でも、短時間でも集中して学習すれば、効率的に勉強時間を積み重ねられます。まとめて1時間勉強するのも、30分を2回勉強するのも同じ1時間分の勉強時間です。
スキマ時間を使った勉強のコツ:
・通学中の電車内で教養科目の問題を解く
・アルバイトの休憩時間に暗記や過去問を確認する
・就寝前の30分で暗記科目を復習する
スキマ時間を意識的に活用することで、まとまった時間が取れない日でも効率的に学習時間を確保できます。特に忙しい大学生や社会人受験生にとって、毎日の積み重ねが合格への大きな力となるでしょう。
勉強時間を先に確保しておく
公務員試験に合格するためには、勉強時間を先にスケジュールに組み込みましょう。「空いた時間に勉強しよう」と考えると、思うように時間を確保できず、計画どおりに学習を進められないことが多いためです。先に勉強時間を決めておくことで、日々の学習の習慣化と効率化が可能になります。
たとえば、「1日のスケジュールで、毎日21時〜23時を勉強時間に固定する」と決めたら、遊びやアルバイトなどの予定は、その時間以外に組み込むようにしましょう。勉強時間を先に確保することで、集中して取り組むことができ、効率的かつ計画的に学習できます。
試験日から逆算してスケジュールを立てる
試験日から逆算して、勉強時間のスケジュールを作るのもおすすめです。試験日まで1年ある人と、半年ある人では1日に必要な勉強時間は違います。試験日が近ければ近いほど、1日に必要な勉強時間は増えていくでしょう。「1日に何時間勉強が必要か」を考え、勉強時間を確保してください。
1日単位で決めるのが難しい場合、「1週間で△時間必要」と考え、週で調整する方法もあります。効率的に勉強するためにも、試験勉強を始める前にスケジュールを考えておきましょう。
「公務員の難易度はどのくらい?試験別の合格率や対策のコツを解説」の記事でも、公務員試験の勉強時間の配分について解説しています。こちらもあわせて参考にし、勉強時間を確保しましょう。
かんたん1分!無料登録公務員試験の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員試験に独学が向いている人
公務員試験に独学で挑むことは可能ですが、すべての人に向いているとは限りません。
独学が向いているのは、自分で学習計画を立て、モチベーションを維持しながら進められる方や、特定の分野で学力がある程度備わっている方です。また、通信講座やオンラインリソースを活用して効率よく学習を進めることも、独学で合格を目指す際の大きなポイントとなります。
独学の利点としては、時間や費用の面での自由度が高いことが挙げられるでしょう。一方で、情報の更新や苦手科目の克服が難しいというデメリットもあります。自分に合った勉強スタイルを見極め、必要に応じたサポートも検討することが大切です。
かんたん1分!無料登録公務員試験の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員試験を独学で突破するための対策
上述のとおり、公務員試験は独学でも合格が可能です。ここでは、独学で合格するために必要な対策を6つ解説します。
問題集を繰り返し解く
公務員試験を突破するために、まずは問題集を繰り返し解きましょう。1冊の問題集を繰り返し解き、問題集の内容はすべて解けるようにすることをおすすめします。
問題集を同時に複数用意すると、出題内容の違いによって混乱してしまう可能性が。また、解けない問題をそのまま放置すると、試験で点数を落とす原因にもなりかねません。1冊の問題集が終わったら自分の苦手が分かるはずなので、改めて苦手分野や勉強が足りない分野の問題集に取り組みましょう。
苦手分野はなくしておく
公務員試験を独学で突破するためには、苦手分野を重点的に克服しておくことが重要です。公務員試験は出題範囲が広く、得意分野だけでは安定した得点を確保できません。苦手分野を放置してしまうと、大幅に点数を落とすリスクがあります。
たとえば、数学や論理問題が苦手な場合は、基礎から演習を繰り返して解けるレベルにしておきましょう。法律や経済の分野で不安がある場合も、過去問や参考書を使って重点的に学習します。どの分野も最低限の理解を持つことで、試験で苦手分野ばかり出題された場合にも対応可能です。
独学で公務員試験に合格するには、苦手分野を放置せず、すべての科目で一定の得点を取れる状態を作ることがポイント。得意科目だけで安心せず、苦手分野の対策に力を入れましょう。
配点の高い問題を優先して対策する
試験対策では、特に配点の高い問題や科目を優先して取り組みましょう。たとえば、次のような科目は配点が高くなる傾向にあります。
・数的処理
・文章理解
・社会科学
・憲法
・民法
・経済
範囲の広い公務員試験では、すべての対策が間に合わないこともあるでしょう。そのため、高得点を狙いやすい問題に集中的に取り組み、点数確保を目指すのも一つの方法です。
集中力アップのためにタイマーを活用
合格者の多くが実践している、勉強時間をタイマーで計ることも効率的な勉強方法の一つ。決まった時間で区切りながら効率よく学習を進められるだけでなく、勉強と休憩をしっかり分けることで集中力を維持することが可能です。
たとえば、ポモドーロ・テクニックなどの「25分勉強+5分休憩」のような区切り方で進めると、長時間の勉強でも集中力が続きやすくなるでしょう。
また、タイマーで実際に計測することで自分の勉強時間を把握し、目標に対して進捗を確認するのにも役立ちます。時間管理を意識することで、試験に向けた計画的な学習が叶うでしょう。
モチベーションを維持できるようにする
独学で公務員試験に取り組む場合、モチベーションを維持することが合格への重要なポイントです。
公務員試験は半年~1年以上の長期戦になることが多く、一人で勉強を続けているとどうしてもやる気が下がりやすくなるもの。やる気が低下すると学習効率も落ち、計画どおりに進められなくなるリスクがあります。
モチベーション維持のためには、同じく公務員を目指す友人を作り、進捗を報告しあったり、勉強会を定期的に開催したりして、お互いに刺激を与えあうと良いでしょう。SNSやオンラインコミュニティで情報交換を行い、学習環境を整えることも大切です。
独学で合格を目指す場合、一人で抱え込まず、周囲とつながりながらモチベーションを維持することが成功のポイント。計画どおりに学習を進めるためにも、友人やコミュニティを活用しましょう。
試験の最新情報を入手する
公務員試験の最新情報を入手できるように、情報収集は欠かさないようにしましょう。次のような情報を確認しておいてください。
・試験日程
・試験内容
・業務説明会
・インターンシップ
・試験問題
インターネットはもちろん、友人や知人などからも情報を集め、確認漏れがないように準備しておきましょう。また、近年ではSNSを活用し、情報を伝える自治体もあります。SNSを使った就活のコツは「SNSで行う就活の情報収集とは?効率よく行う方法とメリットを知ろう」の記事で解説しているので、参考にしてください。
かんたん1分!無料登録公務員試験の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員試験に向けた独学以外の勉強法
公務員試験の学習は、独学だけでなく通信講座や通学講座(予備校)を活用する方法もあります。それぞれメリットと注意点があるため、自分に合った方法を選ぶことが重要です。
勉強時間の自由度が高い「通信講座」
公務員試験対策で通信講座を利用すると、自分のペースで効率よく学習できる自由度の高さが大きなメリットです。ただし、学習習慣や計画は自分で管理する必要があります。
通信講座は通学の必要がなく、場所や時間に縛られずに学習できるため、効率的に勉強時間を確保できるでしょう。Web学習サポートのある講座であれば、通勤や通学時間を活用して学習することも可能です。さらに、社会的な状況が変化しても、インターネット環境さえあれば学習を継続できます。
通信講座は、自分のペースで効率よく学習したい人に最適です。一方で、学習の習慣づけや計画作りは自分で行う必要があるため、自己管理が得意な人向けの勉強法といえます。
学習計画が立てられる「通学講座」
公務員試験対策で予備校に通学すると、勉強計画や学習習慣をサポートしてもらえる点が大きなメリットです。ただし、学習時間は通学に縛られるため自由度は低くなります。
通学講座では、専任の講師や担任が個人に合わせた学習プランを作成してくれるため、自己管理が苦手な人でも効率よく学習できるでしょう。さらに、定期的に相談することで学習計画の修正や疑問点の解消が可能です。
通学講座は、学習計画や習慣づけのサポートを受けながら着実に勉強したい人に向いています。一方で自由に学習時間を選びたい人や、自分のペースで進めたい人は、通学の制約を考慮して選ぶ必要があるでしょう。
また、公務員試験を勉強する際は、別途自己PRも考えておきましょう。「公務員試験の自己PR例文12選!書き方のコツや評価につながる強みを解説」の記事で自己PRの書き方や例文を紹介しているので、参考にしてください。
かんたん1分!無料登録公務員試験の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員と民間企業を併願する場合のポイント
公務員だけではなく、民間企業の就活を行う学生もいるでしょう。公務員と民間企業を併願する場合、スケジュールや時間の使い方がポイントです。ここでは、公務員と民間企業の両方を目指す場合のポイントを解説します。
試験勉強の時間を確保できるように動く
公務員と民間企業の両方を受ける場合、勉強時間を確保できるようにスケジュールを考えましょう。公務員試験の開始時期と民間企業の採用時期が重なるためです。
公務員と民間企業両方の内定を狙う場合、就活を行いながら公務員試験の勉強を行うことになります。どちらもおろそかにならないように、それぞれ時間を確保して動くのがポイントです。
民間企業を併願する場合、公務員試験以外にSPIなど適性検査の勉強も必要になります。公務員試験とSPIの違いは「SPIと公務員試験の違いは?ボーダーの目安と対策を効率化するコツ5選」の記事を参考にしてください。
民間での面接経験を公務員でも活かす
民間企業での面接経験は、公務員試験でも活かせるので覚えておきましょう。同じ質問をされる場合もあるので、面接対策は公務員と民間企業どちらの選考にも役立ちます。
また、身だしなみやマナーも、公務員と民間企業どちらでも評価されるポイントです。面接での共通点を意識し、効率的に対策を進めるようにしましょう。
スケジュールミスがないように確認しておく
スケジュールミスが発生しないように、予定は念入りに確認しておきましょう。民間企業の就活では、面接だけではなく、説明会への参加やエントリーシートの準備も必要です。「説明会を忘れていた」「試験日と面接の日程が被った」などの問題が起きないように気をつけてください。
また、民間企業の就活に時間を使い過ぎると、公務員試験の勉強時間が確保できなくなる可能性もあります。両立が難しいと感じたら公務員だけに絞るなど、状況に応じて進路を考える必要も出てくるでしょう。
民間企業も検討する場合は、業界や企業について研究しておきましょう。「業界・企業・職種の研究はなぜ重要?就活を効率的に進めるための基礎知識」と「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事も、あわせて参考にしてください。
かんたん1分!無料登録公務員試験の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
公務員試験に必要な勉強時間を知り内定を獲得したいあなたへ
公務員試験合格に必要な勉強時間は、一般的に1000時間といわれています。国家公務員を目指す場合は1500時間ともいわれるので、難易度によって必要な勉強時間は変わることを覚えておきましょう。
また、公務員試験と並行して、民間企業の内定を目指す就活生もいるはずです。公務員と民間企業を併願する場合、より効率的に就活を行わなければ、試験対策や就活準備が不十分になるので気をつけてください。
公務員試験と民間企業の両方を目指す方におすすめなのが、キャリアチケットです。就職エージェントのキャリアチケットでは、専任のキャリアアドバイザーが就活を効率的に行うサポートを実施します。
自己分析や企業研究、面接対策など、内定獲得に必要な準備を進めたい方は、ぜひお任せください。また、あなたの価値観や希望に応じた企業の紹介も実施しています。公務員試験を目指しながら、民間企業の内定もほしい方は、キャリアチケットに登録してみましょう。
かんたん1分!無料登録公務員試験の対策を相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら