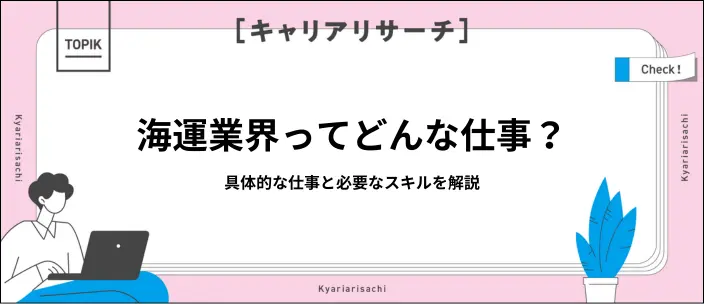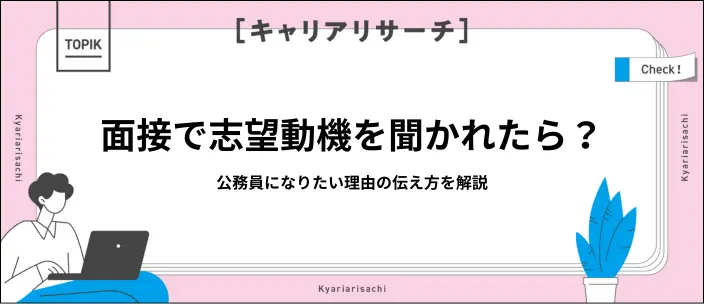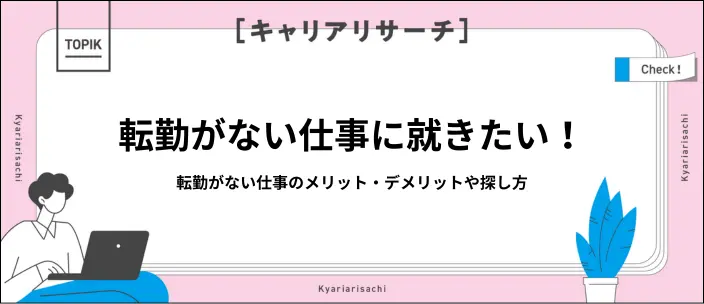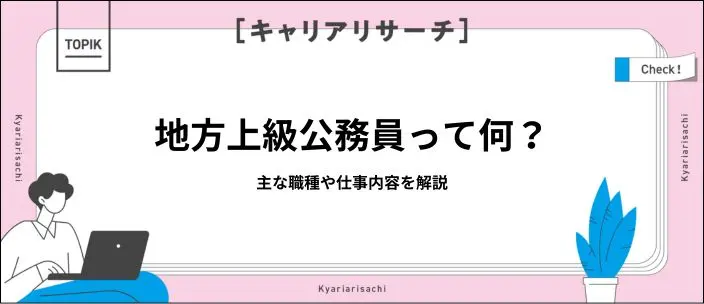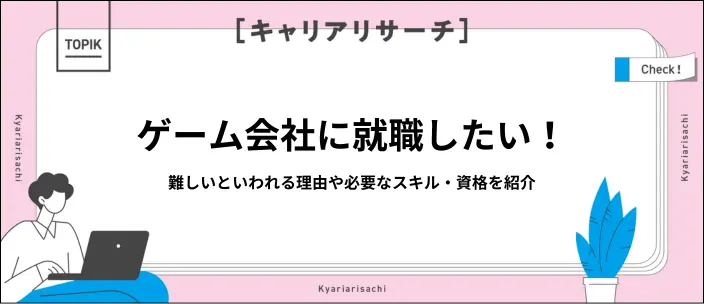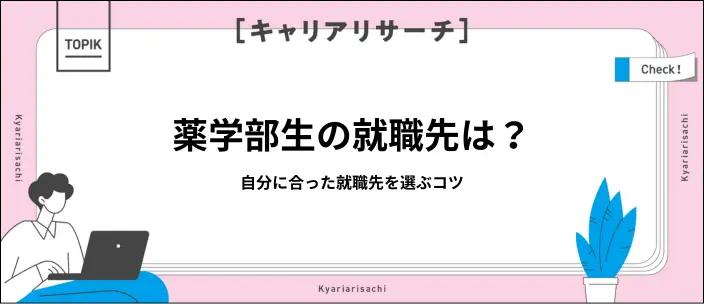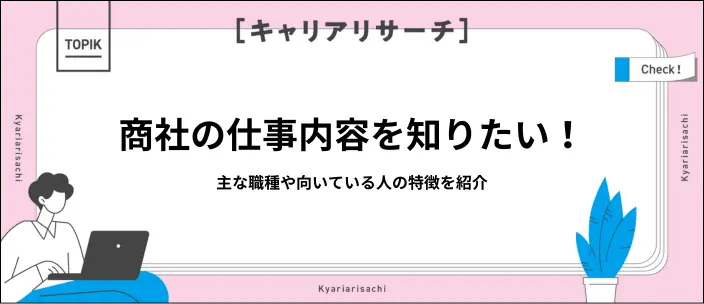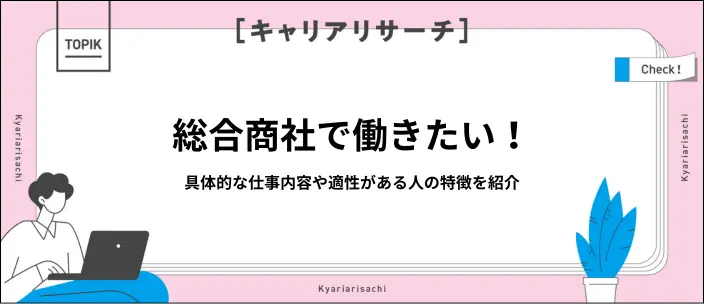このページのまとめ
- 就活で耳にする業界とは「同じ産業に関わる企業の集まり」のこと
- 就活での業界は「メーカー」「商社」「金融」など8つに分類できる
- 就活での志望業界は1つに絞る必要はなく、幅広く興味を持つのも大事

「就活でよく聞く業界ってなに?」「どんな種類があるの?」などと気になる就活生もいるでしょう。業界とは同じ産業に集まる企業のグループを指し、「メーカー」「金融」「マスコミ」などの種類があります。
この記事では、就活で知っておきたい8つの業界を解説。志望業界を探す方法や、絞り方のコツなども紹介しているので、自分に合う企業を見つけるためにも参考にしてください。
かんたん1分!無料登録志望業界の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 就活で業界の絞り方に失敗しないために業種や職種との違いを理解しよう
- 業種の定義
- 業態の定義
- 職種の定義
- 就活で覚えておきたい8つの業界
- メーカー
- 商社
- 小売
- 金融
- サービス・インフラ
- マスコミ(マスコミュニケーション)
- ソフトウェア・通信
- 官公庁・公社・団体
- 就活で業界を絞るメリット
- 自分に合う業界に集中できる
- 就活への負担が減る
- 就活での回答に一貫性が生まれる
- 就活で業界を絞るデメリット
- 業界や企業の選択肢が狭くなる
- 業界全体への理解が浅くなる
- 全落ちするリスクが増える
- 就活における志望業界の絞り方
- 自分が「やりたいこと」から考える
- 自分が「できること」から考える
- 職種を決めてから業界を選ぶ
- 就活における志望業界の絞り方の注意点
- 多くの業界に目を向ける
- 1つの業界に絞る必要はない
- 大学3年生の3月には決めておく
- 業界を理解を深めるための5つのポイント
- 1.ビジネスモデルを理解する
- 2.業界の動向と課題を把握する
- 3.業務内容と働き方を調査する
- 4.給与と待遇を確認する
- 5.得られる知識やスキルを見極める
- 業界研究のおすすめな方法
- 業界本を読む
- 業界研究セミナーに参加する
- 合同企業説明会に参加する
- インターンシップに参加する
- OB・OG訪問を実施する
- 就活で業界について詳しく学びたいあなたへ
就活で業界の絞り方に失敗しないために業種や職種との違いを理解しよう
業界とは、同じ産業に関わる企業の集まりのことです。「メーカー」「商社」「小売」などさまざまな業界があり、業界により取り扱う商品やサービスが異なります。
各業界は、独立して活躍しているわけではありません。ほかの業界と連携して商品やサービスを提供するケースが一般的になります。ここで混同しやすい用語として、業種や業態、職種があります。これらとの違いについても確認しておきましょう。
業種の定義
業種とは、企業が扱う事業の種類です。業界よりも細かく分類され、1つの業界内に複数の業種が存在しています。
たとえば、金融業界は、「銀行業」「保険業」「商品先物取引業」など、複数の業種に分類可能です。1つの企業内でも複数の業種を扱っている場合があるので覚えておきましょう。
業態の定義
業態とは、「どのように商品を売るか」という営業形態で分けた分類のことです。小売業を例にすると、「スーパーマーケット」「百貨店」「コンビニエンスストア」などが業態に該当します。
職種の定義
職種とは、職務の種類のことです。会社内における、個人の役割や仕事内容を指します。たとえば、次のような職種があるので覚えておきましょう。
・営業
・販売
・企画
・マーケティング
・事務スタッフ
・クリエイティブ
・生産
・製造
・品質管理
・研究
・開発
・設計
同じ職種であっても、企業ごとに仕事内容は異なる場合があります。自分が志望する企業でどのような仕事が行われているかは、内定獲得に向けて事前に確認しておきましょう。
職種については、「就活における職種の一覧とは?自分に合う仕事の見つけ方も紹介」の記事で詳しく紹介しているので、参考にしてください。
かんたん1分!無料登録志望業界の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で覚えておきたい8つの業界
就活での業界は、大きく8つに分類できます。それぞれの特徴を解説するので、参考にしてください。
メーカー
メーカーとは、原材料の加工を行い、製品の生産や提供を行う業界です。製造業と呼ばれる場合もあります。主なメーカーには、次のような種類があるのでチェックしておきましょう。
・食品、農林、水産:食材や農林水産物の加工・製造を行う企業
・自動車、輸送用機器:自動車や各輸送機器の製造を行う企業
・素材:繊維、化学、薬品、化粧品などの素材を製造する企業
・機械、プラント:産業機械やプラント設備を製造する企業
・印刷、事務機器関連:印刷機や事務用機器の製造を行う企業
・精密、医療機器:精密機器や医療機器を製造する企業
・鉄鋼、金属、鉱業:鉄鋼や各種金属、鉱産物の製造・加工を行う企業
・建設、住宅、インテリア:住宅や建設資材、インテリア製品を製造する企業
・スポーツ、玩具:スポーツ用品や玩具の製造を行う企業
メーカーが製品を製造するまでには、「研究」「企画」「設計」など複数の工程があります。工程を自社ですべて行うか、一部を他社に任せるかは企業によっても異なるので確認しておきましょう。
メーカーについて詳しく知りたい場合は、「メーカーとは?業務内容や主な職種を解説!商社との違いも」の記事も参考にしてください。
商社
商社とは、メーカーから商品を仕入れて、小売に販売を行う業界です。販売した仲介手数料で利益を得ています。商社は次の2つに分けられるので覚えておきましょう。
・総合商社…分野に関係なく商品やサービスを扱う。事業の幅が広い
・専門商社…特定の分野の商品やサービスを扱う。事業が特化している
総合商社はグローバルに活動している企業が多く、就活生からも人気です。国内外の企業への対応が必要となり、語学力やコミュニケーション能力が求められるので覚えておきましょう。専門商社は特定の分野に特化している点が強みです。それぞれ違いがあるので、事前にチェックして志望動機作成に活かしてください。
商社については、「商社とは?仕事内容や事業など就活生が知るべきポイントをわかりやすく解説」の記事で詳しく紹介しています。
小売
小売とは、メーカーや商社から仕入れた商品を、消費者に販売する業界です。次のような業態に分類できます。
・スーパーマーケット
・コンビニエンスストア
・ドラックストア
・百貨店
・専門店
近年では、ECサイトやスマホアプリのように、インターネットを使ったサービスも増加傾向です。小売業界を目指すのであれば、変化する消費者のニーズを察知し、新しいサービスを生み出す姿勢が求められるでしょう。
小売業界については、「「リテール」の意味とは?営業志望の人はチェック必須!」の記事でも紹介しているので参考にしてください。
金融
金融とは、お金を通じて個人や企業と関わり、経済を支える業界です。金融業界は、主に次の5つに分類されます。
・銀行:預金の預かり、資金の融資、為替取引などを行う
・証券:個人や企業に株式や債券、投資信託、不動産投資信託の売買などを行う
・保険:加入者から保険料を集め、不慮のトラブルにあった加入者に保険金を支払う
・信販(クレジット):預金の受け入れはせず、融資や与信保証を行う
・リース:設備を必要とする企業にレンタルし、リース料を得る
金融業界はお金を扱う業界のため、誠実で信用できる人柄や、専門的な知識を求められます。
サービス・インフラ
サービス・インフラとは、個人や企業にサービスの提供を行い、利益を得る業界です。次のような業種に分類されます。
・不動産:不動産の売買や賃貸、管理を行う企業
・運輸・物流:鉄道、航空、運輸、物流などの交通・輸送サービスを提供する企業
・エネルギー:電力、ガス、エネルギーの供給を行う企業
・フードサービス:レストランやカフェ、フードデリバリーなどの飲食サービスを提供する企業
・観光・宿泊:ホテル、旅行代理店、観光施設などを運営する企業
・医療、福祉:病院、クリニック、介護施設などの医療・福祉サービスを提供する企業
・レジャー・娯楽:アミューズメントパーク、レジャー施設、スポーツクラブなどの娯楽サービスを提供する企業
・コンサルティング:ビジネスコンサルティング、調査、マーケティングなどの専門サービスを提供する企業
・人材サービス:人材派遣、人材紹介、キャリア支援などを行う企業
・教育:学校、塾、オンライン教育サービスを提供する企業
扱っているサービスは、大きくわけて「作ったものを提供する」「情報を提供する」「快適な環境を提供する」の3つに分類可能です。近年は時代の変化に合わせて新しいサービスが生まれ続けており、消費者のニーズを読み取る視点が求められます。
サービス・インフラ業界については、「職種や業種、今後の動向は?サービス業界の概要を知ろう」の記事で解説しています。幅広い分類があるので、あなたがどの分野に興味があるのかチェックしておくといいでしょう。
マスコミ(マスコミュニケーション)
マスコミ業界とは、多種多様な情報を人々に提供する業界です。マスコミは次の3つに分類されます。
・放送:主に電波を通じて情報を発信する
・出版:書籍や雑誌などを作り、情報を発信する
・広告:広告を企画・制作し、広告主に代わってテレビやラジオ、新聞などに出稿する
マスコミ業界は、最新の情報を伝える必要があり、業務が不規則な傾向にあります。また、情報が人々を扇動する恐れもあるため、自律心を持った発信が求められるでしょう。
ソフトウェア・通信
ソフトウェア・通信業界は、情報の伝達や処理に関するサービスを提供する業界です。一般的には、次の3つに分類されます。
・ソフトウェア:システムなどの開発、販売を行う
・インターネット:インターネットを活用したサービスやコンテンツを提供する
・通信:通信機器をつなぐための回線や機器本体の開発と提供を行う
多くの企業がITを活用しており、ソフトウェア・通信業界の需要は高まっている状況です。また、技術の進歩が早い業界になるので、常に新しい知識と技術を学ぶ姿勢が求められます。
官公庁・公社・団体
官公庁・公社・団体は、利益ではなく公益を追求し、民間ではできない公的な事業を行う業界です。官公庁には、「国や地方公共団体の役所」「警察」「日本銀行」などが含まれます。公社、団体には、「公立学校」「病院」「農協」「社団法人」などが含まれるので覚えておきましょう。
また、官公庁の内定を目指す場合、公務員試験の合格が採用の条件となります。一般企業の就活と並行して準備が必要なので、スケジュール管理を行うようにしましょう。
公務員試験合格を目指す方に向けて、「公務員試験合格に必要な勉強時間は?出題内容や試験対策のコツを解説」の記事で勉強の目安を紹介しています。就活が本格化する前から、準備をしておくといいでしょう。
かんたん1分!無料登録志望業界の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で業界を絞るメリット
就活で業界を絞ることにより、1つの業界に使える時間が増えるメリットがあります。業界を絞ることのメリットを詳しく解説するので参考にしてください。
自分に合う業界に集中できる
就活で業界を絞ることにより、自分に合う業界だけに集中できます。就活を効率的に進められ、会社選びや選考対策も楽になるでしょう。
就活では選べる業界が数多く、すべての業界について研究を行うと大変です。自分があまり興味のない業界にまで時間を使い、結局エントリーしないケースも考えられます。
業界を2つか3つ程度に絞っておけば、研究や対策などに多くの時間を使えるでしょう。就活は説明会への参加や選考対策など内定に向けてやるべきことが多いので、効率的に業界研究を行える点はメリットです。
就活への負担が減る
就活に対する負担が減る点も、業界を絞るメリットです。対象の業界が増えるほど業界研究などの負担も増え、就活が大変になってしまいます。
就活で取り組む必要があるのは、業界研究だけではありません。業界研究が終われば企業研究が始まり、選考対策も必要です。
また、就活と並行してアルバイトやサークル、学業を行っている就活生もいるでしょう。業界を絞り、就活への負担を減らすことは、あなたが就活をスムーズに進めるために欠かせません。
就活での回答に一貫性が生まれる
業界を絞ることにより、就活での回答に一貫性が生まれるメリットもあります。業界を選んだ理由が明確にあれば、会社側が納得できる回答ができるでしょう。
どの業界でもよい状態で就活を行うと、「なぜその業界なのか」がないまま選考対策を行うことに。面接で回答した内容に、「ほかの業界でもできるのでは?」「どの業界にも言えることでは?」などと踏み込まれることもあるでしょう。
業界を絞ることで、「△△の理由で、この業界を選んだ」と、根拠のある回答が生まれます。回答に一貫性を持たせるためにも、業界を絞って就活を行うことは欠かせません。
業界を絞るためには、あなたなりの就活の軸を持つことが大切です。就活の軸の考え方を「就活の軸とは?探し方のコツや具体的な方法を例文付きで解説」の記事で紹介しているので参考にしてください。
かんたん1分!無料登録志望業界の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で業界を絞るデメリット
就活で業界を絞ることは、選択肢が狭まるリスクもあります。業界を絞るデメリットについて解説するので、内定獲得に向けて参考にしてください。
業界や企業の選択肢が狭くなる
業界を絞ることにより、業界や企業の選択肢が狭くなってしまいます。たとえば、1つの業界だけに絞ると、該当する会社も少なくなります。仕事内容や職種、働き方などの条件が加わると、エントリーできる会社数はさらに減っていくでしょう。
条件が厳しすぎて、希望する条件を満たす会社がない場合も出てきます。業界を絞ることで、選択肢が狭くなってしまう点はデメリットでしょう。
業界全体への理解が浅くなる
1つの業界だけに集中すると、業界全体への理解が浅くなるデメリットもあります。業界同士はそれぞれ関係性があり、1つの業界だけでは全体を把握することはできません。たとえば、小売が物を売るためには、メーカーが物を作る必要があります。メーカーが物を作るためには、商社から原材料を仕入れなければなりません。
1つの業界だけに絞ってしまうと、ほかの業界の様子がわからず、業界研究が浅くなります。志望業界と関連する業界については、業界研究を行ったほうがよいでしょう。
全落ちするリスクが増える
志望する業界が狭いと、エントリーする会社も減り、全落ちするリスクが高まります。内定を獲得できなかった場合、就活のやり直しが大変になるでしょう。
もし、内定獲得ができず就活をやり直す場合、ほかの業界の選択肢がないため、また1から就活をやり直すことに。「別の業界にも興味を持っていたから、この業界で就活を進めよう」などの方針転換が難しくなります。
内定獲得を目指すためには、全落ちは避けたいところです。就活で全落ちするリスクについては、「就活で全落ちしたらどうする?内定獲得に向けた行動や心構えを解説」の記事も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録志望業界の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活における志望業界の絞り方
就活で志望業界を決める方法には、「やりたいことから考える」「できることから考える」「職種から決める」の3つがあります。それぞれの方法について解説するので、業界選びの参考にしてください。
自分が「やりたいこと」から考える
志望業界を決めるために、まずは自分が何をしたいのかを考えてみましょう。目標や将来の夢が明確になっていると、働きたい業界も見つけやすくなります。
「やりたいこと」を探すためには、自己分析を行いましょう。自分について理解しないと、「やりたいこと」はわからないので気を付けてください。自己分析の方法については、「自己分析とは?おすすめのやり方8選や実施時の注意点を紹介」で紹介しています。
自分が「できること」から考える
自分に何ができるかを考え、業界を選ぶ方法もあります。就活では、「自分ができること」と「企業が求める能力」がマッチした際に、内定が獲得できるからです。
見つけた長所が「コミュニケーション能力が高い」であれば、サービスや商社といった業界で能力を発揮できるかもしれません。また、「自己管理能力が高い」であれば、お金を扱う金融業界で活躍できる場合もあるでしょう。
企業の多くが「求める人物像」を提示しているので、自分の長所がどの業界や企業に適しているかで選ぶのもおすすめです。
職種を決めてから業界を選ぶ
業界を決める前に、職種を選ぶ方法もあります。「どのような仕事をしたいか」から考える方が、選びやすい人もいるでしょう。
職種を決めれば、次にどのようなサービスやものを扱いたいかを考えます。たとえば、営業職を希望する場合、どの業界で営業として働きたいかを具体的に考えます。
また、特定の職種に興味がある場合、その職種にどの業界が強みを持っているかを調べると良いでしょう。たとえば、エンジニアとして働きたい場合、IT業界やメーカーが候補に上がります。自分のスキルや興味にあった業種から選んでも問題ないので、決めやすい方法で選んでみてください。
かんたん1分!無料登録志望業界の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活における志望業界の絞り方の注意点
志望業界の絞り方を間違えると、「エントリーする企業がなくなってしまう」「自分に合わない業界を受け続ける」のように、後々で困る可能性があります。ここでは、志望業界を絞る際の注意点を3つ紹介するので、参考にしてください。
多くの業界に目を向ける
業界を絞る前に、まずは幅広い業界に注目しましょう。最初から特定の業界に絞ってしまうと、選択肢が少なくなってしまいます。
現時点では興味がない業界でも、まずは調べてみましょう。チェックしてみると、「意外に面白そう」「自分の長所が生かせるかもしれない」などの発見があることも。まずはできるだけ多くの業界に興味をもってみてください。
1つの業界に絞る必要はない
志望業界は1つに絞らず、複数もっていても問題ありません。3つほどあれば、エントリーする企業に困ることはなくなるでしょう。
最初から1つに絞ってしまうと、あとから別の業界を目指す場合に、動き出しが遅くなってしまいます。複数業界の企業にエントリーして、より自分に合う業界を探すのもおすすめです。
大学3年生の3月には決めておく
大学3年生の3月ごろには、志望業界を決めておきましょう。3月にはエントリーが開始され、4月にはエントリーシートの提出も行われます。就活が本格化してから志望業界を決める場合、エントリーしたい企業の募集が終わっている可能性が考えられるからです。
また、外資系企業やベンチャー企業の場合は、さらにエントリーが早まります。大学3年生の夏にはインターンの締め切り、秋には選考を開始する企業もあるので気を付けてください。
近年では就活の早期化によりエントリー受付や選考開始の時期が年を追うごとに早くなっています。なるべく早めに受ける志望業界を決めておくとよいでしょう。就職活動のスケジュールについては「就職活動の流れはどう進む?基本的なスケジュールや準備方法を解説」も参考にしてください。早めの準備が肝心なので、余裕をもって動くようにしましょう。
かんたん1分!無料登録志望業界の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
業界を理解を深めるための5つのポイント
業界について調べる際、情報が多すぎて何が重要なのかわからなくなることがあります。そこで、業界理解を深めるための5つのチェックポイントを紹介します。
1.ビジネスモデルを理解する
ビジネスモデルは、企業や業界がどのように収益を得ているかを示します。業界がどのようにして利益を生み出しているか、どのような商品やサービスを提供しているか、そしてどのような顧客層をターゲットにしているかを理解するために、ビジネスモデルを分析することが重要です。
これにより、業界の基本的な仕組みや動向を一目で把握することができます。
2.業界の動向と課題を把握する
業界の動向と課題を把握することは、その業界がどのような状況にあり、どのような問題に直面しているかを理解するために不可欠です。動向を押さえることで、その業界が今後どのように変化し、どのようなスキルや人材が求められているかが見えてきます。
また、業界が直面する課題を理解することは、業界の将来性を判断するためにも重要です。特に、人口減少や高齢化といった社会問題と関連する課題は、業界の持続可能性に大きな影響を与えます。
3.業務内容と働き方を調査する
業界の業務内容や働き方は、就活生にとって非常に重要な情報です。職種によって業務内容が異なるため、自分がどのような職種に興味があるかを考えて情報を収集することが業界選びには欠かせません。
働き方についても、在宅ワークやフレックスタイム制など、自分のライフスタイルに合った企業を選ぶために確認が重要です。また、業務内容が具体的にどのようなものかを知ることで、自分のスキルや適性がどのように活かせるかを判断する材料になります。
業務内容や働き方を調べるためには、企業研究も効果的です。企業研究の進め方は「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事を参考にしてください。
4.給与と待遇を確認する
給与や待遇は企業によって異なりますが、業界によっても大きく異なるため、しっかりと情報収集をしましょう。年収や賞与、昇給に加え、キャリアアップに伴う給与の推移を確認することが重要です。
待遇には、残業時間や年間休日、福利厚生などが含まれます。これらの情報を把握することで、長期的な視点で働きやすい環境を見つけることができます。
5.得られる知識やスキルを見極める
就職後にどのようなスキルや知識が得られるかも重要です。社会人生活は長く、その間に社会も大きく変化します。業界ごとに得られる知識やスキルを理解することで、キャリアの中でどのように成長していけるかを見極めることができるでしょう。
そうすることで、将来的に転職やキャリアチェンジを考える際にも役立つスキルを身につけられます。
かんたん1分!無料登録志望業界の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
業界研究のおすすめな方法
業界について詳しく知るためには、業界研究が必須です。どのようなやり方があるかを知っておきましょう。ここでは、「業界本を読む」「合同企業説明会に参加する」など、業界研究に役立つ5つの方法を紹介します。
業界本を読む
業界について知るために、まずは「四季報」や「業界地図」のような業界本を読みましょう。1冊を繰り返し読み、理解を深めるのがおすすめです。
業界本を選ぶ際は、最新情報が載っている新しい本を選ぶようにしましょう。
業界研究セミナーに参加する
業界研究セミナーに参加し、詳しく学ぶのもおすすめです。業界の指定がない場合や、特定の業界に絞って行われる場合もあるので参加前に確認しておきましょう。
業界研究セミナーでは、その業界に属する企業について詳しく学ぶこともできます。どのような企業があるかを知れば、より業界についての理解を深められるでしょう。業界研究セミナーって何?と思う方に向けて、「業界研究セミナーとは?気になる内容と参加するメリットを解説!」の記事で詳しく紹介しているので参考にしてください。
合同企業説明会に参加する
合同企業説明会では、さまざまな企業の話を聞けます。別の業界や同じ業界内の企業を比較するのにも役立つでしょう。
また、合同企業説明会では、実際に働く社員の方の話を聞けます。Webサイトで調べてもわからなかった内容について、質問してみるのもおすすめです。
合同企業説明会については、「合説ってどんなもの?参加するメリットと有益に過ごすコツ」で詳しく紹介しています。参加する前に、どのようなものか確認しておきましょう。
インターンシップに参加する
インターンシップに参加すれば、説明会よりも詳しい内容を学べます。業界や企業について説明する1dayから、実際の業務を体験できる長期まであるので、内容に応じて参加するインターンシップを選びましょう。
実際に業務を体験すれば、「この業界は自分に合いそう」「業界は好きだけど業務は別のものがいい」などのように、業界や業種を選ぶ参考材料になります。大学3年生の夏ごろから参加できる場合が多いので、チェックするようにしてください。
OB・OG訪問を実施する
OB・OG訪問を実施し、従業員の方の話を聞くのもおすすめです。合同企業説明会よりも詳しい内容を質問できるでしょう。
OB・OGの知り合いがいない場合は、大学のキャリアセンターに相談するのがおすすめです。卒業生を紹介してもらえる場合があります。
かんたん1分!無料登録志望業界の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活で業界について詳しく学びたいあなたへ
就活を成功させるためには、業界について詳しく知っておくのが重要です。業界への理解を深めれあ、自分に合う合わないがわかり、より適した企業に就職できるでしょう。
しかし、業界は種類が多く、調べる内容も決まっておらず大変です。「業界研究はどうやって進めればいいの?」と思う就活生も多いでしょう。
業界研究の進め方に悩む場合は、ぜひキャリアチケットに相談してください。就活のプロであるアドバイザーが、業界研究の進め方をサポート。あなたに合う業界を見つける手助けを行います。
また、業界研究のサポートだけではなく、あなたの適性や興味に合った会社も紹介可能です。キャリアチケットに登録して、自分に合う企業探しを実現し、内定を獲得しましょう。
かんたん1分!無料登録志望業界の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。