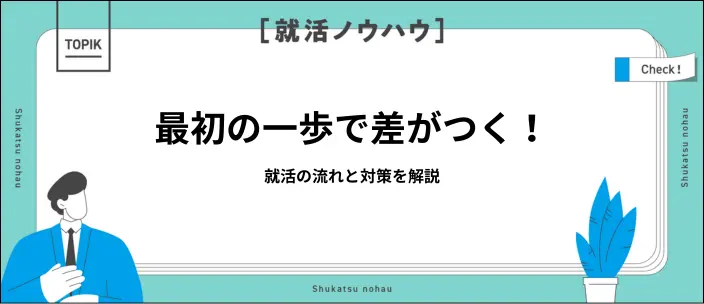このページのまとめ
- 就活の相談先は「家族」「友人」「就活エージェント」などがおすすめ
- 相談内容に合わせて相手を選ぶと、より効果的なアドバイスが期待できる
- 就活相談の機会を最大限に活かすためには、自己分析や質問の整理などの事前準備が大切

「就活の悩みは誰に相談すべきか」と迷ってしまう就活生も多いでしょう。第三者に悩みを相談すると、視野が広がって就活をスムーズに進めやすくなります。相談したい内容に応じて、家族や友人、就活エージェントなどに話を聞いてもらいましょう。
この記事では、おすすめの相談先や相手選びのポイントを解説します。就活の相談をするメリットや注意点もまとめているので、悩みを解消するための参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 就活の相談におすすめの相手15選
- 1.家族
- 2.友人
- 3.サークルやアルバイトの先輩
- 4.大学のキャリアセンター
- 5.大学教授
- 6.OB・OG
- 7.新卒応援ハローワーク
- 8.就活カフェ
- 9.経営者
- 10.就活エージェント
- 11.スカウト型求人サイト
- 12.LINEのオープンチャット
- 13.掲示板や就活口コミサイト
- 14.就活塾
- 15.就活コンシェルジュ
- 就活相談の重要性についてキャリアアドバイザーからのアドバイス
- 就活の相談をする4つのメリット
- 1.就活に対する不安を解消できる
- 2.就活に必要な情報を入手できる
- 3.第三者の意見を取り入れられる
- 4.自分の考えや思いを言語化できる
- 就活の相談に必要な4つの準備
- 1.自己分析を行う
- 2.質問する前に自分で調べる
- 3.質問する理由を整理する
- 4.相談内容に適した相手を見極める
- 就活の状況別|おすすめの相談先
- 悩み別|就活の相談で聞くこと一覧
- 就活の進め方
- 自己分析の仕方
- 企業の選び方
- 選考対策
- 就活の相談をしたほうが良い就活生の4つの特徴
- 1.就活で何をすべきか分からない
- 2.自分に合う就職先が分からない
- 3.内定獲得に向けてレベルアップしたい
- 4.1人で就活をするのがしんどい
- 就活の相談をする際の注意点
- 得た情報を鵜呑みにしない
- 自分とは考えが合わない相談相手もいると理解する
- 相談する人数は数名に絞る
- 活かす前提で相談する
- 就活の基本マナーを押さえる
- 就活相談をして内定獲得に近づきたいあなたへ
就活の相談におすすめの相手15選
就活の相談をする相手は、慎重に選ぶ必要があります。自分のことや就活について知らない人に相談しても、悩みや不安は解決しない可能性が高いでしょう。
ここでは、就活の相談におすすめの相手を紹介します。それぞれの特徴やポイントを理解しながら、自分に合った相談先を考えてみてください。
1.家族
就活においてメンタル面での悩みがある場合は、まず家族への相談がおすすめです。自分をよく理解してくれている分、安心して相談できます。就活のアドバイスをもらうというよりは、愚痴や悩みを聞いてもらうことで、気持ちが軽くなる効果があるでしょう。
また、就活経験のある家族がいる場合は、就活の進め方についてアドバイスをもらえる可能性もあります。体験談を聞いて、どのように内定を得たか聞いてみましょう。
2.友人
一緒に就活している友人も、相談相手としてふさわしい場合があります。同じ状況を分かち合えるため、就活の悩みを相談しやすいのが特徴です。
就活のモチベーションを維持するためにも、仲間や友人の存在は欠かせません。ただし、友人の状況を聞いて落ち込んでしまう可能性もあるので、人と比べてしまいがちな人は注意が必要です。
「友人は内定をもらっている」「自分だけがうまくいかない」などと考えてしまうと、相談しにくくなります。モチベーションを高めるためにも、前向きな姿勢で相談できる友人を選びましょう。
3.サークルやアルバイトの先輩
サークルやアルバイトの先輩など、就活を経験した人に相談するのも良いでしょう。志望する企業や同じ業界に就職が決まっていたり、すでに働いていたりする先輩がいると、より具体的な選考対策を聞ける可能性があります。
先輩のなかに、志望する企業に就職した人がいない場合は、先輩の友人を紹介してもらうのも方法の一つです。ただし、就活の状況は一人ひとりで異なるため、先輩のアドバイスだけを信じるのは避けましょう。
先輩が就職できたからといって、必ずしも同じ方法で自分の就活がうまくいくとは限りません。何人かの先輩の話を聞いたり、ほかの人にも相談したりして、総合的に判断することが大切です。
4.大学のキャリアセンター
大学のキャリアセンターでは、就活の進め方や面接対策、書類の書き方などのさまざまなアドバイスをもらえます。就活支援が専門の場所なので、気軽に利用できるのが特徴です。
また、大学のキャリアセンターが就活セミナーや懇談会、講演会などを主催するケースも。自分の悩みに合わせて、うまく活用してみましょう。
5.大学教授
大学教授も、就活を相談する際の選択肢に入ります。大学教授のなかには専門分野の幅広い知識と経験を持っているだけではなく、業界のトレンドや需要の変化にも詳しい人もいるでしょう。大学教授に就活の相談をすると、志望する業界や企業についての具体的なアドバイスが期待できます。
しかし、実際には修士、博士と進んで大学教授になった人もいるので、大学教授に就活相談するときは、社会人経験が豊富な教授に話を聞いてもらうのがおすすめです。
6.OB・OG
就活で困ったときは、社会人の先輩にあたるOBやOGにも相談できます。OB・OG訪問を通じて、就活の進め方や志望企業の採用傾向などを聞くことが可能です。
もし、部活や学部の先輩に心当たりがある場合は、連絡を取って話を聞けないか確認してみましょう。知り合いに志望企業のOB・OGがいない場合は、大学のキャリアセンターに問い合わせると紹介してもらえます。
OB・OG訪問は、相手に失礼のないようにマナーを守って行いましょう。OB・OG訪問の進め方については、「OB訪問ってどうやるの?アポ取りから進め方まで徹底解説!」の記事も参考にしてください。
7.新卒応援ハローワーク
新卒応援ハローワークとは、大学や大学院、短大、高専、専修学校などの学生や、これらの学校を卒業した人のためのハローワークです。就活に関する悩みも無料で相談できます。
新卒応援ハローワークの特徴は、新卒の就職活動に特化した職員が担当につき、支援してもらえる点です。不安や悩みがある場合には、臨床心理士から心理的なサポートも受けられます。各都道府県にあるため、自宅に近いところを確認してみましょう。
参照元
厚生労働省
新卒応援ハローワーク
8.就活カフェ
就活で悩んだときは、就活カフェで話を聞いてもらうのもおすすめです。就活カフェとは、企業が運営している就活生向けのカフェで、学生同士が交流したり、在籍しているカウンセラーに話を聞いてもらえたりします。
就活カフェのメリットは、無料で電源やWi-Fiを使用でき、就活準備などにも利用しやすい点です。また、就活カフェを運営している企業が主催のイベントを紹介してもらえる場合もあります。
学生同士が気軽に交流できる雰囲気なので、一緒に就活する仲間を見つけて相談してみると良いでしょう。なお、企業の担当者と話す機会があると、選考に参加できる場合もあります。
9.経営者
経営者の知り合いがいる場合は、就活に関する相談をしてみましょう。特に、中小企業やベンチャー企業では経営者が面接する場合も多くあります。面接官の立場でどのような印象を受けるか教えてもらえると、就活で有利です。
経営者の知り合いがいない場合は、就活コンサルタントとして活動している経営者が相談に乗ってくれる就活イベントもあります。経営者と話せる機会は貴重なので、積極的に相談しましょう。
10.就活エージェント
就活に関する悩みが尽きない場合は、就活エージェントへの相談が効果的です。就活の進め方はもちろん、内定が獲得できない不安や、対策を思うように進められない悩みも相談できます。
就活エージェントのキャリアチケットでは、就活のスタートから内定獲得まで、マンツーマンでサポートしています。相談したい内容が多い人や、どうしたら良いか分からない人は、ぜひ気軽に相談してみてください。
11.スカウト型求人サイト
就活で困ったときは、スカウト型求人サイトの活用も検討しましょう。スカウト型求人サイトとは、登録しておくだけで企業からスカウトや選考のオファーを受けられるサービスのことで、「逆求人サイト」と呼ばれる場合もあります。
キャリアアドバイザーが相談に乗ってくれるサービスもあるので、「どのような企業を目指しているか」「選考対策をどのように進めればよいか」など、相談してみましょう。
ただし、すべてのサイトでキャリアアドバイザーが相談に乗ってくれるわけではありません。サイトごとにサービス内容が異なるので、利用の際は事前に確認しましょう。
12.LINEのオープンチャット
LINEのオープンチャットを利用して、就活の相談をする方法もあります。LINEのオープンチャットは、特定のテーマや目的に基づいて参加者が集まり、匿名で発言できるコミュニティです。複数の就活生向けのオープンチャットがあるため、就活の悩みを気軽に相談できます。
LINEのオープンチャットではさまざまな情報が共有されますが、正確性や信頼性には注意が必要です。特に、就活に関する情報は個人の経験や意見も多いため、ほかの情報源もあわせて参考にしたほうが良いでしょう。
13.掲示板や就活口コミサイト
掲示板や就活口コミサイトも、就活の相談をする際に便利なツールです。ただし、掲示板や口コミサイトも、情報の信頼性を見極める必要があります。情報を参考にする場合は、本当かどうか自分で調べて確かめることが重要です。
掲示板などを利用する際は、就職支援の公的機関や大手の求人サイトが運営しているものや、多くのユーザーが登録しているものを選びましょう。なかには、運営元が不明なサイトや怪しいセールスを行うサイトもあるので事前の見極めをしっかり行います。
また、自分の相談や疑問を投稿する際は、内容を明確にするのがポイントです。質問内容が詳しいほど、ほかのユーザーがより適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
14.就活塾
就活塾とは、就職活動中あるいは就職活動を控えた学生に対して、幅広い支援サービスを提供する専門塾のことです。就活塾では、経験豊富なコンサルタントやキャリアアドバイザーから個別指導を受けられます。
就活塾に参加するメリットは、悩みを相談しながら就活ノウハウを身につけられる点です。ただし、就活塾には費用が掛かる場合が多いので、サービスを利用する前に費用やプログラム内容を確認し、自分のニーズに合った就活塾を選ぶ必要があります。
15.就活コンシェルジュ
就活コンシェルジュとは、就活をサポートする専門のコンサルタントやアドバイザーのことです。
就活エージェントをはじめ、キャリアアドバイザーに相談できる方法はいくつかあります。しかし、面談時間に制限がない場合など、就活コンシェルジュを活用するほうがより自由度の高いサポートを受けることが可能です。サービスが手厚い分、費用が掛かるため事前に情報収集を入念に行いましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活相談の重要性についてキャリアアドバイザーからのアドバイス
人に相談しながら就活をすることで、自分にはない視点や選択肢を持てるようになり、より後悔のない意思決定が可能です。
多様な経験を持つキャリアアドバイザーは、あなたの性格やスキルに基づいて意外な業界や職種を提案することがあります。これにより、以下のようなきっかけを得られるでしょう。
・これまで思いつかなかったような、自分に合う業界や企業を知るきっかけになる
・自分のキャリアに新たな可能性を見出せるようになる
また、就活エージェントに相談すれば、上記の観点に加えて、自分の経験や特性がどのような業務や働き方と合うのかを知ることも可能です。ほかにも、企業ごとの選考でのアピール方法を学んだり、書類の添削をしてもらったりできるメリットがあります。
1人で就活をするメリットとデメリットについては、「就活はひとりでは難しい?友達と進める場合のメリット・デメリットを解説」の記事も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の相談をする4つのメリット
就活の相談をすると、精神的にも行動面でもプラスの効果が期待できます。ここでは、具体的にどのようなメリットがあるかを解説するので、ぜひ参考にしてください。
1.就活に対する不安を解消できる
就活の相談をすると、不安を解消できるメリットがあります。不安を抱えたままでは、選考にもマイナスの影響を与えかねないため、早めに解消しておくことが大切です。
相談する相手は、落ち着いて自分の話を聞いてくれる人が良いでしょう。気持ちを落ち着かせたい場合は、アドバイスを求めるのではなく、ただ話を聞いてほしいとお願いするのもおすすめです。誰かに気持ちを伝えると、余裕が生まれてポジティブ思考に転換しやすくなります。
就活では失敗が続くケースもあり、落ち込んでしまう就活生も多いでしょう。就活の不安を解消する方法は、「就活で不安を抱えてしまうのはなぜ?よくある原因や対処法を解説」も参考にしてください。
2.就活に必要な情報を入手できる
就活を有利に進めるために、就活の相談をするのも有効です。Webサイトでは入手できない、リアルな情報を集められるでしょう。
インターネットでは簡単に就職の情報を集められますが、正しい情報ばかりとは限りません。間違った情報を鵜呑みにした結果、失敗してしまう可能性も考えられます。また、ネガティブな情報を見てしまい、気分が落ち込む場合もあるでしょう。
信頼できる情報を得るためには、社会人の先輩に相談したり、就活エージェントのサービスを活用したりするのがおすすめです。過去の選考に関する情報や、採用の傾向を教えてもらえると、内定獲得に向けて就活を有利に進められるでしょう。
3.第三者の意見を取り入れられる
第三者の意見を取り入れ、改善できる点も就活の相談をするメリットです。自分では考えつかなかったアイデアやアドバイスをもらえるでしょう。
たとえば、就活でよく聞かれる質問に「長所と短所」があります。自分で思いつかない場合には、第三者からのイメージを伝えてもらうのも一つの方法です。身近な人に聞くことで、自分のイメージを客観的に教えてもらえます。
就活では行き詰まる場面も多く、自分の力だけではうまくいかないケースも。第三者の客観的なアドバイスを参考にすると、どのように行動すべきか見えてくるでしょう。
4.自分の考えや思いを言語化できる
就活の相談をすることで、自分の考えや思いを言語化できる場合もあります。相手に考えを伝えるためには、分かりやすい言葉を選んだり、情報をまとめたりしなくてはなりません。
就活では、エントリーシートや面接のように、自分の考えを伝える場面が多くあります。自分の考えがまとまっていなければ、採用担当者にうまく伝えるのも困難です。
相談を通じてどのように伝えるか考えておけば、面接の練習にもなるでしょう。また、相談相手から、どのような言葉で伝えたらよいかアドバイスをもらえるのもメリットです。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の相談に必要な4つの準備
就活の相談をするためには、自己分析や質問の整理など、事前に準備をする必要があります。相談内容や聞きたいことがあいまいなままだと、悩みを解決できずに終わってしまう可能性もあるでしょう。
ここでは、就活の相談をする前に必要な4つの準備を紹介します。
1.自己分析を行う
自己PRや志望動機の作り方などを相談する際は、前もって自己分析をしておくことが大切です。自己分析が不十分だと、適切なアドバイスをもらえない可能性があります。
就活相談をする相手は、知り合いだけではありません。初めて話す人に相談する場合に備えて、自己分析をしておきましょう。
自己分析にはいくつかの方法があります。1つの方法でうまく自己分析ができなかった場合は、違うやり方で自分を見つめ直してみてください。
自己分析のやり方については、「自己分析とは?就活におすすめの簡単なやり方10選や活用例を解説」の記事で詳しく解説しています。
2.質問する前に自分で調べる
就活の相談をする際は、質問する前に自分で調べておきましょう。調べれば分かることを聞くのは、時間が無駄になってしまいます。
たとえば、「自己PRの書き方が分かりません」と聞いても、どのような点に悩んでいるか伝わりにくいでしょう。「インターネットで調べた自己PRの構成に沿って作成してみましたが、納得がいく文章を書けませんでした。どのように修正したら内容が伝わるか教えてください」のように、具体的に聞くほうがより的確なアドバイスをしてもらえます。
就活の相談をする前に、まずは自分で調べる習慣をつけることが大切です。なお、調べる習慣は仕事をするうえでも役立ちます。
3.質問する理由を整理する
就活の相談をする前に、質問する理由も整理しておきましょう。質問の意図が分かると、相手も答えやすくなります。
たとえば、「面接で自分の強みが伝えられません」という相談の背景には、実際には「強みが見つけられていない」「面接で緊張してしまう」「そもそも伝えるのが苦手」など、さまざまな理由があるでしょう。
この場合、「自分の強みが分からなくて、自己PRが書けません」と聞けば、相手は強みを見つけるためのアドバイスをすれば良いと分かります。相手が回答しやすいように質問を考えるのも、適切なアドバイスをもらうために欠かせないポイントです。
4.相談内容に適した相手を見極める
就活の相談をするときは、悩みや質問内容によって相手を見極める必要があります。相手選びを間違えると、就活の相談をしても悩みや不安を解消できない可能性があるため注意が必要です。
たとえば、就活の進め方に関する悩みは、大学のキャリアセンターや就活エージェントのようなプロに相談すると良いでしょう。一方で、就活をある程度進めている場合は、ほかの就活生との情報共有をはじめ、モチベーションを高められる相手に相談するのがおすすめです。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の状況別|おすすめの相談先
就活の状況別におすすめの相談先を、下表にまとめました。
| 就活を始めたばかりの人 |
・家族 ・友人 ・サークルやアルバイトの先輩 ・大学のキャリアセンター ・大学教授 ・新卒応援ハローワーク ・就活エージェント ・就活塾 ・就活コンシェルジュ |
| 就活を進めている人 |
・OB、OG ・就活カフェ ・経営者 ・LINEのオープンチャット ・掲示板や就活口コミサイト ・スカウト型求人サイト |
| 内定を獲得した人 |
・家族 ・友人 ・大学のキャリアセンター ・就活エージェント ・就活塾 |
必ずしも表に従う必要はありませんが、「誰に相談すべきか分からない」と悩んでいる人は、状況にあわせて相談相手を検討してみてください。
内定を獲得した人のなかには、オワハラに悩む就活生も珍しくありません。オワハラとは、「就活終われハラスメント」の略称で、企業が自社に入社するよう応募者に圧力を掛ける行為を意味します。
内閣府の「令和6年度学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 調査結果 報告書[(18p)」によると、オワハラ経験者は9.4%、そのうち約5割が周囲に相談したと回答しました。主な相談先は、家族や友人、大学のキャリアセンターなどです。
就活の悩みに関して、相談をためらう理由はありません。1人で不安を抱えてしまうと、ストレスから就活で実力を発揮できず、悪循環に陥る可能性があるため注意が必要です。就活の状況にあわせて相談相手を選べると、適切なアドバイスのもと前向きに就活に取り組めるようになるでしょう。
就活エージェントのサービス内容について詳しく知りたい方は、「就活エージェントとは?選び方の5つのポイントと上手な活用法を解説」の記事を参考にしてください。
参照元
内閣府
学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
悩み別|就活の相談で聞くこと一覧
ここでは、就活の悩み別に相談で聞くことを解説します。就活の相談をする機会を有効活用できるよう、具体的な質問例をまとめているので参考にしてください。
就活の進め方
就活について漠然とした不安がある場合は、進め方について相談しましょう。
・就活当時にどのようなことを意識したか(OB、OG)
・誰に就活の相談をしているか(友人)
就活の進め方に正解はありません。「いつから始めるか」「何から始めるか」などは、就活生によって異なります。決まりがないからこそ、就活の進め方について意見をもらい、自分なりの道筋を決めることが大切です。
自己分析の仕方
自己分析がうまくいかない場合は、具体的なやり方を聞いたり、自己理解を深めるための質問をしたりするのがおすすめです。
・学びのなかで自分の成長を感じられたエピソードがあるか(大学教授)
・どのようなやり方で自己分析をするとよいのか(大学のキャリアセンター、就活エージェント)
自己分析は就活の土台であり、必ず行うべき準備だといえます。自己分析のやり方に苦戦している場合は、大学のキャリアセンターや就活エージェントなどのサポートを受けることも積極的に検討してください。
企業の選び方
企業選びで悩んでいる場合も、周囲に相談して意見をもらいましょう。
・現在、業界はどのような課題を抱えているか(経営者、OB、OG)
・大学での学びをどのように活かせるか(大学教授)
企業を適当に選んでしまうと、「仕事内容が合わない」「社内の雰囲気に馴染めない」などの理由でミスマッチを起こしかねません。「このままの選び方でよいのだろうか」と悩んでいる場合は、周囲に意見をもらうのがおすすめです。
選考対策
周囲に相談してアドバイスをもらうと、書類や面接などの選考対策をスムーズに進められます。
・自分の第一印象はどうか(OB、OG)
・志望先から内定を獲得するためにどのような準備をしているか(友人)
たとえば、履歴書やエントリーシートなどは添削を依頼するのがおすすめです。客観的な意見をもらえると、より質の高い内容に仕上がります。
また、面接では受け答えの内容に限らず、立ち振る舞いも評価の対象です。マナーや身だしなみ、表情などは自分で確認するのが難しいため、第三者の意見をもらうと良いでしょう。
面接対策について詳しく知りたい方は、「面接対策は万全?就活に必要不可欠な準備とマナー」の記事も参考にしてください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の相談をしたほうが良い就活生の4つの特徴
「就活で何をすればよいか分からない」「就活疲れを感じている」といった就活生は、周囲への相談がおすすめです。ここでは、就活の相談をしたほうが良い就活生の特徴を紹介するので、自分が当てはまるか確認してみてください。
1.就活で何をすべきか分からない
就活で何をすべきか分からなくなった場合は、周囲に相談しましょう。よく分からないまま行動すると、失敗したときに後悔しかねません。
就活は多くの学生にとって初めての経験であり、分からないことが多くて当然です。就活の進め方をイメージしてみても、具体的な行動が思いつかないケースも考えられます。
就活をよく知る人に相談すると、自分がどうすれば良いか見えてくるでしょう。行動に自信が持てると、物事を前向きに考えられるようになります。
2.自分に合う就職先が分からない
どのような企業が自分に合うか迷っている場合も、周囲への相談が必要です。相談の結果、自分のやりたいことや目標が見つかる場合もあります。
大学生は社会経験が少なく、アルバイトをしたことがない人もいるでしょう。自己分析や企業研究を頑張っていても、自分に合う企業のイメージが分からないケースもあります。
イメージが湧かない場合は、仕事について詳しく聞いてみてください。情報を集めて働く姿をイメージできるようになると、自分に向いている企業を探しやすくなります。
企業研究を徹底すると、志望動機を作成する際にほかの就活生との差別化が可能です。企業研究のやり方が分からない場合は、「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」を参考にしてみてください。
3.内定獲得に向けてレベルアップしたい
内定獲得に向けてレベルアップしたい人も、周囲への相談がおすすめです。客観的なアドバイスを取り入れると、就活でのアピール方法を改善できます。
具体的には、自己PRや志望動機を見てもらいアドバイスをもらいましょう。また、模擬面接をして、身だしなみや態度に問題がないか教えてもらうことも大切です。就活を有利に進めるためにも、第三者の意見を参考にしてみましょう。自分だけで考えるよりも、効率良く成長できます。
4.1人で就活をするのがしんどい
1人で就活をするのに疲れてしまった人は、できるだけ早く周囲を頼ることが大切です。気持ちを素直に吐き出せると、考えが整理されて心が軽くなります。自分だけで抱え込むとさらに苦しくなるため、頑張り過ぎないようにしましょう。
就活は1人だけでする必要はありません。友人や家族と協力して進めるのも方法の一つです。「内定がもらえなくてしんどい」「就活が嫌になった」のようなつらさはできるだけ抱え込まず、周りに相談してみましょう。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の相談をする際の注意点
ここでは、就活の相談をする際の注意点を解説します。さまざまな情報を簡単に入手できる分、一度自分で考えてから受け止めるようにしましょう。
得た情報を鵜呑みにしない
相談で得た情報をそのまま鵜呑みにしないよう、真偽を確かめたり、参考程度にしたりすることが大切です。
特に、インターネットでは、名前も顔も分からない人がさまざまな情報を発信しています。ときには、主観的な意見や嘘の情報も流れてくるでしょう。得た情報をすべて信じるのではなく、本当に正しいか確かめるようにすると、情報に悩まされずに済みます。
また、「さまざまな情報に惑わされて、結局何をすればよいのか分からない」という場合は、プロに意見を聞くのがおすすめです。就活エージェントのキャリアチケットでも就活の相談に乗っているので、ぜひ登録してみてください。
自分とは考えが合わない相談相手もいると理解する
相談する相手の考えが、自分と合うとは限りません。無理に理解しようとしたり、相手が間違っていると非難したりしないようにしましょう。
同じ就活生であっても、考え方や価値観、就活の軸は異なります。Aさんが良いと思う企業が、Bさんに合うわけではありません。就活の相談をすると、「考え方が間違っている」「△△するべき」などのように、自分の考えと違うことを言われる場合もあります。
もし、受け入れられないと思う場合は、無理に納得する必要はありません。自分や相手の考え方を無理に変えようせず、必要な意見だけを取り入れましょう。
情報に惑わされないためには、自分なりの就活の軸を持っておくことも大切です。就活の軸の見つけ方については、「就活の軸の回答例文12選!企業の質問に対する答え方のコツや注意点を解説」の記事をご覧ください。
相談する人数は数名に絞る
就活の相談をする相手は、数名に絞るのがおすすめです。多くの人に話を聞くと、情報が多過ぎて混乱してしまう可能性があります。
たとえば、AさんとBさんに相談して意見が違う場合、どちらを採用するか迷うでしょう。場合によってはどちらも信用できなくなり、全く違う意見を採用してしまうケースも考えられます。
情報量が多いほど混乱して決断しづらくなるので、信頼できる数名に絞って話をするのがおすすめです。
活かす前提で相談する
就活の相談は、活かす前提でアドバイスを求めるのがポイントです。相談しただけで満足してしまうと、たとえ不安や悩みを解消できたとしても、就活の結果は変わらないでしょう。相談して得た情報やアドバイスは、行動に移して初めて意味があります。
周囲のアドバイスや提案をもとに、志望動機をブラッシュアップしたり、面接対策を強化したりするなど、活かす前提で相談すると成果につながりやすいでしょう。
就活の基本マナーを押さえる
就活相談にあたって、基本のマナーを押さえておくことも大切です。社会人に相応しいマナーが身についていないと、失礼にあたります。
特に、OB・OGや経営者などに就活の相談をする場合は、言葉遣いに気をつけたり、聞いた内容をメモに残したりすると、好印象につながるでしょう。なお、就活の相談をするときは、依頼時だけではなくお礼の連絡を入れるのもポイントです。
就活の場面でよく使う敬語については、「就活の面接に向けて敬語をチェックしよう!間違いやすい表現も解説」で解説しています。
就活相談の依頼メール例文
メールで就活相談の依頼をする際は、正式名称で宛名を入力し、最後に署名を入れるなど、基本のメールマナーを押さえて作成してください。
OB・OGにメールで就活相談の依頼をする際の例文は、以下のとおりです。
【件名】
OB訪問のご相談(△△大学△△△△)
【本文】
△△株式会社
営業部 △△△△様
お世話になっております。
△△大学△△学部の△△△△と申します。
突然のご連絡で申し訳ございません。
大学のキャリアセンターにて△△様のことを伺い、相談させていただきたくご連絡いたしました。
現在、就職活動中であり、貴社にエントリーしたいと考えております。
貴社の業務内容や働き方について伺いたく、メールをお送りした次第です。
ご多忙中大変お手数ですが、お力添えいただけると幸いです。
もし、お時間をいただけるようであれば、来週の月曜日から金曜日で、△△様のご都合の良い日時を教えていただけますでしょうか。
突然のご連絡で郷愁ですが、何卒よろしくお願いします。
△△大学△△学部△△学科△△△△(氏名)
電話番号:×××-××××-××××
メールアドレス:×××××@××××.jp
相談後のお礼メール例文
メールでお礼を伝えるときは、次の例文を参考にしてください。メールでのお礼は、できるだけ要点を絞って簡潔にすると相手に伝わりやすくなります。
【件名】
OB訪問のお礼(△△大学△△△△)
【本文】
△△株式会社
営業部 △△△△様
お世話になっております。
本日OB訪問させていただいた、△△大学の△△△△と申します。
お忙しいなか、お時間を作っていただき誠にありがとうございました。
△△様の足を使って企業研究するお話は大変勉強になりました。
今回のOB訪問により、△△様のようにコミュニケーションを大事にする方と働きたいと感じました。今後、貴社の選考を突破するために精進してまいります。
また、相談させていただくこともあるかもしれませんが、その際はご指導いただけると幸いです。
貴重なお時間をいただきましたこと、重ねて御礼申し上げます。
引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。
△△△△(氏名)
電話番号:×××-××××-××××
メールアドレス:×××××@××××.jp
就活相談のお礼メールは基本的には型に沿って作成し、加えて何が参考になったのか感想を添えると喜ばれるでしょう。ただし、感想文のような長いメールは読み手が大変なので、端的にまとめるのがポイントです。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活相談をして内定獲得に近づきたいあなたへ
「誰に就活の相談をすべきか分からない」と悩んでいる就活生も多いでしょう。就活で困っているときは、1人で抱え込まず、できるだけ早く周りに相談することが大切です。
就活の相談にあたって、「面倒に思われないか」「本当に悩みを解消できるのか」と不安な場合は、就活エージェントに相談してみてください。
就活エージェントのキャリアチケットは、就活に悩んでいる学生を手厚くサポートしています。選考対策はもちろん、自己分析や企業選びなどの相談も可能です。就活相談をはじめ、すべてのサービスを無料で利用できるため、内定獲得に近づきたい方はぜひご連絡ください。
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら