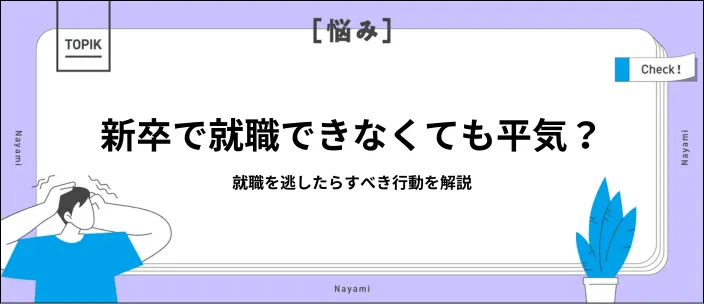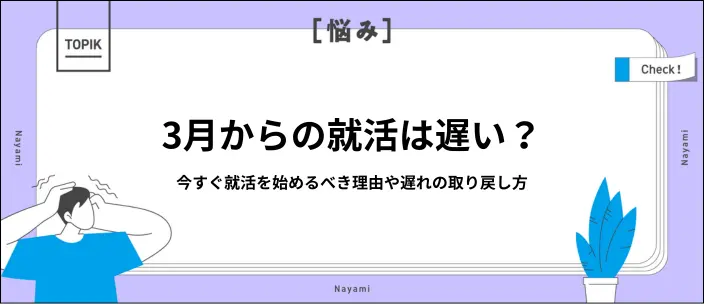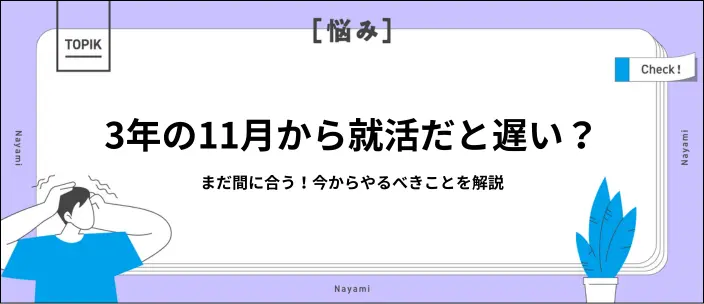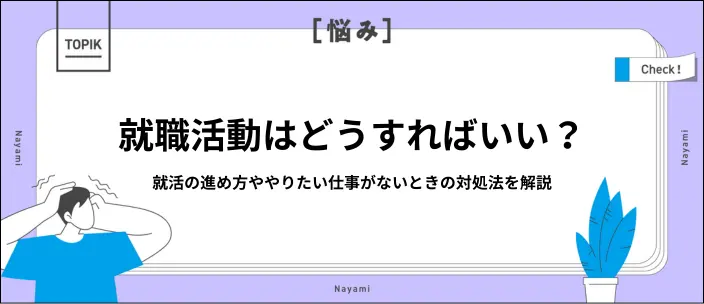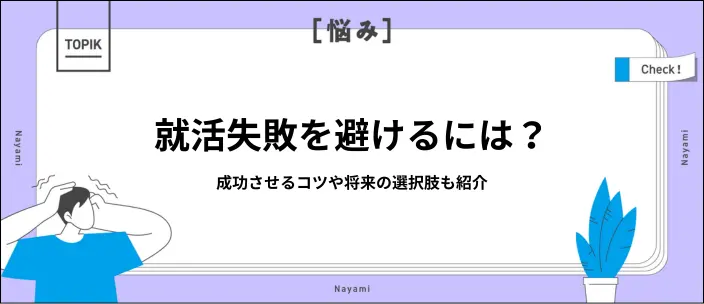このページのまとめ
- 就職先の決め方で重要なのは、就活の軸を見極めること
- 第三者の意見も参考にして、複数の就活の軸を見つけることが大切
- 就職先は、キャリアプランやライフプランを明確にしたうえで決めるのがベター

「就職先の決め方が分からない」「自分に合う仕事の探し方が分からない」と悩む就活生も多いでしょう。就職先の決め方に迷ったときは、就活の軸の明確化が大切です。
この記事では、就職先の決め方や就活の軸から考える判断基準、後悔しないための注意点などを解説します。これから就活を始める方や、内定後の就職先選びに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就職先の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 就職先の決め方の基本は自分と企業について理解すること
- 就職先の決め方で回避できる3つのリスク
- 1.ストレス・病気のリスク
- 2.早期離職のリスク
- 3.働くことそのものが嫌になるリスク
- 就職先の決め方は「仕事内容」が最も多い
- 就職先を決める前に必要な6つの行動
- 1.自己分析をする
- 2.キャリアプランやライフプランを立てる
- 3.業界・企業研究をする
- 4.就活の軸を明確にする
- 5.広い視野で考える
- 6.就職エージェントに相談する
- 就職先の決め方|これから就職活動を始める場合
- 業界で選ぶ
- 職種で選ぶ
- 就活の軸で選ぶ
- 就職先の決め方|内定後に悩んでいる場合
- 企業の規模で選ぶ
- 企業の雰囲気で選ぶ
- 就活の軸と照らし合わせる
- キャリアプランから考える
- 就職先の決め方|やりたい仕事が分からない場合
- 就活の軸別|就職先の決め方で優先すべき基準
- やりがいを重視する軸の場合
- 成長したいという軸の場合
- 価値観・社風を重視する軸の場合
- どの内定先も決定打に欠ける場合の就職先の決め方5選
- 1.内定先の良い点と懸念点を比較する
- 2.内定者イベントに参加してみる
- 3.採用担当者に面談を依頼する
- 4.周囲の意見を聞いてみる
- 5.就職活動を継続する
- キャリアアドバイザーが考える就職先の決め方のポイント
- 「土日休み」「勤務地固定」などの条件だけを就活軸にしないこと
- 選択肢の幅を増やす
- 主観だけで進めない
- 就職先の決め方で後悔しないための注意点
- イメージだけで判断しない
- 他人やインターネットの意見に流されない
- 納得できていない点を放置しない
- 今の価値観や考え方に固執しない
- 離職率が高い企業は注意する
- 就職先の決め方で悩んでいるあなたへ
就職先の決め方の基本は自分と企業について理解すること
就職先の決め方において、基本となる重要な観点は自己理解と企業理解です。
自己理解や企業理解がしっかりできていると、就活の軸の見極めにつながります。就活の軸とは、自分がどのような仕事をしたいのか、どのような働き方を実現したいのかといった企業選びの基準になるものです。就活の軸を明確にすることで、納得できる就職先を決められるようになります。
就職先の決め方に漠然とした不安がある方は、「『就活どうしよう』と不安なあなたへ!悩みの原因と対処法をご紹介」の記事もぜひ参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就職先の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就職先の決め方で回避できる3つのリスク
ここでは、就職先の決め方がよく分からないまま就職した場合のリスクについて解説します。よく考えて就職先を決めることがなぜ重要なのかを理解してから、就活に臨みましょう。
1.ストレス・病気のリスク
就職先の決め方が分からないまま就職した場合、自分に合わない企業に就職してしまう可能性があります。自分に合わない環境はストレスになり、心身ともに健康でなくなるリスクが高まるでしょう。
社会人になると、一般的には1日8時間、週に5日間勤務します。1日のほとんどを仕事に費やすため、自分に合わない環境ではストレスが溜まり続け、体調を崩す可能性が高くなるでしょう。
「何のために働いているのだろう」「仕事を辞めたい」とネガティブな思考に陥り、その結果、業務効率が落ちたり、人間関係のトラブルにつながったりするケースも考えられます。
2.早期離職のリスク
就職先の決め方が不十分だと、理想と現実のギャップが生まれやすくなり、条件面や社風が合わず早期退職のリスクが高まります。
厚生労働省の「学歴別就職後3年以内離職率の推移」によると、令和3年度に大学を卒業した人が3年以内に離職した割合は、34.9%でした。令和4年度および令和5年度に卒業した人も同様に、毎年約10~12%ずつの離職が続いています。
| 勤続年数 | 離職率 |
| 1年目 | 12.3% |
| 2年目 | 12.3% |
| 3年目 | 10.3% |
| 合計 | 34.9% |
引用元:厚生労働省「学歴別就職後3年以内離職率の推移(2p)」
早期退職した場合は改めて就活が必要になりますが、短期間での離職は好印象をもたない企業も多いでしょう。
既卒での就活は新卒と違い、経験がより重視されます。転職をしたいと思っても、未経験では既卒のほうがハードルが上がる可能性が高いでしょう。
新卒で入社した企業で長く活躍するためには、自身の適性や得手不得手をしっかりと理解し、自分の方向性に合った就職先を選ぶのが大切です。
参照元
厚生労働省
新規学卒者の離職状況
3.働くことそのものが嫌になるリスク
合わない就職先で働いていると、仕事に対しての熱意や愛着が次第になくなるリスクが高まります。その結果、労働そのものが嫌になってしまうでしょう。
仕事をするのは生活維持のためだけでなく、自己成長や自己実現には欠かせないものです。そのため、仕事にやりがいを感じるほど心理的な満足感は高まり、自己肯定感にもつながるでしょう。
自分に合った就職先の決め方のコツは「仕事選びで後悔しないためにはどうする?選び方のコツや準備を解説」の記事でも紹介しているので、ご一読ください。
かんたん1分!無料登録就職先の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就職先の決め方は「仕事内容」が最も多い
就職エージェントのキャリアチケットが2023年10月に実施した調査によると、多くの学生が就職先の決め方で仕事内容や給与を重視していることが分かりました。

引用元:キャリアチケット「【2023年10月実施】25卒学生の就活状況についての調査」
また、コロナ禍を機に「希望の勤務地で働ける」「在宅勤務」といった、ワークライフバランスを重視する人も増加傾向にあります。
もちろん、就職先の決め方に正解はありません。人生に正解がないように、企業選びで何を重視するかはあなた次第です。就職先を決めるときは、自分自身が重視している点や価値観がマッチしている企業を選ぶようにしましょう。
就活の企業選びについては「失敗しない企業の選び方10選!あなたに合う企業選びのポイント解説」の記事でも紹介しているので、ぜひご覧ください。
かんたん1分!無料登録就職先の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就職先を決める前に必要な6つの行動
就職先を決めるときは、あらかじめ自己分析や企業、業界研究などをして、就活の軸を定めておくことが重要です。ここでは、就職先を決める際に役立つ行動を6つのステップで具体的に紹介します。
1.自己分析をする
まずは自己分析をしましょう。就職先の決め方で悩んだら、改めて自己分析の内容を整理するのが大切です。
就活を始めたときに行う自己分析と、内定を獲得したあとで行う自己分析では、結果が変わる場合もあるでしょう。就活を通して成長したり、考え方が変わったりするためです。
また、自己分析では不安点や気になる点を言語化してみるのも効果的です。今の自分が何に対して不安を感じて、どのような点が気になっているのかを具体的に書き出してみましょう。
曖昧だった問題が言語化によって明確になると、迷いを解消する手助けになる可能性があります。
自己分析については「自己分析とは?就活におすすめの簡単なやり方10選や活用例を解説」の記事で紹介しているので、参考にしてください。
2.キャリアプランやライフプランを立てる
自己分析で自分の価値観や強みを言語化できたら、5年後、10年後の理想のキャリアプランを明確にしましょう。特定の企業でどのような仕事を担っていきたいかよりも、どのようなキャリアや働き方を実現したいか、ライフプランも含めて人生全体を俯瞰して考えます。
具体的には、「10年後の目標を達成するためには今何が必要か」といった、現在と将来をつなぐ道筋を作りましょう。仕事内容を具体的にイメージできない場合は、「40歳で独立して起業する」「30代でチームリーダーとして人をまとめる立場になる」など、役職や地位で考えるのもおすすめです。
3.業界・企業研究をする
「この企業に就職したい」と決めきれない理由として、業界・企業研究が足りていない場合があります。業界や企業について深く理解して、不安点や気になる点を解消すれば、企業が自分に合うかを明確にできるでしょう。
また、業界・企業研究において、経営戦略や成果などを調査して将来性を意識するのも重要です。衰退が見込まれる場合は、自身の将来的な成長やキャリアが限られる可能性が考えられます。
反対に、調べ過ぎて情報過多になっている場合も要注意です。気になる情報やネガティブな情報が多過ぎても、就職先を決めきれない原因につながってしまいます。
就職エージェントのキャリアチケットでは、一人ひとりに寄り添った就活サポートが可能です。自分に合う業界・企業を理解したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
4.就活の軸を明確にする
自己分析で強みや価値観を理解し、理想のキャリアプランを立てたら、「就活の軸」を明確にしましょう。就活の軸とは、「働くうえで譲れない自分なりの基準」です。
企業の価値観とマッチするのはもちろんですが、「営業がしたい」「土日は休みがよい」など、職種や待遇条件など細かい軸も明確にしておくと、迷ったときに就職先を決めやすくなります。
就活の軸の決め方は「就活の軸とは?探し方のコツや具体的な方法を例文付きで解説」の記事で紹介しているので、参考にしてください。
5.広い視野で考える
就職先を決める際は、視野を広くもつことが大切です。「やりがいさえあればよい」「絶対に知名度の高い会社に入社したい」など、視野が狭い人ほど入社後のミスマッチにつながりやすくなります。
就職選びの基準は、年収や待遇、やりがいなど多くの要素が複雑に絡み合っています。「こんなはずではなかった」と後悔しないために、さまざまな判断基準で俯瞰して考えるのが重要です。
また、就活の軸を明確にするためにも、判断基準をリストアップして優先順位をつけておくのがおすすめ。優先したい条件と妥協できる条件を整理すると、企業を選びやすくなります。
6.就職エージェントに相談する
自分なりに行動して考えても就職先を決めきれないと感じたら、就職エージェントに相談してみましょう。プロの視点から、どのように企業を選べばよいのかアドバイスをもらえます。
また、就職エージェントは、志望する業種や企業の詳しい情報を知っている場合もあるでしょう。自分だけでは得られなかった情報は、判断材料として就職先を決める手助けになる可能性があります。
キャリアチケットでは、あなたの悩みを解消するためのサポートが可能です。企業選びに困ったらぜひご相談ください。
かんたん1分!無料登録就職先の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就職先の決め方|これから就職活動を始める場合
「やりたいことが分からない」「自分に向いている仕事が分からない」などは、これから就活を始める場合に多い悩みです。ここでは、このような悩みをもつ就活生へ向けて、具体的な就職先の決め方を解説します。
業界で選ぶ
これから就活をする場合は、志望する業界から考えてみましょう。業界から就職先を選ぶ際は、最初から1つの業界や企業に絞らないようにするのがポイントです。業界を1つに絞ってしまうと、ほかの情報を得る機会が減って判断材料が少なくなってしまうからです。
業界は、大きく分けると以下の8つがあります。
・小売
・金融
・メーカー
・サービス、インフラ
・広告、出版、マスコミ
・ソフトウェア、通信
・官公庁、公社、団体
まずは自己分析をして、興味のある業界を見つけてみましょう。ただし、同じ業界であっても企業によって事業内容や規模はさまざまです。
職種で選ぶ
自己分析で認識した自分の強みや興味、関心を活かせる分野の職種から選ぶのもおすすめです。自分の得意分野を活かせる職種に就くのは、仕事に対するモチベーション向上にもつながります。
また、自分がやりたくない仕事や、苦手な分野も把握しておきましょう。やりたくないことや苦手なことを職種の候補から除外でき、入社後のミスマッチが起こりにくくなります。
世の中にどのような職種があるか詳しく知りたい方は、「就活における職種の一覧とは?自分に合う仕事の見つけ方も紹介」の記事も参考にしてください。
就活の軸で選ぶ
業界や職種で就職先を決めきれない場合は、就活の軸で選びましょう。自分の強みや大切にしている価値観、考え方を基準として就職先を選ぶのがポイントです。
就活の軸は、具体的に以下のようなものがあります。
・海外に関わる職場で働きたい
・明るく人間関係が良好な職場で働きたい
・ライフワークバランス重視で残業や休日出勤が少ない企業で働きたい
また、就活の軸は5年後10年後のキャリアプランから逆算して、入社後の自分をイメージして考えるのが大切です。就活の軸を定めると理想のキャリアを実現しやすくなります。
たとえば、将来的に海外で働きたい場合は、駐在の可能性がある企業や世界シェアが高い企業を選ぶのがおすすめです。
かんたん1分!無料登録就職先の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就職先の決め方|内定後に悩んでいる場合
複数の企業から内定をもらって、就職先を決めるのに悩むケースもあります。複数の内定先がある場合は、それぞれの企業の特徴をよく理解するのがポイントです。
ここでは、内定後に悩んでいる就活生に向けて、具体的な就職先の決め方を解説します。
企業の規模で選ぶ
企業の規模で就職先を選ぶ場合は、大企業と中小企業、両方のメリットを理解しましょう。
大企業のメリット
大企業には以下のようなメリットがあります。
・福利厚生が充実している
・スケールの大きな業務に携われる
・さまざまな職種に挑戦できる可能性がある
・スキルアップが望める
・社会的信用が高い
中小企業のメリット
中小企業の主なメリットは、以下のとおりです。
・幅広い業務に携われる
・経営陣と距離が近いため、意見や承認が通りやすい
・新しい業務に挑戦しやすい
福利厚生は企業規模に関わらず、中小企業でも充実している場合があります。
「経営陣に近い」のは中小企業のメリットです。社員数が少ないがゆえ、裁量権を持って働ける可能性が高いでしょう。「実力を評価されたい」「早くから主力として活躍したい」と考えるのであれば、中小企業も選択肢に入れてみてください。
大企業と中小企業の違いや、中小企業に就職するメリットについては、「中小企業にはどんなメリットがある?大手企業との違いと合わせて解説」の記事をご一読ください。
企業の雰囲気で選ぶ
説明会や面接など、選考を経て感じた企業の雰囲気から就職先を決める方法もあります。会社の雰囲気や社風とマッチしているかは、長く働き続けるための重要な要素です。
入社後に、「職場の雰囲気が合わない」「想像していたイメージと違った」となれば早期離職につながりかねません。面接で会った採用担当者や説明会での社員の様子から、会社の雰囲気はどうか考えたうえで就職先を選びましょう。
就活の軸と照らし合わせる
複数の内定先から選ぶときも、就活の軸を基準に考えるのがおすすめです。志望先の企業であっても、選考が進む過程で「最初のイメージと違う」と感じる場合もあるでしょう。
そのため、内定後に就職先を決める段階でも、改めて就活の軸と照らし合わせるようにしてください。
キャリアプランから考える
社会人としてのキャリアを想像して、理想のキャリアプランが実現できそうな企業を選ぶのもおすすめです。たとえば、「30歳までにリーダーとして活躍したい」といったキャリアプランがある場合は、実際に20代や30代で活躍しているリーダーがいる企業を選んでみましょう。
20代どころか、早くても40代以降でしかリーダーになれない企業は、理想のキャリアプランを実現する可能性が低くなるためです。自分の目標が達成できるかという視点で、就職先を考えるようにしましょう。
かんたん1分!無料登録就職先の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就職先の決め方|やりたい仕事が分からない場合
自己分析をしても、やりたい仕事が分からない場合もあるでしょう。そのような場合は、自分の強みや資格をスキルアップできる仕事に就くのがおすすめです。もし就職先が自分に合わなかったとしても、ほかの企業で経験値として活かしやすく、転職に有利になる可能性が高いからです。
加えて、ライフプランも並行して考えてみましょう。たとえば、結婚や子育てなどのライフプランによって、産休やリモートワークといった柔軟な働き方が必要になる場合があります。男女問わず、育休やフレックス勤務などの利用実績を調べておきましょう。
さらに、就職先の決め方で後悔しないためのアクションとして、早めに就職エージェントに相談するのもおすすめです。
職場は人生で長い時間を費やす大切な場所です。就職エージェントのキャリアチケットでは、やりたい仕事が分かるまで就活生一人ひとりのペースに合わせて伴走します。一緒にやりがいや楽しさを感じられる就職先を見つけましょう。
また、「就活悩みあるある12選|よくある悩み・失敗談から学ぶ対処法もご紹介!」の記事では就活でよくあるお悩みを紹介しています。興味のある方は併せてご一読ください。
かんたん1分!無料登録就職先の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の軸別|就職先の決め方で優先すべき基準
ここでは、就活の軸の内容別に、何を重視してどのように行動すべきか具体例を紹介します。
やりがいを重視する軸の場合
社会に広く貢献できる仕事をしたい場合は、事業や仕事内容、企業方針などを重視するのがおすすめです。
| 重視すべき基準 | 具体的な行動 | 行動の理由 |
| 事業・仕事内容 | ・数多くの会社説明会に参加する ・興味のある業界のボランティアに参加する・徹底的に業界、企業研究する |
具体的に自分にはどのような業界、職種が向いているかを見極めるため |
| 経営陣や企業方針 | ・企業理念や今後の事業展開を確認する | 自分の価値観に合う社会貢献度や業界内での企業体質を知るため |
成長したいという軸の場合
社会人として幅広いスキルを身につけて成長したい場合は、企業方針や仕事内容、企業風土などを重視するのがおすすめです。
| 重視すべき基準 | 具体的な行動 | 行動の理由 |
| 経営陣や企業方針 | ・会社説明会に参加する ・今後の事業計画を確認する |
入社後に新しいチャレンジができるよう、企業としての成長意欲の高さを見極めるため |
| 仕事内容・企業風土 | ・先輩社員のインタビューを読み込む ・先輩社員から直接話を聞く |
・現場の声から、「どのような経験が積めるか」「どのようなスキルが身につくのか」を知るため ・成長意欲のある社員とともにモチベーション高く働けるかを見極めるため |
価値観・社風を重視する軸の場合
自分の考えや価値観を大切にして働きたい場合は、待遇や働き方、企業風土などを重視するのがおすすめです。
| 重視すべき基準 | 具体的な行動 | 行動の理由 |
| 待遇・福利厚生・働き方 | ・リモートワークやフレックス勤務といった制度の有無や詳細を確認する ・スキルアップのための研修制度の有無や詳細を確認する |
働き方の柔軟性を確認し、ライフステージや環境に合わせた働き方ができるか見極めるため |
| 仕事内容・企業風土 | ・会社の説明会に参加する ・口コミサイトの検索をする ・OB、OG訪問を積極的に行う |
ボトムアップスタイルで若手の意見も反映してくれるか、自分のやり方で仕事を進めていけるかを見極めるため |
上記のように、就活の軸を起点にどのような行動をすべきか考えると、就職先を決めるために必要な情報を得られるでしょう。
かんたん1分!無料登録就職先の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
どの内定先も決定打に欠ける場合の就職先の決め方5選
さまざまな角度から複数の企業を比較しても、なかなか就職先を決めきれない場合もあるでしょう。
ここでは、就職先を決めきれない場合におすすめの方法を紹介します。どの企業も決定打に欠けていると感じている就活生は、ぜひ参考にしてください。
1.内定先の良い点と懸念点を比較する
内定後に就職先を決めきれず悩んでいる場合は、内定先の良い点と懸念点を比較するのがおすすめです。
まず、内定先の良い点と懸念点をそれぞれピックアップしましょう。懸念点は、「我慢できる点」「受け入れるのが難しい点」のように、細かく分類しておくのがポイントです。
たとえば、必ず転勤があるA社と、希望の部署に配属されないかもしれないB社があるとします。もし、「受け入れるのが難しい点」が「転勤」なのであれば、B社を優先すべきでしょう。
同じ業界や職種でも、企業によって雰囲気や労働環境は異なります。良い点の多さや、懸念点が許容できそうかを総合的に考えて、自分に合う企業を選んでみてください。
2.内定者イベントに参加してみる
内定者イベントに参加して企業理解を深めるのも一つの方法です。内定者イベントは企業の雰囲気が分かるだけでなく、ほかの内定者と交流できるメリットもあります。同じ志を持った同期と仲良くできそうであれば、入社後のモチベーションにもつながるでしょう。
内定者イベントは、「座談会」「懇親会」「研修」のように企業によってさまざまです。座談会の内容については、「就活における座談会の目的とは?参加するメリットや質問例を紹介!」の記事を参考にしてください。
3.採用担当者に面談を依頼する
内定先の採用担当者に面談を依頼して話を聞いてもらうのもおすすめです。内定後であっても、企業について分からない点があるケースは少なくありません。
希望の部署に配属してもらえるか、入社後に活躍できるのか、といった懸念や不安は入社前に確かめておきましょう。内定先の対応によって就職先を決められるケースも考えられます。
4.周囲の意見を聞いてみる
就職先を決めきれない場合は、周囲の意見を聞いて客観的な視点で俯瞰してみるのも方法の一つです。自分だけで考えていると、考えが偏ってしまう可能性があります。第三者が冷静に判断した意見も参考に、判断材料を見誤ったり見落としたりしないように就活を進めるのが大切です。
自分だけで解決できそうにないと感じたら、大学のキャリアセンターや就職エージェントに相談するのもおすすめです。
5.就職活動を継続する
就職先を決めきれない場合、納得のいく就職先が見つかるまで就活を続けるのも選択肢の一つです。法律的な視点では、内定獲得後に就活を続けるのは問題ありません。「民法第627条1項」で内定辞退は入社日の2週間前までに申し出れば、労働契約を解除できると定められているからです。
ただし、企業によっては、就業規則に別途条件を定めている場合があるので注意してください。内定辞退はタイミングが遅いほど企業への影響が大きくなるため、早めに辞退の意思を伝えるのが望ましいでしょう。
また、すぐに決めきれない場合は、内定承諾期限の延長を相談する必要があります。内定承諾期限を延長する方法は「内定承諾期間は延長出来る?依頼時のポイントや伝え方の例文を解説」の記事で紹介しているので、ご一読ください。
参照元
e-Gov法令検索
民法
かんたん1分!無料登録就職先の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
キャリアアドバイザーが考える就職先の決め方のポイント
就職先を決めるうえで重要なポイントは、安定して長く働けるかどうかです。自分なりの優先順位を認識できるようになると、就職先とのミスマッチを回避して安定して長く働ける企業を見極められるでしょう。
ここでは、キャリアアドバイザーが考える就職先の決め方のポイントを紹介します。
「土日休み」「勤務地固定」などの条件だけを就活軸にしないこと
休日や勤務地の条件だけを就活の軸にしないようにしましょう。勤務条件も重要ですが、入社後どのように働きたいかといった将来のビジョンがないと、やりがいを感じられず何のために働いているのかを見失ってしまう可能性があるからです。
また、福利厚生や教育制度が充実していても、「制度があるだけ」の企業も多いため、実態を調べるようにしてください。
選択肢の幅を増やす
就活の軸を明確にして志望企業を絞るのが前提ですが、選択肢の幅を狭め過ぎるのは避けましょう。特に、知名度の高さや、何となく楽しそうなイメージの業界だからといった安易な発想は、企業とのミスマッチにつながります。
選択肢を広げるためには、業界・企業研究を通じてこれまで知らなかった企業にも目を向ける必要があります。選択肢を増やすためには、就職エージェントの活用も近道になるので、ぜひキャリアチケットにご相談ください。
主観だけで進めない
自己分析を進めるうちに、無意識に自分の強みを志望業界が求める強みに寄せてしまったり、性格診断で当てはまる箇所だけに目を向けてしまったりと「就活の偽軸」ができてしまう場合があります。
性格診断は参考になる部分も多いので活用するのはおすすめです。ただし、他己分析や第三者の客観的な意見など含め、総合的に考えるようにしましょう。
キャリアアドバイザーは就活サポートのプロです。キャリアアドバイザーについて詳しく知りたい方は、「就活エージェントはやめとけって本当?利用のメリットと失敗しない選び方」の記事もご一読ください。
就活に対して後ろ向きな気持ちをもっている方には、「就活したくない時はどうする?就職以外の選択肢とモヤモヤの解決策を解説」の記事をおすすめします。就活以外の選択肢も紹介しているので、進路に悩んでいる方はぜひご覧ください。
かんたん1分!無料登録就職先の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就職先の決め方で後悔しないための注意点
ここでは、就職先を決めるときの注意点を解説します。以下のポイントに留意せず就職先を決めた場合、後悔するパターンが多いでしょう。
イメージだけで判断しない
就職先を決めるとき、「何となく嫌」「よく名前を聞くから安心だろう」といった漠然としたイメージだけで判断するのはやめましょう。
実際に、一般的なイメージと実態がかけ離れているケースもあります。特定の業界や企業に対して何らかのイメージをもっていても、説明会への参加やOB、OG訪問を通じて、どのような雰囲気なのか自分で確かめることが大切です。
また、実際に入社前に触れ合える社員は限られています。出会った特定の社員の印象だけで企業に対するイメージを決めつけず、多角的な視点で考えるのも重要です。
就職先を決めるときは、漠然としたイメージではなく、「なぜ決めたのか」を明確に言語化できるかどうかで判断しましょう。
他人やインターネットの意見に流されない
就職先を決めるときに、他人やインターネットの意見に流されないように注意してください。
近年は、インターネットの口コミサイトやSNSなどで簡単に企業の評判を調べられるようになりました。便利な反面、他人の意見や口コミは主観が強くなりがちなので注意が必要です。このような不安や疑問は、実際に会社説明会やOB・OG訪問などで実態を把握するようにしましょう。
また、就職診断もデータに基づく一般論に過ぎず、すべてを鵜呑みにするのは危険です。最終的に就職先を決めるのは自分であると意識して、他人の意見はあくまでも参考程度に、自分の考えや感じたことを基準に判断しましょう。
納得できていない点を放置しない
就職先を決めるときに納得できていない点がある場合は、事前に解消しておいてください。納得できていない点をそのままにして就職を決めても、入社後のストレスや早期退職につながる可能性があります。
たとえば、「自分が希望する部署に配属されるか分からない」と感じている場合は、人事に確認すれば不安を解消できるでしょう。
また、納得できていない点があるときは、どの程度納得できていないのかを明確にするのも大切です。たとえば、就職先を決めるにあたって「土日休み」を希望していたとしても、「給与がある程度高ければ土日出勤でも問題ない」と思えるのであれば、就職先の候補として問題ないでしょう。
就職先を決めるときは、「納得できていない点はないか」「問題を解消できるか」といった視点で判断するのが重要です。
今の価値観や考え方に固執しない
就職先を決めるときは、今の価値観や考え方に固執しないように注意が必要です。高校生のころに比べて、大学生の今はさまざまな経験を通して、価値観や考え方が変わった就活生も多いでしょう。
就職先の決め方で後悔しないためには、自己分析をして自分自身の価値観や考え方の軸を理解するのが大切です。ただし、価値観や考え方は常に変化していくものだと理解して、あまり固執しないようにしましょう。
離職率が高い企業は注意する
離職率が高い企業には、何らかのネガティブな要素があるため注意が必要です。離職率の高さは、求人票の内容と実態がかけ離れている、社内の雰囲気が悪くハラスメントが横行しているなど、社員が長い間活躍しにくい環境である可能性を意味します。
就職先を決めるときは、離職率についても調べておきましょう。
なお、企業によっては離職率を開示していない場合があります。離職率を開示していない企業のなかには、データを集めるほど離職者がいないケースも考えられます。離職率を開示していない企業がすべて危険であるわけではないという点も、併せて理解しておいてください。
かんたん1分!無料登録就職先の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就職先の決め方で悩んでいるあなたへ
どのように就職先を決めてよいのか分からず悩んでいる就活生は少なくありません。就職先を決めるときは、「これから就活を始める人」「複数の内定先から選ぶ人」、それぞれの状況に合わせて考える必要があります。後悔しない就職先を選ぶ際は、将来を見据えて自分の主観を基本に多角的に考えましょう。
就職先を自分で決めきれない場合は、就職エージェントへの相談がおすすめです。キャリアチケットでは、後悔しない就活にするために就活生のサポートをしています。就職先の決め方はもちろん、自己分析や企業研究など、これから就活を始める場合でも気軽に利用できるので、ぜひご相談ください。
かんたん1分!無料登録就職先の決め方について相談したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。