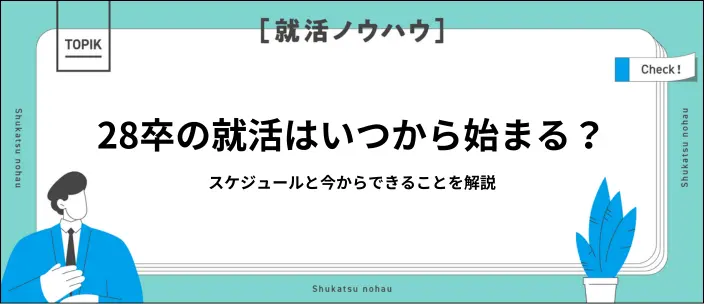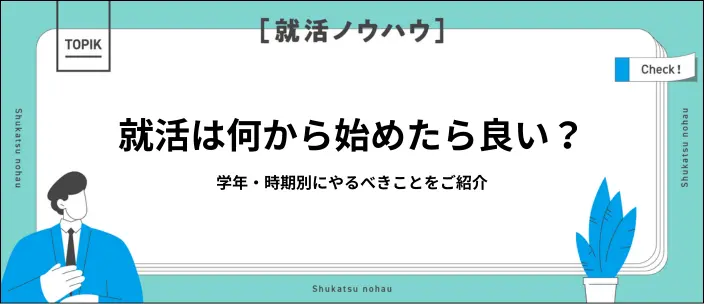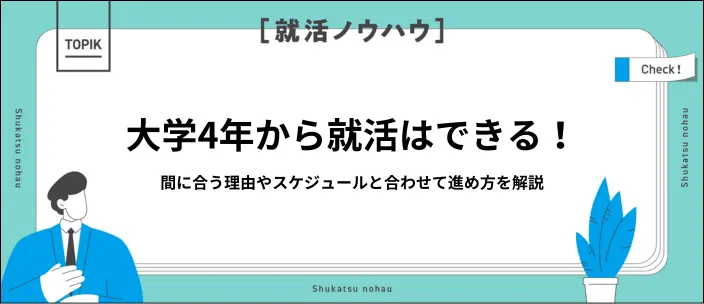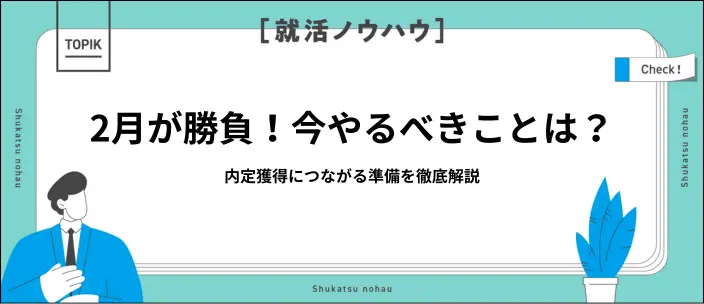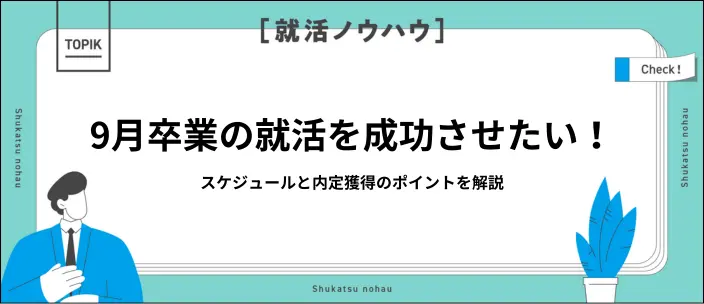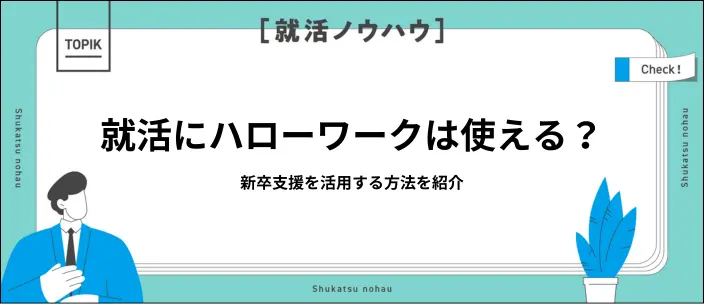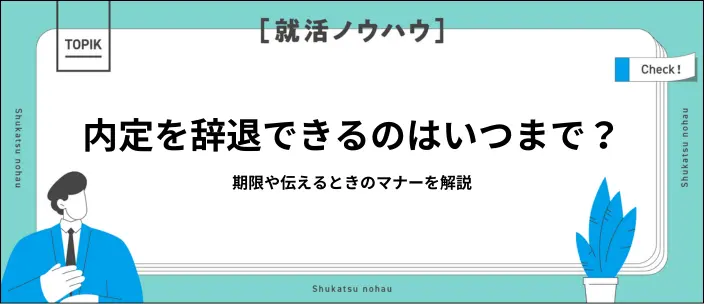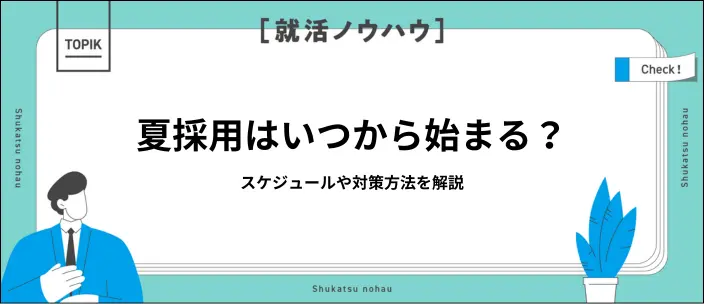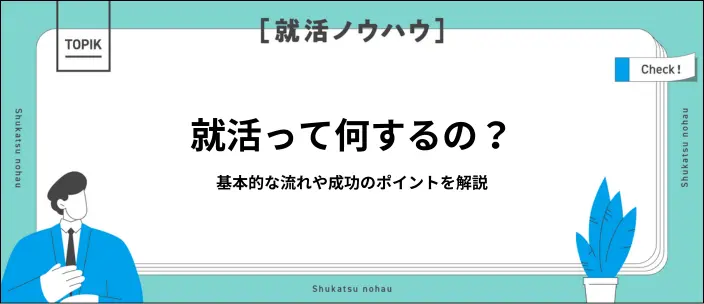このページのまとめ
- 就活の基本的なやり方は「自己分析→企業研究→応募→選考」という流れ
- 就活のやり方と一緒にスケジュールも把握しておくのが大切
- 就活のやり方を相談するなら就活エージェントやOB・OGがおすすめ
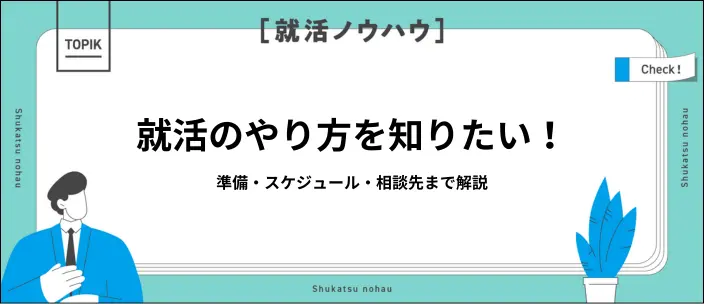
「就活のやり方が分からない」「周りと比べて遅れている気がする」と不安を感じている就活生も多いでしょう。自己分析や企業研究、面接対策など、やるべきことが多くて不安になるのは当然です。
本記事では、就活の基本的なやり方やスケジュール、出遅れた場合の対処法、成功に必要な考え方など、就活を乗り越えるために必要な情報を紹介します。就活生におすすめの相談先もご紹介しているので、困ったときの参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就活のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 就活の基本的な流れとやり方
- 自己分析
- 業界研究
- 企業研究
- インターンシップ
- 就活サイトへの登録
- 就活エージェントへの登録
- 企業へのエントリー
- 合同説明会への参加
- 企業説明会への参加
- OB・OG訪問
- 履歴書・エントリーシートの準備
- 筆記試験
- グループディスカッション
- 面接
- 内々定・内定
- 就活のやり方と一緒にスケジュールも知っておこう
- 26卒の場合のスケジュール
- 27卒の場合のスケジュール
- 就活を始める前にするべき4つの準備
- 1.就活に必要なアイテムの準備
- 2.ビジネスマナー対策
- 3.就活情報の収集
- 4.就活用のメールアドレス作成
- 就活に出遅れた場合の対策のやり方
- 自己分析からスタートする
- やるべきことを明確にして効率的に進める
- 推薦状を活用する
- 通年採用や二次募集に応募する
- ハローワークを効果的に活用する
- 状況別の就活のやり方とポイント
- 博士課程の就活
- 文学部の就活
- 経営学部生の就活
- 体育会系学生の就活
- 就活成功に必要な4つのやり方
- 1.自分の目標をしっかりと定める
- 2.最後まであきらめずにやりきる
- 3.周りの人と比べない
- 4.困ったときは周りの人に相談する
- 就活のやり方がわからないときの相談先
- 就活エージェント
- 大学のキャリアセンター
- OB・OG
- 就活のやり方をエージェントに相談するメリット
- マッチする企業に効率良く出会える
- アピールすべき自分の強みが見つかる
- 時間短縮になる
- 就活のやり方に自信がないあなたへ
就活の基本的な流れとやり方
就職活動を成功させるために、どのように就職活動を進めれば良いかを知っておきましょう。やり方を把握しておくと、内定獲得から逆算して計画を立てられ、今するべき行動が見えてきます。
ここでは、厚生労働省の「大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について」に基づきながら、就活の基本的なやり方を解説しますので参考にしてください。
参照元
厚生労働省
大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について
自己分析
就職活動を始める際は、自己分析から行いましょう。就活の土台となる自分の価値観や考え方、就活の軸を明確にするのが大切です。たとえば、自己PRを作るには、自己分析で自分の強みやスキルを明確にし、アピールしなければなりません。
企業選びでミスマッチを起こさないためには、自分が目指す職種や仕事、希望する条件なども理解しておく必要があります。自己分析を行っておけば、自分の考えが整理でき、どのような方向性で就活を行うかも考えやすくなるでしょう。
自己分析の進め方にはいくつかの方法があります。「自己分析がうまくできない」という就活生は、ほかの自己分析方法を用いて再度やり直してみてください。自己分析の進め方については、「自己分析とは?就活におすすめの簡単なやり方10選や活用例を解説」の記事で解説しています。
業界研究
世の中にどのような企業があるか調べる前に、まずは業界研究を行いましょう。新卒採用では、業界を次の8つに分けるのが一般的です。
・メーカー
・商社
・小売
・金融
・サービス
・通信
・マスコミ
・官公庁
まずはそれぞれの業界について調べて、おおまかに志望先を決めましょう。志望業界が多いと選択肢が多過ぎて混乱するので、2つか3つに絞るのがおすすめです。
業界研究をすることで、今まで知らなかった職種について知れたり、今までは考えもしなかった業界に興味を持ったりすることもあります。
業界研究の進め方については、「業界研究、おすすめの方法は?これから就活を始める人へ」の記事も参考にしてください。
企業研究
業界をある程度調べたら、企業研究を行い、個別の企業について調べてみましょう。興味のある企業については、企業研究で深掘りしていきます。企業研究を行う際は、「企業のWebサイト」や「採用ページ」「企業説明会」を見ながらやるのが効果的です。
企業研究の方法については、「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事も参考にしてください。
インターンシップ
インターンシップへの参加は、Webサイトでは確認できない企業の雰囲気や実際の業務内容を体験できるので、企業研究に役立つでしょう。就活では、大きく分けて「サマーインターン」「オータムインターン」「ウィンターインターン」「スプリングインターン」の4つが行われています。
サマーインターン
サマーインターンとは、夏休み期間中に実施されるインターンシップのことです。就活を控えた大学3年生や大学院1年生が主な対象ですが、企業によっては全学年向けに開催されることもあります。
サマーインターンは、1年を通して開催されるインターンの中でも最も早い時期(主に6〜9月)に行われ、就職活動のスタートダッシュに活用されることが多い傾向です。企業によっては、夏休み前後にも日程が設定されている場合があります。
期間は企業によってさまざまで、3日間ほどの超短期から、1〜3ヶ月にわたる長期型まで存在しているのが特徴です。ただし、多くの企業は1週間程度のプログラムを採用しています。プログラム内容は業界理解や職場体験、社員との座談会などが中心で、企業理解を深める絶好の機会です。
オータムインターン
オータムインターンは、大学3年生の10月から11月ごろにかけて行われるインターンシップです。
ベンチャー企業や中小企業を中心に実施される傾向があるものの、大手企業でもオータムインターンを行うケースは少なくありません。開催期間は企業ごとに異なり、1日だけの短期から、1週間程度、中には3ヶ月~半年におよぶ中長期のインターンも存在します。
短期インターンでは会社説明やワークを通じて業界理解を深める機会があり、長期インターンでは実際の業務に関わりながらスキルを身につけることも可能です。どのような経験ができるかは企業ごとに異なるため、参加前にインターンの目的や内容をしっかり確認しておきましょう。
また、インターン後すぐに早期選考へ進む企業もあるため、志望企業の選考スケジュールを事前に調べておくと安心です。
ウィンターインターン
ウィンターインターンは、大学3年生の12月から2月ごろに行われるインターンシップです。就職活動が本格化する直前の重要なタイミングに実施されます。
1〜3日ほどの短期間で行われるケースが多く、サマーインターンに比べて就活色が濃いのが特徴です。 特に志望度の高い企業のインターンに参加する学生が多く、企業側も本選考直結を視野に入れてプログラムを構成していることがあります。
たとえば、ウィンターインターンを通じて企業理解を深め、特別ルートでの選考案内を受けたり、早期内定に繋がったりするケースも。そのため、ただの職場体験としてではなく、就職活動の一環として参加する意識が求められます。
本選考前のラストチャンスともいえるウィンターインターン。志望企業のインターン情報は早めにチェックし、戦略的に活用するのがポイントです。
スプリングインターン
スプリングインターンは、大学3年生の2月から3月ごろに行われるインターンシップです。
冬のインターンと同様、会社説明会の要素が強く、簡単なグループワークや社員交流などを通じて、企業理解を深めるプログラムが多く見られます。 特に「まだ志望企業を絞れていない」「業界研究が足りていない」と感じている学生にとって、選考前の再確認として参加する価値があるでしょう。
本選考が本格化する前に、自分の志望度や企業理解を最終チェックできるのがスプリングインターンです。
インターンシップの時期や内容については、「インターンシップとは?行う意味や期間別の特徴をご紹介」の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
就活サイトへの登録
企業の選考に参加するためには、就活サイトへの登録をしましょう。企業のWebサイトからもエントリーできますが、1社ずつ探すのは効率が悪いのでおすすめしません。
就職サイトには多くの企業情報が集約されており、サイトを通してエントリーを行い、面接などの選考に参加します。エントリーは大学3年生の3月に一斉解禁ですが、それまでに就活サイトに登録し、企業について調べることは可能です。早めに登録して、エントリーする企業を探しておくと良いでしょう。
就活エージェントへの登録
就活を効率的に進めるために、就活エージェントにも登録しておきましょう。就活エージェントでは、「自己分析」や「エントリーシート・履歴書対策」「面接対策」など、内定獲得に必要なサポートを受けられます。
また、就職活動でのマナーや服装など、就活生が気になる悩みも解消してくれるでしょう。就職活動の時期は不安になりやすいため、アドバイスやサポートをもらえる存在は重要です。
キャリアチケットでも、就活生に向けてアドバイスを実施しており、自己分析から内定獲得まで、マンツーマンであなたの就職活動をサポートいたします。無料でなんでも相談できますので、一人での就活が不安な方はぜひご登録ください。
企業へのエントリー
大学3年生の3月1日から、企業への一斉エントリーが開始されます。気になる企業にはエントリーを行い、説明会や選考に参加しましょう。
一般的なエントリー数は、20から30社程度といわれています。少な過ぎると後から苦労してしまうので、余裕を持ってエントリーしましょう。エントリー企業は絞らず、幅広い業界・職種から選ぶのが就活成功の秘訣です。
合同説明会への参加
合同説明会に参加し、企業選びの視野を広げるのもおすすめです。合同説明会とは、複数の企業が1つの会場に集まり、自社について説明を行うイベントのことを指します。合同説明会のメリットは、1日に複数企業の説明を受けられる点です。複数の企業の説明を聞けるので、企業ごとの比較もしやすいというメリットもあります。
さらに、これまでに知らない企業に出会いやすいのもメリットです。たまたま話を聞いた企業が、自分に合う企業だったというケースもあります。
また、合同説明会に行き、就職活動をともに頑張る就活生と出会えることも。互いに情報交換ができたり、悩みを相談し合ったりできる仲間が見つけられるでしょう。合同説明会については、「合説ってどんなもの?参加するメリットと有益に過ごすコツ」も参考にしてください。
企業説明会への参加
企業にエントリーできたら、企業説明会に参加しましょう。企業説明会は合同説明会とは異なり、個別の企業について説明を受けます。
企業説明会のメリットは、企業についてより深く教えてもらえる点です。合同説明会よりも、事業内容や募集職種など、詳しく説明してもらえる傾向があります。また、企業によっては、企業説明会の参加者のみ選考に進める場合も。企業説明会に参加していないことを原因に、志望企業の選考を逃さないように積極的に参加を検討しましょう。
企業説明会については、「企業説明会の種類や見つけ方は?参加時の注意点や質問の悩みについても解説」の記事で詳しく解説しています。
OB・OG訪問
志望度の高い企業は、OB・OG訪問も行いましょう。OB・OG訪問では、その企業で実際に働く社員から、企業について教えてもらえます。OB・OG訪問のメリットは、Webサイトや企業説明会ではわからなかった部分を質問できる点です。企業説明会よりも質問しやすいので、一歩踏み込んだ質問でも答えてもらえる場合もあるでしょう。
また、企業説明会では教えてもらえなかった内容を志望動機に盛り込めば、企業について詳しく調べていると評価されます。
OB・OG訪問をする場合は、先輩に失礼のないようマナーを守って実施しましょう。また、あらかじめ、質問項目を決めておき、聞き忘れのないようにする心掛けも大切です。OB・OG訪問の進め方については、「OB・OG訪問とは?意味からメリット・流れ・質問例まで就活生向けに解説」の記事で詳しく解説しています。
履歴書・エントリーシートの準備
書類選考に向けて、履歴書とエントリーシートの対策を行っておきましょう。多くの企業で提出が求められるので、どのような内容を書くかはある程度決めておくのが大切です。
履歴書では特に志望動機が評価されるので、企業研究を十分に行いアピールできるようにしておきましょう。
エントリーシートに基づいてされるのは「自己PR」や「ガクチカ」「長所短所」などの質問です。企業独自の質問も多いので、質問の意図を汲み取って答えます。
筆記試験
筆記試験を実施する企業も多いため、筆記試験やWebテストの対策も実施しておきましょう。代表的な試験には、「SPI」や「玉手箱」があります。企業ごとに出題される内容は違うので、あらかじめどのような試験が出題されるか確認しておくと効果的です。
筆記試験対策については、「就活の筆記試験で落ちる人の特徴は?テスト対策でボロボロの結果を防ごう」も参考にしてください。
グループディスカッション
グループディスカッションで自分の強みをアピールするには、事前の対策と練習が不可欠です。GD(グループディスカッション)は限られた時間での発言力や協調性が試されるため、経験の有無がそのまま評価に影響するでしょう。
実際、就活イベントではGD練習の機会が数多く用意されており、初めてでも安心して参加できます。たとえば、キャリアセンター主催のワークショップや、民間の就活支援サービスが開催する模擬GDなどが代表的です。参加することで、発言のタイミングや役割の取り方など、実戦的なスキルを身につけられます。
まずは、自分に合ったGD練習イベントを探して、積極的に場数を踏むことから始めましょう。経験を重ねることで、自分の強みを自然にアピールできるようになります。
面接
面接対策も実施し、実力を発揮できるようにしておきましょう。準備せずに臨むと、緊張したり、話す内容を忘れたりしてアピールできなくなってしまいます。
面接は、面接官との対話、つまり言葉のキャッチボールです。相手が投げてくるボールを受け取り、優しいボールを相手に投げ返す必要があります。そのためには、相手の質問の意図を理解し、的外れな回答をしないことが重要です。
また、面接では話し方や内容はもちろん、第一印象も大切。面接マナーや身だしなみも含めて、対策を進めましょう。なお、模擬面接を受ければ客観的な意見がもらえるのでおすすめです。
面接対策については、「就活でうまくしゃべれない原因と面接下手の克服方法」の記事で詳しく解説しています。
内々定・内定
大学4年生の6月ごろになると、内々定をもらう就活生も増えてきます。10月1日に内定式を行う企業が多いため、このころには内定をもらっている就活生が多く出てくるものです。そのため、「自分はまだ内定がもらえていない」と焦ってしまう人もいるでしょう。
しかし、早く内定が欲しいからといって、やみくもに企業に応募しても、入社後の自分を苦しめてしまう恐れがあります。未来の自分に幸せで充実した社会人生活を送ってもらうためには、今をてきとうに過ごしてはいけません。焦らず確実に前へ踏み出しましょう。
かんたん1分!無料登録就活のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活のやり方と一緒にスケジュールも知っておこう
就活のスケジュールも把握しておくと、スムーズに就職活動を進められます。どの時期に、何をすべきか把握しておきましょう。
26卒の場合のスケジュール
26卒の就活スケジュールは、次のとおりです。
・大学3年生の4月ごろ:自己分析
・大学3年生の6月ごろ:サマーインターンの申し込み開始
・大学3年生の7月から9月:サマーインターンに参加
・大学3年生の10月から11月:オータムインターンに参加
・大学3年生の12月から2月:ウィンターインターンに参加
・大学3年生の3月:企業の一斉エントリー開始
・大学4年生の3月から4月:合同説明会や企業説明会に参加
・大学4年生の5月ごろ:面接などの選考開始
・大学4年生の6月ごろ:内定が出始める
・大学4年生の10月ごろ:内定式
動き出しが早い就活生は、大学3年生の6月ごろから始まるインターンシップに向けて動いています。遅くても、大学3年生の3月の企業のエントリー開始までには自己分析などの準備を済ませておきましょう。
特に自己分析や業界研究、企業研究は就職活動を進めるうえで欠かせません。早い段階から取り組んでおくと、ほかの就活生と差をつけられるでしょう。
26卒の就職活動のスケジュールについては、「就活開始時期はいつ?26卒のスケジュールや具体的な流れを解説」の記事も参考にしてください。
27卒の場合のスケジュール
27卒の場合も、基本的なスケジュールは変わりません。25卒や26卒と同様に、以下のスケジュールで進むと考えられます。
・広報活動開始 :卒業・修了年度に入る3月1日以降
・採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降
・正式な内定日 :卒業・修了年度の10月1日以降
ただし、就活が近づくにつれて変更が起こる場合もあるので、情報は必ずチェックしておきましょう。たとえば、26卒ではインターンシップの内容や仕組みがこれまでとは一部変更となりました。
よりスムーズに就活を進めるには、就職エージェントのサポートを受けるのも一つです。自分だけで就活を進めようとせず、情報収集の面でもアドバイスを受けるとよいでしょう。
参照元
内閣官房
就職・採用活動に関する要請
かんたん1分!無料登録就活のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活を始める前にするべき4つの準備
就活を成功させるためには、事前準備が重要です。ここでは、就活に取り組む前に行うべき4つの準備について詳しく解説します。
1.就活に必要なアイテムの準備
就活が本格化する前に、必要なアイテムを準備しておきましょう。たとえば、次のようなアイテムが必要になります。
・スーツ
・靴
・ネクタイ
・ストッキング
・鞄
・履歴書
・印鑑
特に、スーツや靴などは早めに用意しておきましょう。説明会やインターンシップなどで、急に必要になってもすぐ購入するのが難しいからです。
2.ビジネスマナー対策
ビジネスマナーを学び、好印象を与えられるように準備しておきましょう。たとえば、次のようなマナーが必要になります。
・挨拶
・自己紹介
・スーツの着こなし
・髪型
・電話応対
・書類の書き方
・メールの送り方
また、企業や業界ごとに特有のマナーがある場合、事前に学んでおくと選考の場で差をつけられます。ビジネスマナーに関するセミナーや書籍を活用し、練習を重ねることが大切です。
ビジネスマナーについては、「社会人としての心構えとは?具体例10選や面接での答え方を解説」の記事で解説しています。事前に確認し、勉強しておいてください。
3.就活情報の収集
就活情報は早めに収集し、いつでも動き出せるようにしておきましょう。持っている情報が多ければ多いほど、自分の興味や適性に合った業界や企業も見つけやすくなります。
就活情報は、インターネットや書籍、就活セミナーを使って集めるのがおすすめです。また、先輩や友人、就活エージェントなどに聞いてみても良いでしょう。
就活セミナーでは、就活情報はもちろん、選考対策なども行えます。就活セミナーがどのようなイベントかについては、「就活セミナーとはどんなもの?基本的な内容や参加メリットを理解しよう」の記事で解説しているので、参考にご覧ください。
4.就活用のメールアドレス作成
就活専用に、メールアドレスを準備しておきましょう。エントリーシートの送付や面接の日程調整など、採用担当者とやり取りする場面も多いからです。
就活専用のメールアドレスを作っておけば、普段のメールと混同せず、大事な連絡を見落とすリスクを防げます。また、多くのメールから探す必要もないので、効率的にメールチェックができるでしょう。メールアドレスの作り方については、「就活のメールアドレスはどう決める?基本マナーを解説」を参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就活のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活に出遅れた場合の対策のやり方
スタート時期が遅れるほど採用活動を終える企業が増え、内定獲得できるチャンスが減ってしまうため、就活に出遅れたと感じるときは、今すぐ行動するのが大切です。ここでは、就活に出遅れたと感じる場合に、やるべきことを解説します。
自己分析からスタートする
就活に出遅れたと感じたら、最初にやるべきは「自己分析」です。自分の価値観や強みを整理することで、企業選びや選考対策に一貫性が生まれ、結果的に選考通過率が上がります。
自己分析を通じて「興味のある業界」「自分に合う働き方」「やりたい仕事の方向性」などが見えてくると、エントリーする企業の判断軸となるだけでなく、自己PRや志望動機の内容にも深みを持たせられるでしょう。
実際の選考では、「あなたの強みは?」「なぜその業界を志望するのか?」といった質問が定番です。自分の経験を振り返り、強みやエピソードを整理することで、説得力のある回答ができるようになります。
出遅れた就活こそ、焦らず土台となる自己分析から丁寧に進めましょう。自己分析の詳しい進め方については、「自己分析のやり方おすすめ10選!正しく長所を理解するコツも解説」の記事で解説しています。
やるべきことを明確にして効率的に進める
就活に出遅れたと感じているなら、まず「やるべきこと」を整理し、効率的に進める工夫をしましょう。限られた時間で結果を出すには、優先順位と計画性がカギを握ります。
たとえば、選考に進むには志望企業を決めなければなりません。そのためには、就活サイトへの登録や業界・企業研究、企業比較など、事前準備が大切です。加えて、選考対策としてエントリーシート(ES)の作成や履歴書準備、面接対策、グループディスカッションや適性検査の練習など、やることは多岐にわたります。
やるべきことが見えていないと、焦りばかりが先行してしまうでしょう。まずは「今、自分が何をすべきか」を明確にし、一つずつ取り組むことが成功への近道です。
就活でやるべきことについては「就活は3月からでは遅い?スケジュール・今すぐやること・注意点を解説」の記事で解説しています。
推薦状を活用する
推薦状を活用すれば、就活で有利に選考を進められる可能性があります。大学や教授からの推薦があることで、「信頼できる人物」として企業からの評価が高まりやすくなるためです。
実際、企業によっては推薦枠でしか選考を受けられないケースもあり、推薦状を持っている学生は書類選考が免除されることもあります。また、推薦選考は通常選考よりも倍率が低く、チャンスをつかみやすいのも大きなメリットです。
ただし、注意点もあります。推薦状を使って内定をもらった場合、基本的には辞退ができません。辞退すると、教授や大学に迷惑をかけるだけでなく、今後の後輩たちの推薦枠にも悪影響を及ぼす可能性があります。推薦を受ける際は、志望度の高い企業に絞って慎重に判断しましょう。
就活での推薦状についてさらに詳しく知りたい方は「就活で使う推薦状とは?メリットデメリットや使用する影響を解説」の記事を参考にしてください。
通年採用や二次募集に応募する
就活のスタートが遅れて大学4年生の夏や秋ごろになってしまっても、通年採用や二次募集を活用すれば、まだまだ内定獲得のチャンスはあります。これらの採用枠は一次募集に乗り遅れた学生でも応募可能であり、実際に優良企業が採用を継続しているケースも多いためです。
通年採用とは、年間を通じて採用活動を行っている企業のこと。特にベンチャー企業や成長中の企業では、時期にとらわれず柔軟に人材を確保しようとする傾向があります。
一方、二次募集は、一次募集で予定人数を満たせなかった企業が追加で行う採用活動です。応募者が少なかったり、内定辞退が出たりしたタイミングで行われるため、思わぬ企業に出会える可能性もあるでしょう。
通年採用や二次募集は、就活で出遅れた人にとって「逆転の一手」になり得ます。あきらめる前に、採用枠がある企業をこまめにチェックして、積極的に応募していきましょう。
ハローワークを効果的に活用する
ハローワークは、多くの求人情報と充実したサポートが受けられるため、就活に役立ちます。幅広い職種の求人が揃っているだけでなく、専門の相談員から履歴書の書き方や面接対策など具体的なアドバイスが受けられるのがメリットです。
ハローワークでは、希望条件に合った仕事を探すことができ、さらに相談員と面談を重ねることで、自分に合った求人の提案や選考対策のポイントを教えてもらえます。特に初めて就活をする学生や情報収集が不安な方にとって、安心して利用できる環境が整っているでしょう。
ハローワークの詳しい利用方法については「ハローワークの使い方は?求人端末や新卒応援を活用する方法を紹介」の記事を参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就活のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
状況別の就活のやり方とポイント
ここでは、就活生の状況別に就活のやり方やポイントをまとめています。学部や部活ごとに進め方や注意点が異なるので、確認しておきましょう。
博士課程の就活
博士課程の学生が就職活動を行う際には自己分析をしっかりと行い、研究成果だけでなく、その過程で身につけたスキルや経験を整理しましょう。
博士課程の学生が学部生と異なる点として、専門性の高さが挙げられます。そのため、専門分野にマッチした企業選びが重要。また、企業側のニーズと自身のキャリアプランを照らし合わせることで、より具体的な職種や業界への応募が可能です。
就活を進める上で、博士課程の学生は独自の価値をしっかりとアピールし、職務経験が少ない場合でも、研究を通じて培った深い知識や解析能力を前面に出していくことが求められます。
博士課程の就活についてさらに詳しく知りたい方は「博士課程の就活で失敗しないために!求人探しや成功のコツなどを解説」の記事を参考にしてください。
文学部の就活
文学部の学生は、幅広い知識と高いコミュニケーション能力を武器に、多様な業界での就職が期待できます。特に金融業界、広告業界、出版業界などが文学部生の強みを活かしやすい分野です。文学部生は、文章力や情報収集力、教養が豊かで、これらを活かすことで多くの職種に適応できます。
就職活動では、自身の特技や得意分野を活かす資格取得も有効です。たとえば、TOEICや教員免許、簿記など、専門性を高める資格が推奨されます。また、インターンシップへの参加やアルバイト経験も就職活動において大きなアドバンテージとなり得るでしょう。
文学部の強みを活かせる就職先の見つけ方については「文学部の強みを活かせる就職先の見つけ方|おすすめの業界や資格も紹介」の記事で詳しく解説しています。
経営学部生の就活
経営学部の学生に適した就職先は、その学びを生かせる多岐にわたる業界にまたがります。特に金融やコンサルティング、マーケティング、人事など、経営的視点が求められる職種がおすすめ。これらの分野では、経営学で培った戦略的思考や問題解決スキルが直接活かされます。
就職活動を始めるにあたって、まずは自己分析を行い、どの業界や職種が自分のスキルや価値観に合っているかを見極めることが重要です。また、積極的にインターンシップに参加し、実務経験を積むことで、より具体的なキャリアプランを描く手助けとなります。
経営学部出身者は、その分析能力と経営知識を活かして、多くの業界で活躍することが期待されています。自己分析を基に、適切な企業選びを行い、充実した就職活動を目指しましょう。
経営学部の就職先について詳しく知りたい方は「経営学部におすすめの就職先は?就活時のポイントや評価される資格も解説」の記事を参考にしてください。
体育会系学生の就活
体育会系学生は精神的な強さやチームワークを重視する体質が評価される一方で、自己PRが似通ってしまうことや、精神論に偏りがちな点が課題です。
就職活動では、早めの準備とOB・OG訪問、短期インターンシップの活用が推奨されています。体育会系の学生は、礼儀正しさや明るい性格も強みになるため、これらを活かした自己PRを心がけましょう。
体育会系の就職活動についてさらに知りたい方は「体育会系は就職に有利?企業が抱く印象や就活のポイントを解説」の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
かんたん1分!無料登録就活のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活成功に必要な4つのやり方
ここでは、就活成功に向けて大切な、4つのやり方を紹介します。就活対策はもちろん、心構えも必要なので、参考にしてみてください。
1.自分の目標をしっかりと定める
就活を成功させるためには、まず「自分の目標をはっきり定める」ことが欠かせません。明確な目標があると、就活の軸がブレずに行動でき、志望動機も説得力のあるものになります。
たとえば、「将来こうなりたい」というキャリアビジョンがしっかりしていると、企業選びや自己PRが自然と目標に沿ったものになり、選考で評価されやすくなるでしょう。逆に目標が曖昧だと、「とりあえず応募」になりがちで、志望動機が弱くなったり、自分に合わない企業に進んでしまったりするリスクも高まります。
詳しくは「とりあえず応募はOK?就活生の平均エントリー数と企業の選び方について」の記事で解説しています。
2.最後まであきらめずにやりきる
就職活動は途中であきらめず、納得いくまでやりきることが成功につながります。なぜなら、就活は長期戦であり、途中で投げやりになると精神的に立ち直るのが難しくなり、内定を得られないまま卒業を迎えてしまう可能性が高まるからです。
たとえば、就活期間中は面接の不合格や思うように進まないことが続くため、疲れや不安でモチベーションが下がることもあります。しかし、そこで諦めてしまうと、努力が無駄になりかねません。逆に、少しずつでも前に進み続けることで、内定獲得のチャンスが増えます。
毎日の頑張りを自分で認めながら、あきらめずに一歩ずつ進みましょう。
3.周りの人と比べない
就活は周りの人と比べず、自分のペースで進めることが成功のポイントです。人と比較して焦ったり落ち込んだりすると、精神的な負担が増え、本来の自分らしさや志望動機がぶれてしまいます。
たとえば、SNSで「友達が内定をもらった」という投稿を見て自分だけが遅れていると感じ、自己肯定感が下がることもあるでしょう。しかし、就活は早さではなく、自分に合った企業を見つけることが目的です。無理に他人と競う必要はありません。
必要ならSNSを一時的に離れて、自分の軸を見失わないようにしましょう。自分のペースでじっくり取り組んで強みや志望理由をしっかり固め、結果的に納得のいく内定を得ることが大切です。
4.困ったときは周りの人に相談する
就職活動で困ったときは、家族や友人、就活エージェントなど、信頼できる人に相談することが大切です。就活は一人で抱え込むと精神的に疲弊しやすく、相談することで気持ちが軽くなり、前向きに活動を続けやすくなります。
不安や悩みを誰かに話すことでストレスが減り、具体的なアドバイスや新しい視点をもらえることもあるでしょう。また、客観的な意見を聞くことで、自分では気づかなかった強みや改善点を見つけられる場合もあります。
就活について誰に相談するか迷ったら、「就活相談先のおすすめ15選!悩み別の聞くこと一覧や相手選びのコツも解説」も参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就活のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活のやり方がわからないときの相談先
就活のやり方がわからないのであれば、就活エージェントやキャリアセンターなどに相談しましょう。就活のプロに任せておくと安心です。就活のやり方について相談できる、3つの相談先を紹介します。
就活エージェント
就活のやり方を聞くなら、就活エージェントがおすすめです。あなたの状況や悩みにあわせて、的確なアドバイスがもらえます。
就活エージェントのメリットは、就活のあらゆる悩みに対応し、具体的なアドバイスをもらいやすい点です。自己分析や面接対策など、具体的な対策についても教えてもらえます。キャリアチケットのように無料で利用できる就活エージェントも多いので、ぜひ活用してください。
大学のキャリアセンター
大学のキャリアセンターでも、就活のやり方を教えてもらえます。大学にあるので、授業の合間に相談しやすい点がメリットです。
ただし、就活が本格化すると利用者が増えるので気をつけましょう。予約をしなければ利用できない場合もあるので、事前に確認しておいてください。
OB・OG
OBやOGのように、就活経験者に相談するのもおすすめです。実際に、どのように就活を進めていったのか教えてもらえるでしょう。
特に、志望企業のOB・OGであれば、自己PRや志望動機をどのように答えたのか、どのような点が評価されるのか教えてもらえる場合もあります。実際にその企業で働く人ならではの視点になるので、参考にすると良いでしょう。
かんたん1分!無料登録就活のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活のやり方をエージェントに相談するメリット
就活の進め方をエージェントに相談することで、以下のようなメリットがあります。「自分ではもうどうしたら良いのかわからない」「自分の強みがわからない」と悩んでいる就活生は、一度就活のプロである就活エージェントに相談してみるのも選択肢の一つです。
マッチする企業に効率良く出会える
エージェントのアドバイザーは、数多くの就活生と企業のマッチングを実現してきたプロなので、どんな企業があなたのやりたいことや強み、価値観に合うのかをその場で判断してくれる場合が多いです。
また、就活生がやってしまいがちな企業選びの間違いについても詳しいアドバイザーが多いため、都度正しい企業選びの方法を教えてくれるでしょう。
アピールすべき自分の強みが見つかる
人事の観点でどのような強みをアピールしたら良いかを教えてくれるだけでなく、過去の経験をじっくりと深堀り、あなたの知らなかった強みを見つけることもできます。
人に自分の経験や学びを話しているうちに、自分では気づかなかった強みが見えてくることもよくあります。一人で抱え込まず、まずは気軽に相談してみましょう。
時間短縮になる
エージェントのなかには、自己応募のときに必要な書類の作成や日程調整を代理で行ってくれるところもあるため、やることの多い就活の時間を短縮できます。
時間が短縮できれば、その分自己分析に時間を使ったり、インターンシップに参加することもできるでしょう。ほかのことに時間を使え、内定に向けてより自分にあった企業を見つけられるはずです。
かんたん1分!無料登録就活のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活のやり方に自信がないあなたへ
実際に就活を始めようとしても、やり方が多過ぎて迷ってしまう人もいるのではないでしょうか。決められたやり方があるわけではなく、時期や順番などは人によって変わります。どこから手を付ければ良いかわからなくなってしまうでしょう。
就活に自信がないと感じている方には、就活エージェントのキャリアチケットがおすすめです。キャリアチケットでは、専門のキャリアアドバイザーがあなたの就活を一からサポートします。
就職活動でわからないことがあってもキャリアアドバイザーに相談ができるため、効率良く進められるのがメリットです。不安や悩みを解消し、自信をもって就職活動を進められます。就活に不安を感じている人は、ぜひキャリアチケットの利用をご検討ください。
かんたん1分!無料登録就活のやり方について相談する
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。