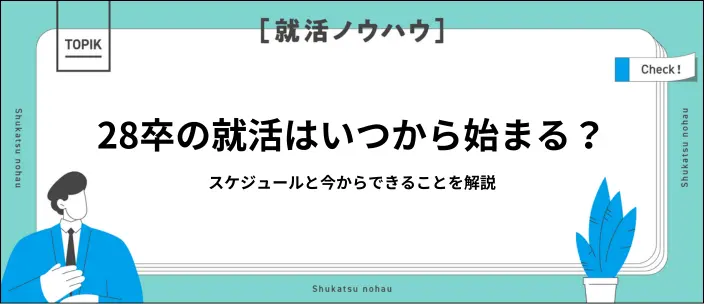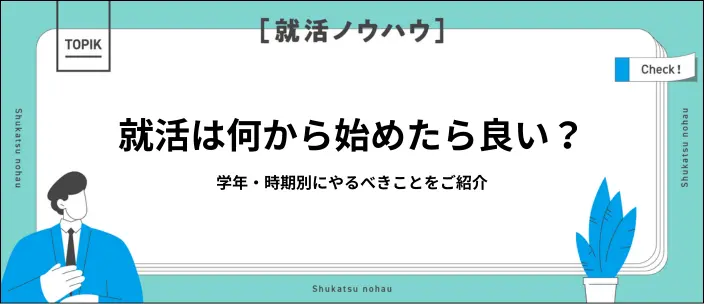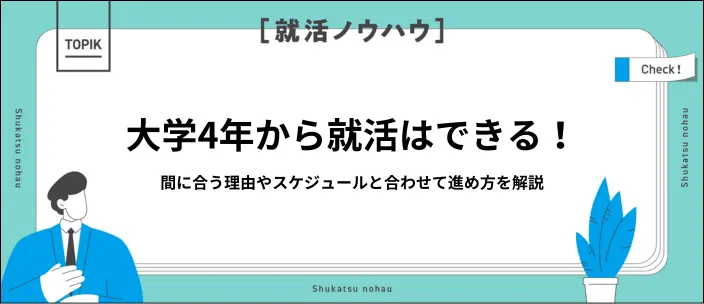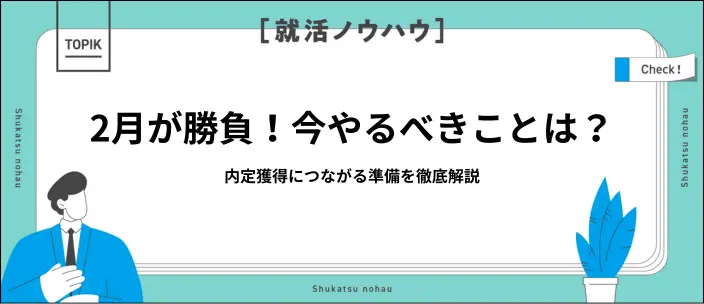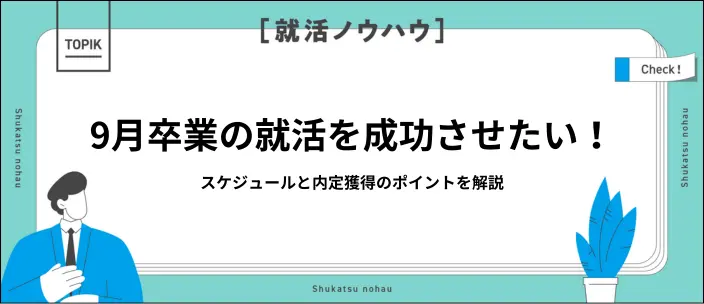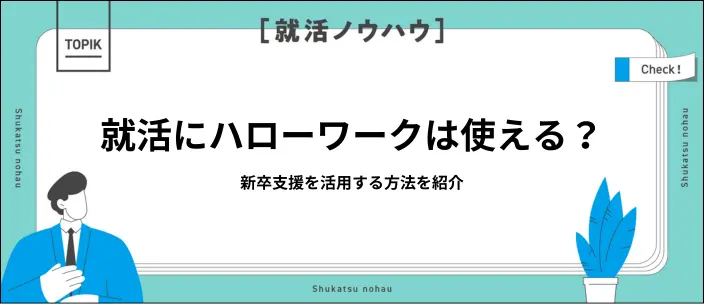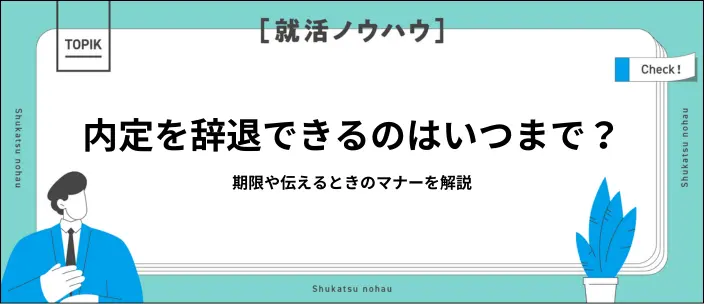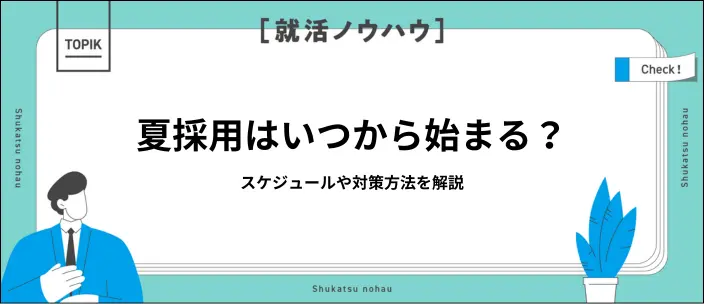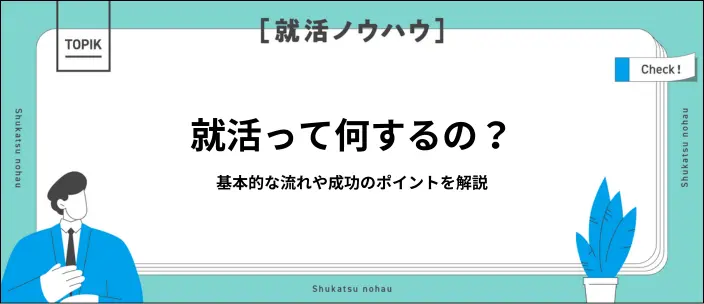このページのまとめ
- 就活の流れを把握しておくと、スムーズに対策が進められる
- 就活の流れを把握していないと、何をすればいいかわからず迷いやすい
- 就活の流れがわからない場合、キャリアセンターや就職エージェントに相談する

「就活の流れってどんな感じ?」「就活スケジュールはどうやって進んでいくの?」などと気になる就活生も多いでしょう。就活の基本的な流れや就活スケジュールを把握しておくことで、万全の状態で選考に参加することができます。
この記事では、就活の基本的な流れや、必要な準備を解説。最後まで読めば就活の流れを理解でき、内定獲得に向けて必要な行動をとれるはずです。
かんたん1分!無料登録就職活動の流れを把握したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
- 26卒の就活の流れは?スケジュールやいつまでに何をすべきか解説
- 2025年1月まで:冬のインターンシップと早期選考のチャンス
- 2025年2月まで:自己分析などの就活準備
- 2025年3月以降:企業へのエントリー開始
- 2025年5月以降:選考への最終準備
- 2025年6月以降:面接などの選考に参加する
- 2025年7月:最終面接の準備
- 2025年9月以降:秋採用のチャンス
- 2025年11月:冬採用への準備開始
- 就活を成功させるために必要な準備の流れ
- 就活に使うアイテムをそろえる
- 自己分析を行う
- 業界研究を行う
- 企業研究を行う
- ビジネスマナーを学ぶ
- インターンシップに参加する
- 興味のある企業にエントリーする
- 説明会に参加する
- 履歴書やエントリーシート準備をする
- 適性検査対策をする
- 面接対策をする
- 就活の流れを知らずに進める際の問題点
- 就活の動き出しが遅くなる
- 就活準備が不十分になる
- 企業にエントリーするタイミングを逃す
- 就活を成功させる6つのポイント
- 1.就活の軸を明確にしておく
- 2.第三者にアドバイスをもらう
- 3.幅広い企業にエントリーする
- 4.企業は条件以外の部分も確認する
- 5.内定直結型イベントにも参加する
- 6.就活の情報は積極的に集める
- 就活の流れを学んでスムーズに内定を獲得したいあなたへ
26卒の就活の流れは?スケジュールやいつまでに何をすべきか解説
就活を成功させるためには、まずは基本的なスケジュールを把握しておきましょう。ここでは、25卒が就活を行う流れを解説します。
2025年1月まで:冬のインターンシップと早期選考のチャンス
1月は多くの企業が冬期インターンシップを実施している時期で、就職活動に先駆けての貴重な機会となります。この時期にインターンシップを体験することで、実際の業務を経験し、希望の業界や企業の取り組みを身近に感じることができます。
また、一部の企業ではこの時期から早期選考を行う場合もあり、積極的にエントリーすることで就活競争を有利に進めることができるでしょう。
2025年1月中にやっておきたい就活の準備については、「就活は1月からでも内定に間に合う!やっておきたい準備とスケジュールを解説」の記事でも解説しています。
2025年2月まで:自己分析などの就活準備
2025年の2月までに、基本的な就活準備を終わらせておきましょう。2024年の3月からは、エントリーが一斉に解禁され、準備を行う時間がなくなるからです。
エントリー開始までに必要な準備には、次のようなものがあります。
・自己分析
・業界研究
・企業研究
・インターンシップ
・OB・OG訪問
就活で最初に行いたい準備は、自己分析です。自己分析は自己PRや志望動機を考えるだけではなく、企業選びの軸を考えるためにも欠かせません。自己分析ができていないと、企業へのエントリーが始まってもどのような業界や企業を調べればいいかわからなくなります。これから就活の準備を始める方は、「自己分析とは?おすすめのやり方8選や実施時の注意点を紹介」を参考に自己分析から取り組んでみてください。
2025年3月以降:企業へのエントリー開始
2025年3月からは、企業へのエントリーが一斉に解禁されます。合同説明会や企業説明会も始まるので、興味のある企業の話を聞きに行きましょう。
内閣府の「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)」によると、企業説明会やセミナーに参加した時期のピークが3月です。4月以降は説明会への参加者も減り、説明会を開催する企業も減っていきます。
企業によっては、エントリーシートなどの書類選考が始まる場合もあります。書類選考を突破できないと面接に参加できない企業もあるので、選考対策は入念に行ってください。
参照元
厚生労働省
学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査
2025年5月以降:選考への最終準備
5月は就活において、準備のラストスパートを掛ける時期です。一般的には6月ごろに面接が開始されるので、対策をしっかりしておきましょう。
また、面接までにやっておくべきことは「就活生が5月にやるべきこととは?効率よく就活を進めて内定を掴み取ろう」の記事で解説しているので参考にしてください。
2025年6月以降:面接などの選考に参加する
2025年の6月になると、面接などの選考が解禁されます。また、政府主導の就活ルールに従っている企業の場合、内々定が出始める時期も6月です。
内閣府の「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について(概要)」によると、就活生の約9割が6月までに内々定を取得しています。6月以降も積極的に選考に参加し、内定取得を目指しましょう。選考への参加だけではなく、説明会への参加や選考の準備などもあるので、スケジュール管理に気をつけてください。
夏採用に向けての対策については「夏採用で内定を獲得するにはどうする?企業の探し方やポイントを解説」の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
2025年7月:最終面接の準備
7月は、就職活動が最も熱を帯びる時期です。大手企業では最終面接やグループディスカッションが頻繁に行われます。
最終面接は、これまでの面接での評価を基に、改めて入社意欲を確認する重要な場です。従って、初回や二次面接の際の話と整合性が取れていない場合、面接官に疑問を抱かれるリスクがあります。
多くの学生が就職活動で複数の会社を受けることが普通です。どの企業に何を志望理由として伝えたかをしっかりと覚えておくことが、最終面接に臨む上で非常に重要です。以前の面接内容をもう一度振り返ってみましょう。
7月を迎えても内定が出ず、不安や焦りを感じている就活生の方は「7月の就活活動を成功させる方法は?選考が長引く理由や対策ポイントを解説」を参考にしてください。
2025年9月以降:秋採用のチャンス
9月以降は秋採用が始まります。春や夏に採用ができなかった企業や内定辞退が発生した企業が採用を続けているため、夏の選考で内定を得られなかった就活生にとってチャンスです。
企業によっては、内定者が決まり次第、すぐに採用選考を終える場合もあるので、興味のある会社には早めにエントリーし、チャンスを逃さないようにしてください。
9月以降の秋採用については「就活は9月からでも不利にならない?内定なし回避に向けた対策を解説!」の記事で詳しく解説しています。
10月に内定式を設定している企業が多いため、秋採用は9月からはじまり、11月には募集が減ってゆき採用枠が減少します。春や夏採用に比べて短い期間で実施されるので、それまでに自己分析や企業研究、面接対策などの準備をしておきましょう。
2025年11月:冬採用への準備開始
11月には、冬採用に向けた準備を始める時期です。この時期には、改めて業界研究や企業研究を深め、次のステップに備えましょう。就活で大切なのは、「内定を獲得できるかではなく」「自分にあう企業の内定を獲得できるか」です。内定をゴールとせず、納得いくまで就活をやり切りましょう。
11月までに内定が決まらない方は「就活生が11月まで内定なしだったら?今すぐにやるべきことを解説」の記事を参考にしてみてください。
かんたん1分!無料登録就職活動の流れを把握したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活を成功させるために必要な準備の流れ
就活を成功させるためには、事前の準備を行い、万全の状態で選考に参加することが大切です。準備ができていないと、慌ててしまったり、失敗を恐れて自信がなくなったりと、実力を発揮できなくなってしまいます。
ここでは、就活成功に向けて必要な準備や行動を紹介するので、参考にしてください。
就活に使うアイテムをそろえる
まずは就活開始に向けて、必要なアイテムを買いそろえておきましょう。説明会や選考の予定が急に入り、買いに行く時間がないケースもあるためです。
・スーツ
・シャツ
・靴
・ネクタイ
・かばん
・履歴書
・証明写真
たとえば、スーツはサイズが合わないとだらしない印象につながるため体に合うものを購入しますが、すぐに用意できない場合もあります。また、証明写真を写真館で撮影する場合、予約が必要になります。すぐに撮影できるわけではないので、余裕をもって準備しておくのがおすすめです。
自己分析を行う
自己分析を行い、自分の強みや価値観、志望する条件などを整理しておきましょう。自己分析で自分のことを理解することで就活の軸が明確になり、就活を進めやすくなります。
自己分析の方法は、過去の出来事やエピソードを振り返るのが一般的。次のような内容を振り返り、強みや価値観を明確にしましょう。
・何を経験したか
・なぜその活動に取り組んだのか
・具体的にどんな行動をしたか
・どんな課題に直面したか
・課題に対してどのように行動したか
・経験から学んだことは何か
自己分析の内容は、自己PRや志望動機など選考に必要な項目を考える情報となります。アピールにつなげるためにも、自己分析は入念に取り組んでください。
業界研究を行う
どのような業界があるかを知るため、業界研究を行いましょう。業界ごとに業務内容や事業の特徴があるため、一つずつ研究を行ってください。
業界は一般的に、次の8つに分けられます。
・メーカー
・商社
・小売
・金融
・サービス
・通信
・マスコミ
・官公庁
すべての業界にエントリーすると就活の軸がぶれてしまうので、2つか3つに絞るとよいでしょう。ただし、1つだけにしてしまうと、視野が狭くなりやすいので気をつけてください。
また、業界研究を行う場合は、次のような方法で進めるのがおすすめです。
・業界団体の公式Webサイトを調べる
・業界に関する就活本を読む
・ニュースや新聞で業界の動向をチェックする
・業界研究セミナーに参加する
・合同企業説明会に参加する
業界研究の進め方は、「業界研究、おすすめの方法は?これから就活を始める人へ」の記事で詳しく解説しています。
企業研究を行う
興味のある企業が見つかれば、企業研究も行いましょう。企業研究の内容が、志望動機や自己PRの内容に活かせます。
企業研究は、次のようなポイントに注目して実施しましょう。
・代表取締役の氏名、経歴
・企業理念
・社風
・提供する商品、サービス
・業務内容
・ターゲットとなる顧客
・企業の歴史
・今後の成長性、将来性
・競合他社と比べた強み、弱み
・勤務条件
企業のWebサイトや企業説明会、OB・OG訪問などを活用し、情報を集めてみてください。企業研究の方法については、「企業研究とは?目的や手順を解説!ポイントを押さえて就職成功を目指そう!」の記事でも詳しく解説しています。
ビジネスマナーを学ぶ
ビジネスマナーを学び、好印象を与えられるように準備しておきましょう。ビジネスマナーが身についていると、「社会人に向けての準備ができている」とプラスに捉えられるはずです。立ち振る舞いはもちろん、言葉遣いも含めてビジネスシーンにふさわしい行動をしてください。
インターンシップに参加する
インターンシップに参加し、仕事や業界についての理解を深めるのもおすすめです。Webサイトや企業説明会だけではわからない、企業の雰囲気や業務内容も体感できるでしょう。
インターンシップに参加するメリットは、自分に合う仕事なのか、業界なのかを見極められる点です。希望していた仕事も、実際に体験してみるとイメージと違う場合もあります。
入社後のミスマッチを避けるためにも、インターンシップをとおして仕事内容を理解したり、企業や業界について学んでおくことは大切です。
25卒以降のインターンシップの変更点
25卒からは、インターンシップの定義が変わります。これまでインターンシップと呼ばれていたものが、インターンシップではなくなるので覚えておきましょう。
経済産業省の「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」によると、インターンシップは以下の4つに分類されます。
・タイプ1:オープン・カンパニー
・タイプ2:キャリア教育
・タイプ3:汎用型能力・専門活用型インターンシップ
・タイプ4:高度専門型インターンシップ(試行)
今回の変更により、「タイプ3:汎用型能力・専門活用型インターンシップ」は大学3年生以上でしか参加できなくなりました。1年生や2年生の場合は、「タイプ1:オープン・カンパニー」「タイプ2:キャリア教育」に参加することになります。
また、1年生や2年生が参加できるプログラムは、「インターンシップ」の表記が使えなくなりました。そのため、「インターンシップ」と呼ばれるプログラムについては3年以降、2年生まではインターンシップではなく、業務理解を深めるためのプログラムが行われるようになります。
これからインターンシップに参加する際には、「インターンシップの定義を満たしているか」の確認が必要です。参加前に定義やプログラムの内容について、確認してから参加するようにしてください。
参照元
経済産業省
現大学2年生より、インターンシップのあり方が変わります!
興味のある企業にエントリーする
興味のある企業を見つけたら、積極的にエントリーしておきましょう。エントリーをしていないと、説明会や選考に参加できない企業もあるためです。
企業へのエントリーは、就活サイトを使って行うのが一般的。就活サイトには多くの企業情報が登録されているので、志望する業界や職種で絞って企業を探してみましょう。
エントリー数の目安は、20社から30社程度とされています。多すぎるとスケージュール管理が難しく、少なすぎると選考に落ちた場合に受ける企業がなくなるためです。基本的には興味のある企業はエントリーしておき、説明会や選考を受けるなかで、志望する企業を絞っていくとよいでしょう。
エントリーについては、「就活におけるエントリーとは?開始時期や応募数などを解説」の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。
説明会に参加する
興味のある企業を見つけたら、積極的に説明会に参加しましょう。Webサイトではなく、採用担当者に話を聞くからこそわかることもあります。
説明会には「合同説明会」と「個別説明会(企業説明会)」があります。
合同説明会とは、複数の企業が一つの会場に集まり、ブースごとに簡単な企業説明を行う会のこと。合同説明会に参加することにより、一度のイベントで複数企業の説明を受けられるメリットがあります。
合同説明会では多くの企業が参加しているため、自分の知らない企業に出会えるのもポイントです。たまたま話を聞いてみた企業が、自分の希望にマッチすることもあるでしょう。
企業説明会は合同説明会よりも説明時間が長く、より企業について詳しく知れるメリットがあります。
また、企業によっては企業説明会に参加した学生のみが選考に進めるケースもあるので覚えておきましょう。説明会の会場でエントリーシートが配られる場合もあるため、選考に参加したい企業の説明会には必ず参加するようにしてください。
履歴書やエントリーシート準備をする
選考に向けて、履歴書やエントリーシートの準備をしておきましょう。書類選考を突破できなければ、面接に参加できないケースが多いからです。
履歴書では、学歴や志望動機が評価されます。特に、志望動機は企業に対する熱意や入社意欲を伝える箇所なので、評価される書き方を意識しましょう。エントリーシートでは、「自己PR」や「ガクチカ」「長所・短所」などが聞かれる傾向にあります。あなたの強みやスキル、人柄をアピールするものなので、対策が欠かせません。
どの企業でも提出が求められるので、必ず対策しておきましょう。エントリーシートの書き方に悩む就活生には、「エントリーシートとは?履歴書の違いや基本を押さえて選考を突破しよう」の記事を参考にしてください。
適性検査対策をする
SPIや玉手箱など、適性検査の対策をしておきましょう。適性検査の得点が低いと、選考に落ちてしまう企業もあります。
適性検査とは、就活生の仕事への適性や基礎的な能力を見極める検査です。国語や数学に近い問題が出題される傾向にあり、対策しなければ高得点は難しいでしょう。
また、企業独自の一般常識問題を出題したり、時事問題をたずねたりする企業もあります。企業ごとにどのような適性検査を実施するかは違うため、事前に確認して対策を進めておきましょう。
適性検査の種類については、「就活の適性検査とは?検査の種類や特徴、受ける際のポイントをご紹介!」、一般常識問題については「就活で問われる一般常識問題とは?出題内容や選考突破に向けた対策を解説」の記事で解説しているので、それぞれチェックしておきましょう。
面接対策をする
面接はどの企業でも行われるので、必ず対策しておきましょう。質問への回答はもちろん、入退室のマナーなども練習しておくことが大切です。
また、面接は1対1で行うものだけではありません。以下のような種類があるので覚えておきましょう。
・個人面接:学生1人に対して行われる面接
・集団面接:複数の学生が同時に受ける面接
・グループディスカッション形式:ほかの学生とチームを組み、与えられたテーマを議論する面接
・プレゼンテーション形式:与えられたテーマに対して、学生側がプレゼンする面接
面接ごとに対策が違うため、それぞれの状況を想定した面接練習を行うのがおすすめです。友人に協力してもらったり、キャリアセンターや就職エージェントのサポートを借りたりしてみましょう。
面接でよく聞かれる質問
面接でよく聞かれる質問を予想して、回答を用意しておくことも必要です。面接では次のような質問がされやすいので、覚えておきましょう。
・自己紹介をしてください
・自己PRをしてください
・志望動機を教えてください
・学生時代に力を入れたことは何ですか
・大学では何を研究していますか
・長所、短所を教えてください
・弊社は第一志望ですか
・△年後はどうなっていたいですか
・就職活動の軸は何ですか
・最近の気になるニュースを教えてください
回答する内容は、企業によって変えましょう。たとえば、違う企業なのに全く同じ志望動機を伝えてしまうと、「自社のことを調べているのだろうか?」「どの企業にもあてはまる内容だ」などと思われてしまいます。
面接でよくある質問については、「面接でよく聞かれることは?頻出質問集とそれぞれの答え方を例文付きで解説」の記事でまとめています。企業ごとに回答を用意し、アピールできるように準備しておきましょう。
かんたん1分!無料登録就職活動の流れを把握したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の流れを知らずに進める際の問題点
就活の流れを知らずに動いてしまうと、就活を始めるタイミングを逃したり、企業に申し込むチャンスを逃したりと問題が発生します。就活の流れを知らない場合の問題点を紹介するので参考にしてください。
就活の動き出しが遅くなる
就活の流れを知らない場合、いつ就活を始めるべきかわからなくなります。就活の動き出しが遅くなり、思うような就活が実現できない場合があるでしょう。
たとえば、動き出しが遅くなると、「希望する企業のエントリーがすでに終わっていた」となることも。周囲の就活生が選考通過や内定獲得をしていることに焦り、不安になる可能性もあるでしょう。
就活の一斉解禁は大学3年生の3月になるため、遅くてもそれまでには準備を終えておきたいところです。就活の流れやスタート時期を把握し、スタートに遅れないようにしてください。
就活をいつから始めればよいかについては、「大学生の就活はいつからいつまで?始めるタイミングや必要な準備を解説」の記事を参考にしてください。
就活準備が不十分になる
就活の流れを知らないことにより、準備が不十分になる恐れもあります。どのような準備が必要かを知らず、何をしていいかわからない状態に陥るためです。
就活の流れを知っておけば、「夏休みの間に自己分析は終えておこう」「冬休みの間にエントリーする企業に目星をつけておこう」などのように、余裕をもって準備ができます。しかし、流れを知らないと必要な準備がわからず、いつ動けばいいのかもわかりません。
就活は準備不足になってしまうと、希望の企業に応募できなかったり、選考に落ちたりと後悔しやすくなります。あらかじめ流れを把握しておき、どのようなスケージュールで動くかを考えておきましょう。
企業にエントリーするタイミングを逃す
就活の流れを知らないと、希望する企業のエントリーを逃すことも増えます。企業によってエントリー開始の時期は異なり、気づいたら応募を締めきっている場合もあるからです。
経団連に加入している企業であれば、大学3年生の3月、就活が一斉解禁される時期にエントリーが開始されます。しかし、経団連に加入していない企業は一斉解禁に従う必要はないため、3月よりも前にエントリーを受け付けています。
たとえば、外資系企業やマスコミ業界などは、大学3年生の秋ごろからエントリーが始まる傾向です。ベンチャー企業や中小企業も、3月より前にエントリーできる企業があるでしょう。
志望する企業がある場合は、いつエントリーが始まるのか調べておくことが大事です。エントリー締め切り後には選考を受けられないため、どのような流れで選考が始まるかを知っておいてください。
就活に関する悩みは、「就活悩みあるある12選|よくある悩み・失敗談から学ぶ対処法もご紹介!」の記事でも、よくある悩みや不安を解説しているので、参考にしてください。
かんたん1分!無料登録就職活動の流れを把握したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活を成功させる6つのポイント
ここでは、就活を成功させるために必要な、6つのポイントを解説します。
1.就活の軸を明確にしておく
就職活動を始める前に、就活の軸を明確にするところから始めましょう。就活の軸とは、働くうえで譲れない、自分なりの基準のことです。「人と関わる仕事がしたい」「関わった人を笑顔にしたい」など、人によってことなるため、就活の軸を定めるには、自分が何をしたいのか理解することが大切です。
就活の軸を見つけるためには、自己分析を行いましょう。自分の考えや価値観を整理して、自分だけの軸を探してください。就活の軸については、「就活の軸とは?探し方のコツや具体的な方法を例文付きで解説」で詳しく解説しています。
2.第三者にアドバイスをもらう
自分一人で頑張ろうとせず、友人や家族など、第三者の力も借りましょう。履歴書や面接などのアドバイスをもらうのはもちろん、不安や悩みを聞いてもらうのもおすすめです。
また、就活エージェントに相談してサポートを受けるのもよいでしょう。就活のプロに依頼すれば、内定獲得に向けて具体的なアドバイスがもらえます。
就活で相談する相手については、「就活相談先のおすすめ15選!適切な相手選びのポイントや注意点も解説」も参考にしてください。
3.幅広い企業にエントリーする
エントリーする企業の業種や業界の幅は、なるべく広げましょう。有名企業だけではなく、中小企業やベンチャー企業を見るのも忘れてはいけません。
エントリーする幅が狭いと、自分から選択肢を潰してしまいます。最初は幅広い視野で考え、徐々に絞っていくとよいでしょう。
また、選択肢が狭いと選考に落ちて持ち駒がなくなってしまう恐れもあります。内定がなくて焦らないように、視野を広げてエントリーしてみてください。
4.企業は条件以外の部分も確認する
企業を選ぶ際は、条件以外の部分もチェックしておきましょう。給料や知名度などの条件だけで考えていると、ミスマッチが起きやすくなります。たとえば、企業の社風が自分に合うかは重要です。一緒に働く人との相性が悪いと、好きな仕事内容でも続きません。
5.内定直結型イベントにも参加する
説明会と選考が同時に行われる、内定直結型イベントにも参加してみましょう。興味のある企業の選考を、効率的に受けられます。
また、面接やグループディスカッションの練習ができるのもメリットです。選考では経験が大事なので、第一志望の選考前に練習しておくとよいでしょう。
6.就活の情報は積極的に集める
就活で必要な情報は、自分から積極的に集めましょう。以下のような方法や場所で、就活情報を集めることができます。
・企業のWebサイト
・求人情報
・就活サイト
・就活セミナー
・キャリアセンター
・就職エージェント
企業のWebサイトや就活サイトからは、企業情報や仕事の情報、選考の情報などを調べられます。自分の希望する仕事なのか、どのような選考準備が必要かなどを知れるでしょう。
就活セミナーや就職エージェントでは、自己分析や選考対策など、就活を進めるうえで欠かせない情報を得られます。「就活の流れがわからない」のような、就活に関する悩みも相談できるでしょう。
かんたん1分!無料登録就職活動の流れを把握したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら
就活の流れを学んでスムーズに内定を獲得したいあなたへ
就職活動をスムーズに進めるためには、全体の流れを把握しておくことが大切です。どのような流れで進むのかを知り、いつまでに、どのような対策が必要かを考えましょう。
しかし、初めての就職活動では、どのように進めればよいか悩むこともありますよね。もし、一人での就職活動が不安な場合は、就活エージェントのキャリアチケットにご相談ください。
キャリアチケットでは、就職活動の準備から内定獲得まで、アドバイザーがマンツーマンでサポートいたします。些細な質問であっても、なんでも質問してください。
また、面接対策や書類選考対策など、選考突破に必要な準備もアドバイスします。就活のプロに任せて、第一志望の内定獲得を実現しましょう。
かんたん1分!無料登録就職活動の流れを把握したい
自分の価値観とあった企業に出会える!27卒のスカウト登録はこちら

本記事の監修者
淺田真奈(あさだまな)
大学時代は接客のアルバイトを3つかけもちし、接客コンテストで全店1位になった経験をもつ。新卒では地方創生系の会社に入社をし、スイーツ専門店の立ち上げからマネジメントを経験。その後、レバレジーズへ中途入社。現在はキャリアチケットのアドバイザーとして、学生のキャリア支援で学生満足度年間1位と事業部のベストセールスを受賞し、リーダーとしてメンバーのマネジメントを行っている。